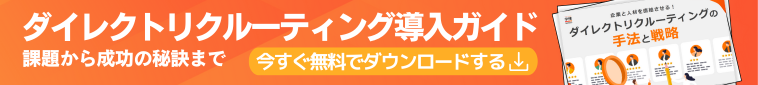中途採用を成功させるポイントをケーススタディで解説|評価基準も
公開日:2024.07.19
更新日:2025.12.14

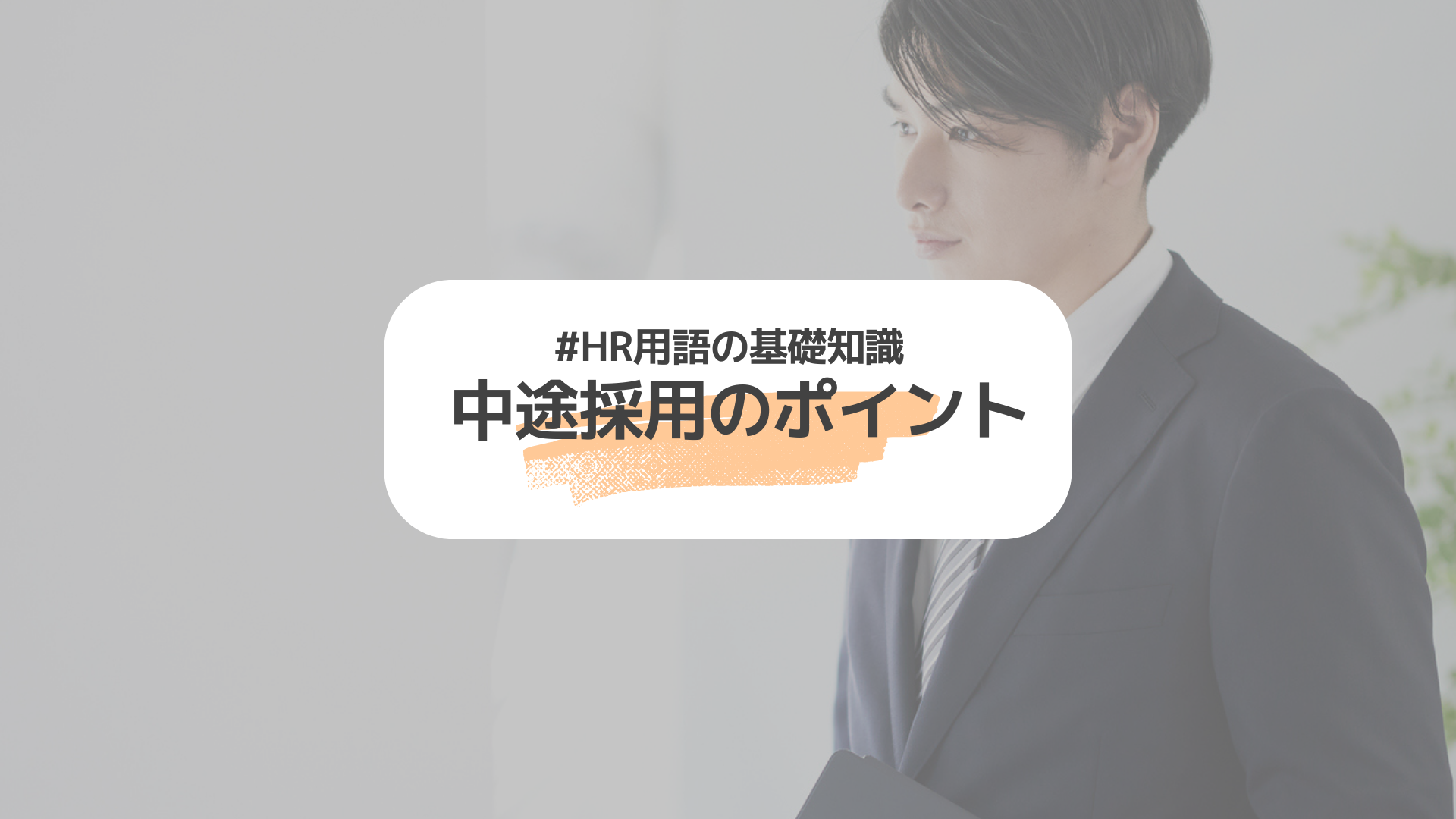
採用担当者の多くが、一度は「中途採用は難しい」と感じたことがあるのではないでしょうか。中途採用には新卒採用とは異なる特徴があり、経営層や現場のオーダーにこたえて採用人数を確保するためには、ポイントをおさえた採用活動を行わなければなりません。
この記事では、中途採用がうまくいかずに悩んでいる採用担当者に向けて、採用基準の重要性や策定方法、人材を見極めるポイントなどを解説します。中途採用のポイントをおさえて、採用を成功させましょう。
中途採用を成功させられない理由

中途採用に限らず、いまは採用全体の難易度が上がっています。経営層や現場の「即戦力となる優秀な人材がほしい」という要望に対し、採用担当者がすぐに適切な人材を見つけてこられるわけではありません。自社の求める人材を採用するために、計画立てた活動が必要になります。
そもそも、中途採用を成功させられない理由は何なのでしょうか。失敗例とその理由、成功させるポイントを見てみましょう。
失敗例1:採用競争が激しく優秀な人材を採用できない
まずは、求人を出しても、自社の求めるターゲットをなかなか採用できないケースです。
待てど暮らせど応募がこない場合もあり、選考が始められずに活動の序盤でつまずくことになります。
こういったケースを放置して求人内容や採用活動の改善を行わないと、ポストが空いたまま、年中人材を募集し続ける事態に陥ります。
理由①:優秀な人材はより条件のいい求人に流れる
スペックの高い人材はなかなか採用市場に現われません。なぜなら、そのような人材は、勤め先の企業が離れさせまいと何かと手を打っているからです。
ほかにも、企業はより優秀な人材を求め、求職者はより良い企業を求めるのが採用市場の常です。双方が今いる立ち位置よりも上を求めるクロス構造がこの失敗例を引き起こしていると考えられます。
企業が余裕をもって提示できる条件で「採用できる人材」と、それよりも上のスペックをもつ「採用したい人材」では、採用難易度が大きく異なります。
また、優秀な人材には取引先からのスカウトやフリーランスといったさまざまな選択肢があり、オープンな採用活動を行わないケースもあります。
たとえ採用市場に現われた場合でも、引く手あまたですぐに就職先が決まってしまうことが多いです。他社も優秀な人材が市場に現れるのをいまかいまかと待ちわびているので、採用競争が起こり、最終的にはより良い条件の求人に人材が流れます。
同時期に一斉スタートを切る新卒採用と比べると、一定期間に中途採用市場にいる優秀な人材の数には限りがあり、大きな母集団形成ができることは期待できません。
ポテンシャル採用とは、その人が現在もっているスキルや経験よりも、将来性やカルチャーマッチなどを重視して採用する手法を指します。おもなターゲットは、既卒や第二新卒、キャリアチェンジを考える20代の若手層です。
高度なスキルをもつ人材の給与水準は、採用難によって上昇傾向にあります。ハイキャリア人材の争奪戦で採用コストが釣り上がってしまったときと比べ、入社後の育成を前提にポテンシャル採用を行ったほうが、費用を抑えられる場合も多いです。
理由②: 売り手市場が続いている
2021度は新型コロナ感染症の影響で、各社は採用を控えました。しかし、2022年度に多くの業種で回復傾向となり、2023年度も引き続き求人倍率の上昇が予想されています。
厚生労働省の発表によると、2024年5月の有効求人倍率は1.24倍、新規求人倍率2.16倍です。
※出典: 厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年5月分)について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40905.html)
少子化による生産年齢人口の減少も続いており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれています。
※出典:総務省「令和4年版 情報通信白書|生産年齢人口の減少」(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd121110.html)
企業間の人材獲得競争が続くなか、今後もしばらくは採用難が続くでしょう。
求人を出すだけでは十分な応募が集まらない場合は、自社の認知度を高める施策に取り組む必要があります。SNSやオウンドメディアによって企業文化を定期的に発信し、まだ採用市場に現れていない潜在的な求職者にも共感を抱いてもらうことで、将来的に質の良い母集団形成が可能になるでしょう。
失敗例2:期待ほどの活躍をしてもらえなかった
スキルや経験を評価されて中途入社した社員には、即戦力が期待されます。しかし、時には、さまざまな要因によって採用時に期待したほど活躍してもらえない場合もあります。
理由①:面接官のスキルが不足している
採用担当者には、応募書類と、通常1回か2回の面接という短い時間のなかで求職者の適性を判断する高いスキルが求められます。
前職と仕事内容が異なるキャリアチェンジの場合は一から教える必要があり、費用も時間もかかります。しかし、未経験者のなかにも高いポテンシャルをもった人材もいます。
それとは逆に、スキルや経験は申し分ないが、カルチャー面でフィットしないパターンも多くあります。
このように、中途採用と言っても、第二新卒や既卒、キャリアチェンジを狙う他業界からの未経験者、高いスキルや経験をもつキャリア人材など、採用対象は多様です。求職者はさまざまな背景を持っており、人材の見極めが難しいのです。
自社に優秀な人材を見極めるスキルがなければ、プロに頼るのもひとつの手です。
採用代行サービスは、採用計画の立案から面接時の対応、内定者フォローまでを幅広くサポートしています。人材紹介サービスは、客観的な視点で自社に合う人材を見極めてから面接を設定してもらえるので、ある程度フィルタリングされたうえで選考を始められます。自社の採用ターゲットに直接アプローチできるダイレクトリクルーティングサービスを利用するのもおすすめです。
外部サービスを利用する際はとくに、採用基準や評価基準などを明確にして、優秀な人材の取りこぼしがないように気を付けましょう。
理由②:中途社員が新しい環境に慣れるには時間がかかる
同業種からの中途入社者で高度なスキルや知識をもっていたとしても、やり方や環境が変われば、すぐに本来の実力を発揮するのは難しいかもしれません。周囲から即戦力として高く期待されている場合は、本人に過度なプレッシャーを感じさせ、体調を崩してしまう可能性も考えられます。
オンボーディングとは、新入社員が自社に定着して活躍できるように働きかける施策を指します。
中途入社者にも、企業文化やルールを学ぶ研修が必要です。オンボーディング施策はほかに、同時期に中途入社した社員が仲を深められるウェルカムパーティー(歓迎会)や、企業が金額を負担するランチ会などの例があります。
オンボーディングによって、新入社員は自身が歓迎されていると感じ、緊張から解放されていち早く実力を発揮できるでしょう。
失敗例3:早期離職されてしまった
早期離職とは、新しく入社した人材が3年以内に離職することを指します。
その人材の採用にかかった費用と利益の採算がとれる前に辞められてしまうと、経済的損失になるほか、再び採用活動を行うコストも追加で発生します。
理由①:採用ミスマッチが発生した
厚生労働省によると、令和4年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由で、前年と比べて上昇幅が最も大きかったのは男性では「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」、女性は「仕事の内容に興味を持てなかった」でした。
※出典:厚生労働省「令和4年 雇用動向調査結果の概要」(https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/23-2/dl/gaikyou.pdf)
働き手の中で、ライフワークバランスやキャリアにおける自己実現を重視する傾向が高まっています。選考の中で企業と求職者がお互いの情報を十分に伝え切れなかったり、採用したい(されたい)があまりに事実とは異なる過剰なアピールをしてしまったりすると、入社したあとで「想定と異なる」という気持ちから早期離職につながるでしょう。
理由②:転職癖がある人材だった
短期間にささいな理由で転職を繰り返す、いわゆる「転職癖」がある人材も採用市場には存在します。何かしらの目的と計画性をもっている人材は別ですが、もしスキルや協調性の不足を選考で見抜けなかった場合、自社も短期間で離職されてしまう可能性が高まります。
数年で複数の企業に入社実績がある人材にはキャリアの目的や計画を質問して、自社で長く働いてもらえそうかを見極めましょう。
書類選考や面接で見るべき基本的なポイントは「中途採用で良い人材を見極めるポイント」章で紹介します。
失敗例4:プロパー社員となじまなかった
中途入社者は新たな知識やマインドを持ち込んでくれますが、中には変化を受け入れられず、前職でのやり方に固執してしまう人もいます。今の会社でどう生かすかといった姿勢がなく、本人のこだわりがあまりにも強いと、プロパー社員との間に軋轢が生じるかもしれません。
理由①:選考の際にプロパー社員との親和性を考慮しなかった
同業種からの採用の際に多いのは、ハロー効果によって適切な評価が下せないケースです。ハロー効果とは、対象人物のひとつの好意的要素から無意識にすべてをポジティブなほうへ判断してしまうこと。つまり、スキルや経験の面で魅力的な人物に対して、カルチャーマッチをつい軽視してしまう傾向があるのです。
採用要件を改めて確認し、求める人材像のカルチャー面を明文化して採用基準に取り入れましょう。たとえば、「向上心のある性格」「自主的に動ける人物」などです。
自社で活躍しているプロパー社員の特徴を洗い出して、ペルソナを作成するのもよいでしょう。
理由②:面接官と現場の求める人材像が異なっていた
実際に面接を担当する社員と現場社員とで、採用目的が異なっているケースです。
たとえば、現場では業務の垣根を超えて自ら手を動かしてくれる人材を求めているにも関わらず、面接を担当する役職者は将来性を踏まえて専門性の高い人材を採用するといったケースがよく起こります。新入社員の教育を担当するのは現場なので、ニーズに沿わない人材だと現場に余計な負担がかかることもあります。
採用に関わる人全員で採用要件を共有しましょう。採用要件は、現場の採用ニーズに基づいたものでなくてはなりません。
また、とくに技術職などの専門的な知識を要する職種では、面接官が候補者のスキルを正確に判断できない場合があります。一度は現場社員に面接官を担当してもらうようにしましょう。
中途採用を成功させるポイント

そのほかにも、中途採用を成功させるために、押さえておくべき基本的なポイントがいくつかあります。ここではおすすめの採用活動の時期や、採用基準の見直しなどについて解説します。
採用市場が活性化する時期を狙う
採用スケジュールがほとんど決まっている新卒採用と異なり、中途採用は会社の都合に合わせて採用活動を行えます。しかし採用市場が沈滞している時期に募集をかけても、求める人材が市場に少数しかいないので応募者の数は増えません。
中途採用では採用市場が活性化する時期を狙うことが、成功のポイントです。一般的に採用市場が活性化するのは、2月中旬から3月下旬と、8月中旬から9月下旬です。しかし新型コロナの影響で各社が採用を手控えたときのように、採用動向は常に変化します。いつでも採用を開始できるように、常に採用動向に対してアンテナを張り巡らせておきましょう。
また採用市場が活性化する時期には、他社も採用活動を行います。ライバルが増えるので、争奪戦に勝つために自社なりの戦術を立ててください。
採用スケジュールは逆算して立てる
採用計画は、会社の経営戦略と事業の発展に欠かせません。人材の欠乏は、会社の存続に関わります。もし「〇月までに3名」のように入社予定時期のオーダーが現場から上がっているなら、入社予定時期に間に合うように逆算してスケジュールを立てましょう。
採用計画を立てる全体の流れは次のとおりです。
- 経営層や現場へのヒアリング(いつまでに、どのような人物が、何人ほしいか)
- これまでの実績から自社採用の課題を抽出
- 採用基準を作成(必要人数や雇用形態も確定する)
- 採用手法(求人広告、スカウト、人材紹介など)の選定
- 採用スケジュールの決定
採用スケジュールは、求人を開始して書類選考や面接を行うのに最低1カ月、入社して活躍を始めるまでに2カ月程度はみましょう。また採用をゴールにせず、育成研修が終わるまでをゴールとして計画すると良いです。
採用基準を見直す
採用計画の中でも、採用基準の策定は重要です。公平に評価するための指針となる採用基準がないと、面接官の好き嫌いで採用が決定される恐れがあります。
面接を担当する社員の部署や立場によって見るポイントを明確にしておくと、選考の基準がよりはっきりしていきます。パートごとにポイントをおさえておきましょう。
- 人事:おもに人物面や、退職理由など、ネガティブな要素がないかに注力
- 現場:おもにスキル面や、一緒に働くメンバーとして好ましいか
- 経営陣:会社のビジョンや方針に対する共感度などのマッチング
また既存の採用基準があったとしても、使いまわせるとは限りません。採用動向や現場の求める人物像は変化するため、その都度見直して採用基準を最新のものにしましょう。
採用基準の策定方法
採用基準の策定方法は次のとおりです。
- 転職トレンドの把握
- コンピテンシーの洗い出し
- 現場や経営者層とのすり合わせ
- コンピテンシーの確定
- 各選考フローに反映
まず、転職トレンドを把握します。求人倍率が高く採用難易度が高い時期には、採用基準が厳しいままでは欠員の補充もままなりません。また求職者が望んでいるものの傾向(ワーク・ライフ・バランスや企業の安定性など)を把握しておくのもポイントです。
次に求める人物像を明確化します。コンピテンシーとは、高い業績を出している人物に共通する特性です。新しい人材を必要としている部署において、モデルとなる優秀な人材をピックアップして、成果につながる行動を分析しましょう。
現場や経営者層とコンピテンシーをすり合わせて修正を行い、求める人物像を確定します。コンピテンシーが確定しても、各選考フローで応募者を見極められなければ意味がありません。最後にコンピテンシーに当てはまる人物かを見極めるための、評価基準や質問項目を整えます。
自社のビジョンや魅力を積極的にアピールする
求職者に「この会社は魅力がない」と思われてしまわないように、ホームページやSNS、求人広告、面接時などを利用して、自社のビジョンや魅力をアピールしましょう。
特に注意が必要なのは、面接です。面接では企業が評価するだけでなく、求職者からも評価されます。求職者に否定的な質問をしたり、威圧的な態度をとるのはデメリットが多くおすすめできません。面接官には事前に威圧的な態度を取らないように伝えておくと良いです。
また誰が面接するかも、ポイントです。効果的なアピール方法には、最終選考での社長面接があります。社長自らが自社のビジョンや企業文化、自社の魅力などを語れば、説得力が強くアピール効果も大きいでしょう。
スピード感をもって対応する
採用にはスピードも大切です。選考がゆっくり進んでいると先に他社から内定が出て、そちらに入社してしまうリスクがあります。応募者が併願していることを忘れずに、連絡事項はスピーディーに行いましょう。
現職で活躍中の求職者は、平日昼間の時間帯になかなか面接予定を入れられません。早朝や夜遅めの時間帯の面接も受け付ければ、日程調整がスムーズになります。
ほかにも、連絡時間や頻度にも気を使うと、会社に対する好感度はアップします。連絡する際は、求職者が過度な不安を抱いてしまわないように、相手の気持ちに配慮しながら対応するようにしましょう。
「働きたい」と思ってもらえる企業イメージを作る
中途採用か新卒採用かに関わらず、求職者が優位な売り手市場が続いており、人材獲得に悩む企業は増えています。
採用活動を行う時期やアピール方法を工夫しても、外からみて「働きたい」と思ってもらえる企業でなければ応募は集まらないでしょう。
そのためには、SNSや採用サイト、ブログ、イベントなどを通じて地道なカルチャー発信を続ける手法があります。noteなどのブログサービスやX(旧Twitter)などは無料で始められるのでおすすめです。長期で取り組みを続けられる工数と環境を用意しましょう。
自社に良い企業イメージを抱いている人材は、たとえ一度不合格になっても数年後にスキルアップして再度選考を受けてくれたり、自分以外のマッチしそうな人材に紹介してくれたりする可能性が高まります。
また、入社後にも「働き続けたい」と思われることが重要です。株式会社学情が実施したアンケートでは、「転職したい理由」で多いのは「給与・年収をアップさせたい」「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい」「残業を減らしたい、休日を確保したい」などでした。
※出典:株式会社学情「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(転職理由)2023年8月版」(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/230802/)
実際に、ワーク・ライフ・バランスの実現は政府が推し進めるほど働き手にとっては重要な要素になっています。直接の採用活動だけでなく、採用ターゲットに「働きたい」と思ってもらえるような職場づくりに並行で取り組むことが、人材獲得への最短の道といえます。
そのほかにも、既存社員に職場を好きになってもらえれば、リファラル採用につながるのもメリットです。
中途採用で良い人材を見極めるポイント

選考のなかでどのように人材を見極めたら良いのかを知らなければ、求める人材は採用できません。書類選考と面接において、人物を見極めるポイントをそれぞれ解説します。
書類選考時の見極めポイント
書類のどのような点を評価するのかを決めておかなければ、優秀な人材を取りこぼしてしまいます。ここでは書類選考時に着目すべきポイントを、3つ紹介します。審査基準や評価方法を決める際の参考にしてください。
文書作成スキルや基本的なマナー
ざっと書類に目を通しながら、誤字脱字、誤変換、文章の読みやすさ、正確さなどを確認します。誤字脱字があったから不合格というわけではありませんが、推敲をしっかり行わずに書類を提出している可能性が高く、頻度や募集しているポジションによっては合わないでしょう。
長文の志望動機からは熱意が伝わるものですが、だらだらと書かれていたり同じ内容が繰り返されたりしている場合、読み手を意識していないのがわかります。
最近ではインターネットに掲載されている模範文をそのまま記載している書類も少なくありません。読み手を意識してわかりやすい文章作成を心がけているか、自分の言葉で表現しているかもポイントです。
経歴やスキル
経歴やスキルは、入社後に即戦力として活躍できるかを見極める重要な項目です。募集要件に合致した経歴や、スキルを持っているか確認します。
職種名が一緒でも、仕事内容が異なる場合があるので注意してください。経歴やスキルで気になる点があれば、面接時に確認できるようにメモを残すと良いです。
また「ポテンシャルの高そうな人材だけれど、今回の募集要件に合わない」という求職者は、他部署で採用できないか検討するのもおすすめです。すぐに書類を破棄せずに、面接で別のポジションに興味があるか求職者に声をかけてみましょう。
実績
これまでの実績が、事実に基づいて相対的(できれば数字)に表されているかどうかも重要なポイントです(何人中何位の成績や、何%の達成、その成果が社会に与えたインパクトなど)。
また、社内評価がわかるような、表彰などの記載もポイントになります。
転職理由と在籍期間
転職理由と在籍期間は、早期退職しやすいかの判断材料になります。
1~3年で転職を繰り返している場合、飽き性で転職しても長く続かない可能性があります。しかしやむを得ない事情やポジティブな理由のケースもあるので、在籍期間と転職理由はセットで考えましょう。
次のチェック項目に当てはまる求職者は、離職リスクが高い可能性があるので注意が必要です。
- 履歴書の年月日の記入漏れが多い
- 他業種・他職種間の転職が多い
- 長く勤めていても昇給・昇格をしていない
- 1~3年以内に転職を繰り返す
書類のみでは判断しづらい場合には、書類選考では不採用にせず、面接時に不明点を質問してみてください。
面接時の見極めポイント
短時間で求職者を見極めるためには、事前の準備が必要です。求職者はほとんどの場合、回答を用意しています。表面だけ面接の形をとっても、なかなか本音の部分は見えません。
採用基準を面接フローにしっかり落とし込み、どのような質問をしたら相手の本音を引き出せるのか事前に準備をしておきましょう。ここでは面接時の、ポイントを3つ紹介します。
退職理由と入社の動機
「退職理由と入社の動機」は、自社で活躍し長く働いてもらえるかを確認するための質問項目です。
「今の会社では、やりたいことができない」というような答えがよくありますが、退職理由や入社の動機としては不十分です。即戦力として長く活躍できるか見極めるためには、病気や家族の問題など相手が触れてほしくない点に配慮しつつ、一歩踏み込んで詳細を聞いていきましょう。
たとえば、求職者が前職の退職理由を「長時間労働が常態化していたため」と答えたとします。長時間労働には、会社の業績不信や長時間労働の常態化といった会社側が問題のケースと、ミスの多さや仕事の遅さなどの本人が問題のケースがあります。
面接官は、次の質問で、問題があったのは会社なのか本人なのかを見極めなければなりません。独りよがりで「会社が悪い」と責任転嫁しているなら、入社しても同様の問題を起こしてしまいます。
また、退職理由の本音をうまく聞き出せない場合、入社動機から探るのも有効です。次の会社に求めるものを尋ねると「ワーク・ライフ・バランス」「給料」「人間関係」などの回答が出てきますが、ほとんどのケースで前の会社では得られなかったものです。
- 「転職を決意したきっかけはなんですか?」
- 「どのような基準で、転職先を選定されていますか?」
- 「前の会社で実現したくてもできなかったことはありますか?」
- 「次の会社に求めることはなんですか?」
即戦力として活かせる経験とスキル
中途採用で入社した人は、即戦力を期待されます。現場が求めている経験やスキルを求職者が持っているか、採用基準に沿って面接で確認しなければなりません。
しかし、専門職や技術職の場合、人事担当者が詳細まで確認するのは困難です。
可能なら現場を知る社員に同席してもらい、専門的な質問で深掘りしてもらいましょう。現場社員の同席が難しい場合には、求職者に具体的なエピソードを尋ねると、良い判断材料が得られます。
- 前職の仕事内容について詳細を教えていただけますか?
- 〇〇(会社が求めている経験やスキル)の経験は、何年くらいありますか?
- 業務において苦労した点を、エピソードを交えて話していただけますか?
臨機応変なコミュニケーション力
コミュニケーション力が必要なのは、営業職や接客業だけではありません。どのような職種でもコミュニケーション力は重要です。
面接官との相性によって評価が左右されやすいので、評価のブレに注意しながら求職者を評価しましょう。
コミュニケーション力とは、人間関係を円滑に構築・維持する能力です。明るくよく話す外交的な人が、必ずしもコミュニケーション力があるとはかぎりません。
一方通行で話す人よりも、双方向でコミュニケーションできる人のほうがコミュニケーション力が高いと言えます。
そのため、話す内容だけではなく、話の聞き方、相槌や笑顔、言葉のキャッチボールのうまさなど、さまざまな観点からコミュニケーション力を評価してください。
評価方法には、自己紹介のようなプレゼンテーションの時間を与える方法や、答えの範囲を制限しないオープンクエスチョン(例:「〇〇についてはどう思いますか?」)を投げかける方法があります。また、事前に回答を準備しておけない質問を挟み、臨機応変なコミュニケーション力をみても良いでしょう。
- 簡単に自己紹介していただけますか?
- もしやったことのない業務を任されたとしたら、最初に何をしますか?
- 同僚や上司との人間関係で大事なことは何だと思いますか?
事前に評価基準をすり合わせておくことも大切
ひとえに面接といっても、フェーズによって評価するポイントが異なります。おもに採用担当者が採用基準に合致しているかを確認する一次面接、現場の担当者が同席してスキルやともに働いていけるかを確認する二次面接、社長や役員との顔合わせも兼ねた最終面接などです。
採用基準を決め、フェーズごとの評価基準を取りまとめておくのが人事の役割です。
また、面接官の個人的な好き嫌いや評価のばらつきによって優秀な人材を逃さないためにも、事前に採用基準を面接官と共有する必要があります。選考メンバーを集めて打ち合わせをする時間を取り、面接で確認してほしいポイントを明確に伝えましょう。
中途採用後のフォローも忘れずに

採用担当者の役割は、求職者の入社後も続きます。早期退職を減らすためにも、求職者を採用後に放置してはいけません。特に中途採用の場合、周囲が「教えなくてもできるだろう」「そのうち馴染むのでは」などと考えがちです。
入社後には人的つながりのフォローやヒアリングを行い、早く会社になじめるようにフォローしましょう。少なくとも入社後2カ月程度は見守る必要があります。また企業理念や、部署単位の業務・役割を知ってもらうためにも社員教育が必要です。
採用のポイントを押さえマッチング精度が高い選考を実現しよう

中途採用では現場が求める人数分、スキルや経験を持つ人を確保する必要があります。優秀な人材は採用市場にそれほど多くないため、採用戦線に勝つために自社なりの戦略をもって臨まなければなりません。
採用活動の時期、採用基準の策定、選考フローごとの評価基準など、採用のポイントを押さえて、マッチング精度の高い選考を実現しましょう。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。