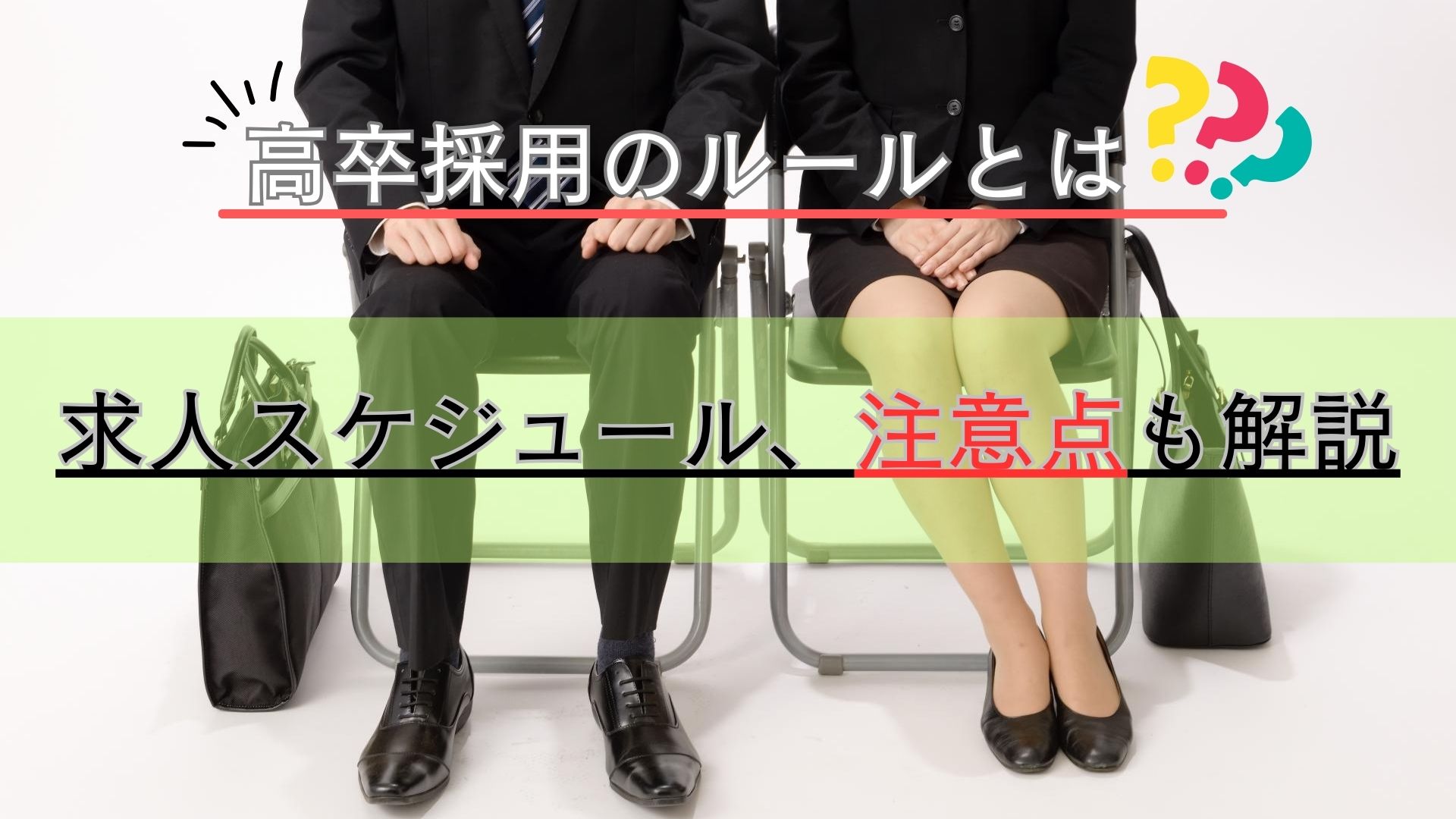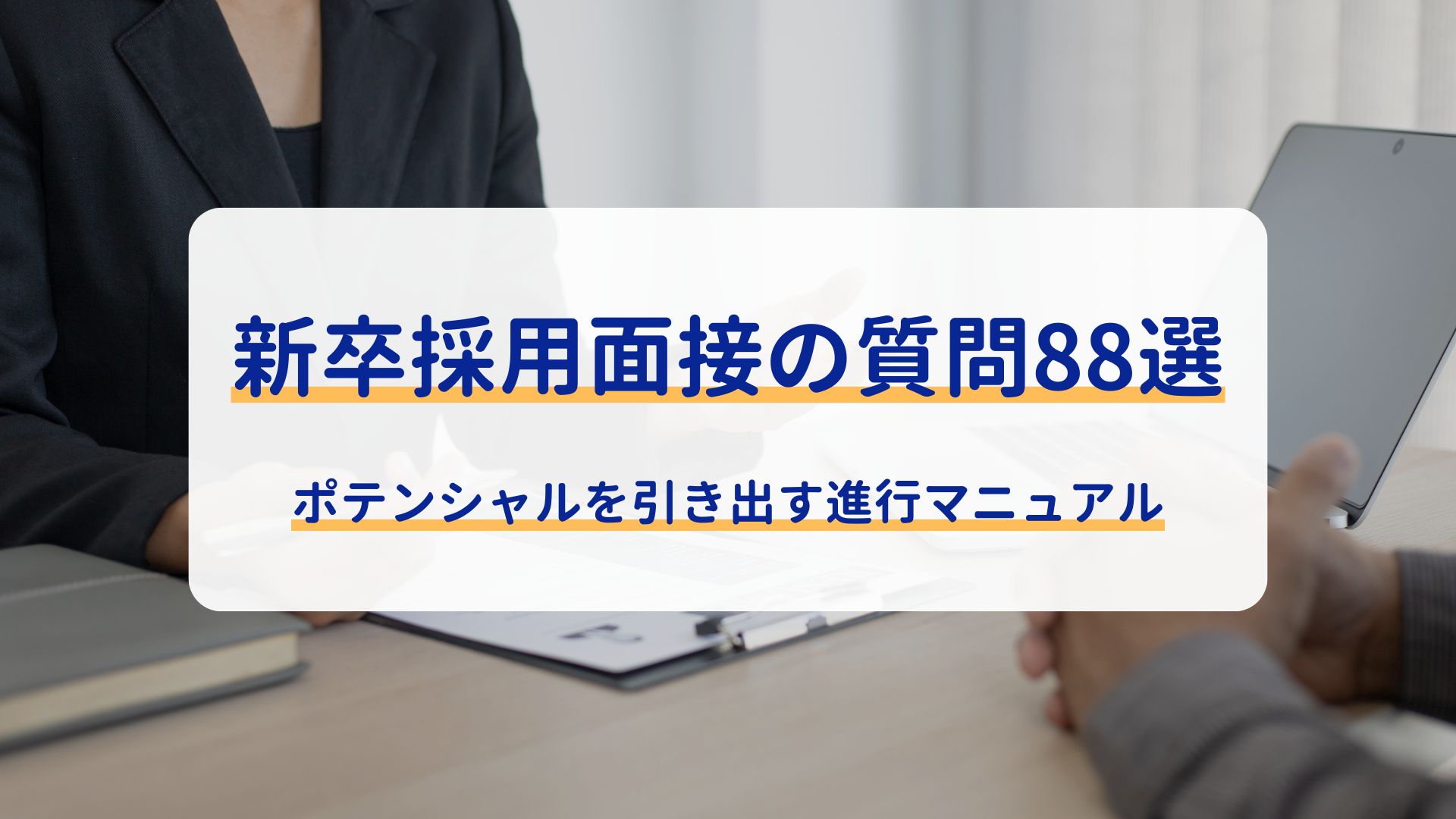少子化によって労働人口が減少し、採用市場では採用難が続いています。人材獲得競争が激化し、新卒採用や即戦力採用が難しくなっているのです。
そこで、最近では第二新卒採用に注目が集まっています。
本記事では、第二新卒採用のメリット・デメリットや採用を成功させるポイントなどについて解説します。第二新卒採用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
第二新卒とは
第二新卒とは、学校を卒業後に就職してから3年以内で離職し、再び職を探している人材のことです。大学卒業後すぐに就職している場合は、25〜26歳くらいまでの層を指します。
近年、採用市場では人材獲得競争が激化しており、とくに即戦力採用が難しい状況です。そのため、多様な人材を採用するべく、第二新卒採用に取り組む企業が増えています。
第二新卒はヤングキャリアやキャリア層と比べるとスキルや経験は浅いですが、高いポテンシャルを持つ人材が多く存在しています。成長意欲や仕事に対する意識の高さに注目が集まり、転職市場での需要が高まっているのです。
第二新卒はいつまで?
第二新卒・既卒・ヤングキャリア・キャリアの違いは、次の通りです。
|
年齢 |
社会人経験 |
定義 |
|
|
既卒 |
|
なし |
学校卒業後、留学やボランティア活動に力を入れるなどして、進学も就職もしていない人材 |
|
第二新卒 |
25~26歳 |
3年未満 |
1~2年の社会人経験を持つポテンシャル人材 |
|
ヤング |
26~29歳 |
3年以上 |
3~7年の社会人経験があり、同業種でのステップアップまたはキャリアチェンジを考えている人材 |
|
キャリア |
30歳以上 |
8年以上 |
高いスキルと経験がある即戦力人材 |
第二新卒の明確な定義はなく、企業によって判断が変わる場合があります。おおよそ社会人経験が浅い、若手人材を指す場合が多いでしょう。
第二新卒は新卒採用or中途採用?
第二新卒は、正社員としての職務経験があるため、中途採用として扱われます。一方、2010年に青少年雇用機会確保指針が改正されたことにより、学校卒業後3年以内の既卒者は新卒枠で応募ができるようになりました。
新卒の採用難によって第二新卒採用に注目が集まっている
近年、新卒の採用難によって、第二新卒採用に注目が集まっています。
株式会社学情の調査によると、20代キャリア採用の実施理由は「新卒採用だけでは、若手採用を充足できない」が最多でした。また、採用計画に関する調査では、キャリア採用と新卒採用の割合は「5:5」が最多です。「キャリア採用の人数を、前年度より増やす予定」と回答した企業が3割を超えています。
長引く採用難を乗り越えるため、第二新卒を含む20代のキャリア採用に注目が集まっているのです。
※参考:株式会社学情「20代を対象としたキャリア採用に期待することに関する調査」
※参考:株式会社学情「採用計画に関する調査」
第二新卒を採用する5つのメリット

第二新卒を採用するメリットについて解説します。
ポテンシャル採用が目指せる
第二新卒は、働く意欲が高い人材が多いため、ポテンシャル採用に向いています。
ポテンシャル採用とは、経歴や実績だけでなく、求職者の潜在能力にフォーカスした採用活動のことです。人材獲得競争の激化により即戦力採用が難しくなっている今、即戦力採用だけでなく、成長意欲やチャレンジ精神が高いポテンシャル採用を目指す企業が増えてきています。
これまでは、第二新卒採用を積極的に行っていた企業が多くなかったため、将来の幹部候補になり得る優秀な人材が眠っている可能性があります。
仕事への目的意識が高い
第二新卒を含む1990年代半ばから2010年代半ば生まれの「Z世代」と呼ばれる層には、キャリア形成において必要以上に企業に頼ることなく自身で構築していきたいと考える傾向があります。
株式会社学情の調査によると、社会人経験3年未満の「第二新卒」が転職で実現したいことは「希望する仕事に従事できること」が最多です。この調査結果により、第二新卒は「仕事のやりがい・達成感」を重視していることが明らかになりました。
第二新卒を含む20代の転職では、転職を通じてキャリアを形成したいと考える人が増加傾向にあります。実際に企業側からも「成長意欲が高い」「キャリア形成への関心が高い」などの声が多く聞かれます。
※参考:株式会社学情「転職理由に関する調査」
※参考:株式会社学情「20代採用の採用活動に関する調査」
柔軟性があり適応力が高い
第二新卒は社会人経験が浅く、前職の企業文化に染まり切っていないため、基本的なビジネススキルを持ちつつ、新しい知識や経験を吸収する柔軟性に長けた人材が多い傾向にあります。
即戦力採用は高いスキルと実績は持っていますが、前職のやり方を引きずる方もいます。いくら能力が高くても、自分本位な働き方では、幹部候補として活躍してもらうのは難しいかもしれません。
一方で、仕事に対する意欲が高い人材が多い第二新卒は、新しい仕事のやり方も柔軟に吸収できるため、将来の幹部候補としての成長が期待できるでしょう。
研修などの教育コストが抑えられる
第二新卒は、前職で基本的なビジネスマナーやパソコン操作の研修を受けている場合が多いため、入社後の基礎的な研修が必要ありません。研修を行う場合も、能力に応じて研修内容を省略できるので、研修や教育に必要なコストを抑えられます。
内定者フォローの期間が短い
第二新卒は、入社までの期間が短いため、内定者フォローの期間が短くて済みます。
新卒採用は入社時期が決まっているので、長期にわたって内定後フォローを行わなければなりません。内定者フォローの期間が長期化すると、採用担当者の工数と負担が増加してしまいます。
また、入社までの期間を短くすることで、入社意欲を高い状態で維持しやすく、内定辞退率の減少効果も期待できるでしょう。
第二新卒を採用するデメリット
第二新卒を採用するデメリットについて解説します。
早期退職のリスクがある
第二新卒は、3年以内で離職していることから、再び早期退職するリスクも少なからずあります。
前向きな理由で転職する人も多いものの、なかには「仕事が合わなかった」「会社が嫌だった」など、ネガティブな理由で退職する人もいることも事実です。選考時に「早期退職を繰り返していないか」「離職癖がついていないか」などをチェックしましょう。
スキルや経験が比較的浅い
第二新卒は、スキルや経験が比較的浅いため、即戦力にならない可能性が高いです。
第二新卒の転職は、キャリアチェンジが多く、専門知識や業界独自のルールなどは研修で教えなければなりません。即戦力が必要な場合は、第二新卒よりも社会人経験が長いヤングキャリアやキャリア層の採用を目指した方が良いでしょう。
第二新卒採用を成功させる3つのポイント

第二新卒採用を成功させるポイントについて解説します。
採用要件を明確化する
第二新卒採用を実施する際は、企業が求める人物像を明確化することが大切です。
スキルや経験、仕事に対する価値感などは、求職者によって大きく異なります。ポジティブな理由で転職する方がいる一方、仕事が嫌で逃げるように辞めてしまった方もいるかもしれません。また、求める人物像によっては、第二新卒よりヤングキャリアやキャリア層の方が適している場合もあります。
採用のミスマッチを防ぐためには、求職者のパーソナリティに関する項目を含んだ採用要件を設定しましょう。
退職・転職理由を聞く
早期退職のリスクを回避するには、前職の退職理由を聞くことがポイントです。
面接で退職理由を聞いてしまうと、選考を突破するために嘘の理由を答える可能性があります。誤った情報はミスマッチを誘発し、双方に損失を与えるため、選考前にカジュアル面談を設けて相互理解を深めるのがおすすめです。
カジュアル面談とは、選考前に企業と求職者がリラックスしながら対話してお互いの知りたい情報を交換する機会のことです。カジュアル面談では合否を出さないため、本音で話せます。
カジュアル面談は、ミスマッチの防止だけでなく、面談数の増加によって志望度アップなどの効果も期待できます。
第二新卒に特化した採用手法を選ぶ
第二新卒採用を成功させるには、採用ターゲットに適した採用手法を選びましょう。
大手求人サイトは、登録者数が多い一方で、掲載企業数も多いため求人情報が埋もれてしまう可能性があります。しかし、特化型の求人サイトであれば、採用ターゲットに効率良くアプローチできます。
そのため、第二新卒採用を目指すなら20代のキャリア採用に特化した「Re就活」がおすすめです。登録会員数の93.3%が20代で、さらに登録者数280万人のうち、195万人がヤングキャリア・第二新卒です。
働く意欲の高い求職者が多いので、ポテンシャル採用に適しています。
第二新卒採用を目指すなら20代のキャリア採用に特化した「Re就活」がおすすめ
近年、人材不足を解消するために、第二新卒採用に注目が集まっています。第二新卒には、働く意欲や自己成長に対する意識が高い求職者が多く、新卒採用に苦戦している企業が、第二新卒採用にシフトしていく傾向が見られます。
株式会社学情では、これまで第二新卒採用や20代のキャリア採用を数多くサポートしてきました。第二新卒採用にお困りの方は、株式会社学情へお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。