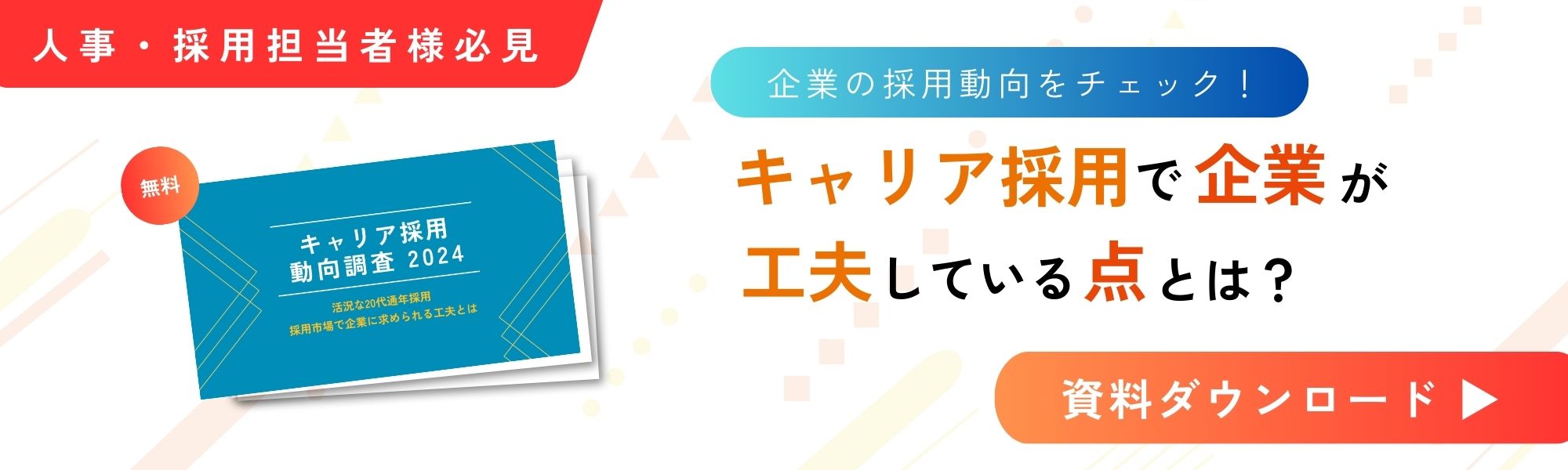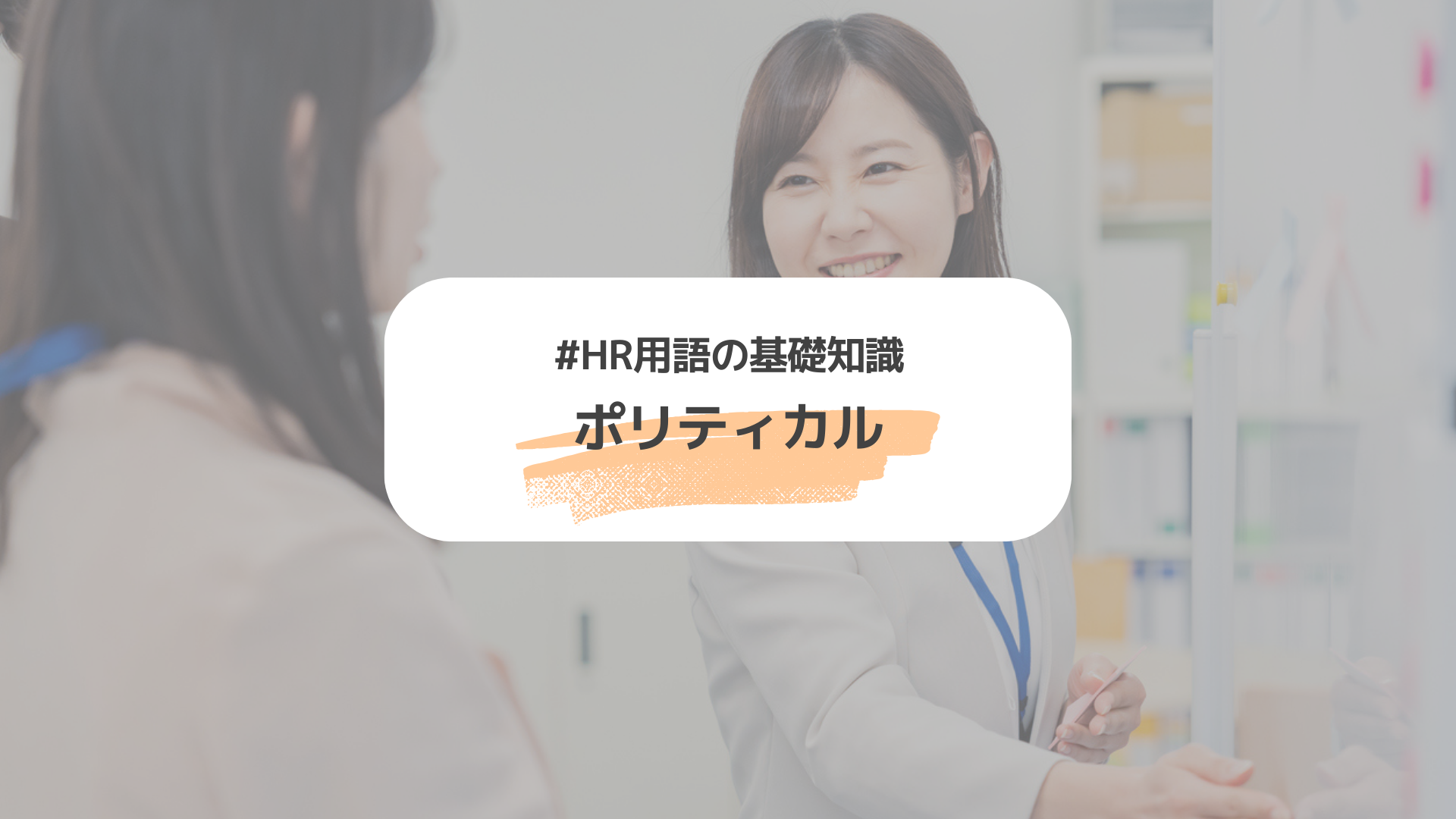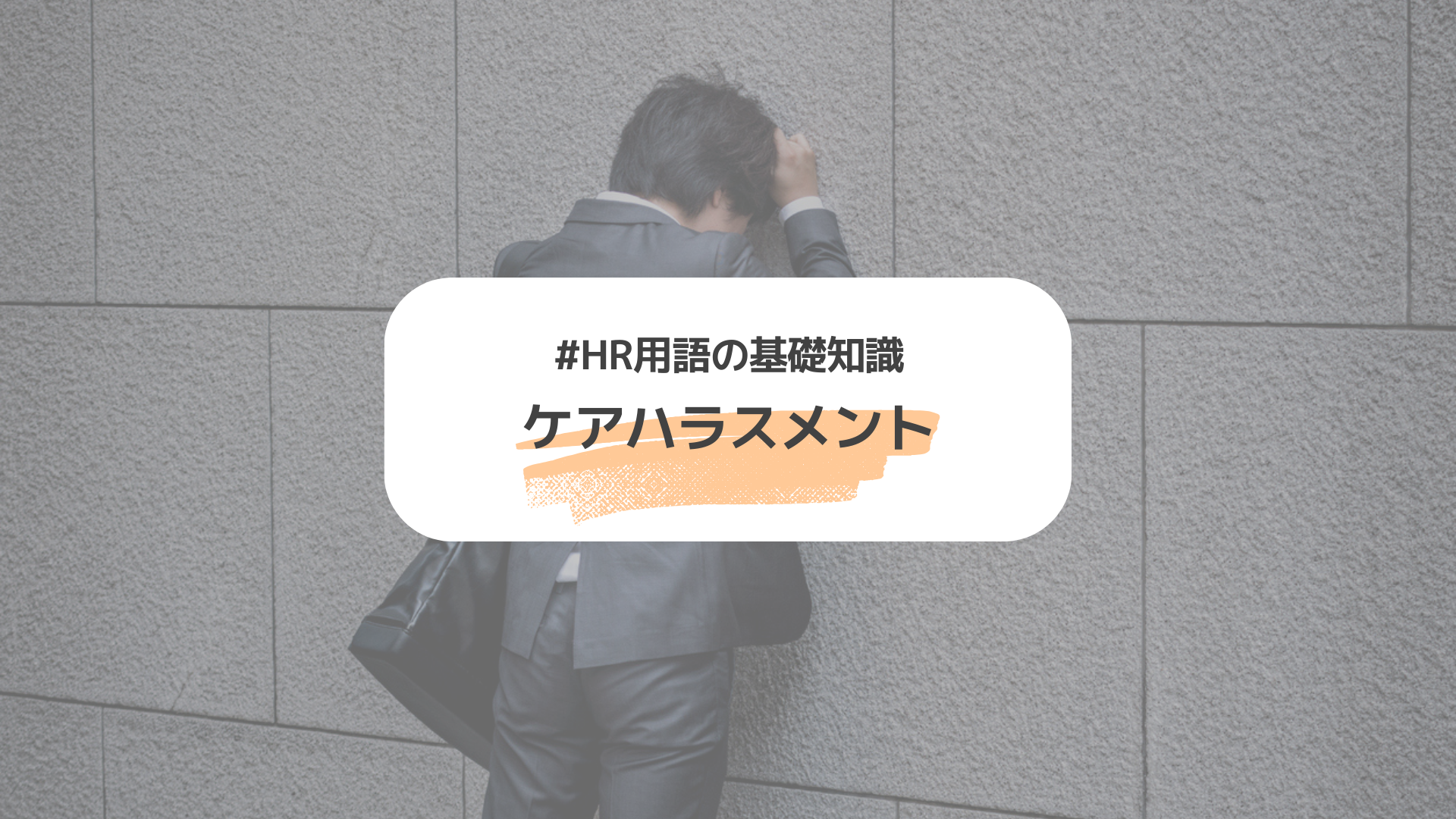【自己診断】HSPとは?特徴や長所の活かし方、上手な付き合い方
2024.02.05


「HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)」とは、ひといちばい繊細な気質を持って生まれた人々を指します。この特性は「DOES(ダズ)」と呼ばれ、深い思考、刺激への敏感さ、共感力、感覚の鋭さなどで現れます。
この記事では、HSPの特徴や生き方、日常での注意点などを詳しく解説します。
HSPとは
HSPとは「ひといちばい繊細な人」です。
「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の頭文字をとって、「エイチ・エス・ピー」と読みます。SNSなどでは「繊細さん」とも呼ばれています。
HSPは、生まれつき視覚や聴覚などの感覚が敏感だったり、非常に感受性が高く繊細だったりする気質のことを指します。疾患ではありません。
この特性は、アメリカの心理学者、エレイン・N・アーロン氏が1996年に提唱しました。アーロン氏の説では、HSPは全人口の15~20%とされます。つまり、5人に1人はHSPの傾向があるのです。
稀ではないHSPですが、その気質をもつか否かの判断は主観によるところがおおきく、周囲の共感を得るのがむずかしいと考えられます。このために生きづらさを抱えるHSPの人々も多いでしょう。
しかし、この「生きづらさ」は、その特性にどう付き合っていくかによって緩和できます。
HSPの特徴|「DOES(ダズ)」と呼ばれる4つの特性
HSPは、周囲の状況にとても敏感です。この気質をもつ方は職場や家庭等の中で気疲れしやすく、生きづらく感じている方も多いと言われています。
提唱者のアーロン氏が「DOES(ダズ)」と名付けた4つの特性があります。
- Depth of Processing(深い思考)
- Overstimulation(刺激への敏感さ)
- Emotional response and empathy(共感力)
- Sensitivity to Subtleties(感覚の鋭さ)
それぞれくわしく説明します。
Depth of processing(深い思考)
- 一を聞いて十のことを想像できる。
- 調べ物をはじめると深く掘り下げ、その知識の深さについて周囲に驚かれる。
- お世辞をすぐに見抜いてしまう。
- 物事を始めるまでにあれこれ考え、時間がかかる。
- その場かぎりの快楽よりも、生き方や哲学的なものごとに興味があり、浅い人間や話が嫌い。
Overstimulation(刺激への敏感さ)
- 人混みや大きな音が苦手。
- 友達との時間は楽しいものの、気疲れしやすい。帰宅すると、どっと疲れる。
- 映画や音楽、本等の芸術作品にとても感動して泣きやすい。
- 他人のちょっとした言動に傷つき、いつまでも忘れられない。
- ささいなことでも過剰なほど驚いたり、ショックを受けたりする。
Empathy and emotional responsiveness(共感力)
- 人が怒られていると自分のことのように感じて、傷ついたり、お腹が痛くなったりする。
- 悲しい映画や本などの登場人物に感情移入して号泣する。
- 人のちょっとした仕草、目線、声などに敏感で、相手の機嫌や思っていることがわかる。
- 幼児や動物の気持ちも察することができる。
Sensitivity to subtleties(感覚の鋭さ)
- 機械音や時計の音が気になってしまう。
- 強い光や日光のまぶしさが苦手。
- 近くにいる人の口臭やたばこの臭いで気分が悪くなってしまう。
- カフェインや添加物に敏感に反応する。
- 肌着のタグやチクチクする素材が気になってしまう。
- 第六感が働き、よく当たる。
HSPのセルフチェックリスト
HSPの傾向をもつかどうかは、ある程度自分で確認することができます。
以下のセルフチェックリストに、少しでも当てはまれば「はい」/まったく当てはまらないか、あまり当てはまらない場合には「いいえ」と答えてください。
- 自分をとりまく環境の微妙な変化によく気づくほうだ。
- 他人の気分に左右される。
- 痛みにとても敏感である。
- 忙しい日々が続くと、ベッドや暗い部屋などプライバシーが得られ、刺激から逃れられる場所にひきこもりたくなる。
- カフェインに敏感に反応する。
- 明るい光や強い匂い、ざらざらした布地、サイレンの音等に圧倒されやすい。
- 豊かな想像力を持ち、空想に耽(ふけ)りやすい。
- 騒音に悩まされやすい。
- 美術や音楽に深く心動かされる。
- とても良心的である。
- すぐにびっくりする(仰天する)。
- 短期間にたくさんのことをしなければならない時、混乱してしまう。
- 人が何かで不快な思いをしているとき、どうすれば快適になるかすぐに気づく(たとえば電灯の明るさを調節する、席を替える等)。
- 一度にたくさんのことを頼まれるがイヤだ。
- ミスをしたり、物を忘れたりしないようにいつも気をつける。
- 暴力的な映画やテレビ番組は見ないようにしている。
- あまりにもたくさんのことが自分のまわりで起こっていると、不快になり、神経が高ぶる。
- 空腹になると、集中できないとか気分が悪くなるといった強い反応が起こる。
- 生活に変化があると混乱する。
- デリケートな香りや味、音、音楽等を好む。
- 動揺するような状況を避けることを、普段の生活で最優先している。
- 仕事をする時、競争させられたり、観察されていると、緊張し、いつもの実力を発揮できなくなる。
- 子供のころ、親や教師は自分のことを「敏感だ」 とか 「内気だ」 と思っていた。
引用:「ささいなことにもすぐに「動揺」してしまうあなたへ。」エレイン・N・アーロン(著)・冨田香里(訳)講談社/ソフトバンク文庫
質問のうち12個以上に該当した場合は、HSPの気質があるとされます。また当てはまるものが多いほど、HSPの度合いも高いとされます。
ただし、逆に「はい」がひとつかふたつしかなくても、その度合いが極端に強い場合は、HSPの気質があるとされます。
HSPの長所・短所
HSPにはストレス(刺激)に弱い一面がありますが、裏を返せば、それだけ他者からの刺激を深く細かく捉える能力に恵まれているともいえます。
HSPの長所と短所を整理します。
HSPの長所
ひとの言動から相手の気持ちを察する能力や共感力が高く、気配りや思いやりをもった行動ができる人が多くみられます。
また、感受性や想像力が豊かで、クリエイティブなことに対して深い理解をしめす傾向もあります。
- 共感力が高く、人の痛みがわかる。
- 思いやりがあり、気配りができる。
- 「人を助けたい」「役に立ちたい」との感情が強い。
- 細かいところに気付く。
- こつこつ努力する。
- 感受性や想像力が豊かでクリエイティブ。
- 共感力が高く、人に配慮ができる。
- 心配性(先のリスクを想像し、対策を考える)。
- 空気を読む力、察する能力が高い。
- 丁寧に仕事をする。
- 誰とでも平等に接することが出来る。
共感力や、相手を尊重し理解する力は、他者との良好な関係を築くのに役立ちます。人間関係やチームワークで優れた成果を出せるでしょう。
また、自分の疑問を追求するために深く情報収集ができ、整理も得意なので、学習や研究といった専門的な分野での活躍が期待できます。
HSPの短所
一方、気を遣いすぎて疲れてしまったり、傷つきやすかったりする一面もあります。
- マイナス思考に支配されてしまうことがある。
- 人の言動を過剰に気にしてしまうときがある。
- 失敗を恐れて優柔不断な面がある。
- 些細なことで傷ついてしまう場合がある。
- 過去の失敗がいつまでも引きずってしまうことがある。
- マルチタスクが苦手な傾向がある。
- 丁寧なあまり、時間がかかりすぎることがある。
本人がHSPの気質と上手く向き合うには
対処するには、自分にとってのストレッサーを上手く避けるなどの「ストレスコーピング」が効果的な場合があります。コーピングとは、ストレスがかかる状況に対処するための方法や戦略を指します。
コーピングの例:
- 苦手な場所には行かない
- 環境の変化があった際、いつもより体調に注意する
- 他人の感情を強く受け止めすぎないようにする
くわしい種類と特徴、導入方法などはこちらの記事をご覧ください。
HSPの傾向をもつ人との上手な付き合い方
HSPの傾向をもつ人は、気遣いができるゆえに疲れやすかったり、自分自身を責めやすかったりする面があります。しかし、企業や周りからの働きかけによって、得意な分野でポテンシャルを発揮させることができれば非常に頼りになる存在です。
職場にHSPの傾向をもつ人がいたときの上手な付き合い方を紹介します。
HSPという特徴への理解と共感
HSPは生まれ持った気質であり、治療すれば治る疾患ではありません。まずは周囲の人々がその特徴を理解することが大事です。
相手を「HSP」というくくりで見るのでなく、「相手が何をされたら不快か」「相手はどのような対応を望んでいるか」と、相手の立場に立って話を聞けるとよいでしょう。なぜなら、人によってもつ特徴や度合いは異なるからです。
たとえば、大きい音が苦手な人には「話すときにボリュームを抑えてほしい」、感受性が豊かな人には「冗談を冗談として受け取れないので控えてほしい」などの要望があるかもしれません。
適切な環境づくり
HSPの傾向がある人に能力を発揮してもらうには、自分のペースを守ることができる環境が何よりも重要です。
光や音などの外部の刺激にひといちばい敏感に反応してしまう特徴を理解し、集中スペースや個人ブースなど、まわりの刺激を遮断できる環境を用意するとよいでしょう。リモートワークなどの多様な働き方に対応できる制度も効果的です。
得意とするタスクの割り当て
一度にたくさんの人とコミュニケーションをとると過剰に気疲れしてしまう傾向から、イレギュラーに対応し続けなければならない職種には向いていないケースが多いです。
自分を責めすぎてしまう場合もあるので、ノルマ達成が必要な仕事やマルチタスクの業務もあまりおすすめできません。
逆に、コミュニケーションをとるのは特定の人数だけで済み、ひとりで成果物に向けて没頭できる仕事や、プレッシャーが少なくクオリティを追い求められる職種では、高い能力を発揮するでしょう。HSPの傾向をもつ人に向いている仕事の具体例は次章で紹介します。
HSPの傾向をもつ人が向いている仕事3例
HSPの傾向をもつ人が向いている仕事には、HSPの特性を活かせる仕事があります。
この章では、例として3つ紹介します。
正確さが必要な仕事
完璧主義でコツコツと努力することが得意なHSPの傾向をもつ人は、とくに数字の正確さが必要な経理や秘書、データ分析が重要となるマーケティング業務などに向いています。
この仕事では、HSPの以下の長所が活かせます。
- 細かいところに気付く。
- 丁寧に仕事をする。
クリエイティブな仕事
イラストレーターやデザイナー、ライター職などに向いています。たとえば、見たことがない事象についても想像力をはたらかせたり、広く深い情報収集を行ったりすることで、質の高い結果物を残してくれるでしょう。
この仕事では、HSPの以下の長所や特徴が活かせます。
- 感受性や想像力が豊かでクリエイティブ。
- 調べ物をはじめると深く掘り下げ、その知識の深さについて周囲に驚かれる。
IT・WEB関係の技術職
IT・WEB関係の仕事では、プログラムを正確につくる力やリスクヘッジの能力が求められます。頻繁に人とかかわる職種ではなく、また、成果主義の文化もあるので、自分のペースで淡々と仕事をするのが好きな人に向いています。
この仕事では、HSPの以下の長所が活かせます。
- 丁寧に仕事をする。
- 心配性(先のリスクを想像し、対策を考える)。
- 細かいところに気付く。
- こつこつ努力する。
IT人材の需要は近年急激に伸びています。HSPの傾向をもつ人にとって追い風にもなっており、企業と求職者のマッチングの重要性は今後も伸びていくでしょう。
Re就活テックは、即戦力ITエンジニアと企業のマッチングを実現しています。
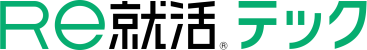
まとめ
HSPには「DOES(ダズ)」と呼ばれる4つの特性があり、相手の細かな気持ちの変化に気付きやすく、クリエイティブなことに対する深い理解があるのが特徴でした。
5人に1人はHSPの傾向があるといわれています。一見、ネガティブな要素にも見えるHSPの気質を味方につけることで、企業は非常に頼りになる人材を手に入れられます。
すべての人が働きやすい環境や適材適所の人材配置について考えてみてはいかがでしょうか。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。