中途採用の離職率が高い理由は?離職の原因や定着率を上げる対策を解説
公開日:2025.10.24
更新日:2026.01.25


近年、日本企業の離職率は上昇傾向にあり、特に中途採用者の早期離職が課題となっています。
高い離職率は、企業の成長を妨げるだけでなく、既存社員の負担増や採用コストの増加にもつながるでしょう。
本記事では、離職率が高い原因と、定着率の高い採用を実現するための具体的な方法を解説します。
中途採用の離職率の現状と平均(企業の平均離職率とは?)
中途採用においては、入社後の定着率が採用成果を左右する重要な指標となります。企業の平均離職率を見ると、業種や企業規模によって差はあるものの、近年は人材の流動性が高まり、中途採用者の早期離職が課題となるケースも少なくありません。
特に入社後1年以内の離職は、採用コストや教育コストの損失につながるだけでなく、現場の負担増や組織全体の士気低下を招く可能性があります。そのため、単に採用人数を増やすだけでなく、離職率の推移を把握し、従業員の定着につながる施策を講じることが重要です。
中途採用における離職率の推移や、従業員の定着に効果的な対策については、離職率の推移や従業員の定着に効果的な対策を解説という視点から整理することで、自社の課題や改善ポイントを明確にしやすくなります。
日本企業の離職率と動向
近年、日本企業の離職率は上昇傾向にあり、多くの企業が人材の定着に課題を抱えています。その割合と動向について詳しく解説します。
離職率は15.4%と上昇傾向
令和5年の離職率は15.4%で、前年から0.4ポイント上昇しました。これは、労働市場の流動性が高まり、労働者がより良い条件や希望に合った職場を求めていることを示しています。
一方、入職者数の割合は16.4%で、3年連続で離職率を上回っています。入職超過は企業が積極的に人材を採用していることを表し、労働市全体の求人需要が非常に強いということです。
離職率が上昇傾向にある今、人材の定着が企業にとって大きな課題となります。優秀な人材を獲得し続けるためには、人材流出を防ぐための対策と、魅力的な採用活動の両方が必要です。
※参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査」
中途採用では離職率が高い傾向
リクルートワークス研究所が実施した、中途採用者の3年以内離職率に関する調査結果を次の表にまとめました。
| 離職率 | 企業割合 |
| 30%以上 | 4.6% |
| 20~30%未満 | 10.2% |
| 10~20%未満 | 13.1% |
| 5~10%未満 | 19.9% |
| 5%未満 | 52.3% |
離職率が20%を超える企業の割合は、14.8%にものぼります。中途採用の離職率は二極化しており、多くの企業では低い離職率を保っているものの、一部の企業では高い離職率が大きな課題になっています。
※参考:リクルートワークス研究所「企業調査による人材定着率の新卒・中途比較」
産業別ではサービス業の離職率が高い
産業別の離職率は次の通りです。
| 区分 | 離職率 |
| 建設業 | 10.1% |
| 製造業 | 9.7% |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10.4% |
| 情報通信業 | 12.8% |
| 運輸業、郵便業 | 10.3% |
| 卸売業、小売業 | 14.1% |
| 金融業、保険業 | 10.5% |
| 不動産業、物品賃貸業 | 16.3% |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 26.6% |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 28.1% |
| 教育、学習支援業 | 14.8% |
| 医療、福祉 | 14.6% |
「生活関連サービス業、娯楽業(28.1%)」が最も高く、続いて「宿泊業、飲食サービス業(26.6%)」という結果でした。
宿泊や飲食業を含むサービス業全般は、他の産業と比べて賃金が低い傾向にあります。
それに加え、労働時間や休日が不規則であること、そして人間関係のストレスなども、離職率が高い要因として考えられます。
※参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査」
企業規模別では中小企業の離職率が高い
企業規模別の離職率は次の通りです。
| 企業規模 | 令和5年 離職率 | 令和6年 離職率 |
| 1000人以上 | 14.2% | 13.2% |
| 300~999人 | 16.1% | 14.7% |
| 100~299人 | 19% | 16.6% |
| 30~ 99人 | 16% | 15.4% |
| 5~ 29人 | 15.6% | 15.8% |
いずれも中小企業(100~299人)の離職率が最も高く、大企業(1000人以上)が低い結果となりました。
中小企業の離職率が高い原因は、大企業のような福利厚生やキャリアパスの多様性が不足している点にあります。さらに、小規模企業特有のアットホームさや柔軟性が失われつつある可能性も考えられます。
※参考:厚生労働省「性、企業規模別入職・離職率」
離職率の算出方法と基準
離職率は、企業の健全性を示す重要な指標です。離職率の基本的な算出方法から、その数値をどう捉えるべきかの基準までを分かりやすく解説します。
中途採用の離職率を算出する方法
離職率とは、一定の期間内に会社を退職した従業員の割合を示す指標です。離職率の計算方式は、公的機関や企業によって異なります。
厚生労働省の雇用動向調査で用いられている算出方法は次の通りです。
| 離職率=〇年間の離職者数 ÷ 1月1日時点の常用労働者数 × 100 |
中途採用の離職率を算出する場合は、次の計算式に当てはめてみましょう。
| 離職率=中途入社後〇年以内に離職した人数 ÷ 当該期間中に中途入社した人数 |
離職率の基準値とは
離職率は企業規模や産業で変動するため、「何パーセント以上で高い」と一概に判断はできません。しかし、近年離職率が上昇傾向にあることや、全体の離職率を踏まえると、注目すべき基準値が見えてきます。
離職率のおおよその基準値は次の通りです。
| 高い離職率 | 20%以上 |
| 平均的な離職率 | 15%前後 |
| 低い離職率 | 10%前後 |
離職率が高いことによる悪影響
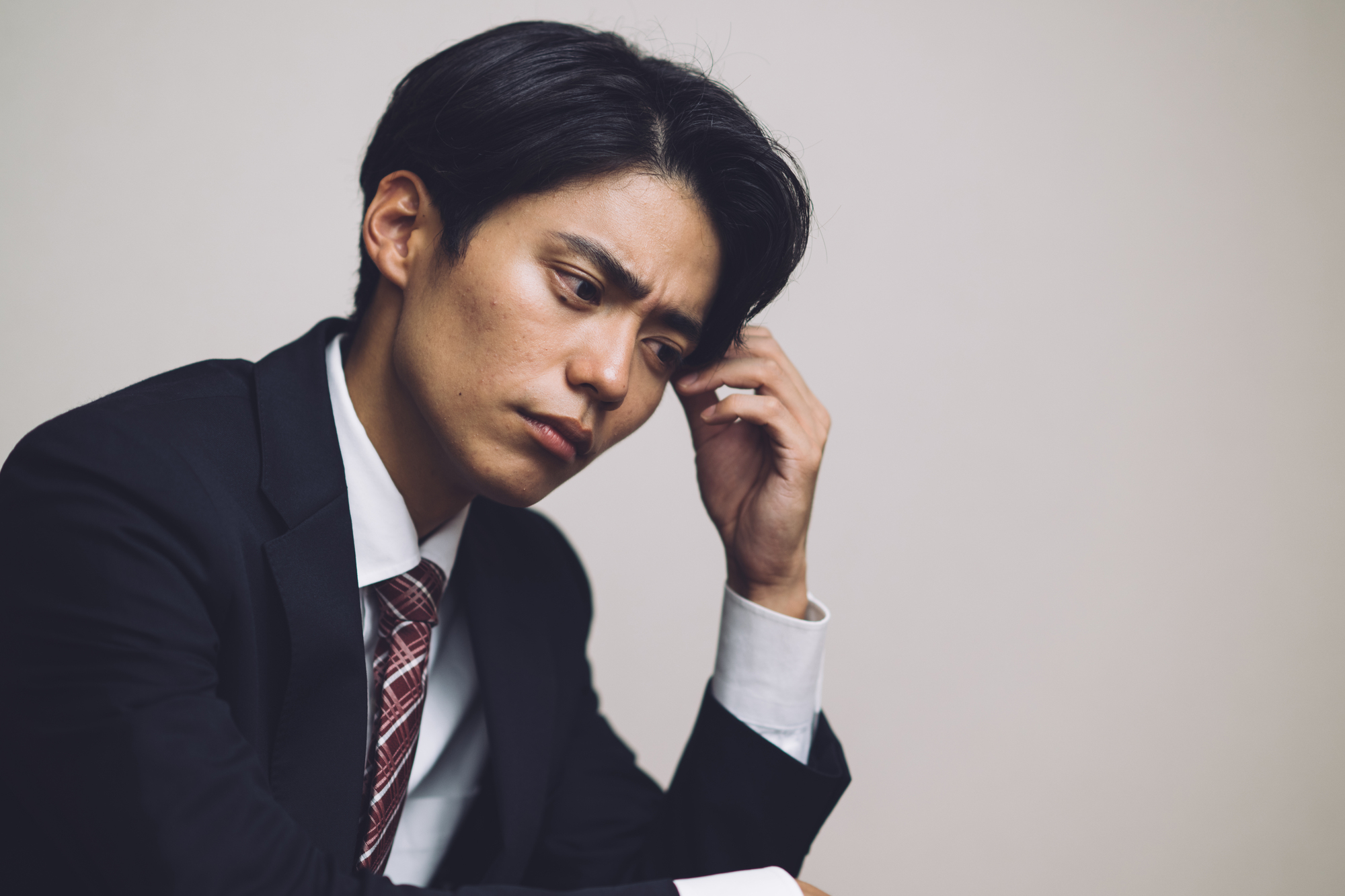
高い離職率は、企業にさまざまな悪影響を及ぼします。人材の流出が引き起こす具体的なデメリットや、それが経営に与える負の連鎖について詳しく解説します。
採用コストが増加する
離職率が高いと、企業は常に新しい人材を採用し続ける必要があり、採用コストが増加します。
採用コストは、求人広告の掲載費用、人材紹介会社への手数料といった直接的な費用だけではありません。求人票の作成や書類選考、面接内定者フォローといった採用担当者の人件費もかかります。
コスト増加は、企業の利益を圧迫し、成長を阻害する大きな要因にもなります。
教育投資が無駄になる
新入社員は、OJTやOff-JTなどの研修を通じて業務に必要な知識やスキルを習得します。しかし、人材が定着しないと、せっかく投じた教育投資は無駄になってしまうでしょう。
教育投資には、研修プログラムの企画・実施費用や外部講師への謝礼に加え、指導にあたる先輩社員の時間や人件費も含まれます。
これらの費用が無駄になることは、企業にとって大きな損失です。
コア人材が育たない
コア人材とは、企業の成長に不可欠な高い専門性やマネジメント能力を持ち、組織の中核を担う人材のことです。
こうした人材は、長年の経験と教育投資を通じて育成されるため、離職率が高いと育ちにくくなります。
コア人材が不足すると、知識やノウハウの流出、若手社員の成長停滞といった問題が発生しやすくなります。
このような状況は、企業の競争力低下や将来の事業継続性にも悪影響を及ぼしかねません。
他の社員に負担がかかる
社員が頻繁に辞めていくと、残された他の社員に過度な業務負担がかかります。
多くの場合、すぐに後任を補充できないため、残された社員が退職した社員の業務を引き継がなければなりません。
引き継ぎ業務が加わることで、残業時間や休日出勤が増えることがあります。
このような状況が続くと、社員の不満が募り、モチベーションの低下や生産性の低下を招いてしまうでしょう。
企業イメージが悪化する
離職率が高いと、求職者は「何か問題があるのではないか」「働きにくい会社なのでは」といった疑念を抱き、採用市場における企業の魅力度が低下します。
その結果、優秀な人材が集まりにくくなってしまいます。
また、社内においても、社員の定着が悪いと、残された社員のモチベーションが低下し、組織の雰囲気が悪化するなどの悪影響を及ぼしかねません。
即戦力採用が難しくなる
即戦力として期待される優秀な人材は、転職市場で非常に人気が高く、複数の企業からアプローチを受けています。
求職者が優位な状況では、安定性や将来性、働きやすさに強みのある企業が選ばれやすい傾向があります。
離職率が高い企業は、「長く働き続けられないのでは」という懸念を求職者に与えかねません。その結果、より定着率が高く安定した企業に、優秀な人材が流れてしまいます。
中途採用者が早期離職する主な原因
中途採用者の早期離職の大きな要因として挙げられるのが、入社前に抱いていたイメージと、入社後の実態とのギャップです。いわゆる「リアリティショック」と呼ばれる状態に陥ると、仕事へのモチベーション低下や不安感が強まり、結果として早期離職につながることがあります。
このような採用ミスマッチは、業務内容や働き方、評価制度、職場の雰囲気などが十分に伝わっていない場合に起こりやすい傾向があります。また、企業側にとっても早期離職は、再採用のコスト増加や組織への悪影響といったデメリットを伴います。
採用ミスマッチが起きる原因や、その防止策、さらに早期離職によって企業が被る具体的なデメリットについては、採用ミスマッチが起きる原因と対策、早期離職による企業のデメリットも解説の観点で整理しておくことが重要です。
中途採用者が流出する原因7つ
中途採用は即戦力として期待されますが、早期離職は多くの企業にとって大きな課題です。なぜ中途採用者の離職が起こるのか、その原因を詳しく解説します。
採用のミスマッチが多い
採用のミスマッチは、選考時に相互理解を十分に深められていないことで発生しやすくなります。
たとえば、「求人情報と実際の業務内容が異なる」ことや、「面接で企業の良い面ばかりを強調する」ことも、ミスマッチを誘発する要因です。
また、また、人事部門と現場担当者の間で、求める人材像や求人票で提示する情報に認識のズレがある場合も、大きな採用ミスマッチにつながります。
採用のミスマッチが生じると、「期待していた仕事ができない」「企業文化に馴染めない」といった不満につながり、早期退職を招く可能性が高まります。
賃金や待遇が見合っていない
優秀な社員ほど、自身のスキルや経験、貢献度に対して、受け取っている給与やボーナスが適切であるかを意識しています。
もし賃金や待遇が見合っていないと感じれば、モチベーションの低下や不公平感の増大につながりかねません。その結果、より良い条件を求めて転職してしまう可能性が高まります。
賃金や待遇が他社に比べて劣っていると、優秀な人材を引き止めることは困難となるため、定期的な見直しが必要です。
人間関係が悪化している
離職率が高い企業では、人間関係の悪化が共通して見られます。
たとえば、コミュニケーション不足によって業務が停滞したり、困っているときに助けを求められなかったりする環境では、社員にストレスが蓄積され、離職につながる可能性が高まります。
さらに、頻繁に人が辞めることで、残された社員の業務負担が増え、コミュニケーションを取る余裕がなくなるという悪循環に陥るケースも少なくありません。
オンボーディングが不十分
オンボーディングとは、新しく入社した社員が組織にスムーズに適応し、早期に活躍できるように支援する一連のプロセスです。
即戦力採用であっても、新しい環境に適応するには十分なサポートが欠かせません。オンボーディングが不十分だと、業務への適応の遅れや、企業文化への不適応などにつながる可能性があります。
その結果、本来のパフォーマンスを発揮できないことに不安やストレスを感じ、早期退職につながるケースも多いです。
キャリアプランのミスマッチ
キャリアプランのミスマッチは、入社前に求職者が描いていた自身のキャリアパスや成長の方向性と、企業が提供できる役割や将来性が合致しない場合に生じます。
キャリアプランのミスマッチには、次のようなケースがあります。
- 習得したいスキルや経験を積む機会がない
- 新しい業務に挑戦できない
- 希望するキャリアパスを歩めない
- 自身の働きに対する評価が曖昧
このようなミスマッチは、社員のモチベーションを低下させる可能性があるため、積極的な対策が必要です。
企業文化や風土に馴染めない
カルチャーミスマッチは、人の価値観や働き方が、入社後の職場の雰囲気や慣習と合致しない場合に生じます。
特に中途採用では求職者のスキルや実績に注目してしまい、カルチャーフィットを見落としてしまうケースが少なくありません。
カルチャーミスマッチには、次のようなケースがあります。
- チームプレイ中心のオープンな文化を期待していたのに、実際は個人プレーが中心で助け合いの少ない環境だった。
- 「ワークライフバランスを重視している」と説明されていたのに、実際は休日出勤や長時間残業が常態化しており、プライベートな時間を取りにくかった。
- 「実力主義で、若手でも成果を出せばどんどん昇進できる」と期待していたが、実際は年功序列の風土が根強く、成果を上げても評価に反映されにくかった。
このようなギャップがあると、仕事へのモチベーションが低下して早期退職につながるリスクが高まります。
早期に結果を求められるプレッシャー
即戦力として期待される中途社員は、入社前から高いパフォーマンスを求められる傾向があります。
しかし、優秀な人材であっても、新しい環境や企業文化、業務の流れを把握するには一定の時間が必要です。
十分なオンボーディングやサポートがないまま、すぐに成果を出すことを期待されると、過度なストレスや強いプレッシャーを感じてしまいます。
こうした状況は、社員の自信喪失やモチベーションの低下を招き、本来の能力を発揮する前に、早期離職を引き起こす可能性が高まります。
定着率の高い中途採用を成功させる方法9つ

中途採用者の定着は、企業の持続的な成長に不可欠です。採用後のミスマッチを防ぐとともに、入社した社員が早期に戦力として貢献できるよう、具体的な施策を解説します。
採用基準を明確にする
採用基準とは、企業が求める人材を定義するための評価項目です。求めるスキルや資格、実績などの表面的な条件だけでなく、入社後に期待する活躍についても具体的に定義しましょう。
即戦力として期待する中途採用では、スキルや経験といった能力面に注目しがちです。しかし、社員が企業に定着し、組織として成果を出すためには、カルチャーフィットも欠かせません。
採用基準を明確化するには、採用ペルソナの設定が効果的です。求める人物像をより具体的に設定することで、採用のミスマッチを防ぐことができます。
人事部と現場の認識をすり合わせる
人事部だけで採用要件を設定すると、現場の社員との間で求める人物像にズレが生じやすくなります。
認識のズレを防ぐためには、採用要件の設定や面接に現場担当者にも加わってもらい、認識をすり合わせることが重要です。
共通した評価基準を持つことで、入社後のギャップを減らし、早期離職の防止にもつながるでしょう。
こうした連携は、採用活動の効率を高めるだけでなく、現場が求める真の即戦力を見極めるうえでも欠かせません。
ダイレクトリクルーティングを活用する
ダイレクトリクルーティングとは、企業の採用要件に適した人材を、人材データベースから探し出し、スカウトメールを使って直接アプローチする採用手法です。
スカウトメールを通じて、求職者のキャリアプランや興味に合わせた情報を提供することで、入社後のギャップを減らし、採用のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。
20代転職に特化した「Re就活」では、基本属性や経験、志向性など詳細なサーチとアプローチが可能です。
また、希望人材の自動抽出や自動配信機能が備わっているため、採用担当者の負担を軽減できるでしょう。
さらに、スマートスカウトアシスト機能を活用すれば、スカウトメール案を自動生成できるので、初めてダイレクトリクルーティングを導入する企業でも活用しやすいです。
入社後の業務内容と役割を明確に伝える
入社後のギャップを防ぐには、事前に業務内容と役割を伝えることが重要です。
採用面接や内定通知の段階で、実際に担当する業務内容や与えられる裁量、チーム内での役割を明確に伝えましょう。曖昧な説明は、早期退職の原因になります。
また、使用するツールやチーム体制、連携する部署なども事前に共有することで、入社後のイメージを具体化でき、ミスマッチを防ぐことができます。
可能であれば現場の社員との対話機会を設けるのも効果的です。実際に対話することで、求職者はよりリアルに働く姿をイメージしやすくなります。
候補者に適した給料を提示する
従来の求人サイトでは、「年収350万〜800万円も可能」といった幅のある年収表記が一般的です。
しかし、このような表記は具体的な金額が分からず、求職者に不安を与えたり、入社後のギャップにつながったりする可能性があります。
ダイレクトリクルーティングなら、求職者のスキルや経歴に合わせて個別に給与を提示できます。現実的な金額を提示できるため、求職者も自身の将来像をイメージしやすくなるでしょう。
スカウトメールを送る際は、「なぜその金額なのか」を明確に伝えることが非常に重要です。
評価の根拠を明示することで、求職者の市場価値を理解していることを示し、信頼関係の構築につながります。
ネガティブな情報も正直に伝える
中途採用者の定着率を高めるためには、企業のネガティブな情報や課題も正直に伝えることが重要です。
良い面ばかりを強調しすぎると、入社後に現実との大きなギャップが生まれ、早期離職の原因になります。
ネガティブな情報を正直に伝えたうえで「どう改善しようとしているのか」「あなたにどう貢献してほしいのか」を明確にすることで、求職者は入社後の状況を具体的にイメージしやすくなります。
課題に対する具体的な改善策もセットで伝えるのがポイントです。そうすることで、誠実かつ前向きな姿勢を伝えられ、求職者に余計な不安を与えることなく信頼関係を築けるでしょう。
採用動画を活用する
採用動画を活用すると、テキストや画像だけでは伝えきれない企業の魅力やリアルな雰囲気を、視覚と聴覚に訴えかけられます。
たとえば、社員のインタビューを通じて仕事のやりがいや一日の流れを紹介したり、オフィスの様子やチームの雰囲気を映したりするのも効果的です。
このような情報により、求職者は入社後の具体的なイメージを掴みやすくなります。
株式会社学情が制作する“職場体感型”採用動画「Job Tube」は、制作スタッフが企業を訪問してインタビューするため、第三者目線で企業の魅力や強みをアピールすることが可能です。
初めて採用動画を制作する企業でも、中途採用のノウハウを持ったスタッフが担当するため、質の高い動画制作が期待できるでしょう。
カジュアル面談を実施する
カジュアル面談とは、企業と求職者の相互理解を深めるための機会です。選考の合否に直接関係しないため、面接では聞きにくいような質問でも、本音で話し合うことができます。
これにより、入社後のギャップを減らし、ミスマッチのない採用につなげられるでしょう。
20代転職に特化した「Re就活」には、面談打診ができる「カジュアル面談機能」が備わっています。
企業は、求職者の職務経歴書を確認してヘッドハンティングメールを送ったり、自社に興味を持っている求職者に対して面談をオファーしたりすることが可能です。
また、求職者からも企業にカジュアル面談を申し込めるため、幅広い求職者との出会いが期待できます。
入社後のフォロー体制を整える
中途採用者の早期戦力化と定着には、次のような継続的な支援が重要です。
- オンボーディング
- OJT
- メンター制度
- 役割と評価基準を明確にするための目標設定
- フォロー面談
- 社内イベント(ランチ会、交流会)
このような多角的なフォロー体制は、入社後のギャップを最小限に抑えるだけでなく、社員のパフォーマンス向上と早期離職防止に直結します。
退職者からのフィードバックを活用する
退職者は、企業の良い点だけでなく、内部の課題や不満を率直に教えてくれる貴重な存在です。
退職時にエグジットインタビュー(退職面談)を実施し、離職理由や職場環境、人間関係、業務内容などについて深くヒアリングしましょう。
この際、本音を引き出すために、直属の上司ではない人事担当者や第三者が面談を行うと効果的です。
得られたフィードバックは、部署や役職に関わらず、組織全体で共有・分析し、具体的な改善策へと活用することが重要です。これにより、既存社員の満足度向上にもつながります。
オンボーディング体制の整備
中途採用者の定着率を高めるためには、入社後の早い段階で企業や業務への理解を深めてもらうことが重要です。そのためには、オンボーディングとは何かを正しく理解したうえで、計画的な受け入れ体制を整備することが欠かせません。
業務内容の説明だけでなく、組織の文化や価値観、期待される役割を丁寧に伝えることで、入社後の不安や戸惑いを軽減できます。また、オンボーディング体制が整っている企業ほど、早期離職の防止や戦力化のスピード向上につながりやすい傾向があります。
オンボーディングの目的やメリット、成功させるためのポイントを押さえた施策設計が、結果的に中途採用者の定着率向上につながります。
中途採用の離職率を下げるには、マッチング精度の高い採用を目指そう!
日本企業、特に中小企業は離職率が高い傾向にあります。社員の定着率を向上させるには、社内制度の見直しに加え、マッチング精度の高い中途採用を実現することが重要です。
ダイレクトリクルーティングサイト「Re就活」なら、自社の採用要件に合う求職者に直接アプローチできます。
さらに、求職者の志向性や希望に沿ってメール内容をカスタマイズできるため、質の高いマッチングが可能です。
中途採用の離職率にお悩みの方は、株式会社学情へご相談ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。









