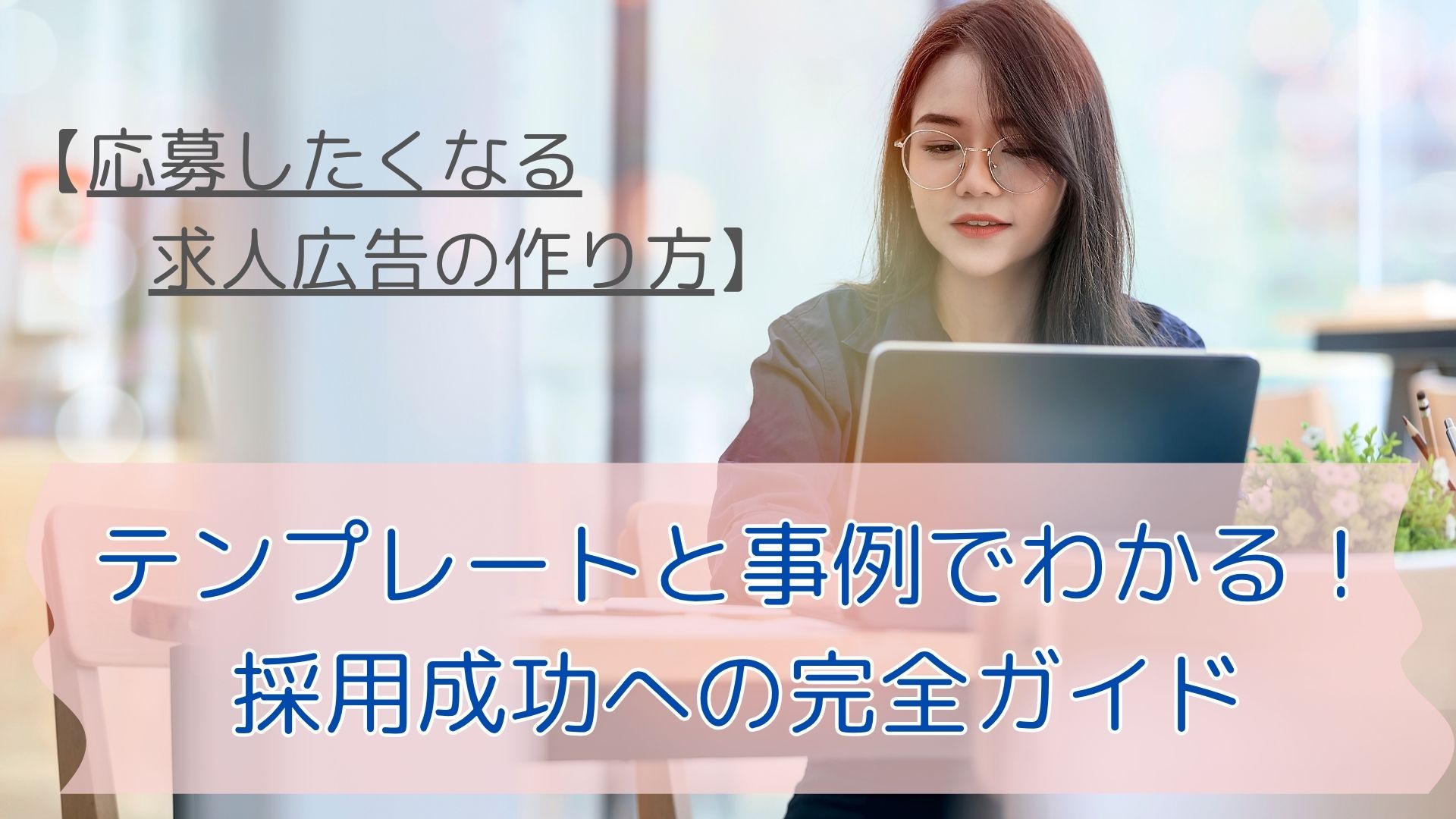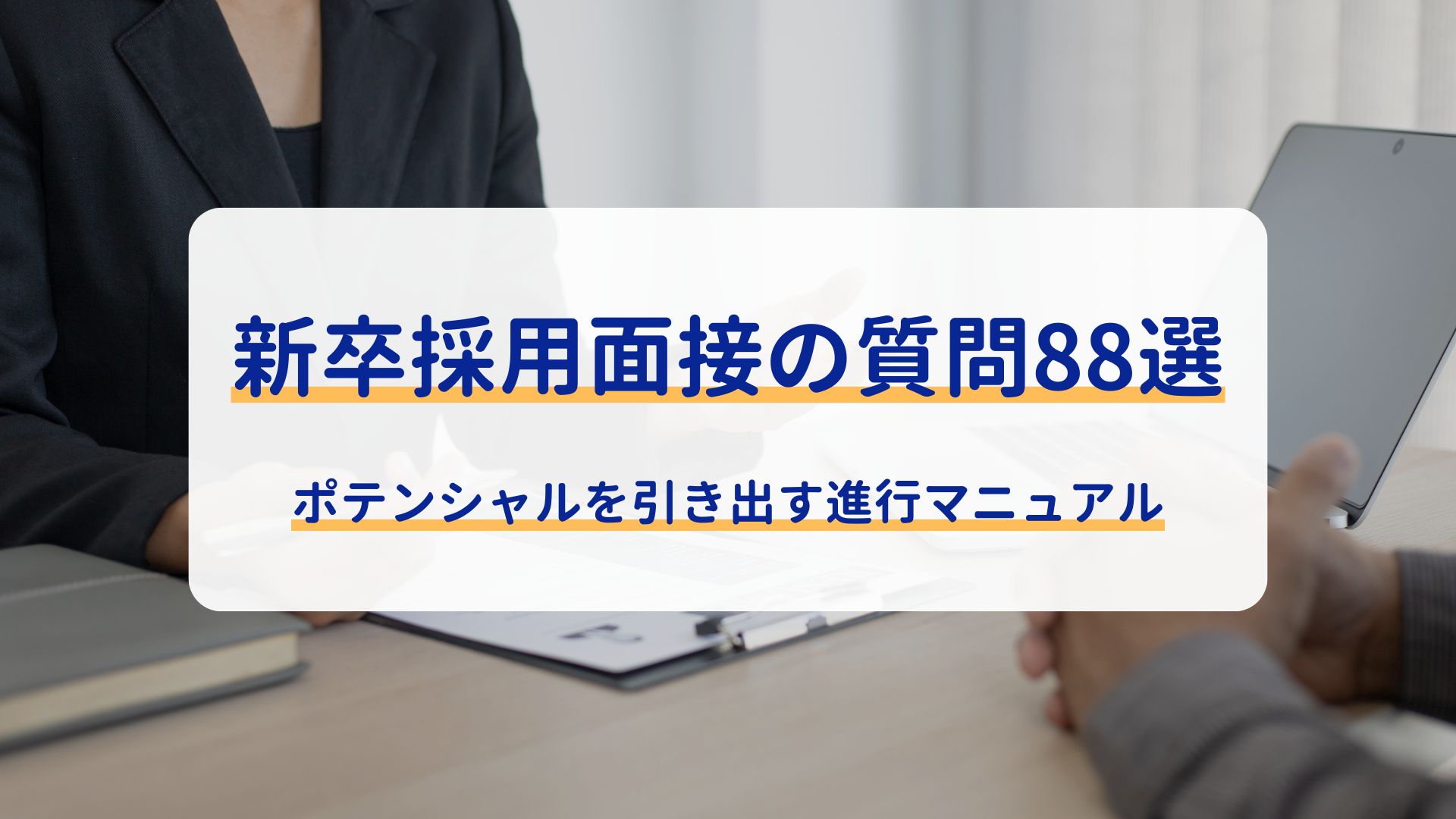近年、従来の採用手法に加えて、さまざまなアプローチ方法が登場しています。この記事では、基本的なものからトレンドの採用手法までご紹介します。
記事の最後に選び方と成功事例も載せていますので、ぜひお読みください。
採用手法の比較一覧
採用手法にはさまざまな種類があり、それぞれ得意不得意の分野があります。そのため、採用活動を効率的に進めるには、採用ターゲットや課題に適した手法を選ぶことが重要です。
採用手法を一覧にして紹介します。
|
採用手法 |
採用コスト |
母集団 |
マッチング精度 |
採用工数 |
|
求人サイト |
◯ |
◎ |
◯ |
◯ |
|
人材紹介 |
△ |
△ |
◎ |
◎ |
|
ヘッドハンティング |
△ |
△ |
◎ |
◎ |
|
合同企業セミナー |
△ |
◎ |
◯ |
△ |
|
ハローワーク |
◎ |
△ |
△ |
◎ |
|
求人検索エンジン |
◎ |
◎ |
△ |
△ |
|
求人チラシ・張り紙 |
◎ |
△ |
△ |
△ |
|
ダイレクトリクルーティング |
◯ |
◯ |
◎ |
△ |
|
リファラル採用 |
◎ |
△ |
◎ |
◯ |
|
アルムナイ採用 |
◎ |
△ |
◎ |
◯ |
|
SNS採用 |
◯ |
△ |
◯ |
◯ |
|
オウンドメディアリクルーティング |
◯ |
△ |
△ |
△ |
|
ミートアップ採用 |
◎ |
◯ |
◎ |
◯ |
|
インターンシップ |
◎ |
◯ |
◎ |
△ |
|
キャリアセンター訪問(大学訪問) |
◎ |
△ |
◯ |
△ |
代表的な採用手法7つ
新卒採用・中途採用における代表的な採用手法について解説します。それぞれの特徴やメリット・デメリットをおさえましょう。
代表的な採用手法は次の通りです。
- 求人サイト
- 人材紹介
- ヘッドハンティング
- 合同企業セミナー
- ハローワーク
- 求人検索エンジン
- 求人チラシ・張り紙
求人サイト

求人サイトとは、企業の採用広告を掲載し、求職者からの応募を集めるWeb媒体のことです。新卒採用や中途採用だけでなく、アルバイト・パート採用でも広く活用されています。
採用活動を行うにあたり、まずは求人サイトへの広告掲載を検討する方が多いのではないでしょうか。
求人サイトは、新卒採用向けやキャリア(経験者)採用向けなど、採用ターゲットによって媒体が分かれている場合が多いです。特にキャリア採用向けのサイトには、幅広い求人を扱う「総合型」と、職種や地域に特化した「特化型」があります。
近年、求人数が求職者数を上回る「売り手市場」が続き、人材獲得競争が激化しています。そのため、応募を集めるためには求人広告の内容を工夫する必要があるでしょう。
費用の目安:
・新卒採用:80万〜200万円(通年)
・中途採用:30万〜140万円(4週間)
・パート・アルバイト:4万〜40万円(2週間)
メリット:
- 数百万人単位の登録者にアプローチできる
- 採用人数によって費用が変わらない
- 画像や動画を使って仕事内容や企業の魅力をアピールできる
デメリット:
- ひとりも採用できなかった場合でも料金がかかる
- 求人情報が埋もれてしまう可能性がある
- 就職・転職潜在層にアプローチするのが難しい
人材紹介

人材紹介は、採用を行っている企業と求職者をマッチングさせるサービスです。人材紹介会社に所属するコンサルタントが、採用要件に適した人材を探し、企業に紹介します。
求人サイトを運営する会社が同時に人材紹介サービスを展開しているケースも多く、大規模な人材データベースを持っているのが強みです。
費用は、成功報酬型であることが多く、内定承諾もしくは入社に至るまで費用がかかりません。
ただし、優秀な人材ほど年収が高く、支払う成功報酬も高額になる可能性があります。人材紹介を利用するのが適切か、事前に確認しましょう。
費用の目安:
成功報酬の金額は、入社した人材の想定年収の30~35%程度
たとえば、年収500万円の場合、報酬額は150万~175万円程度
メリット:
- コンサルタントが求職者の抽出や選考の日程調整などを行うため、採用担当者の業務負担が軽減される
- 求職者との面接に集中できる
- コンサルタントが自社の魅力や採用要件を客観的に伝えることで、これまでとは異なる層の求職者に出会える
デメリット:
- ひとり当たりの採用コストが割高になる可能性がある
- 自社に採用ノウハウが蓄積されにくい
- 人材紹介会社からすぐに紹介を受けられないこともある
ヘッドハンティング
ヘッドハンティングは、企業の採用要件に適した人材をサーチし、企業と求職者をマッチングさせるサービスです。
ヘッドハンティングには、採用要件に適した人材を独自のルートで探し出す「サーチ型」と、ヘッドハンティング会社のデータベースから採用要件に適した人材を抽出する「登録型」があります。
主に専門性の高いポジションや、経営層をターゲットに行われる採用手法です。サーチ型の場合、転職を考えていない人も採用要件に適していれば候補者になるため、質の高い採用が期待できます。
費用は成功報酬型であることがほとんどです。サーチ型では、成功報酬とは別に着手金が必要な場合があります。
費用の目安:
成功報酬の金額は、入社した人材の想定年収の30〜40%程度
たとえば、年収800万円の場合、報酬額は240万〜320万円程度
また、報酬額とは別に着手金が必要な場合がある
メリット:
- 高いスキルを持つ人材を採用できる
- 転職市場にあまり現れない人材にもアプローチできる
- 新規事業など、水面下で採用活動を進めたいときに向いている
デメリット:
- 採用までに時間がかかる
- 優秀な人材ほど高収入なため、採用コストが高くなりやすい
- 役員や経営陣との選考や面談のスケジュール調整が難しい
合同企業セミナー
合同企業セミナーとは、複数の企業が集まり、学生や求職者に会社説明や採用に関する情報を提供するイベントのことです。合同説明会や合同企業説明会とも呼ばれます。
イベントは、50社程度の中規模のものから、300~400社集まる大規模なものまでさまざまです。求人サイトと同様に、幅広い業界や業種が集まる「総合型」と、職種や地域に特化した「特化型」のイベントがあります。
合同企業セミナーで自社のブースに求職者を集めるには、積極的な声がけや目をひく装飾などの工夫が必要です。
新型コロナウイルスの流行以降は、オンライン形式でも開催されるようになりました。新卒採用向けのイメージが強かった合同企業セミナーですが、近年はキャリア(経験者)採用向けのイベントも増えています。
費用目安:
相場は75万〜160万円程度
※開催規模や日数、出展ブースの大きさなどによって異なる
メリット:
- 一度に多くの求職者と接触でき、効率的な母集団形成が可能
- 自社の魅力や雰囲気を直接アピールすることで、企業の認知度や志望度向上につながる
- 求職者との双方向のコミュニケーションによって採用ミスマッチを減らせる
デメリット:
- 知名度の高い企業に求職者が集まる
- 出展の準備や当日のブース運営などに工数がかかる
- 人事以外の部署からも人員を集めなければならない場合も
ハローワーク
ハローワークとは、厚生労働省が運営する公共職業安定所のことです。全国500カ所に窓口があり、誰でも無料で利用できます。
企業が求人を掲載するには申請が必要です。窓口か、ハローワークのインターネットサービスから利用手続きを行いましょう。
費用目安:無料
メリット:
- 若い世代から60歳以上までの幅広い世代の求職者に働きかけられる
- 国が運営しているサービスなので、求職者にとって安心感がある
- 無料で利用が可能
デメリット:
- 全国一斉募集ができない
- 求人の文字数が限られている
- 専門的なスキルや即戦力採用には不向き
求人検索エンジン
求人検索エンジンは、一般的な検索エンジンと同様にキーワードで求人情報を検索できるサービスです。インターネット上に掲載されている求人広告だけでなく、企業の採用ホームページなどもヒットします。
求人サイトと異なるのは、インターネット上に公開されている大小さまざまな企業の求人情報をクローリング(プログラムがWebページを巡回し、情報を集める仕組み)している点です。自社に採用ページがなく、クローリングの対象にならない企業でも、求人検索エンジンに直接求人を掲載することができます。
求人検索エンジンの有料オプションは基本的に「クリック課金型」で、設定する価格によって表示順位が変わるので、費用と効果の適正なバランスの見極めが必要です。
費用目安:
無料 ※上位表示させる有料オプションもある
メリット:
- 求人サイトと異なり、配信をコントロールできる
- クリック率などの分析結果をもとに、より効果的な運用が目指せる
- 複数の職種を募集するのに向いている
デメリット:
- 専門的な知識をもつ人材が社内にいないと運用が難しい
- 頻繁に求人情報を更新しなければならない
- クローリングの条件を満たさないと読み込んでもらえない
求人チラシ・張り紙
求人チラシや張り紙は、誰でも簡単にできる採用手法のひとつです。紙に求人情報を記載して貼るだけなので、採用コストもほとんどかかりません。
求人チラシや張り紙は、貼れる場所が限定されるため、チェーン展開している店舗などで活用されていることが多いです。店舗数が少ないと、求人サイトのように幅広い求職者にアプローチすることは難しいでしょう。
一方、「地元の人材を採用したい」「採用コストをおさえたい」場合には便利です。
費用目安:
無料(ポスターを制作する場合は制作費がかかる)
メリット:
- 採用コストをおさえられる
- 専門的なスキルやノウハウが必要ない
- すぐに求人募集ができる
デメリット:
- 幅広い求職者にアプローチできない
- 即効性は期待できない
- 求人チラシを貼れる場所が少ない
トレンドの採用手法6つ

売り手市場が続き、従来の採用手法だけでは求める人物を獲得しにくくなっています。人材獲得競争が激化するなかで、マッチング精度の高い採用を成功させるには、新たな採用手法の導入を検討してみましょう。
トレンドの採用手法は次の通りです。
- ダイレクトリクルーティング
- リファラル採用
- アルムナイ採用
- SNS採用(ソーシャルリクルーティング)
- オウンドメディアリクルーティング
- ミートアップ採用
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングは、企業が求職者に直接アプローチする採用手法です。具体的なアプローチ方法は、スカウトメールの送付やヘッドハンティングのほか、対面型のイベント、SNS採用などがあります。
近年の売り手市場の影響で、求人広告だけで応募を集めるのがむずかしくなっている中、「攻め」の採用として注目されています。終身雇用が当たり前ではなくなりつつあり、働き手が主体的なキャリア形成を意識するようになったのも要因のひとつでしょう。
株式会社学情が提供する「Re就活キャンパス」や「Re就活」「Re就活30」では、求職者に直接アプローチするスカウト機能が利用できます。
費用目安:
スカウトメールなどの機能がある求人サイトを利用する場合は、広告掲載料がかかる
※成功報酬型のダイレクトリクルーティングサービスもある
メリット:
- マッチング精度の高い出会いが期待できる
- 潜在層にも積極的にアプローチできる
- 社内に採用ノウハウを蓄積できる
デメリット:
- 人材の抽出やスカウトメールの作成など、採用担当者の業務負担が増える
- 効率的に運用するためのノウハウが必要
- 就職・転職の意欲が低い場合、採用までに時間がかかる
リファラル採用
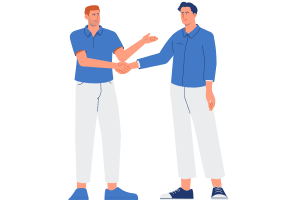
リファラル採用は、自社に合う人材を既存社員から紹介してもらう採用手法です。すでに自社で活躍している人から紹介してもらうため、企業の考え方や価値観を理解している人材との出会いが期待できます。
縁故採用とは異なり、必ず採用する必要はありません。紹介を受けたあとの選考ルートはほかの採用手法と変わりません。
また、費用は採用の有無に関係なく、紹介してくれた社員にインセンティブを支払うケースが多いです。
ただし、インセンティブを報酬として支払うと有料職業紹介の扱いになり法に触れる可能性があるため、賃金として支払いましょう。
費用の目安:
インセンティブの額は1万~50万円と企業によって幅広い
メリット:
- 自社をよく知っている社員が紹介する人材なので、マッチング精度の高い出会いが期待できる
- 求人広告や人材紹介より採用コストをおさえられる
- 即戦力採用につながりやすい
デメリット:
- いつ紹介してもらえるかが不明確で、期限がある採用には不向き
- 不採用の場合に紹介者と応募者の関係が悪くなる可能性がある
- 候補者のタイプが偏りやすい
アルムナイ採用

アルムナイ採用とは、自社で一度働いていた社員を再雇用する採用手法です。定年退職を除き、本人に働き続ける意志があったものの、出産や育児、配偶者の転勤といったやむを得ない事情で退職した社員が「アルムナイ」に該当します。
自社で活躍していた人材のため、業務内容や企業文化を理解しており、即戦力としての活躍が期待できるでしょう。即戦力人材を採用する手法として注目されています。
アルムナイ採用を行うには、退職時に再雇用制度があることを伝え、アルムナイネットワークを維持することが大切です。SNSや、アルムナイに特化したサービスを利用するのが一般的ですが、定期的な交流会を開く企業もあります。
費用の目安:
広報活動や外部サービスを利用する場合は費用がかかるが、基本的に無料
メリット:
- マッチング精度の高い採用が期待できる
- 即戦力としての活躍が期待できる
- 客観的な視点から自社の課題を見つけられる
デメリット:
- アルムナイネットワークの維持に工数がかかる
- 既存社員との格差が生まれると不満の原因になる
- 離職へのハードルが下がる可能性がある
SNS採用(ソーシャルリクルーティング)
SNS採用は、SNSでの情報発信によって企業の認知度やブランド力アップを狙い、興味をもった求職者に直接ダイレクトメールなどで応募を促す採用手法です。ソーシャルリクルーティングとも呼ばれています。
SNS採用は、採用ブランディングとダイレクトリクルーティングの両方の側面を備えており、成功すれば質の高い母集団形成が可能です。
利用する媒体には、LINEやX(旧Twitter)、Instagram、YouTubeなどの一般的なSNSをはじめ、WantedlyやLinkedInなどのビジネスに特化したものがあります。
SNS採用はすぐに効果が出ないことがほとんどです。長期的な運用を視野に入れ、改善を図りながら活用しましょう。
なお、発信する情報の内容や方法によっては、炎上する可能性があります。その情報が適切であるか、企業イメージを損なうものでないかなどを確認することが大切です。
費用目安:
基本的には無料 ※有料の広告やオプションなどもある
メリット:
- ファンがつき、自社への志望度が高まる
- 情報の拡散によって自社を知らない層にもリーチできる
- リアルタイムで情報発信ができる
デメリット:
- 採用ターゲットに興味をもってもらえるコンテンツを作り続けなければならない
- 長期的に運用するための人員と環境が必要
- 炎上するリスクがある
オウンドメディアリクルーティング
オウンドメディアリクルーティングとは、採用ホームページやブログ、SNSなど、自社が所有するメディアを使った採用活動のことです。
採用活動のオンライン化が進むなか、Webを通じて企業の雰囲気を伝えようと、採用動画が注目されています。採用ホームページや会社説明会で動画を流すだけでなく、YouTubeにアップロードして知名度の向上を図る企業も多いです。
オウンドメディアリクルーティングでは、社員が働く理由や新しい取り組みについてのインタビュー、役職者の考え方などを発信することで、企業理解を深めたり、志望度を高めたりする効果が期待できます。
自社でページを立ち上げるほかにも、noteなどの外部プラットフォームを活用することも可能です。また、SNSと併用することで効果的に知名度を上げられます。
費用目安:
メディアの立ち上げを外部に依頼する場合は、100万~300万円程度
※依頼する範囲やクオリティによって大きく変わる
メリット:
- 価値観に共感を抱いた求職者からの応募を集められるため、マッチング精度が高い
- 企業の知名度の向上につながる
- 競合他社と差別化しやすい
デメリット:
- マーケティングやSEOなどについての運用ノウハウが必要
- 短期間で効果が出にくい
- 初期コストやランニングコストがかかる
ミートアップ採用
ミートアップ採用とは、情報交換や交流会などのイベントを通じて就職・転職顕在層と接点を持ち、採用につなげる採用手法のことです。
イベントの開催形式には、フリートークや勉強会、短時間でプレゼンテーションを行うLT(ライトニングトーク)大会などがあります。
実際に働いている社員と参加者が交流を深めることで、自社への志望度や理解度を高める効果が期待できます。また、自社のカルチャーや仕事内容を理解したうえで選考に進むため、採用のミスマッチを防ぐ手段としても効果的です。
費用目安:
自社で実施する場合は無料
※有料サービスや広告費などに費用がかかることがある
メリット:
- 求職者と直接コミュニケーションが取れる
- 自社への志望度や理解度を高められる
- 自社の魅力や強みを伝えやすい
デメリット:
- イベントに参加する人員が必要
- イベントの準備や運営に工数がかかる
- 効果を得るには中長期的な運用が必要
新卒採用で用いられる採用手法
新卒採用と中途採用では、同じ採用手法が用いられることも多いですが、なかには新卒採用ならではの手法もあります。
新卒採用で用いられる採用手法は次の通りです。
- インターンシップ
- キャリアセンター訪問(大学訪問)
インターンシップ
インターンシップとは、学生の適性や進路の見極め、専門分野における実践力の向上などを目的に実施する就業体験のことです。
従来のインターンシップは「1dayインターンシップ」と呼ばれ、会社説明会のようなものも含まれていましたが、2025年卒業の学生を対象としたインターンシップからルールが変わりました。
インターンシップを実施するには「5日間以上」など一定の条件を満たし、かつ就業体験を盛り込まなければなりません。インターンシップを実施する際は、実施条件を満たしているか確認しましょう。
費用目安:無料
メリット:
- 優秀な人材の確保につながる
- 相互理解が深まる
- 企業イメージの向上を期待できる
デメリット:
- 準備や実施にマンパワーが必要
- 人事以外の人員も用意しなければならない
- 短期間で学生を見極めるのが難しい
インターンシップの種類や三省合意改正による変更点などについて詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
キャリアセンター訪問(大学訪問)
キャリアセンターとは、その大学に在学している学生や卒業生を対象に、就職や進路をサポートする部署のことです。就職支援課やキャリア支援センターと呼ぶこともあります。
求める人物像に適した学生が在学している大学を訪問し、求人票を置いてもらったり、学内企業説明会に参加したりすることで、採用につなげる採用手法です。
定期的に訪問することで、大学とのコネクションができ、学生を紹介してもらえることもあります。
しかし、人気の大学は、すでに学生から人気の高い企業とコネクションを持っており、知名度の低い企業は学内企業説明会の案内が来ないケースも少なくありません。その場合は、定期的にイベントの情報を問い合わせましょう。
費用目安:無料
メリット:
- 優秀な学生と早期に接点が持てる
- 採用コストをおさえられる
- 自社の知名度向上を期待できる
デメリット:
- 採用担当者の業務負担が増える
- 信頼関係を構築するまで時間がかかる
- 遠方の大学にアプローチしにくい
新卒採用と中途採用のトレンド
採用市場では売り手市場の傾向が強まっており、競合他社との人材獲得競争が激化しています。そのため、さまざまな採用手法を組み合わせた「攻め」の採用が注目されています。
それぞれのトレンドと特徴をおさえ、自社の採用活動に取り入れましょう。
新卒採用のトレンド
新卒採用では、従来の求人サイトでの「マス型採用」と併せて、「ダイレクトリクルーティング」や「オウンドメディアリクルーティング」などを使った個別採用を導入する企業が増えています。
学生側も、もともと知っている企業や志望度が高い企業にはマス型の求人サイト経由で自ら応募し、名前を知らない企業やBtoB企業からはダイレクトリクルーティング型のサービスに登録してスカウトを待つ傾向が強いです。また、SNSで情報収集をする学生が多いため、SNSを活用した情報発信に注力している企業が多く見られます。
新型コロナウイルスの流行で採用活動のオンライン化が進みましたが、現在は対面形式とオンライン形式を併用している企業が増えています。
株式会社学情が実施した2025年卒採用の企業調査では、対面形式の合同企業セミナーに参加する企業の割合が前年を3.2ポイント上回る39.7%でした。
※参考:株式会社学情「2026年3月卒業予定者/採用動向調査レポート」
中途採用のトレンド
中途採用では、即戦力の人材確保を重視する傾向から、会社を退職した人材を再雇用する「アルムナイ採用」や、社員から友人や知人を候補者として紹介してもらう「リファラル採用」が注目されています。
また、マッチング精度の高い採用を目指し、選考の合否とは関係なく、企業と求職者がお互いに情報交換をする場である「カジュアル面談」を導入する企業が多いです。
株式会社学情が20代の就職・転職希望者を対象に実施した調査によると、20代の8割以上がカジュアル面談への参加を希望していることが明らかになりました。
さらに、カジュアル面談を通じて「志望度が上がった」と答えた20代は約6割に達し、この結果から、カジュアル面談は企業と求職者の双方に大きなメリットがあることがわかります。
※参考:株式会社学情「転職意識調査レポート2024」
採用手法の効果をより高める施策
それぞれの採用手法の効果を最大化するには、特別な施策が必要です。これまで紹介してきた採用手法と併せて実施すると効果的な施策について解説します。
採用マーケティング/ブランディング
採用マーケティングや採用ブランディングは、中長期的なスパンで自社の認知を拡大させる施策です。
採用マーケティングは、採用活動にマーケティングのフレームワークを取り入れた考え方です。採用マーケティングでは「認知」「興味」「応募」「内定」といった段階をファネル(じょうご)として捉え、ファネルごとに適したチャネル(採用手法)を選択してアプローチします。その上で、採用活動を数値化して、継続的にPDCAを回します。
採用ブランディングは、ファネルの最初の部分である「認知」を推し進める役割を果たします。企業が持つ魅力や価値を整理した上で、採用説明会・インターンシップ・Webサイトなどのあらゆる場で一貫したコンセプトを発信し、自社で働くこと自体をブランド化します。
ふたつの考え方に共通しているのは、就職・転職潜在層に普段から企業の価値を十分に伝え、自社の考え方に共感する人材からの応募や志望度の向上を図るという目的が含まれることです。
「売り手市場」のなかで他社との差別化を行うためにも、採用マーケティングや採用ブランディングの重要性はより増していくでしょう。
カジュアル面談
カジュアル面談とは、選考の合否とは関係のない、企業と求職者がリラックスした雰囲気のなかでお互いに情報交換をする場です。オンライン形式やカフェ、オフィス見学を兼ねて社内の会議室などで開かれます。
カジュアル面談は相互理解を深めるのに効果的な施策です。お互いに本音で話し合えるので、ミスマッチによる選考・内定辞退や入社後の早期退職の防止につながります。
また、選考プロセスにカジュアル面談を取り入れることで、応募のハードルが下がり、より多くの求職者と出会いやすくなるでしょう。
就活カフェ
新卒採用では、就活カフェを利用する企業も増えています。就活カフェとは、就職活動中の学生が無料でWi-Fiや電源を使えるフリースペースです。
ミートアップ採用の会場として利用できる就活カフェもあります。カフェ内にサイネージ広告やパンフレットを設置したり、カジュアルなOB・OG訪問や企業面談を実施したりと、学生との接点を増やすきっかけ作りに最適です。
就活カフェの多くはスポンサーからの協賛金で運営されているので、利用する際は料金がかかります。
採用代行(RPO)
RPOは「Recruitment Process Outsourcing」の略称で、採用代行サービスのことです。代行を依頼できるサービスは、採用計画から母集団の形成、応募者の対応・管理、選考に関する対応、内定者のサポートまで様々。幅広く対応してくれます。
中小企業では、採用担当者が労務や人事などを兼務しているケースが多く、マンパワー不足に悩んでいる方も多いでしょう。特に、ここ数年は採用難易度が高まっており、十分なリソースの確保が必要です。
採用代行を利用し、採用業務の一部を外注することで、面接や面談などに注力でき、採用の質を高められます。
採用管理システム(ATS)
ATSは「Applicant Tracking System」の略称で、採用管理システムのことです。面接日程の調整や選考結果の自動集計など、採用に関する情報を一元管理できます。
複数の求人媒体を利用していると、管理が複雑になりがちです。そのため、求職者への対応が遅れることで、優秀な人材が他社に流れてしまう可能性があります。
このような課題を解決するために、採用管理システムを活用する企業が増えています。
採用管理システムの利用料金の相場は、月額2万〜10万円程度です。月額費に加え、初期費用がかかる場合もあります。具体的な導入手順や比較ポイントはこちらの無料ダウンロード資料をご覧ください。
採用ピッチ資料
ピッチとは短いプレゼンテーションを意味し、採用ピッチ資料は求職者に企業の魅力や強みを伝えるための資料を指します。
採用ピッチ資料は、会社概要や企業パンフレットとは異なり、採用に特化した資料なので、求職者が知りたい情報をわかりやすくまとめるのが特徴です。
採用ピッチ資料を作成する際は、透明性のある内容を心がけましょう。魅力や長所だけでなく、課題や短所などネガティブな情報も取り入れることで、入社後のミスマッチ防止につながります。
採用ピッチ資料には、基本的な採用情報に加えて、次のような項目を設けます。
- 企業のミッション・ビジョン
- 今後の事業展開
- 企業文化
- 自社の課題
- オンボーディングや能力開発について
- 求める人物像・適切でない人物像
- 離職率
- 評価制度
タレントプール
タレントプールは、英語の「Talent(優秀な人材)」と「Pool(蓄積する)」を組み合わせた造語であり、人材情報を蓄積するデータベースです。「人材プール」と呼ぶこともあります。
採用には至らなかったものの、応募や選考で出会った優秀な人材の情報を、データベース上で管理すれば、アプローチするべき人材が絞りやすくなります。
求人広告とは異なり、自社で情報を管理するため、掲載費がかかりません。上手く運用できれば、採用コストの削減にもつながります。
自社に最適な採用手法を選ぶための4ステップ

自社に適した採用手法を選ぶための方法を、4ステップに分けて紹介します。
- 採用課題を洗い出す
- 採用ニーズを整理する
- 採用ターゲットに合った採用手法を選ぶ
- いくつかの手法を組み合わせる
1.採用課題を洗い出す
最適な採用手法を選ぶには、自社の採用課題を整理することが肝心です。
新しく採用活動を始める場合は、採用活動の目的を明確にしましょう。また、採用活動を行っているのに採用につながらない場合は、何らかの課題を抱えている可能性があります。そのため、具体的な採用課題の洗い出しが必要です。
採用課題には、次のようなものがあります。
- 採用ターゲットに合った人材からの応募がない
- 応募の数が少ない
- 選考に時間がかかり、候補者の管理が追いつかない
- 選考の通過率が低い
- 入社後の定着率が低い
- 採用に費用をかけられず、効果が出ない など
2.採用ニーズを整理する
採用ニーズを整理するには、採用要件を明確にすることが重要です。採用要件とは、採用したい人材の特徴やスキル、実績などを整理したものを指します。
採用ターゲットは条件によって分類されたグループ(集団)であるのに対して、採用ペルソナとは「企業が入社してほしいと思う架空の人物像」のことです。
採用要件やペルソナがない場合は、募集する職種の現場にヒアリングを行うなどして、詳細な条件を設定しましょう。
採用要件やペルソナを設定することで、採用に関わるすべての社員と、求める人物像のイメージを共有しやすくなります。
3.採用ターゲットに合った手法を選ぶ
採用手法には、それぞれで異なるメリットとデメリットがあります。採用ターゲットが変われば、適した採用チャネルも変わります。
たとえば、採用ターゲットは即戦力なのに、中長期的な施策のオウンドメディアリクルーティングのみに取り組んでいても目的は達成されません。この場合は、アルムナイ採用や、採用要件や期限を正確に伝えた上での人材紹介サービスが適切でしょう。
カルチャーマッチを重視するケースでは、オウンドメディアリクルーティングやSNS採用などの採用ブランディング+ダイレクトリクルーティングが適しています。
専門的なスキルをもった人材が欲しいのであれば職種に特化した求人サイト、採用にあまりコストがかけられない場合はSNS採用やリファラル採用…というように、採用ターゲットと社内のリソースを踏まえた検討が必要です。
4.いくつかの手法を組み合わせる
高度な知識やノウハウが不可欠な採用手法ひとつに絞ってしまうと、採用がなかなか進まないケースが予想されます。例を挙げれば、ダイレクトリクルーティングはスカウトメールの質によって成否が左右されます。
また、ミートアップで出会った人材にカジュアル面談で理解を深める場を設けるといった柔軟性も重要です。
ほかにも、採用チャネルによって出会える求職者の層が変わるので、母集団の内訳を偏らせない点でも複数の採用手法の併用は効果的です。
ダイレクトリクルーティングのノウハウがない際は、外部に依頼するのもおすすめです。ダイレクトリクルーティングサイト会員数4年連続No.1「Re就活キャンパス」を運営する株式会社学情にぜひお問い合わせください。
採用手法を選ぶ際のポイント
採用活動を効率的に進めるには、採用手法の選び方が重要です。選び方を間違えると、採用活動が長期化したり、採用のマッチング精度が低下したりする可能性があるので注意しましょう。
採用手法を選ぶ際のポイントは次の通りです。
- 採用手法のメリット・デメリットを理解する
- 手法ごとの採用コストを把握する
- 特化型の媒体を選ぶ
- 他社の採用成功事例を参考にする
採用手法のメリット・デメリットを理解する
採用手法には、それぞれメリット・デメリットがあります。採用活動を効率的に進めるには、採用手法のメリット・デメリットを理解し、採用課題に適した手法を選ぶことが大切です。
採用手法の効果だけでなく、採用コストや期間、必要な工数など、その採用手法を適切に運用できるかも確認しましょう。
魅力的な採用手法であっても、採用コストが見合わなかったり、人手不足で十分に活用できなかったりすれば、期待する効果が得られないかもしれません。
手法ごとの採用コストを把握する
採用手法を選ぶうえで、採用コストは大切な判断基準です。効果的な採用手法であっても、いくつも導入したり、予算以上のコストをかけて取り入れたりするのは難しいでしょう。
たとえば、人材紹介で10人採用するとなると、1,000万以上の採用コストがかかります。反対に、採用コストが低いものや無料で利用できる手法ばかりを取り入れても、期待する効果を得られない可能性があります。
手法ごとの採用コストを把握し、予算や費用対効果と併せて検討することが大切です。
特化型の媒体を選ぶ
求人サイトや人材紹介、合同企業セミナー、ダイレクトリクルーティングなどには、総合型と特化型の媒体があります。
採用ターゲットによっては、総合型よりも特化型の媒体の方が効率的にアプローチでき、応募数の増加やマッチング精度の向上などが期待できます。
たとえば、経験者採用を目指すなら、20代後半から30代の転職に特化した「Re就活30」がおすすめです。キャリアアップやこれまでの経験を活かした転職を希望する登録者が多く、経験者採用に向いています。
他社の採用成功事例を参考にする
採用手法を選ぶ際は、他社の採用成功事例を参考にしましょう。採用ターゲットや課題によって適切な採用手法が異なるため、他社の事例を参考にすることで、より具体的にイメージしやすくなります。
他社の採用成功事例を参考にする際は、まず自社の採用課題を洗い出してから、似たような採用課題を抱えている企業の事例を探してみてください。
ただし、必ずしも同じ効果が得られるとは限りません。採用市場の動向や採用課題の細かい違いによっても効果が左右される点を考慮に入れましょう。
採用手法ごとの成功事例
採用手法ごとに成功事例をご紹介します。新しい採用手法を導入する際の参考にしてください。
動画を活用した採用ブランディングによる採用成功事例
|
業種・規模 |
200人規模の不動産会社 |
|
課題・ニーズ |
自社の魅力を学生に訴求するための動画の作成 |
|
活用したサービス |
JobTube |
|
効果 |
業務内容や会社の雰囲気等を理解し、興味を持って選考に進んでくれた学生が増加 |
「堅い」企業イメージを払拭するために“職場体感型採用動画”「JobTube」を作成。マイページ上で視聴してもらうことで会社・仕事への理解や、志望度が向上しました。
キャリア(経験者)採用向け合同企業セミナーによる採用成功事例
|
業種・規模 |
3000人規模の繊維製品メーカー |
|
課題・ニーズ |
自社と接点のなかった20代転職希望者からの応募増 |
|
活用したサービス |
Re就活、転職博 |
|
効果 |
期待以上に質の高いマッチングを創出、定期的に採用に成功 |
キャリア対象の合同企業セミナーにはじめて参加し、1日で100人近くの求職者と接触。また、来訪者のほとんどが当社の採用ターゲットと一致する20代で、個別面談によって応募を増やすことに成功しました。
人材紹介による採用成功事例
|
業種・規模 |
800人規模のIT・通信会社 |
|
課題・ニーズ |
人材獲得競争の激化により、20代人材の母集団形成が困難に |
|
活用したサービス |
Re就活エージェント |
|
効果 |
2年間で20人の20代・若手人材の採用に成功 |
20代人材の母集団形成が困難な状況下で、「Re就活エージェント」を利用。質の高い求職者をコンスタントに紹介してもらい、2年間で20人の採用に成功しました。
自社の課題に適した採用手法を選ぼう!
採用活動を成功させるには、自社の課題に適した採用手法を選ぶことが大切です。自社の採用課題を洗い出し、最適な手法を検討しましょう。
株式会社学情は、新卒採用や第二新卒採用、キャリア採用などをサポートするサービスを展開しています。採用手法の選定にお悩みの方は、株式会社学情へお問い合わせください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。