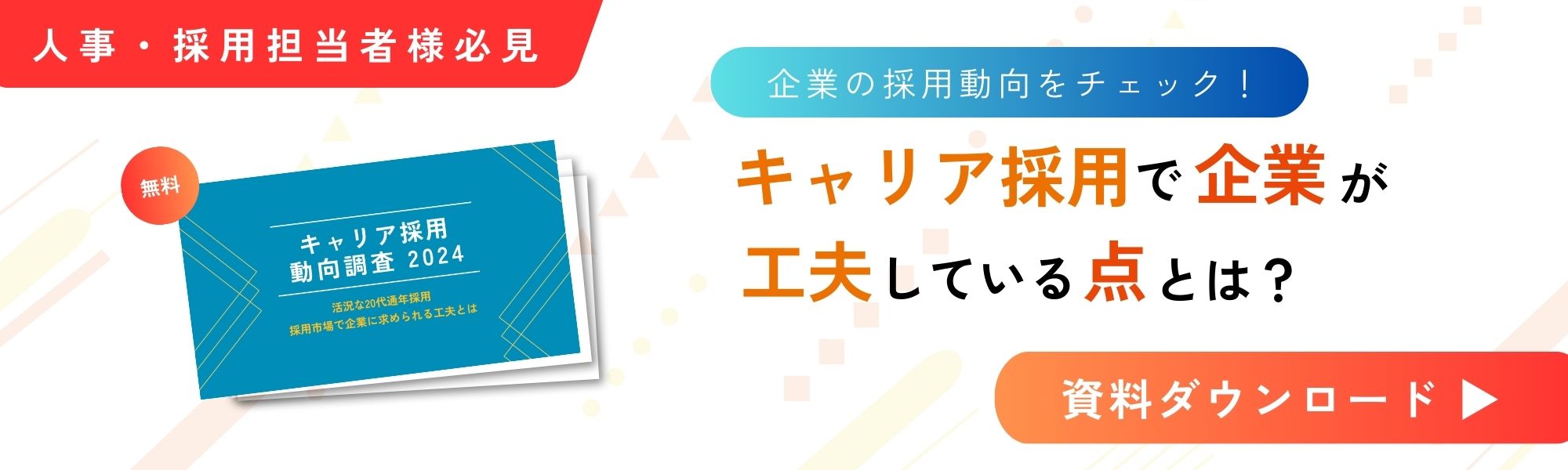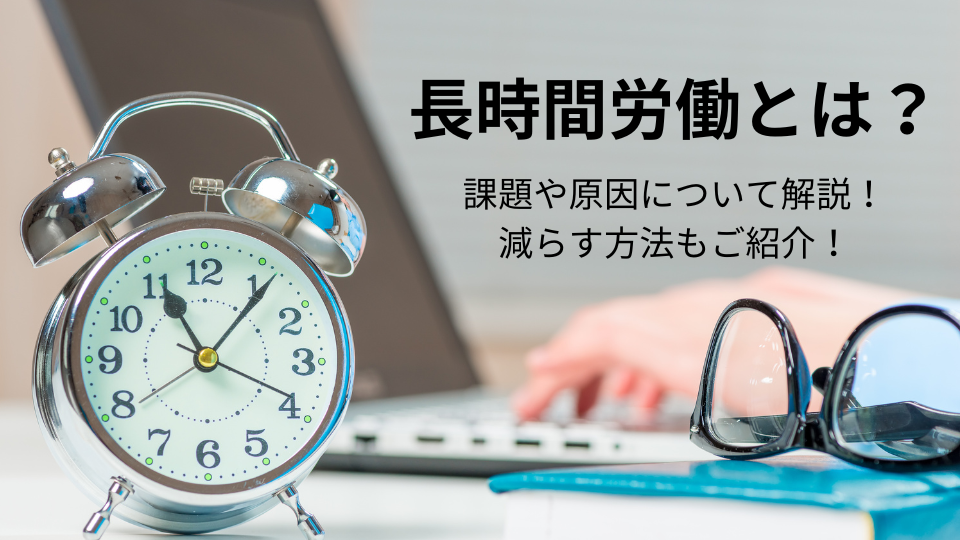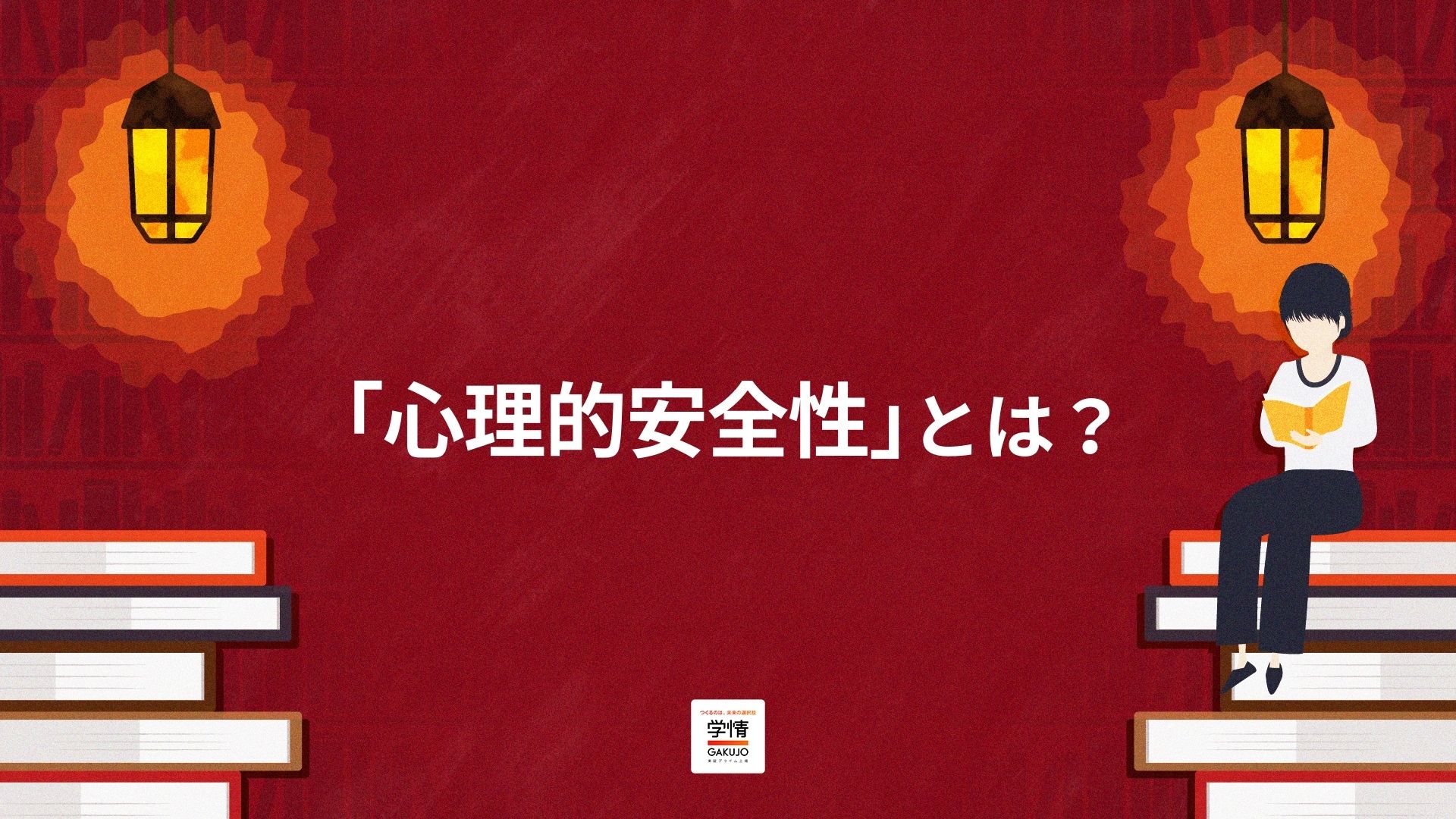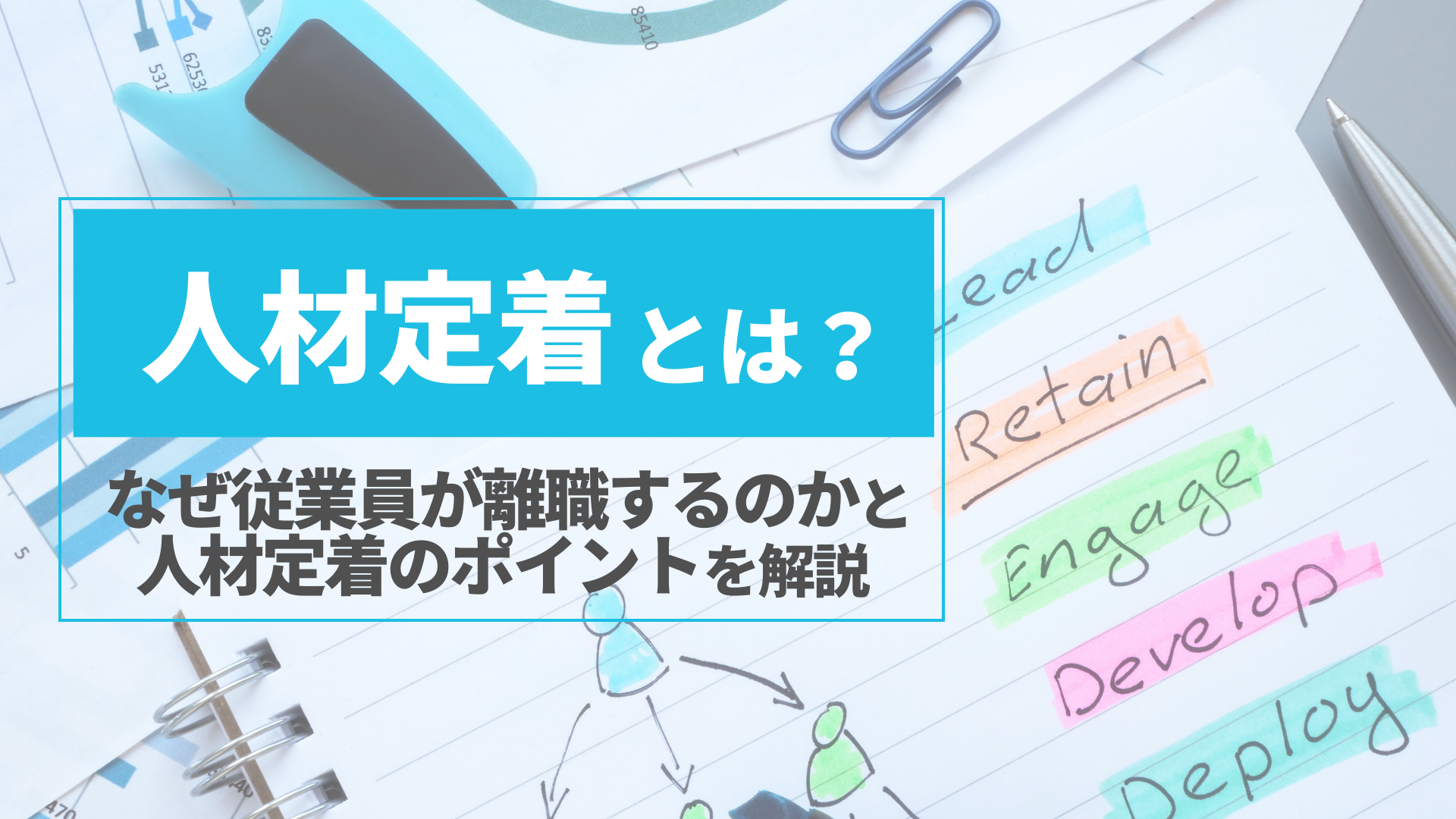VUCAとは|予測不可能な現代で求められるスキルと人材、採用方法
2023.09.14


VUCA(ブーカ)とは、変化が激しく将来の予測が難しい現代を表した言葉です。この記事では、VUCA時代に必要なスキルや人材、VUCA時代を生き抜くために企業や組織がどう対応するべきかをご紹介します。
VUCAとは
VUCA(ブーカ)とは、
- Volatility(変動性)
- Uncertainty(不確実性)
- Complexity(複雑性)
- Ambiguity(曖昧性)
の頭文字を取った言葉で、先行きが不透明で変化の激しい現代を表します。将来の予測がむずかしい状況でも最善の意思決定をおこない、ビジネスを成功に導くために重要な考え方として注目されています。
それぞれの言葉の意味
VUCAのそれぞれの言葉の意味をご説明します。
Volatility(変動性)

Volatilityとは、「不安定さ」「変わりやすさ」を意味する英単語です。VUCAでは、事象の変わりやすさ、しかも急激な変動性を指しています。
日々、急速に進化するテクノロジーによって、新しい事業やビジネスチャンスが生まれています。
Volatility(変動性)を象徴する、アメリカのビデオ・DVDのレンタルチェーン店「ブロックバスター」の事例があります。同社は、2004年には9,094店舗を展開する有名企業でしたが、動画配信サービスの台頭がきっかけになり2010年に破産しました。
新たなビジネスチャンスを逃さないためには、世の中の潮流に常に敏感でいつづけること、また、その変動性にすぐに対応できる俊敏さが求められます。
Uncertainty(不確実性)

Uncertaintyとは、「確信のないこと」「不確かさ」を意味する英単語です。VUCAでは、今までのやり方では通用しなくなり、将来の予測に確信がもてなくなった状況を指しています。
年功序列制度や終身雇用は崩壊しつつあり、働き方は多様化しています。新しい常識にどう対応していくか、不確実な将来の見通しをどう立てるかが、企業にとって重要な課題です。
Complexity(複雑性)

Complexityとは、「複雑さ」「複雑なもの」を意味する英単語です。VUCAでは、グローバル化などの影響でビジネスが複雑になったことを指しています。
交通網の発達やデジタル技術の進歩によって各国の距離が近づき、海外への進出は以前より容易になりました。しかし、それに伴い、異文化理解のむずかしさや地球規模の課題が顕在化 しています。価値観の多様化によって市場ニーズが細かく枝分かれしていることも複雑性を表す一例でしょう。
多様なニーズに応えるには、さまざまなバックグラウンドを受容し、理解する態度が必要です。
Ambiguity(曖昧性)

Ambiguityとは、「両義性」「不明確さ」を意味する英単語です。日本語の「曖昧」は「内容が捉えにくく、はっきりしないこと」という意味ですが、英語の「Ambiguity」には「ひとつの事柄が複数の意味をもっていること」のニュアンスがあります。
VUCAの他の3要素である、変動性(Volatility)・不確実性(Uncertainty)・複雑性(Complexity)が組み合わさることでAmbiguity(曖昧性)が生まれるとされています。
日々新しい技術やサービスが開発され(Volatility)、過去の経験から将来の予測を立てるのが難しくなり(Uncertainty)、物事の要素が多元化する(Complexity)ことで、ある特定の出来事に対してたったひとつの正解を導き出せるケースは稀になりました。これがVUCAにおける曖昧性を指しています。
このような環境では、とにかく行動してみる勇気をもった意思決定と、失敗をいとわない姿勢が大切です。
VUCAという言葉が注目されるようになった背景
現代は、異常気象や急速なテクノロジーの進化、多様化するニーズなどによって、将来の予測を立てにくい 時代です。
こうした不確かさの中で、企業や組織は状況に合わせてすばやく 行動し、時代に合った人材を育てなければなりません。そこで、現代の課題を言語化し、どう対応すべきかを表現した「VUCA」の考え方が重要視されています。
VUCAは、もともと軍隊で使われていた言葉です。当時は、アメリカとソ連 の冷戦が終結した1990年代以降、東西対立という単純な敵対構造から、複雑でわかりにくい世界への移行を表す言葉でした。2016年の世界経済フォーラム(ダボス会議)で用いられたのがきっかけで、経済・ビジネス界でも一般的に使われるようになりました。
戦況についていけない兵士が生き延びられないように、ビジネスシーンでも状況変化にすばやく 適応し、組織と行動を変えていくことが求められるようになったのです。
似た言葉との違い|BANI、RUPT、TUNA
- Brittle(脆い)
- Anxious(不安な)
- Nonlinear(非線形の)
- Incomprehensible(不可解な)
この言葉は、「IFTF(Institute For The Future:未来研究所)」のジャメイ・キャッシォ(Jamais Cascio)氏が作りました。VUCAが現代の課題と、それに対する適応の必要性を表すのに対し、BANIは実現すべき未来のために何が必要かを表現したものです。
RUPTとは、
- Rapid(急速な)
- Unpredictable(予測不可能な)
- Paradoxial(逆説的な)
- Tangled(もつれた)
の頭文字です。RapidやTangledの語からは、VUCAよりもさらに速く、より複雑に 物事が進展していくことを強調しているようにも感じられます。
TUNAは、
- Turbulent(激動の)
- Uncertain(不確かな)
- Novel(新しい・奇抜な)
- Ambiguous(曖昧な)
の頭文字で、Forbesの記事によると、オックスフォード大学ではVUCAより身近な用語として使われているようです。本質的には似ていますが、VUCAよりそれぞれの言葉に強い印象を受けます。
VUCA時代に必要とされるスキル
VUCAそれぞれの性質に対応する形で、求められるスキルを紹介します。
Volatility(変動性)に必要とされるスキル
Volatility(変動性)に対応するには以下のようなスキルが求められます。
- 臨機応変に、急激な変化にも対応する力
- 固定観念にとらわれない柔軟な考え方
- テクノロジーへの理解力+情報収集処理能力
VUCA時代では、たとえばスマートフォンの登場など、テクノロジーの進化によって人々の価値観をおおきく転換する急激な変化が起こります。既存の成功事例が正しいと思いこまずに、 状況にあった対応を模索する力が必要です。
それには、普段からアンテナを張り続け新しい技術の情報を常に吸収する習慣、その情報を正しく理解したうえで適切に取捨選択をするスキルが求められます。DXへの適応力も必要です。
Uncertainty(不確実性)に必要とされるスキル
Uncertainty(不確実性)に対応するには以下のようなスキルが求められます。
- 新しいやり方をトライアンドエラーしていく行動力
- 仮説を立ててアプローチする力(問題解決力)
- 迅速な意思決定
VUCA時代では、たとえその業界で長年の経験をもっている人材でも、明確な答えを導き出すのは至難の業です。なぜなら、それまでのセオリーが成り立たない可能性が高いからです。
このような環境では、市場を十分に観察して理解し、それに沿った仮説を立ててアプローチできる人材がキーを握ります。たとえまったく新しいやり方であっても 迅速に実行を決定し、失敗しても要因を見つけてトライアンドエラーしていける人材が、物事を成功に導くでしょう。
OODA(ウーダ)ループもVUCAと同じく元は軍事用語なので、相性がいいとされています。
OODA(ウーダ)ループ
OODA(ウーダ)ループとは、
-
- 観察する(Observe)
- 状況を理解する(Orient)
- 決める(Decide)
- 動く(Act)
をくり返すフレームワークです。
よく知られているPDCAサイクルに替わり、VUCA時代に対応する手法として注目を浴びています。
計画(Plan)からはじまるPDCAサイクルとは異なり、OODAループは観察からはじまります。
先行きが不透明な現代では、初めに立てた計画どおりに物事を完遂できる可能性は低いです。複雑な市場ニーズを観察して状況を理解し、迅速な決定・実行をする、このフレームワークは、VUCA時代により適切といえるでしょう。
Complexity(複雑性)に必要とされるスキル
Complexity(複雑性)に対応するには以下のようなスキルが求められます。
- 複雑な市場・経済を分析する力
- 多様性を受け入れるコミュニケーションスキル
VUCA時代では多くの人がそれぞれの価値観にしたがって動くため、市場全体を一括で把握することは困難です。そんな複雑な要素をひとつひとつ分解して、本当はなにが求められているのかを理解する人材がいれば、市場で優位に立てるでしょう。
企業には、多様な価値観を受け入れるコミュニケーションスキルも必要です。
Ambiguity(曖昧性)に必要とされるスキル
Ambiguity(曖昧性)に対応するには以下のようなスキルが求められます。
- 物事の本質を見抜き、複数の解釈に惑わされない価値観
- 自分の頭で考える力
- 環境に影響されない「ポータブルスキル(=持ち運び可能なスキル)」
曖昧性に満ちた世界では、他人の解釈に惑わされずに冷静に情報を収集し 、問題の本質を見抜く力が求められます。言い換えれば「自分の頭で考える力」が必要です。
また、近年ではAI技術がめざましい発展を遂げており、「AIに人間の仕事が奪われる」というような話を耳にします。しかし、AIは過去のデータに基づいて判断 しますから、前例のない課題や感性に即した仕事は不得意です。
この点においても、これからの人材には「自分の頭で考える力」が必須といえるでしょう。
業務内容や時代背景に影響されない「ポータブルスキル」も重要です。「ビジネス基礎力」とも捉えられます。高いレベルでポータブルスキルを身につけた人材は、どのような会社や業界でも必要とされるのです。
VUCA時代を企業が生き抜くためには?
VUCA時代を企業が生き抜くには、前章で紹介したスキルをもった人材が必要です。以下のふたつの方法を紹介します。
①既存社員を育成する
②新しく人材を採用する
①既存社員を育成する
まずは既存社員を育成する方法があります。
研修等をおこない、自ら考える力やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に貢献するスキルを育てます。具体的な方法には、ロジカルシンキング研修やデジタルスキルを再開発する「リスキリング」があります。
迅速に意思決定し行動に移すマネージャーの効率的な育成も、VUCA時代の企業には必要です。企業によるエンパワーメント(権限委譲)とは、一般的に、指示→合意→援助→委任の4段階を踏んで部下を育成することを指します。ステップを踏みながら徐々にマネージャーの権限を部下に委譲していき、新たなマネージャーに育て上げます。
また、問題解決能力やプレゼンスキル、コミュニケーション能力などを含んだ汎用性の高いスキル、つまり、ポータブルスキル(=持ち運びできるスキル)も重要な要素です。
ポータブルスキルを育てるには、厚生労働省の研修資料の活用や、外部の研修サービスの利用がおすすめです。
※参考:ポータブルスキル見える化ツール(職業能力診断ツール)(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23112.html)
②新しく人材を採用する
VUCA時代を生き抜く組織づくりには、外から新しく人材を採用する方法もあります。
キャリア(経験者)採用を行い、上の章で紹介したスキルをすでにもった人材を採用できれば、即戦力の増加が期待できます。既存社員にもよい影響をあたえ、メンバーを引っ張ってくれる頼もしい存在となるでしょう。
ほかには、VUCA時代に適応する価値観をもった人材のポテンシャル採用もひとつの手です。
業界や時代に影響されないほど高いレベルでスキルを身につけた人材は、市場価値が高く、激しい採用競争が予想されます。
自社の採用リソースに限界がある際や、即戦力人材を勝ち取れない場合には、ポテンシャル採用がおすすめです。
ポテンシャル採用では、即戦力人材と比較してスキルや経験が少ない一方、VUCA時代に適応する価値観をもっている人材を採用します。入社後は、計画的な研修によって、VUCA時代に必要なスキルを身につけた人材に育成します。
VUCA時代に生まれ育ったZ世代は、この時代に即した価値観をもっています。次の章で特徴を紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
VUCA時代を生きるZ世代の特徴
「VUCA」という用語はおもに2000年代に流行しました。 1990年代後半~2012年に生まれたZ世代は、VUCA時代に育ち、急速なテクノロジーの進化や国際的な経済の変動のなかで価値観を形成してきたといえるでしょう。
日本生まれのZ世代は、東日本大震災や新型コロナウィルス感染拡大を幼児期~青年期に経験していて、昨日までの当たり前が急激に変わる可能性があることを無意識に知っています。
100%の正解がないVUCA時代において、自ら答えを模索していく必要を肌で感じているのです。
デジタルネイティブ
Z世代は「デジタルネイティブ」と呼ばれ、情報収集とその取捨選択の能力に長けています。子どものころからデジタルツールに慣れ親しんでいて、デジタルでの情報収集が当たり前だったためです。目的によって情報収集の方法を自然に使い分けている傾向があります。
自ら発信することにも意欲的であり、全体的にインターネットリテラシーが高いのも特徴です。
ダイバーシティ&インクルージョン
Z世代は多様性の受け入れに好意的です。
インターネット上の膨大な情報に簡単にアクセスできる環境で育ち、幼いころからさまざまな価値観に触れる機会が豊富でした。多様な考え方に共感し、自分ごととして受け止められるZ世代には、他人との違いを個性として認められる人が多く見られます。
自律的なキャリア形成
Z世代は、自身のキャリアを過度に企業側に委ねず自律的に形成していくことへの関心を高めています。年功序列制度や終身雇用の崩壊などにより、大企業に就職しても生涯安泰といえなくなってきたVUCA時代では、自然な流れともいえます。
具体的に「なぜこの会社で働くのか」「自分はどのような分野で価値を提供していくのか」「どのような経験を積み、どのようなスキルを身に付けていくのか」を重視しています。言い換えれば「ポータブルスキル(=持ち運び可能なスキル)」が大事だと捉えているのです。
Z世代に効果的な採用方法
Z世代を効果的に採用するには、彼ら・彼女らの価値観に合わせた採用方法がおすすめです。
-
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、スカウトメールなどで学生に直接アプローチする採用手法です。個性を大事にするZ世代には、「あなたのこういうところに魅力を感じました!」といったOne to Oneのメッセージが心に響くでしょう。
-
動画発信
企業や社員の雰囲気をリアルに伝えられる動画発信も、Z世代に魅力をアピールするのによい施策です。
Z世代は失敗したくないという価値観を持っている傾向が強いことから、今後働く会社のオフィスの雰囲気や一緒に働く同僚の人となりは、ミスマッチを防ぐために必須の 情報となるでしょう。 -
SNSの活用
Instagram、Twitter、YouTubeなど、Z世代によく利用されているSNSで自社の魅力をアピールするのも有効です。求職者の興味にフォーカスした投稿を続けていれば、ファンが増えてより多くの人の関心をあつめられます。アカウント作成自体は無料でできるため、初期コストの低い施策といえるでしょう。
まとめ|先行き不透明なVUCA時代に対応できる組織づくりを
VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字からなる言葉で、将来の見通しが立ちづらい現代を表す言葉です。
VUCA時代の企業には、迅速な意思決定をできる人材や、新しいテクノロジーへの対応力、巧みな市場分析で多様なニーズを理解するスキルなどが必要です。
これまでの常識が通用しなくなったなかでも、時世に沿った既存社員の育成と新規人材の採用で、VUCA時代を生き抜く組織づくりを目指しましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。