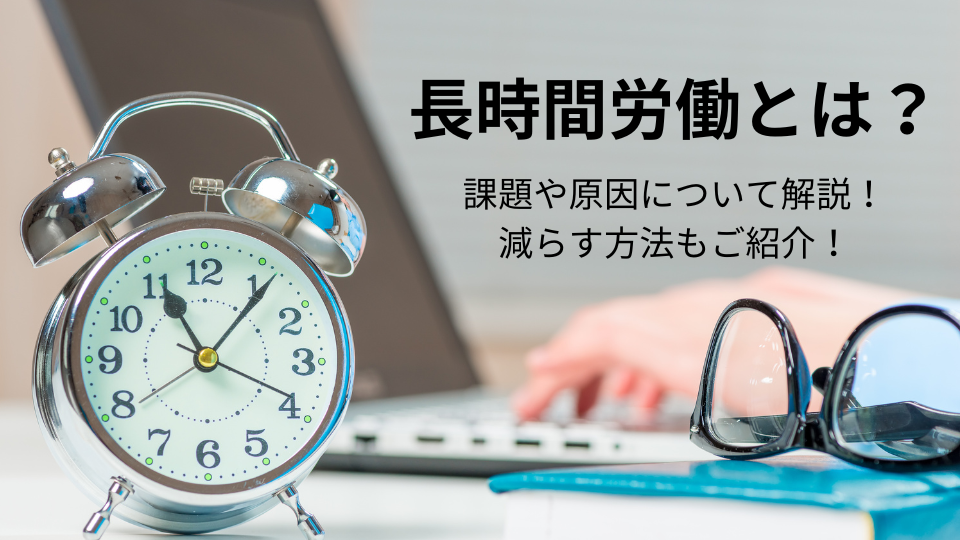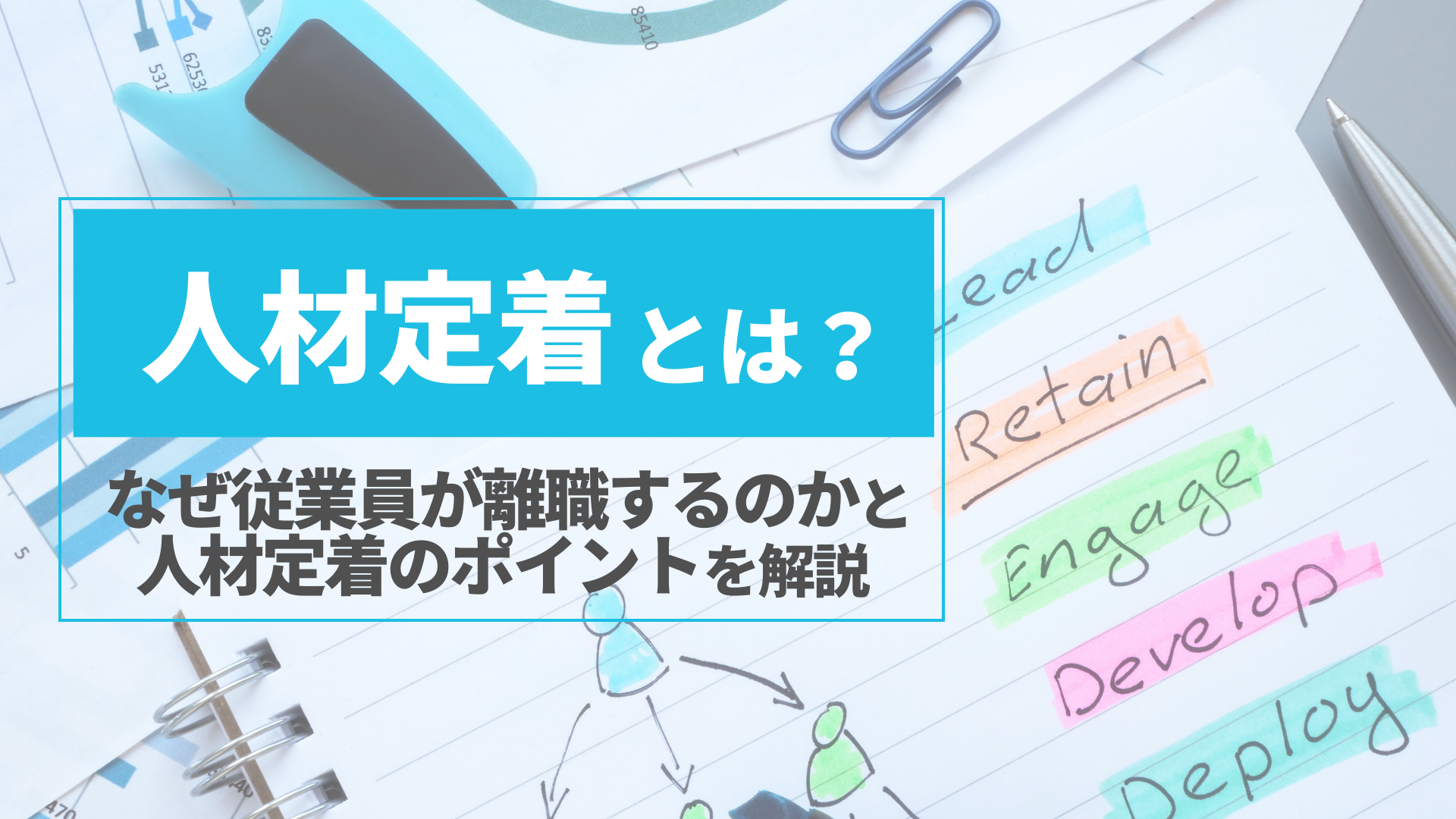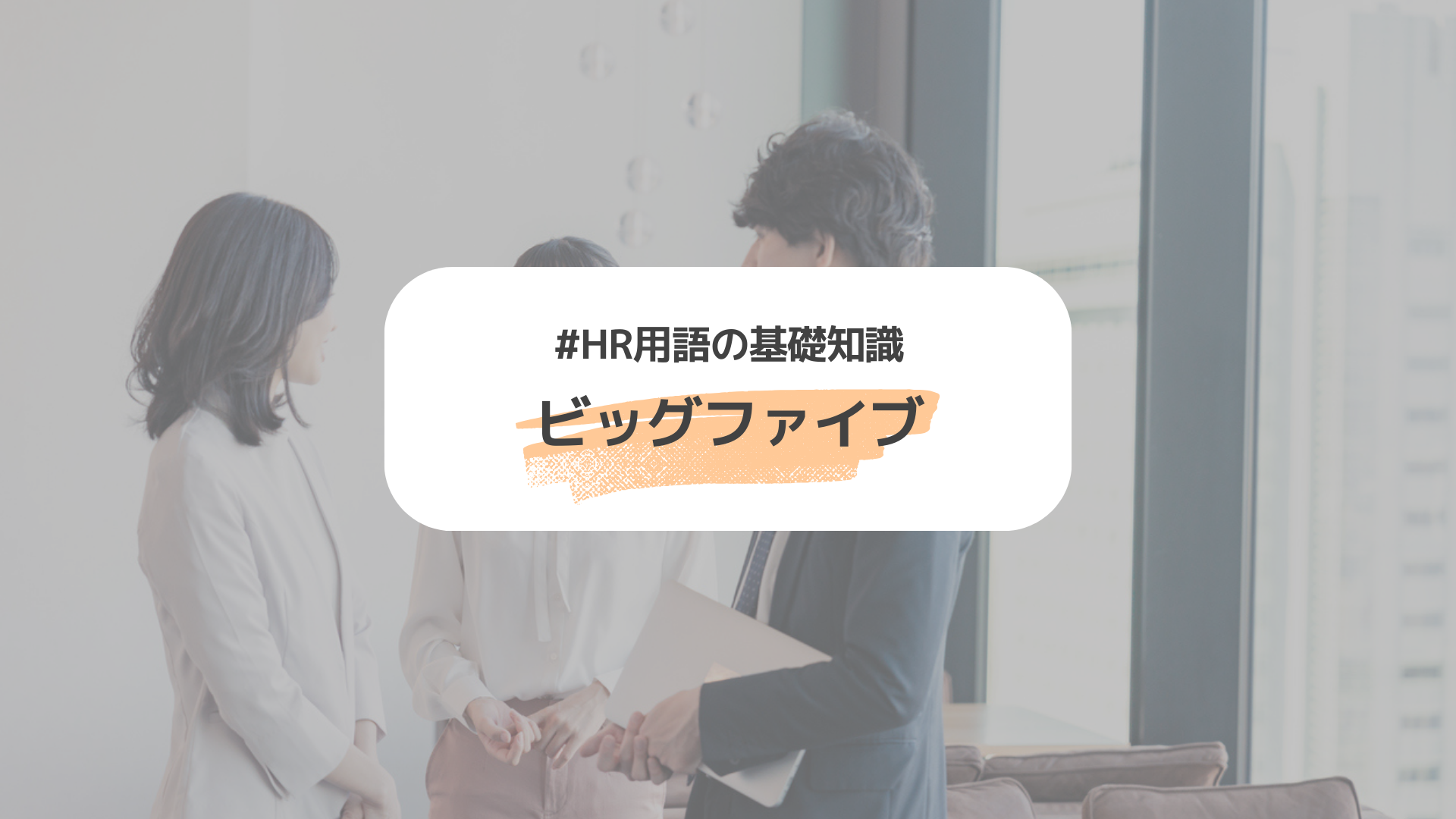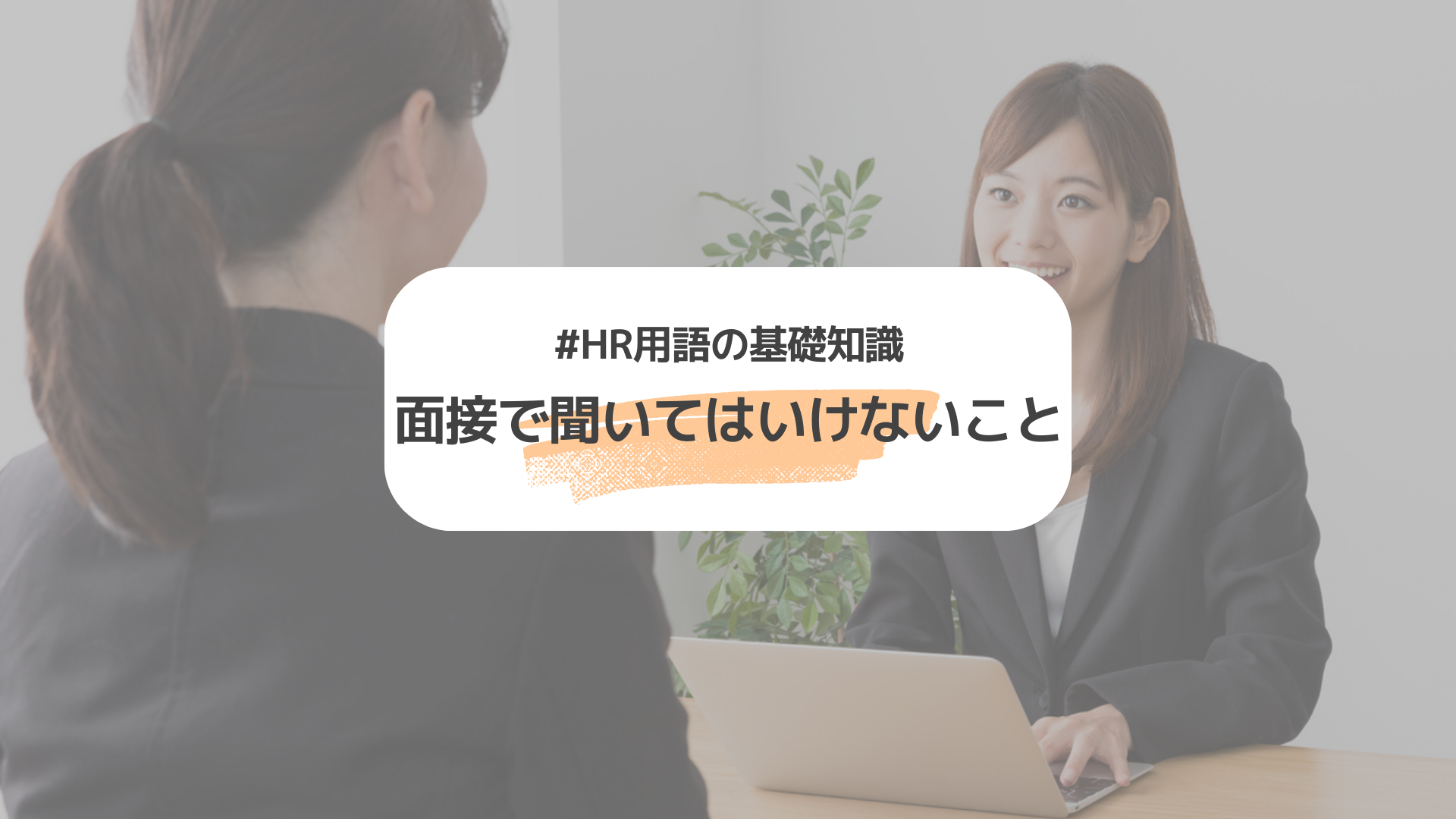心理的安全性を高めるには?チェック方法と今すぐできる取り組みを紹介
2024.02.01

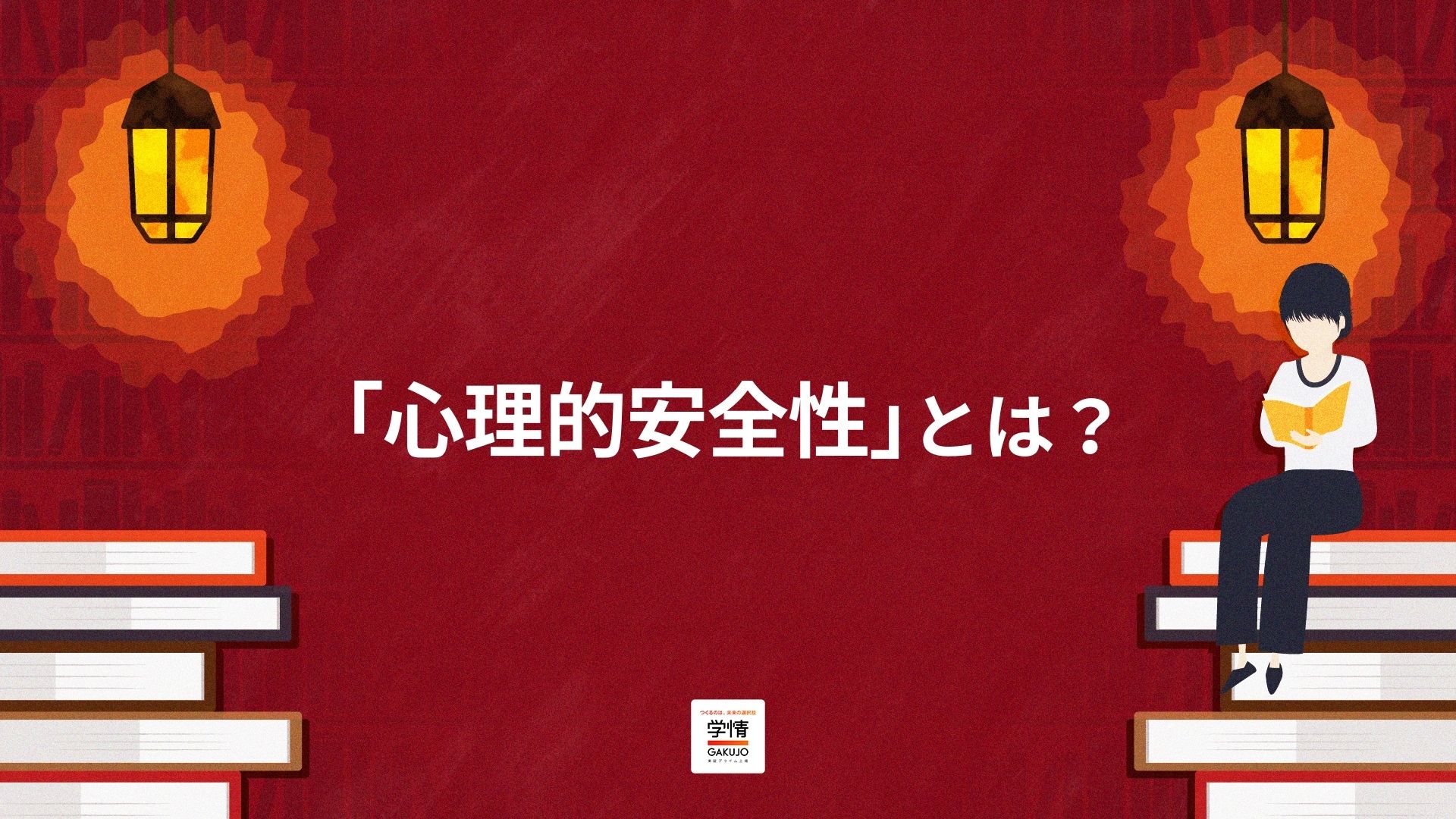
2012年のGoogleの調査によって、「心理的安全性」が良好なチームをつくるのに重要な要素であることが広まりました。
心理的安全性が低いと何が起こるのでしょうか。あなたのチームは心理的安全性を保てていますか。ぜひこの記事でチェックして対策してみてください。
心理的安全性とは
「心理的安全性(psychological safety)」とは、ビジネスに関する心理学用語のひとつで、ハーバード大学で組織行動学を研究するエイミー・エドモンドソン教授が1999年にこの概念を提唱しました。エドモンドソン教授によると心理的安全性は「チームにおいて、他のメンバーが自分が発言することを恥じたり、拒絶したり、罰をあたえるようなことをしないという確信をもっている状態であり、チームは対人リスクをとるのに安全な場所であるとの信念がメンバー間で共有された状態」と定義されています。
近年、イノベーションや生産性向上が重要であることの議論が盛んに行われていますが、そのためには空気を読まない発言や、伝統を否定するような発言があっても、組織内で拒絶されず、評価が下がらない場を作らなければなりません。Googleは2012年から約4年間をかけて、成功し続けるチームに必要な条件を探る「プロジェクト・アリストテレス」を実施、社内の数百に及ぶチームを分析対象とし、より生産性の高い働き方をしているのはどのようなチームなのか調査しました。
その結果、「心理的安全性の高いチームのメンバーは、離職率が低く、他のチームメンバーが発案した多様なアイデアをうまく利用でき、収益性が高く、マネージャーから評価される機会が2倍多い」ということが判明したことで、心理的安全性という言葉が広く知られるようになりました。その後日本でも、農林水産省が発表した「食品製造業における労働力不足克服ビジョン」(2019年)や、金融庁の「金融行政のこれまでの実践と今後の方針」(2019年)で活用される等、注目を集めています。
ぬるま湯組織との違い
心理的安全性が高いチームでは、自分の意見を遠慮せず誰とでも言い合えます。しかし、ただの「仲良しの集まり」とはまったく違うものであることを理解しなければなりません。
誰かがミスをしたときを例に考えてみましょう。
ただの仲良しこよしなら仲間の肩を叩いて「仕方ないよ」と慰めるだけかもしれません。
しかし、心理的安全性の高いチームでは、次はどのようにすれば同じミスを防げるかを周りのメンバーと率直に議論するでしょう。
前者では、失敗の報告自体はされるかもしれませんが同じミスが繰り返されます。ミスがあるということは、その度にフォローをする人間もいるということです。
誰も言わないだけでチーム内には不満が溜まっていき、人間関係の悪化につながる可能性があります。
それに対して、心理的安全性の高いチームでは、率直な意見交換によって生産性が高いのが違いです。
心理的安全性が低いとどうなる?
では心理的安全性が低い組織では、どのようなことが起こるのでしょうか。エドモンドソン教授は心理的安全性が低い状態で起こりうる以下の4つの不安についても発言しています。
- 無能だと思われる不安
- 邪魔をしていると思われる不安
- ネガティブだと思われる不安
- 無知だと思われる不安
発言したときに、「そんなことも知らないのか」「ミーティングが進まない」などと思われないか不安になる環境は、心理的安全性が低いと述べています。このような不安によって、ミスが見逃されたり、防げたはずの失敗が起きたりする可能性が高くなります。
- 無知と思われない、邪魔をしないようにと発言・質問を控える
- 無能と思われないようにミスを隠す
- ネガティブと捉えられないように、否定的な意見を言わない など
心理的安全性が高い組織をつくるメリット
心理的安全性が高い組織をつくることで、企業にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
メンバーのパフォーマンス向上
お互いを認め合い、尊重し合うという価値観の共有が職場内に根付くため、社員同士が切磋琢磨するようになります。自発的な学習も増え、個人のポテンシャル向上に繋がっていきます。そしてメンバー全員が安心しながら集中して仕事に取り組むことができるため、パフォーマンスが向上し業務の生産性が高まります。また、人は何かに集中してのめり込むと神経伝達物質であるドーパミンの分泌量が増えるため、更にやる気や集中力が増加するという好循環が生まれます。
イノベーションの推進
心理的安全性が高い組織では多様な価値観が認められるため、様々な個性や能力を持つ社員が組織の目標や課題に対して自由に議論できる環境が整っています。建設的な議論が行えるため、問題の早期発見・解決に繋がります。また、自分の意見を否定されるという不安がないため、個人の意見やアイデアが多く集まり、創造性に富んだアイデアに発展する可能性が高まります。
そして職場全体のコミュニケーションが活性化することで、社員間の共有もされやすくなります。このように心理的安全性が高く保たれていることによって、新しい物事や困難に立ち向かいやすくなるため、イノベーションが生まれやすい組織が出来上がります。
エンゲージメントの向上
エンゲージメントとは、社員の組織に対する愛着や思い入れを意味しています。居心地がいい、仕事がしやすいなど、心理的に安全な職場で働く社員は離職率が低いとされています。仕事へのやりがいが生まれ、自分の能力や特技を活かしながら業務に取り組めるため、今の会社で長く働きたいと思うようになります。その結果、優秀な人材の流出や退職の抑制にも効果があります。
自社の心理的安全性をチェックするには
心理的安全性が高まっているのか、取り組みを始める前はどのくらいなのかを知るためには、現状を計測することが大切です。2つの計測方法を参考にして、自社の心理的安全性をチェックしましょう。
「7つの質問」で計測する
エドモンドソン教授は、心理的安全性を7つの質問で計測する方法を提唱しました。設問に対して、「強くそう思う」「そう思う」「どちらとも言えない」「あまりそう思わない」「そう思わない」で回答し、度合いを見極めます。
1.チームの中でミスをすると、たいてい非難される
2.チームのメンバーは、課題や難しい問題を指摘し合える
3.チームのメンバーは、自分と異なるということを理由に他者を拒絶することがある
4.チームに対してリスクのある行動をしても安全である
5.チームの他のメンバーに助けを求めることは難しい
6.チームメンバーは誰も、自分の仕事を意図的におとしめるような行動をしない
7.チームメンバーと仕事をするとき、自分のスキルと才能が尊重され、活かされていると感じる
1、3、5は「そう思わない」に近く、度合いが低いほど心理的安全性が高い、一方、2、4、6、7は「強くそう思う」が多く、度合いが高いほど心理的安全性が高いと判断されます。
「3つのサイン」が見られるか確認する
心理的安全性が高い職場には、以下の3つのサインが見られるということも、エドモンドソン教授は提唱しています。
1.ポジティブな発言が多い
2.ミスや問題についても話す機会が多い
3.職場に笑いとユーモアがある
困難な状況でも前向きに捉え、ポジティブな発言が交わされている、成功以外の話も話題になる、笑いとユーモアで職場が明るいといった場合は、心理的安全性が高いケースが多いでしょう。チームメンバーの会話や雰囲気などを観察し、上記のサインが見られるか観察すると、心理的安全性の高低を確認できるはずです。
心理的安全性を高めるには
実際に筆者のチームで行っている心理的安全性を高めるための取り組みを2つご紹介します。
GOOD&NEW
GOOD&NEWとは、24時間以内に起きた「よかったこと(GOOD)」と「新しい発見(NEW)」をひとりずつ発表するアイスブレイクです。発表時間は30秒~1分以内の短時間とし、発表後には必ず全員で拍手をするのがルールです。
筆者のチームでは毎朝の会議でルーレットを回し、誰かひとりが発表しています。ほかに話したい人がいればもちろん自由に発表できます。また、内容は仕事に関係なくてもOKです。
そこでメンバーの意外なバックグラウンドや趣味を知って普段のコミュニケーションにも活かせますし、拍手をする/されることで、ポジティブな気持ちで1日のスタートを切れます。
アサーティブ・コミュニケーション
アサーティブ・コミュニケーションとは、自分も相手も大切にする自己表現のことです。自分の考えや気持ちを正直に伝えますが、相手の反応を受け止めようともします。
たとえば、見たいテレビがあるが食事に誘われたとき、無理に付き合うのはアサーティブではありません。
もしくは「急に言われても困る!」と怒って電話を切るのもアサーティブではありません。
「私が見たいテレビがあるのだけれど、今日がいいの?」と、自分の気持ちも伝えながら相手の意向も受け止めようとするのがアサーティブ・コミュニケーションです。
(出典:アサーション入門――自分も相手も大切にする自己表現法 (講談社現代新書) – 平木 典子 著)
実践しようとするとなかなかむずかしいですが、大事なのはバックグラウンドが異なるメンバーが集まってチームを構成しているのを忘れないことです。
まとめ
社員が言いたいことを安心して言える「心理的安全性」の高い組織は、さまざまなメリットが期待できます。ただし、仲が良いだけの職場は、ぬるま湯組織となってしまうリスクがあることも忘れてはいけません。そのため、良好な人間関係を保ちつつ、常に業務に対するモチベーションを高く維持させることが必要です。信頼関係を築きながら仕事への意欲も高められるピアボーナス等を活用して、心理的安全性の高い環境を実現しましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。