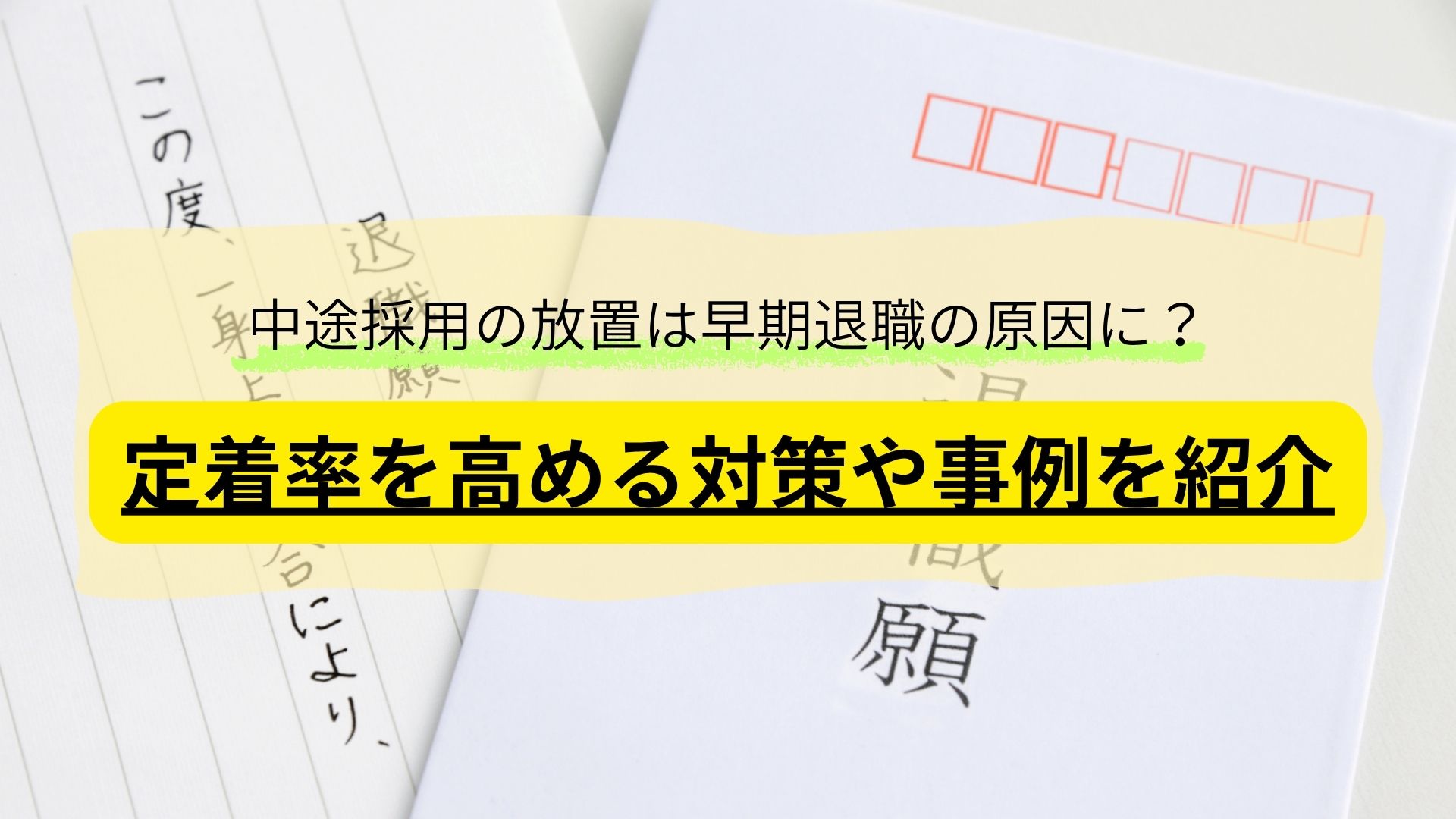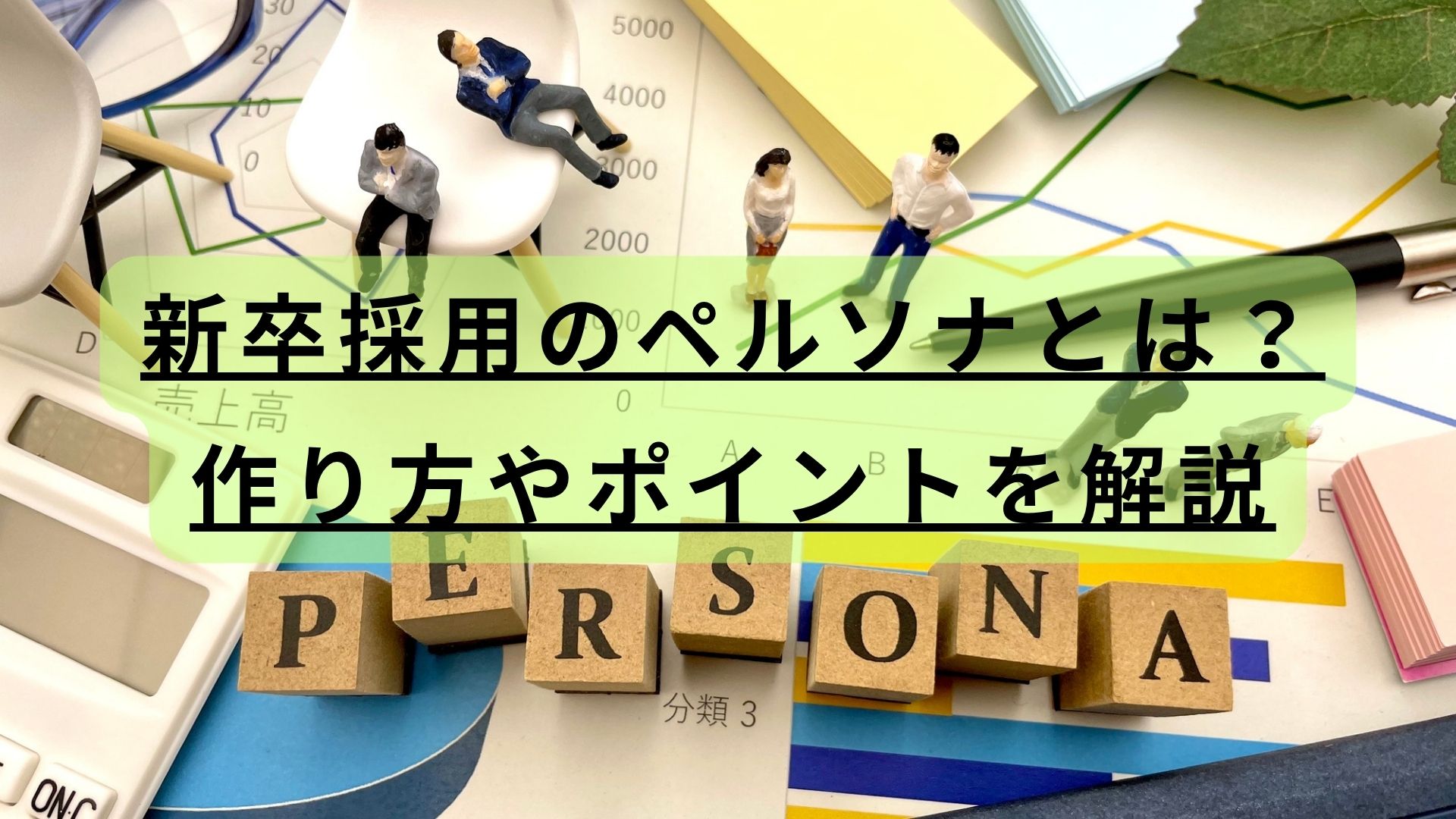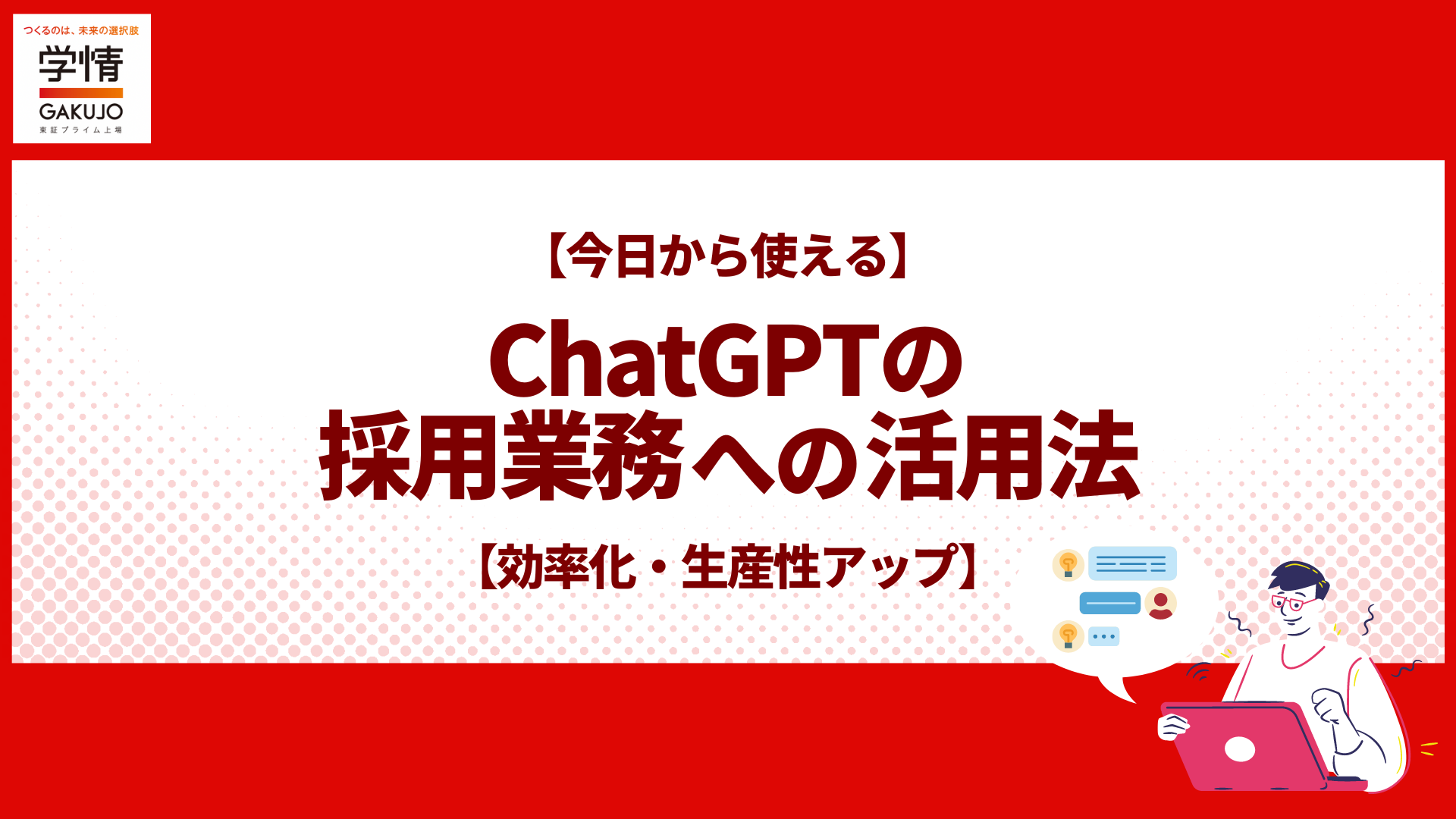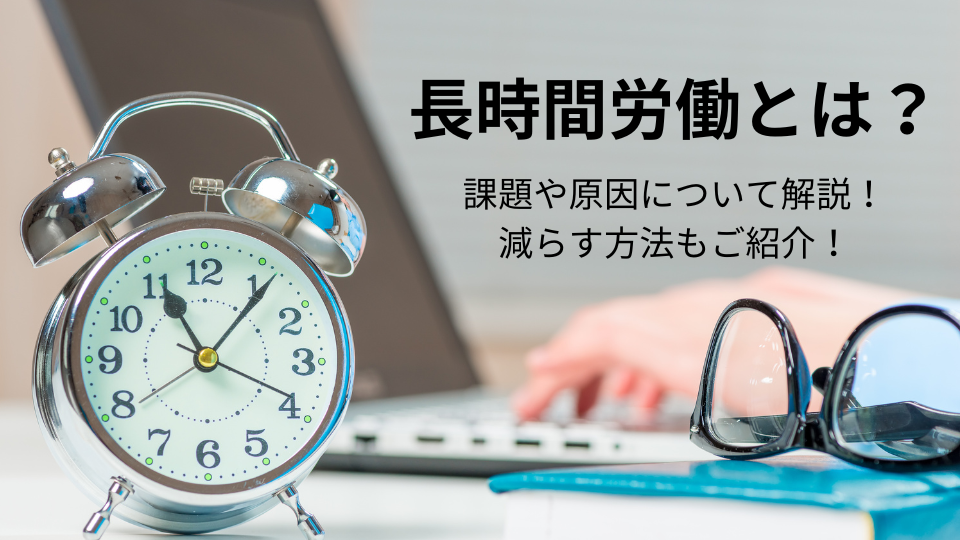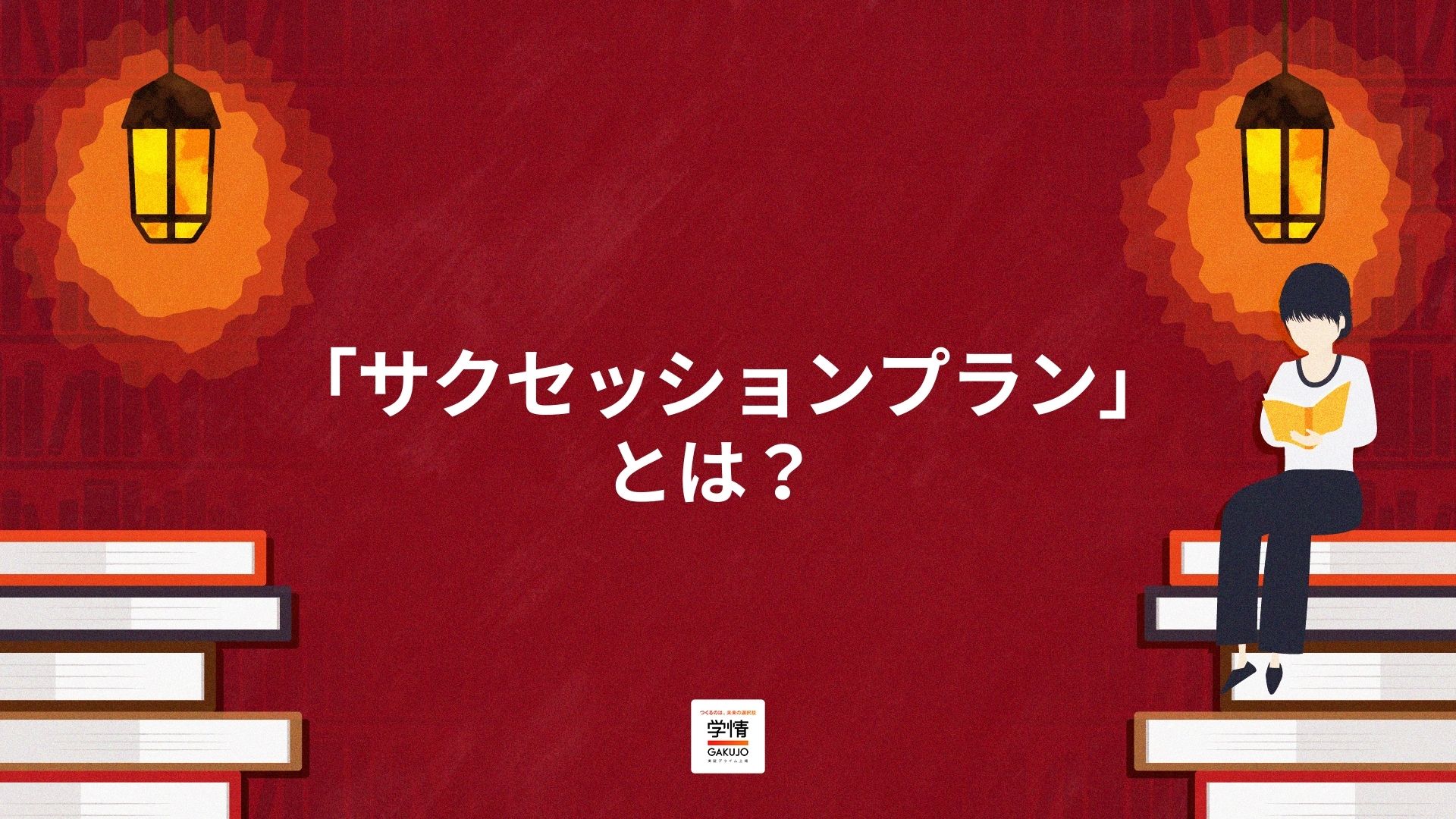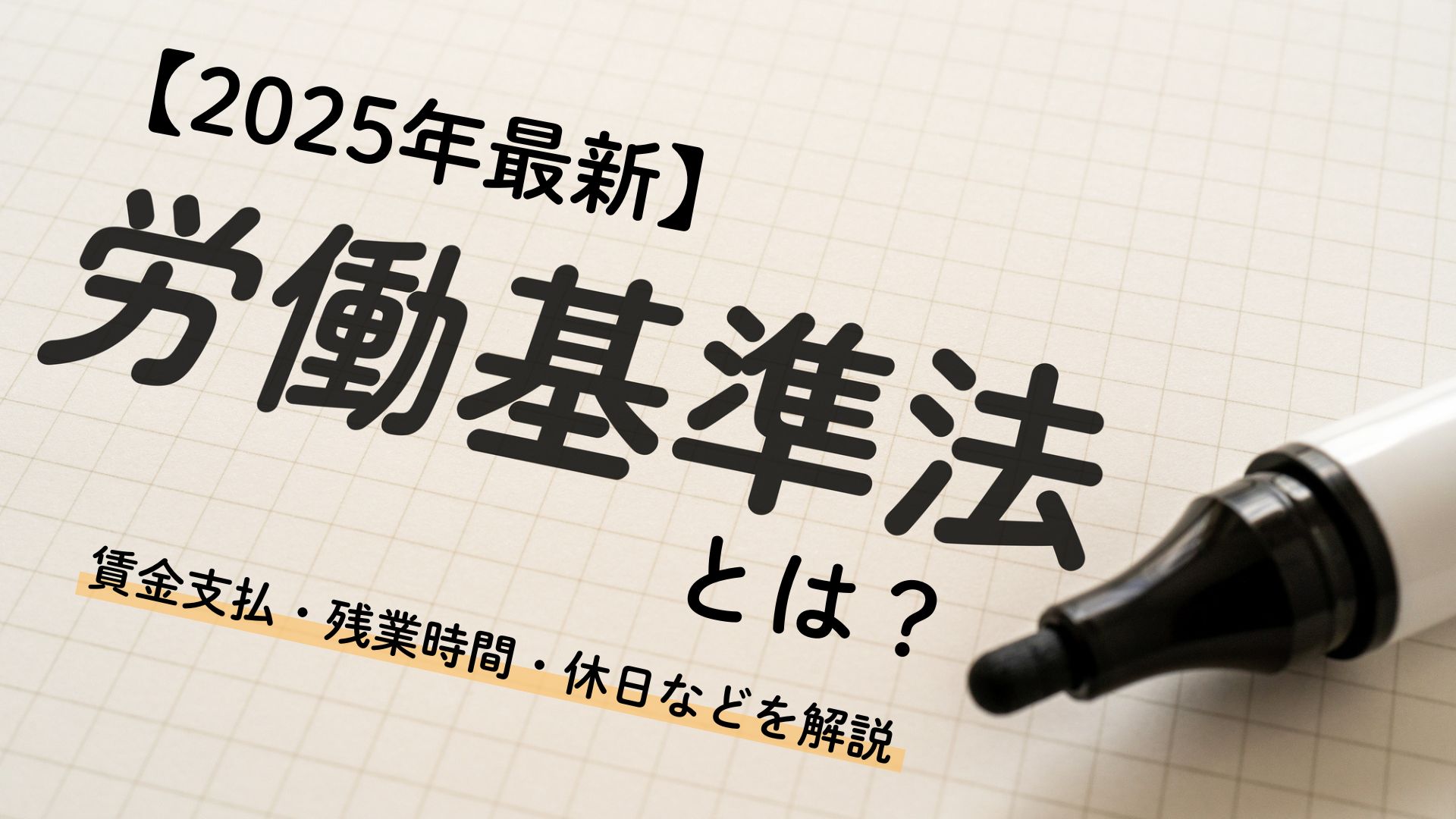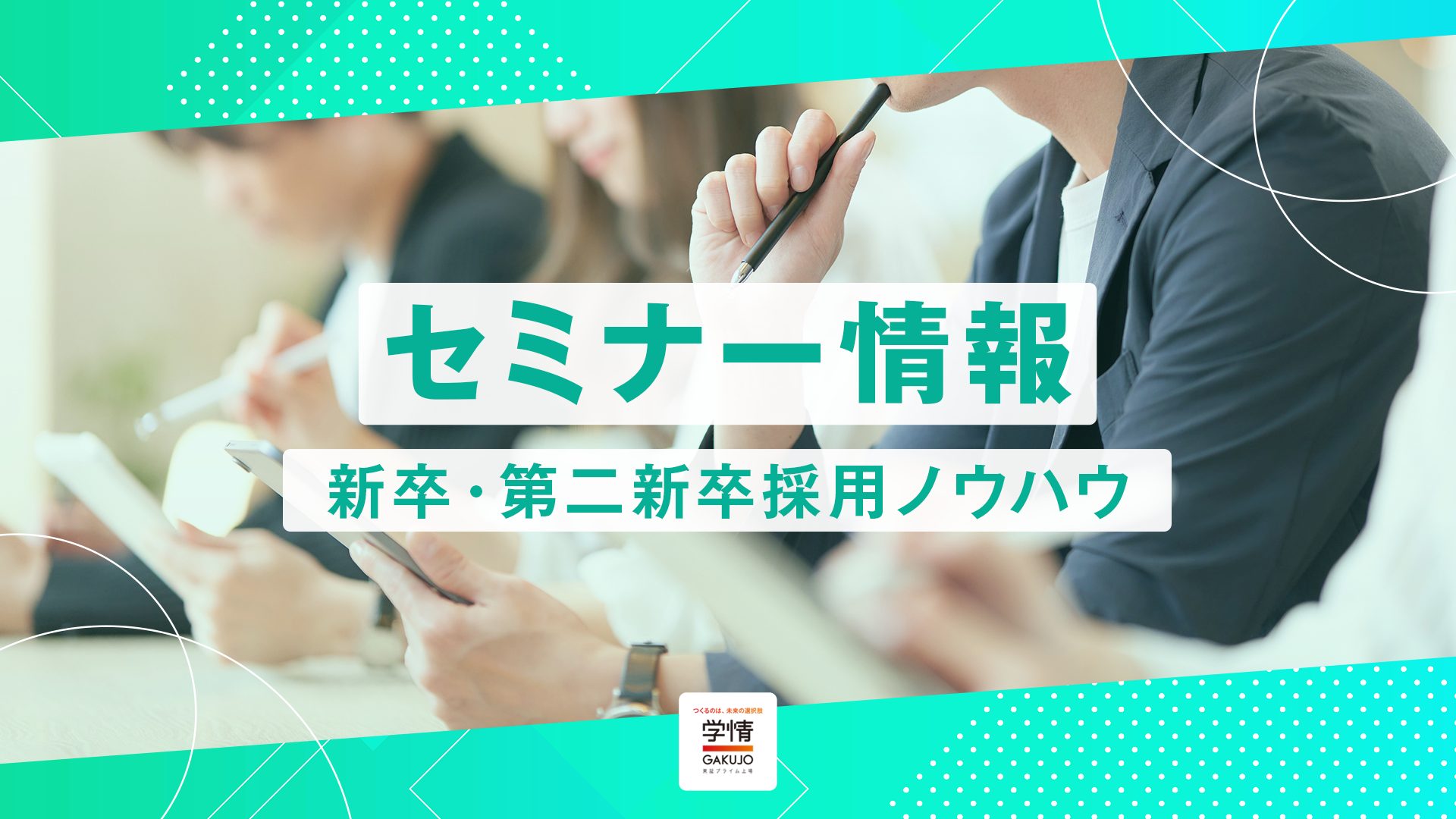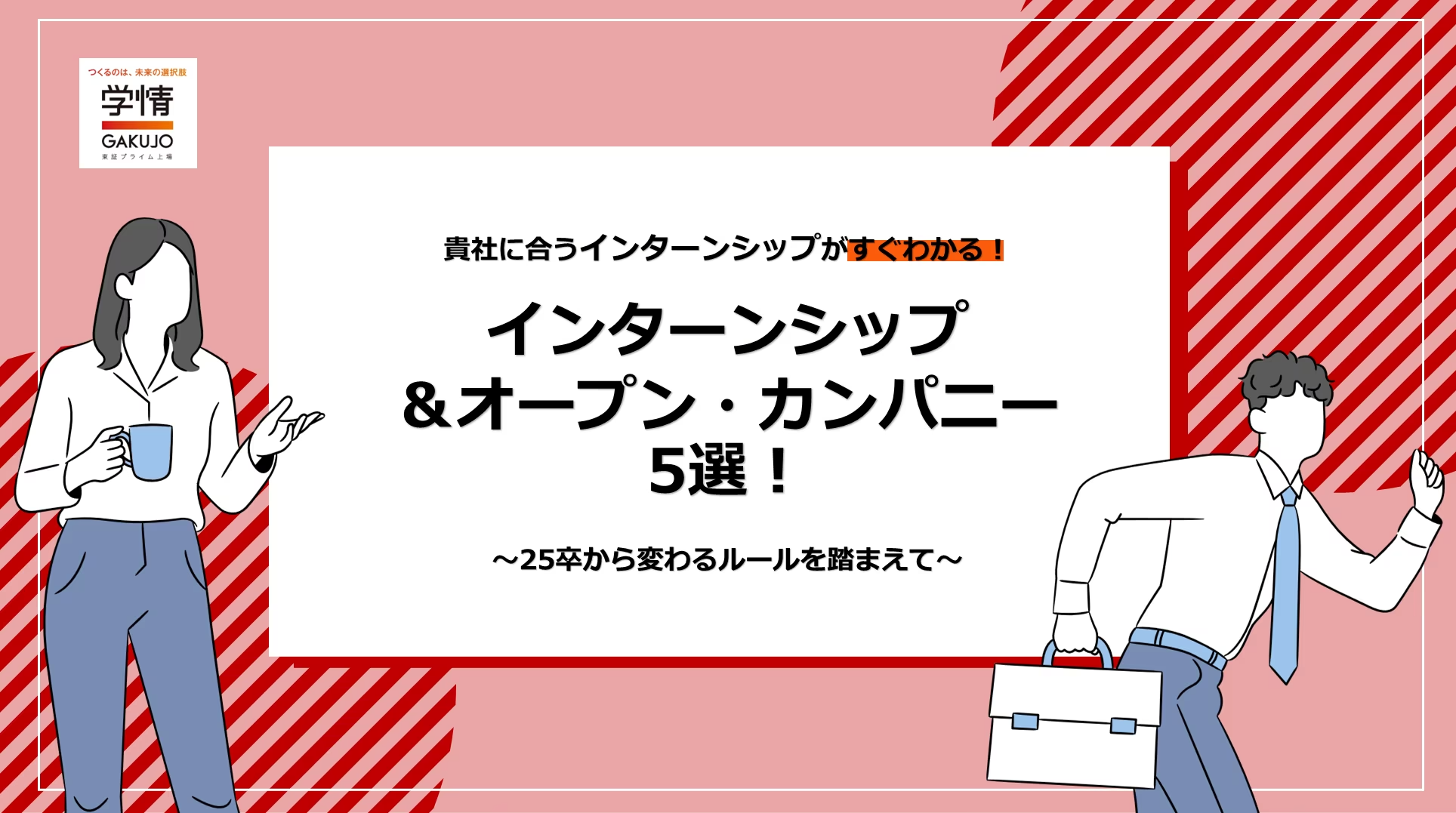Pick up article
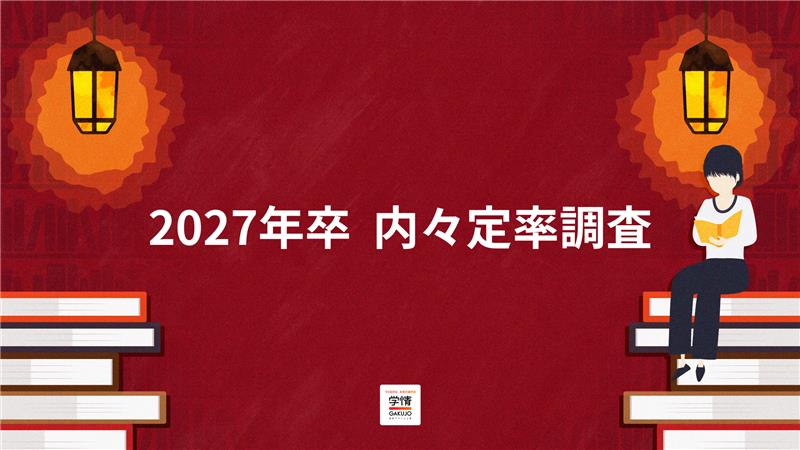
1月末時点の内々定率48.5%、5割に迫るもほぼ前年並み
Pick up article
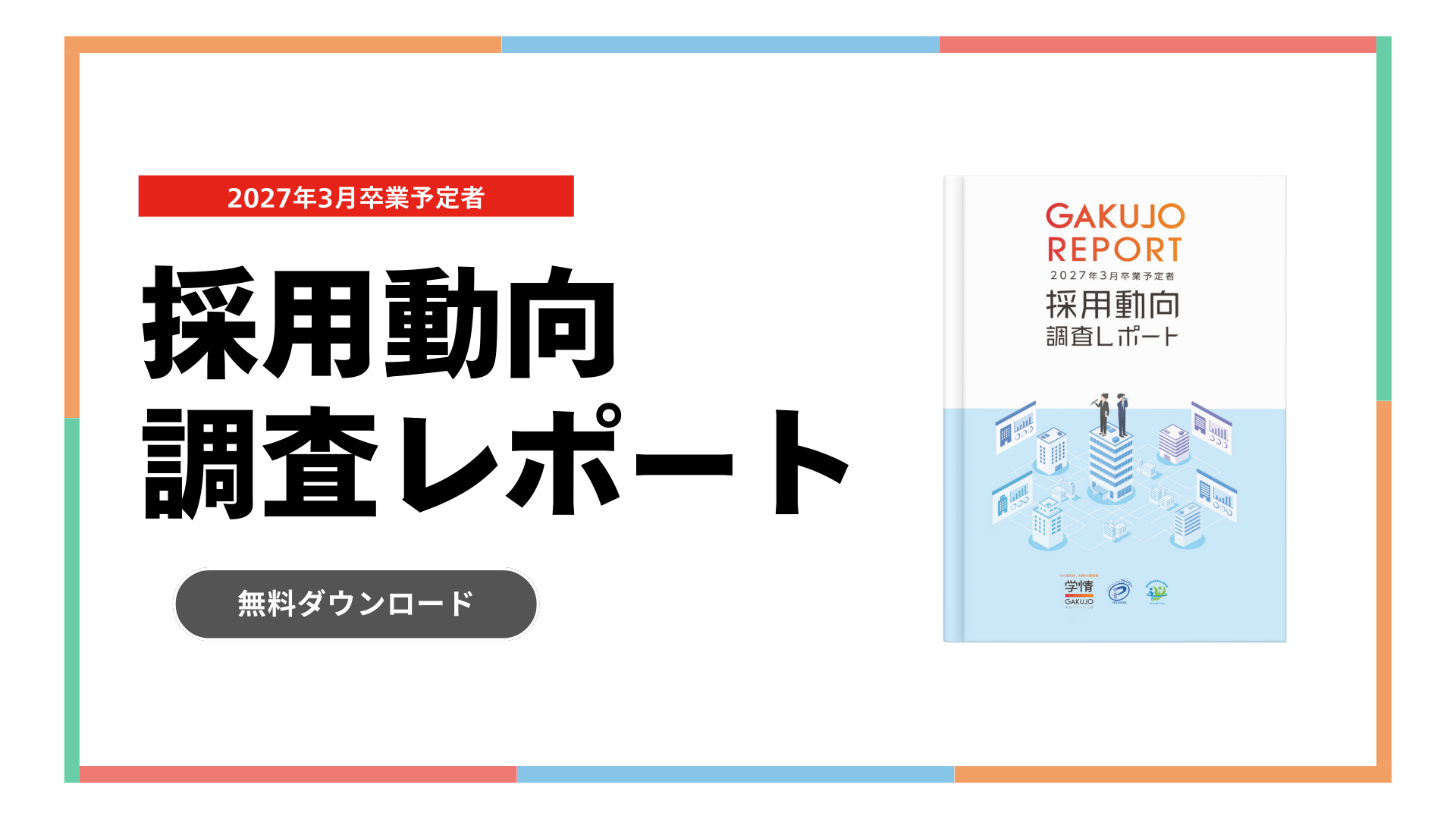
2027年3月卒業予定者/採用動向調査レポート
Pick up article
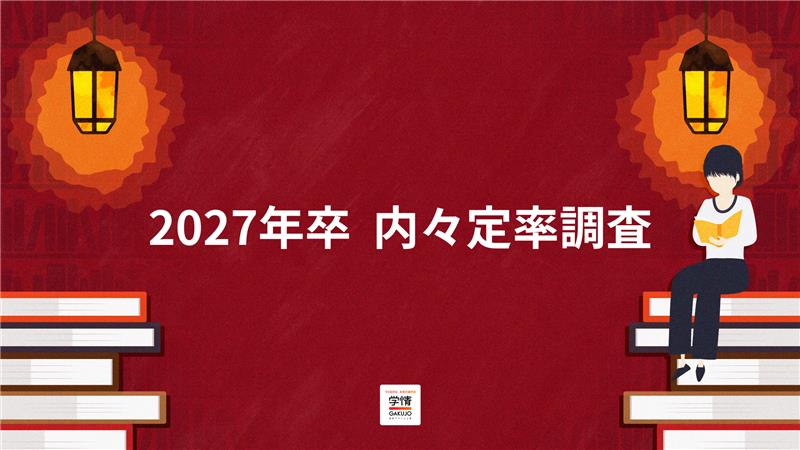
12月末の内々定率37.4%、4割に迫るも前年比微増。文系33.1%、理系は46.3…
Pick up article

【2026年2月5日開催】若手採用カンファレンス2026
異次元の新卒・中途…
Pick up article
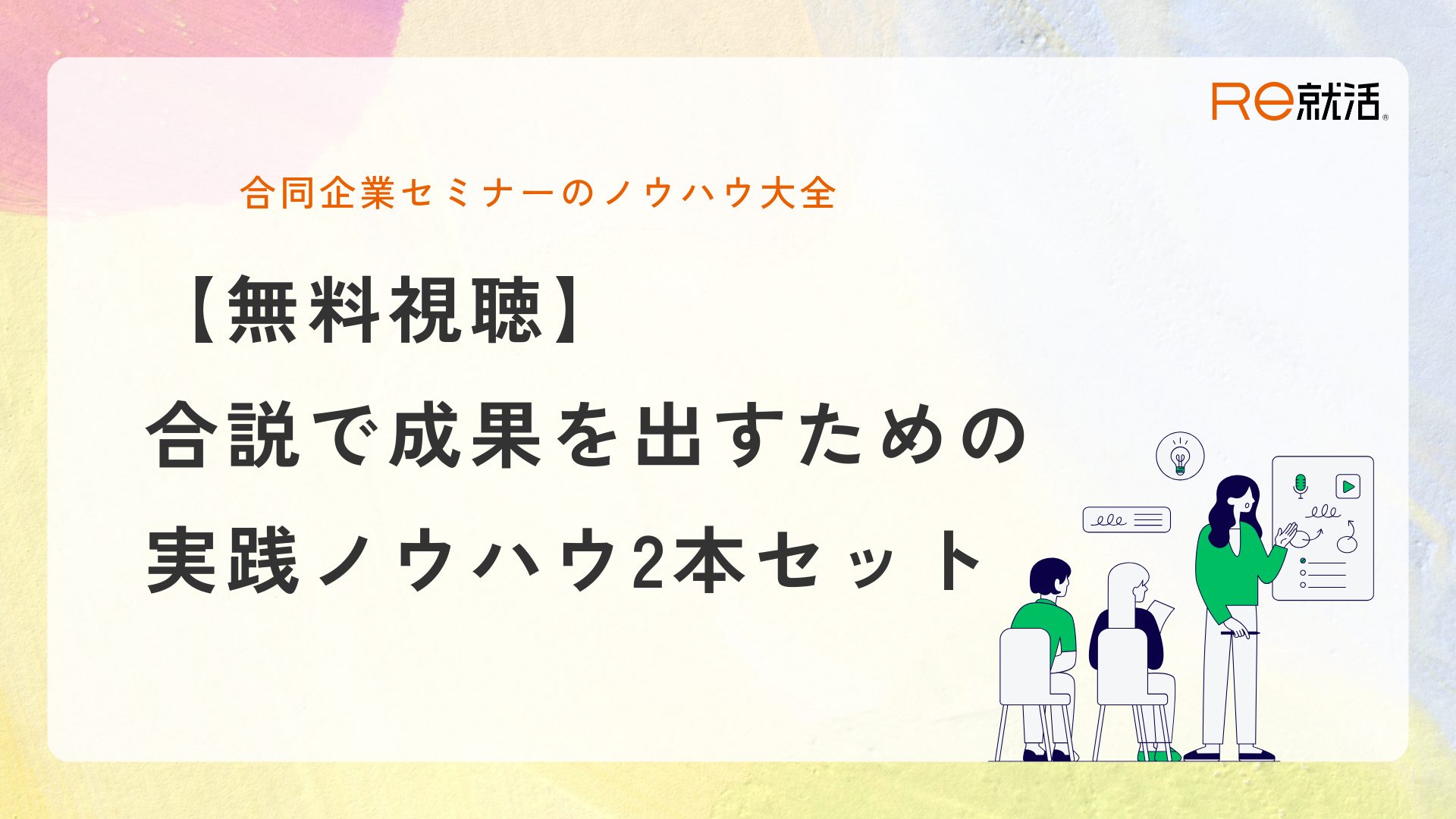
合同企業セミナーを成功させる秘訣を一挙公開!
採用成功のための動画…
Pick up article
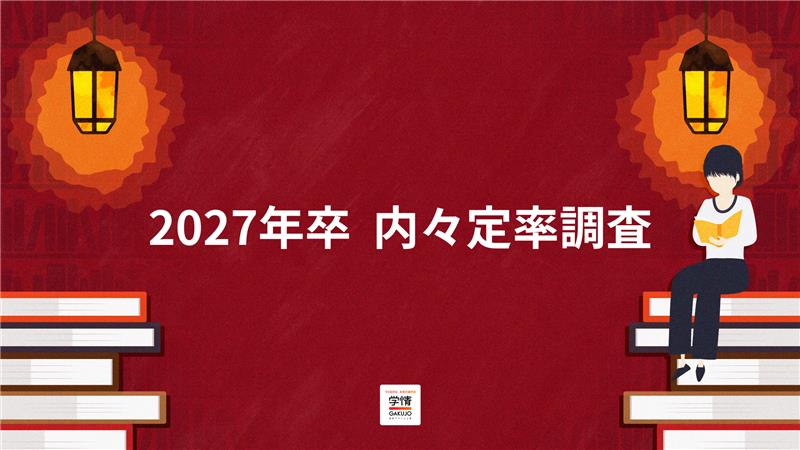
11月の内々定率29.3%、文系 24.4%、理系は 40.7%の高率で早くも4割台に…
Pick up article
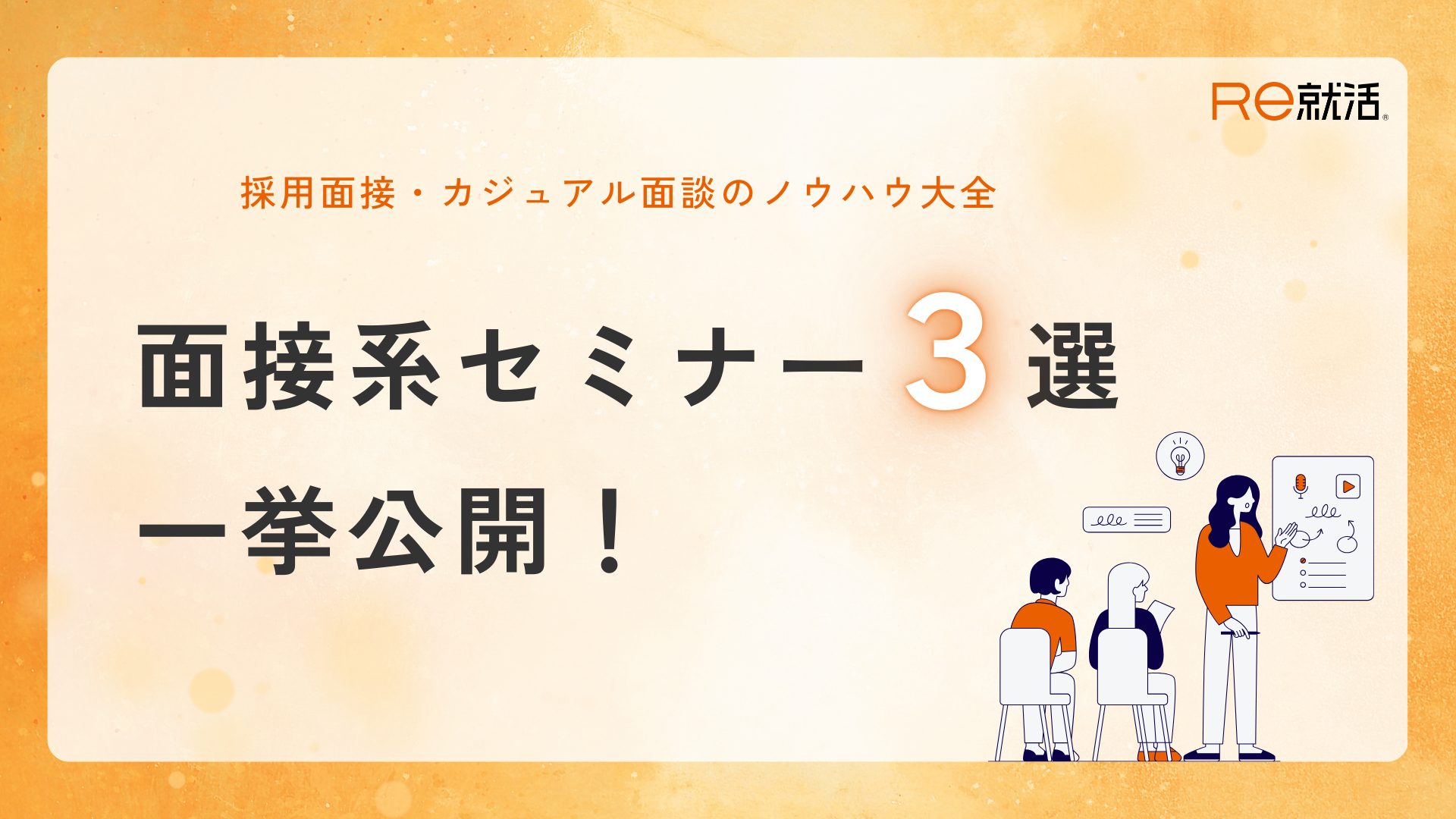
面接・カジュアル面談の極意を一挙公開!採用成功のための動画アーカイブ
Pick up article
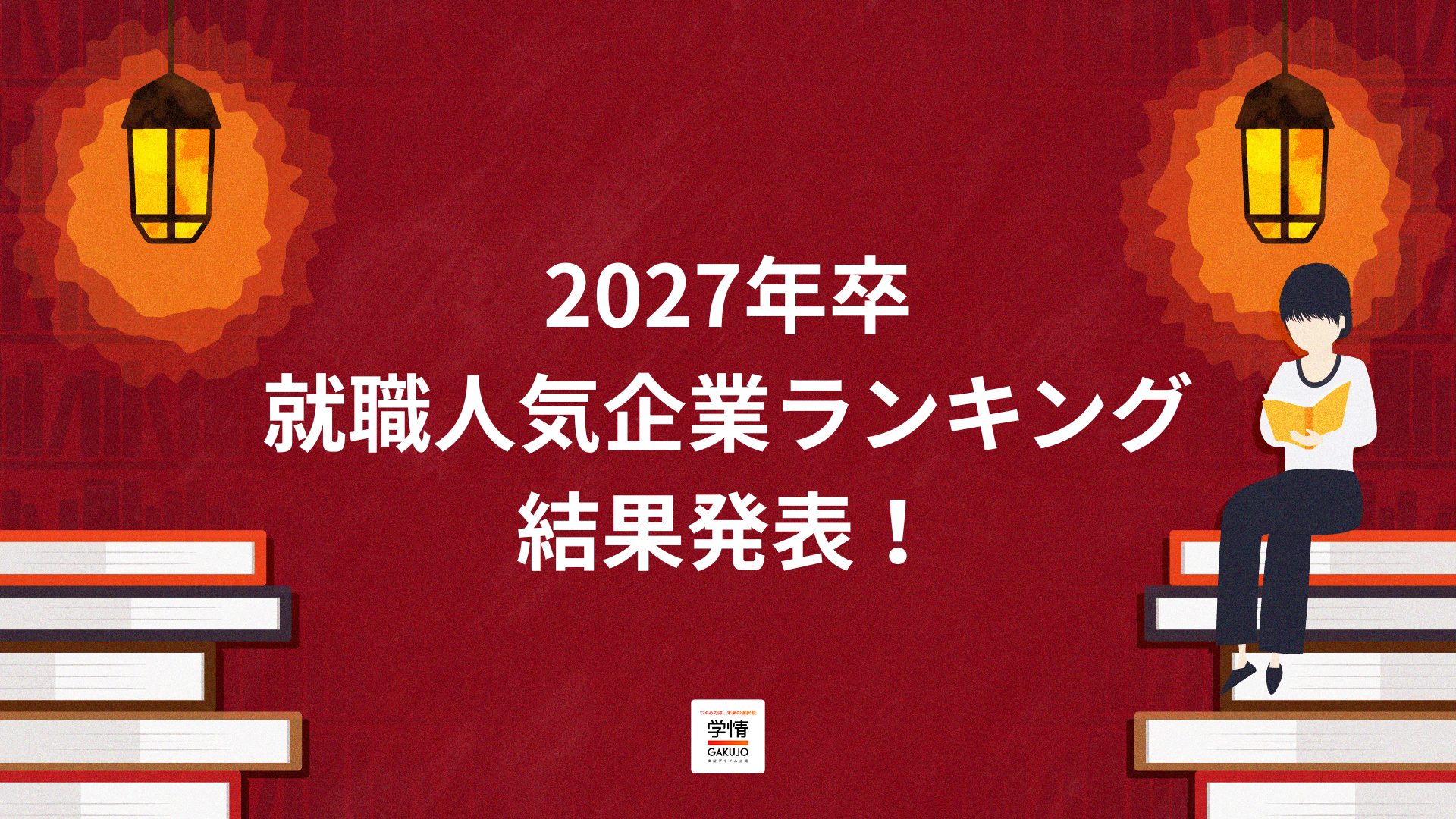
2027年卒「就職人気企業ランキング」を発表!
トップは8年連続のあの…
Pick up article

Re就活とは?特徴と強み、掲載フローや金額、活用事例を徹底解説!
Pick up article

【27卒最新】新卒採用スケジュール|学生と企業の最新動向から27卒を予測
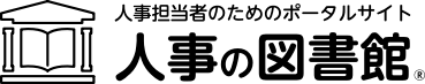
人事の図書館とは?
就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、
株式会社学情が運営するオウンドメディアです。
採用ノウハウ資料
人事業務に関する
お役立ち情報が満載!