中途採用に適した求人媒体とは?
おすすめ5選と選び方を紹介
公開日:2025.09.19
更新日:2026.01.22

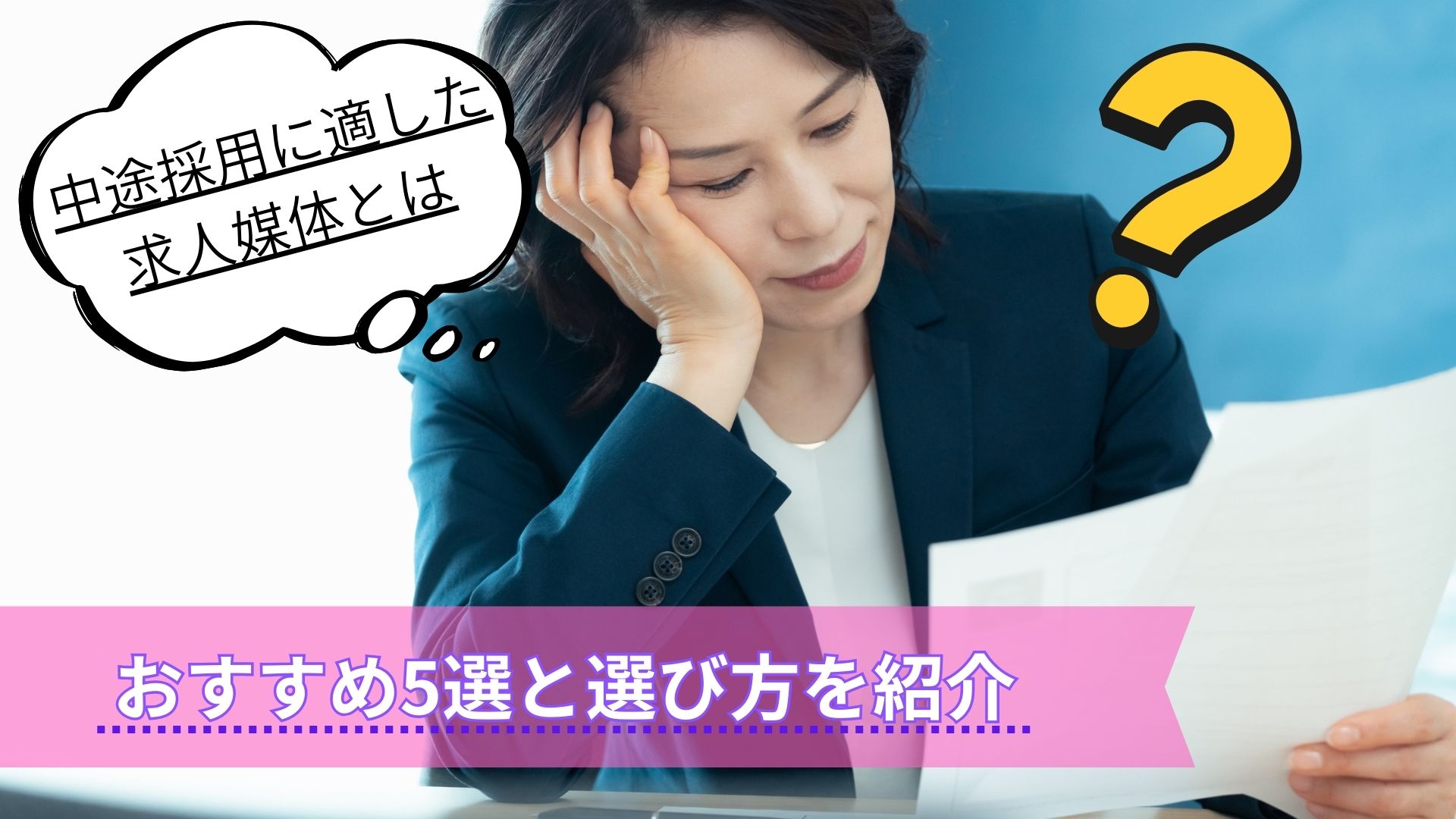
「求人を出しても応募が来ない…」「どの転職サイトを使えばいいのかわからない」と悩む企業は少なくありません。
中途採用に取り組む企業にとって、求人媒体の選定は成果を大きく左右する重要なポイントです。しかし、数ある選択肢の中から自社に合った媒体を見極めるのは簡単ではないでしょう。
そこで本記事では、代表的な中途採用向け求人媒体の比較をはじめ、それぞれの特徴や活用のコツ、選定時に押さえておくべきポイントをわかりやすく解説します。
読了後には「自社に最適な求人媒体の選び方」が明確になり、効率的かつ戦略的な採用活動をスタートしやすくなります。
「中途採用を成功させたいけれど、どこから手をつけるべきかわからない」と感じている方は、ぜひこの記事を最後までご覧ください。
代表的な中途採用向け求人媒体の比較表
まずは、代表的な中途採用向け求人媒体を一覧で紹介します。
|
媒体名 |
媒体のタイプ |
課金体系 |
特徴 |
|
掲載型+スカウト型 |
掲載課金型 |
|
|
|
リクナビNEXT |
掲載型+自動マッチング |
クリック課金型 |
|
|
エン転職 |
掲載型 |
掲載課金型 |
|
|
マイナビ転職 |
掲載型+スカウト型 |
掲載課金型 |
|
|
dodaダイレクト |
スカウト型 |
掲載+オプション課金 |
|
中途採用向け求人媒体を選ぶ際には、次のポイントを押さえておきましょう。
- 事前に採用ターゲットを明確化しておく
- 媒体のユーザー層・掲載実績を確認する
- 料金体系を確認する
- 掲載期間を確認する
- サポート体制の有無を確認する
- 過去の掲載結果や他社の活用事例を確認する
上記のポイントを知っておくことで、より効率よく採用活動を進められます。
中途採用向けのおすすめ求人媒体5選

求人媒体を選ぶ方法としてWeb上で公開されている転職サイトランキングを参考にする方法もありますが、自社により適した媒体を選ぶためには、各媒体の特徴を踏まえたうえで自社に最適なサービスを選ぶことが重要です。
ここでは、中途採用におすすめの求人媒体を5つご紹介します。おすすめの求人媒体の概要や特徴をわかりやすく記載しているので、ぜひ参考にしてみてください。
1.Re就活
20代の若手人材を採用したい企業にとって、「Re就活」は非常に有力な選択肢です。若くて意欲的な「第二新卒」や「ポテンシャル層」に特化しており、他媒体と比較してもターゲットのマッチ率が高いのが特徴です。
「Re就活」には、次のような強みがあります。
- 20代向け転職サイト7年連続No.1(2019年~2025年 東京商工リサーチ調べ)
- 転職イベントの20代動員数No.1(2020年 東京商工リサーチ調べ)
- 「Re就活エージェント」は20代登録比率No.1(2021年~2025年 東京商工リサーチ調べ)
- ダイレクトスカウトやカジュアル面談機能で、選考前の接点づくりが可能
- 専任のカスタマーサクセス担当が掲載や採用を支援
- オフラインでのイベント・セミナーでも求職者との接点づくりが可能
たとえば、従来の求人媒体では反応が得にくかったケースでも、カジュアル面談やイベントを通じて自社の魅力を伝えられる可能性があります。
20代を積極的に採用したいカルチャーフィット重視の企業にとって、「Re就活」は費用対効果の高い媒体といえるでしょう。
2.リクナビNEXT
幅広い年代や職種の中途人材をターゲットにしたい企業におすすめなのが「リクナビNEXT」です。大手ならではの高い認知度と豊富な登録者数により、多様な人材との接点を持つことができます。
多様な人材との接点を持てる理由は、掲載情報の自動連携やマッチング精度の高い機能にあります。たとえば、求人情報は連携サイトにも同時に掲載されるため、より多くの求職者の目に触れる仕組みが整っています。また、求人内容に近い条件の登録者に対して自動で情報が通知される機能もあり、マッチングの機会を逃しません。
さらに、料金体系はクリック課金型が採用されており、実際に求職者の関心が可視化された段階で課金が発生するため費用対効果を高めやすい点も特徴です。初めて利用する企業でも無料相談や運用サポートを受けられるため、採用に不慣れな企業でも安心して活用できます。
採用ターゲット層が幅広い、あるいは母集団形成を重視したい企業にとって、「リクナビNEXT」は安定感と拡張性を兼ね備えた媒体といえるでしょう。
3.エン転職
「エン転職」は、定着率の高い採用を実現したい企業に適した求人媒体です。単なる応募数ではなく採用後のミスマッチを防ぐ設計に力を入れており、継続雇用を重視する企業に支持されています。
その理由は、求人情報の質にあります。「エン転職」では、取材を通じて企業の魅力や現場のリアルな声を丁寧に伝えるスタイルを採用しており、応募者が企業理解を深めたうえで意思決定できるよう設計されているのが特徴です。また、職場の雰囲気やカルチャーを含めた詳細情報の提供が徹底されており、求職者との認識ギャップを最小限に抑えられます。
さらに、スマートフォンでの閲覧を意識した見やすく使いやすいUI設計や、若手求職者に響くプロモーションの実施も特筆すべきポイントでしょう。
「エン転職」は短期的な採用効果だけでなく、採用後の活躍や定着まで見据えた媒体を探している企業にとって有効な選択肢のひとつです。
4.マイナビ転職
全国規模で多様な人材を募りたい企業は、「マイナビ転職」の利用も検討してみましょう。「マイナビ転職」は大都市圏だけでなく地方エリアでの採用にも強く、地域ごとの採用ニーズに柔軟に対応できる点が評価されている媒体です。
エリア別・業種別の多彩な掲載枠とスカウト機能の組み合わせによって、企業側の求める人材に対して的確なアプローチが可能。また、職種・業種・企業規模を問わず、幅広い掲載実績があるため、多くの企業で活用しやすいのが特徴です。
加えて、登録者の情報に基づいたマッチング支援機能が充実しており、ミスマッチの少ない応募を促すことができます。企業からの直接アプローチも可能なため、受け身の採用だけでなく攻めの採用に活用できる点も魅力です。
エリア戦略を重視する企業や異なるポジションで複数の採用を同時に行いたい企業にとって、「マイナビ転職」は柔軟性と網羅性のバランスが取れた媒体といえるでしょう。
5.dodaダイレクト
スピード感のある採用活動を実現したい企業には、「dodaダイレクト」が非常に有効です。求職者データベースを活用し、自社から積極的にアプローチできる「ダイレクトリクルーティング型」の代表的な媒体として知られています。
「dodaダイレクト」の魅力は、採用の初動を早める仕組みが整っていることです。企業側が求人を公開するとマッチした人材にすぐにスカウトを送ることができ、早ければ1日以内に面談設定まで進むケースもあります。また、目的に応じて料金プランを選べる点も導入しやすい理由のひとつです。
さらに、専門のカスタマーサクセス担当が企業ごとに配置され、スカウト文の作成や人材検索のアドバイスなど、運用面のサポートが受けられるのも魅力。初めてダイレクトリクルーティングを行う企業でも、手厚い支援を受けながら活用できます。
スピーディーに即戦力人材と出会いたい、あるいは採用工数を短縮したいと考えている企業にとって「dodaダイレクト」は検討価値のある媒体といえるでしょう。
目的別の中途採用向けおすすめ求人媒体
採用を成功させるためには、目的に合う求人媒体を選ぶことも重要です。ここでは、目的別の中途採用向けおすすめ求人媒体を紹介します。
自社に興味を持った人とマッチングしたい
自社のカルチャーやビジョンに共感した人材を採用したい場合、選考前のコミュニケーションが取れる媒体を選ぶと効果的です。こうした接点を設けることで、企業理解と納得感のある応募を促進できます。結果的に志望動機が明確な求職者とマッチングしやすくなり、入社後の定着も期待できます。
たとえば「Re就活」は、カジュアル面談機能によって選考前にライトな対話を実施でき、価値観の擦り合わせが可能です。また「Wantedly」のようなカルチャーフィット重視型の媒体では会社のビジョンや日常の雰囲気を投稿で発信することができ、共感を得た人材からの応募が期待できます。SNSとの連携や社内風景が見えるコンテンツを活用することで、さらに理解を深めてもらうことも可能です。
「条件」だけではなく「共感」で応募してくれる人と出会いたい企業は、選考前にコミュニケーションが取れる媒体を活用するとよいでしょう。
即戦力の中途人材を採用したい
即戦力として活躍できる中堅・専門職人材を採用したい場合は、ハイクラス層や経験豊富な人材を対象とした媒体を活用することが重要です。スキルや経歴が明確な層を対象とすることで、入社後すぐに成果を上げられる人材と出会いやすくなります。
こうした媒体にはキャリア意識の高い人材が集まりやすく、履歴書や職務経歴書の内容も整理されているため、選考効率の大幅な向上も期待できるでしょう。
たとえば「ビズリーチ」や「dodaエージェント」は、管理職や専門職など経験豊富な人材を対象としており、職務内容やスキル、実績が詳細に記載されたプロフィールを確認しながらスカウトを送ることができます。さらに、エージェントのサポートによって書類選考や面談設定の負担を軽減できるため、採用担当者のリソースが限られていてもスムーズな進行が可能です。
スピーディーかつ確実に戦力となる人材を迎え入れたい企業にとって、専門性と即効性を兼ね備えた媒体の活用は有効な手段といえるでしょう。
できるだけ採用コストを抑えたい
予算に限りがある中でも人材を確保したい場合、無料もしくは低コストで利用できる求人媒体を活用することが現実的な選択肢となります。費用を抑えながらも、母集団形成につなげられる手段は複数存在します。
高度な機能を備えた有料媒体に比べるとシンプルな設計ではあるものの、使い方次第で高い効果が期待できるでしょう。
たとえば「Indeed」や「求人ボックス」のような求人検索エンジンは無料掲載やクリック課金で運用できるため、広告費を柔軟に調整できます。また、自社ホームページの求人情報と連携させれば、追加コストなしで検索結果に表示させることも可能です。さらに、ハローワークのような行政系の無料サービスも、地域や年齢層によっては有効な採用チャネルとなります。
コストを最小限に抑えながらまずは試験的に採用活動を始めたい企業の場合、これらの媒体であれば無理なく導入できるでしょう。
地方や地元で働きたい人を探したい
地域密着型の人材を確保したい場合には、地元志向の強い求職者に届く求人媒体を活用しましょう。地方在住者やU・Iターン希望者は地元企業との接点を持ちにくいため、地域に根ざした媒体を通じて、露出を高める工夫が効果的です。
たとえば「地方特化型の求人サイト」や「地域密着のフリーペーパー」「地元の新聞社が運営するWeb媒体」は、地域に住む求職者からの閲覧率が高く、情報の信頼性も評価されやすい傾向にあります。また、「ハローワーク」や「自治体の運営する就職支援サイト」は完全無料でありながら、地域に関心を持つ層と接点を持ちやすい媒体です。自社が地元で長く事業を続けてきた実績を伝えることで、応募者に安心感と親近感を持ってもらえるでしょう。
地域貢献や地元定着を重視する企業にとって、こうした媒体は単なる採用ツールにとどまらず企業ブランド強化の一手にもなります。
特定職種・業界に強い人材を採用したい
専門性の高い職種や業界における人材採用には、分野特化型の求人媒体の活用が効果的です。
特化型媒体には該当業界の知識や就業経験を持つ求職者が集まっており、採用側との情報のギャップが発生しにくくなります。そのため、一般的な媒体よりもマッチング精度が高く、効率のよい採用活動が期待できます。また、応募段階からスキルや職種理解のある人材と出会えるため、書類選考や面接の質の向上も狙えるでしょう。
たとえば、IT業界であれば「Green」、建設業界であれば「建設転職ナビ」など、各分野に特化した媒体が複数存在します。こうした媒体では、求人原稿の作成段階から業界に即した表現やキーワード選定のサポートを受けられることが多く、より専門性の高いアプローチを実現しやすくなります。
必要なスキルセットを明確に持った人材に効率よくリーチしたい企業にとって、特化型媒体は採用の質とスピードを両立できる有力な手段です。
求人媒体の活用がおすすめの企業
企業によっては、求人媒体を活用することでより採用活動を効率よく進められる可能性があります。ここでは、求人媒体の活用がおすすめの企業を紹介します。
採用ノウハウや人事体制が限られている企業
社内のリソースが限られていたり、専任の人事担当がいない企業にとって、求人媒体の活用は採用活動を効率化する強力な手段です。
多くの求人媒体では原稿作成支援や自動マッチング機能、応募者管理ツールを提供しており、採用の属人化を防ぎながら標準化されたフローで進められるよう設計されています。媒体側のサポートやツールを活用すれば、最小限の工数で採用を進めることが可能です。
たとえば、「Re就活」や「dodaダイレクト」のような媒体ではカスタマーサクセス担当がつき、原稿の方向性の提案やスカウト文の添削などを支援しています。そのため、社内に専門知識がなくても安心して採用活動を行うことができます。
採用に不慣れな中小企業や突発的な人材補充が必要な場面でも、求人媒体を上手く活用すれば限られた体制でも成果を出せる採用体制が構築可能です。
継続的に中途採用が発生する企業
中長期的に複数のポジションで人材確保を行う企業では、求人媒体の活用によって採用活動の仕組みを標準化し、効率的に運用することが可能です。
多くの媒体では年間契約や複数枠での掲載プランを用意しており、単発よりもコストパフォーマンスを高めながら継続的な採用活動を展開できます。また、同じ媒体を継続利用することで原稿やスカウト文の改善ノウハウが蓄積され、徐々に成果につながりやすくなります。
定期的な採用ニーズに対応しつつ、コストと労力を最適化したい企業にとって、媒体の継続利用は戦略的な投資といえるでしょう。
採用ブランディングを強化したい企業
企業の魅力を伝え、求職者にポジティブな印象を与えたいと考えている企業であれば、求人媒体を単なる募集手段ではなく、ブランディングの重要な発信チャネルとして活用するのもよいでしょう。
多くの求人媒体ではテキストだけでなく、写真やインタビュー、動画などを通じて企業のカルチャーや価値観を伝える機能が備わっています。そのため、採用活動を強化しながら、企業の認知度や好感度の向上に直結する情報を効果的に発信することが可能です。
採用を通じて自社の存在価値や世界観を広く伝えたい企業にとって、求人媒体はブランディングと採用を同時に進められる強力なツールとなるでしょう。
中途採用向け求人媒体を選ぶ際のポイント
採用活動を効率よく進めるためには、自社に合う求人媒体の選定が必要です。たとえば、以下のようなポイントを押さえることで適切な求人媒体を選びやすくなります。
- 事前に採用ターゲットを明確化しておく
- 媒体のユーザー層・掲載実績を確認する
- 料金体系を確認する
- 掲載期間を確認する
- サポート体制の有無を確認する
- 過去の掲載結果や他社の活用事例を確認する
ここでは、中途採用向け求人媒体を選ぶ際のポイントを解説します。
事前に採用ターゲットを明確化しておく
求人媒体を選定する際は、まず採用したい人物像を明確にすることが最も重要です。ターゲットが曖昧なままでは、どの媒体が自社に適しているのか判断できず、非効率な媒体選定になりかねません。
また、媒体ごとに年齢層や職種・志向性など、集まる求職者の属性は異なります。採用ターゲットと媒体の利用者層が合致していなければ、応募が集まったとしても成果にはつながりにくいでしょう。
たとえば「第二新卒の若手を採用したい」のか「即戦力のエンジニアを探している」のかで、選ぶべき媒体は異なります。採用前には年齢、経験年数、保有スキル、志向性といった要素をもとにペルソナ設計を行い、それに合った媒体を検討してみてください。
求人情報を誰に届けたいのかを明確にすることで、媒体選定だけでなく、原稿設計やスカウト内容の質も向上し、全体として無駄のない採用活動を実現できます。
媒体のユーザー層・掲載実績を確認する
求人媒体を選ぶ際は、その媒体にどのようなユーザーが集まっているか、どのような企業が掲載されているかを事前に確認することが重要です。想定している人材と媒体利用者の属性が合っていなければ、効果的な採用にはつながりません。
媒体によって強みとしている職種・業種・地域が大きく異なっているため、どれほど媒体の規模が大きくても、自社の採用ニーズに合致しなければ成果に直結しにくいです。また、同業他社がどのような媒体を使っているかを確認することも、自社の媒体選定の参考になります。
求職者の層と掲載企業の傾向を事前に把握することで、媒体の「見た目の規模」に惑わされることなく、自社に合ったチャネルを戦略的に選ぶことができます。
料金体系を確認する
求人媒体を選ぶ際には、その料金体系を事前に把握し、自社の予算や採用スタイルに適しているかどうかを確認することが欠かせません。費用が発生するタイミングや課金方式によって、採用活動のリスクとリターンが大きく異なるため、注意が必要です。
一般的に求人媒体では「掲載課金型」「クリック課金型」「成果報酬型」など異なる課金モデルが採用されており、それぞれにメリット・デメリットがあります。たとえば、クリック課金型は求職者の反応に応じて課金されるため、反響の見込みが立てやすいのが特徴です。また、成果報酬型は採用が決まった段階で費用が発生するため、初期費用を抑えたい場合に有効です。
自社の採用頻度や緊急性、確保したい人材の難易度を考慮したうえで、どの料金体系がもっとも合理的かを見極めることが費用対効果の高い採用活動につながります。
掲載期間を確認する
求人媒体を選定する際は、掲載期間の長さや更新頻度のルールを確認しておくことが大切です。媒体ごとに「1週間単位」「30日間固定」「更新無制限」など掲載ルールが異なっているため、自社の目的に応じて最適な媒体を選ぶようにしましょう。仮に掲載期間と採用スピードの相性が合っていないと、タイミングを逃して応募数が伸び悩むリスクなどが想定されます。
短期集中での採用を目指すのであれば、即日掲載・即日スカウトが可能な媒体や、更新によって検索上位に表示されやすくなる媒体を選ぶと効果的です。一方で、長期的に継続採用を行う場合は、期間延長や複数掲載の割引プランがある媒体を選ぶとコストを抑えながら運用できます。
採用の緊急度やポジションごとの特性に応じて掲載期間の長さと更新の自由度を見極めることで、タイミングを逃さない戦略的な媒体運用が実現します。
サポート体制の有無を確認する
求人媒体を選ぶ際は、掲載後のサポート体制がどの程度整っているかを事前に確認しておきましょう。とくに社内のリソースが限られている企業では、媒体側の支援が採用成果に直結するケースも少なくありません。
たとえば求人原稿の作成、スカウト配信、応募者対応、効果測定といった各工程において、媒体がどこまで支援してくれるかで、採用担当者の負担や成果の精度は大きく変わります。実務的な支援を受けられるかどうかは、費用対効果に直結する判断材料です。
自社の人事体制や経験値に合わせて、どこまで外部のサポートを活用するかを見極めることで、限られた時間と予算の中でも確実な採用成果が狙えます。
過去の掲載結果や他社の活用事例を確認する
求人媒体を選定する際には、その媒体が実際にどの程度の成果を上げているのか、過去の掲載結果や他社の活用事例を事前に確認しておくことが有効です。実績に裏付けられた媒体選びを行うことで、採用活動の成功確率が高まります。
事例や実績データからは、媒体の紹介資料や営業トークだけではわからない「実際の効果」や「運用時の注意点」が見えてきます。とくに同業他社や同規模企業の成功事例は、自社での再現性を見極めるうえで参考になるでしょう。
たとえば、応募数や通過率、採用単価といったKPI(重要業績評価指標)の実績データを開示している媒体であれば、他社との比較検討もしやすくなります。また、企業インタビュー記事などで実際の活用プロセスが紹介されていれば、導入後のイメージも明確になります。
媒体の選定にあたっては、スペックや料金だけでなく「誰がどう使って、どう成果を出したか」という事例情報を確認することで、より信頼性の高い判断が可能です。
求人媒体の種類と特徴

求人媒体には、さまざまな種類と特徴があります。ここでは、代表的な求人媒体の種類とそれぞれの特徴を解説します。
求人情報サイト
求人情報サイトは掲載型で自由度が高く、幅広い層にアプローチできる媒体です。初めて中途採用を行う企業から、定期的に人材を募集する企業まで、業種・職種・地域を問わず活用されています。
求人情報サイトでは企業側が原稿を主導して作成し、自社の強みや社風を自由に打ち出すことができます。さらに、複数の求人を同時に掲載できる柔軟さもあり、ポジションや雇用形態に応じた訴求が可能です。
さらに、多くの求人情報サイトでは複数の掲載プランが用意されており、掲載期間や表示位置、原稿構成の違いによって、コストと効果のバランスを調整することができます。採用期間や緊急度に合わせて、柔軟にプランを検討できる点も大きな魅力です。
幅広く母集団形成を行いたい場合や、自社ブランディングも兼ねて採用活動を行いたい企業にとって、求人情報サイトは非常に有効な媒体といえるでしょう。
求人検索エンジン
求人検索エンジンは求人情報を自動で収集・掲載することで、求職者の検索行動に幅広く対応できる媒体です。
求職者がインターネットで検索したキーワードに応じて求人が表示される仕組みとなっており、求人を能動的に探す層にリーチしやすく、条件検索に敏感なユーザーにも訴求できます。また、自社サイトや他媒体と連携しながら、コストを抑えて効率的に露出を拡大できる点も特徴です。
求人検索エンジンには無料掲載が可能な媒体も多く、クリック課金型を選べば閲覧された分だけ費用が発生するため、低リスクで運用することができます。さらに、自社ホームページと連携させれば、独自に掲載している求人情報を広く拡散することも可能です。
予算を抑えながらも露出を増やしたい企業や、検索経由での応募を重視したい企業にとって、求人検索エンジンは費用対効果の高いチャネルとなるでしょう。
人材紹介
人材紹介は、求職者とのマッチングや選考の一部を代行するサポート性の高い媒体です。「転職エージェント」とも呼ばれており、採用の難易度が高いポジションや、迅速かつ確実な採用が求められる場面でとくに効果を発揮します。
採用の難易度が高いケースで効果を発揮しやすい理由は、エージェントが事前に候補者と面談を行い、企業の要件に合致する人材を選定・推薦してくれるためです。書類選考や面談日程の調整も任せられるため、採用担当者の工数を大幅に削減できます。
また、一般的に「成果報酬型」で提供されており、採用が決定した場合にのみ費用が発生するため、初期費用が不要な点も大きな魅力です。とくに専門職やマネジメント層、ハイクラス人材の採用においては、候補者の質や動機形成まで含めて手厚い支援を受けることができます。
採用の精度とスピードを両立したい企業や、社内での採用リソースが限られている企業にとって、人材紹介は信頼性の高い選択肢となるでしょう。
業界・職種特化型求人媒体
業界・職種特化型求人媒体は、特定の分野に特化した求職者が集まる専門性の高い媒体です。対象業界の知識やスキルを持つ人材が集まっており、募集要件との適合率が高いため、ターゲットが明確な採用において効率よくマッチングを図るための手段として非常に有効です。
また、応募段階から専門性を備えた人材と出会えることで、書類選考・面接の精度が高まり、採用後の活躍にもつながりやすくなります。
多くの業界・職種特化型求人媒体では、業界事情に精通した担当者による原稿作成支援やスカウト文のアドバイスなど、領域に合わせたきめ細かいサポートが受けられるのも特徴です。求職者とのコミュニケーションも業界用語が通じやすく、スムーズな意思疎通が可能になります。
専門性を重視したポジションを効率的に採用したい企業にとって、業界・職種特化型媒体は確度の高い候補者と出会うための有効な選択肢のひとつです。
ハローワーク・行政系求人媒体
ハローワークや自治体が運営する求人媒体は、費用をかけずに地域密着型の採用活動を行いたい企業にとって有効な選択肢です。掲載は完全無料で、予算を抑えつつ採用活動を進められます。
国や自治体が運営しているため求職者の登録数が安定しており、とくに地元での就職を希望する人材や、ミドル〜シニア層の利用率が高い傾向にあります。また、職業訓練や相談支援などと連携しており、意欲の高い求職者も少なくありません。
加えて、Webサイトだけでなく窓口掲示もあるため、インターネットを利用しない層にアプローチできる点も大きな魅力でしょう。ただし、掲載フォーマットがやや定型的で表現の自由度は限られているため、原稿作成の工夫が求められます。
スカウト・ダイレクトリクルーティング媒体
スカウト・ダイレクトリクルーティング媒体は、企業側から求職者に直接アプローチできる能動的な採用手法に適した媒体です。待ちの姿勢に頼らず、欲しい人材にピンポイントで接触することができます。
具体的には企業が登録者のプロフィールを検索し、希望する条件に合った人材にスカウトメッセージを送れる仕組みとなっており、応募を待つだけでは出会えない人材にアプローチすることが可能です。とくに転職潜在層や高スキル層に対しては、こうした直接的な接触が有効になるでしょう。
また、スカウト機能を活用することで求人を閲覧していなかった層にも自社を認知してもらえるため、母集団の質と数を同時に高められます。また、職務経歴や志向性が可視化されているため、書類選考の前段階で一定のマッチングが可能です。
中堅層〜ハイクラス人材を確実に獲得したい企業や、スピード感を持って採用を進めたい企業にとって、スカウト・ダイレクトリクルーティング媒体は戦略的に活用すべき手段だといえるでしょう。
中途採用で成果を出すための求人媒体活用術
求人媒体を使った採用活動では活用のコツを知っているだけで、その効果に大きな違いが生まれます。ここでは、中途採用で成果を出すための求人媒体活用術を紹介します。
複数媒体の併用で母集団を確保する
中途採用で成果を出すには、1つの媒体に依存するのではなく、複数の求人媒体を併用して幅広い母集団を形成することが効果的です。
媒体ごとに強みとする職種や年齢層、地域が異なるため、それぞれの媒体が持つ特性を活かすことで、質と量のバランスが取れた応募を確保できます。ある媒体では反応が薄かった人材層が、別の媒体では活発に動いているということも珍しくありません。単一チャネルではリスクが偏るため、複数媒体による分散が効果の安定につながります。
たとえば、若手向け媒体とハイクラス向け媒体を併用することで、幅広い年齢層をカバーすることが可能。掲載型媒体とスカウト型媒体を組み合わせれば、受動的な流入と能動的なアプローチを同時に実現できます。応募者の属性ごとに媒体を使い分けることで、採用効率も高まるでしょう。
特定の層に偏らない採用を実現したい、または複数のポジションを同時に募集したい企業にとって、媒体の併用は成果を最大化するための基本戦略といえます。
媒体特性に合わせた原稿設計を行う
求人原稿はどの媒体に掲載しても同じというわけではなく、媒体ごとの特性に合わせて最適化することで応募率やマッチ度が大きく向上します。各媒体にはターゲットとする求職者の傾向や、反応が出やすいフォーマット、コンテンツの構成に違いがあり、媒体の強みを活かした表現や構成が成果の分かれ道になります。
たとえば、検索流入が多い媒体ではSEO(検索エンジン最適化)に強いキーワード設計が重要ですが、カルチャーフィット重視の媒体ではストーリー性やビジュアルの工夫が求められるでしょう。
また、媒体によってはテンプレートやレイアウトが決まっており、強みを伝える位置や表現のトーンにも違いがあります。そのため、すべての媒体に同じ原稿を流用するのではなく、それぞれに最適な表現へ調整することが効果的です。
媒体の特性に応じた原稿設計を行うことで伝えたい魅力を確実に届けられ、応募者の質と量の両面において、成果を高めることが可能になります。
スカウト機能・レコメンド機能を活用する
求人媒体をより効果的に活用するためには、スカウト機能やレコメンド機能を積極的に使うことが重要です。待ちの姿勢に加えて、自社からアプローチする手段を取り入れることで、応募数・マッチング精度ともに向上します。
スカウト機能やレコメンド機能では条件に合った人材に対して直接的に接点を持つことができ、応募意欲を引き出せます。とくに転職潜在層や求人情報を受け身で見ている求職者にリーチするには、自社発信のアクションが効果的です。
たとえば、スカウト機能ではプロフィール情報をもとにパーソナライズされたメッセージを送ることができ、受信者側の関心を高めやすくなります。レコメンド機能では、自社の求人に興味を示しそうな登録者に対して自動的に情報がを届けられます。
能動的に採用活動を行うことで通常では接点を持てない層にもアプローチできるため、応募者の幅を広げたい企業や採用スピードを高めたい企業は、このような機能を積極的に活用するとよいでしょう。
採用KPIを設定し定期的に見直す
中途採用で成果を上げ続けるためには、明確な採用KPIの設定と定期的な見直しが欠かせません。KPIとは「Key Performance Indicator(重要業績評価指標)」の略で、採用活動の成果を数値で可視化するためのものです。感覚的な判断ではなく、データに基づいて運用することで継続的な改善につながります。
採用活動は「掲載すれば終わり」ではなく、母集団形成から内定・入社まで複数のプロセスを経るため、それぞれの段階で成果を数値化しなければ改善すべきポイントが見えにくくなります。
たとえば、応募数・書類通過率・面接通過率・内定率・採用単価などの指標を定め、媒体ごとにデータを収集・比較することで、費用対効果の高いチャネルや改善すべき選考フローの明確化が可能です。こうした定量的な分析によって、媒体の乗り換えや原稿改善の判断が適切に行えるようになります。
データを基に採用活動をマネジメントする体制を構築すれば、属人的な判断から脱却し、組織全体で採用成果を安定的に高めていくことが可能になるでしょう。
最適な求人媒体を選定して精度の高い採用活動を実現しよう
求人媒体は、それぞれ強みとする業種・職種・年齢層が異なり、料金体系やサポート体制にも差があります。中途採用を成功させるには、ターゲットに応じた求人媒体の選定と、それぞれの特性を活かした運用が不可欠です。目的に合った媒体の選定・媒体ごとの最適な原稿設計・機能の活用・KPIによる効果測定などを的確に行うことで、より精度の高い採用活動を実現することができるでしょう。
とくに、母集団形成に課題を感じている企業や、採用ノウハウに不安のある企業は、求人媒体の機能と支援を積極的に取り入れてみてください。本記事で紹介した各媒体と選定ポイントを踏まえ、自社に最適なチャネルを選び、戦略的な採用を進めていきましょう。
「Re就活」は、経験もポテンシャルもある20代・若手人材に特化した求人媒体です。専任のカスタマーサクセス担当が急な即戦力採用から数十人規模の通年採用まで、ご採用計画に応じた最適なプランを支援します。求人媒体の選定にお悩みの際は、ぜひこの機会に「Re就活」をご検討ください

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。









