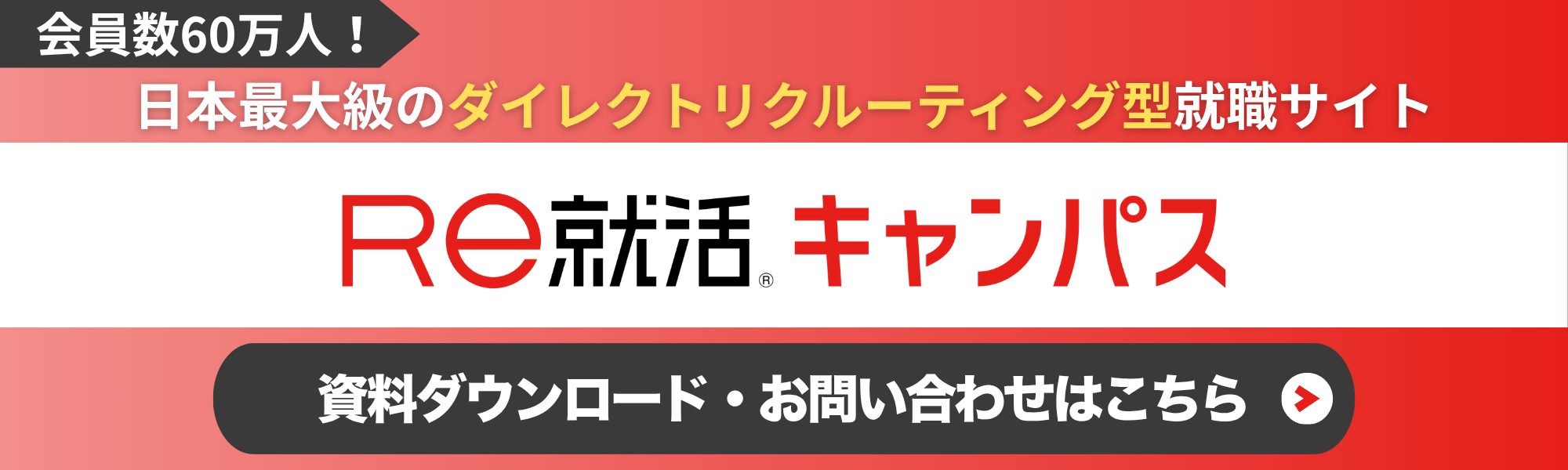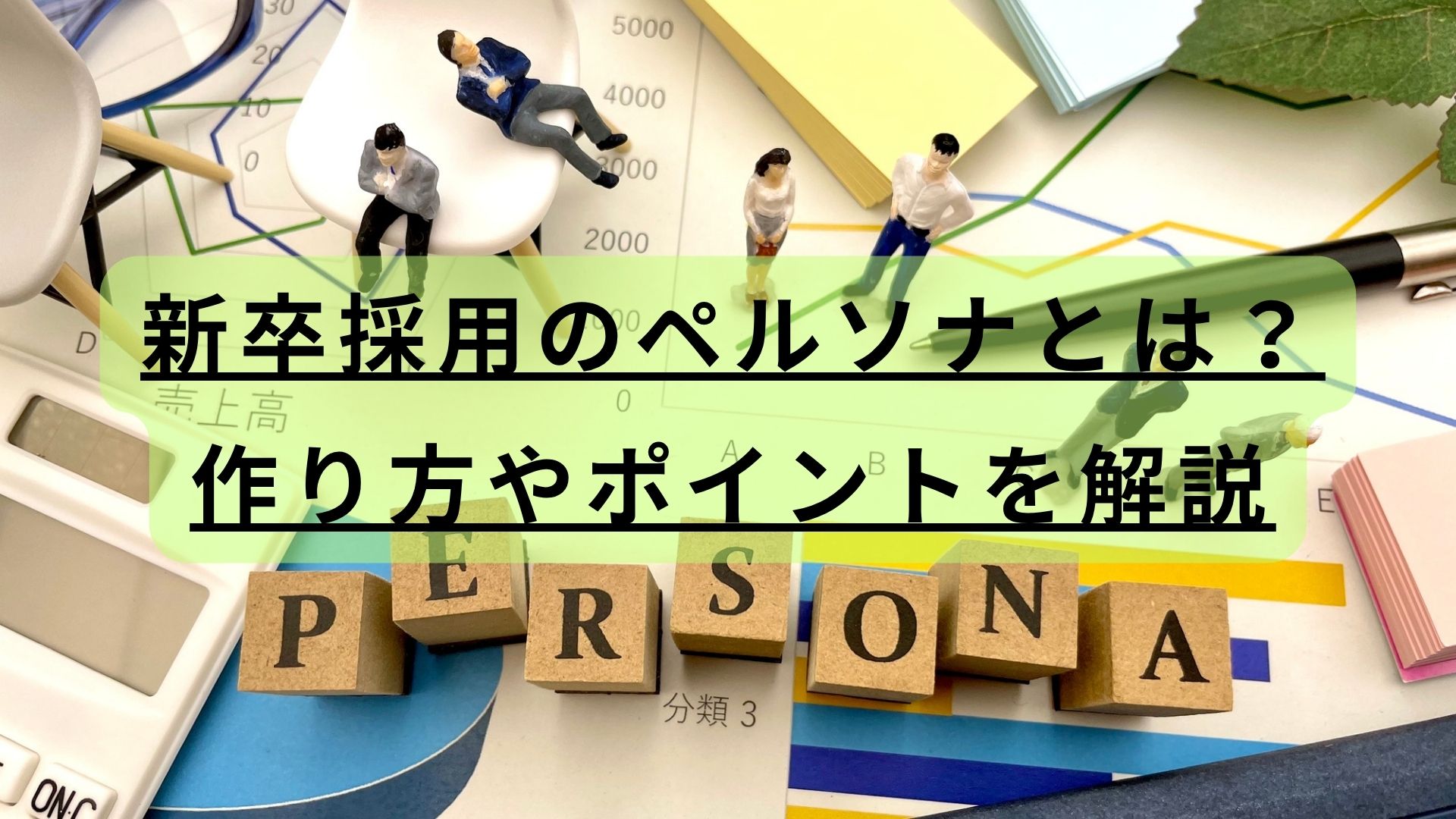新卒採用において、母集団形成ができずに悩んでいる方は多いのではないでしょうか。マッチング度の高い採用を目指すには、質の高い母集団形成が重要です。
本記事では、母集団を増やす方法や母集団形成を成功させるポイントについて解説します。母集団形成に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
新卒採用の母集団形成とは
母集団形成とは、自社の求人に興味を持っている学生を集めることを指します。ただ人数を集めるのではなく、自社の採用要件に適した人材を集め、質の高い母集団形成を行うことが重要です。
特に新卒採用においては、希望する業界や職種が定まっていない学生も多いため、企業理解を深める工夫が必要です。たとえば、合同企業セミナーやインターンシップなど、実際に働く従業員とコミュニケーションを取る機会を設けるのも良いでしょう。
質の良い母集団形成ができるかどうかが、採用活動の成否を左右します。とくに中小企業は、大手企業と比べて知名度が低く、母集団形成に苦戦するケースが多いため、課題に適した対策が必要です。
新卒採用で母集団形成が必要な3つの理由
新卒採用を成功させるには、質の高い母集団形成を行うことが必要です。ここでは、新卒採用で母集団形成が必要な理由について解説します。
人材獲得競争が激化しているため
近年、少子化による労働人口の減少が進み、人材獲得競争が激化しています。
リクルートワークス研究所の調査によると、2026年卒の大卒求人倍率は1.66倍となっており、前年より0.09ポイント低下しました。
採用難が続くなか、大手企業では買い手市場、中小企業では売り手市場といった採用格差が生じています。自社の採用要件に適した人材を採用するには、十分な母集団形成が重要です。
実際に、採用の現場からは悲鳴に近い声が上がっています。
学情のレポートによると、ある製造業では近年の母集団減少により、エントリー数がピーク時の半分ほどになってしまいました 。こうした状況を受け、同社は新卒採用計画を見直し、第二新卒採用にも本格的に着手することを決めています 。
もはや新卒採用だけに固執していては、計画通りの人員確保は困難です。母集団形成のチャネルを多様化させることが、今の採用市場を乗り切る鍵と言えるでしょう。
※参考:リクルートワークス研究所「第42回 ワークス大卒求人倍率調査(2026年卒)」
:株式会社学情「企業の動向・学生の動向【2025年1月号】」
採用のミスマッチが増加しているため
母集団形成が不十分だと、限られた候補者の中から採用しなければならず、採用のミスマッチが生じる可能性があります。
マンパワーグループ株式会社の調査によると、8割超の人事担当者が新卒採用後のミスマッチを経験しているという結果となりました。また、そのうちの6割が、新入社員の早期退職を経験しています。
企業と求職者のミスマッチは、選考辞退や内定辞退率が増加するだけでなく、採用に至っても早期退職を誘発する可能性があるので注意が必要です。
※参考:マンパワーグループ株式会社「新卒採用におけるミスマッチの状況に関する調査」
選考辞退・内定辞退による欠員を補填するため
母集団形成ができていないと、選考辞退や内定辞退が発生した際に、採用予定人数を下回ってしまいます。そのため、採用目標を達成するには十分な母集団形成が重要です。
株式会社学情の調査によると、2025年卒の内定辞退率は、前年2024年卒とほぼ同じ水準でした。売り手市場が進むことで多くの企業が内々定辞退の急増を危惧していましたが、前年並みと落ち着いています。
ただし、学生側はエントリーする企業を絞り込む傾向が強まっているため、人材獲得が難しいことには変わりありません。
母集団形成では、採用プロセスごとの人数を割り出し、採用目標を達成するのに必要な人数を予測して目標数値を決定します。
※参考:株式会社学情「2025年3月卒業予定者/就職戦線中間総括」
新卒採用における母集団形成のメリット

新卒採用における母集団形成のメリットは次の通りです。それぞれのメリットについて詳しく解説します。
- 計画立てて採用活動を進められる
- 採用要件に適した人材を採用できる
- 採用コストを削減できる
- 採用活動の効率化を図れる
計画立てて採用活動が進められる
計画立てて採用活動を進めるには、母集団形成が欠かせません。とくに新卒採用は一括採用のため、母集団形成を行うことで、採用計画が立てやすくなります。
母集団形成を行うには、採用プロセスごとに獲得人数を設定しましょう。採用プロセスごとの目標に達しない場合は、過去の実績を参考にしながら、再び採用計画を練っていきます。
母集団形成を行わないと、採用活動の見通しが立たず、採用人数が不足する可能性があるので注意が必要です。
採用要件に適した人材が採用できる
十分な母集団形成を行うことで、採用要件に適した人材が採用しやすくなります。
新卒採用は、中途採用と比べて幅広い候補から母集団を形成できます。そのため、経験や資格のフィルターがなく、学生の中身や人間性などのポテンシャルを重視した母集団形成が可能です。
企業と学生のマッチング精度を高めることで、採用率が向上するだけでなく、早期離職を防ぐ効果も期待できます。
採用コストを削減できる
十分な母集団形成ができれば、効率的に採用活動が進められ、採用コストの削減にもつながります。
反対に母集団形成ができないと、目標の採用人数を獲得できず、追加募集をしなければなりません。採用が長期化すれば、それだけ採用コストが増加してしまいます。
また、新卒採用の方が中途採用と比較して、母集団形成にかかるコストが安い傾向にあります。これは、中途採用は即戦力や実績を求めるケースが多く、新卒採用と比べて母集団を形成しにくいからです。
採用活動の効率化を図れる
募集の段階から採用要件に適した人材を絞り込むことで、選考や面談にかかる工数を削減できます。
従来の採用活動は、応募数を重視する傾向にありました。しかし、大量の応募者から採用要件に適した人材を見極めようとすると、選考プロセスが煩雑化しやすくなり、採用工数が増えてしまいます。
一方、募集段階から人材を絞り込めば、応募数は少なくなるものの、採用要件に適した学生に絞って集められるため、選考や面談を効率的に進められます。
新卒採用で母集団を形成する方法

新卒採用で母集団を形成する方法には、次のような採用手法があります。
- 求人サイト
- 人材紹介
- ダイレクトリクルーティング
- 合同企業セミナー
- リファラル採用
- ミートアップ採用
- オウンドメディアリクルーティング
- インターンシップ
- 大学のキャリアセンター
- 新卒採用のRPO(採用代行)
新卒採用で効率良く母集団を形成する際のポイントは、採用計画に応じて、最適な手法を選ぶことです。
特に近年、採用活動の早期化により、広報解禁の3月以降にプレエントリーを集めるのは年々難しくなっています。
学情のレポートでは、ある小売企業で3月以降のプレエントリーが前年比2割減になるなど、多くの企業が苦戦を強いられている実態が報告されています 。
こうした状況を受け、多くの企業は従来の求人サイトだけに頼るのではなく、合同企業セミナーへの出展を増やすなど、学生と直接会えるチャネルを多様化させる動きを強めています 。
※参考:株式会社学情「企業の動向・学生の動向【2024年4月号】」
以下で紹介する各手法の特徴を理解し、自社に合った組み合わせを検討することが重要です。
求人サイト
求人サイトに自社の求人情報を掲載し、採用要件に適した求職者を募る方法です。
求人サイトは、媒体ごとにそれぞれ特色や得意分野が異なります。掲載媒体を選ぶ際は、サイトの登録者数だけでなく、採用ターゲットに適した媒体かどうかかもチェックしましょう。
|
メリット |
デメリット |
|
・一度に多くの学生に求人情報を見てもらえる ・採用人数によっては採用単価を低くおさえられる ・写真や動画で企業の魅力をアピールできる |
・採用できなくても掲載費がかかる ・求人情報が埋もれてしまう可能性がある ・自社を知らない学生にアプローチするのが難しい |
人材紹介
人材紹介とは、人材紹介会社から採用要件に適した人材を紹介してもらう方法です。
キャリアアドバイザーは企業の採用要件を熟知しているため、学歴や資格の有無だけでなく、求職者のパーソナリティも考慮して、マッチング精度の高い人材を紹介することができます。
|
メリット |
デメリット |
|
・採用要件に適した人材を採用できる ・採用するまで費用がかからない ・学生の抽出や日程調整などの工数を削減できる |
・成功報酬額が高い ・自社に採用ノウハウが蓄積されにくい ・すぐに紹介を受けられないこともある |
ダイレクトリクルーティング
ダイレクトリクルーティングとは、スカウトメールなどを使い、企業が求職者へ直接アプローチする方法です。
従来の新卒採用は、求人サイトや人材紹介などを使い、求職者からの応募を「待つ」採用が主流でした。近年、待つだけでは十分な応募を集めるのが難しくなり、採用要件に適した求職者に直接アプローチできる「攻め」の採用に注目が集まっています。
|
メリット |
デメリット |
|
・潜在層にも直接アプローチできる ・マッチング精度の高い出会いが期待できる ・社内に採用ノウハウを蓄積できる |
・スカウトメールの作成など、業務負担が増える ・効率的に運用するためのノウハウが必要 ・大量採用には向いていない |
新卒採用でダイレクトリクルーティングを活用するなら、株式会社学情が運営する「Re就活キャンパス」がおすすめです。企業からのスカウトと学生からの逆オファーで、効率的な母集団形成が期待できます。
合同企業セミナー
合同企業セミナーとは、企業が求職者に対して、会社説明や面談を行うイベントのことです。
合同企業セミナーには、幅広い企業や学生層を対象とした「総合型」と、業界や学部などに特化した「特化型」のイベントがあります。また、開催規模は大規模と中小規模に分かれ、大規模なイベントでは数千人から数万人の学生が来場します。
|
メリット |
デメリット |
|
・選考の短期化や志望度の向上が期待できる ・一度に多くの学生と出会える ・企業の魅力や強みを直接アピールできる |
・イベントに参加する人員が必要 ・知名度の高い企業に学生が集まりやすい ・準備や当日のブース運営に工数がかかる |
株式会社学情では合同企業セミナー「就職博」を開催しています。「就職博」は、リアルイベントだけでなく、オンラインイベントも開催しているため、幅広い学生へのアプローチが可能です。
リファラル採用
リファラル採用とは、内定者や新入社員に大学の友人や後輩を紹介してもらう方法です。必須ではありませんが、採用に至った際は紹介してくれた方へインセンティブを支払う場合があります。
採用インセンティブの相場は1万円〜30万円ほどなので、採用コストを抑えながら採用要件に適した人材の採用が目指せます。
ただし、インセンティブの支払い方法や金額によっては、職業安定法の第40条に反し、違法となる可能性があります。インセンティブを支払う際は「賃金や給料という形で支払う」「支払額が高額になり過ぎない」などの点に注意しましょう。
|
メリット |
デメリット |
|
・マッチング精度の高い採用が期待できる ・採用コストをおさえられる ・早期離職を防止しやすい |
・同じタイプの人材に偏りがち ・すぐに紹介を受けられないこともある ・不採用の場合に紹介者と応募者の関係が悪くなる可能性がある |
ミートアップ採用
ミートアップ採用とは、勉強会や座談会などのイベントを通じて学生と接点を持ち、採用につなげる採用手法のことです。実際に働いている社員と交流することで、詳しい仕事内容や入社後のキャリアプランをイメージしやすくなります。
また、仕事内容や企業文化を理解して選考に進むため、マッチング精度の高い採用が期待できます。
|
メリット |
デメリット |
|
・相互理解を深められる ・自社への志望度や理解度を高められる ・自社の魅力や強みを直接アピールできる |
・イベントに参加する人員が必要 ・準備や当日のイベント運営に工数がかかる ・効果を得るには中長期的な運用が必要 |
オウンドメディアリクルーティング
オウンドメディアリクルーティングとは、採用ホームページやブログ、SNSなど、自社が所有するメディアを使った採用活動のことです。
求人情報を発信して学生からの応募を募るだけでなく、企業の魅力や強み、文化などの情報を発信することで、企業知名度や採用ブランディングを高める効果もあります。
|
メリット |
デメリット |
|
・マッチング精度の高い採用が期待できる ・企業の知名度向上につながる ・競合他社と差別化しやすい |
・専門知識やノウハウが必要 ・魅力的なコンテンツを発信し続けなければならない ・初期コストやランニングコストがかかる |
インターンシップ
インターンシップとは、学生に向けて企業が実施する就業体験プログラムのことです。実際の業務を体験することで、企業や仕事内容に対する理解が深まり、学生の志望度向上につながります。
また、企業文化や仕事内容を理解したうえで選考に進むため、マッチング精度の高い採用が期待できます。
ただし、インターンシップを実施するには、一定の基準を満たさなければなりません。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
|
メリット |
デメリット |
|
・仕事内容や企業文化の理解が深まる ・優秀な人材を早期発見・獲得できる ・入社後のギャップを軽減できる |
・準備や実施に工数がかかる ・指導担当者を用意しなければならない ・社内調整が必要 |
大学のキャリアセンター
大学のキャリアセンターとは、在学生や卒業生の就職や進路選択などを支援する部署のことで、就職課や就職センターなどとも呼ばれます。企業からの求人情報を学生に提供しています。
まずは大学訪問を行い、求人情報の設置を依頼します。社内にOB・OGがいる大学だと、コンタクトを取りやすいでしょう。
定期的に連絡を取りながらコネクションを作ることで、学生の紹介や学内の合同企業セミナーの案内などを受けやすくなります。
|
メリット |
デメリット |
|
・採用ターゲットに効率的にアプローチできる ・採用コストを削減できる ・優秀な人材と早期に接触できる |
・多様な人材を採用するのに向いていない ・人気の大学は人材の獲得競争が激しい ・短期的な採用には向いていない |
新卒採用のRPO(採用代行)
RPO(採用代行)は、企業の採用活動をサポートする採用代行サービスです。企業は、採用のプロフェッショナルによる戦略に基づいた広範な母集団形成から応募者管理、選考調整といった採用業務を外部に委託できます。
これにより、人的リソースが限られた企業でも、担当者の負担を軽減しつつ、効果的な母集団形成が可能です。
|
メリット |
デメリット |
|
・採用担当者の業務負担を軽減できる ・採用業務の効率化を図れる ・母集団形成のための適切な動きが取れる |
・自社に採用ノウハウが蓄積されない ・企業の魅力が学生に伝わりにくい ・担当者が自社のことを十分に理解していないと、ミスマッチが生じる可能性がある |
新卒採用で母集団形成を成功させる6つのポイント
最後に、新卒採用で母集団形成を成功させるポイントについて解説します。
これらのポイントを実践する上で、現在の採用市場における2つの重要な変化を理解しておく必要があります。それは「採用活動のさらなる早期化」と「学生の活動の二極化」です。
学情のレポートによれば、ある中堅IT企業では、前年と同じ採用手法を続けた結果、プレエントリー数が2割も減少しました 。これは、早期から積極的に動く学生と、年明け以降に動き出す学生との二極化が進んでいるためです 。
漫然と待っているだけでは、意欲の高い学生との接点を持ち逃してしまいます。だからこそ、採用要件を早期に固め、適切な手法で、積極的に学生と会いに行くという基本動作が、これまで以上に重要になっているのです。
※参考:株式会社学情「企業の動向・学生の動向【2025年2月号】」
新卒採用で母集団形成を成功させるには、次の6つのポイントをおさえましょう。
- 採用計画を策定する
- 採用要件を明確にする
- 自社に適した採用手法を選ぶ
- スカウトメールを工夫する
- 学生と積極的に会う
- 母集団形成を検証する
採用計画を策定する
採用計画とは、自社の事業内容や経営方針に沿って、採用活動の目的や目標を定めた計画のことです。
計画を立てずに母集団形成を行うと、無駄なコストや工数の増加などを招く可能性があります。効率的な母集団形成を行うには、ターゲットや採用人数を明確に設定し、計画に沿って最善の手法を選ぶことが重要です。
また、採用計画を策定することで、コストを抑えつつ、マッチング精度の高い採用が期待できます。
採用要件を明確にする
質の高い母集団を形成するには、採用要件を明確にすることが大切です。
採用要件を設定する際は、採用ペルソナを設定しましょう。学歴や資格の有無だけでなく、仕事に対する価値感や何にモチベーションを感じるかなど、求職者のパーソナリティに関する項目を入れることで、求職者の人柄と社風のマッチングが確認できます。
採用ペルソナを、人事担当者だけでなく、配属先や選考に関わる社員とも共有することで、共通認識を持って効率良く選考を進められます。
自社に適した採用手法を選ぶ
効率良く母集団形成を行うには、自社に適した採用手法を選ぶことが重要です。
たとえば、大手求人サイトは登録者数が多いですが、求人掲載数も多いので情報が埋もれてしまう可能性があります。とくに知名度の低い中小企業は、企業側からの積極的なアプローチが必要です。
ダイレクトリクルーティングを併用することで、企業知名度が低くてても母集団形成がしやすくなります。
スカウトメールを工夫する
ダイレクトリクルーティングを使って母集団形成を行う際は、スカウトメールの内容を工夫しましょう。
定型文のスカウトメールは、学生の目に止まりにくく、読み飛ばされる可能性があります。学生の興味を引くには、「あなたに会いたい」という熱意を伝えることが大切です。
「学生のどこに興味を持ったのか」「どんな活躍を期待しているのか」など、特別感のある内容にすると、興味を引きやすくなります。
学生と積極的に会う
学生と直接会ってコミュニケーションを取ることで、相互理解が深まりやすくなります。
企業側からの一方的な情報発信だけでは、求職者の疑問や要望に対応できないかもしれません。直接会って対話することで、学生の知りたい情報を的確に提供できます。
株式会社学情が主催する「就職博」は、年間延べ20万人以上の学生が来場している合同セミナーです。多くの学生が参加するため、短時間で効率的な母集団形成ができます。
母集団形成を検証する
母集団形成を検証する方法は次の通りです。
- 母集団形成の目的と目標を明確にする
- 採用ターゲットの分析
- 現状の課題の把握、分析
- 競合他社の分析
- 採用手法の分析と選定
- 施策の実行と効果測定
- 改善策の検討と実行
最善だと思っていた手法でも、結果が出ないことは珍しくありません。質の高い母集団形成を目指すには、PDCAサイクルを回し、自社に適した手法を見つけ出すことが大切です。
また、これを繰り返すことで、自社に採用ノウハウが蓄積されます。
母集団形成の事例
母集団形成の成功事例を参考に、自社に適した対策を検討してみましょう。
株式会社岐阜造園
|
課題・ニーズ |
・説明会参加率など、母集団の質の強化 ・サポート体制の充実 |
|
活用したサービス |
・Re就活キャンパス ・JobTube |
|
効果 |
施工管理職をはじめ、4人の内定者を確保 |
株式会社岐阜造園は、庭園の設計・施工・メンテナンスなどを手がける建設会社です。
質の高い母集団形成を目指し「Re就活キャンパス」を導入。株式会社学情のスタッフがサポートしながら運営し、その結果、会社説明会への参加率は50%以上と劇的に改善しました。さらに企業理解の深い学生からの応募が増え、ミスマッチの減少にも成功。
株式会社大垣書店
|
課題・ニーズ |
母集団の質に課題、イベントでの情報発信を重視 |
|
活用したサービス |
・Re就活キャンパス ・就職博 ・就活サポートmeeting |
|
効果 |
毎年5~10人の採用に成功 |
株式会社大垣書店は、書店運営をはじめ、出版事業や飲食事業を手がける会社です。
母集団の質を改善するため、学生とのコミュニケーションを重視した採用活動を実施。「就職博」や「就活サポートmeeting」では、学生と中身の濃い面談を行うことで、会社や仕事への理解度、志望度が高まった学生の獲得に成功しました。それから毎年母集団の質が高まっていると実感されています。
新卒採用の母集団形成には求職者に直接アプローチできる
「Re就活キャンパス」がおすすめ
近年、少子化による労働人口の減少が進み、人材獲得競争が激化しています。今後も新卒採用は厳しい状況が続くと予想され、従来の採用手法だけでは十分な母集団形成ができないかもしれません。
応募数を獲得しにくいからこそ、数だけでなく質を重視した母集団形成が必要です。新卒採用サイト「Re就活キャンパス」では、独自の検索システムで、自社の採用要件に適した求職者を絞り込み、効率的にアプローチできます。
新卒採用の母集団形成に悩まれている方は、株式会社学情にお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。