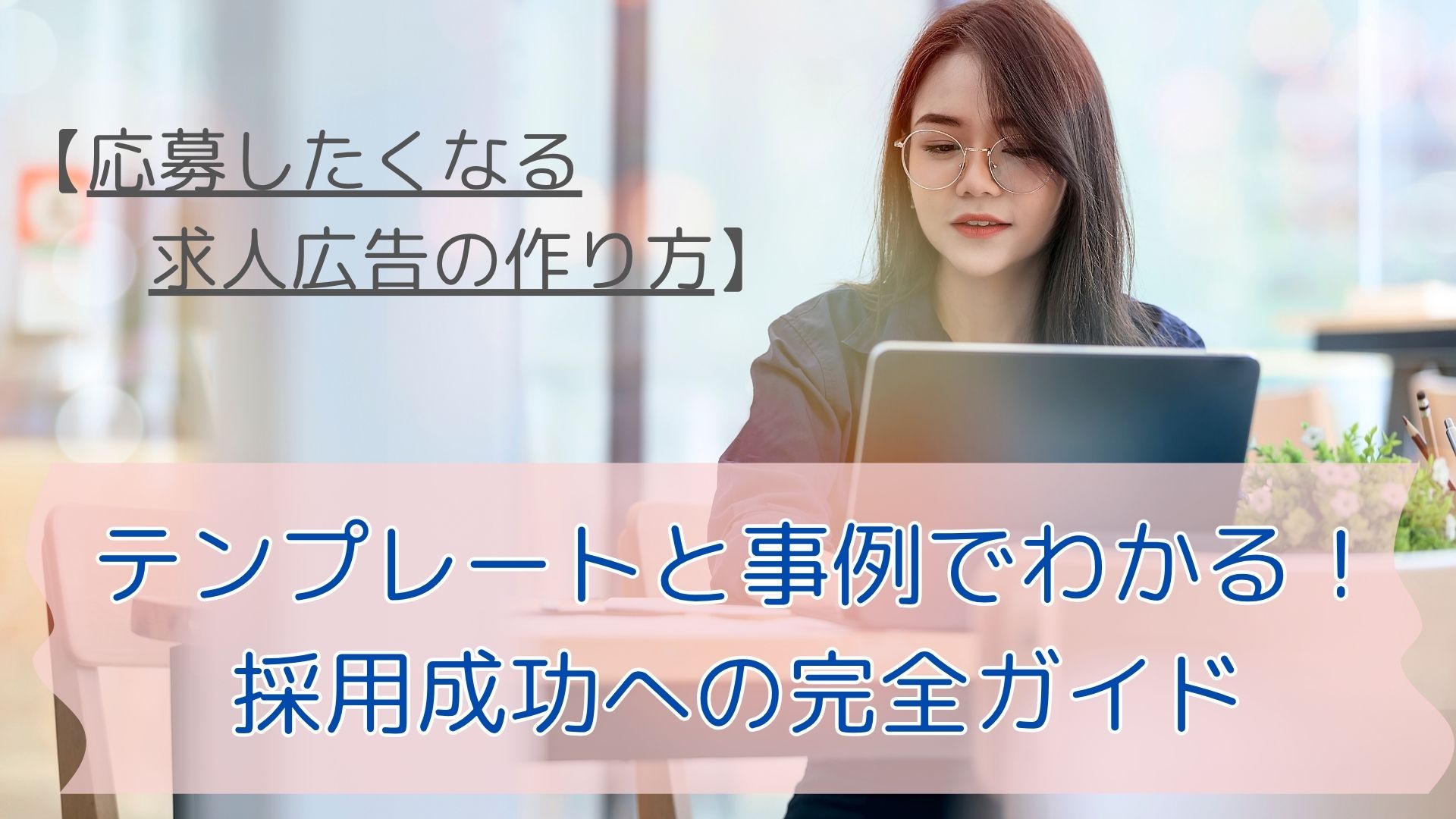ポテンシャル採用は、慢性的な人手不足や採用難を打開する手段として注目を集めている採用方法です。第二新卒や既卒を対象に、ポテンシャル採用を導入する企業が増えています。
本記事では、ポテンシャル採用が注目される理由やメリット・デメリットなどについて詳しく解説します。
ポテンシャル採用とは?
ポテンシャル採用とは、求職者の潜在能力を評価基準とする採用方法のことです。第二新卒や既卒など、社会人経験の浅い求職者を採用ターゲットにすることが多く、求職者の人柄や将来性、企業文化に適しているかなどを評価します。
ポテンシャル採用は何歳まで?
ポテンシャル採用に年齢制限はありませんが、一般的には20〜30代の求職者を想定していることが多い傾向にあります。
ポテンシャル採用の対象となる既卒や第二新卒、ヤングキャリアの定義は次の通りです。
|
社会人経験 |
年齢(大卒の場合) |
|
|
ヤングキャリア |
3年以上 |
26〜29歳 |
|
第二新卒 |
3年未満 |
25歳以下 |
|
既卒 |
なし |
− |
ポテンシャル採用と中途採用の違い
社会人経験を持つ人材を採用する場合は、求職者のスキルや年齢に関係なく中途採用に分類されます。ポテンシャル採用は、その中途採用のなかで求職者の潜在能力を評価基準にしているものを指します。
中途採用は一般的に即戦力となる高いスキルや経験が求められるため、スキル重視の採用を「即戦力採用」や「キャリア採用」と呼び、ポテンシャル採用と差別化していることが多いです。
ポテンシャル採用が注目される理由

従来の中途採用では、高いスキルや経験を持つ即戦力採用が主流でした。しかし、近年はポテンシャル採用に注目が集まっています。
多くの企業がポテンシャル採用に着手している理由について解説していきましょう。
売り手市場が続いている
近年は、売り手市場が続いており、人材獲得競争が激化しています。令和6年10月分の有効求人倍率は1.25倍、新規有効求人倍率は2.24倍と依然高い水準です。
中途採用市場では、即戦力採用が難しくなっています。そのため、将来の幹部候補となり得る人材を採用し、社内で育成する方向にシフトする企業が増加しているのです。
※参考:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年10月分)について」
新卒採用だけでは若手採用を充足できない
株式会社学情の調査によると、20代を対象にしたキャリア採用を実施している理由で最も多かったのは「新卒採用だけでは、若手採用を充足できないから」でした。
人材獲得競争は、新卒採用市場においても激しく、十分な採用人数を確保するのが困難な状況です。そのため、戦略的な採用として、20代採用を実施している企業が増加しています。
※参考:株式会社学情「「20代を対象としたキャリア採用に期待すること」に関する企業調査」
少子化が続いている
総務省統計局の人口推計によると、2023年の15歳未満人口は前年に比べ32万9000人減少し、総人口に占める割合は11.4%と過去最低を記録しました。
少子化の傾向は今後も続くと予想されており、ますます若手層の採用が難しくなっていくでしょう。
また、社内の高齢化が進んでいる企業では、ポテンシャル採用を行い、組織の若返りを図っている動きがみられます。
※参考:総務省統計局「人口推計(2023年(令和5年)10月1日現在)」
多様な人材を求める傾向が強まっている
転職市場では、新卒採用や即戦力採用などの枠組みを超え、多様な人材を求める傾向が強まっています。
従来の採用手法では、第二新卒や既卒、海外留学経験者などは、新卒採用や即戦力採用に分類されず、採用ターゲットにならないことが多くありました。しかし、社会人経験が浅くとも潜在能力の高い人材は多くいます。
最近は、属性だけで判断せず、求職者のポテンシャルを評価する動きが活発になっています。
ポテンシャル採用のメリット
ポテンシャル採用のメリットは次の通りです。
- 幅広い求職者と出会える
- 働く意欲の高い人材が採用できる
- 企業文化や社風になじみやすい
それぞれについて詳しく解説していきましょう。
幅広い求職者と出会える
ポテンシャル採用は、求職者の潜在能力を評価するため、これまで採用ターゲットでなかった層の人材とも出会えます。
一方、実務経験など高い能力を求める傾向があり、出会える求職者が限られてしまいます。場合によっては、応募につながらないことも少なくありません。
ポテンシャル採用であれば、多角的視点で求職者を評価するため、出会いの数が増え、採用につながりやすくなります。
働く意欲の高い人材が採用できる
20代の若手層は、社会人経験は浅いものの、働く意欲の高い人材が多くいます。
株式会社学情の調査によると、社会人経験3年未満の「第二新卒」の転職理由は「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい」が最多でした。また、社会人経験 3 年以上の「ヤングキャリア」の転職理由でも、「給与・年収をアップさせたい」に次いで、「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい」が2番目に多い結果となっており、働く意欲の高さがうかがえます。
※参考:株式会社学情「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(転職理由)2024年9月版」
企業文化や社風になじみやすい
ポテンシャル採用で採用する人材は、社会人経験が浅く、前職の企業文化や社風に染まっていない可能性が高いでしょう。新しい環境にもなじみやすく、しっかりと研修や教育を行えばどんどん吸収できます。
反対に、特定の企業文化や社風が抜けていないと、独自のやり方を貫いてしまったり、周囲に溶け込めず孤立してしまったりすることがあります。早期退職の原因になることもあるため、企業文化になじめるかは大切なポイントです。
ポテンシャル採用のデメリット
ポテンシャル採用にはメリットがある一方、デメリットもあります。デメリットを理解したうえで、採用計画を立ててみましょう。
ポテンシャル採用のデメリットは次の通りです。
- 人材育成や研修が必要
- 自社に適した人材を見極めるのが難しい
それぞれについて詳しく解説していきます。
人材育成や研修が必要
社会経験は持っているものの、入社後に人材育成や研修が必要な場合も少なくありません。
ポテンシャル採用のなかには、前職でビジネス研修を受けていない人もいます。また、研修を受けていても自社の研修内容と異なっていたり、人によって基礎スキルに差があったりすることも多いです。
ポテンシャル採用を実施する際は、人材育成や研修が必要だと考えておいた方が良いでしょう。
自社に適した人材を見極めるのが難しい
求職者の潜在能力は、具体的な数値や資格で表せないため、選考時に見極めることが非常に難しい傾向があります。採用要件や評価基準が定まっていないと、面接官によって評価がブレてしまうこともあります。
自社が求める人物像とマッチしているか見極められないと、採用後にミスマッチが生じ、早期退職につながることも珍しくありません。
ポテンシャル採用を成功させる方法

ポテンシャル採用を成功させるには、いくつかポイントがあります。採用成功のポイントをおさえ、自社に適したポテンシャル採用を実施しましょう。
採用要件を明確にする
マッチング精度の高い採用を目指すには、採用要件を明確にします。
求職者のどのような部分を評価するかは企業によって異なるため、採用要件が明確でないと、評価基準がブレてしまい、ミスマッチを誘発する可能性があります。
特にポテンシャル採用は、求職者の能力を数値化できないため、採用要件をより細かく設定することが大切です。
採用要件の設定については、こちらの記事もご覧ください。
採用要件や評価基準を社内で共有する
採用要件や評価基準を設定したら、それを社内で共有しましょう。人事部だけでなく、選考に関わる経営陣や社員と情報を共有することで、共通認識を持ちながら採用活動が進められます。
求職者の人柄や価値観を重視するポテンシャル採用では、評価基準が曖昧だとミスマッチを誘発する可能性があるため、注意が必要です。
研修制度を整える
採用者が持つポテンシャルを十分に発揮させるには、研修制度やサポート体制を整えることが重要です。
ポテンシャル採用は、キャリアチェンジの人が多いため、業界や職種の基礎が学べる研修を実施しましょう。また、基本的なビジネススキルについても、人によって習得度合いが異なるため、研修内容に入れておくと安心です。
また、以下のような取り組みも有効です。
- メンター制度の導入: 配属部署の先輩社員が業務の進め方やスキルアップをサポートする
- オンボーディングプログラム: 入社初期の不安や戸惑いを軽減し、社内の仕組みや文化にスムーズに馴染めるよう支援する
- 定期的な1on1面談: 上司や人事がキャリアビジョンを確認し、追加研修やジョブローテーションの機会を提供する
ポテンシャル採用の選考で重視すべきポイント
ポテンシャル採用においては、「即戦力」としてのスキルや職務経験だけでなく、将来の成長可能性を多角的に評価することが重要です。ここでは、選考で特に重視したい4つのポイントを紹介します。
学習意欲・成長意欲
ポテンシャル採用で最も重視される要素の一つが、学習意欲や成長意欲です。これまでの社会人経験が浅くても、自己学習や資格取得の実績や過去に苦手分野を克服した経験を確認することで、候補者の伸びしろを把握できます。
学習意欲が高い人材ほど、環境や仕事の変化に柔軟に適応し、自らスキルアップを図ろうとします。未経験でも積極的に知識を吸収する姿勢があるかどうかを見極めることが、ポテンシャル採用の鍵です。
コミュニケーション力
どのような職種でも、チームメンバーやクライアントとの連携が求められます。そこで、コミュニケーション力の有無はポテンシャル採用において重要なチェック項目となります。
ポテンシャル採用で求めるのは完璧なプレゼンテーション能力ではなく、周囲との意思疎通を円滑にする素養です。面接ではグループディスカッション形式を導入するなど、候補者のコミュニケーションスタイルを観察できる工夫が有効です。
将来のキャリアビジョン
ポテンシャル採用では、応募者が「将来的にどんな仕事をしたいのか」「どんなスキルを伸ばしたいのか」というキャリアビジョンを持っているかどうかも大きな選考材料となります。
企業側も候補者のキャリアビジョンを把握することで、入社後の配属先や育成プランを検討しやすくなります。お互いの将来像がかみ合うかどうかは、長期的な定着にも関わる重要要素です。
価値観のマッチ度
ポテンシャル採用では、候補者が持つ価値観や企業文化へのフィット感も重視されます。即戦力採用以上に、「入社後の活躍をサポートする土壌」や「本人のモチベーションを長く保てる環境」があるかがポイントとなるためです。
価値観のミスマッチがあると、せっかくポテンシャルを感じられる候補者でも、定着や活躍に支障をきたすケースが出てきます。面接や適性検査などで「どんなときにやりがいを感じるか」「どんな働き方を好むか」を確認し、相互理解を深めることが大切です。
ポテンシャル採用に効果的な採用チャネルや手法
ポテンシャル採用を実施する際は、若手層や未経験層と出会いやすいチャネルを有効活用しましょう。具体的には、以下のような手段があります。
求人サイト
多くの求職者が利用する求人サイトは、企業と若手人材が最初に出会う場になりやすいチャネルです。20代や未経験歓迎を前面に打ち出す、成長環境をアピールするなどのポイントを抑えることで、ポテンシャル採用に適した層を集めやすくなります。
求人サイトには多種多様な募集が並ぶため、「ポテンシャルを重視している」ことが伝わる求人内容を作ることが重要です。
人材紹介
人材紹介サービス(エージェント)は、キャリアアドバイザーが候補者の希望や適性を見極めたうえで企業にマッチングする仕組みです。アドバイザーが候補者の経歴だけでなく、学習意欲や人柄を把握し、企業カルチャーに合いそうな人材を推薦してもらうことが可能です。
人材紹介を利用する際は、「ポテンシャル採用に力を入れたい」という方針を明確に伝え、エージェントとの認識を合わせておくことが大切です。
リファラル採用
リファラル採用とは、社員からの紹介を通じて人材を採用する方法です。社員が「自社のカルチャーや仕事の進め方を理解できそう」と感じる人材を推薦するので、ミスマッチを防ぎやすいのが特徴です。
社内のリファラル制度を周知徹底することで、社員が自発的に「この人は成長しそう」という人材を紹介する機会が増え、効果的に母集団を形成できます。
SNS・採用広報
近年、SNSや採用広報を活用した情報発信も注目されています。特に若い世代はSNSを通じて企業の雰囲気や社員の働き方をチェックするケースが多いため、ポテンシャル採用には有効な手段です。
SNSを含めた広報活動を継続的に行い、「自社は若手を歓迎し、育成に力を入れている」ことをアピールするのがポイントです。
ポテンシャル採用に成功した企業の事例
ここでは、実際にポテンシャル採用を導入している企業の事例をご紹介します。具体的な取り組み内容を参考に、自社の採用活動に活かしましょう。
株式会社スリー・イー様
「アジアを代表するITインフラ企業」を目指す同社は、設立から20年で社員数1,000名超の成長を遂げました。業績好調に伴い、毎年約200名を新たに採用する中、特に第二新卒や未経験人材の採用において、効率よく質の高い人材を確保することが課題となっていました。
そこで、20代若手層に特化した学情の「Re就活」を導入。年間を通じて継続的に掲載し、職種や時期に応じて柔軟に調整を加え、スカウトメールの運用を強化しました。また、学情の担当者が企業カルチャーや採用ターゲットを深く理解し、イベント運営においてもきめ細やかなサポートを実施。これにより、月に最大8名の採用を実現しました。
※参考:株式会社学情「株式会社スリー・イー様|エンジニアを育成する独自のメソッドを武器に、月8人の第二新卒採用に成功。」
株式会社ワコール様
新卒採用がメインであった同社は、多様な価値観を持つ人材を採用し、柔軟な組織風土を醸成するために、20代を対象としたポテンシャル採用に注力しています。以前は自社採用サイトのみを活用しており、応募者層が限られていましたが、学情の「Re就活」と「転職博」を導入することで、ターゲット層への効率的なアプローチが可能となりました。
「転職博」では、1日で予想を超える100名近くの20代求職者と出会い、そこから入社に繋がった社員が現在活躍しています。また、「Re就活」では、短期間で100件以上のエントリーを獲得し、非常に高いマッチング精度を実感。これにより、ポテンシャル採用が大きく前進し、定期的な採用の成功を収めています。
※参考:株式会社学情「株式会社ワコール様|期待以上に質の高いマッチングを創出、当社の20代採用計画になくてはならない企画に。」
学校法人近畿大学様
本学では、長年キャリア採用を行っており、これまでは他社の転職サイトを活用していましたが、応募者層は主に30代以上で、即戦力の人材が中心でした。そこで、20代若手社会人をターゲットにしたポテンシャル採用に注力するため、学情の「Re就活」を導入。特定の職種に限定せず、成長を期待できる若手人材の採用を目指しました。
「Re就活」を活用し、従来の広告内容を見直すことで、若手社会人に向けたPRを強化。特に人事部門などのイメージが伝わりにくい業務についても、より多くの応募者の関心を引きつけることができました。2018年から毎年定期的に利用し、安定的な若手人材の採用に成功しています。
※参考:株式会社学情「学校法人近畿大学様|利用開始後、毎年コンスタントに20代若手社会人を採用。」
20代転職に特化した「Re就活」でポテンシャル採用を成功させよう!
ポテンシャル採用は、求職者の潜在能力を評価する採用方法です。売り手市場が続き、人材獲得競争が激化するなかで、ポテンシャル採用に注目が集まっています。
ポテンシャル採用を実施するなら、20代転職に特化した「Re就活」がおすすめです。20代の会員登録割合が93.3%と高く、はじめて転職にチャレンジする会員が75.2%にのぼります。
働く意欲の高い登録者が多いため、採用要件に適した求職者へ効率的にアプローチできます。
ポテンシャル採用を検討されている方は、株式会社学情へお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。