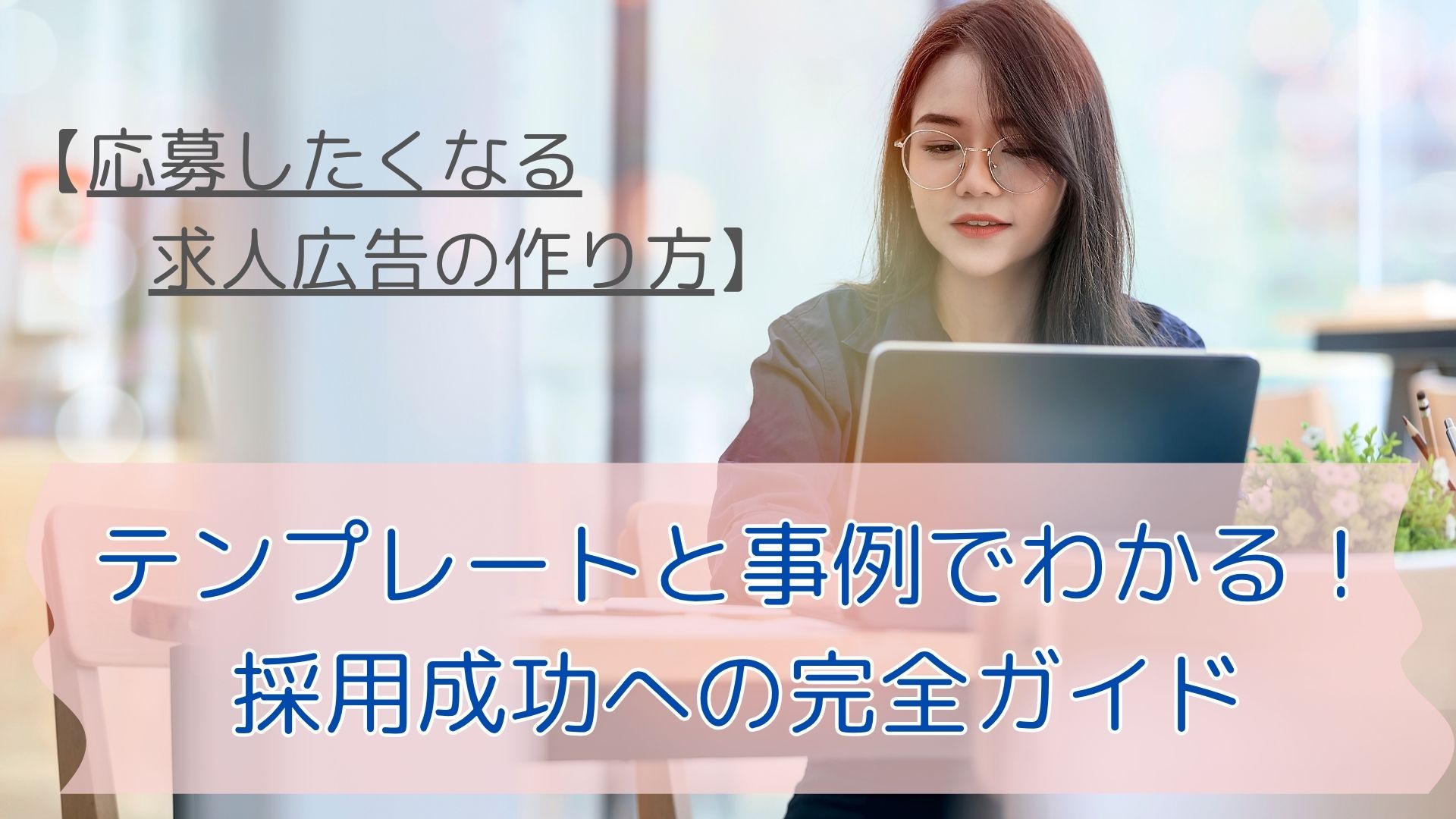従来は、採用活動を自社ですべて行うのが一般的でした。しかし、時代の流れに伴い、採用活動の手法も変化しています。近年は、外部に採用活動の一部を依頼するRPOを利用する企業も増えています。
そこでこの記事では、RPOの基礎知識や依頼できるサービス内容などを解説します。RPOを導入するメリットや向いている企業も紹介するので、自社で導入する際に役立ててください。
RPOとは
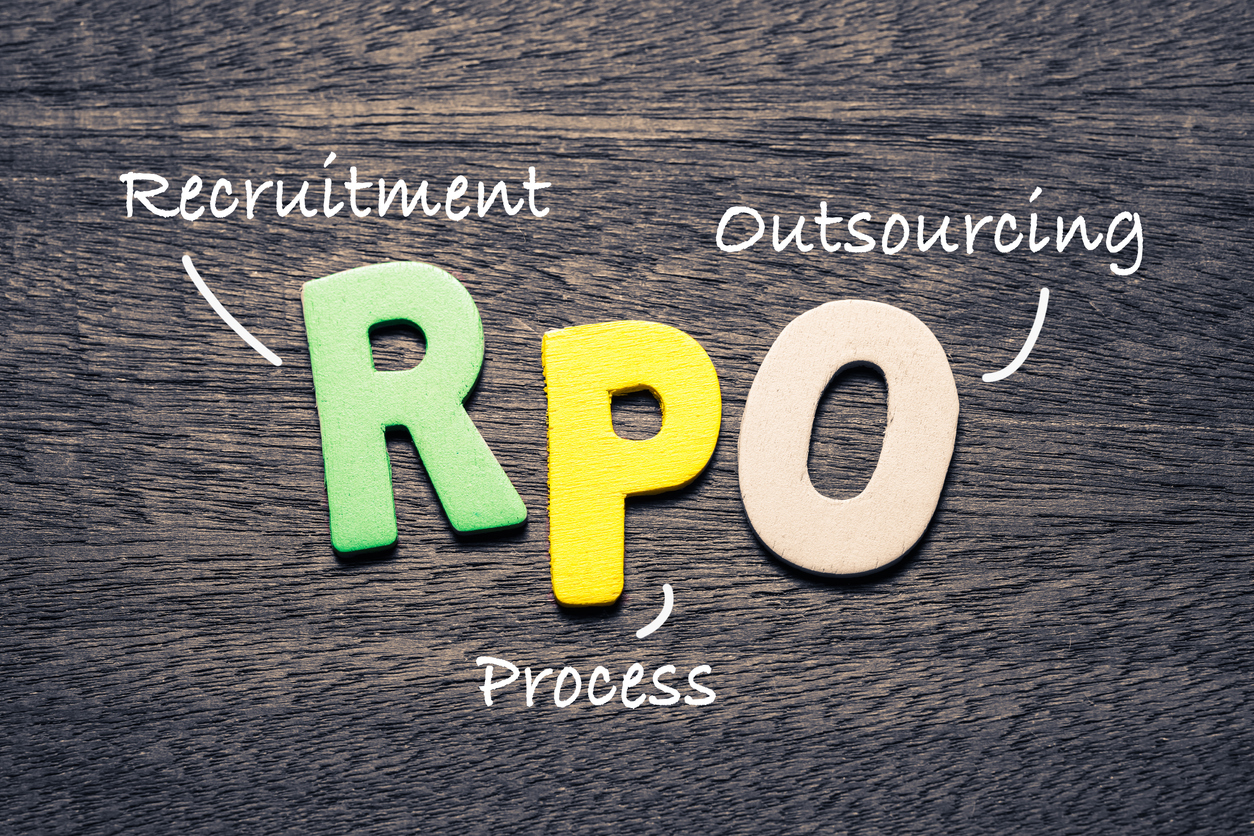
まずは、RPOの基礎を把握しておきましょう。RPOは、1970年代にアメリカで事務代行という形で誕生したサービスです。その後、日本では1990年頃から利用され始めました。日本では事務代行ではなく、採用代行に特化したサービスとして登場しました。
採用代行サービスのこと
RPOは「Recruitment Process Outsourcing」の略称で、企業の採用活動をサポートする採用代行サービスです。採用アウトソーシングと呼ばれることもあります。
採用代行を依頼できるサービスは、採用計画や母集団の形成などさまざまです。サービスのなかには、内定後のフォローやキャリアマネジメントまで幅広く対応しているところもあります。企業側は、サービス側に採用活動のすべてまたは一部の依頼が可能です。
企業がRPOを導入すると、採用担当者の負担軽減や採用活動の質の向上などの効果が期待できます。ただし、ほとんどの採用活動を依頼すると自社にノウハウが蓄積されない側面もあるため、何らかの対策も必要です。
採用コンサルティングとの違い
RPOと類似したサービスには、採用コンサルティングがあります。採用コンサルティングとは、企業が抱える採用活動に関する課題を解決するために、ノウハウを提供するサービスです。
RPOと採用コンサルティングの大きな違いは、採用活動をどこが主体で進めていくかです。RPOは業務のすべてまたは一部を外部に依頼するため、他社主体で進めていきます。一方の採用コンサルティングは自社主体で採用活動を進め、必要に応じて他社からアドバイスを受ける形になります。
採用コンサルティングのおもなサービス内容は、次のとおりです。
- 採用マーケティング
- 採用プロモーション
- 採用ブランディング
- イベント企画・運営 など
RPOには採用計画や母集団の形成など、採用コンサルティングに関わる業務が含まれているケースも多い傾向にあります。
RPOで依頼できるサービス内容

RPOで依頼できるおもなサービス内容は、次のとおりです。
- 採用計画
- 母集団の形成
- 応募者の対応・管理
- 選考に関する対応
- 内定者のサポート
それでは、各サービス内容を詳しく紹介します。
採用計画
RPOでは、企業の採用活動の指標となる採用計画に関する業務を提供しています。採用計画は、経営戦略の一つです。優秀な人材を確保し、事業を発展させるためには、適切な採用計画は欠かせません。
RPOに依頼できる採用計画のおもな業務は、次のとおりです。
- 採用活動における課題分析
- 費用対効果の分析
- 採用管理システムの提案
- エージェントコントロール など
採用計画をプロに任せられるため、自社が採用活動の目標を達成できるプランニングが期待できます。サービスによっては、採用サイトの構築や改善に関する業務にも対応してもらえます。
母集団の形成
自社の求める人材を集めるには、応募者の質を高めるための母集団の形成が重要です。単に多くの応募者を集めるだけでは、自社の条件に合う人材が集まるとは限りません。母集団を上手く形成できれば、応募の時点で自社の条件やスキルなどを確認しながら採用活動を進められるため、より採用の質を高めることが可能です。
RPOに依頼できる母集団の形成に関するおもな業務は、次のとおりです。
- 求人媒体への出稿手続き
- 会社説明会の企画から実施
- リファラル採用の促進
- インターンシップの企画から実施
- SNSの運営管理
- エントリーシートの作成
- エントリーへの対応
- スカウトメールの作成から返信対応 など
サービスの多くは採用業務を代行するなかでノウハウを蓄積しているため、自社にとって効率的な手法での母集団の形成が期待できます。
応募者の対応・管理
求人を出したあとは、応募者の受付や書類の回収などのさまざまな対応が必要です。人事担当者の業務は多岐にわたるため、応募に関する対応や管理などに手間がかかりすぎるとコア業務に集中できない可能性があります。
RPOには応募対応・管理に関する業務など、次のような依頼も可能です。
- 応募者の受付
- 日程調整
- 書類の回収・確認
- 問い合わせへの対応 など
選考の日程調整や進捗確認などの細かい業務にも対応してもらえるため、採用担当者はコア業務に集中しやすくなります。
選考に関する対応
優秀な人材を獲得するには、選考による見極めが重要です。優秀な人材の獲得を目指すなら、採用活動のプロであるRPOに依頼するのも選択肢の一つです。事前にサービス側と企業側で選考基準を擦り合わせるため、自社に適した人材が見つかる可能性があります。
RPOに依頼できる選考に関するおもな業務は、次のとおりです。
- 応募者のスクリーニング
- 応募書類の回収と管理
- 書類選考
- 適性試験・筆記試験の実施と管理
- 選考のスケジュール設定
- 面接会場の選定
- 面接の準備・代行・管理
- 合否決定
- 合否連絡 など
選考に関する対応は、応募者が多くなるほど担当者の負担が大きくなります。多くの応募者とのやり取りが必要な面接の日程調整を依頼し、面接自体は自社の面接官が担当することも可能です。
RPOには、合否決定や合否連絡の依頼もできます。ただし、サービス側と企業側で認識に齟齬があると、採用ミスマッチを招くおそれがあるため、依頼するかは慎重に検討しましょう。
内定者のサポート
企業側は選考の合否を決定し、内定を出したあとも油断禁物です。さまざまな理由により、入社までに内定辞退をする応募者もいるのが現状です。
Re就活キャンパスの「2026年卒内々定率調査2025年4月度」によると、「内定(内々定)獲得企業への入社意思を教えてください」という設問に対して、2社以上の内定(内々定)を得た学生のうち3.1%、また、1社の内定(内々定)を得た学生のうち4.4%が「入社する気はない」と回答していることがわかっています。
|
入社意思 |
1社のみ内々定を獲得 |
複数社の内々定を獲得 |
|
強く入社を希望する |
52.7% |
56.0% |
|
他企業で内定(内々定)を得られなければ、入社を検討する |
43.0% |
40.9% |
|
入社する気はない |
4.4% |
3.1% |
※出典元:株式会社学情「2026年卒 内々定率調査 2024年4月度」
辞退者が出ると、再度選考が必要になります。内定辞退を防ぐには、入社まで丁寧に応募者のフォローをすることが大切です。RPOでは、次のような内定者のサポートも依頼できます。
- 内定者とのコミュニケーション
- 内定者サイトの運営・管理
- 内定者研修の企画・実施
- 内定辞退者との個別面談 など
採用活動のなかでも内定者の管理は重要な業務になるため、豊富な実績かつノウハウを持ち合わせているサービスに依頼しましょう。
各企業がRPOに注目している背景

厚生労働省の資料では、非正規労働者を採用する従業員1,000人以上の大手企業101社のうち、27.0%が導入済み、14%が2年以内に導入を検討していることがわかっています。
※出典元:厚生労働省「今後の人材サービスの展望」
近年、多くの企業がRPOに注目している背景には、人材獲得競争の激化や採用活動におけるマンパワー不足などが関係しています。
人材獲得競争の激化
人材獲得競争の激化により、RPOを活用して効率的な採用活動をしたいと考える企業が増えています。その背景には、少子高齢化を起因とする生産年齢人口の減少により、多くの業界で人材不足が深刻化していることが関係しています。
優秀な人材は、より労働環境の良い企業で働きたいと考える傾向が強いのが実情です。優秀な人材を獲得するのが難しくなってきているため、採用競争力を向上させたい企業がRPOに注目しています。
採用活動におけるマンパワー不足
企業がRPOに注目する理由には、採用活動に多くのマンパワーが必要になったことが考えられます。近年、採用チャネルの多様化や就職活動期間の早期化・長期化の影響で、より多くのマンパワーが求められるようになりました。
近年はマンパワーを充足させなければ、新卒からの応募を十分に集められない状況にもなっています。
人材不足を課題に抱えている企業は少なくなく、担当者の増員も難しいのが実情です。採用活動に関わる担当者の負担を軽減するために、RPOの導入を検討する企業が増えています。
なお、就職活動期間の長期化、早期化、通年化については、こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。
RPOを導入するメリット

RPOを導入すると自社の採用活動をサービス側に任せるため、一定のコストが発生します。その代わりに、企業側には担当者の負担軽減や採用活動の質の向上などのさまざまなメリットが期待できます。
採用担当者の負担軽減につながる
RPOを導入すれば採用活動に関する多くの業務を依頼できるため、自社の担当者の負担軽減につながります。採用活動では書類の確認や応募者の対応など、多岐にわたる業務をこなさなければなりません。
業務の負担が増えることで、コア業務に充分な時間を費やせない可能性もあります。サービス側に多くの業務を任せれば担当者の工数を減らせるため、本来行うべきコア業務に時間を費やせます。
採用活動の質の向上が期待できる
RPOにレポーティングや分析を依頼すると、採用活動の見直しに役立ちます。RPOでは、レポーティングや分析のサービスも提供しています。採用活動に関する実績とノウハウを持ち合わせているため、客観的な立場で採用活動の分析が可能です。
採用活動の進捗状況は、レポーティングという形で共有されます。サービス側はレポーティングをもとに現状を分析し、改善点を指摘してくれるため、PDCAサイクルを回しやすくなります。
採用コストを削減できる
RPOに採用活動を依頼すると、採用コストの削減が期待できます。採用活動に関わる担当者を増やせば、マンパワー不足を解消できるかもしれません。しかし、自社で新たに従業員を採用して担当者を増やすよりも、RPOに依頼したほうが採用コストを削減できる可能性があります。
また、採用活動には、求人媒体への掲載費用や転職サイトへの成功報酬などのさまざまなコストが必要です。採用までに時間がかかれば求人の掲載期間が長期化し、その分コストがかかります。RPOを導入すると効率的に採用活動が進められるため、短期間で採用に至れば採用コストをおさえられます。
RPOの導入で懸念されるデメリット

RPOを導入するとさまざまなメリットが期待できる一方で、いくつかのデメリットもあります。デメリットによる悪影響も懸念されるため、導入する前に何らかの対策を検討しておきましょう。
採用活動のノウハウを蓄積できない
RPOを導入すると、採用活動に関する多くの業務をサービス側に依頼することになります。効率的に採用活動ができても、自社がすべてを担当しているわけではないため、ノウハウを蓄積しにくい側面があります。
自社にノウハウを蓄積するには、サービス側と定期的に情報を共有する機会を設けることが大切です。企業側とサービス側の認識違いが生じる可能性もあるため、積極的にコミュニケーションを取るようにしましょう。
採用ミスマッチが起きるリスクがある
RPOを導入して採用活動の多くを依頼すると、自社が求める人材が集まらず、採用ミスマッチが起きるリスクがあります。採用ミスマッチが起きると内定辞退者や早期離職者が増え、定着率の低下につながります。
RPOは、採用活動のプロです。しかし、サービスを利用して人材を獲得しても、すべての内定者が無事に入社し、長期間自社に定着してくれるとは限りません。RPOのサービス側はあくまでも他社なので、自社が求める条件に合う人材を正しく見極められるとは限りません。ミスマッチの可能性をゼロにはできないのが現状です。
採用ミスマッチのリスクを低減するには、自社が求める人材をサービス側ときちんと共有しておくことが重要です。
情報漏洩の可能性が高まる
採用活動では応募者の個人情報や企業の経営に関する情報など、重要情報に触れる機会が多々あります。情報管理が行き届いていないサービスの場合、情報漏洩のリスクがあるので注意が必要です。
情報漏洩を防ぐには、ISMS認証やプライバシーマークを取得しているサービスを選びましょう。ISMS認証やプライバシーマークは、情報管理が適切な企業のみが取得できます。また、情報セキュリティに関して、従業員にきちんと教育できているかも併せて確認しておくと安心です。
採用プロセスの把握・主導がしにくくなる
RPOを導入すると、外部のサービス側が大部分の実務を担うため、企業の採用担当者が選考状況や応募者の反応を十分に把握しにくい場合があります。認識の行き違いが起きると、優秀な候補者への対応が後手に回り、採用機会を逃すリスクも。
定期的な報告や社内との連携体制を整え、採用プロセスを「自社主体」でコントロールできる仕組み作りが重要です。
RPOの導入が向いている企業

RPOのメリットやデメリットを考慮した上で、導入が向いている企業は次のとおりです。
- マンパワーが不足している企業
- これまでの採用活動で成果が現れていない企業
- 求める人材からの応募が少ない企業 など
担当者不足の状態では、コア業務に時間を費やすのが難しくなります。RPOには、応募者のスクリーニングや採用スケジュール管理などの一部の業務でも依頼可能です。ノンコア業務をRPOに依頼すれば人手不足を解消し、担当者はコア業務に専念できるでしょう。
RPOは、採用活動に関する実績やノウハウを持ち合わせています。これまでの採用活動で十分な成果が得られていない場合は、採用活動のプロに任せることで、課題が解消される可能性があります。
また、応募者が多くても、自社が求める人材からの応募が少ないケースも珍しくありません。RPOは自社の課題を分析し、適切な採用計画を策定してくれるため、求める人材の獲得が期待できます。
RPO導入の失敗例と対策
RPOは採用活動の効率化や担当者の負担軽減に大きく寄与しますが、導入方法や運用体制を誤ると期待した成果を得られない場合があります。
ここでは、よくある失敗パターンと、その対策をあわせて解説します。
コミュニケーション不足で採用ニーズが伝わらなかったケース
企業側が求める人物像や社風、応募者との接し方などを十分に伝えないままRPOに依頼してしまい、募集要件とズレた候補者ばかりを集めてしまうケースです。早期離職や内定辞退の増加につながりがちです。
対策としては、サービス利用開始前に具体的な採用目標や自社カルチャーを共有し、定期的な打ち合わせやレポートで認識をすり合わせることが重要になります。
コスト優先でサービス品質が不足したケース
料金の安さだけを基準にRPOを選んだ結果、進捗管理や応募者対応に遅れが生じたり、選考の質が十分でなかったりする事態が発生することもあります。結果的に、優秀な人材を逃して採用コストがさらに膨らんでしまう例も。
対策としては、サービス提供範囲やサポート体制、実績を総合的に評価し、自社の採用計画に合った品質を担保できる業者を選ぶことが大切です。
RPO導入の流れ
RPOを導入する際は、あらかじめ社内で担当業務や優先度を整理し、RPO事業者との連携体制をしっかり構築することが大切です。ここでは導入の一般的なステップを例示します。
ステップ1:採用課題の整理と業務範囲の明確化
まずは自社の採用上の課題を明確にし、「どの工程を」「どの範囲まで」外部に依頼したいかを整理します。大量採用が必要なのか、専門職の採用に苦戦しているのかなど現状を洗い出し、RPOサービスに求める要件をリストアップしておきましょう。
ステップ2:RPO事業者のリサーチと比較検討
複数のRPO事業者からサービス内容や見積もりを取り寄せ、対応可能な業務範囲・料金・実績・コミュニケーション体制などを比較します。同じ「採用代行」でも得意分野やノウハウは各社異なるため、自社の業界や職種に強い事業者を選ぶと成功率が上がります。
ステップ3:提案内容のすり合わせと契約締結
事前ヒアリングを経て具体的な提案を受け取り、業務範囲や目標、スケジュール、費用などの条件を最終的にすり合わせます。契約の際は、情報管理体制(機密保持や個人情報保護)や途中解約時の対応、成果報酬の有無など細部まで確認しましょう。
ステップ4:サービス開始・進捗管理
業務がスタートしたら、RPO事業者と定期的に連絡を取り合い、採用進捗や応募者の反応を共有しながら運用を進めます。面接調整や書類選考結果のレポートなどを細かく把握し、自社で判断すべきところはタイムリーに意思決定を下すことが重要です。
ステップ5:定期的な効果検証と改善
一定期間ごとに成果を評価し、母集団形成や選考基準の見直しなど必要な改善策を協議しましょう。RPO事業者を上手くパートナーとして巻き込み、PDCAを回すことで、より効果的・効率的な採用活動を実現できます。
RPOを導入する際のポイント

RPOを上手く活用するには、いくつかおさえておきたいポイントがあります。ポイントをおさえた上でRPOを導入し、効率的な採用活動を目指しましょう。
依頼する業務範囲を明確にする
RPOを導入する際には、どの業務をどの範囲まで依頼するかを明確にしておきましょう。依頼できる業務範囲は、サービスごとに異なります。サービスによっては、自社が希望するすべての業務に対応していない可能性もあります。
まずは自社が依頼を希望する業務範囲を明確化し、対応できるサービスを探しましょう。自社で担う業務とサービス側に依頼する業務をきちんと線引きし、担当者同士で共有しておくことも大切です。
業者と定期的に情報共有する
RPOに業務を依頼したあとは任せきりにせず、定期的に情報共有する機会を設けるようにしましょう。サービス側に採用活動を任せきりにすると、自社が求める条件がきちんと伝わっておらず、採用ミスマッチにつながるおそれがあります。
サービス側に依頼する業務範囲が広い場合でも、定期的に情報共有する機会を設け、認識にズレが生じないよう心がけましょう。また、自社が求める人材の効率的な獲得を目指すなら、ダイレクトリクルーティングが有効です。
ダイレクトリクルーティングとは、自社が求める人材に直接応募を促す採用手法です。気になる人材に積極的にアプローチできるため、優秀な人材の獲得や採用活動の効率化などの効果が期待できます。
過去の支援実績や得意分野を確認する
RPOを選ぶ際は、過去の導入事例や成功実績をチェックしましょう。類似業界・職種の採用に強いか、どのような成果を上げているかなど、得意分野が自社のニーズと合致しているかを見極めることが大切です。
コミュニケーション体制を整えられるか
進捗報告や連絡手段が自社の採用担当者と合っていないと、応募者対応の遅れや情報共有のタイムラグにつながります。定例ミーティングの頻度や連絡方法(メール・チャットツールなど)を確認し、スピード感ある連携が可能かを見極めましょう。
料金体系が明確で自社予算に合っているか
RPOには「月額固定型」「成果報酬型」「両方の組み合わせ」など、様々な料金形態があります。自社の採用目標や採用期間に合わせて、費用面で無理が出ないかを必ず確認してください。追加料金やオプション費用の有無もチェックし、トータルコストを試算しておくのがおすすめです。
契約期間や解約条件に柔軟性があるか
採用活動は市況や人員計画によって変動するため、契約途中で条件変更や打ち切りが発生する可能性があります。最低契約期間の長さや途中解約時の違約金、契約延長の可否など、柔軟に対応できるか事前に確認しておくと安心です。
自社の状況に応じた部分的な利用も検討する
すべての採用業務を丸ごと外注するのではなく、面接調整や書類選考など一部工程だけを任せる方法もあります。繁忙期や大量採用が集中する期間だけスポットで活用するなど、自社の状況に応じて使い分けることで、無駄なコストを抑えながら採用効率を高めることが可能です。
おすすめのRPOサービス
採用活動の負担を軽減し、より効果的な人材獲得を目指す企業には、信頼できるRPO会社の導入が大きな助けとなります。
人事ライト(株式会社アールナイン)
株式会社アールナインが提供する「人事ライト」は、求人設計からスカウト送信、面接対応、内定者フォローまでを一貫して支援する採用代行サービスです。
採用代行に特化して15年。母集団形成に依存しない戦略設計と、選考移行率の向上に重きを置いた丁寧な支援に定評があります。
|
対象 |
新卒採用、中途採用 |
|
サービス内容 |
採用計画から内定者フォローまで幅広く支援 |
|
強み |
母集団形成に依存しない戦略設計・選考移行率の向上に重きを置いた丁寧な支援 |
サービスサイトURL:https://r09.jp/jinji-light-service/
RPOを上手く活用して担当者の負担を軽減しよう

採用活動のなかには、企業側が直接関わるべき業務もあります。ノンコア業務とコア業務を振り分けし、ノンコア業務をRPOに依頼すると、担当者はコア業務に集中することが可能です。
採用活動を効率化するにはRPOのほかに、ダイレクトリクルーティングを活用する方法もあります。ダイレクトリクルーティングは自社の条件に合う人材に直接アプローチできるため、効率的に採用活動を行えます。
ダイレクトリクルーティングを活用するなら、Re就活がおすすめです。Re就活では、ターゲットの学生のみに直接アプローチできるオリジナルダイレクトメールとスカウトテレフォンサービスを提供しています。
セミナー予約を獲得できるため、効率的に母集団を形成することが可能です。詳しい内容を知りたい企業様は、ぜひこちらからお問い合わせください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。