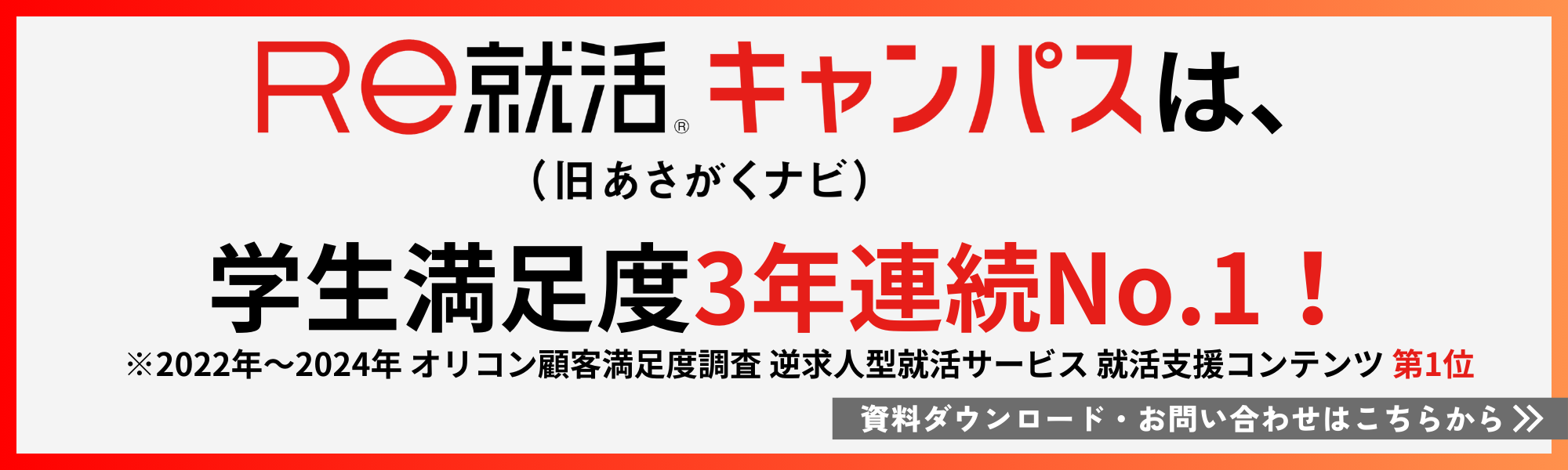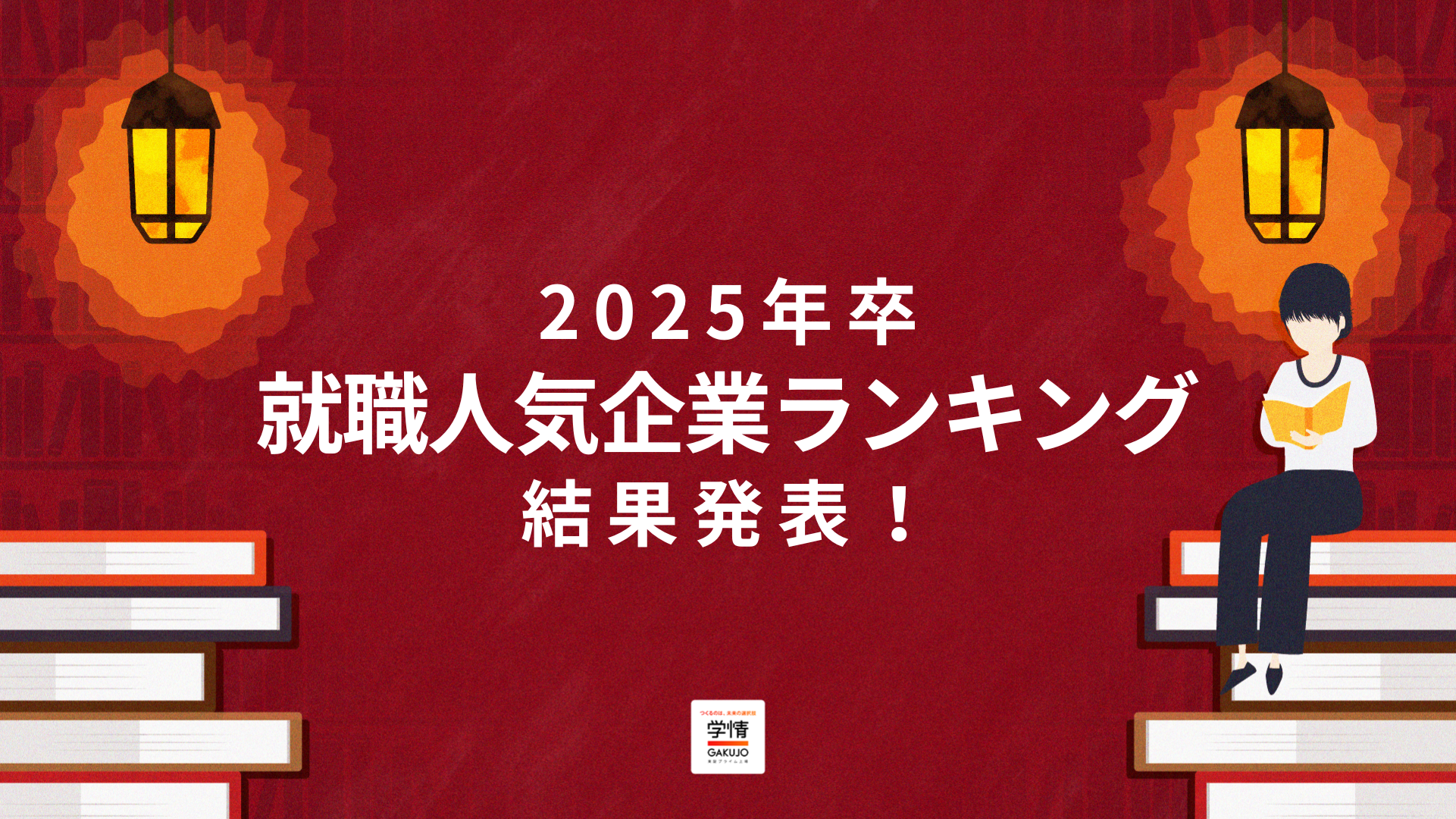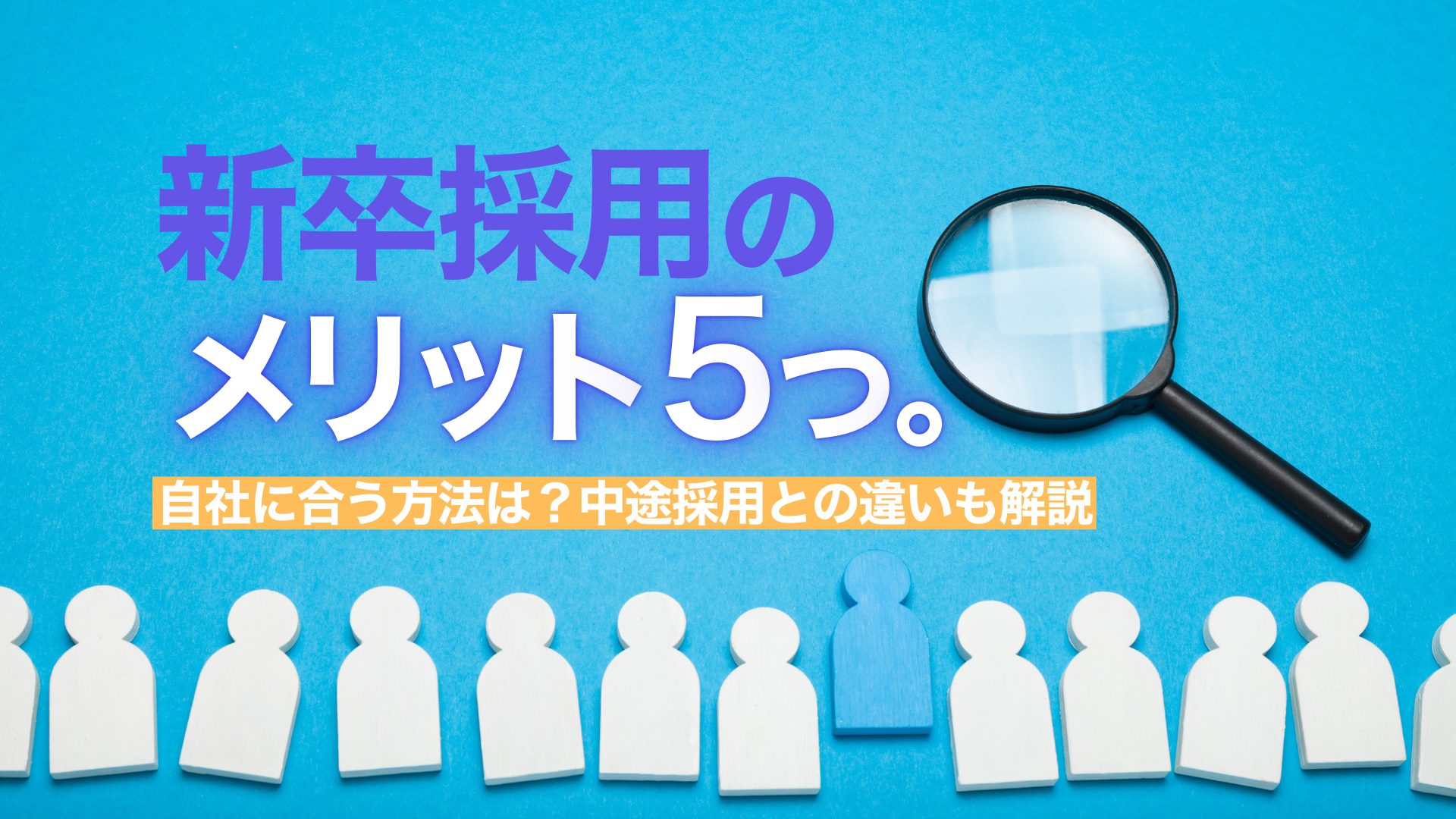
新卒採用のメリットには、社会人未経験の人材を中長期的な目線で育成できること、組織の新陳代謝を促せることなどが挙げられます。加えて、採用活動のしやすさの面でも、コストが抑えられることやスケジュールの立てやすさなどのメリットがあります。
近年は、売り手市場が続いていることから新卒採用のみで採用目標を達成することが難しくなってきています。そもそも新卒でなければならない理由がわからず、お困りではないでしょうか?この記事では、新卒採用と中途採用とを比較しつつ新卒採用のメリットについて詳しく解説します。
新卒にこだわらない、今の市況に適した効果的な採用方法もご紹介しておりますので、ぜひ最後までお読みください。
新卒採用とは
新卒採用とは、企業が大学や専門学校などを卒業予定の学生(新卒者)を採用することです。
一般的には、新卒者が社会人として初めて就職する機会を指します。
新卒採用はもともと「新卒一括採用」と呼ばれる手法が一般的でした。新卒一括採用は、新卒者を対象に決まった時期にまとめて選考活動を行います。高度経済成長期から浸透し、日本になじみのある「終身雇用」や「年功序列」などの制度と相性が良かったために定着したといわれています。
ほかにも、一括で採用活動を行うことで、そのつど採用活動を行うよりもコストが抑えられることも、新卒一括採用が広まった一因とみられます。
しかし、近年は、学生の動き出しの早期化や内定辞退による長期化の影響で、採用活動自体のスタートが早く・終わりも遅くなってきています。そんな中で徐々に実施する企業が増えてきているのが「通年採用」です。
一括採用と通年採用の違い
新卒採用には、一括採用だけでなく通年採用という方法もあります。
新卒一括採用は決められた時期に一斉に採用活動を行うのに対して、通年採用は時期を決めずに年間を通して採用を行います。
通年採用とひとくちに言っても、企業によって実施方法はさまざまです。
- 年間で複数回の選考を開くことで通年採用としている企業
- 実際に常に門戸を開いており、応募があり次第、随時選考を行う企業
- 一度選考で不合格となっても、何度も再チャレンジできる制度を設ける企業
など
中途採用との違い
新卒採用は卒業予定の学生を対象に一括で採用するのに対し、中途採用は社会人経験のある人材を対象にスポットで採用活動を行います。
中長期的な教育を前提にポテンシャルを求めるなら新卒採用、スキルや経験を重視する即戦力採用なら中途採用のほうが適しています。
中途人材の種類
ひとくちに「中途採用」と言っても、新卒採用と異なり、採用できる人材は多岐にわたります。
| 年齢 | 社会人経験 | 定義 | |
| 既卒 | なし | 学校卒業後、留学やボランティア活動に力を入れるなどして進学も就職もしていない人材 | |
| 第二新卒 | 25~26歳くらい | 3年以内 | 1~2年の社会人経験を持つポテンシャル人材 |
| ヤング キャリア |
26~29歳 | 3年以上 | 3~7年の社会人経験があり、同業種でのステップアップまたはキャリアチェンジを考えている人材 |
| キャリア | 30歳以上 | 8年以上 | 高いスキルと経験をもつ即戦力人材 |
新卒採用のメリット
では、新卒採用を実施するメリットは一体何なのでしょうか?この記事では5点ご紹介します。
企業文化を受け入れやすい人材を採用できる
新卒学生はまだ社会人経験がない状態なので、教えられたことを吸収しやすいといえます。
キャリア(経験者)採用だと、すでに他社の文化が基準になっている場合があり、新しい企業文化を受け入れるのに時間がかかるケースが考えられるのです。
その点、新卒学生は社会人になって初めて経験する企業が自社になることから、より自然に企業文化を受け入れてもらえる可能性が高いです。
組織の年齢構成を変えられる
たとえば、特定の世代の社員が多数を占めている場合、その世代の社員が同時期に定年を迎えることが想定できます。
この場合、労働力とノウハウを一斉に失うことになり、組織の弱体化は免れません。
毎年新しい人材が入ってくることで、スキルが高いベテランから若年層へと知識を継承することができ、業務の属人化を防げます。かつ、組織内の年齢層のバランスをとることができます。
そのほかにも、組織の新陳代謝が行われることで、新しいアイデアが生まれる環境を創出できるでしょう。
既存社員のモチベーションアップにつながる
新卒採用は既存社員にもメリットがあります。後輩に恥ずかしい姿は見せられないと、既存社員のモチベーションアップにつながるのです。
新入社員の育成という新しいタスクが増えることで既存社員の普段の業務のマンネリ化を防ぎ、新しい視点を取り入れることができます。また、新入社員に教えることで、既存社員は自分の知識もより深めることができます。
採用コストが抑えられる
採用には多くのコストがかかります。たとえば求人広告の掲載費や採用担当者の人件費、その他経費などです。
新卒一括採用では、採用広報・選考・研修までをまとめて実施することでコストを抑えられます。
複数回に分けて採用活動をするよりも、まとめて採用を行うことで一人当たりの採用単価が安価になるのです。
採用担当者の負担も抑えられます。
選考や研修のスケジュールが立てやすい
現在の政府主導の採用ルールは以下の通りです。新卒一括採用を実施する多くの企業がこのスケジュールに従って採用活動を行います。
広報活動解禁:卒業・修了前年度の3月1日(例:2024年卒学生なら2023年3月1日)
選考活動解禁:卒業・修了年度の6月1日(例:2024年卒学生なら2024年6月1日)
内定出し解禁:卒業・修了年度の10月1日(例:2024年卒学生なら2024年10月1日)
このように予めスケジュールが決まっていることで計画的に準備を進めることができます。
これに加えて、学部3年・4年ないしは修士1年・2年を対象に、夏季休暇中のインターンシップが実施されます。
2025年卒業予定の学生を対象にしたプログラムからは三省合意改正でルールが変わっており、「必ず就業体験が参加日数の半分以上」などの一定の条件を満たすプログラムだけが「インターンシップ」という名称を使うことができるようになりました。ほかにも、企業説明を行うような1dayのプログラムである「オープン・カンパニー」や、「キャリア教育」も、学部1年・2年を対象に早期から開催されています。
三省合意改正によって変わったルールの内容について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
新卒採用のデメリット
新卒採用にはデメリットもあります。メリットとデメリットの両方を踏まえて自社に合った採用方法を選択することが重要です。
戦力になるまで時間がかかる
新卒採用はポテンシャル重視の採用手法であり、新卒者が入社してから戦力になるまでは一定の時間がかかります。
研修期間は会社によってまちまちですが数か月~1年程度かかると考えたほうがよいでしょう。
時間だけでなく、教育コストもかかってきます。
内定から入社まで、フォローの期間が長い
「選考や研修のスケジュールが立てやすい」章でご紹介した通り、新卒採用はスケジュールがあらかじめ決まっています。夏ごろに内々定出しをしたとしても、翌年入社日の4月1日までの長期間、学生のフォローをする必要があるのです。
近年の学生の就職活動の傾向を見ると、既に内々定・内定を持っていても就職活動を継続し、複数の企業を比較検討して最終的に1社を選ぶケースが増えています。学生の内々定・内定辞退を防ぐため、定期的に懇親会や内定後面談を実施するコスト・採用担当者の工数がかかります。
内定者フォローにはおさえるべきポイントがいくつかあります。こちらの記事でくわしく紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
内定辞退・早期離職のリスク
適切なフォローを行っていたとしても、就職活動の傾向から一定数の内定辞退は避けられないと考えるべきです。
また、就職後3年以内の離職率は新規大卒就職者で31.5%であるとのデータがあります。(参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表します」https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00005.html)
せっかくコストをかけて採用しても損失になる可能性があります。これは、新卒者に社会人経験がなく、就業後を具体的にイメージできずにミスマッチが起きてしまうことも一因でしょう。
新卒採用のポイント
ここまで新卒採用のメリット・デメリットをご紹介してきましたが、そもそも新卒者でなければならない理由とはいったい何なのでしょう?
もちろん新卒一括採用には、毎年同じスケジュールで活動ができる、コストが抑えられるなどのメリットはあります。
しかし、ポテンシャルを重視するのなら、新卒だけではなく、既卒・第二新卒・ヤングキャリアを含めた「20代若手」もターゲットになり得ます。実はこの記事でご紹介した5つのメリットのうち4つは新卒者だけでなく20代若手にも当てはまるのです。
- 企業文化を受け入れやすい人材を採用できる
- 組織の年齢構成を変えられる
- 既存社員のモチベーションアップにつながる
- 採用コストが抑えられる
選考や研修のスケジュールが立てやすい←新卒一括採用にのみ当てはまる
5つ目のメリットは20代若手採用には当てはまりません。新卒一括採用と異なり、中途採用は基本的に通年採用であることが多いからです。
しかし、通年で採用活動を行うことにも「内定辞退があっても柔軟に対応できる」などのメリットがあります。
自社の採用目的が何なのかを改めて振り返り、目的に合った採用手法を選ぶことが採用成功のポイントです。
まとめ|新卒採用のメリットを把握して自社に合った採用活動をしよう
いかがでしたでしょうか?
新卒市場での採用競争は、少子化によって激化の一途をたどっています。自社の採用目的を明確にし、目的に応じて採用対象の再検討を行いましょう。ときには新卒だけにこだわらず、ポテンシャル採用なら既卒・第二新卒・キャリアチェンジを狙うヤングキャリア層も採用対象に加えることが対策として有用です。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。