中途採用が難しい10の理由とは?失敗例や解決策を詳しく解説!
公開日:2025.08.22
更新日:2025.12.31

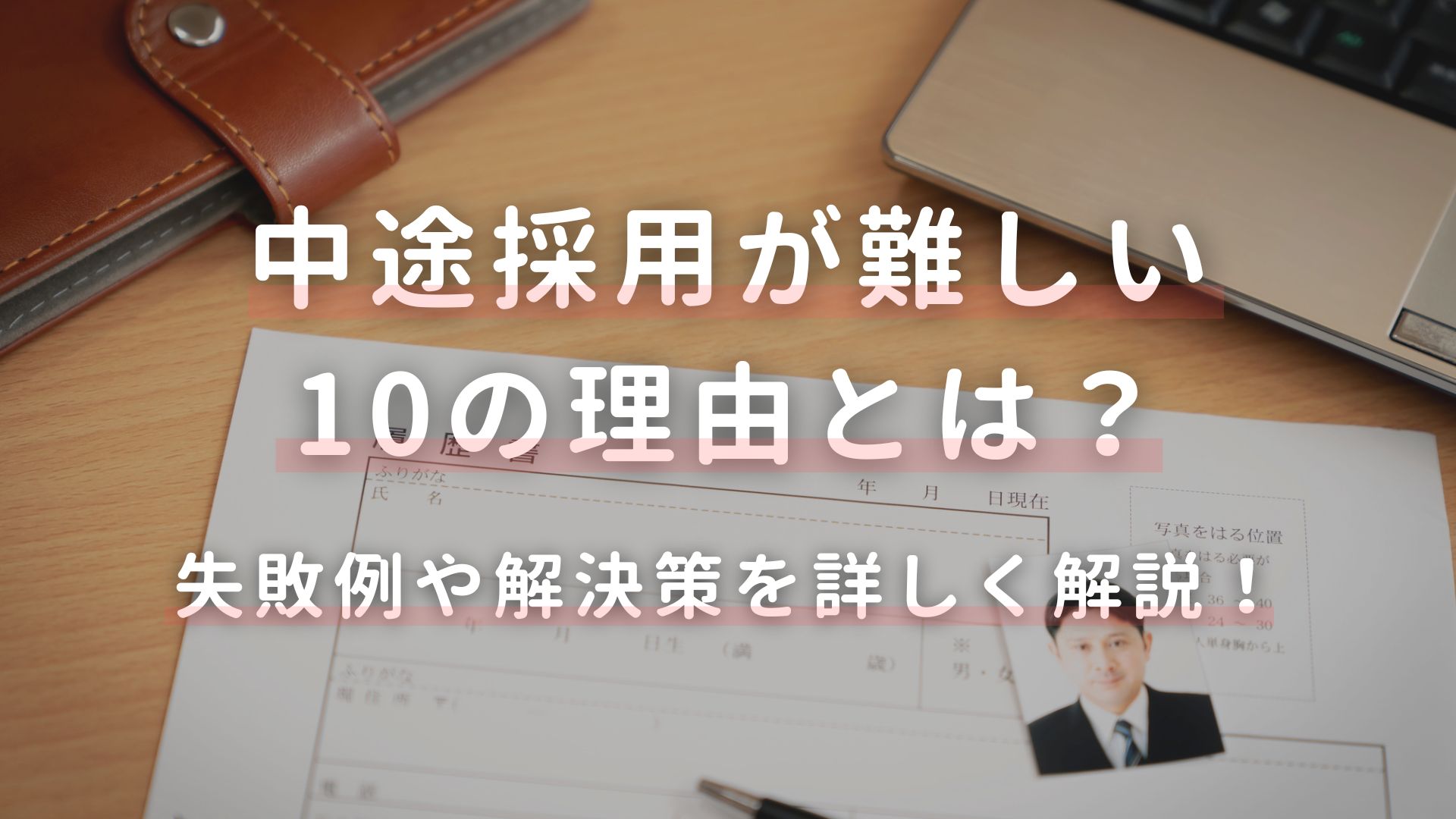
中途採用が難しいと感じている人事労務担当の方は多いでしょう。売り手市場が進み、十分な人材を採用できない企業が増えています。
本記事では、中途採用が難しい理由や採用活動に関する失敗例、解決策について解説します。中途採用に悩んでいる方は、ぜひ今後の採用活動の参考にしてください。
中途採用が難しい理由10選
専門性や経験が求められる中途採用は、以前から難しい傾向にありました。近年は採用市場や求職者の特徴の変化により、さらに難しさが増しています。
まずは、中途採用が難しい理由について解説します。
有効求人倍率が高い傾向にある
有効求人倍率とは、厚生労働省が毎月発表しているもので、求職者1人あたり何件の求人があるかを示す値です。有効求人倍率が1以上は求人に対して応募が不足しており、1以下は求人に対して応募が多い状況を表しています。
新型コロナウイルスの影響で有効求人倍率が落ち込んだ時期もありましたが、現在は増加傾向にあります。2025年1月の有効求人倍率は1.26倍、その月だけの新規求人倍率は2.32倍を記録しており、採用が難しくなっているのが現状です。
※参考:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和7年1月分)について」
即戦力人材の採用競争が激化している
中途採用では、多くの企業が即戦力人材の採用を目指しているため、人材の獲得競争が激化しています。
経験やスキルが重視されやすい中途採用は、母集団形成が非常に困難です。豊富な経験や優れた知識を持つ人材は、どの企業も即戦力として採用したいので競争率が高まります。
選考や内定につなげられても、優秀な人材ほど引く手あまたなので、選考や内定の辞退も多いでしょう。内定を出すだけでなく、入社までつなげるのも難しい状況なのです。
採用手法の多様化
近年、求職者のニーズに応えるため、採用手法が多様化しています。
従来の採用活動は、求人サイトや人材紹介、ハローワークなどを活用するのが主流でした。しかし、現在は従来の採用手法に加えて、ダイレクトリクルーティングやSNS採用(ソーシャルリクルーティング)、リファラル採用などを導入する企業が増加しています。
採用手法の選択肢が増えたことで、新たなノウハウが必要となり、自社に適した手法の選定や運用が難しくなっています。
採用要件を明確に定めるのが難しい
採用活動を効率的に進めるには、採用要件を明確に定めることが大切です。採用要件が不明確だと、ミスマッチを誘発し、選考や内定につながっても辞退されるリスクが高まります。
中途採用の場合、求めるスキルや経験、資格などを細かく設定しなければならない難しさがあります。そのため、募集するポジションの上司や同僚となる人にヒアリングしながら採用要件を決めましょう。
人材の見極めが難しい
中途採用には、求職者を募る難しさだけでなく、人材を正しく見極める難しさもあります。
新卒採用では、求職者の潜在能力を評価するポテンシャル採用が多いですが、中途採用ではポテンシャルと、すでにもっている能力や経験のどちらも見極めなければいけません。
華やかなキャリアを持つ求職者でも、自社で活躍できる人材とは限らないのです。
シンプルな質問だけでは、求職者の潜在能力や自社との相性が見極められないかもしれません。多角的な質問を用意し、さまざまな角度から求職者のことを知ることが大切です。
多角的な視点から、入社後に活躍できる人材を見抜くため、中途採用の面接で質問するべきことリストで公開しています。
採用活動のリソースが足りない
中途採用では、人員不足や欠員補充など、早急に採用活動を進めなければならないケースが多いです。採用を急ぐあまり、面接や内定後のフォローに十分なリソースが割けず、ミスマッチを誘発してしまうことも少なくありません。
大手企業では業務ごとに担当部署が分けられている場合が多いですが、中小企業では採用担当者がそれ以外の仕事を兼任している場合も多いでしょう。他の仕事が忙しく、採用業務が疎かになってしまいがちです。
転職活動の負担が大きい
在職中に転職活動をするには、仕事の合間に求人情報を探し、面接を受けるために仕事のスケジュールを調整しなければなりません。さらに、現職の会社に転職活動をしていることを知られないよう、気を配る必要があります。
在職中の転職活動は、求職者にとって時間的・精神的な負担が大きいものです。そのため、転職を考えていても、具体的な行動に移せない人もいます。
中途採用を成功させるには、転職潜在層にアプローチすることも大切です。
優秀な人材ほど転職市場に登場しない
人材獲得競争の激化や採用手法の多様化により、従来の採用手法だけでは優秀な人材を獲得しにくくなっています。優秀な人材は競合他社からもアプローチを受けているため、求職者からの応募を待っているだけでは、他社に流れてしまうのです。
優秀な人材を獲得するには、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用など、新しい採用手法を導入し、企業側からのアプローチを強化する必要があります。
また、自社から優れた人材が流出しないよう対策することも重要です。その対策として、待遇面の改善やキャリア開発などに取り組む企業が増えています。
企業の知名度が影響しやすい
企業の知名度が低く、母集団形成や内定受諾に苦戦する企業も少なくありません。
特に中小企業は知名度が低く「よく知らないから応募しない」「知名度の高い企業の方が安心」などの理由で応募が集まらなかったり、内定承諾が取れなかったりするケースがあります。
採用広報や広告などを用いて企業知名度を上げる方法もありますが、中小企業では人材不足や予算の制限によって着手できていないケースも多いのが現状です。
仕事に対する価値観の多様化
近年、仕事への価値観が多様化しています。
株式会社学情が実施したアンケートでは、社会人経験3年以上の「ヤングキャリア」の転職理由は「給与・年収をアップさせたい(50.8%)」が最多でした。第二新卒の転職理由は「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい(35.0%)」が最多です。
一方でヤングキャリア・第二新卒ともに「残業を減らしたい、休日を確保したい」「より会社の風土や考え方が合う企業で働きたい」といった希望も上位に上がっています。
さらにコロナ禍以降は、リモートワークやフレックス制、時短勤務など働き方が注目され、企業選びのポイントになっています。これらのことから、仕事に対する価値観が多様化しているといってよいでしょう。
※参考:株式会社学情「転職意識調査レポート2024-20代・若手人材の「転職観」を紐解く」
中途採用で失敗しやすい8つのポイント

ここまで、中途採用が難しい理由について解説してきました。採用が難しいのは、売り手市場や採用競争の激化などの環境要因もありますが、採用活動の方法に問題がある場合も少なくありません。
中途採用で失敗しやすいポイントについて解説します。
求人募集をしても応募が来ない
求人サイトに掲載しても応募が来ないのは、以下のような理由が考えられます。
- 労働条件が他社と比較して劣っている
- 企業の知名度が低い
- 企業の強みや魅力を伝えきれていない
求職者のなかには、複数の企業を比較して条件が良い企業を選ぶ方が多くいます。とはいえ、特に中小企業は、いきなり大手企業と同条件にするのは難しいでしょう。
求職者を募るには、求人サイトへの掲載だけでなく、求職者に対して企業側から積極的に魅力を伝えることも大切です。
採用要件が厳しすぎる
中途採用では、即戦力を求めることが多く、採用要件を厳しく設定する傾向があります。しかし、最初からターゲットを絞りすぎると、対象となる人材が少なくなり、母集団形成が難しくなってしまいます。
採用活動の状況によっては、応募条件をゆるめることも大切です。
たとえば、社内の研修・教育制度を整え、ポテンシャルのある若手人材を育てる方針にシフトするのもひとつの方法です。
対象を広げることで、多様な人材にアプローチしやすくなります。
カルチャーフィットを意識していない
カルチャーフィットとは、自社の文化や価値観と、求職者の性格や価値観が合致している状態のことです。優れた人材であっても、カルチャーフィットを理由に早期退職につながってしまうケースもあります。
採用のミスマッチを防ぐには、求職者のスキルや実績だけでなく、カルチャーフィットを意識した採用活動が大切です。そのためには、採用要件を設定する際に、求職者の性格や価値観に関することも細かく決めておきましょう。
競合他社と差別化できていない
求人サイトには、同エリアで同じ職種の求人情報が複数掲載されています。そのため、複数の求人情報から自社に興味を持ってもらうには、競合他社にはない独自の魅力や強みを積極的に発信しなければなりません。
給与や待遇の高さをアピールすることも有効ですが、すぐに改善するのは難しい場合もあるでしょう。企業文化や入社後のキャリアパスなども競合他社との差別化を図るうえで重要なポイントです。
選考スピードが遅い
選考スピードが遅く、優秀な人材を取りこぼしている企業は少なくありません。
転職意欲の強い求職者ほど、早く転職活動を終えたいと考えているでしょう。選考スピードが遅いと求職者の負担になってしまい、内定辞退に繋がる可能性があります。
- 選考期間が長い
- 返信が遅い
選考スピードを速めるには、選考フローの見直しが重要です。面接回数を減らしたり、スムーズに日程を決められるよう面接の候補日を多めに用意したりするのもよいでしょう。
選考・内定辞退が多い
せっかく選考につながり、内定出しをしても、途中で辞退されてしまう場合があります。
- 志望度の高い他社から内定が出た
- 雇用条件が求職者の希望と合致しなかった
- 社風が合わなかった
選考や内定辞退を防ぐには、求職者の返事を待つだけでなく、企業側からのアプローチが必要です。たとえば、雇用条件のすり合わせのためにオファー面談を組むのもよいでしょう。ただ書類を送るよりも求職者の不安や疑問を払拭しやすくなります。
入社後の定着まで想定していない
採用のミスマッチは早期退職の大きな要因です。採用に至ったものの、入社後にミスマッチが発覚し、早期退職につながるケースも目立ちます。
早期退職が繰り返されると、再び採用活動を行わなければならず、採用コストや工数が余計にかかってしまいます。そのため、中途採用を成功させるには、入社後の定着までを想定した採用活動が不可欠です。
マッチング精度を高めるには、採用要件の明確化や、相互理解を深めるためのカジュアル面談実施などが効果的です。
入社後の研修・教育体制が不十分
中途採用は前職の経験があるため、特別な研修や教育は必要ないと考える企業もあるでしょう。しかし、研修・教育制度が不十分だと、新しい環境に馴染めず、早期退職を誘発する可能性があります。
企業が変われば仕事のやり方や価値観も変わるため、優秀な人材であっても研修や教育は必要です。仕事の流れや職場の雰囲気を早期に把握できるように、研修・教育体制を整備しましょう。
中途採用を成功させる8つのポイント

中途採用を成功させるために、いくつかのポイントをおさえましょう。いくら求人広告を打ち出しても、自社に適した方法でなければ十分な効果が得られません。
中途採用を成功させるためのポイントは次の通りです。
- 採用マーケティングを行って企業ファンを増やす
- 採用計画を見直す
- 採用手法を見直す
- 採用要件を明確にする
- 求人の情報量を増やす
- 母集団形成の段階で候補者を絞り過ぎない
- 選考スピードを速める
- クチコミなどのネット上の評価を向上させる
採用マーケティングを行って企業ファンを増やす
採用マーケティングとは、採用活動にマーケティングの要素を取り入れることです。企業知名度を上げるだけでなく、理想の人材を採用するまでの戦略を立てます。
近年、労働市場は人材不足や価値観の多様化により複雑化しています。人材を募るだけでなく「どのような企業なのか」「企業の魅力は何か」などの情報を発信しなければなりません。
採用マーケティングを実施することで、優秀な人材を獲得し採用のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。効果を発揮させるには、継続的にPDCAを回すことが大切です。
採用計画を見直す
採用計画を定期的に見直せば、労働市場の変化や競合他社の動向に対応できます。定期的に見直さないと、採用活動を効率的に進められず、無駄な採用コストがかかったり、慢性的な人手不足に陥ったりするリスクが高まります。
採用計画を見直すポイントは次の通りです。
採用手法を見直す
中途採用を成功させるには、自社が求める人物像に適した採用手法を選ぶことが重要です。採用手法は多岐にわたり、それぞれに特徴やメリット、デメリットがあります。
|
メリット |
デメリット |
|
|
求人広告 |
多くの求職者にアプローチできる |
採用につながらない場合もある |
|
人材紹介 |
採用要件に適した人材が採用できる |
成功報酬額が高い |
|
転職イベント |
求職者に直接会ってアプローチできる |
出展費以外にも装飾品や参加する社員の人件費がかかる |
|
ダイレクト |
採用要件に適した求職者と出会える |
スカウティングに時間と労力がかかる |
|
リファラル採用 |
マッチング率が高く、 |
似ている人材に偏りやすい |
まずは、自社の採用状況や課題を把握し、採用手法を見直してみましょう。
採用要件を明確にする
採用要件とは、採用したい人材の人物像やスキル、経験などのことです。採用要件を明確にすることで、採用のミスマッチを防いだり、採用戦略を立てやすくなったりします。
採用要件を設定する際は、募集するポジションと同じ部署やチームの社員とともに採用要件を擦り合わせるようにしましょう。
決定した採用要件は、人事部だけでなく採用に関わる社員とも共有します。採用要件を共有すれば、共通認識を持ちながら選考が進められるでしょう。
求人の情報量を増やす
求人情報の不足は、入社後のミスマッチを引き起こしたり、企業の魅力を十分伝えきれなかったりする可能性があります。求人の情報量が不足している場合は、内容を見直しましょう。
求人情報に加えるべき項目は次の通りです。
- 具体的な仕事内容
- 企業理念やビジョン
- 具体的なキャリアパス
- 社員のインタビュー
- 具体的な昇給モデル
- 写真や動画を活用した企業PR
- 研修・教育制度
- キャリア開発制度
- 評価制度
母集団形成の段階で候補者を絞り過ぎない
母集団形成が難しい場合は、候補者を絞り過ぎているかもしれません。採用要件を明確に決めるのは良いのですが、要件が厳しすぎると求職者の母数が少ないため、母集団形成が難しくなってしまいます。
母集団形成を行うには、採用要件を明確にしつつ、最初から候補者を絞りすぎないように注意しましょう。幅広い人材を候補に入れ、ポテンシャル採用を検討するのもおすすめです。
選考スピードを速める
選考スピードが遅いと、求職者が他社へ流れてしまう可能性が高まります。求職者は同時に複数社の選考を受けているため、選考途中で辞退されることも珍しくありません。
他にも選考スピードが遅いと、求職者に対して「別の候補者と比較されている」「判断を渋っている」などネガティブな印象を与える可能性があります。
反対に選考スピードが速ければ、それだけ評価が高い印象を与えることができます。求職者の志望度を下げないためにも、一次面接から内定出しまでの期間は2週間程度にしましょう。
クチコミなどのネット上の評価を向上させる
求職者は企業を判断する際に、ネット上のクチコミを参考にする傾向があります。クチコミの評価が低いと、求職者に不安感を与える可能性があるため、評価を向上させることが大切です。
評価を向上させるには、次のような対策が有効です。
- 誤情報には削除依頼を出す
- 返信機能を使って適切に対応する
- ポジティブな情報を発信してイメージの向上を図る
また、採用における企業評価を向上させるには、従業員満足度を高めましょう。働きやすい環境作りや待遇面の改善などを行うことで、従業員満足度が高まり、悪いクチコミを減らせます。
ただし、企業評価の改善は一朝一夕には達成できません。長期的な視点を持ち、継続的に取り組む必要がある点に留意しておきましょう。
中途採用の成功事例
中途採用の成功事例を紹介します。採用計画の見直しや採用手法の選定などの参考にしてください。
カタニ産業株式会社の事例
|
課題・ニーズ |
支店ごとの実情に即した20代・若手人材の採用 |
|
活用したサービス |
Re就活 |
|
効果 |
名古屋・大阪で5人の20代・若手人材を採用 |
カタニ産業株式会社は、創業120年を超えるスタンピングフォイル(ホットスタンプ箔)の専門商社です。
組織の刷新を図るため、若手採用に着手。20代採用に特化した「Re就活」を導入し、スカウトメールを駆使しながら、採用要件に適した人材にアピールしていきました。その結果、予定数を超える4人の若手人材の採用に成功。また、別の支店でも募集開始から2カ月で、3年間の社会人経験を有する方の採用につながりました。
株式会社タカラの事例
|
課題・ニーズ |
20代前半・第二新卒層の採用強化 |
|
活用したサービス |
・Re就活 ・転職博 |
|
効果 |
約5カ月間で5人の総合職を採用 |
株式会社タカラは、粘着ラベルやシール、テープ、フィルムなどを扱う専門商社です。
事業の特性上、文章だけで仕事内容を伝えるのが難しいため、求職者と直接コミュニケーションが取れる合同企業セミナー「転職博」を中心に採用活動を実施しました。株式会社学情のスタッフが求職者をアテンドし、円滑なブース運営をサポート。「転職博」と並行して「Re就活」での掲載も行い、約5カ月間で5人の総合職が採用につながりました。
株式会社シナプスイノベーションの事例
|
課題・ニーズ |
第二新卒採用を、自社に合った人材紹介サービスで実現したい |
|
活用したサービス |
Re就活エージェント |
|
効果 |
20代・第二新卒人材を2年で20人採用 |
株式会社シナプスイノベーションは、製造業向けのITソリューションを提供しているソフトウェアメーカーです。
求職者に効率よく企業の魅力をアピールするため、人材紹介やダイレクトリクルーティングを中心とした採用活動にシフト。キャリアアドバイザーが採用要件を熟知しているため、内定率だけでなく、定着率の高い採用が可能です。2年間で20人以上が「Re就活エージェント」経由で入社しましたが、退職者はわずか1人でした。
中途採用が難しいときは「Re就活」を使ったポテンシャル採用がおすすめ
母集団形成ができず、中途採用が難しいときはポテンシャル採用を検討してみましょう。
「Re就活」は第二新卒や既卒、ヤングキャリアなど働く意欲や成長意欲が高い20代転職に特化した求人サイトです。会員数280万人を誇る求人サイト以外にも就活エージェントや転職フェア「転職博」などのサービスを展開し、企業の採用ターゲットに適したアプローチ方法をご提案いたします。
20代ポテンシャル採用を検討されている方は、株式会社学情へお問い合わせください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。









