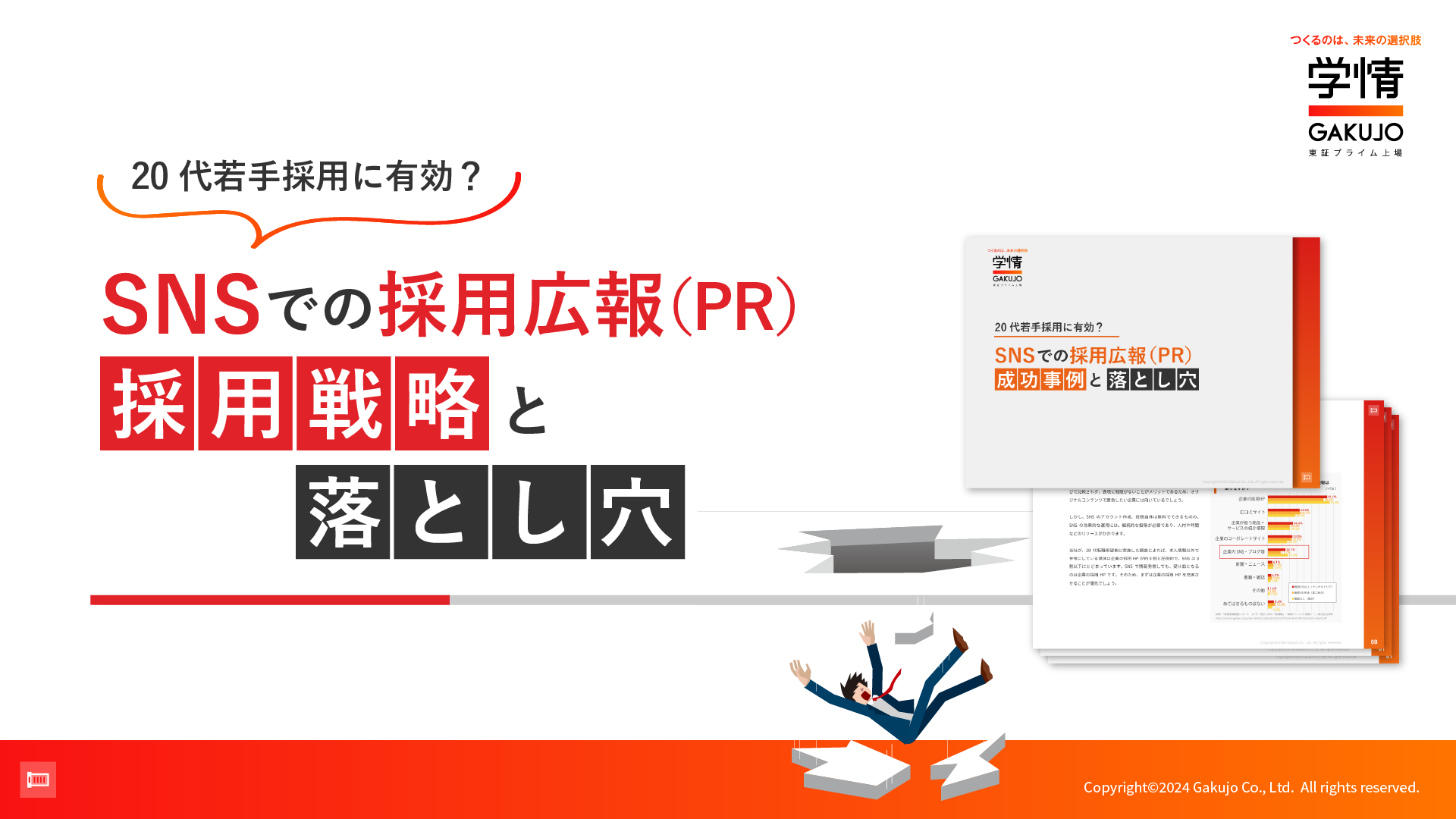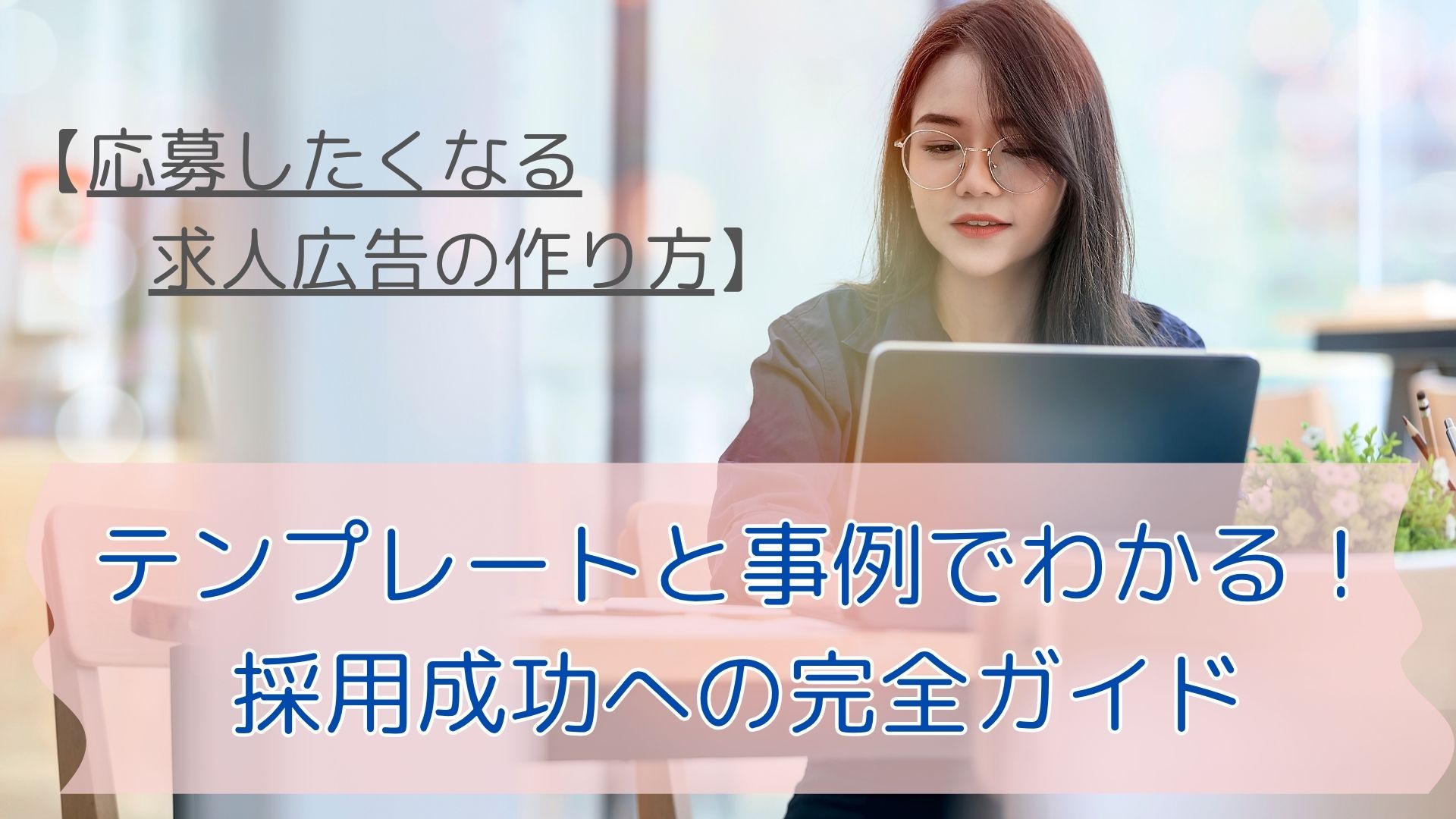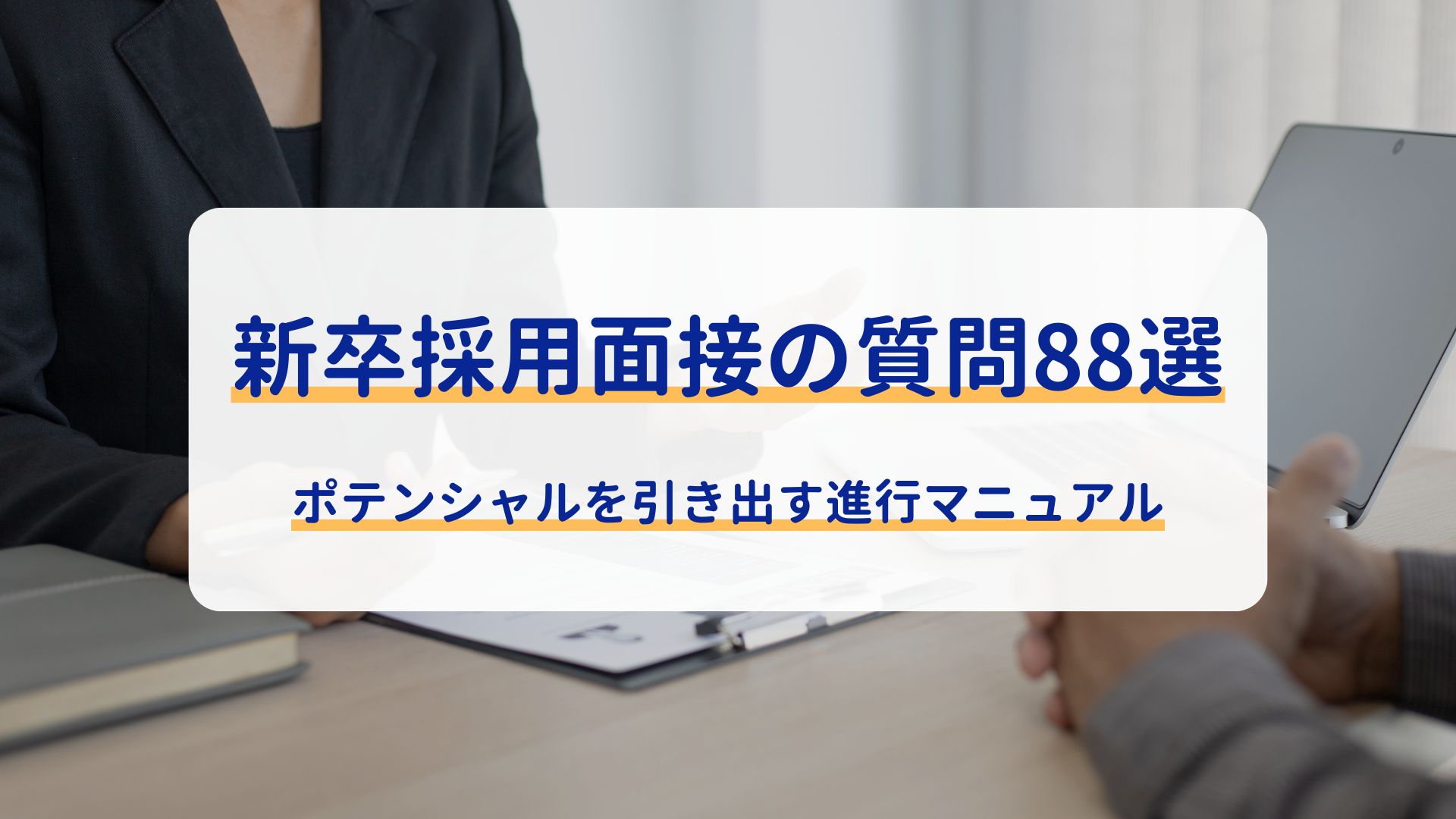SNS採用はソーシャルリクルーティングとも呼ばれ、近年注目されている採用活動の一つです。身近なコミュニケーションツールとなったSNSの活用は、採用活動においてもさまざまなメリットがあります。
本記事では、SNS採用の導入を検討している採用担当者に向けて、SNS採用の基礎知識やメリット・デメリット、おすすめの媒体を詳しく解説します。
SNS採用を導入する際の手順や、成功させるためにおさえておきたいポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
SNS採用とは

SNS採用とは、その名前のとおりSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を活用した採用活動のことです。「ソーシャルリクルーティング」とも呼ばれています。
SNSはインターネット上のコミュニティサイトです。いつでもどこでも、誰でも気軽に情報発信が可能で、ユーザー同士でつながりを持つことができます。代表的なSNSは「LINE」「X(旧Twitter)」「Facebook」「Instagram」などです。
SNSを通して企業の認知度アップや求人掲載、スカウト活動を行うことを「SNS採用」と呼んでいます。
SNS採用が注目を集めている理由

これまで、インターネット上で情報収集や調べ物をするときには、「Google」や「Yahoo!」といった検索エンジンが使われてきました。
しかし近年、若者世代を中心にSNSを使ってリアルな情報を集める傾向が強まっています。背景には、公式発表されている内容よりも、実際のユーザーの声や口コミのほうが信頼されるようになってきたことがあげられます。
SNSの利用者は年々増加傾向にあり、若者だけでなくあらゆる年齢層で身近になってきました。そのため、SNSは新卒採用・中途採用を問わず、採用活動において影響力があるツールの一つとされています。
SNS採用のメリット・デメリット

SNS採用を導入する際にはメリットとともにデメリットも把握し、対策を考えておきましょう。それぞれを詳しく解説します。
メリット
SNS採用のメリットは次のとおりです。
- 幅広い層にアプローチできる
- 拡散力がある
- リアルタイムで情報発信ができる
- 採用コストをおさえられる
求人サイトや人材紹介のような採用方法では、就職や転職の意思がハッキリしているサイト登録者にしかアプローチができません。
一方、SNS採用なら「転職を今すぐには考えていない」「まだ大学1、2年生なので就職活動を始めていない」といったような、就職や転職の潜在層にもアプローチできます。
また、SNSはシェア機能による拡散力があるため、幅広い層や大人数へ情報を届けられるのもメリットです。日常的に利用されているSNSならではの気軽な情報発信で、企業の取り組みやイベントなどもリアルタイムで伝えられます。
加えてSNSは無料でアカウントを作成できるため、採用コストがおさえられるのも魅力です。
デメリット
低コストで幅広い層にアプローチできるSNS採用ですが、導入時にはデメリットもあることを念頭に置いて検討しましょう。SNS採用のデメリットは次のとおりです。
- 運用に手間がかかる
- 即効性はない
- 社内コンテンツの量が必要
- 炎上する可能性がある
SNSで効果を上げるためには、定期的な情報発信が欠かせません。せっかく求職者に興味を持ってもらっても、情報の発信頻度が低ければ次第に興味が薄れていきます。
多くのアカウントが日々投稿を更新するため、更新頻度が低ければあまり画面に表示されなくなり、求職者の目に触れる機会も減っていくでしょう。そのため、継続的に内容のあるコンテンツを発信し続ける必要があり、運用に手間がかかります。
また、SNSは運用を始めたからといってすぐに効果が出るものではありません。良いコンテンツを増やして継続的な発信をすることによって、徐々にフォロワーが増え、認知度が上がっていく仕組みです。
そのため、中長期的な運用計画が必要となることを覚えておかなければなりません。常に発信を続けていくため、社内でのイベントやトピックとなるような取り組みなど、いわゆる「ネタ」になることの種類や数も必要になるでしょう。
そしてSNSで最も注意すべきなのは「炎上」です。炎上とは、Web上で非難が殺到する状態を指します。SNSは不特定多数のユーザーが閲覧するため、人によって受け取り方が異なり、不適切な表現があれば思わぬ形で非難や批判が殺到してしまう可能性があります。そのため、SNS担当者はネットリテラシーに配慮して運用することが大切です。
SNS採用活動におすすめの媒体7選

おすすめの媒体とその特徴を解説します。自社が導入するにはどの媒体が合っているのかを見極める参考にしてください。
LINE(ライン)
「LINE(ライン)」は日常的に利用しているユーザー数が多く、手軽な連絡手段としても幅広い世代で活用されているSNSです。
多くの人が慣れ親しんでいるツールのため、コミュニケーションのやり取りがスムーズに行えるでしょう。LINEはメールと異なり、開封率が高く、反応をもらいやすいのが特徴です。
LINE公式アカウントを活用すれば、ユーザーへ直接メッセージを送ったりタイムラインにお知らせを投稿したりすることができます。
メッセージは友だち登録をしている全員に向けて一斉送信もできますが、1対1の個別のやり取りも可能なため、相手に対して確実に伝えたいメッセージを届けられることもLINEの魅力です。
また、SNSに慣れ親しんでいるZ世代・20代若手にも受け入れられやすいのが特徴で、メールより心理的ハードルが低く、配信を見てもらえる可能性が高まります。
LINEを活用したSNS採用を導入するなら、新卒向けの「Re就活キャンパスコミュニケーター」がおすすめです。LINEを通して学生とコミュニケーションをとり、スムーズなやり取りを実現します。
高い返信率を確保し、応募者管理やリマインド配信が自動化できるため、採用活動におけるコミュニケーションコストを大幅に削減できるでしょう。
X(エックス)※旧Twitter(旧ツイッター)
「X(エックス)※旧Twitter(旧ツイッター)」は、10~30代の若者層が多く利用しているSNSです。実名制ではなく匿名のアカウントで、投稿できる文字数も少ない「つぶやき型」のSNSであるため、その分気軽かつスピーディーに発信できるのが特徴です。
最新情報をすぐに更新できるためリアルタイムの情報が交換できます。また、リツイートや「いいね」機能による二次拡散力が驚異的と言えるでしょう。ハッシュタグ検索ができるため、不特定多数のユーザーの目に触れる機会を作りやすいSNSです。
文字数は140字以内と決まっており、簡単に投稿できるため気軽に運用できます。発信できる情報量に限りはありますが、運用を継続しやすいSNSと言えるでしょう。
Instagram(インスタグラム)
「Instagram(インスタグラム)」は、10~20代からの人気が高いSNSです。写真や動画によって社内の雰囲気やイベントの様子などを伝えやすいのが特徴です。
「インスタ映え」という言葉が流行したほど、写りが綺麗でおしゃれな写真の投稿が主流になっています。ビジュアル的な訴求効果が高いSNSであるため、企業の世界観を演出するのに向いています。
Twitterに比べて拡散性は低いため、より多くのユーザーに投稿を届けるにはハッシュタグを使うなどの工夫が必要です。写真や画像、動画などの素材が用意できれば比較的簡単に投稿できるため、運用が継続しやすいツールと言えるでしょう。
Facebook(フェイスブック)
「Facebook(フェイスブック)」は、世界中で多くの人が利用しており、国内では特に30〜40代の利用者が多いSNSです。文章や写真によって、日記を公開するような形で投稿できます。
実名登録制となっており、ほかのSNSに比べて信頼が担保されているのが特徴です。
Facebookでは公式アカウント機能を使って、企業のページを作成可能です。投稿では写真とともに長文も掲載できるため、より詳細に情報を伝えられるでしょう。
なお、企業のページに「いいね」が押されると、「いいね」を押したユーザーのタイムラインに情報が流れます。そのため、「いいね」を押してもらえれば企業のページがさまざまな人の目に触れやすくなるでしょう。Facebookには分析機能も付いているため、PV数や反応をもらった数などの効果測定もできます。
YouTube(ユーチューブ)
「YouTube(ユーチューブ)」は、音声付きの動画を自由に投稿、閲覧できるSNSサービスです。幅広い年代に利用されています。
直接コミュニケーションを取ることはできませんが、動画の公開コメント機能でコメントを残してもらえば、コメントに返信する形でメッセージを伝えられます。
YouTubeはライブ配信をしたり、時間の長い動画をアップロードしたりできるため、企業の紹介や社内の雰囲気、イベントの様子などをより詳細に分かりやすく発信できます。
YouTubeを利用した採用活動には、JobTubeシリーズがおすすめです。
JobTubeシリーズでは、企業のリアルや日常を知れる動画を企画・制作。動画ならではの臨場感で働くイメージをリアルに想起させられます。「企業の新しい一面を動画で伝えたい」場合は、ぜひ活用を検討してください。
LinkedIn(リンクトイン)
「LinkedIn(リンクトイン)」は、ビジネス目的で、転職希望や転職情報を収集する目的の人も多く登録しているSNSです。海外ではLinkedIn経由の転職が多く、日本でも大手企業からベンチャー企業までさまざまな採用実績を持つメディアとなっています。
Facebookと同じく実名登録のため信頼性があり、幅広い年齢層の方に利用されています。ビジネスに特化したSNSであるためプライベートのSNSと使いわけているユーザーが登録している傾向です。
企業ページでは求人情報を掲載したり、ダイレクトにスカウトメールも送ったりできるため、企業の認知拡大から採用までの一連のプロセスをカバーするツールと言えるでしょう。
YOUTRUST(ユートラスト)
「YOUTRUST(ユートラスト)」は、一般の転職サービスではなかなか出会いにくい優秀な人材を採用できる可能性のあるキャリア系SNSと言われています。幅広い職種の人が仕事仲間などとのリアルなつながりを中心として利用しており、ユーザーの転職や副業意欲が可視化されています。
ユーザーの転職意欲の状況に合わせて、絞り込み機能やスカウト文面のカスタマイズ機能も活用できるため、気になる人をリスト化してアプローチすることができます。
SNS採用の導入手順

SNS採用を導入する際の具体的な手順は次のとおりです。
- 目的を決める
- ターゲットを決める
- SNSの媒体を選ぶ
- 運用フローを決める
- 配信コンテンツの方針を決める
- スケジュールやルールを決めて配信を開始する
まずはSNS採用によって実現したい目的を明確にします。「企業の認知度を高めて、応募者数を増やしたい」「就職・転職潜在層にもアピールしたい」「採用後のミスマッチを減らすためにリアルな職場環境を伝えたい」など、なぜSNS採用を導入するのかを明確にしておくことが大切です。
次にSNS採用でどのような人にアプローチしたいのか、ターゲット設定をします。採用したいターゲットはどのようなSNS媒体に集まっているのかを考え、ターゲットに対して訴求するのに適した媒体を選択しましょう。
媒体が決まったら、SNS運用担当者や更新頻度、運用マニュアルなど、具体的な運用フローを決めていきます。担当者は一人に負担がかかり過ぎないように、複数人にすると良いでしょう。
投稿をアップする際にも複数人が関わってチェックすることで、不適切だと捉えられる表現が含まれていないかをさまざまな視点から確認できます。
その後は、どのような内容のコンテンツを配信していくか方針を考えましょう。SNSでは一般的な求人広告や採用情報と異なり、よりカジュアルな情報発信が可能です。そのため、自社が伝えたい企業情報ばかりを配信するのではなく、ユーザーが知りたいことや興味・関心を持っていると考えられるようなコンテンツを考えると良いでしょう。
コンテンツの方針が定まったら、どのようなスケジュールで配信するか決めておきます。「時間があるときに」「必要に応じて」では更新頻度が下がったり投稿の間隔が空いたりしてしまうため、「何曜日の何時に誰がどのような内容のコンテンツをアップするか」といったように具体的な割り振りを決めておくと良いでしょう。
最後に、決めたスケジュールで配信を開始します。SNSはすぐに効果が出るものではないため、中長期的な視点で継続的に取り組みましょう。
SNS採用を成功させるためのコツ

SNS採用を成功させるためにおさえておきたいポイントは次の3つです。
- 自社のターゲットに合うSNSを選定する
- 情報は継続的に発信する
- 競合SNSの内容を分析する
それぞれのポイントを詳しく解説します。
自社のターゲットに合うSNSを選定する
SNS採用を行う際は、媒体選びが重要です。自社が採用したい人物像や求めるスキルを持った人材はどのような媒体に登録しているのかを把握し、ターゲットの利用率が高いSNSを選びましょう。
優れたコンテンツを定期的に配信しても、自社が採用したいと考える人材の目に触れなければ、求める効果は得られません。
そのため、まずは自社が求める人物像を詳細に設定しましょう。年代、スキル、経歴、背景などを想定した詳しいペルソナ設定を行い、媒体を選ぶことが大切です。
情報は継続的に発信する
SNSは情報が埋もれやすいため、継続的に最新の情報を発信することを心がけましょう。さまざまな人が日々新しい投稿を更新していくため、一度アップした情報は日に日に古くなります。
SNSは新着情報から上位表示される仕様のため、投稿が古くなるほど目に触れる機会が少なくなっていきます。そのため、定期的に更新を続けられるように、コンテンツ制作や運用フローに十分なリソースを確保しておきましょう。
運用面においては、特に人的リソースの確保が課題になりがちです。社内の人員が限られている場合、タスクの効率化を図ることが重要です。投稿のスケジュール管理や各種データの収集・分析ができる専門のツール、無駄な作業を削減できるワークフローツールやタスク管理ツールの活用も検討してみると良いでしょう。
また、媒体によっても理想的な更新頻度が異なります。たとえば、LINEが毎日届くと、通知がわずらわしく感じられてユーザーからブロックされてしまう可能性があります。そのため、媒体の特徴を理解して頻度を決めることが重要です。
競合SNSの内容を分析する
競合他社がどのようにSNS採用を行っているのかを知っておくことも大切です。同じ業界で同規模の競合他社がSNS採用を成功させているなら、配信コンテンツの方向性や運用方法が自社にとっても有効な可能性があります。
参考にして戦略が立てられるだけでなく、競合他社にはない自社の魅力を打ち出すこともできるでしょう。競合他社のSNS内容を分析し参考にすれば、より効果的で独自性の高いコンテンツを作ることができます。
SNS採用の効果測定とKPI
SNS採用は、継続的に運用を続けることで徐々に効果が高まる手法です。しかし、どれだけ投稿を増やしても、指標を持たずに運用していては成果を実感しづらく、担当者のモチベーション低下にもつながりかねません。
ここでは、効果測定に役立つ代表的なKPIや、実際にデータを分析して運用を改善する際のポイントを解説します。
効果測定に活用できる指標(KPI)の例
SNS採用の成果を客観的に把握するには、数値化できるKPI(重要業績評価指標)を設定しましょう。以下は代表的なKPIの例です。
これらのKPIを定期的にモニタリングし、設定した目標値や前月・前期との比較を行うことで、SNS採用の成果を数値で捉えることが可能となります。
1. フォロワー数・登録者数
SNS上で企業アカウントをフォローまたは友だち登録している人数を測定します。企業の情報に関心を持つユーザーの数を可視化でき、ブランディングや認知度向上の度合いを確認できます。
2. エンゲージメント率
投稿に対する「いいね」やコメント、シェア(リツイート)などの反応を合計し、投稿が閲覧された回数(インプレッション数)で割って算出する指標です。応募数に直結しづらい段階でも、投稿内容がターゲット層に刺さっているかを測る目安になります。
3. 応募率・採用率
SNS上での情報発信をきっかけに応募・内定につながった人数や割合を追跡します。応募フォームや面談予約ページへのリンクに専用のURLパラメータを設置することで、SNS経由の応募数を正確に把握できるでしょう。
4. CPA・CPS(コスト指標)
SNS運用で費用が発生する場合は、「応募1件あたりにかかった費用(CPA)」や「採用1件あたりの費用(CPS)」を計測します。コスト意識を持つことで、費用対効果を検証しやすくなり、無駄な支出を減らせます。
分析結果を踏まえた運用改善のポイント
KPIを設定してデータを集めたら、分析結果をもとに運用の改善を図りましょう。以下のポイントを押さえると、SNS採用の精度がさらに向上します。
KPIを設定してデータを可視化し、分析結果を踏まえて改善を繰り返すことで、SNS採用の施策をより高い精度で運用できます。費用対効果も測定しやすくなるため、社内での合意形成や予算獲得もしやすくなるでしょう。
1. ターゲット層とのギャップを再確認
思ったよりもエンゲージメント率が低い場合、投稿内容がターゲット層のニーズから外れている可能性があります。ペルソナを再設定し、興味を持ってもらえそうな話題(社内制度の紹介、社風が分かるエピソードなど)を増やすことが大切です。
2. 反応の良い投稿を徹底分析
いいねやコメント数が多かった投稿は、どの時間帯に、どんな切り口で発信したのかを詳しく振り返ります。ビジュアル要素(動画や画像)が強かったのか、社員の声が中心なのかなど、ユーザーが魅力を感じたポイントを把握し、同様の企画を継続することで効果を高められます。
3. 複数のSNSを比較検証する
企業の認知度やターゲット層によっては、InstagramよりもX(旧Twitter)のほうが反応が良い、といった違いが出ることも珍しくありません。媒体ごとにフォロワーの属性や特徴を分析し、反応の高いSNSに注力するのも有効な戦略です。
4. 継続的なPDCAサイクルを回す
分析結果から改善策を試し、またデータを見直すというPDCAサイクルを回し続けることで、投稿の質や採用効率は着実に向上します。短期間で結果が出なくても焦らず、中長期的な視点でSNS採用に取り組むことが肝要です。
SNS採用の成功事例
採用活動に SNS を活用する企業は、従業員数 1,000名以上の大企業から、50名以下の中小企業まで、多岐にわたります。また活用しているツールもさまざまです。
事例①:IT企業(従業員数 約7,000名)
大手 IT 企業の A 社は、採用広報において複数のメディアを駆使して情報発信を行っています。同社のオウンドメディアでは、社員のストーリーや仕事の裏側を紹介し、X やInstagram でもタイムリーな情報を発信しています。特に、Instagram では新卒採用者に向けたアルバイトの一日を動画にまとめるなど、親しみやすいコンテンツを展開し、採用ターゲット層への認知拡大に成功しています。
事例②:IT・人材会社(従業員数 約2,000名)
人材紹介事業などを主軸に様々な事業を展開するB社。採用ページでは社長の起業までのストーリーを漫画で紹介したり、YouTuberを使って広報をしたり、ユニークな策を多数行っています。またTikTok広告なども行い、あらゆる所からの認知–応募を狙って発信しています。
事例③:化粧品会社(従業員数 約50名)
東京都のメンズコスメブランドC社は、YouTube を活用した採用PRを行っています。公式チャンネルでは、製品開発の裏側や社員インタビュー、創業者の起業ストーリーや経営哲学を語る動画シリーズを公開。チャンネル登録者数は 7万人を超え、ブランドに共感する若手クリエイターからの応募が増加しています。
SNSでの採用広報について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
SNSを利用して効率的な採用活動を目指そう

現代において身近なコミュニケーションツールであるSNSを活用すれば、採用活動でもさまざまなメリットが見込めます。
企業の認知拡大から母集団の形成、採用情報の発信、説明会の案内やダイレクトスカウトまで、さまざまな採用プロセスで役立つため、今後導入する企業も増えていくと考えられます。
SNS採用を成功させるには、媒体ごとの特徴や登録しているユーザー層を理解して、採用課題の解決や求めるターゲットへの訴求ができる媒体を選ぶことが大切です。
現代社会にマッチしたSNSを活用して、効率的な採用活動を目指しましょう。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。