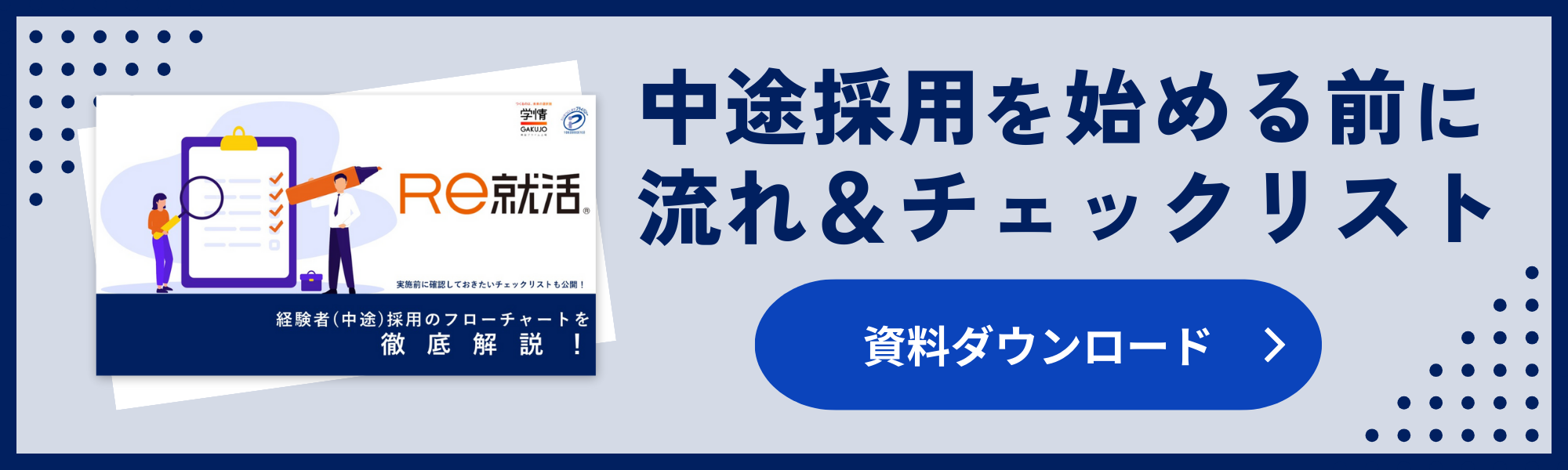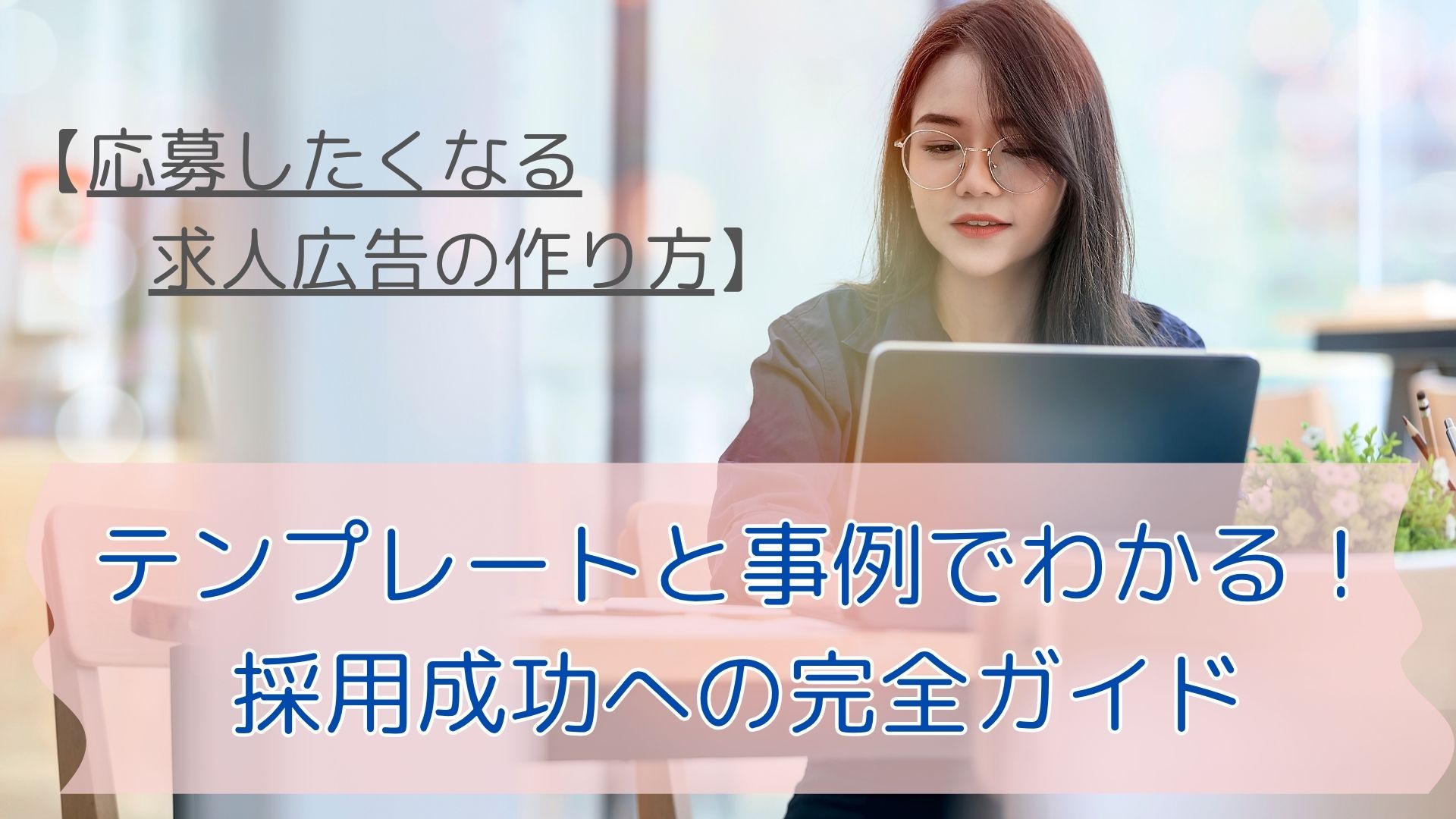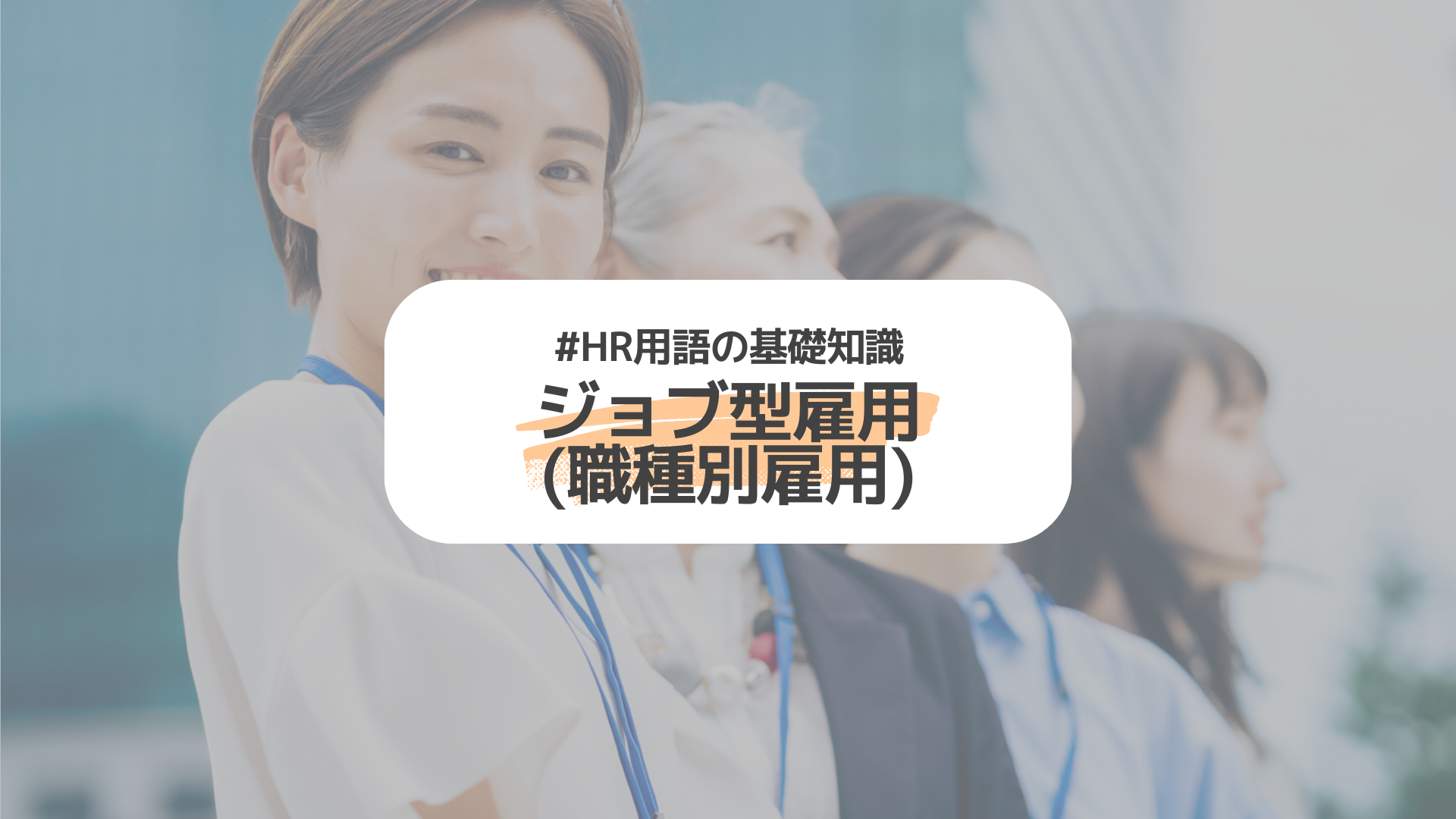
ジョブ型雇用(職種別雇用)は職務内容に適したスキルや経験を持つ人材を雇用する方法です。即戦力となる専門性の高い人材の確保や、早期離職・採用後のミスマッチ防止が期待できることから、近年導入する企業が増えています。
本記事ではジョブ型雇用の定義やメリット・デメリット、従来のメンバーシップ型雇用との違いや導入方法について詳しく解説します。
ジョブ型雇用が向いている企業と向いていない企業、導入するときの注意点、ジョブ型雇用を導入する際に役立つサイトも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ジョブ型雇用とは

ジョブ型雇用とは必要な職務内容に対して適したスキルや経験を持つ人材を採用する方法です。ジョブ型雇用の定義や従来のメンバーシップ雇用との違いを解説します。
職務内容に合わせた人材採用のこと
ジョブ型雇用は、その名の通り「仕事」の内容に合わせた人材採用方法です。企業の中で必要な部門や部署の職務内容に対して適したスキル・経験を持つ人を雇用します。
職務内容は「ジョブディスクリプション」と呼ばれる職務記述書によって明確に提示され、これに基づいて雇用契約を行うのがジョブ型雇用の特徴です。
職務記述書には、勤務地・勤務時間・職務内容・責任の範囲・報酬などの雇用条件が明記されており、この条件に合わせて働くことが求められます。したがって部署の異動や転勤、昇格や降格なども基本的には発生しません。
従来のメンバーシップ型雇用との違い
日本ではこれまで「メンバーシップ型雇用」が一般的な雇用方法でした。メンバーシップ型雇用とは、雇用企業の求める人物像に合致する人材を採用し、入社後に適性を判断して担当職務を決める方法です。新卒採用した人材を教育し、適性を見て各部署に配属するため、戦力になるまで時間がかかるという問題がありました。
一方、ジョブ型雇用は職務に対して既に適したスキルを持っている人材を採用するため、即戦力になるという点が大きな違いです。そのほかの違いについて、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を比較した一覧は次の通りです。
| ジョブ型 | メンバーシップ型 | |
|
業務の内容・ 範囲 |
|
|
| 評価基準 | 業務の成果 |
|
| 採用方法 | キャリア採用・新卒 | おもに新卒一括採用 |
| 採用基準 |
|
|
| 異動・転勤 | なし | あり |
|
キャリア アップ |
|
定期異動にともなって経験を積み、年齢や勤続年数に応じて管理職に昇格していく |
| 解雇 | 一般的には該当職務がなくなれば解雇 | 基本的には終身雇用で、解雇制限が厳しいためよほどの理由がなければ解雇しない |
ジョブ型雇用が注目されるようになった背景

ジョブ型雇用はアメリカやカナダ、ヨーロッパ諸国で主流の雇用方法です。もともと主体的にキャリアを築いていくジョブ型の働き方が一般的であったアメリカやヨーロッパ諸国に対し、日本はこれまでメンバーシップ雇用が主流でした。
しかし、ビジネスがグローバル化した現在、国際競争力を高めるためには専門性の高い人材が不可欠です。求めるスキルや経験、専門的な職務内容を明確に提示して、その条件に特化したスペシャリストを獲得する必要性が高まってきています。
また、2020年には日本経済団体連合会(経団連)が「経営労働政策特別委員会報告」において、従来のメンバーシップ型雇用の良さを取り入れながらもジョブ型雇用を推進していくべきだと提言しました。この提言により、従来のメンバーシップ型雇用や終身雇用制度の限界とジョブ型雇用の必要性に注目が集まったことも背景の一つです。
求職者側でも、職務内容や責任の範囲、求められている仕事や評価が明確であるジョブ型雇用に魅力を感じる人が増えてきています。多様な働き方や仕事に対するさまざまな価値観に対応できるジョブ型雇用は、働き手側からのニーズも高まっていると言えるでしょう。
ジョブ型雇用を導入するメリット・デメリット

現代のニーズや働き方に合っているジョブ型雇用ですが、導入した場合にはどのようなメリットやデメリットがあるのでしょうか。企業から見た場合と求職者から見たメリット・デメリットをそれぞれ詳しく解説します。
ジョブ型雇用のメリット
ジョブ型雇用のメリットを見ていきましょう。
求職者にとってのメリット
ジョブ型雇用は自分の得意分野に特化して能力を発揮できる働き方です。求職者からすると、得意分野での業務になるため成果を上げやすく、評価が高まることでモチベーションアップにもつながります。
また、特定分野に限定した業務を行うことによって、より専門性や生産性が高まり、仕事そのものがスキルアップのための手段となるでしょう。
2022年のRe就活キャンパスによるアンケート調査では、2024年に大学・大学院を卒業する学生の7割が「ジョブ型雇用に興味がある」と回答しています。その理由は「どんな仕事をするかが明確だから」という回答が58%、次いで「配属される部署が決まっているから」が42.3%、「学んだことやスキルが活かせるから」が30%となりました。
「配属ガチャを防ぎたい」「仕事内容が明確だとミスマッチも防げると思う」「スキルを磨き専門性を高めたい」といった声が見られ、ジョブ型雇用は求職者からも求められている傾向が高いことがわかります。
※出典:2024年卒学生の就職意識調査(ジョブ型) 2022年4月版(https://service.gakujo.ne.jp/jinji-library/report/220421/)
企業にとってのメリット
企業にとってのメリットは、専門性の高い人材や即戦力となる人材を迅速に採用できることです。即戦力となるスペシャリストを確保することで、さらなる業務効率化や生産性の向上、競合に対する優位性の獲得が狙えます。
また、雇用条件が明確であるため、採用後のミスマッチによる早期離職を防げることもメリットです。業務の成果に応じた正当な評価もできるため、従業員のモチベーションアップも図れます。
ジョブ型雇用のデメリット
ジョブ型雇用のデメリットを解説します。
求職者にとってのデメリット
ジョブ型雇用では、担当部署や該当する業務自体がなくなった場合、失職する可能性があります。従来のメンバーシップ雇用では、担当部署や業務がなくなっても他部署への異動や転勤などによって失職することはありませんでした。
しかしジョブ型雇用では、「仕事」に対して人材をつけるため、その業務がなくなったり、求められる業務の水準に達していなかったりする場合には離職となるケースがほとんどです。
また、常に専門分野における成果を期待されるため、自己研鑽やスキルアップのための努力が欠かせません。これらが負担に感じる場合はデメリットとなるでしょう。
企業にとってのデメリット
ジョブ型雇用の場合、ほかに好条件の企業があると転職されてしまう可能性があります。専門性の高いスペシャリストであるからこそ転職のハードルが低く、人材が流出しやすいのはデメリットと言えるでしょう。
また、ほかの部署で人手が足りなくなったとき、異動または転勤といった流動的な対処が困難です。会社都合で職務内容を変更できないため、別の部署で人手が必要になっても、基本的には新たに採用を考えなければならない点に注意しましょう。
ジョブ型雇用では専門性が高い業務を限定的に行うため、「この仕事はあの人にしかわからない」といったように業務が属人化してしまうケースもあります。
ジョブ型雇用が向いている企業・向いていない企業

ジョブ型雇用は特性上、向いている企業と向いていない企業があります。それぞれ詳しく解説していきます。
ジョブ型雇用が向いている企業
スキル重視で専門性の高い業務を任せられる人材を探している企業はジョブ型雇用に向いていると言えます。たとえばIT、エンジニア、デザイン、クリエイティブ系などの企業です。
チームで仕事をするというより個人のスキルが重視されるような場合や、時短勤務や在宅勤務、子育て・介護との両立などさまざまな働き方が選択可能な企業にも良いでしょう。
ジョブ型雇用が向いていない企業
一人にさまざまな業務を経験させて幅広いスキルを身につけさせたい場合や、ジョブローテーションなどで多角的な視野を持った管理職候補を育成したい企業には、ジョブ型雇用は向いていません。チームでコミュニケーションを取りながら一つの目標を達成させたいというケースも、ジョブ型雇用よりメンバーシップ雇用のほうが合っています。
また、ジョブ型雇用では専門的な業務に特化して働く分、業務が属人化しやすい特徴があるため、従業員全員が同程度のスキルを持つことや同じ業務をできるようにしたい企業には向いていないと言えるでしょう。
自社にジョブ型雇用を導入する流れ

ジョブ型雇用を導入する際は次のような流れで進めることになります。
- 業務内容と範囲の把握
- 職務記述書(ジョブディスクリプション)作成
- 給与・評価基準の決定
- 社内への周知
一つずつの手順を詳しく見ていきましょう。
1.業務内容と範囲の把握
ジョブ型雇用を導入する際は、まず業務の内容を明確にする必要があります。現場の状況を整理し業務内容や任せたい業務範囲、業務の目的や責任などを把握しましょう。
現場にとってどんなスキルを持った人が必要なのかをハッキリさせず、漠然としたまま採用活動を行うと想定していた結果につながらない可能性もあります。そのため、現場の管理者や実際に該当職務を行っている人がいれば、直接ヒアリングをして何が必要なのかを明確にすることが大切です。
その上で、求めるスキルや経験など条件を明確化していきます。採用後のミスマッチを防ぐため、「どこからどこまでを任せるのか」を明文化し、給与や評価方法、勤務地や時間などの雇用条件も決めていきます。
2.職務記述書(ジョブディスクリプション)作成
業務内容や範囲、雇用条件が決まったら、職務記述書(ジョブディスクリプション)を作成します。職務記述書は、職務内容や職務要件を記載した書類です。採用活動や評価の際に使われます。
職務記述書に記載されるおもな項目は次の通りです。
- 職種・所属
- 職務内容・職務目的
- 職務責任・職務範囲
- 必要なスキル・知識
- 必須資格・優遇資格
- 人物特性
- 会社概要
- 給与・勤務地・勤務時間
- 待遇・福利厚生
企業や職種によって項目の詳細は異なりますが、このほかにも入社後のポジションである職務等級や上司となる人の名前、部下の人数なども記載します。
3.給与・評価基準の決定
これまで年功序列型の給与・評価体制をとってきた企業は、制度の見直しが必要となります。ジョブ型雇用では、任せる職務内容や役職、期待する成果などに合わせて給与を決定する必要があるため、成果に応じた定量的な評価をする基準を細かく設定しましょう。
評価方法や評価基準が曖昧な場合、求職者が不安を感じる可能性もあります。入社してから不満を持って「話が違う」などのトラブルにつながりかねません。採用前にしっかりと評価制度を確立しておく必要があります。
4.社内への周知
最後にジョブ型雇用を導入することを社内で周知します。十分な理解が得られないままに進めてしまうと、ジョブ型雇用と既存のメンバーシップ雇用の従業員の間で不公平感が生じてしまう可能性があります。
従業員同士の摩擦や不満の高まりによる離職など、新たな問題の発生が懸念されるため、既存の従業員に対して導入の意図などをしっかり説明することが大切です。既存のメンバーシップ型雇用の従業員と協働できる環境づくりも行いましょう。
メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用を導入する際は、十分な準備をしてから導入することを心掛けましょう。
自社にジョブ型雇用を導入するときの注意点

ジョブ型雇用を導入する際には、前述したとおり評価制度の見直しや追加業務の依頼に注意する必要があります。また、既存のメンバーシップ型雇用の従業員との連携にも配慮しなくてはなりません。ジョブ型雇用を導入する際に気をつけるべきポイントを解説します。
評価の透明性・正当性の担保
ジョブ型雇用は従来のメンバーシップ雇用と評価方法が異なります。メンバーシップ雇用ではおもに勤続年数やチームへの貢献度、人物像や上司との関係性などが評価に関わりますが、ジョブ型雇用ではそれらに関わらず、成果のみで評価を行うのが一般的です。
その分、評価方法や基準を明確に示しておくことが重要になります。ジョブ型雇用の場合結果が出せなければ解雇も起こり得るため、評価の透明性や正当性を常に担保しておかなければなりません。
あとになって不満やトラブルに繋がらないよう、採用時に評価方法や評価基準を提示して、細かい部分の確認やすり合わせなどを行いましょう。
また、メンバーシップ型雇用の従業員にもジョブ型雇用のような成果による評価制度を導入すると、混乱や「納得できない」といった不満が発生する可能性もあります。それぞれの雇用方法や担っている役割に応じた評価制度に配慮する必要があることを念頭においておきましょう。
追加業務内容の決定は慎重に行う
採用後に、当初の予定より忙しくなってしまい、追加業務を任せたい状態になることもあるでしょう。しかし、追加業務を依頼する際には注意が必要です。最初の求人内容を逸脱した業務を依頼した場合は契約違反になるケースもあります。
はじめに職務記述書を作る際、業務を限定し過ぎてしまうと、採用後にあれもこれもと追加することになりかねません。あとから追加業務が発生しないよう、業務範囲の設定は慎重に検討して行いましょう。やむを得ず追加業務を依頼する際も、内容の決定は対象の従業員とよく話し合って行ってください。
従業員間のコミュニケーションを円滑にできるようにする
これまでメンバーシップ型雇用を行ってきた企業の場合、ジョブ型雇用と従来のメンバーシップ雇用の従業員の間でトラブルが発生する可能性があります。
なぜなら、専門業務の成果を追求するジョブ型雇用の従業員と、企業全体やチームに貢献することを考えるメンバーシップ型雇用の従業員が一緒に働くことになるためです。たとえば両者の間にコミュニケーションエラーが起きて、関係性が悪化することも考えられます。
既存の従業員が、ジョブ型雇用の従業員の担う役割や求められている成果を把握し、連携を取れるような環境を考えましょう。
ジョブ型雇用で専門性の高い人材を確保しよう

ジョブ型雇用は、専門性の高い人材を迅速かつ効率的に確保できる採用方法です。注意点もあるため、十分な準備をしてから導入しましょう。
2024年卒業予定の大学生・大学院生を対象に行ったアンケート調査では、ジョブ型雇用に興味を持っている学生が7割を占め、「ジョブ型のインターンシップがあれば参加したい」という声も7割を超える結果となりました。
終身雇用制度が当たり前ではなくなってきた現在、企業にキャリア形成を委ねるのではなく、主体的にキャリアを築いていきたいという学生の意向が表れています。自社の求める人材や今後の成長に向けて、ジョブ型雇用という手段も選択肢に入れておくと良いかもしれません。
ジョブ型雇用を導入して「狙った職種や学部の人材を確保したい」と考えているなら、「Re就活キャンパス」がおすすめです。Re就活キャンパスは、 、会員数60万人を超えるダイレクトリクルーティングサイトです。
ジョブ型雇用を導入したばかりの場合やダイレクトリクルーティングが初めての場合も、充実した機能で徹底支援します。ぜひご相談ください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。