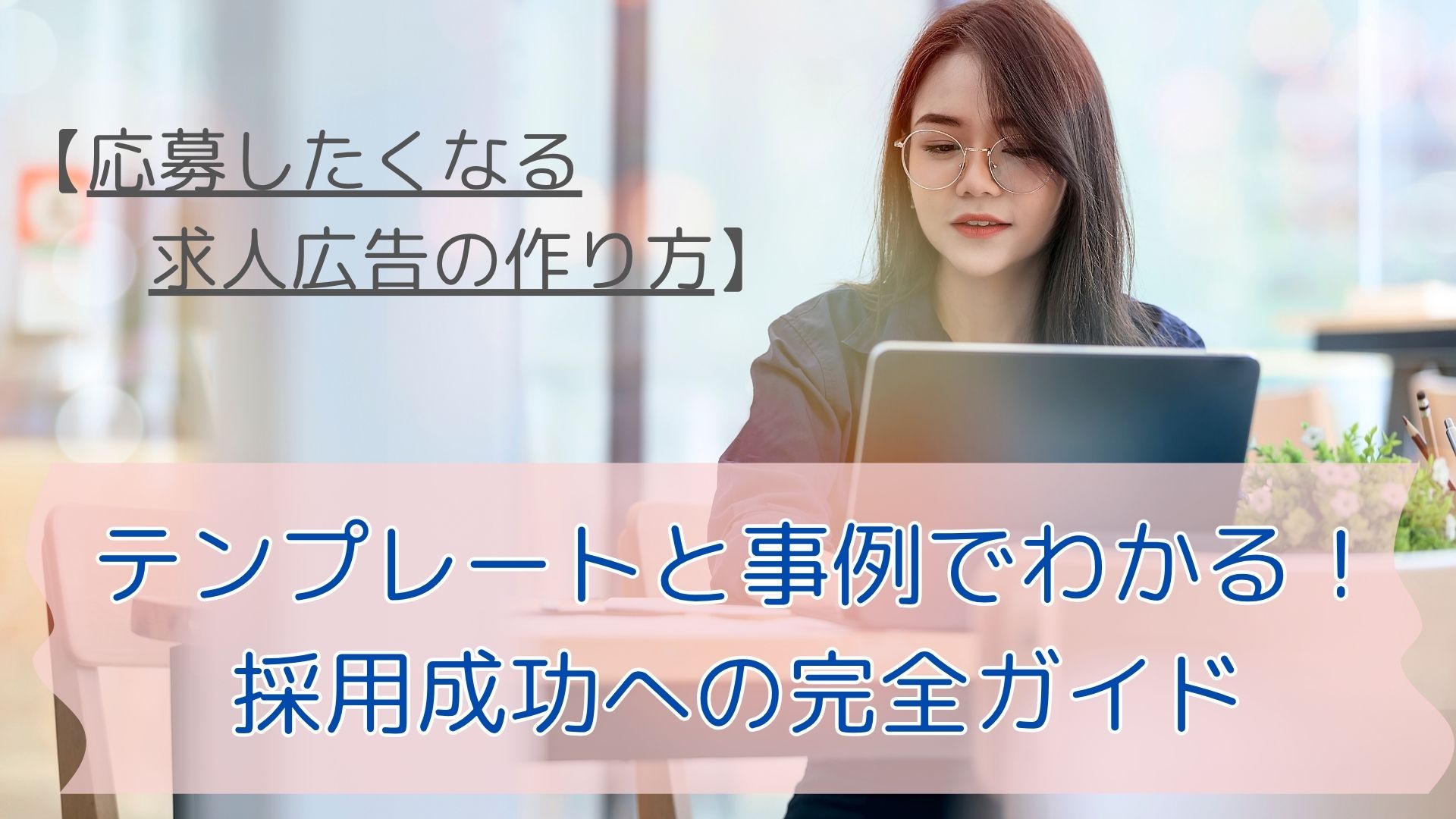採用ブランディングは、近年の企業の採用戦略において注目されるキーワードとなっています。自社において、定着率の高い優秀な人材を計画的に獲得したい場合、企業の採用戦略にブランディング要素を取り入れることは非常に重要です。
この記事では、採用ブランディングをテーマに、その目的や導入するメリット、実務上での具体的な進め方を解説します。具体的にどのようなアプローチを取れば良いのか、どんな成功例があるのかも紹介するので人事担当者の方はぜひ参考にしてください。
採用ブランディングとは
まずは、採用ブランディングという言葉そのものの意味を知りましょう。定義と具体例を参考に、採用ブランディングの意味を解説します。
採用ブランディングの定義
採用ブランディングは、企業が優秀な人材を採用するための戦略的な取り組みを指す言葉です。採用市場での存在感を発揮するため、「自社で働くこと」そのものをブランド化するための手法といえます。
ブランド化においては、企業が自らの持つ文化や価値観を明確に伝え、求職者の印象に残る企業イメージを形成することが求められます。理想像やビジョンの提示だけでなく、従業員の人柄や職場の雰囲気などを通じたリアルな魅力の発信も欠かせません。
たとえば、「この会社で働くことには価値がある」「この会社で働くことが夢である」というイメージを、採用したいターゲットの人材層および周りのステークホルダーから抱いてもらうことを目指しましょう。また、「この会社は●●のようなイメージ・評判があるから、△△のような特徴を持つ人が向いている(もしくは向いていない)」と認知させることができれば、その会社の採用ブランディングは成功といえるでしょう。
その結果、自社が求めるカルチャーとスキルを有した人材の確保を実現でき、企業の業績を高めることができるのです。
採用広報・採用マーケティングとの違い
採用ブランディングと採用広報・採用マーケティングの違いは次の通りです。
|
採用ブランディング |
採用広報 |
採用マーケティング |
|
|
目的 |
企業ブランドの構築 |
優秀な人材の獲得 |
求職者の行動を分析し、採用につなげる |
|
施策 |
自社の魅力や価値を積極的に発信する |
働く環境や既存社員、働き方などの情報を発信し、企業の魅力を求職者に伝える |
求職者のニーズや行動パターンを分析し、戦略的な施策を実行する |
|
効果 |
・求職者とのマッチング精度の向上 ・定着率の向上 |
・応募数の増加 ・企業認知度の向上 |
・応募数の増加 ・求職者とのマッチング精度の向上 |
採用ブランディングは、採用における企業ブランドを構築することです。企業ブランドを高め、求職者に「この企業で働きたい」と思ってもらうことを目指します。
これに対して、採用広報は、自社に興味を持ってもらうための情報を発信する取り組みのことです。採用広報を行うことで、採用ブランディングの構築を図ります。
採用マーケティングは、マーケティングの考え方や手法に基づき、求職者の行動を分析して採用につなげることです。採用マーケティングを実施し、効率的な採用広報につなげます。
採用ブランディングが注目される背景
採用ブランディングが注目されるようになった背景には「少子高齢化による人手不足」や「価値観の多様化とSNSの普及」などの要因があります。それぞれについて詳しく解説していきましょう。
少子高齢化と労働力不足
日本の生産年齢人口は、1995年の8716万人をピークに減少傾向にあります。2021年には7450万人でしたが、2050年には29.2%減の5275万人まで落ち込むと予測されています。
労働力不足に伴い、採用市場では人材獲得競争が激化し、採用は一層難しくなっています。優秀な人材を確保するには、独自の魅力や強みを効果的にアピールし、競合他社との差別化を図ることが不可欠です。
※参考:内閣府「令和4年版高齢社会白書」
価値観の多様化とSNSの普及
株式会社学情の調査によると、社会人経験3年未満の第二新卒の転職理由で最も多かったのは「もっとやりがい・達成感のある仕事がしたい」でした。
この結果から、第二新卒採用においても仕事のやりがいや自身の成長を重視する傾向が強く、就職活動や転職活動に対する価値観が多様化していることがうかがえます。
加えて、SNSの普及により、求人情報だけでは伝えきれない情報を、SNSを通じて発信する動きが活発になっています。
※参考:株式会社学情「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(転職理由)2024年9月版」
採用ブランディングの目的
採用ブランディングは、おもに次の2点を目的に実施されます。
- 求職者の自社に対するイメージアップ
- 今後の採用市場における人手不足対策
それぞれの詳細を解説します。
求職者の自社に対するイメージアップ
採用ブランディングは、求職者に対し企業の魅力や理念を伝える手段として効果的です。自社の理念や入社のメリットを発信することで、求職者との間に共感や信頼を育てることができます。
また、採用ブランディングは求職者の注目を集める手助けにもなります。相性の良い求職者の目も引きやすくなり、より自社とマッチした人材を探しやすくなるでしょう。
今後の採用市場における人手不足対策
現代の採用市場では人手不足のリスクが高まっており、対策として採用ブランディングを行い求職者の数と質を確保しようという流れが出てきています。
帝国データバンクが2025年1月に全国の1万1014社を対象に行った調査によると、従業員の人手不足を感じている企業は全体の53.4%に上り、コロナ禍(2020年4月)以降で最も高くなりました。
おもな原因は少子化による労働人口の総数の減少にあり、さらに業界ごとの問題が重なっています。たとえば、IT業界では需要が拡大している一方で、供給が追いついていません。
また、飲食業界や宿泊業界ではアフターコロナの急回復にもかかわらず、人手が十分に戻っていない状況です。
今後の採用市場は、ますます「売り手市場」となることが予想されます。求職者に対して採用したい企業の数が多い「売り手市場」のなかで他社との差別化を行うためにも、採用ブランディングの重要性はより増していくでしょう。
※参考:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年1月)」
採用ブランディングを構築する方法

採用ブランディングを構築する方法はさまざまです。効果を最大化するには、企業の採用課題に適した方法を選びましょう。
採用ブランディングを構築する主な方法は次の通りです。
- 採用サイトを制作する
- SNS・ブログを運用する
- イベント・セミナーを開催する
- 採用動画・映像コンテンツを制作する
- 採用担当者・面接官へのトレーニングを実施する
- 採用コピー(キャッチコピー)の作成
- その他の採用ブランディング施策
それぞれ詳しく解説します。
採用サイトを制作する
採用サイトとは、採用活動に特化したホームページのことです。コーポレートサイトとは異なり、企業のビジョンや社員インタビュー、社内イベントの様子など、独自のコンテンツが発信できます。これにより、求職者に自社の価値を効果的に訴えかけ、共感を得やすくなります。
また、企業ロゴやイメージカラー、フォント、写真などの情報からも、企業の個性やカルチャーを印象づけることが可能です。
SNS・ブログを運用する
SNSやブログは、大勢の求職者や、若い世代の求職者に向けた情報発信に適した採用ブランディングの手法の一つです。企業の日常や業務の魅力などを定期的に発信し、長期的に印象を深めることができるでしょう。
合同企業セミナー
合同企業セミナーは、求職者に直接企業の魅力や強みをアピールできるイベントです。実際に現場で働く社員と求職者が交流することで、企業文化や組織の雰囲気を伝えやすくなります。
人事部以外の社員が参加する場合は、自社の採用ブランディングを熟知した人材を選びましょう。また、事前に採用ブランディングについてしっかりとすり合わせを行うことも大切です。
採用動画・映像コンテンツを制作する
近年はYoutubeなどの動画サイトで情報収集を行う人も多くなっているため、動画コンテンツによる採用ブランディングも有効です。従業員や職場の雰囲気、業務内容を文章より具体的に伝えることができます。
採用担当者・面接官へのトレーニングを実施する
企業の情報を「発信する」という側面で見た場合、会社説明や面接を行う採用担当者も情報発信源の一つといえます。そのため、採用において企業が発信していきたいメッセージを明確にし、採用担当者が適切に情報を発信できるように事前に教育をしておくことは重要です。
たとえば採用面接において、自社の面接官が採用媒体で発信している情報と異なる内容を求職者に説明してしまうと、自社のブランドイメージに影響を与えてしまいます。
そのため、採用担当者が企業の重要な情報発信源であることを認識し、適切な説明ができるように社内の体制を整えておくようにしましょう。
採用コピー(キャッチコピー)の作成
採用コピーとは、求人広告や企業の採用ページ、採用イベントのパンフレットなど、採用関連のメディアやツールに使用される短い文章やフレーズのことです。採用コピーは、企業の価値観や求める人材を簡潔に伝える手段となります。
採用コピーを作る際は、ターゲットを明確にして、シンプルでわかりやすいものを目指しましょう。他社と差別化できる、独自性を意識することも重要です。正確かつ魅力的に企業の特徴を伝えるコピーを作成し、外部に発信することで、理想的な人材の採用につながります。
インターンシップ/オープン・カンパニー
インターンシップやオープン・カンパニーは、企業文化や働き方を体験してもらえる貴重な機会です。実際に仕事の様子を見たり、業務を体験したりすることで、学生に企業の印象を強く残すことができます。
なお、2025年卒の学生を対象としたインターンシップから、実施ルールが変更されました。詳細はこちらの記事をご参照ください。
採用ブランディングのメリット・期待できる効果
採用ブランディングを実施することによって、次のメリットや効果を期待できます。
- 自社の認知度の向上
- 採用に関する一貫した情報発信
- 求人における応募者数の増加
- 採用ミスマッチの防止
- 採用コストの削減
- 既存従業員のモチベーション向上
それぞれの詳細を解説します。
自社の認知度の向上
採用ブランディングを通じて自社の強みや魅力を発信することで、企業の認知度を向上させることができます。知名度が高まれば高まるほど潜在的な志望者が増え、相性の良い人材からの応募が期待できるようになるでしょう。
また、求職者に対する企業価値だけでなく、サービスや商品の価値が高まる副次的な効果も期待できます。取引相手に従業員が満足して働ける会社であると認知されれば、事業に対する信頼や理解も得やすくなります。
採用ブランディングは採用面だけでなく、事業の成績にも作用する取り組みといえるでしょう。
採用に関する一貫した情報発信
採用ブランディングでは、自社が求める人材像や自社の魅力を整理し、明確化することが欠かせません。採用担当者は発信する情報に一貫性を持たせやすくなり、自信を持って求職者にアピールできるようになるでしょう。
企業の目標や方針が明確に定まっていることを求職者に伝えられれば、「しっかりとしたビジョンのある企業だ」「自信を持って発信をしている」といった好印象を与えることができます。
求人における応募者数の増加
採用ブランディングによって求人の応募者数の増加を期待できます。事業内容や社風などの魅力を伝え求職者の興味を引きつけられれば、応募者総数は増加し、より多くの母集団から優秀な人材を厳選できます。
応募者数を増やすためには、ただ自社を知ってもらうだけでなく、他社との差別化を行う必要があります。求職者が候補の企業を比較したときに「この会社ならでは」と感じられる要素を採用ブランディングで押し出していきましょう。
たとえば、雇用条件や優遇制度だけでなく、企業文化や働く環境などの要因で他社との差別化を図れます。システムや制度面に加え、自社のなかに存在するヒトや気風に起因する魅力を知ってもらうことも大切です。
採用ミスマッチの防止
採用ブランディングは自社の価値観やビジョンを理解した求職者の応募を促せるため、入社後のミスマッチを防止できます。企業側・求職者側の両方が、お互いの性質に納得した状態で採用できるようになるでしょう。
新入社員と企業のミスマッチは、入社後すぐの退職の原因となります。スキルが企業と合わない、感性の相性が悪いなど、ミスマッチの原因はさまざまです。
しかし、あらかじめ企業に合った人材のイメージ像を提示できれば、適切な人材からの応募を期待できるようになります。企業側の合否判定にも「自社が行った採用ブランディングに適しているか?」という視点を加え、採用基準を明確化できます。
また、採用ブランディングに成功すれば、自社に愛着を感じて入社する人材を増やせます。新入社員の定着率を向上させ、短期間での退職者数をおさえることもできるでしょう。
採用コストの削減
採用ブランディングには将来的な採用コストの削減が期待できます。
新たな採用戦略を取る以上、短期的にはコストをかけて取り組むことになります。しかし採用市場におけるブランドが形成されれば、求職者が自発的に自社を選択してくれるようになるため、必要以上の広告や人材紹介を使用する必要がなくなります。
採用ブランディングが成功していれば、自社の名前そのものが強い力を持ちます。求人開始と同時に、求職者からの注目を集められる可能性が高まるでしょう。短期間で効率良く人材を確保できるため、社内の採用業務にかかるコストをおさえられます。
既存従業員のモチベーション向上
採用ブランディングでは自社の強みや魅力を整理・発信する必要があります。企業文化や職場の雰囲気を発信する採用ブランディングは全社的な取り組みとなるため、会社全体が企業理念やビジョンなどを再認識する機会にもなります。
自社の目指す理想やこれまでに達成した実績は、求職者へのアピールとなるだけでなく、自社の従業員自らが誇らしさを感じることのできるシンボルにもなります。自社への愛着が高まり、業務におけるモチベーションの向上にも寄与できるでしょう。
採用ブランディングには、意欲が高く自社に共感する人材を集めるとともに、既に在籍している従業員の愛社精神や肯定感を高める効果もあると言えます。
採用ブランディングの課題
採用ブランディングを適切に実施できれば大きなメリットを得ることができますが、実施にあたっての課題も存在しています。おもに、次の2点が代表的な課題といえるでしょう。
- 効果が出るまでに時間がかかる
- 社内全体で取り組む必要がある
効果が出るまでに時間がかかる
採用ブランディングには即効性がなく、中・長期的視野で取り組む必要があることを理解しておきましょう。一般的に、採用ブランディングの効果が現れるのは1~3年後とされています。
通常のマーケティングと同様に、ブランドはすぐに形成されるものではありません。自社の価値観や文化を、求人市場に浸透させるには時間がかかります。継続的な情報発信と更新を行い、存在を意識してもらいやすくする必要があるでしょう。
社内全体で取り組む必要がある
採用ブランディングは人事担当者だけでなく、社内全体で取り組むものです。求職者に提示するコンセプトやメッセージを社内で共有し、現場でのギャップが生じないように認識を一致させる必要があります。
足並みを揃えないまま採用ブランディングを行うと、実態と異なるメッセージを求職者に伝えてしまう恐れがあります。採用に成功しても入社後に悪印象を与え、ミスマッチや退職といったマイナス効果につながってしまうでしょう。
採用ブランディングの進め方

採用ブランディングを実際に進める場合には、次の手順に沿って行うようにしましょう。
- 採用ターゲットを明確にする
- 自社を分析し「魅力」を整理する
- コンセプトを決めキャッチコピーを考案する
- 情報を発信するメディアを決定する
- 運用の開始・検証・改善
採用ブランディングは経営陣や人事担当だけが進めるものではありません。価値観や認識を統一させるために社内全体で取り組む必要があります。採用ブランディング実施の意図やプロセスを広く共有し、協力を得られるようにしましょう。
1.採用ターゲットを明確にする
まずは採用ターゲットを明確にしましょう。スキルや経験、人物像を仮定し、ターゲットを絞り込みます。仮定された人物の行動や意思の傾向を考察し、興味関心を惹きつけられるメッセージを研究・作成しましょう。
人物像の仮定を行う際には、実在性(リアリティ)を感じられる設定を行うことが有効です。履歴書に記載する能力・経歴面の情報はもちろん、理想の働き方や趣味、家族構成など、生活感を感じられる要素を加えることが大切です。
人物像を仮定することで、「どのようなメッセージに興味を持つのか?」「どの媒体ならメッセージを見てくれるのか?」というシミュレーションが行いやすくなります。明確になったターゲットは、今後の採用ブランディングの軸となるでしょう。
2.自社を分析し「魅力」を整理する
続いて、採用市場における自社の立ち位置を把握しましょう。競合他社や、類似した条件を提示している企業のなかで「自社にしかない魅力は何か?」と自己分析を行う必要があります。
自社に対する分析と魅力の発見は、採用ブランディングを成功させるための鍵です。会社の文化、仕事の内容、職場環境などを軸に、自社の魅力をピックアップしていきましょう。
分析の過程では、口コミサイトでの評価やフィードバックにも目を向けることが大切です。ネガティブな内容が見られた場合には、求職者の不安や心配を和らげる情報発信を行いましょう。
しかし、自社の魅力をどのように発見・発信すれば良いのかわからないという人も少なくはありません。参考となる魅力の例を、会社・仕事・環境の三軸から紹介します。
会社の魅力
会社組織そのものの魅力では、おもに次のような情報を提示することが有効です。
- 今後のビジョン
- 経営者の理念
- 業務の社会的意義
- 独自性
これらの情報は、自社にしか発信できないメッセージを伝えることができます。他社と差別化を図れる優位性を意識してピックアップするようにしましょう。
仕事の魅力
社内で行う仕事の魅力は、おもに次の要素から発信しましょう。
- 募集するポジションと裁量
- 仕事の特徴
- 具体的な業務内容
- 業務を通じて身につくスキル
できるだけ客観的な視点から、明確な魅力をあげることが大切です。従業員の声などを通じて提示できれば、求職者の信頼を高められるでしょう。
環境の魅力
職場環境の魅力は、次の要素から発信できます。
- 社風
- 先輩・同僚
- 社内制度・労働条件
- 福利厚生
- ワーク・ライフ・バランス
社内で一緒に働く先輩・同僚が活躍している様子や社内の雰囲気などをピックアップして紹介することが大切です。同時に、給与や福利厚生などの待遇面の魅力もあげていきましょう。
3.コンセプトを決めキャッチコピーを考案する
採用ブランディングでは一貫性が大切です。採用コンセプトを決定し、ターゲットの興味や共感を得るキャッチコピーを作成しましょう。決定されたコンセプトとキャッチコピーを中心に、採用ブランディングに取り組むことになります。
コンセプトやキャッチコピーの決定では、企業の理念や製品・サービスの特徴などを考慮して、自社の特色を表現することが重要です。たとえば、製造業であれば、製品やものづくりを通して実現したいビジョンや未来を提示することが有効でしょう。
コンセプトは求人広告で打ち出す文章や画像などのコンテンツの方向性を決定し、キャッチコピーは取り組み全体の要約となります。ターゲットに響く言葉や印象を意識して、明確な表現を盛り込むようにしましょう。
4.情報を発信するメディアを決定する
ターゲットとなる層に適したメディアを選定することは、採用ブランディングを成功させるための鍵となります。自社サイトや求人媒体、イベントポスターやSNSなどから、ターゲットの注目を集めやすいメディアを選ぶことが大切です。
たとえば、20代の応募者をターゲットとする場合、世代の利用率が高いSNSや、新卒向けのイベントを活用することが効果的です。
また、採用ブランディングでは継続的な発信も重要です。求人サイトや自社ブログ、各SNSなど、長期運用に向いたメディアも利用しましょう。
5.運用の開始・検証・改善
準備が整い次第、採用ブランディングの情報発信をスタートします。
コンセプト・キャッチコピーの一貫性を維持し、常にターゲットの存在を意識した発信を心がけましょう。また、求人サイトの口コミやアンケートサイトを定期的にチェックし、必要であれば修正をかけることも大切です。
内定者の十分な確保や一定期間の経過により、採用選考が終了しても、採用ブランディングは終わりません。自社が実施した採用ブランディングの効果を検証し、次の採用活動に向けての改善を行いましょう。
社会情勢や市場、求職者のニーズの変化や競合他社の動向に応じて、採用ブランディングのやり方も柔軟に見直す必要があります。採用活動のたびに検証と改善を行い、長期にわたるブランドの確立を実現しましょう。
採用ブランディングに取り組む際のポイント7つ
採用ブランディングに取り組む際のポイントは次の通りです。
- 共通認識の醸成と協力体制の整備
- 顧客向けブランディングとの違いをおさえる
- ターゲットの価値観に響くメッセージを設計する
- 誇張表現は避ける
- 採用ブランドの一貫性を保つ
- PDCAサイクルを回し改善を繰り返す
- 長期的な視点で効果検証する
それぞれの詳細を解説します。
共通認識の醸成と協力体制の整備
採用ブランディングを成功させるには、ブランドイメージを全社で共有することが大切です。ブランドイメージと実情に乖離があると、採用に至ってもミスマッチが生じ、結果として選考・内定辞退や早期退職を招く可能性があります。
加えて、社員にも形だけのブランドイメージという印象を与え、不信感につながりかねません。採用ブランディングを行う際は、実状に適したブランドイメージを策定し、全社で共通認識を醸成しましょう。
顧客向けブランディングとの違いをおさえる
採用ブランディングと顧客向けブランディングを混同しないようにしましょう。どちらも社外に発信するアウターブランディングとはいえ、採用ブランディングはあくまで求職者に向けて情報発信する際に用いる戦略です。
顧客向けブランディングでは、商品やサービスの価値を伝え、購入や利用を到達点とします。しかし、採用ブランディングで伝える情報は、自社そのものの企業文化や理念、ビジョンで、目標は優秀な人材の採用です。
たとえば、食品会社の顧客向けブランディングでは商品のおいしさを強調しますが、採用ブランディングではおいしい商品そのものを作る仕事の価値や、実現のために必要なスキル、姿勢をアピールする必要があります。
採用ブランディングと顧客向けブランディングの違いを理解し、自社の求めたい人材に合った情報を発信できるようにしましょう。
ターゲットの価値観に響くメッセージを設計する
ターゲットの価値観に響くメッセージを作り、それが伝わる採用プロセス設計することをTMP設計(Targeting Messaging Processingの略)といいます。キャッチーなコピーにこだわる必要はなく、自社が持つ独自の魅力や強みが伝わりやすいように工夫しましょう。
さらに、そのメッセージを採用プロセスのなかで、どのように伝えるかも重要なポイントです。たとえば、採用動画や会社説明会のスライドに盛り込んだり、面談や座談会でメッセージに沿った会話展開を意識したりする方法などが挙げられます。
誇張表現は避ける
自社を良く見せたいとしても、誇張表現に手を出すことは控えましょう。採用後に新入社員が実態を見てミスマッチを感じ、早期退職されてしまう恐れが高まります。人員の補填のため、結果的に余計な採用コストをかけることにもなるでしょう。
誇張表現は一時的に注目を集めることはできるかもしれませんが、長期的には企業の信頼性とブランドを損なうリスクがあります。
失った信用は簡単には取り戻せません。採用ブランディングにおいては、自社の実態と理念に基づいた発信を行うことが大切です。
採用ブランドの一貫性を保つ
一貫性のある採用ブランドや情報は、求職者に信頼感を与えます。しかし、企業が発信しているメッセージが二転三転すると、求職者は何を信じて良いか分からなくなり、企業への不信感につながりかねません。
採用ブランドの一貫性を保つには、常にブランドイメージに則った対応が大切です。たとえば、求人サイトのキャッチコピーや面接時の対応、採用パンフレットのデザインなども、ブランドイメージに沿うように工夫しましょう。
PDCAサイクルを回し改善を繰り返す
採用ブランディングは長期的な運用によって効果を発揮するため、PDCAサイクルを回しながらブラッシュアップすることが重要です。
まずはKPI(重要業績評価指標)を設定し、効果測定を実施します。それによって得た情報を分析することで、課題の発見や改善につながります。
さらに、PDCAサイクルを回すことで、課題や方向性のズレを早期にとらえられ、採用ブランディングの精度も向上するでしょう。
長期的な視点で効果検証する
採用ブランディングの効果を実感するまでには、早くても数カ月から半年程度の期間が必要です。即効性のある施策によって短期間で効果が見えても、ブランドイメージがまだ浸透していないため、ミスマッチが生じやすい側面もあります。
企業のブランドイメージが採用市場、ひいては社会全体に浸透し、企業評価が確立されるまでには2〜3年程度を要します。そのため、すぐに目に見える効果が得られなくても、継続的な効果検証と改善を重ねていくことが重要です。
採用ブランディングの成功事例
採用ブランディングの成功事例について紹介します。採用ブランディングを実施する際の参考にしてください。
アイリスオーヤマ株式会社
アイリスオーヤマ株式会社は、生活用品・家電製品の企画、製造、販売を行う総合メーカーです。
企業の知名度は高まっていたものの、就活における学生の認知度・理解度に課題を感じていました。そこで合同企業セミナー「インターンシップ博」に出展。
学生に直接企業の魅力を伝えられ、インターンシップ参加学生の増加につながりました。さらに人気企業ランキングは47位にまで上昇し、徐々に学生の間でも、就職先のひとつとしてアイリスオーヤマの存在が浸透しつつあると実感されています。
東洋不動産株式会社
東洋不動産株式会社は、主に事業用不動産に特化した総合不動産流通企業です。
堅い企業イメージを刷新するため、株式会社学情が提供する“職場体感型採用動画”「JobTube」を導入。動画制作がパッケージ化されているため、コストや労力をかけずに新卒採用に特化した採用動画を作成できました。
3分程度のショート動画と20分程度のフルバージョンの動画を制作し、学生の視聴環境に合わせて使い分けることで、閲覧数の増加に成功。その結果、企業理解を深めてから選考に進む学生が増えました。
伊藤忠商事株式会社
伊藤忠商事株式会社は、国内外における商品の輸出入、三国間取引、そして事業投資を幅広く展開する総合商社です。
総合商社は学生からの人気が高く、例年多くの応募が集まるものの、企業理解が浅いまま就職先を決める学生が多い傾向にありました。
優秀な人材を獲得するため、幅広い学生にアプローチできる「Webインターンシップ博」に出展。異業種とコラボセミナーを行うことで、異業種志望の学生にも効率的にアピールできました。その効果もあり、就職人気企業ランキングで(注1)4年連続1位を獲得しています。
(注1)同社は2026年卒学生対象の人気ランキングで7年連続1位
採用ブランディングを実施して優秀な人材を集めよう
採用ブランディングは採用市場において自社をブランド化し、イメージや認知度のアップをはかるための戦略です。応募者数の増加やミスマッチを防ぐ効果が期待でき、今後の労働人口の低下にも対応できる可能性が高まります。
採用ブランディングを実施するためには、長期的かつ、全社的な取り組みが必要です。適切なターゲティングや自社の業務・理念に対する理解も欠かせません。自社の在り方を見つめなおし、適切な進め方で採用ブランディングを実施しましょう。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。