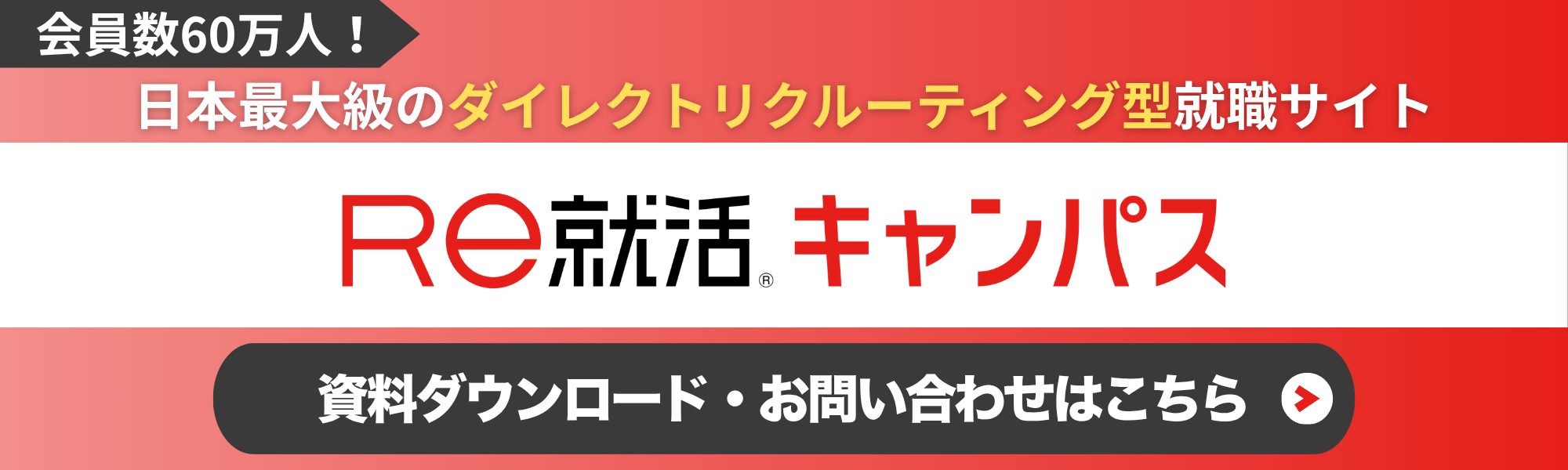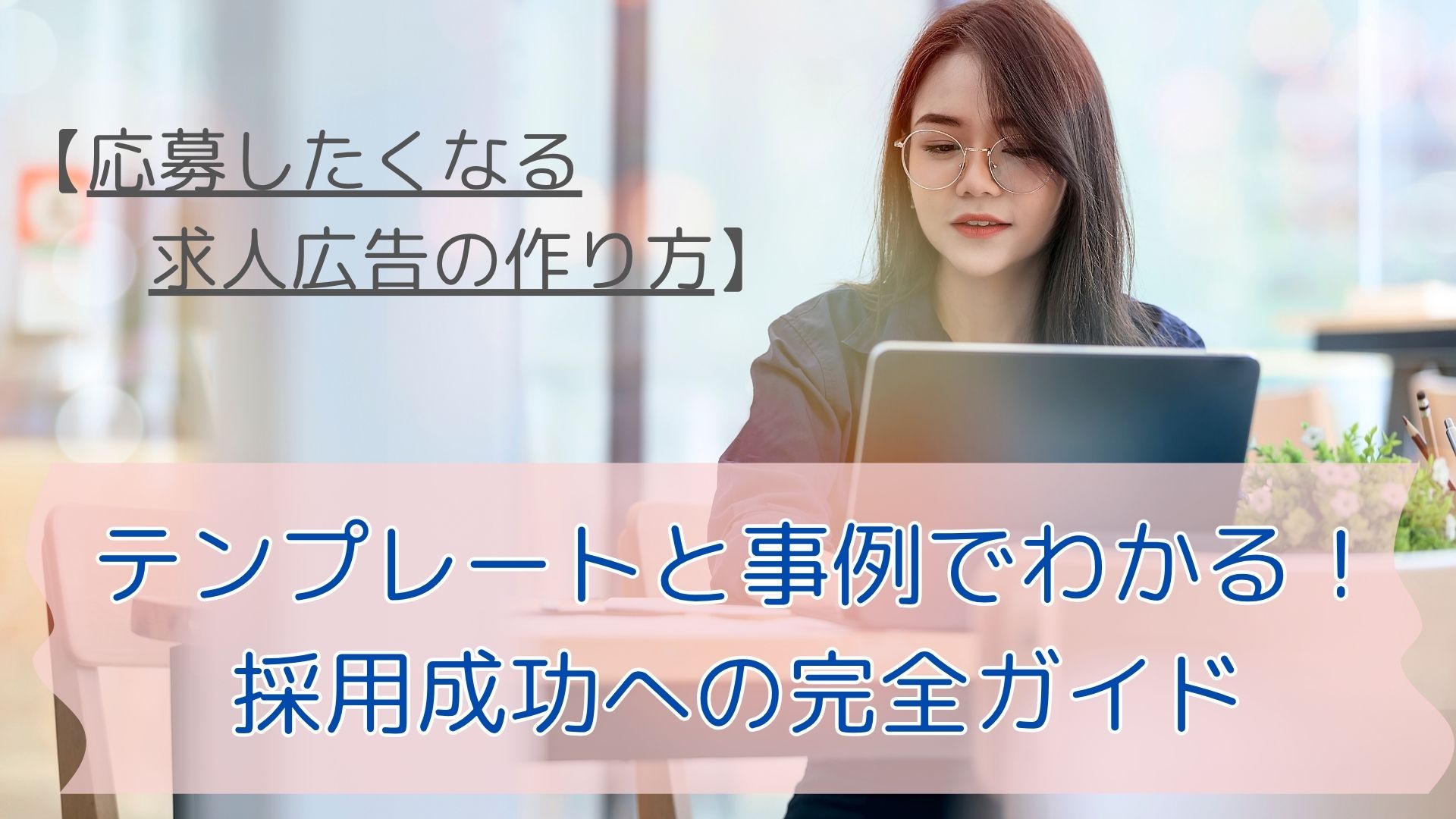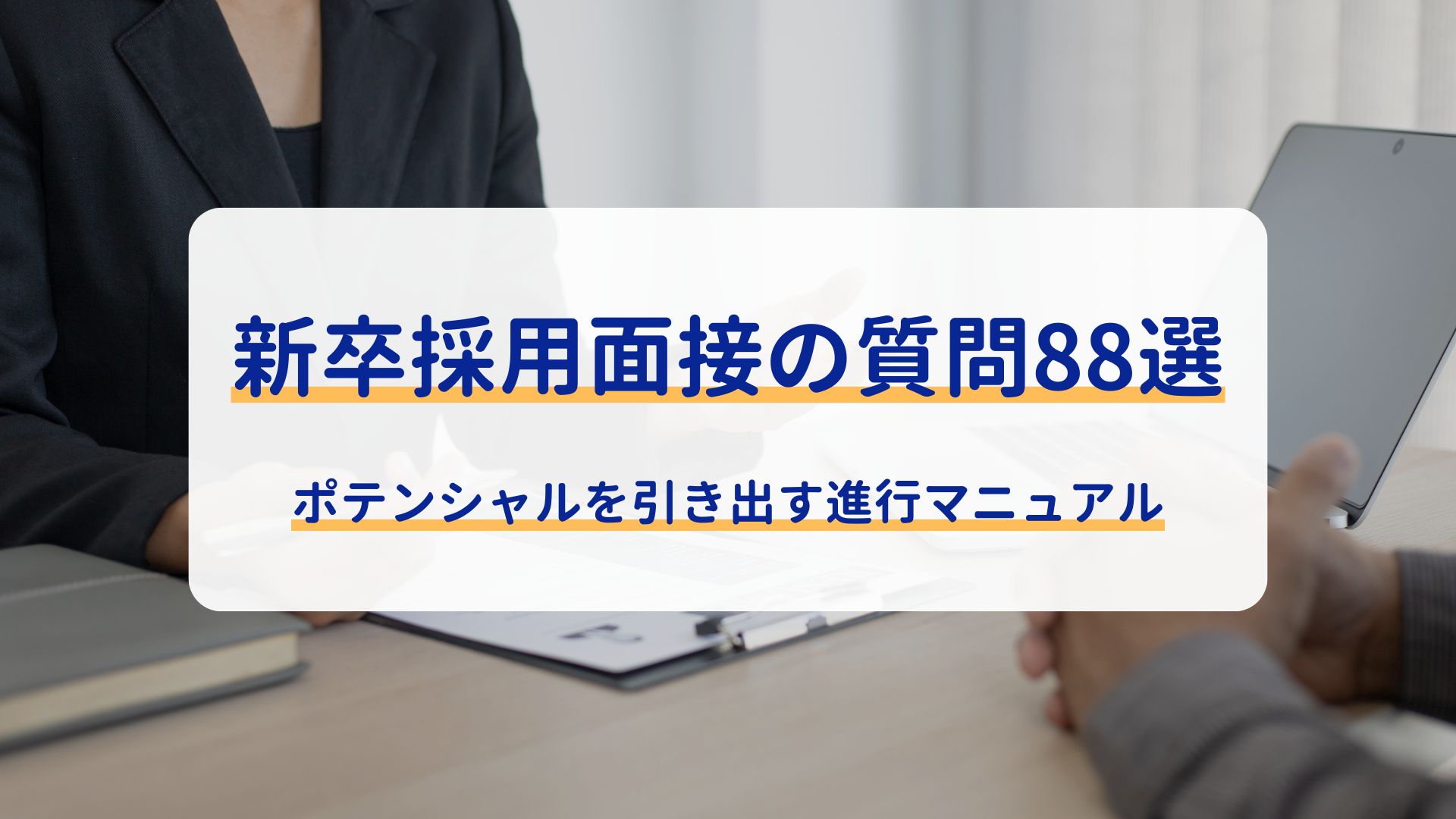採用広報は、人材を採用する目的で行う企業の情報発信です。情報社会である現代では、企業は優秀な人材を獲得するために採用広報活動が欠かせなくなりました。
本記事では、採用広報の詳しい意味や注目されている背景、具体的な手法と手順を解説します。採用広報を成功させるためのポイントも紹介するので、採用広報に取り組む際の参考にしてください。
採用広報とは

採用広報とは、採用を目的として企業や業界の情報発信をすることです。広報を見た人に、自社への就職や転職を検討してもらえるように行います。
採用広報のおもな目的は次のとおりです。
- 企業の認知度を拡大し、ターゲット母集団を形成する
- ターゲットとなる人材からの応募を増やす
- 企業の魅力を伝え、選考中の離脱を防ぎ内定承諾率を上げる
- 自社で働くイメージを醸成し、入社後のギャップを低減する
採用のための広報ではありますが、求職者だけをターゲットにした活動ではありません。入社後のミスマッチによる早期離職を防止するため、企業の文化や風土を伝えて社内のイメージを醸成することも採用広報が果たす役割です。
採用広報が注目される3つの背景

採用広報が注目される背景として、次の3つがあげられます。
- 人材競争の激化
- 企業選びの基準が多様化
- 企業による情報発信のニーズが増加
それぞれ詳しく解説します。
人材競争の激化
現在、少子化の影響で新卒採用も中途採用も売り手市場となり、働き手となる人材の獲得競争が激化しています。就職希望の「顕在層」のみへのアプローチでは、十分な人材を確保できないのが現状です。採用広報によって「潜在層」へもアプローチする必要があります。
採用広報により企業の認知度が向上するため、まだ就職活動を始めていない潜在層にも広く自社の魅力を伝えられます。潜在層の人材がいざ就職を考えた際に、応募先の選択肢に入るかもしれません。
激化する人材競争のなか、自社へ興味を持つ母集団を形成して応募数を増やすためには、採用広報で広く自社の魅力を伝えることが重要と言えるでしょう。
企業選びの基準が多様化
働き方改革や感染症拡大などの影響によって、求職者の企業を選ぶ基準が多様化してきました。リモート勤務やフレックス勤務、時短勤務や副業の可否など、「希望する働き方ができるかどうか」が企業選びの基準になるケースも増えています。
特にZ世代ではその傾向が強く、「なぜこの企業で働きたいと思うのか」「仕事を通してどのような自己実現をしたいのか」など、明確な就職の軸を持って就職活動を行う人が多いようです。
また、情報化社会の発達によって、さまざまな企業の採用情報が容易に入手できるため、求職者の選択肢の幅も広がっています。価値観が多様化する中、企業が求める人材を確保していくには、まず求職者に「自社に応募したい」と思ってもらえるかが重要です。
自社の存在を知り、就職先として検討してもらうために、採用広報を活用してZ世代の関心を集めるような情報を提供していく必要があるでしょう。
企業による情報発信のニーズが増加
SNSや口コミサイトなどの普及によって多くの企業情報が溢れるなか、情報の信頼性や透明性が重要視されるようになってきました。応募先企業の選定において、求職者は単に求人票のテンプレートに沿った内容だけでなく、現場の生の声や透明性の高い情報を重視しています。
そのため、企業には自社の理念や価値観をはじめ、信頼できる情報を発信することが求められています。採用広報を通して、自社の魅力をオープンな姿勢で求職者へ届けることが必要です。
採用広報を実施する3つのメリット

採用広報を実施すれば、認知拡大による応募者の増加やミスマッチの防止、採用コストの削減が見込めます。それぞれ詳しく解説します。
認知拡大による応募者の増加
採用広報では、求職者が利用しているサイトやメディア、SNSなどを通して企業の理念や魅力、風土、働き方などを広く発信できます。企業認知度の向上と拡大が期待できるでしょう。
採用広報では、自社に魅力を感じる求職者の母集団を形成するために、ターゲットを絞った情報発信を行う必要があります。ターゲットに対して魅力的な部分を言語化してアピールすれば、競合他社との差別化や、応募者の増加も見込めるでしょう。
求職顕在層だけでなく潜在層への企業認知も促せるため、中長期的な視点で応募者の増大にもつながります。
採用ミスマッチの防止
採用広報では、求職者に自社のカルチャーやビジョンをわかりやすく届けられます。求人原稿だけの場合より自社を深く理解してもらいやすいため、入社後のミスマッチによる早期退職を防げる可能性が高まるでしょう。
たとえ優秀な人材を採用できたとしても、入社後にミスマッチで早期離職してしまっては採用成功とは言えません。採用広報では、入社後の定着まで考えた情報発信ができることがメリットです。
採用広報を通して自社への理解と共感を促し、求職者の志望度を高められれば、選考過程での離脱を防ぎ、内定承諾率も高められるでしょう。
採用コストの削減
十分な人数が採用できなかった場合、人材紹介やスカウト媒体を利用することもありますが、成功報酬や利用料など採用コストがかかります。
自社メディアやSNSを活用した採用広報により、応募者数や必要なスキル・経験を持った人材の数が増えることで、追加募集に伴う採用コストをおさえられます。また、選考の手間や関与する人員の数も減らすことが可能です。
さらに、選考プロセス中の離脱率や入社後のミスマッチを防止できれば、総合的に採用コストの節約につながるでしょう。
採用広報を出すメディアの種類と特徴

採用広報を発信する媒体は、大きく次の3種類に分けられます。それぞれの特徴は次のとおりです。
| 種類 | 広報媒体 | 特徴 |
| アーンドメディア |
|
|
| オウンドメディア |
|
|
| ペイドメディア |
|
|
アーンドメディア
アーンドメディアには、X(旧Twitter)やFacebook、Instagram、LINE公式アカウントなどのSNSや口コミサイトなどが該当します。SNSでリアルな現場の声を届け、求職者との交流の起点となる点が特徴です。
アーンドメディアは、コメント機能やダイレクトメッセージなどで直接双方向のコミュニケーションを取ることが可能です。信頼関係を構築するのに適した媒体と言えるでしょう。
認知してもらうまでに時間はかかりますが、継続的な発信をすればフォロワーが増えるでしょう。不特定多数の目に触れる機会が増え、結果的に自社のことを知らなかった潜在層へもアプローチが可能になります。
オウンドメディア
オウンドメディアには、自社のブログや採用サイトなどが該当します。掲載内容を自由に設定できるため、伝えたい情報を詳細に記載できます。求人広告とは異なり、幅広いコンテンツを届けられるのが特徴と言えるでしょう。
たとえば、従業員へのインタビュー記事や企業説明会・インターンシップなどの実施レポート、代表からの挨拶や企業理念の詳しい紹介などがあげられます。
企業文化や風土がわかるイベントの風景や、さまざまな働き方をしている従業員の声、商品開発に対する想いや開発過程などを掲載すれば、企業への理解や共感も深められるでしょう。
自社サイトであれば、直接エントリーできるWebフォームを設置することも可能です。Webサイトの構築や運用にはコストがかかる点に注意しましょう。
ペイドメディア
ペイドメディアには、Web広告や駅の広告、就活・転職イベントへの出展などが該当します。企業が支払って利用するメディアで、不特定多数への情報発信が可能です。就活・転職イベントでは求職顕在層へダイレクトにアプローチができるでしょう。
ペイドメディアは自社の認知度を拡大するのに効果的ですが、アーンドメディアやオウンドメディアに比べて高額な費用がかかる可能性があります。
アーンドメディアやオウンドメディアが中長期的な採用広報手段である一方で、ペイドメディアは短期的にエントリー数を集めることに向いていると言えるでしょう。
採用広報を実施する流れ

採用広報を実施するおもな流れは次のとおりです。
- 採用広報のチームを作る
- 自社の魅力を分析する
- 応募者のペルソナ像を策定する
- 配信するメディアを選定する
- コンテンツを作成する
それぞれの手順を詳しく解説します。
1.採用広報のチームを作る
まずは採用広報のプロジェクトチームを結成します。大手企業では広報専門の部署を設置し、組織として広報活動を行う場合が多いでしょう。スタートアップ企業や中小企業の場合は、専門部署や専任担当者ではなく、人事担当者や経営陣のメンバーが広報を兼任する場合もあります。
理想となる採用広報チームの役割と作業分担は次のとおりです。
- プロデューサー:採用戦略立案・マネジメント
- ディレクター:制作進行管理
- 広報担当:記事の公開・拡散、採用戦略との連動
- SNS担当:SNS運用
- インタビュアー:質問項目設計とインタビュー実施
- ライター:記事執筆
- 編集:編集や校正
- フォトグラファー:従業員や職場風景の撮影
社内の人的リソースの関係で、さまざまな部署の担当者が採用広報関連の業務を兼任する場合もあります。社内リソースを考慮しながら必要な人員を集め、採用広報の推進体制を作りましょう。
限られた社内リソースの中で、採用サイトの運営やコンテンツ制作、SNS発信などをすべて社内でまかなうのは難しいと感じる企業も多いでしょう。
そこでおすすめなのが、採用広報を支援するサポートサービスの活用です。
「社内のリソースだけでは手が回らない」「プロの手を借りて、より魅力的な採用広報を行いたい」と感じたら、学情の「採用関連ツール制作」をぜひご活用ください。
2.自社の魅力を分析する
次に、4P分析や3C分析などで自社の魅力を分析します。効果的な採用広報を行うには、多角的な分析に基づいた戦略設計が欠かせません。
4P分析とは、企業理念(Philosophy)、人・文化(People)、事業・業務内容(Profession)、働き方・待遇(Privilege)の4つの視点で分析を行う方法です。4P分析によって自社の強みを明確に視覚化すると、訴求する方向性が定まりやすくなります。
3C分析は自社(Company)、競合(Competitor)、候補者(Candidate)の3つの視点で分析を行います。3C分析ではおもに、求職者が求めていて競合他社が提供できないような自社の強みを分析可能です。
さまざまな視点から自社の持つ魅力や他社と差別化できる強みを見つけましょう。
3.応募者のペルソナ像を策定する
自社の魅力を明確にしたら、ターゲットとなる人材のペルソナ像を考えます。どのような人材を採用したいのか、性別や年齢、趣味、価値観など細かく具体的に設定しましょう。箇条書きで列挙するのがおすすめです。
設定したペルソナに沿って広報内容を作成していくと、自社がアピールしたい情報を一方的に届けるだけでなく「求職者が興味を持つような情報」「ターゲットが知りたがっている内容」を発信できるようになるでしょう。
4.配信するメディアを選定する
ペルソナを設定したら、配信するメディアを選びましょう。設定したペルソナが使用しているメディアや目につきやすいメディアを選定します。
20代をターゲットにするならば20代のユーザー数が多いX(旧Twitter)やInstagram、YouTubeなどが良いでしょう。自社がターゲットとする求職者へ理想的な状態で情報を届けられるよう、適切なメディアを選ぶことが大切です。
5.コンテンツを作成する
配信メディアが決まったらコンテンツを作成します。コンテンツ内容の例は次のとおりです。
- 企業のビジョン
- 経営陣からのメッセージ
- 従業員のインタビュー
- オフィス環境の紹介
- 働き方の紹介
- 研修・勉強会のレポート
- 社内イベントの様子 など
設定したペルソナが求めているコンテンツはどのような内容か、自社はどのような切り口で何を伝えたいのかなどを検討し、コンテンツを作成しましょう。
採用広報を成功させるポイント

採用広報を成功させるためには、多角的かつ長期的な視点が必要です。ポイントとしては次の4点があげられます。
- 採用数以外でKPIを設定する
- 採用広報の方法を随時改善する
- 部署を越えて協力を仰ぐ
- 採用広報のサポートサービスを活用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
採用数以外でKPIを設定する
採用決定数はさまざまな要因で決まるため、採用数をKPIに設定してしまうと、採用広報の成果が見えづらくなる可能性があります。採用広報に期待できる効果を把握するには、採用数ではなく目標に至るまでの細かいプロセスごとにKPIを設置します。
「KPI」とは、Key Performance Indicatorの略称で、「重要業績評価指標」です。目標の達成度合いの計測や監視のために置く指標を意味しています。
採用広報のKPIは、コンテンツの発信数や既読率、メディアへの流入数(PV数)などに設定すると良いでしょう。内定承諾率や、入社後の定着率、早期離職率にKPIを置くのも効果的です。
採用広報の方法は随時改善する
採用広報では、初回に考えられた施策が相応しいとは限りません。そのため、状況に応じて随時改善することが必要です。設定したKPIを見ながら効果を測定し、必要であれば情報の発信方法や頻度、コンテンツの内容などを見直しましょう。
投稿内容やコンテンツ制作ばかりに集中するのではなく、採用広報活動を俯瞰して、一貫性があるか・メディアごとのメッセージにブレがないかなども随時チェックします。
部署を超えて協力を仰ぐ
人事部や経営陣だけでは、コンテンツのリソースを充分に確保できない可能性があります。充実したコンテンツを継続的に発信するには、部署を超えた協力体制が欠かせません。複数の部署に協力を仰ぎ、全社的に採用広報に取り組む姿勢が大切です。
採用広報では社内のさまざまな情報を多角的に発信しようと、各部署への取材やインタビューを行うこともあるでしょう。
社内の人的なリソースが確保できずに頓挫するケースも多いため、人事部だけではなく、ほかのさまざまな部署にも採用広報に協力してもらう必要があります。インタビューや取材協力、コンテンツ作成依頼などに快く対応してもらえるような関係づくりも大切です。
全社的に取り組むことで幅広い社内情報を求職者へ伝えられ、魅力的な情報発信となるでしょう。
採用広報のサポートサービスを活用する
効率的かつ効果的な採用広報を行うには、サポートサービスの活用がおすすめです。
採用広報を成功させるには、採用関連のさまざまなツール制作が欠かせません。採用サイトやコーポレートサイト、自社の魅力を伝えるための資料やパンフレットも必要ですが、全て一から自社で制作するには多大な工数と人員が必要です。
学情の採用関連ツール制作サービスなら、40年以上の就職情報事業で得られたノウハウを駆使して、Webサイトやパンフレットの作成をサポートします。単なるデザイン制作に留まることなく、企業の魅力をしっかりと伝えられるサイトやパンフレットづくりをサポートします。
採用広報におけるKPI設計のポイント

採用広報は、ただ情報を発信するだけでは、なかなか成果が見えにくいという特徴があります。そのため、発信の効果を正しく把握し、戦略的に改善していくためには、KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。
KPIとKGIは、KGIの達成に向けた指標がKPIという関係です。適切なKPIを設定することで、各施策の効果が数値として明確になり、何がどれだけ成果を生んでいるのかが可視化されます。これにより、データに基づいた適切な改善サイクルを回し、より効果的な採用広報へとつなげることができます。
ここでは、KGIの達成に向けた進捗を測るための中長期的な指標と、採用広報活動の効果を短期的に把握するための指標を、具体的に紹介します。
KGI:採用活動のゴールを設定する
まず、採用活動の最終的なゴールとなるKGIを明確にすることが大切です。最終的な目標が不明確なままだと、その達成に向けた中間目標であるKPIを設定しづらくなってしまいます。そのため、KGIを起点にしてKPIを決めていくことが重要になります。
採用KGIとしては、「最終的に何人の人材を採用するか」を設定するのが一般的です。たとえば、「〇カ月以内に事務職を〇名採用する」「半年以内に新規プロジェクトに必要な即戦力を〇名確保する」といった形です。また、今後退職予定の社員数も把握しておくと、実際に必要な採用人数をより正確に見積もることができます。
中長期KPI:採用活動の成果を測る
KGIを達成するためには、その途中のプロセスを評価する指標であるKPIを設定する必要があります。特に、中長期的な視点で採用活動の成果を測るためには、中長期KPIを明確にすることが重要です。
中長期KPIでは、採用活動全体の成果や、採用後の人材の活躍状況を測定します。その第一歩として、応募数・書類通過率・面接通過率といった指標を事前に設定し、効果的な広報活動の計画と進捗管理を行いましょう。
採用広報のゴールは、単に応募者を増やすことではありません。企業の価値観を共感・理解した人材を迎え入れ、長く活躍してもらうことが最終的な目的です。結果として、採用コストの削減や早期離職率の低減につながり、組織全体にプラスの影響をもたらすでしょう。
短期KPI:採用広報の効果を可視化する
中長期KPIが「採用全体の成果を評価する指標」であるのに対し、短期KPIは「採用広報の発信活動そのものの効果」を測るための指標です。採用広報がどれだけの人に届き、どれくらいの反応を得られたのかを可視化することで、広報戦略の改善につなげることができます。
具体的には、以下のような指標が挙げられます。
コンテンツ公開数・更新頻度
どれだけコンテンツを公開し、更新するかの目標を設定します。たとえば、「月に10本のブログを公開する」など、具体的な数値を定めることで、安定した情報発信をしやすくなります。
PV(ページビュー)・UU(ユニークユーザー)数
目標となるページビュー数やユニークユーザー数を設定することも大切です。「採用サイトの訪問者数を月に5000人以上にする」といった具体的な目標を立てることで、コンテンツの効果を客観的に分析し、より効果的な発信方法を検討できます。
エンゲージメント(いいね・シェア・コメント数など)
採用広報活動を通じて、どれくらいエンゲージメントが得られるかを前もって目標設定します。たとえば、「SNSで1週間に100件のいいねやシェアを目指す」などの目標を立てることで、発信内容の質を高め、より多くの人に情報を届けやすくなります。
これらの指標をもとに、「どの媒体に力を入れた結果、どのくらいの反響があったのか」を振り返ることが重要です。アクセス解析ツールやSNSのインサイト機能を活用し、定期的にデータをチェックしましょう。
もし想定よりも反響が少ない場合は、発信する内容や配信のタイミングを見直すことで、より効果的な採用広報につなげることができます。
採用広報の最新トレンド

近年、SNSの普及や働き方の多様化により、採用広報の手法も大きく変化しています。
従来の求人広告や企業説明会だけでなく、自社独自のメディアを運用したり、特定の職種に特化した広報を行ったりする企業が増えてきました。特に、エンジニア向けの技術広報や、社員が情報発信を行う取り組みなど、新たな手法が注目を集めています。
このように、企業ごとに工夫を凝らした採用広報が行われる中で、「どのような施策が実際に効果を生んでいるのか」を知ることは、今後の戦略を考える上で重要です。
ここでは、現在のトレンドとなっている具体的な施策と、実際に成果を上げている成功事例を詳しく紹介していきます。
SNS・動画を活用した採用広報
InstagramやX(旧Twitter)、YouTubeなどのSNSや動画プラットフォームを活用することは、現在の採用広報における代表的なトレンドのひとつです。
短い動画や写真を通じて、職場の雰囲気や社員のリアルな声を伝えることで、求職者に親しみを感じてもらいやすくなります。特に若年層の求職者にとっては、テキストよりもビジュアルコンテンツのほうが直感的に情報を得られるため、企業の魅力を効果的に発信できる手法といえるでしょう。
こうしたSNS活用を成功させるためには、単に投稿するだけでなく、以下のような工夫が求められます。
SNS専用のチームを組成
人事部や広報部の担当者だけでなく、現場の社員やインターン生なども巻き込み、さまざまな視点から企画を考え、定期的な投稿を行う。
裏側を見せるコンテンツ
オフィスツアー動画や、社員の1日密着企画など、文章だけでは伝わりにくい職場の雰囲気を可視化し、求職者の理解を深める。
双方向のコミュニケーション
コメント欄への返信や、ライブ配信を活用して求職者の疑問に直接答えることで、よりエンゲージメントを高める。
SNSを継続的に運用することで、フォロワー=潜在的な応募者を徐々に増やしていくことができ、結果として長期的な採用ブランディングの強化にもつながるでしょう。
技術広報によるエンジニア獲得
IT市場の拡大に伴い、エンジニア人材の確保が年々難しくなる中で、「技術広報」の重要性が増しています。企業が自社の開発プロセスや技術スタック、エンジニアの働き方を積極的に発信し、それに共感したエンジニアを採用につなげる取り組みです。
単に求人情報を掲載するだけでなく、技術力や開発環境の魅力を伝えることで、求職者に「この会社で働きたい」と思ってもらうことを目指します。
技術広報の具体的な施策として、以下のような手法が有効です。
社内エンジニアブログや勉強会レポートの発信
実際のコード事例や技術的な課題へのアプローチを公開することで、企業の技術力や開発文化をアピール。
カンファレンスやイベントへの登壇機会を増やす
社内エンジニアが外部の技術イベントやカンファレンスで登壇し、自社の開発手法やノウハウを発信。業界内での認知度向上につながる。
GitHubなどを活用したオープンソース活動の推進
社内のリポジトリを一部公開したり、オープンソースプロジェクトに積極的に貢献したりすることで、企業の透明性や技術力の高さを示す。
エンジニアにとって魅力的な職場とは、自由度の高さや、最新技術への挑戦を支援する環境が整っているかどうかが重要なポイントとなります。そのため、技術広報ではこうした魅力をしっかり打ち出し、ターゲットとなるエンジニア層に響く情報を発信することが求められます。
採用広報の成功事例
近年、企業が自社の魅力を多角的に発信する「採用広報」は、優秀な人材の採用・定着や自社ブランディングにおいて大きな効果を発揮しています。
ここでは、競合記事本文で取り上げられている3社の成功事例を紹介し、それぞれの施策や効果を簡潔にまとめます。
自社の状況と照らし合わせながら、参考にできるポイントをぜひ見つけてみてください。
株式会社岐阜造園
課題・ニーズ
・説明会参加率など、母集団の質の強化
・サポート体制の充実
活用したサービス
・JobTube
・Re就活キャンパス
効果
施工管理をはじめ、4人の内定者を確保
株式会社岐阜造園は、庭園の設計・施工・メンテナンスを行う会社です。新卒採用に取り組んでいるものの、説明会参加率が低く、母集団の質に課題を感じていました。また、採用担当が1人で他の業務と兼務していたため、採用業務に注力できていない状況でした。
そこで、企業の雰囲気や社員の生の声を届ける動画サービス「JobTube」をご提案。作成した動画を会社説明会や自社の採用サイトで配信することで、企業理解の促進・志望意欲の醸成を図りました。
その結果、20%程度であった説明会参加率は50%以上に改善し、24卒では採用難易度が高いと言われる施工管理職を含め、4人の内定者を獲得しました。
アイリスオーヤマ株式会社
課題・ニーズ
早期段階での学生の認知度・理解度の向上
活用したサービス
・就職博
・Re就活
効果
・インターンシップ参加学生の増加
・4人の第二新卒者を採用
アイリスオーヤマ株式会社は、生活用品の企画・製造・販売を行う企業です。積極的な広告活動により、知名度は上がっていましたが、就活における学生の認知度や理解度が低く、応募数の増加に繋がっていませんでした。特に、どのような仕事があるのか、どんな思いで働いているのかといった具体的な内容が学生に伝わっていないことが課題でした。
そこで、株式会社学情が主催する「Super Business Forum」や「インターンシップ博」などの合同企業セミナーをご提案。学生に対して、就職先としてのアイリスオーヤマという存在を浸透させるよう意識しました。
その結果、学生間の認知度が向上し、インターンシップ参加学生も増加しました。また、20代向け転職サイト「Re就活」を組み合わせることで、4人の第二新卒者を採用することができました。
その他の事例
近年、SNSを活用した採用広報が注目を集めています。特に、20代の若手採用を目指す企業にとって、SNSは非常に効果的なツールとされています。SNSを通じて企業の魅力を発信し、若手求職者とのコミュニケーションを図ることで、より多くの人材を引きつけることができます。
例えば、InstagramやX(旧Twitter)を活用して企業文化や社員の声を発信することで、求職者にリアルな職場の雰囲気を伝えることができます。
SNSでの採用広報について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
中長期的な視点で効果的な採用広報に取り組もう

人材獲得競争が激化し、情報が溢れる現代社会では、SNSやWebサイトを使った採用広報に注目が集まっています。どのようなメディアで採用広報を行う場合でも、まずは自社のことを知ってもらい、継続的に発信内容を見て、求職者に自社への興味・関心を持ってもらう必要があります。
自社への理解・共感を促し、求職者が「この企業で働きたい」と思うような志望動機を醸成して実際の応募へ結びつけることが採用広報の目的の一つです。
採用広報は短期間で成果が見えるものではないため、中長期的な視点でゴールを設定し、逆算しながら計画を立てる必要があるでしょう。必要に応じて情報発信の方法やコンテンツ内容を見直しながら、全社的に広報活動へ取り組むことが大切です。
自社にとって効果的な採用広報活動を行い、求める優秀な人材を確保しましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。