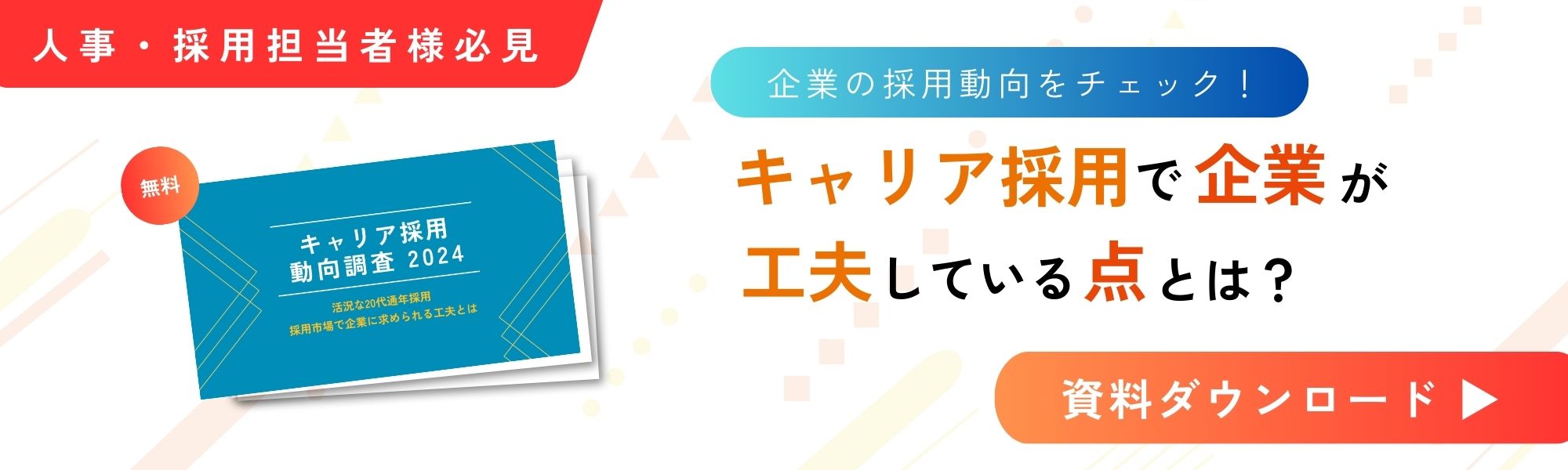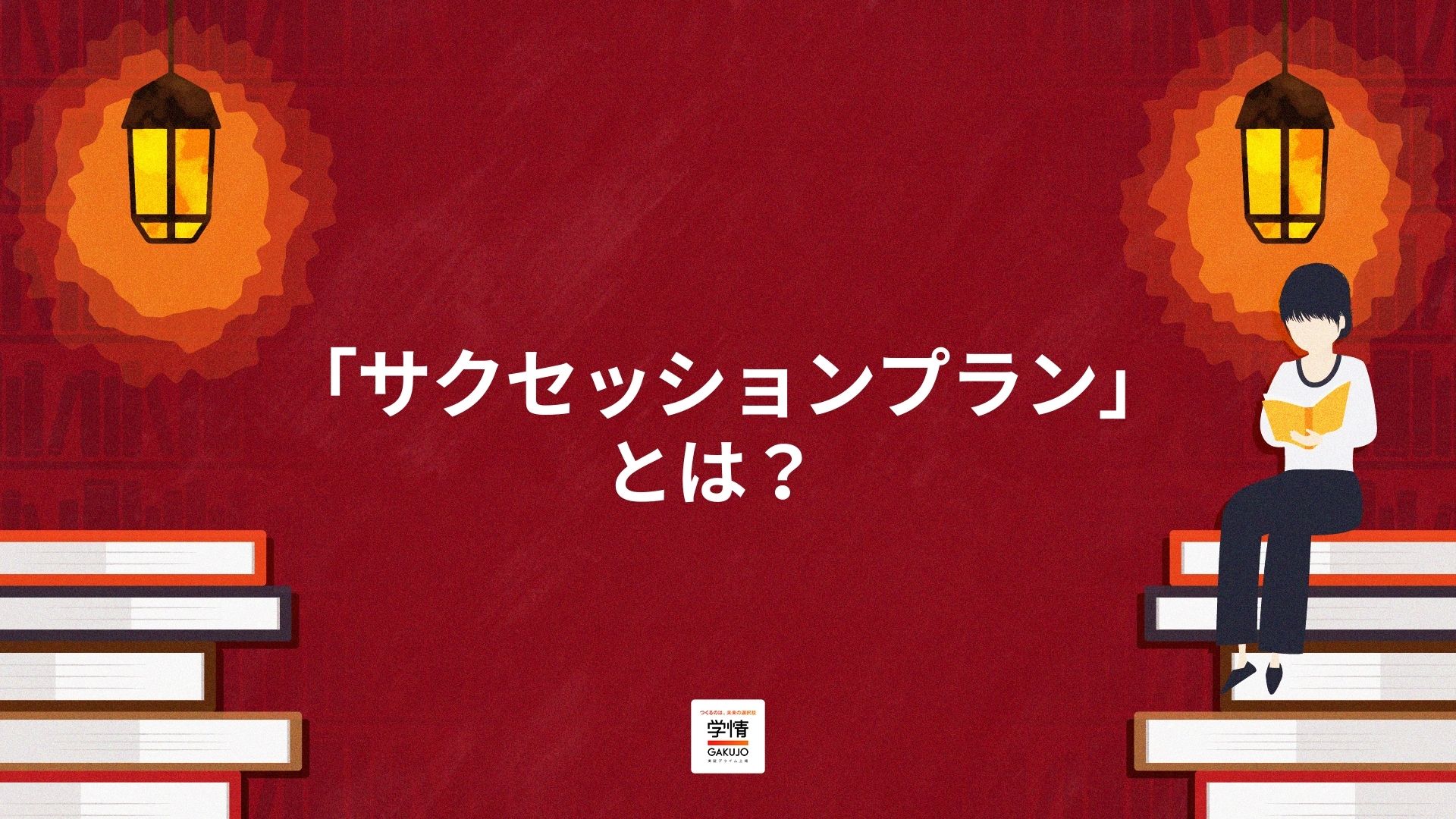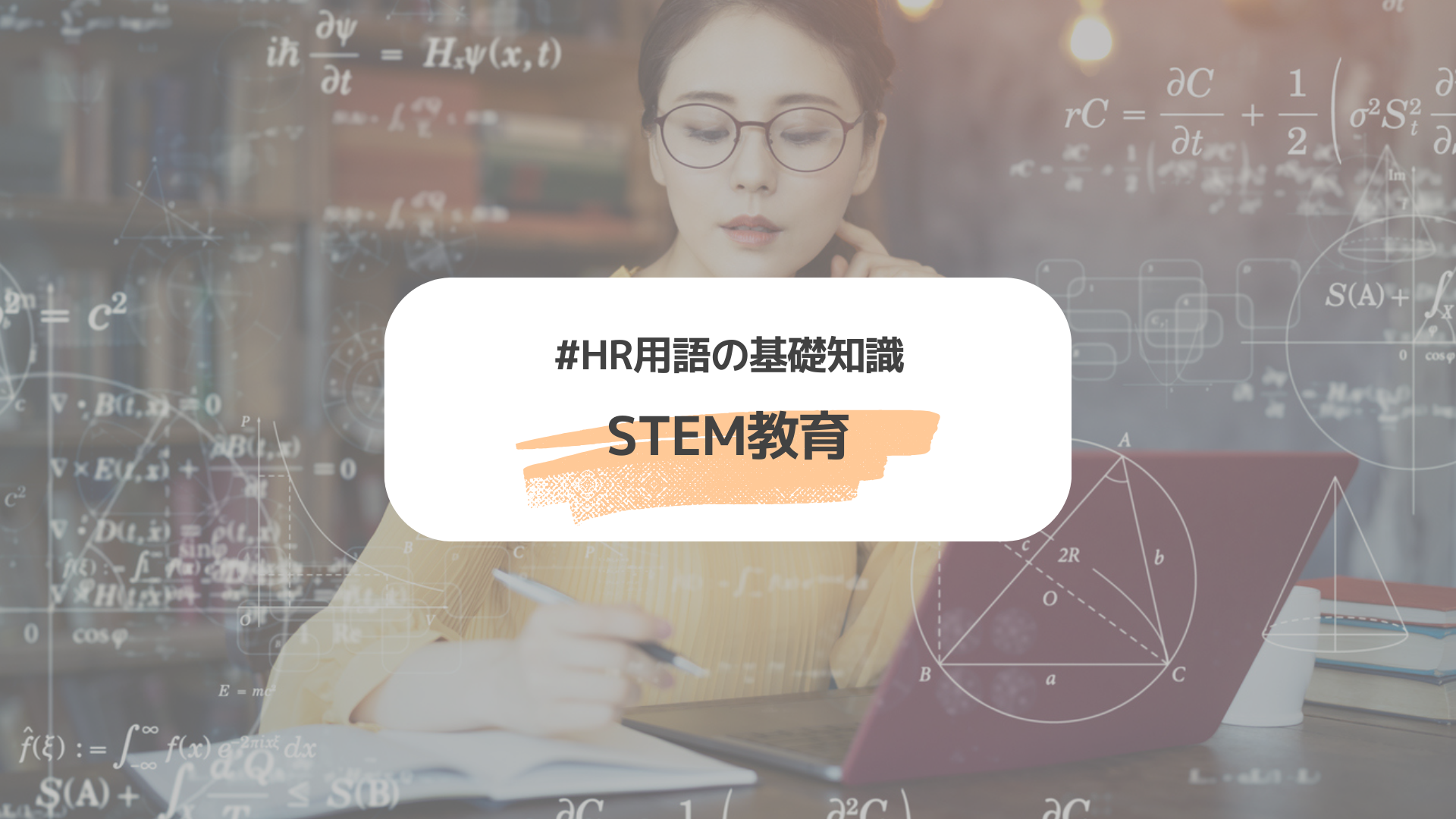
近年では「STEM教育」をはじめとする、教科横断的な学習を取り入れる教育機関が世界中で増えてきています。日本国内でも、学習指導要領の改訂やSSH・SGHの指定など、さまざまな施策が展開されています。
STEM教育の目的は、AIやIoTなど急速な技術の発展や多様化する社会に対応可能な人材を育てることです。
本記事では、STEM教育の詳しい内容や「STEAM教育」との違い、STEM教育が現在求められている背景を解説します。世界各国や日本の企業の取り組み事例も紹介するので、STEM人材を活かして企業が成長するための参考にしてください。
STEM教育とは

STEM教育は、科学や技術などに重きを置き、IT社会やグローバル社会に必要な能力を育てるための教育です。詳しい内容と、似た言葉である「STEAM教育」との違いを解説します。
科学や数学に重点を置いた教育
「STEM」は、「Science・Technology・Engineering・Mathematics」の頭文字をとったものです。この頭文字の「科学・技術・工学・数学」分野の教育に力を入れ、IT社会に適応できる人材を生み出そうとする教育が「STEM教育」です。
従来までは「教師が教えた内容を、生徒が覚える」といった教育スタイルが主流でした。しかし、それでは生徒が自発的に考え、問題解決をする能力が育ちにくくなります。
そこで、「学ぶ側の生徒が自ら情報収集し、問題解決する」という教育スタイルのSTEM教育が生まれました。STEM教育では生徒がパソコンやインターネットなどを利用して自分で情報収集し、必要な情報を見極めて判断しながら問題解決をしていく学習スタイルを取ります。STEM教育を取り入れた授業の一環としては、プログラミングや理科実験、ものづくりなど、探求や創造的な体験活動があげられます。
「自ら学ぶ力」によって、自発性や創造力、判断力、論理的思考力や問題解決能力などを養い、IT時代における国際競争力を持った人材を育てることが狙いです。
STEAM教育との違い
STEM教育と似た言葉に「STEAM教育」があります。STEAM教育は、STEM教育にアート(Art)の要素を取り入れたものです。
今後発展していくAIを活用した仕事をするためには、STEMに加えて「アートとデザイン」による「善や美への理解」が必要だと考えるのがSTEAM教育です。
アートの要素が入ることで、デザイン、感性などを含めて自由な表現や発想といった柔軟性が加わります。アートによって、創造的な表現もできるようになってもらうことが狙いです。
STEM教育で身に付くスキル

STEM教育で身に付くと考えられているスキルは次の7つです。
- 統計力
- 問題解決力
- 創造性
- 論証力
- 知的好奇心
- データ重視の意思決定
- 融通性
統計力は、確率やエラー率がどの分野でも問題の理解につながるため必要です。たとえばさまざまなデータから確率やエラー率、傾向などを読み取ることができれば、より市場価値の高い商品やサービスの開発、問題を解決する戦略などが立てられるようになるでしょう。
問題解決力はあらゆる分野において社会が求めている重要なスキルであり、創造性はさまざまなアイディアや異なる視点を生み出すためには欠かせません。
論証力は、主張を裏付ける証拠をもとに分析的・批判的思考スキルを使って論証することを意味しています。知的好奇心は分野を超えて学び、常に前進し続けるために必要なものと言えるでしょう。
また、最善の問題解決をするためには、科学的なデータや根拠に基づいた意思決定をすることも重要です。加えて、新しい需要やさまざまな状況に臨機応変に対応するためにも、コミュニケーション力を含めた融通性・協調性が必要とされています。
STEM教育が求められる理由

STEM教育が求められている背景には、IT社会へ適応できる優秀な人材の不足に対する懸念があげられます。STEM教育が求められている理由を詳しく見ていきましょう。
IT社会へ適応するため
現代では、世の中の多くの技術や仕組みにITが活用されるようになりました。ITの仕組みを理解し、使いこなせる優秀な人材を育てるため、ITリテラシーを高める必要性が重視されています。
今後、さまざまな分野でAIやロボットが代替作業をするようになっていくでしょう。それらのテクノロジーを理解し、管理する人材や技術者なども必要とされています。
益々発展が予想されるIT社会へ適応できる人材を確保するためにも、STEM教育によって自ら学ぶ力や問題解決力などを身に付けた人材を育成することが必要です。
創造性や協調性を向上させるため
今後は、決まった工程の作業やデータ入力など、単純な仕事はAIによって代替される可能性が高まっています。
一方で、創造性や協調性を必要とする分野においては、AIが代替できないものもあります。芸術や教育、医療分野など、人間にしかできないこともあるでしょう。
STEM教育では、さまざまな分野を超えて共通するパターンや問題を発見し、自ら情報を収集することで解決の糸口を見つけていきます。
このような主体的で横断的な学びによって、創造性や協調性など、先に解説したような7つの能力が養われます。そのなかで、人間にしかできない分野で活躍できる人材を育てられるでしょう。
世界のSTEM教育の現状
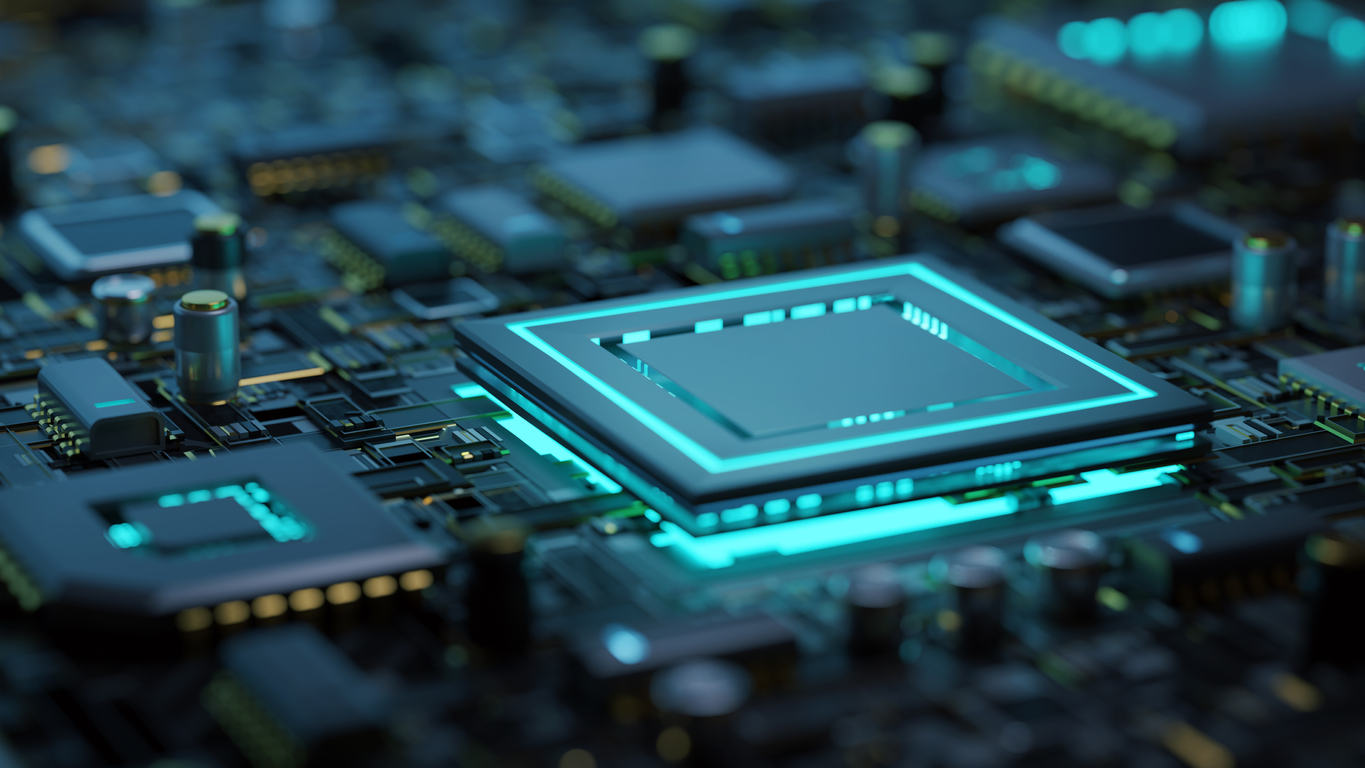
現在、注目されているSTEM教育ですが、世界ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。各国の現状を詳しく見ていきましょう。
日本のSTEM教育
日本では、STEM教育の一環として2020年度から小学校の授業でプログラミングが必修科目となりました。
また、文部科学省は「SSH(スーパーサイエンスハイスクール)」を支援しています。これは科学技術系の人材を育てる目的で行われた施策で、2022年には217校がSSH指定校となりました。SSHは、学習指導要領で規定されている内容を超え、先進的な理数科教育に取り組む高校を認定する取り組みです。
ほかにも、国際科学技術コンテストや科学の甲子園の実施、次世代科学者育成プログラムの推進などが行われています。STEM教育を広めるためにさまざまな研究機関や教育協会が設立されており、日本のSTEM教育は今後益々普及していくと予想されます。
中国のSTEM教育
中国では、2017年からSTEM教育が義務教育に盛り込まれました。2019年からは10年かけた「中国STEM教育2029革新行動計画」が発表されており、中国国内でも益々STEM教育が浸透していくでしょう。
また、将来ユネスコが主導するSTEM教育機関が上海にできる予定です。そのほかにも上海、天津でイノベーション人材育成プログラムを実施しています。
アメリカのSTEM教育
アメリカではオバマ大統領の就任後から国をあげてSTEM教育に取り組んできました。世界に先駆けて2000年代からSTEM教育に注力し、2018年には「STEM教育戦略」を発表しました。STEM教育戦略が掲げるおもな内容は次のとおりです。
- 2020年までにSTEM教育指導教員を10万人養成する
- 高卒までにSTEM教育を受けたことのある若者を50%増加させる
- 職業訓練でSTEM教育を講習し、仕事で必要な技術の学習機会を設ける
大学では、中高生までを対象とした参加体験型のプログラムを開発し、大学・大学院でSTEM教育を専攻した場合、通常1年の学生ビザで企業研修が受けられる「OPT」を最大3年間受けられる制度を導入しています。
EUのSTEM教育
ヨーロッパでは、2015年にSTEM教育に関する機関が発足し、EU加盟国で戦略的な支援のプラットフォームを構築しました。
より早い段階では、2004年にイギリスで科学とイノベーションに関する投資フレームワークが作成されました。EU全体では、STEM関連職の選択や、大学でのSTEM分野専攻を奨励するとともに、EU圏内の国や非営利団体で多くの成功事例を体系的に研究しています。
EU加盟国同士で施策を分担し合いながら実践することによって、EU全体で優秀なSTEM人材を育成しています。
タイのSTEM教育
タイでは、国の機関の一つである国立科学技術開発庁が、課題解決のコンテストを開催しました。教育機関にはIoTのプログラム環境を提供し、プログラミング用のマイコンボードを中学・高校に20万台配布しています。
また、学校に3Dプリンターのようなデジタル工作機械を備えたメイカースペースを設けるなど、AI時代に向けてSTEM教育に力を入れています。
STEM教育に関する企業の取り組み事例

現在日本では、STEM教育に関する企業の取り組みも増えてきています。STEM教育スクールの開校やものづくり系のイベント、教育サポートシステムの提供など、企業の取り組み事例を紹介します。企業として、STEM教育に対する関わり方を考える参考にしてください。
STEM教育のスクールを開校
一般的な塾のように、STEM教育に関するスクールも開校されています。これから益々発展していくIT社会を生き抜くためには、正解のある教科別の学びだけでなく、教科を超えて横断的に問題解決を学ぶ必要があるでしょう。
STEM教育スクールのカリキュラム内容の例は次のとおりです。
- ブロック・プログラミングを使ったものづくり体験
- ゲームやアニメーション作成
- ロボット制御
- 算数の文章題の絵画表現 など
子どもを対象にプログラミングやロボットの作成、動画・ホームページ作成をはじめ、プレゼンの仕方などアウトプットの学習も行い、STEM教育で期待されるさまざまなスキルの獲得を目指すスクールが増えてきています。
子ども向けのイベントを開催
STEMの分野に興味をもってもらうため、子ども向けに自社の技術を活用したイベントを開催している企業もあります。
ものづくり系の企業では、電子工作やプログラミングなどの体験授業を提供しています。実際に体験することで、子どもたちに科学技術の魅力や面白さを知ってもらうことが狙いです。
また、ロボットの開発過程や電子部品を紹介することで、ものづくりを支える技術者の仕事に興味を持ってもらうキャリア教育や、電気エネルギーと環境の相関関係を考える環境教育などの出前授業も行われています。
STEM教育のサポートシステムを提供
STEM教育を浸透させるために、サポートシステムを提供している企業もあります。eラーニングをより効率化し、受講生それぞれの学習状況を適切に把握し管理するために開発されました。
たとえば、「LMS(Learning Management System)」と呼ばれる学習管理システムがあります。学習状況を管理する側向けに、受講生の学習時間や個々の理解度・進捗状況・テストの成績や課題の提出状況などを把握できるシステムです。
また、「LXP(Learning Experience Platform)」と呼ばれるサポートシステムもあります。STEM教育を受ける人向けに、学びたい分野に関する教材の検索や学習状況を踏まえたおすすめ教材を紹介する研修管理システムです。
STEM人材の活用により企業が成長するには

企業が競争力を高め、より成長していくためには、将来的にSTEM人材を活用できる環境づくりが欠かせません。STEM人材を活用するために企業がおさえておくべきポイントを紹介します。
STEM人材の受け入れ体制を構築しておく
企業がSTEM人材を活かすためには、まず受け入れ体制が必要です。能力がある優秀なSTEM人材を採用できたとしても、能力を発揮してもらえなければ意味がありません。
そのため、まずは人事部内で自社の抱える課題に対し、どのような人材が必要なのかを見極めましょう。必要なSTEM人材を確保するための採用活動を計画します。
STEM人材が採用できた際には、各部署・チームでの受け入れ体制も必要です。能力を十分に発揮して活躍できる職場環境にすること、公平に評価する制度などを整えます。
また人事や教育の分野でもICTを活用し、従業員のデータ管理や人材開発プラットフォームの導入、社内eラーニング研修なども検討すると良いでしょう。
既存従業員の成長をサポートする
STEM教育で身に付けられるスキルは、未来を担う子どもだけでなく現代社会を支える大人にとっても必要です。ITやAI技術が刻々と進化するなか、現在の従業員に対してもSTEMに準ずる教育を行うことは、企業の成長のために重要と言えるでしょう。
将来STEM人材が入ってきたとき、指導する側にもスキルや知識がなければSTEM教育を受けた人材を活かしきれない可能性があります。そのため、ITリテラシーを高めるための研修機会や、先に紹介したLMS、LXPなどの学習機会を設けると良いでしょう。
また、IT関係の資格を取得するとインセンティブ・手当が出るなど、既存従業員の成長を促す施策を導入するのも一つの方法です。
受け入れ体制を整えてSTEM人材が活躍できる場を作ろう

STEM教育やSTEAM教育は、これからのIT社会・グローバル社会に適応する国際競争力を持った人材を育てるために重要な教育システムです。
「自ら情報収集して問題解決する」「教科や分野の枠を超えて横断的に考える」といった学びが浸透することで、グローバル社会や労働市場における総合的な問題解決力の高い人材を生み出すことができるでしょう。
STEM・STEAM人材を企業が活かして成長するためには、企業内にも知識と受け入れ体制が必要です。既存の従業員へのSTEM教育や研修、学習機会を設けるなどのサポートを行い、企業全体のITリテラシーを高めましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。