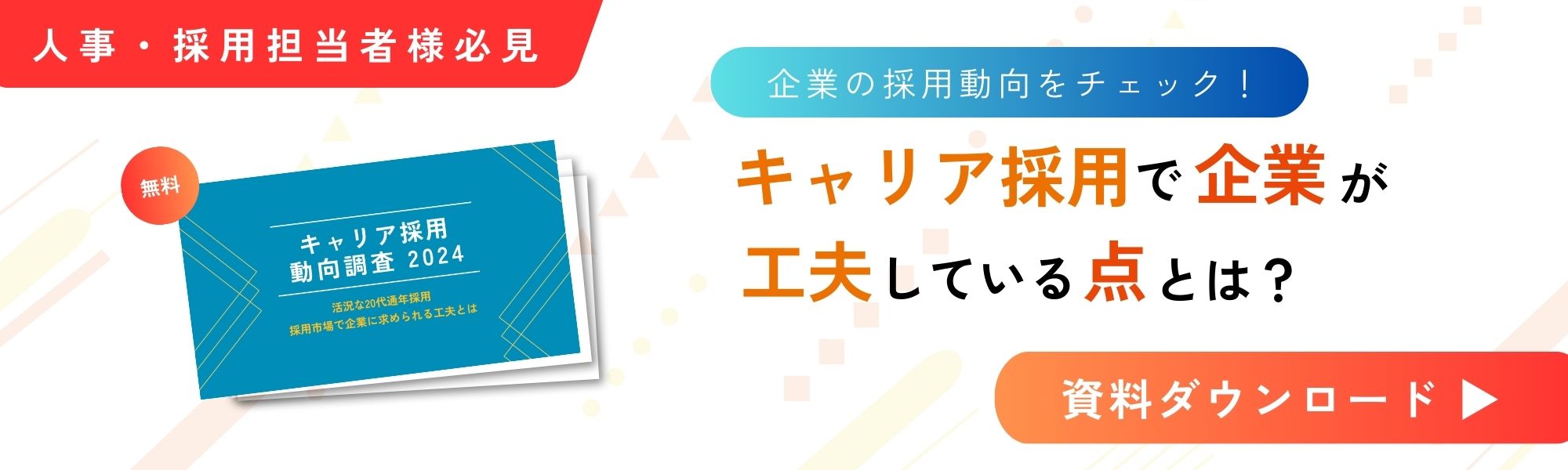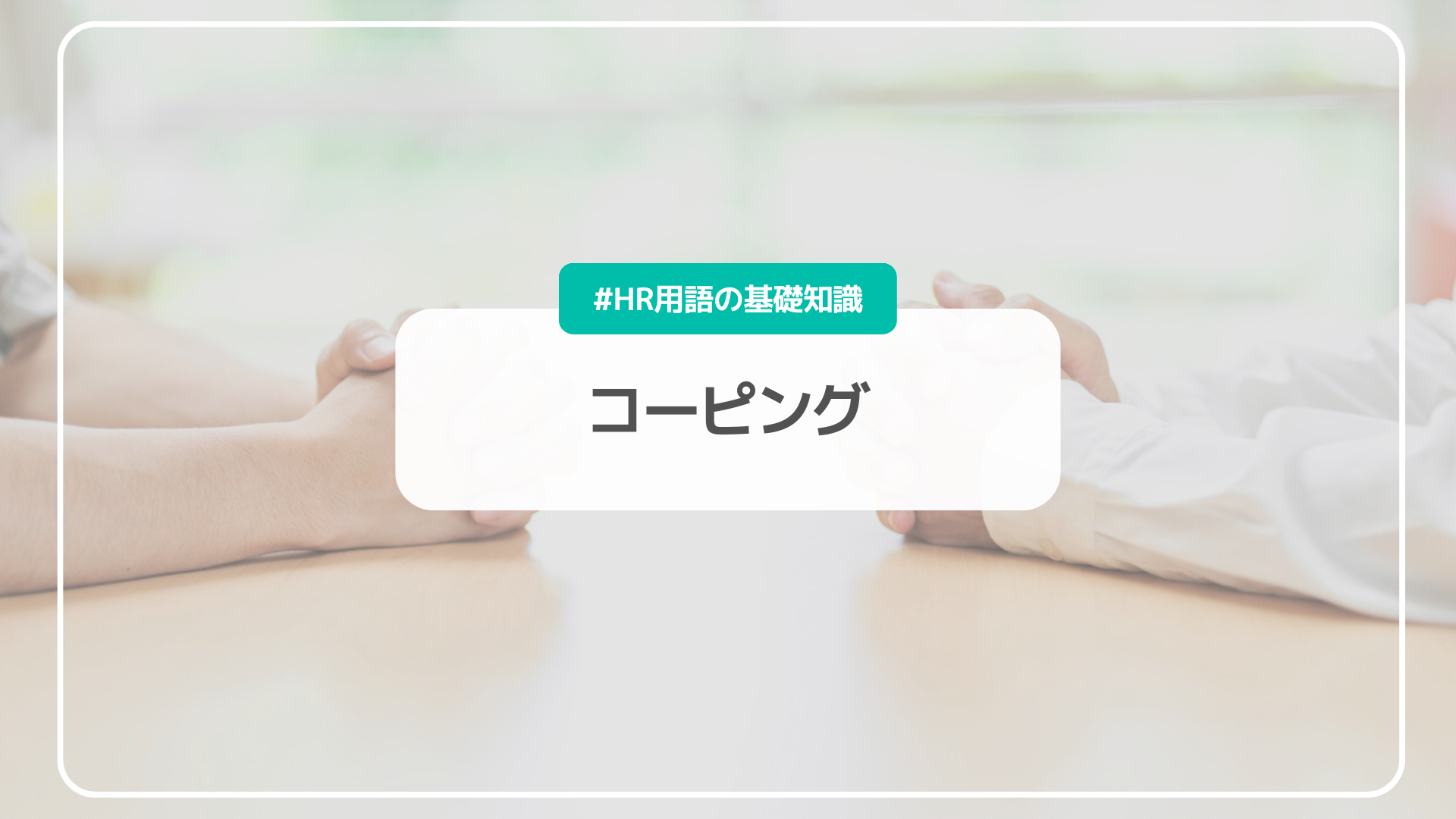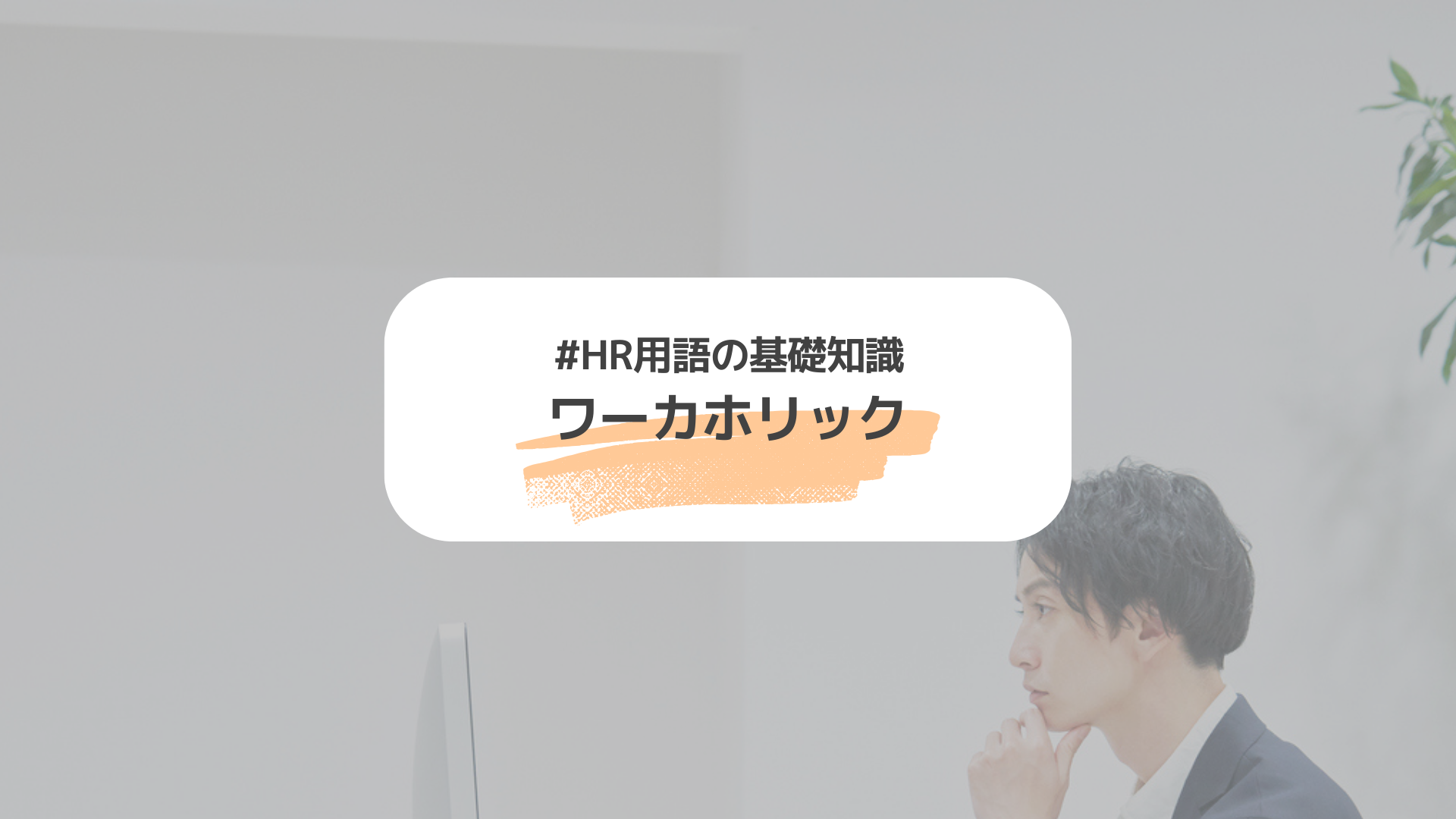
働く環境の改革を図る上で、ワーカホリックの問題は避けて通れません。ワーカホリックの問題があると、さまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
しかし、ワーカホリックという言葉を聞いたことがあっても、どのような意味を持ち、なぜ対策しなければならないのか詳しく知らない人も多いのではないでしょうか。
本記事ではまず、ワーカホリックがどのようなものか詳しく解説します。さらに、ワーカホリックになりやすい人の特徴や具体的な対策も紹介します。
ワーカホリックとは

ワーカホリックとは、プライベートより仕事を優先して、ときには自分の健康を害してまで休みを取らずに働き続けてしまう状態や人を指します。
ワーカホリックという言葉は、英単語で仕事という意味の「Work」と、アルコール中毒を意味する英単語「Alcoholic」を組み合わせた造語です。日本語では「仕事中毒」を意味します。
ワーカホリックになると体調を崩したり、精神的な問題を抱えたりするケースも見られます。
休みなく仕事をしていても、病気になってしまうと業務効率が下がります。精神的にも余裕がなくなり、新しいアイディアが出にくくなることもあります。ワーカホリックになってしまった場合は、早めに対処して治すことが重要です。
ワークエンゲージメントが高い人との違い
ワークエンゲージメントとは労働者が自身の仕事に情熱をもって積極的に取り組む状態を指します。
ワークエンゲージメントが高い人は、ワーカホリックと同様に仕事に対して積極的に取り組む傾向があります。しかし、ワーカホリックは受動的で仕事に対してネガティブなイメージを持ちます。一方で、ワークエンゲージメントが高い人は自己肯定感が高く、活発に行動する特徴があります。
ワークエンゲージメントが高い人は、仕事に対してポジティブな姿勢を持っており、ワーカホリックのように仕事をしていないと不安を感じることはありません。
ワーカホリックになりやすい人の3つの特徴

ワーカホリックになりやすい人に見られる3つの特徴を解説します。
プライベート時間も仕事のことばかり考える
プライベートの時間も仕事のことばかり考えてしまうのは、ワーカホリックになりやすい人の特徴です。
休息を無駄だと感じてしまうため、休日でも仕事をしていないと、焦燥感や不安に襲われてしまいます。さらにワーカホリックの度合いが強くなると、休むことに罪悪感を感じる人もいます。
休日も資料作りや次の仕事に向けての準備をしてしまうため、身体的にも精神的にも休まるときがありません。仕事をしている時間は長くなる一方、適度な休息をとっていないため、集中力や生産性は低下します。
集中力や生産性が低下すると、「もっと頑張らなければならない」と焦り、さらに仕事のことばかり考える悪循環に陥るケースがあるので注意が必要です。
仕事以外にやりたいことがない
「仕事以外にやりたいことがない」「夢中になれるものがない」人も、ワーカホリックになりやすい傾向にあります。仕事をしていないときの時間を持て余した結果、空いている時間すべてを仕事に使ってしまうからです。
休日や空き時間まで仕事をしてしまう場合は、自分の意識や生活を見直すべきかもしれません。仕事以外で夢中になれるものや、趣味を持つようにしましょう。
趣味として、ジム通いやジョギング、ウォーキングなど身体を動かす活動が理想的です。また、草野球やフットサルなどのチームスポーツもおすすめです。適度な運動は、ストレス解消に役立ちます。
趣味を楽しんでいる時間は、なるべく仕事のことは考えないようにしましょう。仕事以外の時間を楽しもうとする意識や充実した時間を持つだけでも、ワーカホリック対策として効果的です。
責任感が強く完璧主義
ワーカホリックになる人は、真面目で責任感が強く、完璧主義の傾向があります。
責任感が強いあまり、困難な状況に陥っても周囲を頼りません。また、周囲に仕事をふったり相談するのが苦手なため、上司や周囲の人からのサポートを上手に受けられないのが特徴です。その結果、孤立してしまうケースが多く見られます。
完璧主義が強くなると、どれだけ仕事に取り組んでも満足せず、さらに多くの時間を仕事に費やす傾向にあります。
ワーカホリックには、競争心や承認欲求が強い方が多く見られます。周囲からの認知を得ようとして、過度に努力し、結果的に空回りしているケースもあるでしょう。それにもかかわらず、本人は自覚せず、仕事に熱中してしまう傾向があります。
ワーカホリックになるデメリット

ワーカホリックになることで生じる大きなデメリットは、健康状態の悪化と人間関係の悪化です。それぞれを詳しく解説します。
健康状態の悪化
ワーカホリックは、自身の健康より仕事を優先するため、体調不良のリスクが高まります。さらに肉体的にも精神的にも疲労が溜まっていくため、健康状態が悪化しやすいのが特徴です。また、身体的な病気だけでなく、ストレスから精神面での病気にかかるリスクも高まります。
健康状態や精神状態が悪化しても、仕事を優先する姿勢が変わらないのも、ワーカホリックが持つデメリットの一つです。さらに体調を悪化させ、長期入院してしまうケースも考えられます。
人間関係の悪化
ワーカホリックは健康状態だけではなく、人間関係も悪化させます。どのようなシチュエーションでも仕事を優先するため、家族や恋人、友人などとのつながりが希薄になってしまうからです。
仕事を優先するあまり、家族と過ごす時間が減ったり友人関係も疎遠になったりと、本人に自覚がないまま孤立します。
また、仕事の悩みや不満を抱え込んで、同僚や部下に対して当たりが強くなると職場の人間関係も悪化します。
ワーカホリックの人が職場にいると、先に帰りづらくなったり、休日でも仕事の電話をしてくる、周囲の仕事量が増えるなど、一緒に働く人に迷惑や負担をかけることがあります。
結果的に、職場の雰囲気が悪くなり、周囲の人たちも仕事がしにくくなることは、ワーカホリックの大きなデメリットです。
企業ができるワーカホリックへの予防と対策

企業が組織やチームとしてできる予防と、企業が社内で働く個人それぞれに寄り添う形でできる対策を紹介します。
社内のコミュニケーションを促進する
ストレスの解消やつながりの維持は、ワーカホリックの予防になります。コミュニケーションの促進は、モチベーション向上や業務を円滑に進めるためにも重要です。
企業ができる具体的なコミュニケーション促進として、次のような施策が考えられます。
・社内イベント
社内イベントは、社内で働く者同士のコミュニケーションを促進させる手段として効果的です。部署やチームで一体感を持つことで、モチベーションの向上も期待できます。
・1on1ミーティング
1on1ミーティングは、上司と部下が1対1で行う面談です。集団のなかでは発言しづらい人もマンツーマンだと発言しやすくなるため、業務を一人で抱え込んでいないかチェックするのに適しています。
・メンター制度
メンター制度は、直属の上司ではない先輩がメンターとなり、後輩をサポートする制度です。上司には相談しづらいことも先輩には気軽に相談しやすいという特長があり、コミュニケーション促進の方法として用いられています。
・フリーアドレス
フリーアドレスは、オフィスに個人の固定席を設けず、自由に席を選べるワークスタイルです。さまざまな人と接する機会を増やせるため、コミュニケーションの活性化を期待できます。
従業員の業務量を管理する
仕事を抱え込む従業員はワーカホリックになりやすい傾向にあるため、従業員の業務量を把握するのも対策の一つです。
業務の見える化を推進した結果、業務量が多すぎる従業員がいた場合は、管理者が業務の少ない社員へ仕事を割り振るといった対策を講じることで、改善を図ります。
また、従業員の業務量を管理することは、ワーカホリックへの対策だけでなく、業務の効率化や生産性向上にも役立ちます。常に業務量を管理し、随時改善していくことが大切です。
業務に意味付けをする
ワーカホリックは、仕事をしなければならないという強迫観念から受動的な姿勢になりがちです。長期にわたって強迫観念に囚われている状態は、体調不良やメンタル面での病気につながります。
そこで、業務に意味付けすると、受動的ではなく能動的に取り組めるようになるでしょう。たとえば「この仕事は自信の成長やスキル向上につながる」「この目標を達成すれば自社に貢献できる」などです。
業務に意味づけをすると、自己肯定感をアップさせ、ワーカホリックの対策になります。
定期的にメンタルヘルスチェックを行う
企業が定期的に従業員のメンタルヘルスチェックを行い、早期発見の仕組みを整えるのも効果的です。
必要であれば専門家によるカウンセリングを提供し、従業員が適切な方法でストレスを管理できるようにします。相談できる窓口を社内に設置するのもよいでしょう。
また、厚生労働省のストレスチェック制度の実施を検討するのも一つです。労働安全衛生法の改正により、労働者のメンタルヘルス不調のリスク軽減を目的としてストレスチェック制度が導入されています。
労働安全衛生法では、常時50人以上の従業員がいる職場では1年に1回、ストレスチェックの実施が義務付けられています。
※参考:「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(厚生労働省)
社内研修を実施する
社内研修を実施して、ワーカホリックに対する知識や理解を深めましょう。社内の人々がワーカホリックを正しく理解していない状態では、予防や対策を行っても意味がありません。ワーカホリックとはどのようなものかを理解した上で、仕事に対する捉え方やタイムマネジメントの教育を行いましょう。
ワーカホリックの人は、課題の整理や解決が苦手な傾向があります。社内研修を通じて、仕事に対する基本的な考え方や効率的な課題解決方法を学ぶことが、ワーカホリックの予防につながります。企業全体の意識改革を目指して、社内研修を実施しましょう。
ワーカホリックの予防と対策を実施して働きやすい職場を実現しよう

ワーカホリックの人は、仕事に過度に集中するために休息や人間関係を疎かにする傾向があり、健康状態や人間関係が悪化するリスクがあります。
企業はメンタルチェックや社内研修を通じて予防や対策を行うことが重要です。
しかし、ワーカホリックの対策は個人が自ら意識して行動に移すことがポイントになります。こちらの記事で紹介した予防策と対策をぜひ実践してみてください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。