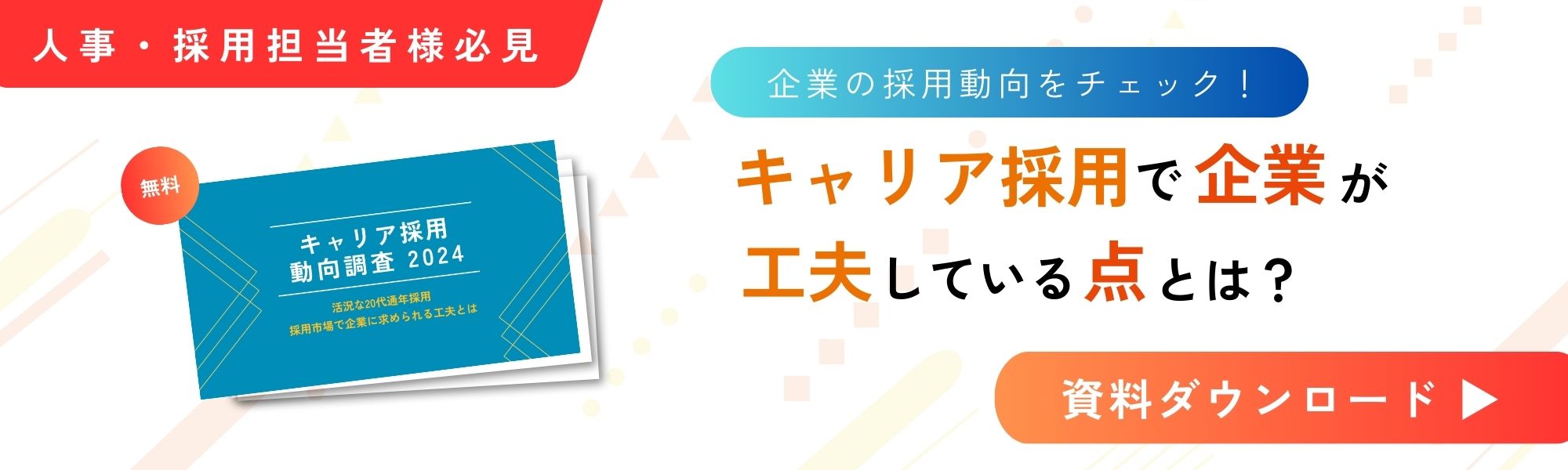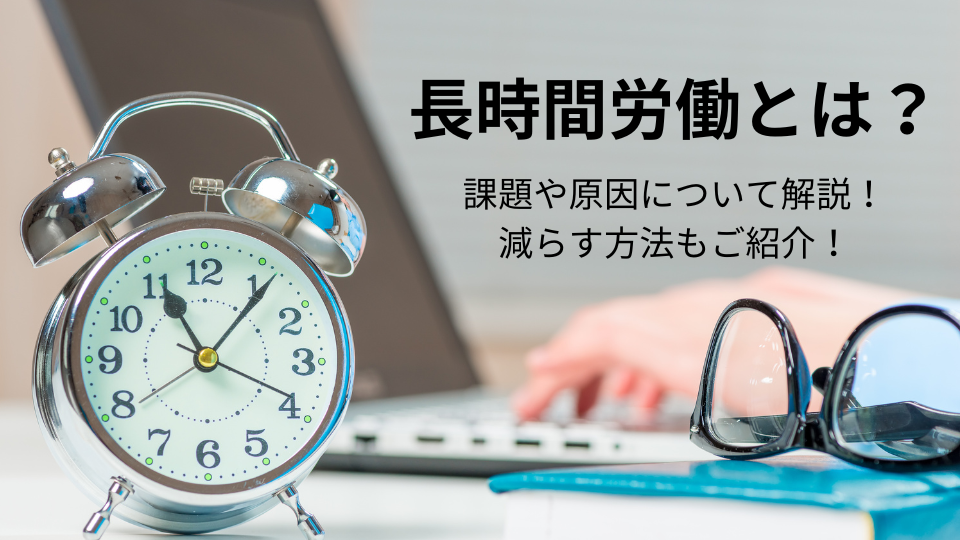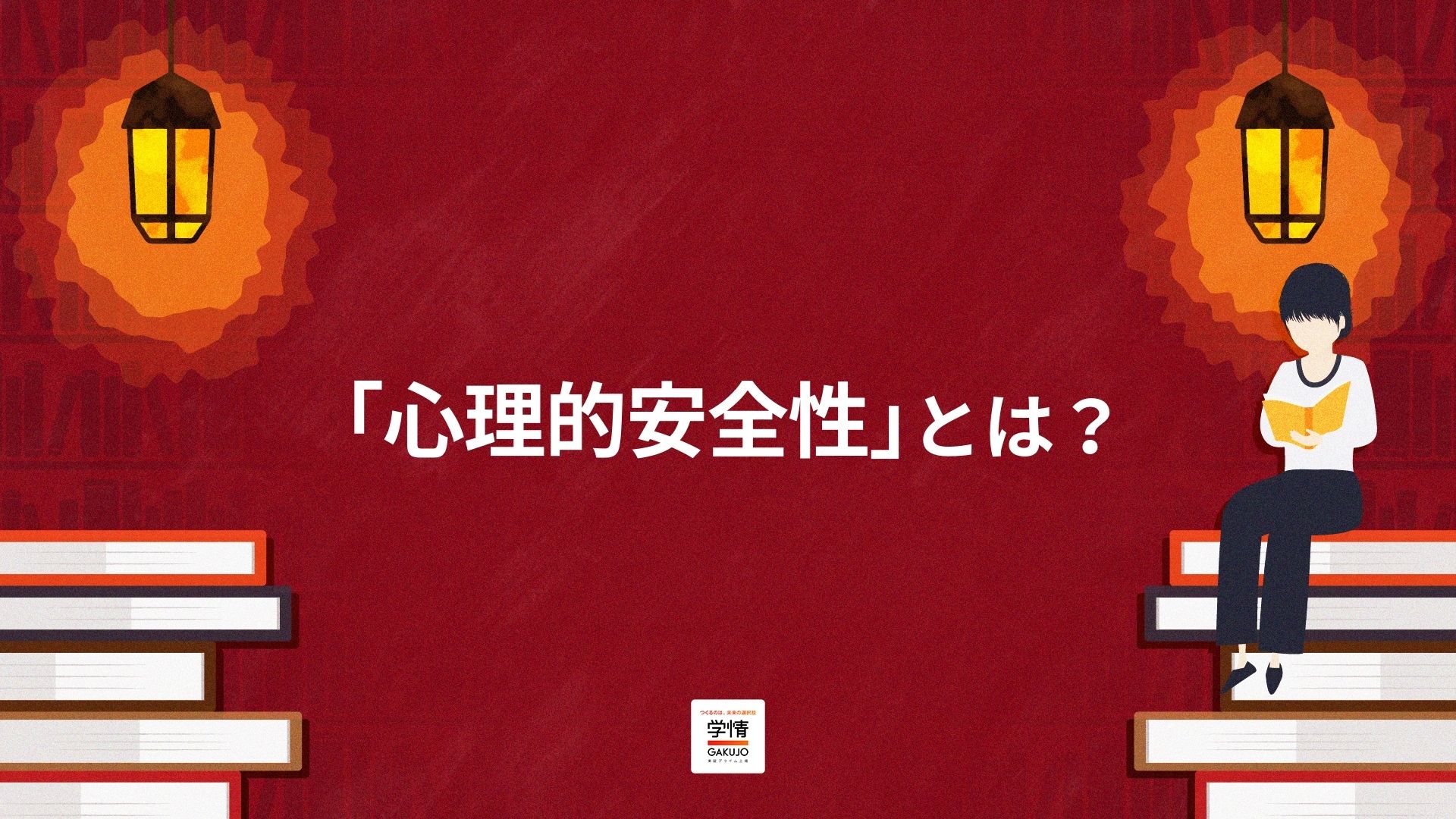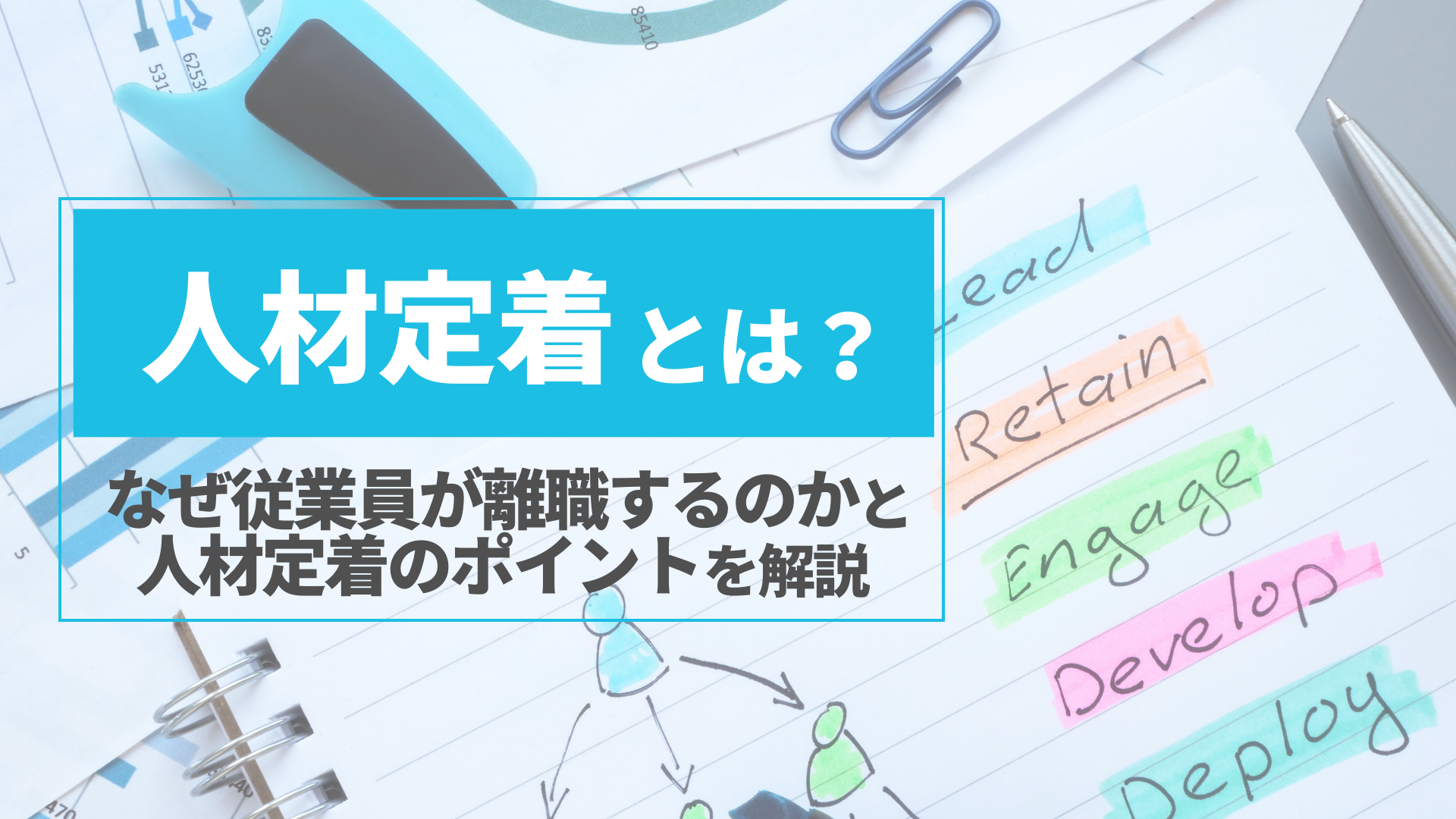リテンションとは?
現代の企業で求められる理由と期待できる効果を解説
公開日:2023.07.07
更新日:2025.02.15


リテンション(retention)とは「保持」「維持」の意味がある言葉です。おもに人事やマーケティングの領域で使われますが、それぞれ意味が異なります。
この記事では人事におけるリテンションの意味や効果、今企業で注目されている理由について分かりやすく解説します。
人事領域におけるリテンションの意味とは?

人事領域において、リテンションとは「人材の確保・維持」のことです。つまり優秀な人材が組織から離職することを防ぐ一連の取り組みのことを指します。
たとえば、給与に不満があったり、人間関係に問題が出たり、あるいはライフスタイルに合わず働きにくいと感じたりなど、さまざまな理由によって社員は離職することがあります。そこで企業側が工夫し社員が抱える悩みを解消すれば、離職防止につなげることができます。
また、リテンションに取り組むことで、社員に対し自社で働くメリットを提示でき、継続して働いてもらいやすくなります。そのため、人材不足に悩む国内企業ではリテンションが重要な課題となっています。
マーケティングにおけるリテンション
「リテンション」という言葉は人事だけでなくマーケティング用語としても使われます。マーケティングでは「既存顧客の維持」の意味があります。新規顧客へのアプローチよりも既存顧客に対する戦略を練った方が売上につながるという考え方です。
新規顧客は、商品やサービスの良さを体験していないため、いきなり初回から高額の商品を購入することは少ないでしょう。一方、既存顧客であれば、その商品やサービスに愛着を抱いているため、初回よりも高額の料金を支払う可能性が高いと言えます。新商品もしくはより高機能な製品の購入や、継続利用も見込めるでしょう。
マーケティングでは「1:5の法則」と呼ばれる考え方があり、新規顧客の獲得は既存顧客の維持に比べて5倍のコストがかかるとされています。そこでリテンションに注力することにより、既存顧客の維持に比重をかけた施策ができ、マーケティング全体のコストをおさえながら売上を伸ばすことが可能となるわけです。
企業にとってリテンションが重要な理由
企業がリテンションの概念に着目し始めたのは、人材不足がおもな原因です。特に近年は少子高齢化と団塊世代の大量退職の影響により労働人口が昔よりも減り、慢性的な人材不足が懸念されています。
総務省の「令和4年 情報通信に関する現状報告の概要」によれば、生産年齢人口(15~64歳)がピークに達したのは1995年頃で、8,716万人でした。しかし、それ以降減少が続き、2010年には8,103万人、2020年には7,509万人まで落ち込んでいます。さらに、2050年には5,275万人と1995年の約6割まで減る見込みです。
※出典:「令和4年 情報通信に関する現状報告の概要」(総務省)
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd121110.html
このように働き手が急速に減っていくなか、企業は優秀な人材を一人でも多く獲得・維持し続けなければ立ち行きません。
また、同時に人材の流動化が進んでいるのも企業にとって問題です。近年は、かつて当たり前だった年功序列・終身雇用の考え方が通用しなくなってきています。働き手はより条件の良い企業へ転職することも多く、特に新卒で入社し、入社後すぐに会社を辞めてしまうケースも後を絶ちません。
厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概況」を見ても、令和3年時点で40~59歳の男性離職率は5.5%であるのに対し、20~24歳の男性離職率は24.2%もあります。女性も同様に、26.9%の人が20~24歳で離職しています。
※出典:「令和3年雇用動向調査結果の概況」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/22-2/dl/gaikyou.pdf
このように働き手が減少し、会社に定着しにくい現状が続いているなか、多くの企業は獲得した優秀な人材を失わないために早急に対策する必要に迫られています。
リテンション施策の種類

では、具体的にどのような施策を講ずればリテンションにつながるのでしょうか。おもなリテンション施策には「金銭的報酬」と「非金銭的報酬」があげられます。
金銭的報酬
代表的なリテンション施策には金銭的報酬があります。給与を上げたり、働きに見合った給与を提示することで人材の流出を防ぎます。
金銭的報酬にはいくつかの種類があります。
- 能力に応じた給与
- 賞与
- インセンティブ
- 家賃補助や家族手当、優待などの福利厚生
- ストックオプション(※自社株の購入権利)
これらを組み合わせた金銭的報酬を用意し、社員に提示することで、社員の働く満足感や働きがい向上につなげることができます。
ただし、金銭的報酬は会社の業績に応じて設定するため、他社よりも高い報酬を必ずしも提示できない場合も少なくありません。このため、金銭的報酬だけをリテンション施策として取り入れるのは難しいと言えます。
非金銭的報酬
リテンション施策のもう一つの種類は、非金銭的報酬です。たとえば、テレワークを導入してワーク・ライフ・バランスの実現を目指したり、スキルアップやキャリア形成のサポートを行う体制づくりに注力したりと、導入できる施策はさまざまです。
ほかにも、次のような施策があげられます。
- 産休や育休の実施
- 有給休暇の取得がしやすい環境作り
- フレックスタイム制やテレワークの導入
- スキルアップ研修の実施
- コーチングやメンタリングの導入によるキャリア形成サポート
- フィットネス施設やスポーツクラブの利用権
- 社員の使いやすい設備や施設の提供
- 社員が自由に発言できる風通しの良い社風
- 部活動やレクリエーションなどによるコミュニケーションの活性化
- 社員旅行の実施
- 社内報で貢献した社員を発表する
仮に金銭的報酬に限界がある企業でも、非金銭的報酬を数多く提供することで社員にやりがいや愛社精神を持ってもらえます。他社にはない魅力を感じてもらえることで、人材が留まりやすくなるでしょう。
リテンション強化で期待できる3つのメリット

リテンションにより得られる3つのメリットを解説します。
離職の防止と採用コストの削減
リテンションによる代表的なメリットは、新たな人材を採用するコストを削減できることです。
社員が退職したら、次の人材を確保しなければなりません。離職率が高いほど採用にかけるコストが増えてしまいます。離職による穴を埋めるために多くの社員に負担がかかってしまい、さらなる離職を招いてしまう可能性があります。
リテンションによって離職を防げれば、採用コストをおさえることができ、自社の業績達成も円滑に進められるでしょう。
社員のモチベーション向上
リテンションは社員のやりがいやモチベーションの向上に役立ちます。働くなかでやりがいや自身の成長を感じてもらえれば、他社に転職する必要性を感じなくなるため、社員の離職防止につなげられるでしょう。
また、社員一人ひとりのモチベーションが向上すれば、仕事の業務効率が向上し、チームひいては会社全体の生産性もアップするはずです。
社内ノウハウの蓄積
リテンションによって、優れた人材を定着させることにより、社内のノウハウを蓄積することが可能となります。
社員の離職によって、その人が持っていた特定の技術、知識、経験など、さまざまなノウハウが会社内から消えてしまいます。さらに、競合他社に採用されると、個人のスキルや経験は他社に活用されてしまうことでしょう。
離職前の引き継ぎによって会社内の人材に伝えることができるのは非常に限られています。不必要な人材流出を防ぐためにも、リテンション強化に取り組むことはとても重要です。
リテンション強化につながる具体的な施策

では、具体的に社内のリテンションを強化するためにはどのようにしたら良いのでしょうか。具体的な施策をいくつかご紹介します。
報酬制度の見直し
まずは、社員が適切に報われているかを確認するために、報酬制度を見直しましょう。努力や成果を適切に評価し給与に反映することは、従業員のモチベーションやエンゲージメントの向上にもつながります。。
たとえば、ボーナスの回数やベース給を増やしたり、勤続年数に応じて給与を段階的に上げていく仕組みを整えましょう。同業種での転職時にはキャリアを活かす人もいるため、競合他社との賃金比較も重要です。
また、インセンティブ(報奨金)や歩合給の導入も検討しましょう。頑張った分だけ報われる給与体系は一つの手段となります。ただし、実績が上がらない社員のやる気を損なったり、社員間の関係悪化を招いたりする可能性もあるため、慎重に検討することが大切です。
社内コミュニケーションの強化
社内のコミュニケーションが活性化するような施策が有効です。社内コミュニケーションの希薄化による人間関係の悪化は離職の原因になります。
まずは、社員が自由に意見や議論を交わせる場を設けることが重要です。たとえば、定期的なミーティングやディスカッションの場を設けることで、社員同士のコミュニケーションを活発化させることができます。また、社内のレクリエーションやイベントを通じて、社員同士の交流を深めることも有効です。
また、横の関係だけでなく縦の関係にも気を配る必要があります。1on1ミーティングを定期的に行い、上司が部下の悩みや相談事に対応できる環境を整えることが重要です。一部の企業では、若手社員が上司に対して助言や指導を行う「リバースメンタリング」という制度を取り入れています。
社員のなかには他の人になかなか相談できない悩みや不満を抱えているケースもあります。こうした場合には、アンケートや意見箱を設置し、匿名で意見を募ることもできます。これにより、社内の人間関係やシステムの改善に役立つ貴重な情報を収集することができます。
ワーク・ライフ・バランスの見直し
プライベートと仕事を両立できるかどうか、ワーク・ライフ・バランスも見直していきましょう。自社において、有給休暇の消化率が低すぎないか、あるいは残業が多すぎないかといったことを確認します。
また、20代や30代の若手社員が多い企業の場合は、産休や育休を取りやすい環境も重要です。その際は、休みを取る社員の業務を均等に分担できる柔軟な組織体制が求められるでしょう。テレワークやフレックスタイムの導入も検討することも大切です。これにより、社員が自由に働き方を選ぶことができるため、育休や産休を取る社員への支援策としても役立ちます。
特に若手社員は結婚や出産、子育て、引越しといったライフスタイルの変化が多いです。柔軟な働き方ができる環境を整えることで、ワーク・ライフ・バランスの見直しができ、転職のきっかけになるリスクを軽減できます。
キャリア形成の支援
キャリア形成をサポートする取り組みも有効な施策の一つです。たとえば研修や資格取得の機会を積極的に設けることで、社員の能力が高まります。会社に在籍することで着実に成長していると社員自身が実感できれば、他社への流出を防ぎやすくなるでしょう。
研修で新たなスキルを身につけたり、資格という目に見えるかたちでの成果を得たりすることは社員のモチベーションを大きく向上させます。ほかにもキャリアコンサルタントの導入、社内公募制の実施などもキャリア形成の支援に有効な方法だと言えます。
社員への権限委譲
社員へ権限の一部を移譲し、自分の裁量で仕事を進められるようにするのもリテンションに有効です。社員が一定の権限を持つことで仕事に対する責任が強く生まれ、仕事へのモチベーションが向上します。
また、社員が自分の判断で仕事を進められることで、上司の業務負担も軽減できるため、結果的に組織内の業務が円滑に進みやすくなるでしょう。
このように、社員がこれまでよりも自分の裁量で進められる仕事を多く持つことで、スキルアップの機会も増えます。経験や技術を磨いて自身の成長を感じられれば、「この会社に在籍してよかった。これからも働き続けたい」と自然と感じてもらえるようになるはずです。
人事制度の見直し
人事制度を見直し、社員が自分の得意な分野で働けているかどうかを確認する必要があります。適材適所という言葉がありますが、同じ社員でも得意な分野と苦手な分野によって成果が大きく変わります。適材適所が実現できていないと、社員が成果が思うように出せないと焦りや不満が生まれ、最終的には離職の原因になるかもしれません。
もし実績があまり上がっていない社員がいる場合は、スキルや適性を見直し、人材の再配置を検討することが良いでしょう。また、社内公募制度を導入し、本人自身が希望する部署・ポジションに転換させることも一つの方法です。
さらに、評価制度も見直すことも重要です。評価の基準を提示し、一定の業務期間を終えたタイミングで適切な評価を伝えることで、社員のモチベーションを向上させることができます。努力しても報われないことや、曖昧な基準での評価がないように、細かなルールを制定することで、公平で透明性のある評価が可能になります。
社員が自分の努力が正当に評価される環境を整えていきましょう。
リテンションで社員の定着率を向上させよう

リテンションとは人事において「人材の確保・維持」を意味します。少子高齢化や団塊世代の大量退職などにより働き手が減っている今、優秀な人材の流出をくい止めるリテンションに注目が集まっています。採用コストの軽減や長期的なノウハウの蓄積がしやすくなるのもメリットです。
リテンションの方法は金銭的報酬、非金銭的報酬を組み合わせるのが一般的で、特に非金銭的報酬は企業によってさまざまな工夫を凝らす余地があります。ライフスタイルの変化に合わせて働きやすい環境、キャリア形成やスキルアップの支援、あるいは社員同士のコミュニケーションを活性化させる場の提供など、できることから始めていきましょう。
リテンションにより、社員の業務へのモチベーションを向上させ愛社精神を養い、長く貢献してもらえる会社を目指してください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。