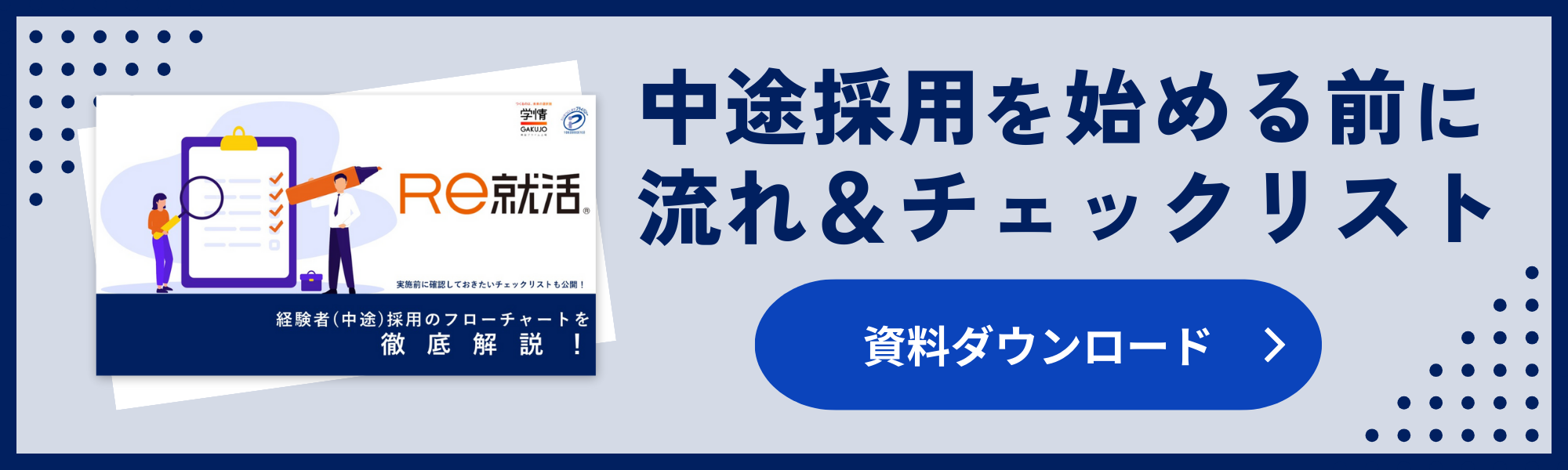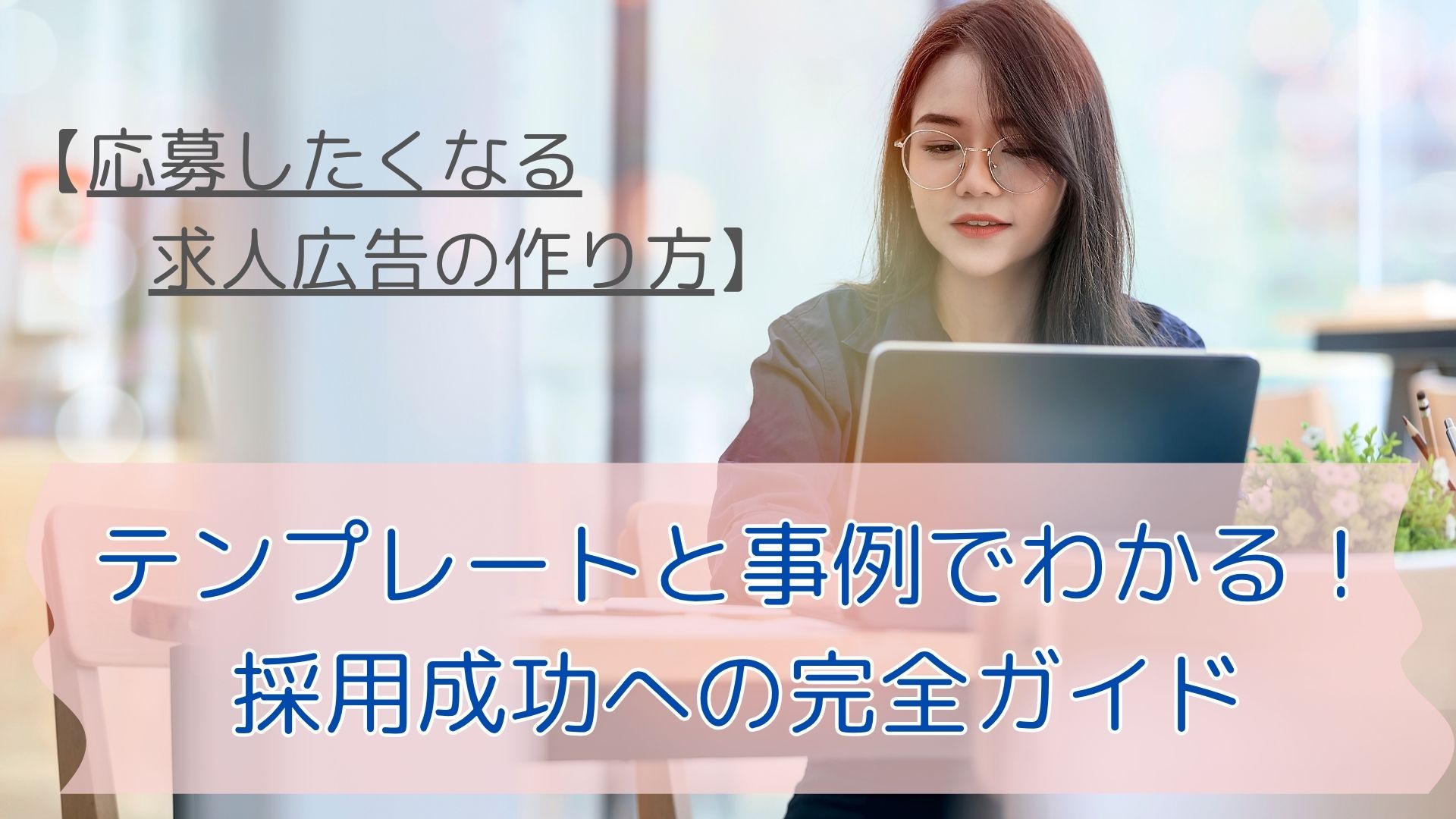特定の業界で働く人や職種のことを、「〇〇カラー」と呼称されることがあります。採用活動を担当する際には、募集する職種が何カラーと呼ばれているのか、どのような特徴があり、どのような採用手法が効果的なのか、今一度確認しておくことが大切です。
本記事では、特定の業種や職種に該当する「ブルーカラー」について詳しく解説します。ほかの〇〇カラーの特徴やブルーカラーで応募者を集める方法も紹介するので、自社の採用活動に役立つ情報が見つかるはずです。
ブルーカラーとは

ブルーカラーとは建設業や製造業などの現場で、生産業務に携わる労働者を指します。青い襟の作業服を着用するケースが多かったため、ブルーカラーと呼ばれるようになったという経緯があります。
ブルーカラーに該当する仕事内容には、次のような専門知識や高い技術、技能が必要なものも含まれています。
- 溶接
- 塗装
- 特殊車両の運転
- 重機の操作 など
たとえば、重機オペレーターや旅客機のパイロットもブルーカラーの一つです。ブルーカラーに該当する業界や職種については、「ブルーカラーに該当する業界や職種」で詳しく紹介します。
ほかの〇〇カラーとの違い

ブルーカラー以外にも、○○カラーと呼ばれる職種があります。採用担当者としてそれぞれの特徴を把握しておきましょう。
ホワイトカラー
ホワイトカラーとは、襟が白いワイシャツを着用して業務を行う労働者です。スーツにネクタイを締め、デスクや人に向かって仕事をしている人を指します。
基本的には、生産に直接関与しない職種を指します。ホワイトカラーの代表的な職種は、次のとおりです。
- 一般事務
- 営業事務
- 総務事務
- 経理事務
- 企画職
- エンジニア
- 弁護士
- 税理士
- 医師 など
このほかには、特定分野に関する研究職や技術職もホワイトカラーに含まれます。
グレーカラー
ブルーカラーとホワイトカラーの中間的な仕事を行う労働者を指します。グレーカラーはブルーカラーやホワイトカラーとは異なり、襟の色が由来の言葉ではありません。
グレーカラーという言葉が生まれた背景には、時代の流れとともに技術が進化し、ホワイトカラーやブルーカラーに分類されない職種が増えてきたことが関係しています。
グレーカラーの代表的な職種は、次のとおりです。
- 生産管理者
- 保安職業従事者
- 情報処理技術者 など
グレーカラーの職種に明確な定義はないものの、一般的には専門職や技術職を指します。
グリーンカラー
おもに環境関連の分野に携わる労働者を指します。言葉の由来は、英語の「Green」に環境保護主義という意味があるからです。グレーカラーと同様、言葉に襟の色は関係していません。
グリーンカラーの代表的な業種は、次のとおりです。
- リサイクル事業
- 林業
- 太陽光発電事業
- 風力発電事業 など
たとえば、太陽光発電の建設に関わる労働者の場合、環境関連の分野に携わるグリーンカラーと、生産業務に携わるブルーカラーの両方に該当するといえます。
ブルーカラーに該当する業界や職種

建設業
建設業は、建設作業や土木作業など建物に関する事業を手掛ける業界です。建設業でブルーカラーに該当する職種は、次のとおりです。
- 型枠解体工
- 足場組立工
- 土木鉄筋工
- 塗装工
- クレーン運転工
- 建築ブロック工
- 左官
- 配管工
- 造園土木作業員 など
職種によっては、法律に基づいて建物を建設したり解体したりします。そのため専門的な知識と技術が必要です。
建物以外にも、道路やダムなどのインフラ工事に携わる労働者もブルーカラーに含まれます。
製造業
製造業は、日用品や家電製品などのさまざまな製品を製造する業種です。製造業でブルーカラーに該当する職種は、次のとおりです。
- 自動車組立設備オペレーター
- アーク溶接工
- 鋳物用鉄溶融工
- 鋳物用鉄溶融設備オペレーター
- スナック菓子製造設備オペレーター
- アルミニウム鋳物工 など
作業には、専門的な知識と技術を必要とするケースも珍しくありません。たとえば自動車は約4,000種類もの部品で構成されており、組み立て工程ではすべての部品を正確に取り付ける必要があります。
また、品質管理や製品の仕分け、検品、梱包に携わる労働者もブルーカラーに該当します。
運輸業
運輸業は、貨物や旅客の運送に関わる業種です。運輸業でブルーカラーに該当する職種は、次のとおりです。
- 電車運転士
- バス運転手
- 宅配便配達員
- 大型トラック運転手
- 貨客船船長
- 航海士
- 船舶機関長
- 航空機操縦士
- 車掌 など
基本的に荷物の運搬や配達に携わる労働者は、ブルーカラーに該当します。また、飛行機や船を操縦して人を運ぶ、航空機操縦士や貨客船船長もブルーカラーです。
鉱業
鉱業は、鉱脈や鉱石から地下資源を取り出す業種です。鉱業でブルーカラーに該当する職種は、次のとおりです。
- 採鉱員
- 石切出作業員
- じゃり・砂・粘土採取作業員
- 石油採取機運転工
- 発破員
- ショベルカー運転工
- 坑内支柱員 など
鉱業のうち、ブルーカラーに該当するのは、おもに鉱山資源を掘削する労働者です。
従来、掘削は手作業で行うのが一般的でした。しかし近年、掘削の効率化や作業員の安全性を向上させるために、重機を使用するケースが増えています。そのため、掘削作業で重機を操作する労働者も、ブルーカラーに該当します。
農林水産業
農林水産業とは、人が生きていく上で必要な食に関する業種です。業種には、農業・林業・水産業が含まれています。農林水産業でブルーカラーに該当する職種は、次のとおりです。
【農業】
- 農耕作業員
- 養畜作業員
- 植木職
- 造園師 など
【林業】
- 育林作業員
- 伐木作業員
- 造材作業員
- 集材作業員 など
【漁業】
- 漁労作業員
- 漁労船の船長・航海士・機関長・機関士
- 海藻・貝類採取作業員
- 水産養殖作業員 など
農林水産業は手作業が必要な職種が多く、肉体労働がメインです。しかし、近年は機械の導入が進み、作業効率化が図れるようになりました。
サービス業
サービス業は、人の暮らしを支えるサービスを提供する業種です。サービス業でブルーカラーに該当する職種は、次のとおりです。
- 修理工
- 自動車整備士
- 警備員
- 清掃員 など
サービス業のうち、修理や整備、警備などに携わる労働者はブルーカラーに該当します。
ブルーカラーの現況

近年は、さまざまな業界で人手不足が社会問題化しています。中でも、ブルーカラーに該当する業界の人手不足は深刻な状態です。
厚生労働省の「労働経済動向調査(令和3年8月)の概況」によると、特に建設業・運輸業において、人手不足が深刻な状態に陥っていることが分かっています。
| 産業 | 不足 | 過剰 |
| 建設業 | 50% | 0% |
| 製造業 | 35% | 7% |
| 情報通信業 | 35% | 2% |
| 運輸業・郵便業 | 42% | 4% |
| 卸売業・小売業 | 18% | 4% |
| 金融業・保険業 | 10% | 1% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 33% | 2% |
| 学術研究・専門・技術サービス | 34% | 6% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 16% | 4% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 33% | 6% |
| 医療・福祉 | 45% | 4% |
| サービス業 | 31% | 4% |
建設業・運輸業以外の業界でも、過剰な労働者を抱えているケースは少なく、いずれの業界も今後人手不足に陥る可能性があります。
ブルーカラーへの応募者を集める方法

厚生労働省の調査から分かるように、一部の業界ではすでに人手不足に陥っています。このような状況の中でブルーカラーの応募者を集めるには、何らかの工夫が必要です。
ここからは、ブルーカラーの職種により多くの応募者を集める方法を解説します。
採用の間口を広げる
総務省の「情報通信白書(令和4年度版)」によると、少子高齢化に伴い、国内の生産年齢人口は1995年をピークに減少傾向にあることが分かっています。
すでに人手が不足しているブルーカラーで人材を確保するには、外国人の採用を検討するのも手段の一つです。
外国人の採用を検討する場合、出入国管理及び難民認定法や労働施策総合推進法などの法律を遵守する必要があり、企業の担当者にはそれらの法律に関する知識が求められます。
また、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野においては、特定技能の在留資格制度を利用して、外国人を雇用することが可能です。
たとえば「ビルクリーニング」や「産業機械製造業」「建設」「造船・ 舶用工業」「自動車整備」「航空」「農業」「漁業」といった分野が該当します。
ただし、特定技能制度の利用には一定の条件があります。制度の詳細は、出入国在留管理庁のサイトでご確認ください。
労働環境を見直す
生産年齢人口が減少傾向にあっても、工夫次第ではブルーカラーへの応募者を集めることが可能です。
たとえば、「有休消化率を上げる」「給与が適正額かどうか定期的に見直す」「労働者のメンタルヘルス対策を行う」といった工夫があげられます。労働環境が求職者にとって魅力的であれば、他社の求人と差別化を図れるでしょう。
近年、ワーク・ライフ・バランスを重視する人が増えています。確保した人材に長く働いてもらうためにも、労働環境の見直しを行いましょう。
また、労働環境が改善されれば、既存の従業員の離職を防ぎ、人材不足の解消にもつながります。
訴求ポイントを整理する
ブルーカラーへの応募を集めるには、求人の訴求ポイントを整理することも大切です。魅力的で応募しやすい求人であれば、応募者を集められる可能性があります。
求人では、次のようなブルーカラーならではのメリットを打ち出します。
- 未経験でもチャレンジしやすい
- 専門的なスキルを身につけられる
- ワーク・ライフ・バランスを実現できる
ブルーカラーには、専門知識が求められるといったイメージを持つ人もいます。そのため、未経験者でもチャレンジしやすいことが分かれば、応募への動機付けになるでしょう。
また、専門的なスキルを身につけられるのも、ブルーカラーのメリットの一つです。専門的なスキルを取得すれば、安定的に長く働けます。
さらに、ワーク・ライフ・バランスを実現することも可能です。ブルーカラーの業務は納期に合わせて計画的に進められるため、残業が少なく、定時に終業するケースが多い傾向にあります。仕事とプライベートを両立できる点も訴求ポイントになるでしょう。
スカウト型採用を導入する
ブルーカラーの応募者を集めるには、スカウト型採用を導入するのも選択肢の一つです。
スカウト型採用とは、企業から応募者に直接アプローチして人材獲得につなげる採用手法です。自社が求める人材を選定した上でアプローチできるため、採用後のミスマッチを軽減できます。
Re就活は、登録会員の93.3%が20代のため、社会人経験のある若手の人材にアプローチできます。スカウト機能では基本属性や志向性などの詳細な条件から、自社が求める人材の条件を絞り込み、スカウトメールを送信できます。自動配信機能を利用すれば、より効率的な採用活動が実現可能です。
ぜひチェックしてみてください。
工夫してブルーカラーの人材を確保しよう

ブルーカラーとは建設業や製造業などで生産業務に携わる労働者を指します。
現在、ブルーカラーに限らず、多くの業種や職種が人手不足を課題に抱えています。このような状況の中でブルーカラーの人材を確保するには、労働環境の見直しや採用の間口を広げるなど、さまざまな工夫が必要です。
求人ではブルーカラーならではのメリットを打ち出し、他社やほかの職種との差別化を図りましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。