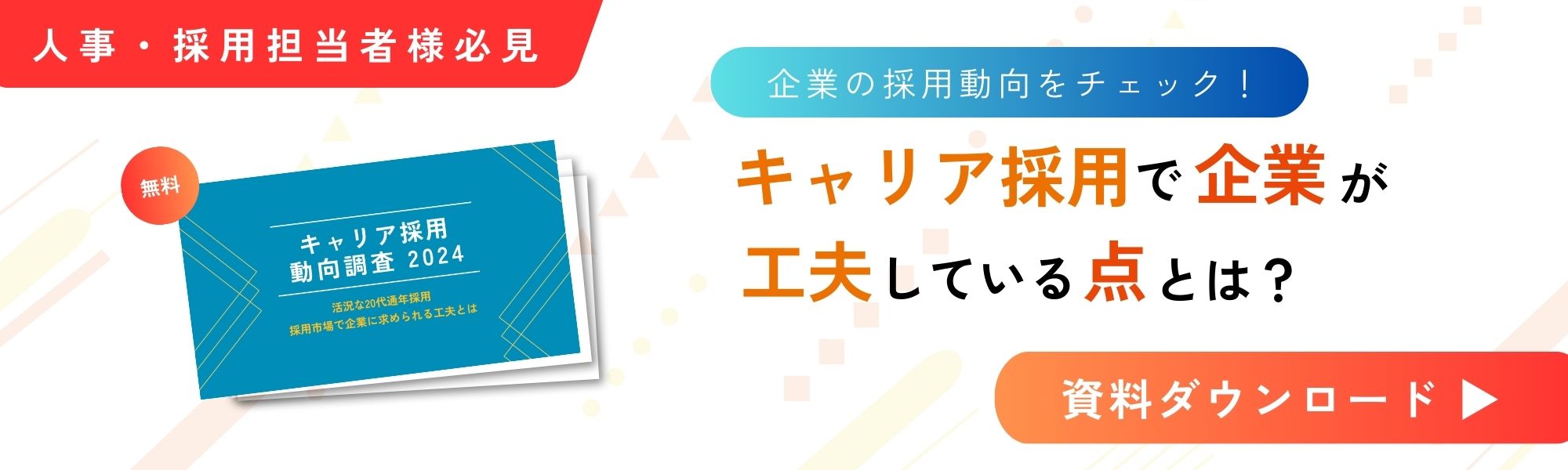経営戦略を立てるにあたって「ケイパビリティを活用すると良い」という話を耳にしたことがあるかもしれません。ケイパビリティとは、直訳すると「能力」や「才能」を意味します。企業経営においては、どのような意味で使われているのでしょうか。
本記事では、ケイパビリティの意味やメリット、また企業全体でケイパビリティを高める方法について説明します。
今後の経営戦略にケイパビリティを活用したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
ケイパビリティとは

企業経営におけるケイパビリティとは、企業が事業を遂行するために必要な知識、技能、ノウハウ、組織文化、人材などのリソースを統合し、独自に形成された、持続的な競争優位性を生み出す力のことを指します。端的にまとめるなら「バリューチェーン全体を通じた組織の遂行能力」と言えます。
ここからは、語源から分かる意味、ビジネスシーンでの定義、コアコンピタンスとの違いから解説していきます。
語源から分かる意味
ケイパビリティ(capability)は、日本語に訳すと次の意味を持ちます。
- 能力
- 機能
- 才能
- 素質
- 将来性
- 可能性 など
企業経営におけるケイパビリティは、これらすべての意味合いを総括した捉え方となり、組織全体の強みを意味する用語となります。
ビジネスシーンでの定義・具体例
ビジネスにおけるケイパビリティは、1992年にボストン・コンサルティング・グループの3人により「バリューチェーン全体を通じた組織の遂行能力である」と定義されました。
具体的には、次のような組織の力を指します。
- 他社にはない商品デザイン
- 高品質な商品やサービス
- 価格の優位性
- 独創的な店舗レイアウト
- 配送システムの効率化 など
これら企業のケイパビリティを構成する要素がほかよりも優れていれば、環境の変化に対応でき、市場競争に勝ち抜くことが可能となります。ケイパビリティは、企業経営の重要な要素の一つであり、戦略的な観点から捉えることが求められています。
コアコンピタンスとの違い
ケイパビリティと同様の意味合いでよく使われる用語が「コアコンピタンス」です。
ケイパビリティが組織全体の強みや能力を指すのに対し、コアコンピタンスは企業の中核を担う技術や能力など、特定の強みを指すといった違いがあります。
なお、ケイパビリティとコアコンピタンスは、相互に関係している側面があります。ケイパビリティが機能しているからこそ、コアコンピタンスを活かすことが可能となります。また、コアコンピタンスを軸としてケイパビリティを強化することができると言えます。
ケイパビリティは企業にとって重要な指標

ケイパビリティは、企業が市場に対応するために重要な指標となります。
グローバル化やIT技術のめざましい進化、新型コロナウィルスの影響や世界各地で起こる紛争など、近い将来でさえ予測が立てにくいとされるVUCA(ブーカ)の時代の現代において、外的要因に左右されやすい企業体質は今の時流に対応しきれなくなりました。
そこで、外的要因の変化にも対応するケイパビリティを企業経営の重要指標と置くことで、市場において安定的な成長を期待することができます。
企業経営におけるケイパビリティの強化が、今後、企業が生き残るために求められる戦略の一つになると言えるでしょう。
ケイパビリティを活かした企業経営をするメリット

ケイパビリティを活用して企業経営するメリットとして、次の2点が考えられます。
- 競合他社との差別化を図りやすい
- 事業の安定・継続に期待できる
それぞれ解説します。
競合他社との差別化を図りやすい
ケイパビリティの強化によって、競合他社との差別化を図れます。ケイパビリティの特徴として「模倣の難しさ」があげられるからです。
ケイパビリティは、企業における事業プロセスを確立させる上で、独自性と組織力がなければ強化できません。組織そのものの強みとなるため、ほかの企業が簡単に模倣することはできないのです。
そのためケイパビリティを強化することで、競合他社より優位に立ち、市場にもアピールすることができます。
事業の安定・継続に期待できる
事業の安定化や継続性強化においても、ケイパビリティは大きく寄与します。
事業プロセスや経営基盤に基づき、企業の組織力を強化できるのがケイパビリティです。企業内でケイパビリティを確立させることができれば、経営が外的要因に左右されにくくなり、経営の安定性が見込めます。経営が安定することで収益性も高まり、事業の長期的な継続も期待できるでしょう。
ただし、ケイパビリティが市場のニーズと合致していなければ、それほど有効なものにはならないので注意が必要です。ケイパビリティをうまく生かすには、市場のニーズを満たしている必要があります。
ケイパビリティを把握する2つの方法

企業におけるケイパビリティを把握するためには、次にあげる2つのフレームワークを使うとよいでしょう。
- SWOT分析
- バリューチェーン分析
それぞれについて、詳しく説明します。
SWOT分析
SWOT分析は「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の4項目で事業内容を分析するフレームワークです。
SWOT分析によって、自社の内部環境と外部環境を明確にさせましょう。
| プラス要因 | マイナス要因 | |
| 内部環境 | Strength | Weakness |
| 外部環境 | Oppotunity | Threat |
- Strength(強み):内部環境のプラス要素(自社の持つ強み)
- Weakness(弱み):内部環境のマイナス要素(自社の弱点)
- Opportunity(機会):外部環境のプラス要素(市場における機会創出)
- Threat(脅威):外部環境のマイナス要素(市場にある脅威)
SWOT分析によって、効果的な経営やマーケティング戦略が立てられます。また、事業の改善点や新規事業のリスクの洗い出しにも効果的です。
内部環境(技術力・ブランド力・サービスなど)と外部環境(市場規模・経済状況・競合の状況など)を合わせて考えることで、自社のケイパビリティが相対的に分析・認識できます。
バリューチェーン分析
バリューチェーン分析とは、自社にどのような付加価値があるか可視化して分析するフレームワークのことを指します。
バリューチェーンとは、原材料から商品が顧客の手にわたるまでの一連の流れにおいて、さまざまな付加価値が連鎖して加わっているという考え方です。生産から消費までに関わる「主活動」(製造・出荷・販売など)と、直接生産などに関わらない「支援活動」(人事・労務・開発など)に分けられます。
バリューチェーン分析は、次のフローで進めるのが一般的です。
- 「主活動」・「支援活動」を細かく洗い出し、可視化する
- それぞれの活動における必要コストを算出する
- 競合と比較し、分析する
バリューチェーンは業種によって内容が異なるため、自社に合わせた分析が必要となります。さらに、SWOT分析も一緒に活用することで、自社におけるケイパビリティ強化にもつなげられます。
ケイパビリティを高める3つの方法

ケイパビリティを高める方法として、次の3つがあげられます。
- 自社の人材育成
- ダイナミック・ケイパビリティ戦略の実施
- ケイパビリティ・ベース競争戦略の実施
自社の人材育成
ケイパビリティの向上には、人材育成が必須です。経営戦略を立てる上で、人材が最も大切な要素なのは間違いありません。
人材育成により社員個人が成長することで、企業の成長にもつながります。具体的な教育の一例は、次のとおりです。
| 人材育成法 | 特徴 |
| OJT |
|
| eラーニング |
|
| メンター制度 |
|
| ジョブローテーション |
|
社員の視野を広げる意味でも、幅広く知識を得られる教育が望まれます。
ダイナミック・ケイパビリティ戦略の実施
ダイナミック・ケイパビリティ戦略は「変化対応力」「自己変革力」とも呼ばれ、変化の激しい環境に柔軟に対応するために組織が行う経営戦略のことです。
ダイナミック・ケイパビリティ戦略には「捕捉(Seizing)」「変革(Transforming)」「感知(Sensing)」の3つのプロセスが求められます。
- 捕捉(Seizing):企業内の資源を応用し、再利用する
- 変革(Transforming):社内の資源を再構築し、変容させる
- 感知(Sensing):企業の経営環境を観察・察知する
これら3つのプロセスにより、市場の変化に合わせて企業の経営体制を柔軟にコントロールします。
また、社内における「デジタルトランスフォーメーション(DX)」の導入も必要不可欠です。
デジタル・トランスフォーメーション(DX)とは、デジタル技術を活用して商品・サービスの提供や開発、さらに社会制度や組織文化なども変革させる取り組みのことを指します。社内の業務効率化を図れるため、ダイナミック・ケイパビリティ戦略において重要な施策だと言えます。
ケイパビリティ・ベース競争戦略の実施
ケイパビリティ・ベース競争戦略とは、ケイパビリティを経営戦略のベースとして、競合との競争を優位にする戦略のことを指します。
ケイパビリティ・ベース競争戦略は、4つの原則に沿って進めるのが基本です。
- ビジネスプロセスを構成要素とする
- 既存のビジネスプロセスを有効活用する
- 部門間のインフラを整備し、戦略的ケイパビリティを構築する
- 経営陣が積極的に推進する
これら4つを実践することによって、競争力を兼ね備えたケイパビリティを構築できます。
ケイパビリティを高める際の確認ポイント

ケイパビリティの向上を図るには、次にあげるポイントを確認しながら進めるとよいでしょう。
- 長期的な視点で取り組む
- 市場ニーズの変化を把握・対応し続ける
- 外部サービス・ツールを活用する
それぞれについて、詳しく説明します。
長期的な視点で取り組む
ケイパビリティは、組織の人材育成によって高めていくものです。人材育成には時間がかかるため、すぐに結果が出るものではありません。
また人材育成も成功するとは限らず、うまくいかないケースも考えられます。
そのためケイパビリティへの取り組みは長期的に捉え、粘り強く継続し、必要に応じて検証と改善を繰り返すことが求められるでしょう。
市場ニーズの変化を把握・対応し続ける
ケイパビリティを高めるためには、市場のニーズに合わせた事業プロセスを確立することが不可欠です。市場のニーズに応えることで、顧客に価値を提供し、競争優位性を獲得することができます。そのため、市場の動向やトレンドを正確に把握し、迅速かつ適切に対応することが重要です。
また、市場のニーズは常に変化していくため、企業は改善を繰り返しながら、新しい価値を創造することが求められます。そのような状況下で、ダイナミック・ケイパビリティの活用が不可欠であり、市場の変化に合わせてケイパビリティを適切に再構築し続けることが求められます。
外部サービス・ツールを活用する
ケイパビリティを高めるためには、企業自身の力だけでは限界があります。外部の専門サービス、ツールを活用することが不可欠です。
たとえば、業務プロセスの改善や効率化には、プロセスマップ作成ツールや業務フロー自動化ツールなどが役立ちます。また、市場調査や競合分析などには、外部の調査会社やコンサルタントのサポートが必要です。
専門の外部サービス・ツールを活用することで、企業は自社の強みを最大限に活かすことができます。また、外部からのアドバイスや知見を取り入れることで、新しいアイディアや視点を得ることもできるでしょう。
ケイパビリティの強化で企業の市場価値を高めよう

ケイパビリティは「バリューチェーン全体を通じた組織の遂行能力」と定義され、企業の市場価値を高めるには非常に有効な施策だと言えます。
企業の市場価値を高めるためには、競合他社との差別化が必要不可欠です。そのためには、企業が持つケイパビリティを強化することが求められます。
まず市場のニーズを把握し、それに合わせて事業プロセスを長期的な視点で改善することが必要です。また、外部の専門サービスやツールを活用することで、よりケイパビリティを高めていくことができます。さらに、ダイナミック・ケイパビリティ戦略と呼ばれる、環境の変化に応じてケイパビリティを適切に再構築することも必要です。
変化が激しい今の時代を生き抜くためにも、企業は自社の市場価値を高めるために、継続的にケイパビリティを見直していきましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。