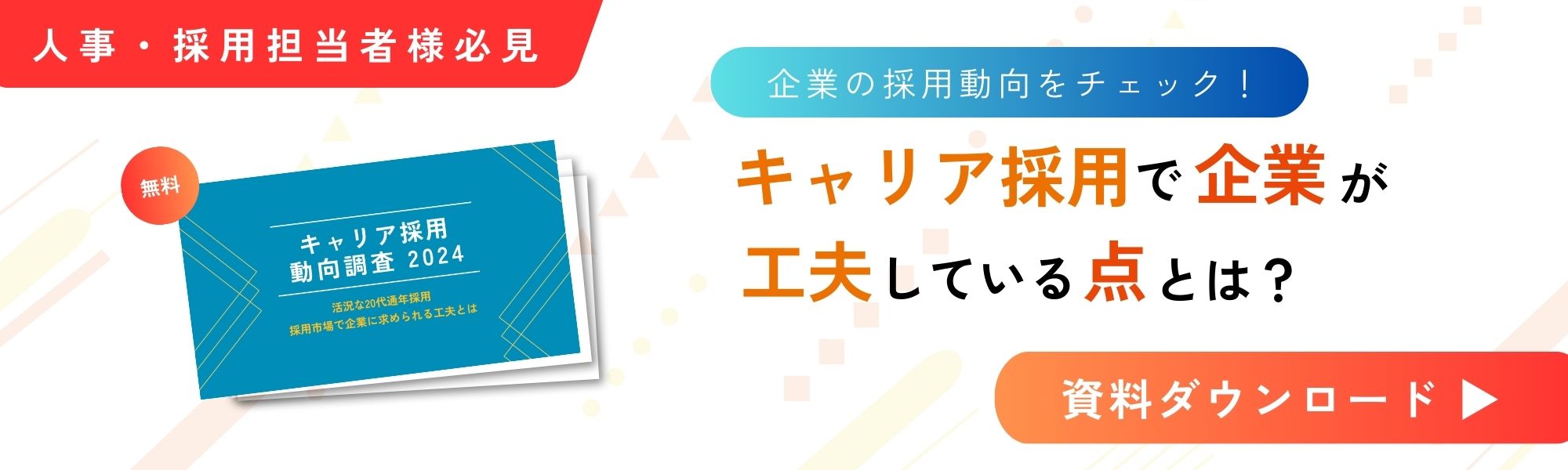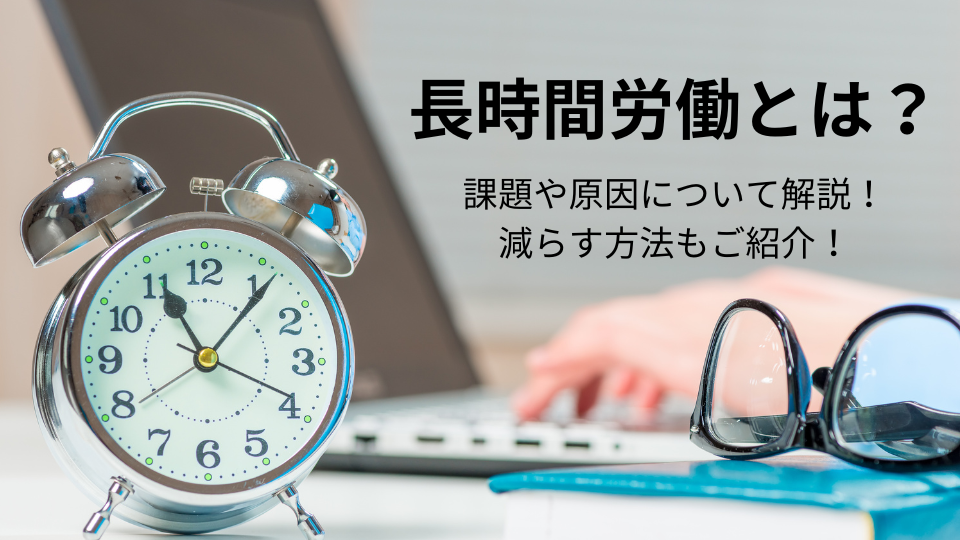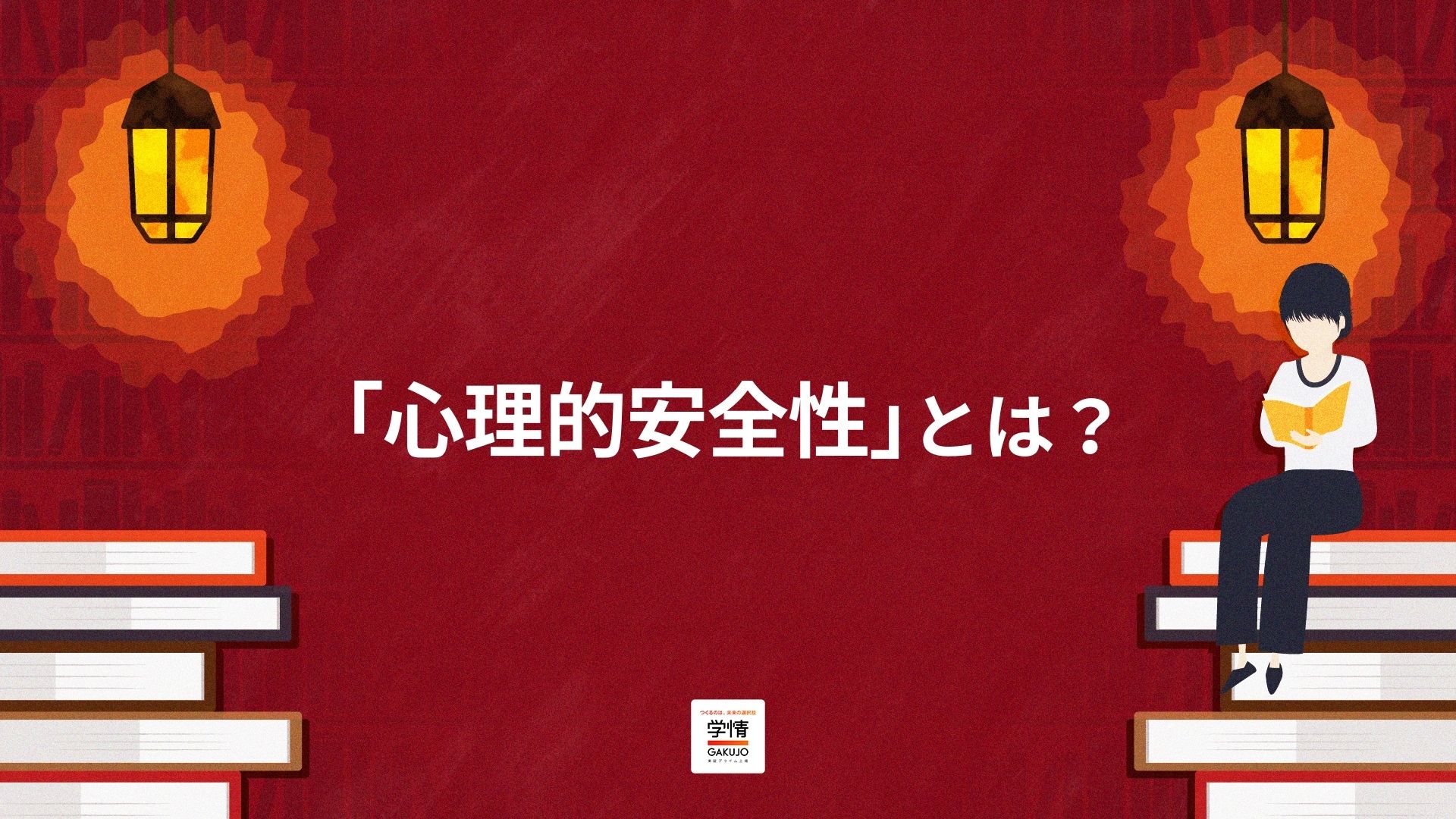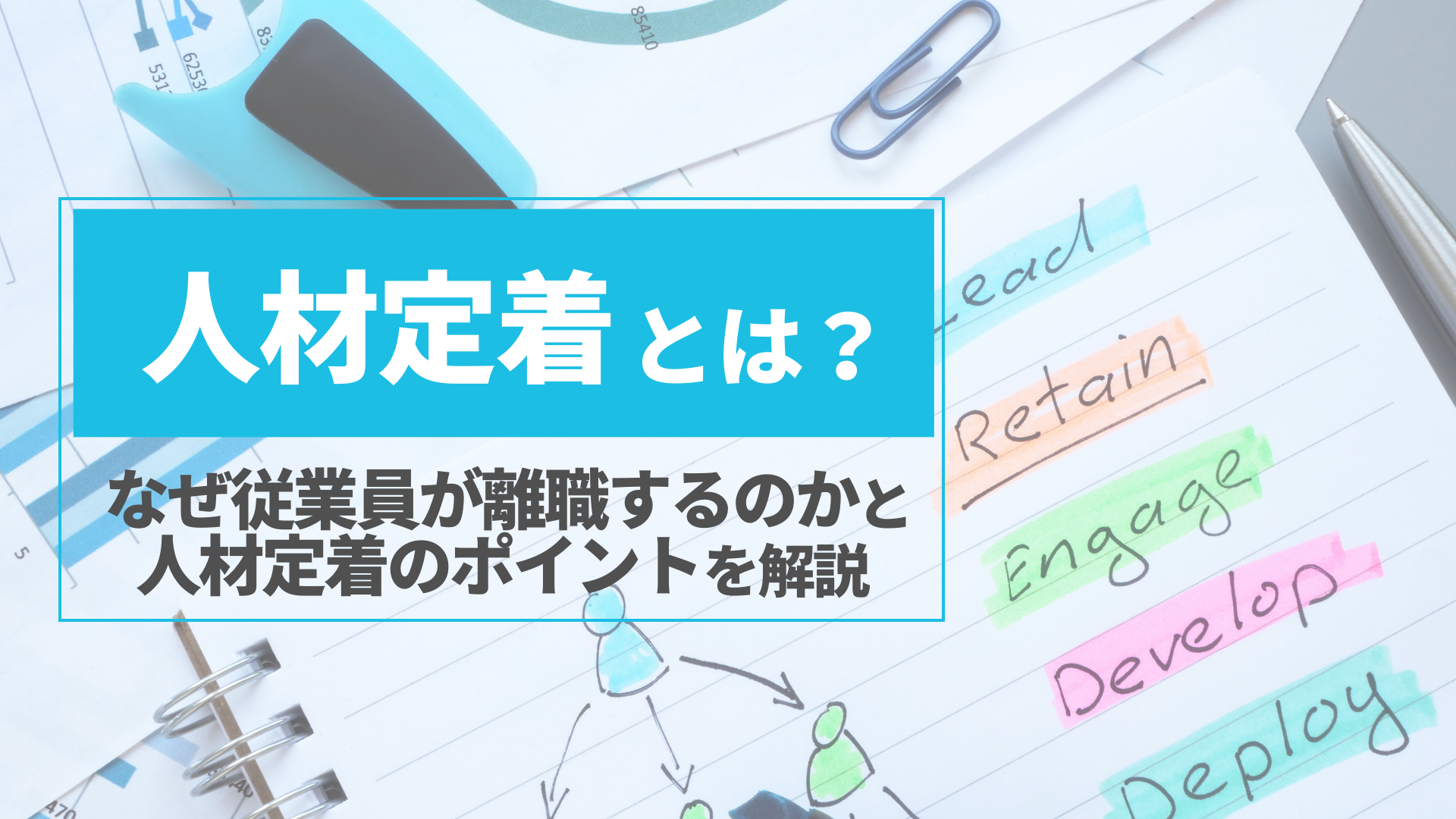労働生産性とは?おもな種類とその計算式、向上させる方法までわかりやすく解説
公開日:2023.05.23
更新日:2025.02.11


労働生産性を計算すると、従業員や企業が生み出す成果を数値で確認できます。視覚化することで、自社の労働生産性の現状の把握や今後の施策検討に役立てることが可能となります。
そこでこの記事では、労働生産性の基礎知識や計算方法などを解説します。労働生産性を向上させるメリットや向上させる方法も併せて解説するので、ぜひ最後までお読みください。
労働生産性とは

労働生産性とは、従業員一人当たりまたは労働時間1時間当たりに生産できる成果を数値化したものです。財務省のホームページでは、「従業員一人当たりの付加価値額をいい、付加価値額を従業員数で除したもの」と定義されています。
※出典:財務省「法人企業統計調査からみる日本企業の特徴 資料2」
https://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/japan/japan02_18.pdf
労働生産性は、従業員一人当たりの労働量や投資額がどれだけ見合っているかを数値化できるため、経営判断の指標の一つとして用いられることもあります。数値が高い場合は、労働力が効率的に働いている状態です。
一方で数値が低い場合は労働力が効率的に働いていないため、労働生産性を向上させるために何らかの対策が必要となります。
労働生産性の種類

労働生産性には、物的労働生産性と付加価値労働生産性の2種類があります。それぞれ、結果が表す意味や計算方法が異なります。両者の大きな違いは、成果の対象です。
物的労働生産性
物的労働生産性は、成果に対して生産量や金額を表す数値です。数値からは、従業員がサービスや商品をどのくらい効率よく生産しているのかが把握できます。
付加価値労働生産性
付加価値労働生産性は、生み出した成果に対しての付加価値を表す数値です。数値からは、従業員が付加価値を生み出すためにどのくらい効率良く働いているかを確認できます。景気指標となるGDP(国内総生産)は、付加価値労働生産性が用いられています。
労働生産性を表す計算式

労働生産性を算出する計算式は、物的労働生産性と付加価値労働生産性で異なります。
物的労働生産性の計算式
物的労働生産性の計算式は、次のとおりです。
- 物的労働生産性=生産量÷労働量
生産量には労働によって生み出された成果、労働量には労働者数を当てはめて計算します。
物的労働生産性の計算例
工場で5人の従業員が3時間で15個の商品を生産した場合、物的労働生産性の数値は次のとおりです。
| 物的労働生産性 | 計算式および数値 |
| 従業員一人当たりの成果 | 生産量(15個)÷(労働者数5人)=従業員一人当たり3個 |
| 従業員一人1時間当たりの成果 | 生産量(15個)÷(労働者数5人×労働時間3時間)=従業員一人1時間当たり1個 |
従業員一人当たりの成果は、生産量15個を労働者数5人で割った結果、従業員一人当たり3個になります。従業員一人1時間当たりの成果は、生産量15個を労働者数5人と労働時間3時間をかけた数値で割った結果、従業員一人1時間当たり1個になります。
付加価値労働生産性の計算式
付加価値労働生産性の計算式は、次のとおりです。
- 付加価値労働生産性=付加価値額÷労働量
付加価値額には売上から諸経費を差し引いた金額、労働量には労働者数を当てはめて計算します。
付加価値労働生産性の計算例
3人の従業員が2時間で30,000円の売り上げを達成した場合、付加価値労働生産性の数値は次のとおりです。なお、商品の材料費や運送費に6,000円かかったと仮定します。
| 付加価値労働生産性 | 計算式および数値 |
| 従業員一人当たりの成果 | 付加価値額(30,000円-6,000円)÷(労働者数3人)=従業員一人当たり8,000円 |
| 従業員一人1時間当たりの成果 | 付加価値額(30,000円-6,000円)÷(労働者数3人×労働時間2時間)=従業員一人1時間当たり4,000円 |
従業員一人当たりの成果は、売上30,000円から諸経費6,000円を差し引いた数値を労働者数3人で割った結果、従業員一人当たり8,000円になります。従業員一人1時間当たりの成果は、売上30,000円から諸経費6,000円を差し引いた数値を、労働者数3人と労働時間2時間をかけた数値で割った結果、従業員一人1時間当たり4,000円になります。
労働生産性の数値と判断基準

労働生産性の数値には、明確な判断基準がありません。
労働生産性の数値は企業の規模や業種などによって異なるため、目安となる基準は企業ごとにさまざまです。たとえば中小企業の場合、数値が1,000万円を超えていれば労働生産性が高いと判断できます。
自社で計算した数値が妥当かを判断するには、類似した規模や業種の他社の労働生産性を計算し、比較するのも手段の一つです。また、労働生産性は一度だけでなく、継続して算出することが大切です。前年や前期などと比較すれば、自社の労働生産性が向上しているか否かを判断できるようになります。
労働生産性を向上させるメリット

労働生産性は、向上させると従業員や企業にさまざまなメリットをもたらします。労働人口の減少が深刻化している状況下では、労働生産性の向上に取り組む企業も多いようです。
コスト削減
労働生産性を計算すると、従業員一人当たりまたは労働時間1時間当たりに生産できる成果が把握できます。数値が低い場合は、労働力が効率的に働いていない状態と判断することが可能です。
労働生産性が向上すると、少ない労働力で成果を生み出せるようになります。残業や休日出勤などの時間外労働が減るため、人件費の削減につながります。削減できた分のコストは従業員の教育や設備投資などに活用し、さらなる生産性の向上を目指すのも手段の一つです。
利益率の向上
近年、労働者不足を課題に抱える企業が増えています。厚生労働省の「労働経済動向調査(令和3年8月)の概況」では、正社員は平成23年8月の調査から41期連続で不足超過であることがわかっています。
特に建設業、医療・福祉、運輸業・郵便業、情報通信業は、労働者不足が深刻な状況です。
| 産業 | 不足 | 過剰 |
| 調査産業計 | 34% | 5% |
| 建設業 | 50% | 0% |
| 製造業 | 35% | 7% |
| 情報通信業 | 35% | 2% |
| 運輸業・郵便業 | 42% | 4% |
| 卸売業・小売業 | 18% | 4% |
| 金融業・保険業 | 10% | 1% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 33% | 2% |
| 学術研究・専門・技術サービス | 34% | 6% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 16% | 4% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 33% | 6% |
| 医療・福祉 | 45% | 4% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 31% | 4% |
※出典:厚生労働省「労働経済動向調査(令和3年8月)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2108/dl/8roudoukeizaidouko.pdf
労働者不足を課題に抱える企業は、労働生産性の向上が急務です。労働生産性が向上すると、従業員一人当たりの生産性が上がります。その結果、より少ない資源や投資で多くの利益を得られるようになります。
ワーク・ライフ・バランスへの貢献
時代の流れとともに個人が持つ価値観が多様化し、近年は仕事とプライベートの両立を目指す動きが加速化しています。仕事に対する価値観も変わり、仕事に重きを置く従来のスタイルは時代に合わない状況です。
ワーク・ライフ・バランスを実現できない労働環境では、離職する従業員が増えるリスクがあります。ワーク・ライフ・バランスとは、仕事とプライベートを調和しようという概念です。
ワーク・ライフ・バランスを重視する従業員が増える中で、長時間労働の是正や有給休暇の取得推進など、企業には働き方改革が求められています。生産性が向上すると従業員一人当たりの労働時間を削減できるため、ワーク・ライフ・バランスの実現に寄与できます。
労働生産性を向上させる方法

労働生産性を向上させるには、業務の標準化と自動化を図るといった方法があります。まずは現在の業務状況を把握し、必要に応じて対策を講じてみましょう。
業務の標準化を図る
労働生産性を向上させるには、業務内容ごとにマニュアルが整備されているか確認しましょう。業務内容のなかにはマニュアルがなく、従業員それぞれが独自の方法で行っているものがあるかもしれません。
マニュアルがなければ完成物の品質にばらつきが生じ、同等に仕上げる作業も必要になるため、時間の無駄につながる可能性があります。業務ごとのマニュアルを整備して標準化を図れば、短時間で効率良く作業が行えるようになります。
業務の自動化を図る
定型的な業務を自動化すると、従業員一人当たりの労働時間を削減できるため、労働生産性が向上する可能性があります。たとえば、RPAやFAなどのツールを導入するのも手段の一つです。
RPAは「Robotic Process Automation」の略称で、これまでは人間が対応していた作業をAIに学習させて自動化する技術のことを指します。定型的な業務にRPAを導入すると、人間での作業に起こりがちなヒューマンエラーを軽減できます。
FAは「Factory Automation」の略称で、製造や設計などの生産工程を自動化できるシステムです。導入によって業務が効率化できるだけでなく、完成物の品質の向上が期待できます。
従業員のスキルアップ
労働生産性と従業員の能力は、決して無関係ではありません。従業員一人ひとりがスキルアップすれば、より効率的に業務を行えるようになるため、労働生産性の向上が期待できます。
そのため企業は従業員のスキルアップに向けたサポート体制を整えることが重要だと言えます。たとえば、OJTやOFF-OJTが受けられる研修制度を整備するのも一つの方法です。スキルアップサポート制度を設け、資格取得やセミナー参加などの費用を補助すれば、従業員の経済的な負担を軽減できます。
労働環境を整備する
従業員が快適に働けるように労働環境を整備すると、生産性の向上につながる可能性があります。たとえば、テレワークやABW※などの多様な働き方を導入するのも一つの方法です。
※ABW:(アクティビティ・ベースド・ワーキングの略。働く場所や時間を自由に選択できる働き方)
総務省の「令和3年版情報通信白書」によると、継続してテレワークを導入している事業者は、平成23年から令和2年までの期間、導入していない事業者よりも労働生産性が高いことがわかっています。
| テレワーク導入済 | テレワーク未導入 | |
| 令和2年 | 759万円 | 517万円 |
| 令和元年 | 805万円 | 623万円 |
| 平成30年 | 947万円 | 636万円 |
| 平成29年 | 877万円 | 611万円 |
| 平成28年 | 957万円 | 599万円 |
| 平成27年 | 922万円 | 730万円 |
| 平成26年 | 791万円 | 610万円 |
| 平成25年 | 964万円 | 602万円 |
| 平成24年 | 848万円 | 587万円 |
| 平成23年 | 823万円 | 594万円 |
※出典:総務省「令和3年版情報通信白書 第1部 特集 デジタルで支える暮らしと経済」
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd112120.html
また、従業員が生産性を高められるように、オフィスのデザインやレイアウトを工夫する方法もあります。たとえば、来客対応が多い部署のワークスペースを応接室の近くに配置すれば、動線が簡素化されて移動時間を削減できます。
労働生産性の向上は働き方改革につながる

労働生産性が向上すれば従業員一人当たりの労働時間を削減できるため、残業や休日出勤などが不要になり、長時間労働の是正につながります。効率良く働けるようになれば、従業員のワーク・ライフ・バランスの実現に寄与することが可能です。
労働生産性の向上とワーク・ライフ・バランスの実現は、働き方改革に直結します。労働環境が改善されれば従業員の離職率も低減できるため、労働生産性の向上と働き方改革は同時に取り組んでいきましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。