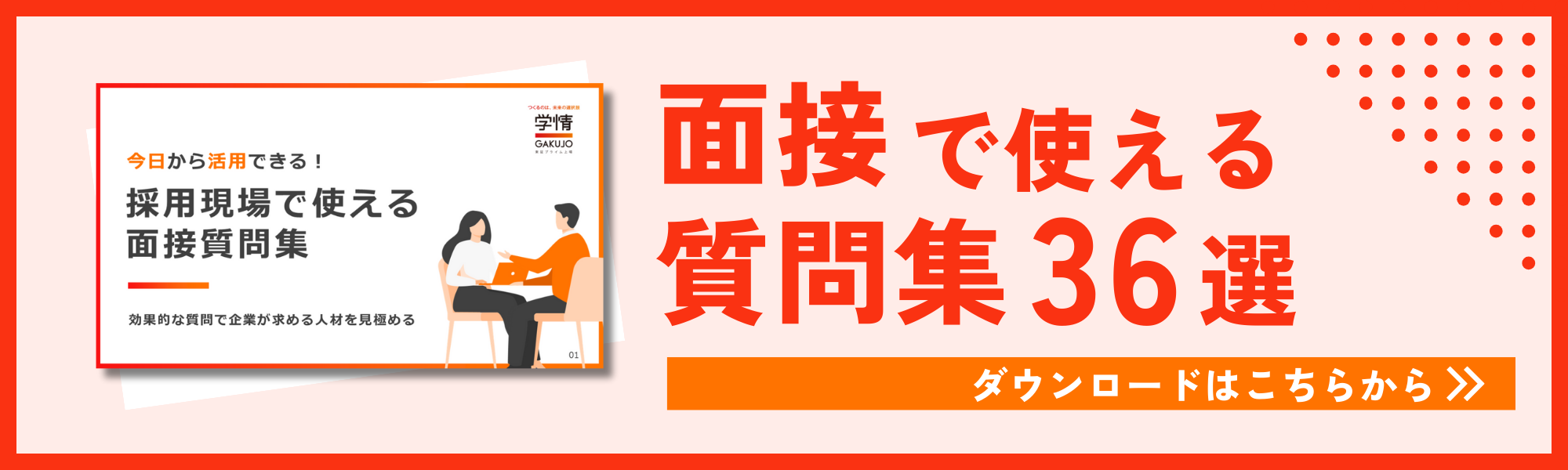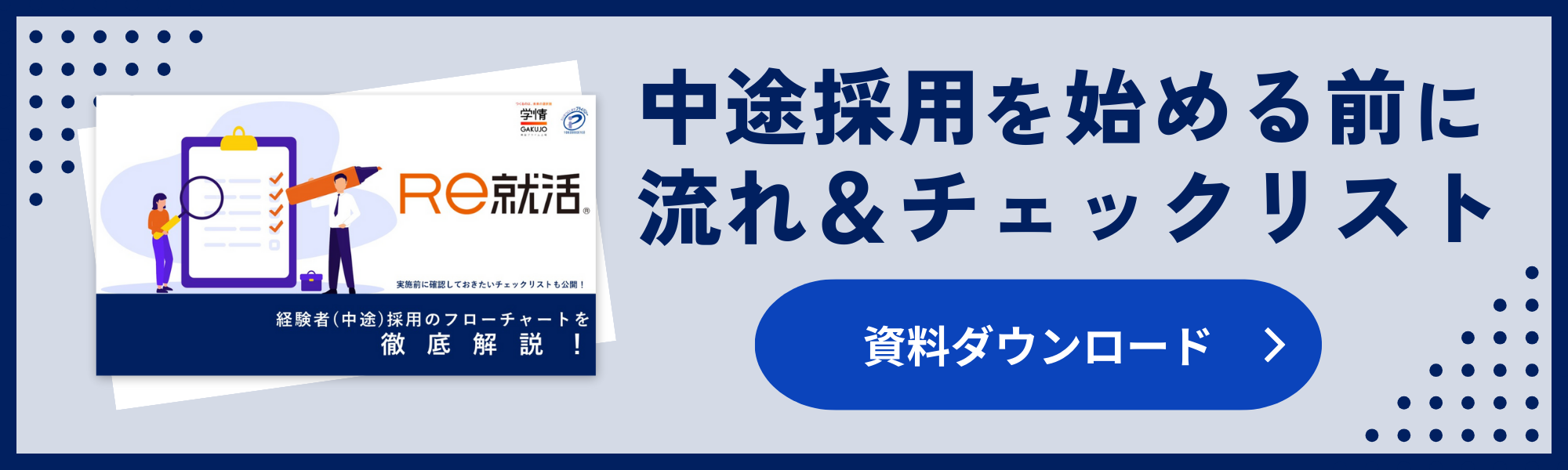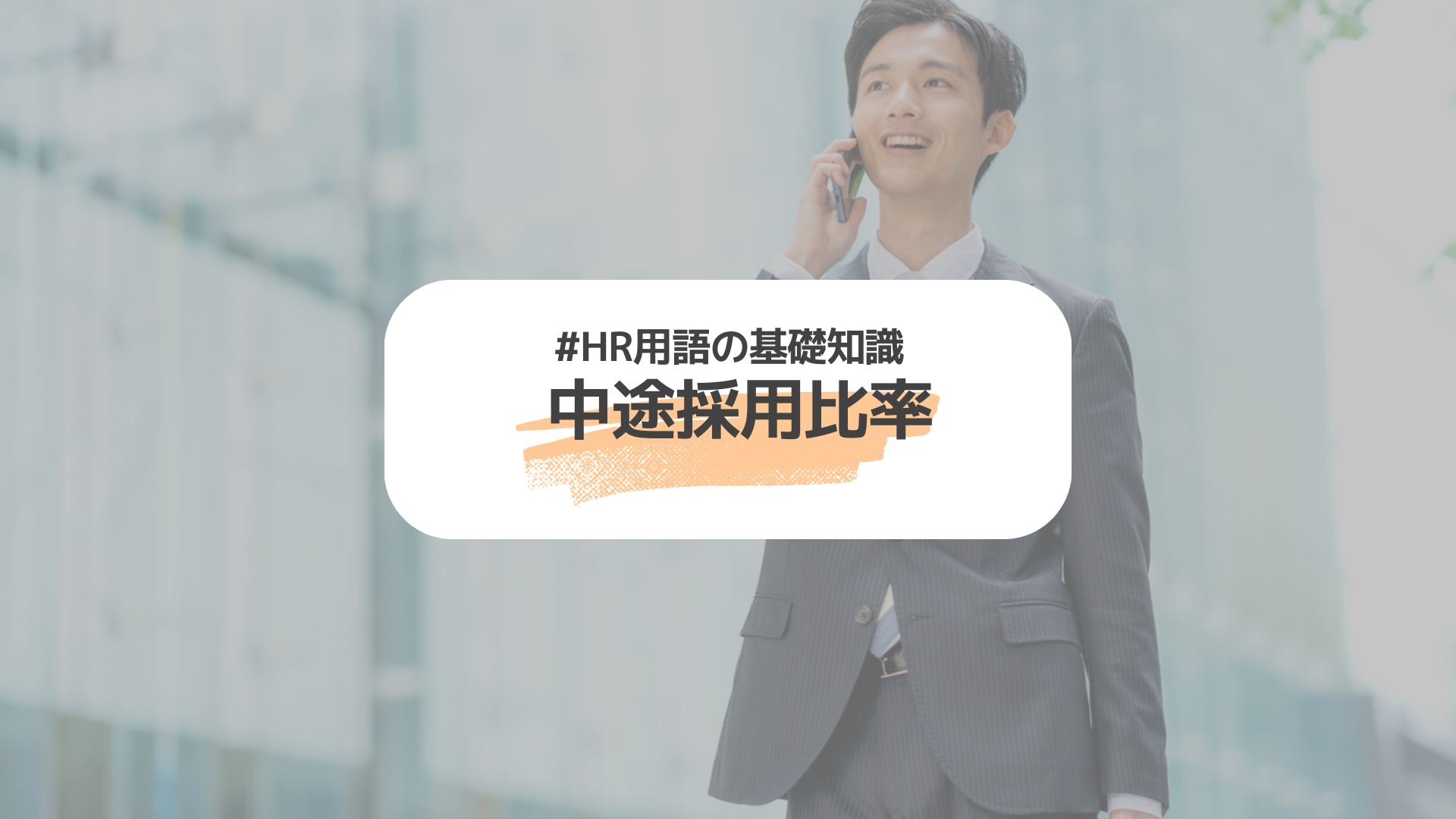
2021年4月から、301人以上の常時雇用を行っている企業は、中途採用比率を公表することが義務化されました。この公表義務について、どのような対応や取り組みをすればよいのか、悩んでいる企業の担当者は少なくないでしょう。
そこで、この記事では中途採用比率の公表義務化に関する各種情報を紹介します。義務化の背景や、中途採用比率を公表するメリットとデメリット、公表に向けて企業が準備しておくべきことについても解説していきます。
中途採用比率の公表義務化とは

中途採用比率の公表義務化とは、労働施策総合推進法第27条の2によって定められた制度です。制度の詳細や対象となる企業や条件を紹介します。
公表義務の対象企業
正規雇用労働者が300人以下の企業は、その規模や性質からすでに中途採用者が多い傾向にあるため、中途採用比率の公表義務を課されてはいません。つまり中途採用比率の公表義務は、いわゆる「新卒採用」の多い傾向のある企業に向けた施策と言えます。
公表が義務化された背景
中途採用比率の公表が義務化された背景には、現在の日本が抱える労働人口と採用事情の傾向のミスマッチがあります。日本は少子高齢化や人口減少といった問題を抱えているため、労働年齢や労働人口を増やすことは現在の国の課題です。
しかし、大企業においては伝統的に新卒採用が重視されることが多々あり、労働者の主体的なキャリア形成や再チャレンジがしにくい環境が指摘されていました。このような企業の体質改善への働きかけが、公表の義務化の目的と言えます。
この情報の公開で労働市場における企業の立ち位置を示すとともに、求職者側の就職活動での情報不足の解消や、労働者が企業を選ぶ際に重要なポイントとなる情報を提供することが狙いとされているのです。
中途採用比率の公表の仕方

中途採用比率の公表の実務について把握し、スムーズに作業できるようにしましょう。
ここでは、具体的な公表の仕方について紹介します。
中途採用比率の計算方法
中途採用比率は、その事業年度の正規採用の「中途採用者÷全採用者×100」で求められます。
中途採用者は、厚生労働省によって「新規学卒等採用者以外」と定義されています。新規学卒等採用者は新たに学校や専門学校などを卒業したもの、あるいはそれと同等の処遇の採用者と定義されています。この条件に該当しないものが中途採用者です。
正規採用者は、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(通称パートタイム労働法)で定義される「通常の労働者」で、一般的な「正社員」にあたるものです。このため、パートなどの非正規雇用は対象外です。
また雇用している非正規雇用労働者を、正規雇用労働者に転換した場合は、転換した事業年度における中途採用として取り扱います。
たとえば、2022年事業年度に採用した労働者150人のうち、非正規雇用者が26人であれば、残りの124人で中途採用比率で計算しますが、その124人のうち22人が中途採用者であった場合は、次のとおりに中途採用比率を計算できます。
- 22(中途採用者人数)÷124(全採用者人数)×100=17.7419……(中途採用比率)
中途採用比率の公表方法
ホームページで公表する場合には、求職者が欲しい情報をまとめたページなどに次のような図表をつくり、自社の中途採用比率を紹介することが有効です。
【中途採用比率の公表例】
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 〇〇.〇% | 〇〇.〇% | 〇〇.〇% |
もし自社にホームページがない場合には、厚生労働省が運営する職業情報総合サイト「しょくばらぼ」を利用する方法があげられます。
「しょくばらぼ」は、企業の勤務実態といった働き方や採用状況に関する企業の情報を検索・比較できる厚生労働省の運営するサイトです。企業として「しょくばらぼ」を利用する場合には登録が必要となるため、事前に手続きを済ませておきましょう。
上記2つの方法以外にも、事業所に提示する、各書類に記載するなどの方法も認められています。求職者の目に届きやすい場所に情報を掲載することが大切です。いずれかの公表方法でも、情報の公表日を公開することが定められているため、忘れずに記載しておきましょう。
中途採用の比率を公表するメリット

- 自社の採用方針のアピールにできる
- 即戦力となる人材が集まりやすくなる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
自社の採用方針のアピールにできる
自社の採用方針をアピールする上で、中途採用者の比率を公表することは重要です。
公表することで、中途採用に対して積極的に取り組んでいることをアピールできます。結果的に、求職者の応募を集めやすくなるでしょう。
また自社内でどのような人材を採用しているか、その人材がどのように活躍しているのか、といった具体的な情報も発信することで、採用ブランドの向上も期待できます。
即戦力となる人材が集まりやすくなる
中途採用比率の高い企業は、即戦力人材の採用にも力を入れているという情報を発信することができます。求職者は気になる企業の中途採用比率を目にすることで、その企業への応募意欲が湧くようになるため、非常に重要だと言えます。
また企業側にとっても、即戦力人材が自社に増え続けると、社員の教育コストの軽減にもつなげられ、より強固な組織づくりを実現できるというメリットもあります。
中途採用の比率を公表するデメリット

中途採用比率の公表のデメリットについても把握しておきましょう。
- コストに見合った成果が得られるとは限らない
- 企業イメージの低下につながる可能性もある
中途採用比率の公表は義務化されているため、デメリットを踏まえた上で、施策を進めていくことが大切です。
コストに見合った成果が得られるとは限らない
求職者が転職活動において、企業の中途採用比率をどれほど重要視しているのかは未知数です。そのため、採用比率の集計と公表に労力や費用をかけても、見合った成果が得られるとは限りません。
ただし、計算は毎年必要であるものの膨大な工数が発生する難しい作業ではないので、コスト面での大きな心配は必要ありません。これら費用対効果も加味しながら、自社で中途採用比率の公表を実施するようにしましょう。
企業イメージの低下につながる可能性もある
自社の中途採用者の比率が低いと、年功序列の社風であると求職者に認識され、企業イメージの低下につながる可能性も否定できません。即戦力や中途者だけでなく、新卒採用予定者からもチャレンジのしにくい企業風土と思われる可能性もあります。
年功序列には人事評価や人材育成、企業独自のノウハウの継承がしいやすいといったメリットがある一方、若手社員が不公平感を抱いたり、成果が評価されにくいと感じたりして優秀な人材から見限られてしまうリスクもあります。
中途採用の比率が低い企業は、自社に見合った中途採用者のあり方を再検討し、積極的に採用することが得策でしょう。
中途採用比率を公表しない場合の罰則

2023年3月現在、中途採用比率の公表は厳密には「努力義務」とされており、罰則はありません。法制度における努力義務とは、従わなかったとしても刑事罰や過料は発生しないということです。
しかし、労働施策総合推進法第33条には「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる」との記述があるため、公表をしないと行政指導を受ける可能性も否定できません。
※出典:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov法令検索
違反した企業に対して何らかの形で罰則が定められる可能性もあるため、公表義務に該当する企業はしっかりと法律に遵守した対応を行っておくべきでしょう。
中途採用比率の公表に向け企業が準備すること

中途採用比率の公表について、必要な作業を大きく分けると、次の3つとなります。
- 比率公表の実務担当者の決定
- 中途採用比率に関する最新情報を収集する
- 中途採用の基準の明確化
それぞれの詳細を解説します。
実務担当者の決定
中途採用比率の計算に必要な各種データの集計や、公表にあたって必要なホームページ内の記事作成が必要になるため、各業務における自社の実務担当者をアサインしましょう。
中途採用比率の計算には過去3年間のデータの集計、公表にはホームページの記事作成など、業務内容は軽いものではないため、担当者個々人の業務負担が増えすぎないように、関係する部署で業務の再配分を行うことも適宜検討しましょう。
中途採用比率に関する最新情報を収集する
すでに触れた通り、中途採用比率の公表の義務化は、2021年に施行された新しいルールです。今後、同制度の内容が一部変更される可能性があります。
公表の対象となる企業や罰則の有無など、変更内容によっては対応方針を変える必要もあるため、厚生労働省のホームページから最新の情報を適時収集しておくようにしましょう。
中途採用の基準の明確化
中途採用比率の公表のメリットを最大化するためには、中途採用者の強化が求められますが、その際に自社の採用基準をあらためて明確にさせる必要があります。
年単位の計画で、中途採用者の目標人数、所属部署、必要ポジションやスキル、採用予算などを綿密に計画しておくようにしましょう。また採用担当者が中心になって、社内の現場メンバーにヒアリングを行い、求められるスキルや理想的な社員像を具体的に整理しておくことも重要でしょう。
中途採用の比率の公表と採用推進で即戦力を獲得しよう

2021年4月以降、301人以上の常時雇用を行っている企業は中途採用比率の公表が求められるようになりました。2023年3月時点では、努力義務として設定されていますが、まずは義務化の内容を理解することが大切です。
中途採用比率を公表することで、自社の採用方針をアピールでき、即戦力となる優秀な人材を獲得しやすくなるというメリットがあります。これを踏まえて、企業は中途採用活動を強化し、公表に向けた準備を一つずつ実施していく必要があります。
公表が義務化されたことで、より企業間の採用競争が激化することが容易に予想されます。企業は、中途採用比率の公表の義務化を積極的に捉え、自社の採用活動に力を入れるようにしていきましょう。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。