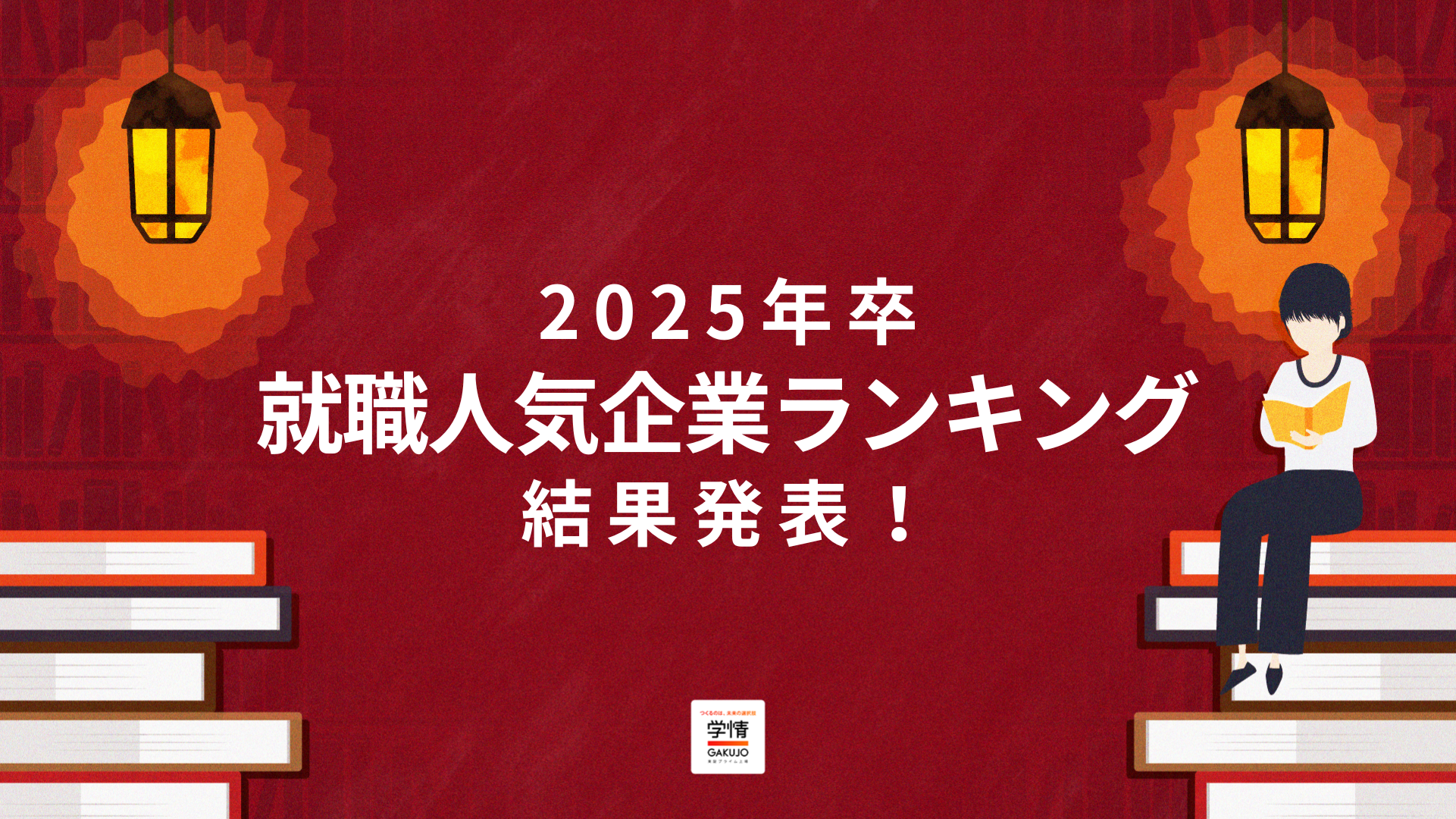チームビルディングとは?得られる効果や成功させるためのポイントを解説
2023.09.26


チームビルディングとは、グループ作業によって従業員のスキルや能力を発揮させる取り組みです。社内コミュニケーションの希薄化や従業員のモチベーション低下などで悩んでいる企業は、チームビルディングに取り組むと課題を解決できる可能性があります。
本記事では、チームビルディングの基礎知識や取り組みで得られる効果などを解説します。
チームビルディングは、一つひとつの段階を踏むことが重要です。チームビルディングの基本的なプロセスや手法も紹介するので、自社で取り組む際に役立ててください。
チームビルディングとは

チームビルディングとは、従業員のスキルや能力を最大限に発揮するための取り組みです。チームビルディングには日常的なコミュニケーションだけでなく、研修やワークショップなども含まれています。
取り組みによってチーム全体で課題に挑み、解決策を見つけるために試行錯誤しながら各メンバーの成長が期待できます。
チームビルディングを成功させるには、チーム全員が目的や役割を理解し、課題を解決するためにお互いにサポートし合える環境を築くことが重要です。
チームビルディングの5つのプロセス

チームビルディングには、チーム力を向上させる上で重要な5つのプロセスがあります。これらのプロセスは、ブルース.W.タックマンが提唱したことから「タックマンモデル」と呼ばれています。
|
プロセス |
状況 |
|
形成期 |
チームが結成されたばかりの時期 |
|
混乱期 |
メンバー同士の意見や主張がぶつかりやすい時期 |
|
統一期 |
各メンバーが自分の役割を認識してチームとしての団結力が高まる時期 |
|
機能期 |
リーダーの指示がなくても各メンバーが自発的に行動できるようになる時期 |
|
散会期 |
チームとしての役割を終える時期 |
1.形成期
形成期はチームが結成されたばかりで、メンバーがお互いをまだよく理解していない時期です。この段階ではメンバー同士が本音を隠しているため、緊張感が漂います。
まだメンバー同士の相互理解が深まっていないため、コミュニケーションを通じて、相互理解を深めることが重要です。
リーダーはチームの方向性を導くために、チームが結成された理由や活動目的、そして組織の目標を全メンバーに明確に示す必要があります。
2.混乱期
混乱期はチームに目標が示され、チームでの活動が始まったばかりの時期です。メンバー同士のコミュニケーションが増えることで、相互理解が進展していきます。
しかし、各メンバーの意見や主張が交わされるため、対立が生まれやすいのもこの時期です。ときには意見が衝突し、チーム内で軋轢が生まれる可能性もあります。
チーム力を高めるには、お互いの考え方や価値観を尊重しなければなりません。表面的なコミュニケーションではうまくいかないケースもあるため、お互いが納得できるまで議論を重ねることが大切です。
3.統一期
統一期はお互いの考え方や価値観への理解が深まり、チームが安定する時期です。
この時期は、各メンバーのスキルや能力を考慮し、役割が与えられます。メンバーが自分の役割を認識してチームとして団結力が高まるため、チームワークが生まれやすい時期です。
また、混乱期を乗り越えた経験があるため、メンバー同士で意見が食い違っても柔軟に解決できる傾向にあります。
ただしメンバーの意見が揃っていても同じ方向に進むとは限らないため、リーダーはチーム全体の方向性を見守る必要があります。
4.機能期
機能期は、リーダーの指示がなくても各メンバーが自発的に行動できるようになる時期です。各メンバーが同じ目的意識を持って行動するため、チームの団結力が一層高まります。
機能期は、リーダーの役割が大きく変化する時期です。メンバーに細かい指示を出すと、自発的な行動を妨げる可能性があります。そのため、リーダーは細かい指示は避け、メンバーの自立をサポートするよう心がけましょう。
5.散会期
散会期は目標の達成や組織再編などにより、チームとしての役割を終える時期です。各メンバーはスキルや経験を身に付け、次の目標に向かって飛躍するタイミングでもあります。
散会期は、リーダーによるサポートは不要です。その代わりに、リーダーはチームが良好な形で解散できるような雰囲気作りを心がけます。
チームの解散を惜しむ姿やお互いを称賛し合う姿が見られる場合は、チームビルディングは成功したといえるでしょう。
チームビルディングへの取り組みで得られる効果

従業員がチームビルディングに取り組むと、社内コミュニケーションの活性化やマインドセットの形成などのさまざまな効果が期待できます。企業が抱える課題を解決できる可能性もあるため、どのような効果があるかを把握しておきましょう。
社内コミュニケーションの活性化
チームビルディングではチーム全体が目標達成という共通認識を持つため、メンバー同士のコミュニケーションの活性化を期待できます。メンバーの相互理解を深め、チーム力を高めるには、コミュニケーションが欠かせません。
コミュニケーション量が増えると、相談や報告、連絡漏れの防止にもつながります。チームビルディングで良好なコミュニケーションがとれれば、チーム機能が向上し、メンバー同士の関係性を強化できるでしょう。
マインドセットの形成
マインドセットとは、先入観から作られる思考パターンや固定化された考え方です。
チームビルディングでは、メンバー同士が協力して共通の目標に向かいながら、各自が自分の役割や貢献の重要性を理解し、目標達成に向けたマインドセットを形成します。
ポジティブなマインドセットが形成されると、メンバーはモチベーションを持って業務に取り組むことができ、ビジネスの成功へとつながります。
従業員のモチベーションアップ
チームビルディングを通じてチームが一丸となって目標達成に向かうと、メンバー一人ひとりの達成感が高まり、モチベーションの向上を期待できます。
モチベーションが高いチームは、困難を乗り越える意欲が高まり、チーム全体のパフォーマンスが向上します。
メンバーが一丸となって成果を上げることで、従業員のモチベーションアップ、さらにはチーム全体の成功に近づくのです。
新たなアイディアの創出
チームには、さまざまな考え方や価値観を持つメンバーが集まります。他者の意見に接することでメンバーの想像力が刺激され、チームにイノベーションをもたらすことになるでしょう。
生産性の向上
チームビルディングによって信頼関係を構築できれば、チーム全体の生産性の向上が期待できます。
そのためには相互理解を深め、各メンバーの強みや弱みを把握しておくことも重要です。メンバーの弱みをカバーし強みを活かすことができれば、チームとしての一体感が生まれます。
こうした相互理解と協力によって、チーム力が強化され、組織としてのパフォーマンスを最大限に発揮できるでしょう。
人員配置の最適化
チームビルディングでは、目標に向かう過程でお互いの考え方や価値観を理解し合い、相互理解が深まります。
リーダーは各メンバーの性格や強み、弱みを見極められ、適切な部署に配置したり、役割を与えたりすることが可能になります。その結果、企業全体の生産性向上を期待できます。
チームメンバーが持つ個々の特性を活かし、効率的に仕事に取り組むことで、より成果を上げることができるでしょう。
チームビルディングを成功させるためのポイント

企業がチームビルディングに取り組んでも、必ず成功するとは限りません。チームビルディングを成功させ、その効果を得るには、いくつかのポイントをおさえておく必要があります。
目標の明確化
チームビルディングに取り組むにあたっては、チームとしての目標を明確化させることが大切です。
チームの目標は、メンバーがお互いをまだよく知らない形成期に共有します。
抽象的な目標ではメンバーに浸透しにくく、チームとしての方向性を見失う可能性があるため、すべてのメンバーが理解できる目標を設定します。
目標が浸透すれば達成に向けたコミュニケーションが活性化し、チームワークを発揮できるようになるでしょう。
メンバーの役割の具体化
チームビルディングに取り組む際には、各メンバーの役割を具体化しておく必要があります。役割があいまいな場合、メンバーは自分が何をすべきかわからず、チームの目標達成に向けて動きにくくなります。
チームワークを発揮するためにも、リーダーはメンバーのスキルや経験を見極め、役割を具体化するようにしましょう。
メンバー同士の価値観の共有
チームで目標を達成するには、メンバーの相互理解が不可欠です。
チーム内のメンバーは、異なるバックグラウンドや経験を持っており、価値観も異なります。この多様性により、異なる意見や視点が得られるため、メンバーは物事をより多角的に捉えることができ、チームの能力を向上させる要因となります。
チームビルディングを成功させるには、他者の意見や主張にも理解を示し、多様性を受け入れられる環境作りも必要です。
チームビルディングのおもな手法

最後に、チームビルディングのおもな手法を紹介します。ゲームやイベントなどの取り組みやすい手法を紹介するので、自社で導入する際の参考にしてください。
ゲーム
ゲームは業務から離れて楽しめるため、緊張感の緩和につながります。
また、楽しさや笑いが共有されることで、チームの一体感が生まれ、チームメンバー同士の結束が強化されるのが特徴です。
チームビルディングで活用できるおもなゲームとして「自分史ワーク」や「共通点探しゲーム」があげられます。
「自分史ワーク」では、参加者が自分の人生や経験について思い出したことや感じることを書き出したり、グループ内で共有したりします。過去の出来事や経験を振り返ることで、自己の成長や変化を理解し、自分自身を客観的に見つめ直す手段となります。
「共通点探しゲーム」は、チームメンバー同士がお互いの共通点を見つけることを目的としたゲームです。
メンバーを複数のグループに分け、各グループでお互いの共通点を見つけるために趣味や興味、経験、価値観などさまざまな要素を話し合います。各グループは見つけた共通点を全体に共有します。相手との意外な共通点に会話も弾むでしょう。
ワークショップ
ワークショップとは、参加者の主体性を重視した活動です。
チームビルディングの一環としてワークショップを活用すると、メンバーひとりひとりが主体性を持って行動できるようになります。
ワークショップの具体例には「チェックイン」「陽口ワーク」があげられます。
「チェックイン」では質問に答える形式で参加者一人ひとりが自己紹介や感想、気持ちなどを共有します。参加者同士の関係性を構築する目的があり、初対面の相手におすすめです。
「陽口ワーク」は陰口の反対言葉として「陽口」を言い合うオンラインでできるワークです。
陽口ワークでは、カメラをオフにしてマイクをミュートにした対象者の称賛や褒め言葉を、ほかの参加者が言います。その後、対象者はカメラとマイクをオンにして、自分に対して言われた内容に対する感想を述べます。この流れを全員の参加者が繰り返します。
陽口ワークの目的は、お互いを承認し合う機会を提供することです。参加者は自分の良いところや価値を再確認し、他者からの肯定的なフィードバックを受け取ることで、自己肯定感の向上にもつながるでしょう。
イベント
イベントでは従業員同士が接する機会が増えるため、コミュニケーションの活性化が期待できます。
仕事以外の面が見えることで、メンバーに対する理解が深まる可能性があります。
チームビルディングの一環となるおもなイベントとしては「エブリバディアップ」や「マシュマロ・チャレンジ」があります。
「エブリバディアップ」ではチームメンバー全員が両隣の人と足が触れた状態で座り、同時に全員で立ち上がることを目指します。もし、一人でも立ち上がれない人がいたら、課題は達成されません。
エブリバディアップでは、全員で立ち上がるという目標達成のために、チームが一丸となって協力します。チームメンバー同士が密接に連携し、タイミングを合わせて行動することが重要です。
「マシュマロ・チャレンジ」もチームビルディングにつながるイベントの一つです。マシュマロ・チャレンジでは決められたアイテムだけで自立するタワーを作り、その高さを競います。最も高いタワーを作ったチームが勝ちとなります。
各チームが使用できるアイテムは次のとおりです。
- マシュマロ:1つ
- 乾燥パスタ:20本
- マスキングテープ:90cm
- ひも:90cm
- はさみ:1つ
実施する際は、記録測定用としてメジャーやストップウォッチを用意しましょう。
より高いタワーを作り上げるためには、チームでの協力が不可欠です。
気軽に取り組めるものからチームビルディングを始めてみよう

チームビルディングを通じて、メンバー同士が率直に意見を交換し合い、意見の相違を乗り越えると、より円滑なコミュニケーションが生まれます。
また、メンバー同士がお互いをより深く理解できるため、信頼関係の構築が可能です。信頼関係がある環境では、率直な意見交換や失敗を恐れずに新たなアイディアを出し合うことができ、生産性の向上につながります。
チームビルディングにはさまざまな手法があります。まずは気軽に取り組めるものから始めてみましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。