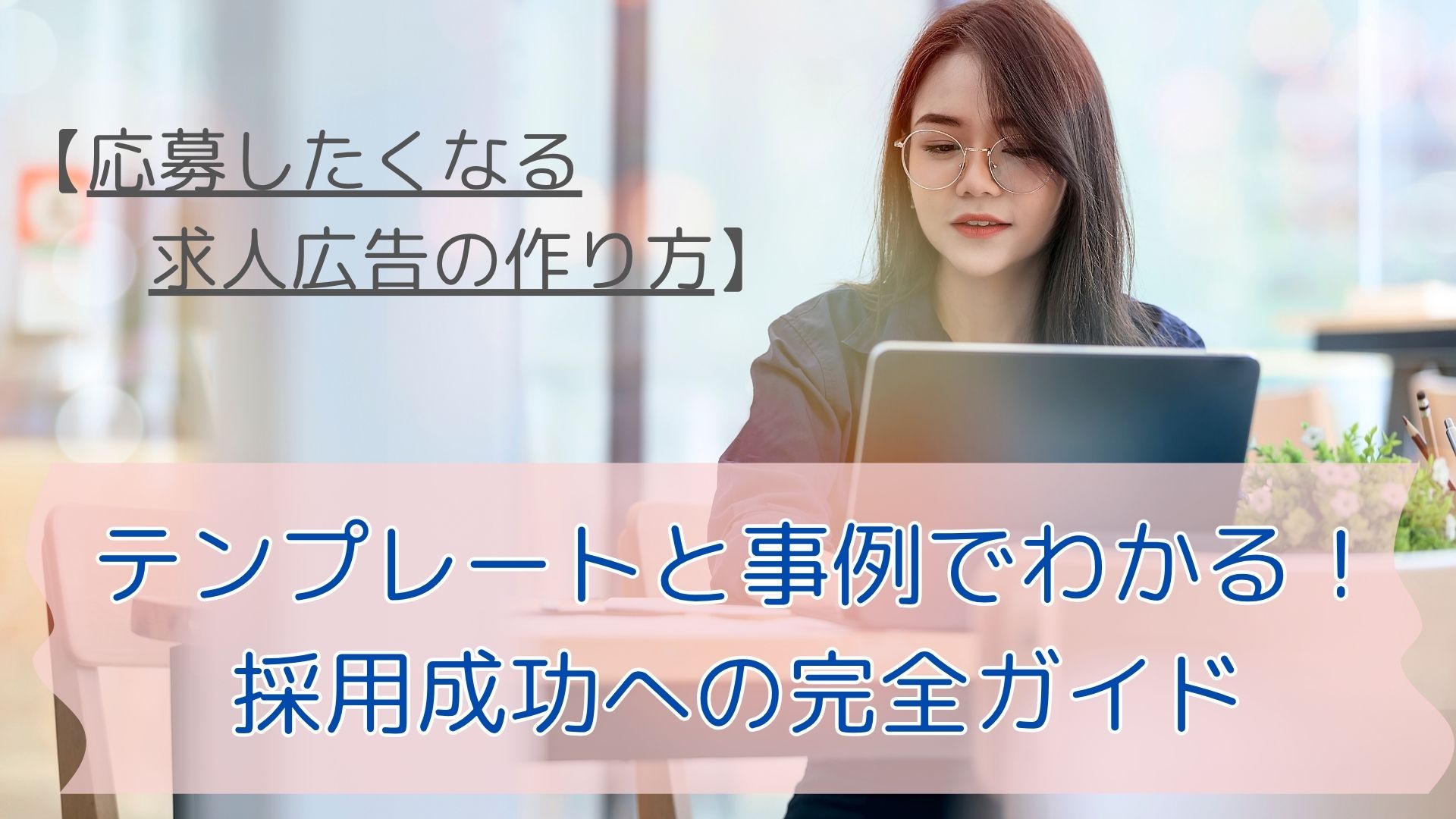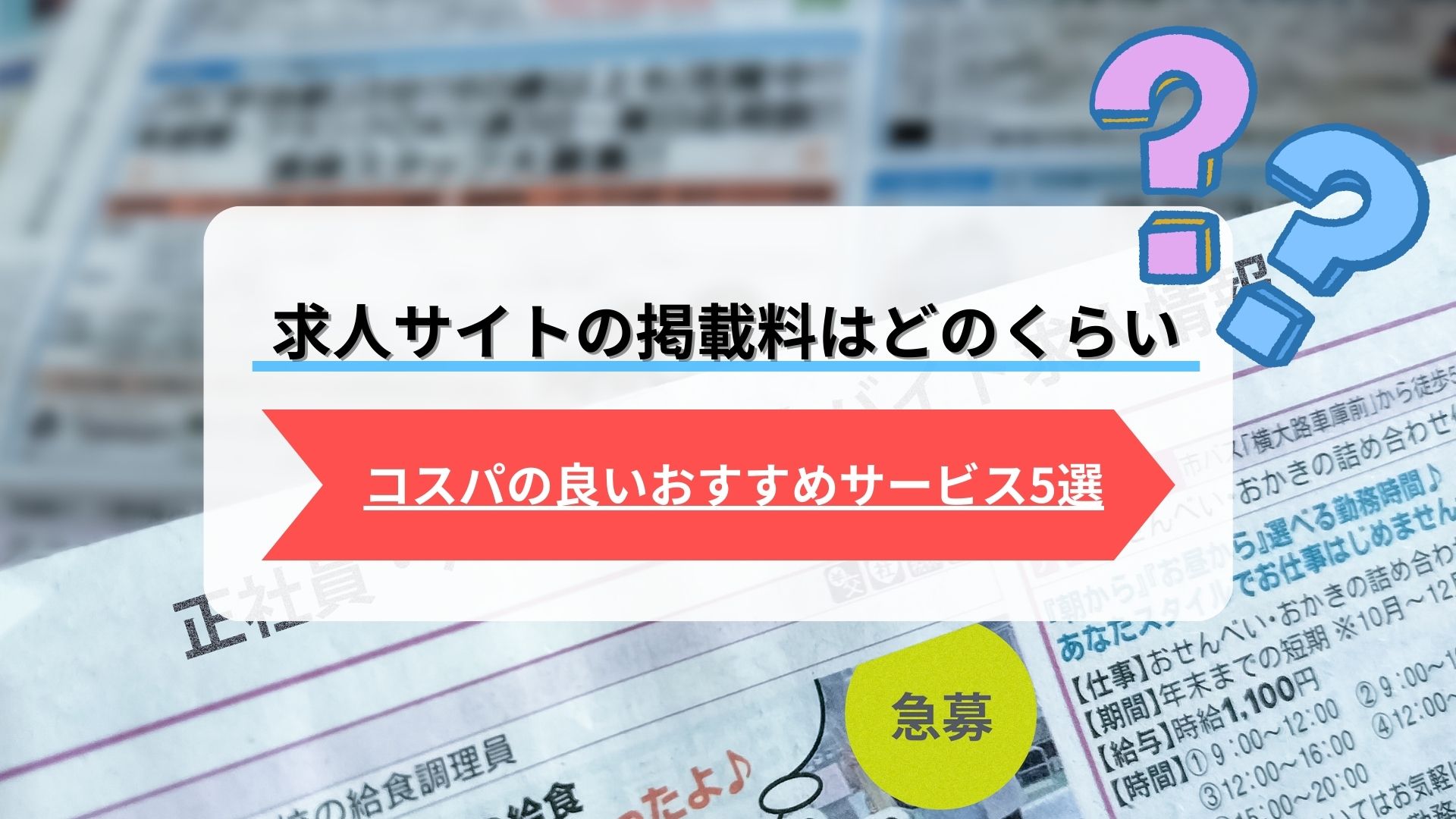
「求人広告にかけられる予算が限られている」「できるだけ低コストで成果を出したい」といったお悩みを抱え、どの求人サイトを使うべきか迷っている企業は少なくありません。
求人サイトの選定は、採用を成功させるためには非常に重要です。掲載料の違いだけでなく、掲載形態やサポート体制、無料プランの有無まで含めて比較することで、自社に合った最適な選択が可能になります。
本記事では、掲載料を重視する企業に向けて、コストパフォーマンスの高い求人サイトを5つ厳選して紹介。さらに、それぞれの求人サイトの特徴や料金形態、向いている採用ニーズを整理しており、比較表もあわせて掲載しています。
「できるだけ予算を抑えて良い人材を採用したい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
掲載料を重視する企業におすすめの求人サイト一覧
掲載料を重視する企業におすすめの求人サイトは次の通りです。
| サイト名 | 料金形態 | 無料掲載の有無 | 想定コスト | 特徴 |
| Re就活 | 掲載型 | × | 38万円~ | 若手・第二新卒に特化 スカウト機能 動画配信 AIスカウトアシスタントあり |
| Wantedly | 掲載型+オプション | △ (トライアルのみ) |
36万円~ | 共感採用 ストーリー投稿 カジュアル面談 企業ブランディングに強み |
| 求人ボックス | クリック課金型 | 〇 | 無料~ | 無料掲載可 クリック課金型 1日500円〜の低予算運用が可能 |
| エンゲージ | 掲載型 | 〇 | 無料~ | 掲載数・期間無制限 自社採用ページ作成 一括掲載機能もあり |
| Indeed | クリック課金型 | 〇 | 無料~ | 高い集客力 スポンサー求人で上位表示 Web面接機能や採用レポート付き(有料) |
掲載料を重視する場合は、次のような点に注意しながら求人サイトを選びましょう。
- 採用ターゲットにマッチした求人サイトを選ぶ
- 無料掲載から始めて反応を見る
- 料金体系が明確な求人サイトを選ぶ
- 料金に含まれているサービス内容を確認する
- 複数媒体を試して効果を検証する
掲載料は選ぶ媒体や求める人材によっても異なりますが、平均的に月数十万円から数百万円程度かかります。自社にとって費用対効果の高い媒体を見つけ、効率良く採用活動を進めましょう。
掲載料を重視する企業におすすめの求人サイトを5つ紹介

求人サイトには、多くの種類があります。ここでは、掲載料を重視する企業におすすめの求人サイトを紹介します。
1.Re就活
「Re就活」は、若手・第二新卒の採用に強みを持つ求人サイトです。最大の特徴は、検索ページでの新着・準新着表示により、出稿予算に関わらず求人を上位表示できる点にあります。
さらに、開封されるまで最大4週間上位表示されるヘッドハンティングメール機能も搭載。ターゲット層に確実にリーチしたい企業におすすめです。
また、職務経歴や自己PRなどからAIが注目ポイントを抽出し、スマートスカウトアシスタントとして最適なスカウト文面を提案するため、メッセージ作成のための労力も削減できます。原稿や掲載画像から短時間で動画を作成し、求職者属性ごとに異なるサムネイルで配信するなど、視認性と訴求力の高い工夫も可能です。
質の高いアプローチをしたい企業にとって、非常にコストパフォーマンスのよい選択肢といえるでしょう。
2.Wantedly
「Wantedly」は共感採用が特徴のプラットフォームで、企業の理念や働き方への共感を重視する採用に適しています。
会社の魅力を伝えるためのストーリー機能や、写真・動画を活用できる会社ページがあり、応募者に対して「雰囲気」や「価値観」をしっかり伝えられます。
また、ダイレクトスカウトやカジュアル面談の機能も備わっており、採用活動の初期段階から関係構築を図れる点も魅力です。さらに、オプションで広告配信やコンテンツ制作代行も利用できるため、時間やノウハウが足りない企業でも手軽にブランディングを行えます。
採用活動を通じて企業の魅力を発信したい企業におすすめです。
3.求人ボックス
「求人ボックス」は求人検索エンジン型のサービスで、コストを最小限に抑えたい企業に最適です。
無料での求人掲載が可能で、より多くの露出を求める場合には有料プランも選べます。有料プランの場合はクリック課金となっており、応募につながる可能性のあるタイミングにだけ費用が発生します。
また、1日500円程度から手軽に運用をスタートすることも可能。小規模事業者や初めて求人広告を出す企業でも比較的導入しやすい媒体です。配信レポート機能も備わっており、運用結果を可視化しながら、PDCAサイクルを回して改善を図ることができます。
4.エンゲージ
「エンゲージ」は完全無料の求人掲載サービスで、掲載数や掲載期間に制限がないことが大きな魅力です。無料ながら、大手検索エンジンや求人検索サイトにワンクリックで一括掲載でき、求人の露出度を高められます。
また、自社採用ページの作成機能もあり、ブランドイメージや募集要項を丁寧に伝えることで応募者の質を高める工夫も可能です。有料プランでは基本機能に加えて、採用成功率を高める機能を利用することができるため、より効果的な採用活動を行いたい場合は検討してみてもよいでしょう。
5.Indeed
「Indeed」は高い集客力を誇る求人検索エンジンです。無料掲載も可能ですが、より多くの露出を求める場合はスポンサー求人(有料掲載)を活用することで効果を高められます。
主な機能としては、競合の動向や自社求人のパフォーマンスを把握できる「採用市場レポート」、パソコンやスマートフォンのブラウザから利用できる「Web面接」、応募者の確認・管理を行える「候補者一括管理」などの機能が備わっています。一部機能はスポンサー求人(有料掲載)でのみ利用可能ですが、採用業務を効率化する機能が充実している点は大きな魅力です。
また、幅広い職種・地域に対応できるため、多様な人材にアプローチしたい企業も検討価値は十分にあります。
コストパフォーマンスの良い求人サイトを目的別に紹介
求人サイトは、目的に応じて選ぶことが必要です。ここでは、コストパフォーマンスのよい求人サイトを目的別に紹介します。
若手や第二新卒を採用したい
若手人材や第二新卒を採用したい場合には、若い世代の登録者が多い求人サイトを選ぶとよいでしょう。
おすすめは、20代の登録者が多い「Re就活」や「マイナビジョブ20’s」です。これらは第二新卒向けに特化しており、まだ職歴の浅い応募者とのマッチング精度が高い点が特徴です。
また、SNS広告との連携も視野に入れることで、Web上での認知拡大と母集団形成を同時に進められます。若手層への訴求力を高めたい企業は、これらの媒体を軸に検討しましょう。
とにかく費用を抑えて採用したい
コスト重視の採用活動では、無料または低価格で始められる求人サイトを活用するのが効果的です。
代表例としては、「エンゲージ」や「求人ボックス」などが該当します。「エンゲージ」は完全無料で期間無制限の掲載が可能、「求人ボックス」は無料掲載に加えてクリック課金型の有料プランも選べます。
また、Googleが提供する「Googleしごと検索(Google for Jobs)」と自社採用ページを連携させることで、自社サイト経由で応募を集めることも可能です。初期投資を抑えつつ採用活動を始めたい企業は、前述のような無料掲載が可能な求人サイトを主軸に検討していくとよいでしょう。
短期間でスピーディーに採用したい
急募案件や欠員補充など、短期間での採用を目指す場合は、集客力の高い媒体を選ぶことが重要です。
たとえば、「doda」や「リクナビNEXT」は掲載直後から応募が期待でき、短期間でのマッチングに適しています。加えて、掲載順位を上げるためのオプションを併用することで、求人情報の露出を最大化し、より多くの応募者を募ることも可能です。
ただし、スピード重視の採用では、媒体選定と並行して応募者の対応体制の整備も欠かせません。即日掲載・即日応募に対応できる運用体制を構築しておくことで、これらの媒体の効果を最大限に活かすことができるでしょう。
地方や地元で働きたい人を採用したい
地域に根ざした人材を採用したい場合は、地元志向の強い媒体を活用してみましょう。
たとえば、「タウンワーク」や「はたらいく」は地域密着型の求人媒体として高い認知度を誇り、地域在住者に向けた訴求がしやすいのが特徴です。
さらに、勤務地の詳細表記や通勤手段の明示など、地域性に配慮して求人情報を書くことも重要です。地元密着型の採用では地元志向の強い媒体を利用するだけでなく、求人情報をローカライズすることが採用成功のポイントとなります。
専門職・経験者を採用したい
専門性の高い職種や即戦力人材を採用したい場合は、ハイクラス向けの媒体を活用するのが効果的です。
たとえば、「Green」はIT・Web系に強く、「ビズリーチ」は管理職や専門職の採用に特化しています。いずれもスカウト機能やダイレクトリクルーティングを活用できる点が特徴です。
採用単価は高くなる傾向にありますが、マッチ度の高い応募が得られるため、結果的に高効率となるケースも少なくありません。求人票の専門性や訴求力を高めることで、採用ターゲット層に響く求人を的確に発信することができます。
採用ブランディングを強化したい
採用そのものだけでなく、企業のイメージ向上や認知拡大も目的とするのであれば、ブランディング重視の媒体を選びましょう。
たとえば、「Wantedly」は企業のストーリーや理念を伝えることに強みがあり、写真や動画を用いたコンテンツによって共感を引き出しやすい設計となっています。このような媒体では、応募数よりも応募者の「質」や「共感度」に注目するのが効果的です。
自社のカルチャーやビジョンに共鳴し、長期的な活躍が見込める人材を惹きつけたい企業にとって有効な手段となり得るでしょう。
掲載料を重視する場合の求人サイトの選び方

掲載料を重視して求人サイトを選ぶ際には、以下のようなポイントを押さえることが大切です。
- 採用ターゲットにマッチした求人サイトを選ぶ
- 無料掲載から始めて反応を見る
- 料金体系が明確な求人サイトを選ぶ
- 料金に含まれているサービス内容を確認する
- 複数媒体を試して効果を検証する
ここでは、掲載料を重視する場合の求人サイトの選び方について解説します。
採用ターゲットにマッチした求人サイトを選ぶ
求人広告の費用対効果を最大化するためには、まず「誰を採用したいか」を明確にすることが重要です。職種やスキル、経験、勤務地など、求める人物像を具体的に言語化しましょう。
また、求人サイトごとにユーザー属性や得意な業種・職種は異なります。たとえば若手を採用したい場合であれば、「Re就活」のような20代向けの転職サイトを利用するなど、採用ターゲットにマッチした求人サイトを選ぶことが大切です。
採用ターゲットと媒体の属性が一致することで、無駄な出稿を減らし、最小限のコストで最大の成果を得ることができます。
無料掲載から始めて反応を見る
求人掲載に不慣れな場合や初めての採用活動では、無料掲載からスタートするのが効果的です。費用をかけずに求人サイトの反応をうかがうことで、低リスクで傾向をつかむことができます。
実際に応募が集まるかどうか、どのような層からの応募があるかを確認したうえで、必要に応じて有料プランやオプションの導入を検討するのが堅実でしょう。
効果を確認しながら段階的に投資することで、費用対効果の高い採用活動が実現できます。
料金体系が明確な求人サイトを選ぶ
求人サイトを選ぶ際は、料金体系の明瞭さをも重視しましょう。料金体系には、主に「掲載型」「成果報酬型」「クリック課金型」などがあります。目的や予算に応じて、最適な形式を選ぶことが重要です。
たとえば、短期で多くの応募を集めたい場合は「掲載型」、コストを抑えながら質の高い応募を狙う場合は「成功報酬型」「クリック課金型」が適しています。
また、オプション費用や追加課金の条件についても事前に確認しておくことで、予算超過のリスクを防げます。複数サイトの料金を比較し、予算に対して最も納得感のある媒体を選定するとよいでしょう。
料金に含まれているサービス内容を確認する
同じ掲載料金でも、含まれているサービス内容は求人サイトごとに大きく異なります。原稿作成の有無・画像撮影・効果分析・レポート提供・サポート体制など、どのサービスが基本料金に含まれていて、どこからオプション料金が必要なのかをしっかり確認しましょう。
たとえば、掲載料金にプロのライターによる原稿作成が含まれていれば、自社での制作費用が不要になり、トータルコストを抑えられます。サポートが手厚い媒体であれば、掲載後の改善提案や運用支援も受けられるため、採用担当者の負担軽減にもつながるでしょう。
このように、費用だけでなく「何が含まれているのか」に注目することで、実質的なコストパフォーマンスを見極められます。
複数媒体を試して効果を検証する
効果的な媒体選定には、実際に複数の求人サイトを試すことが近道です。一定期間、複数の媒体を同時に活用し、応募数・応募の質・採用率・費用を比較検証しましょう。
データを基に成果の高い媒体を絞り込み、次回以降の予算を集中投下することで、採用活動のPDCAサイクルを回すことが可能です。トライアル運用と効果分析を繰り返すことで、自社に最適な採用チャネルが見えてきます。
求人サイトの掲載料の基本
求人サイトの掲載料には、さまざまなスタイルがあります。ここでは、求人サイトの掲載料の基本について解説します。
求人サイトの料金体系の種類
求人サイトには複数の料金体系があり、それぞれの特性を理解した上で選定することが重要です。代表的な料金体系は次の通りです。
| 掲載型(定額制) | 一定期間の掲載に対して定額料金を支払う方式 |
| 成果報酬型 | 応募や採用が成立した場合のみ課金される方式 |
| スカウト課金型 | スカウトメールの送信数や開封数、面談の設定数に応じて料金を支払う方式 |
| クリック課金型(PPC) | 求人がクリックされた回数に応じて料金が発生する方式 |
掲載型は短期間で応募者を集めたい場合に適しています。成功報酬型は応募や採用が成立した場合のみ課金される方式のため、リスクは低いですが、1件あたりの単価は高くなる傾向があります。
スカウト課金型は、対象者を絞って採用活動を実施したい場合に適したスタイルです。クリック課金型は興味を持って閲覧された回数にのみ料金が発生することに加え、1日あたりの予算に上限を設定できるケースも多いため、費用をコントロールしながら利用したい企業におすすめです。
このように求人サイトの料金体系には複数の種類があるため、業種や職種の難易度、自社の採用計画に応じて最適な形式を選ぶとよいでしょう。なお、会計処理上の勘定科目の仕分けとしては「広告宣伝費」または「採用教育費」として計上するのが一般的です。
掲載料に含まれるサービス内容
同じ料金でも、求人サイトごとに提供されるサービス内容には差があります。そのため、料金に含まれている項目を明確に把握し、実質的なコストパフォーマンスを判断することが大切です。
たとえば、掲載料が安くても運用サポートがなく、すべて自社で対応する必要がある場合は結果的に社内工数が増えて非効率になることもあります。とくに原稿作成・写真撮影・動画作成・効果分析・各種サポートなどは、基本料金に含まれるケースもオプションとなるケースも多いため、事前に確認しておくと安心です。
掲載料だけで求人サイトを判断せず、含まれるサービス内容を比較し、もっとも効果的なプランを選びましょう。
求人サイトにおける無料掲載と有料掲載の違い
求人サイトの中には、無料で掲載できるサービスもあります。ただし、サイトによって無料・有料の扱いは異なるため、利用したいサイトがあれば個別に内容を確認しておきましょう。
ここでは、求人サイトにおける無料掲載と有料掲載の一般的な違いについて解説します。
掲載順位や表示回数
求人サイトでの露出量は、無料掲載と有料掲載とで大きく異なる場合があります。
無料掲載は検索結果の下位に表示されることが多く、求職者の目に留まる機会が限定的になるため、応募数にも影響します。一方、有料掲載では検索結果の上位や特集枠に表示されやすく、閲覧数や応募数も一定数期待できます。
掲載順位や表示回数などのロジックは媒体ごとに異なるため、事前に確認しておくことが重要です。とくに採用スピードや露出を重視する場合は、有料プランの活用を検討するとよいでしょう。
掲載できる情報量や表現の自由度
求人票に掲載できる情報の量や表現の幅も、有料プランでは大きく広がるケースがあります。文字数制限が緩和されるだけでなく、写真・動画・レイアウトの自由度が向上する場合も少なくありません。
自由度や情報量が増すことで職場の雰囲気や企業の魅力を多面的に伝えることができ、応募者の理解と共感を促進できます。
一方、無料掲載ではフォーマットが固定されていることが多く、記載できる内容や表現が制限されがちです。自社の魅力を十分に伝えたい場合は、有料プランによる情報の拡充が効果的でしょう。
サポート内容
求人媒体によっては、無料掲載ではサポートが一切受けられないケースもあります。掲載後の改善提案や専任担当者による相談対応などは、有料プランの特典として提供されることが一般的です。また、応募状況のレポート提供が有料プランに含まれているケースもあります。
こうしたサポートの活用は、採用活動の質や効率を高めるために非常に有効です。とくに採用に不慣れな企業や人的リソースが限られている場合には、有料プランの手厚い支援が大きな助けとなります。そのため、求人サイトが提供するサポート体制も費用対効果の一部と考え、比較検討するとよいでしょう。
掲載期間や更新頻度
無料掲載では、掲載期間が短く設定されていたり、自動的に非表示となったりするケースが多く見られます。また、情報の修正や更新に制限がかかるケースも少なくありません。
一方、有料掲載では長期間の掲載が可能であり、期間中の原稿修正や掲載延長も柔軟に対応可能です。採用活動の進捗に応じた情報更新ができるため、長期的な採用活動にも適しています。
継続的に求人情報を表示し続けたい場合や、求人内容を適宜調整する可能性がある場合には、有料プランのほうが運用しやすいといえるでしょう。
求人サイト掲載料の費用対効果を最大化する方法
求人サイト掲載料のコストパフォーマンスを向上させるには、以下のようなポイントを押さえるとよいでしょう。
- 採用ターゲットを明確にする
- 相性重視で媒体を選定する
- 原稿作成はプロへの依頼を検討する
- アクセスや応募のデータを確認する
- タイトル・写真・待遇条件を改善して差別化する
- 募集終了後に応募者の質と採用率をチェックする
- 複数媒体を使用する場合には棲み分けを意識する
ここでは、求人サイト掲載料の費用対効果を最大化する方法を解説します。
採用ターゲットを明確にする
費用対効果を高めるためには、まず「誰を採用したいのか」を明確に定義しましょう。求める職種やスキル、経験年数、勤務地などの条件を洗い出すことで、求人サイトの選定や原稿作成の方針が明確になります。
また、採用ターゲットを明確にすることによって、求人広告の内容に一貫性が生まれ、求職者とのマッチング精度の向上も期待できます。さらに、ターゲットに特化したサイト選定や表現の工夫も可能になり、応募の質が向上するため、結果的に採用単価の低減にもつながるでしょう。
相性重視で媒体を選定する
求人サイトごとにユーザー属性や得意な業種・職種は異なるため、自社の採用ニーズと相性の良い媒体を選ぶことが重要です。求人媒体の特徴を理解し、それぞれの特性を理解して使い分けることで効果を最大化できます。
また、同業他社がどの媒体を利用しているかを参考にすることで、業界内での有効な選択肢が見えてくることもあります。媒体選定は「広く浅く」ではなく「深く的確に」行うことが成果への近道です。
原稿作成はプロへの依頼を検討する
求人広告の原稿は、応募の有無を左右する大切な要素です。表現が曖昧であったり、魅力が伝わらない原稿では、せっかく費用をかけても成果につながりません。求人サイトによっては原稿作成サービスが料金に含まれていることもありますが、含まれていない場合はプロのライターに依頼することも検討しましょう。
とくに、魅力の言語化が難しい職種や競合の多い業界では、外部の専門家による文章で差別化することが効果的です。企業の魅力がしっかりと伝わる原稿を掲載することが、費用対効果の向上につながります。
アクセスや応募のデータを確認する
求人を出した後は、表示回数や応募数、クリック率などのデータを確認しましょう。データ分析によって、どこに改善の余地があるかを明確にできます。
たとえば、表示回数が少ない場合は求人票のタイトルや媒体選定の見直し、クリック率が低い場合は画像や冒頭文の変更を検討しましょう。
また、応募があっても採用につながらない場合は、待遇条件や選考フローの再検討も必要です。数字をもとに行動することで、採用活動の無駄を削減できます。
タイトル・写真・待遇条件を改善して差別化する
求人票の第一印象を決めるのは、タイトルや写真です。他社と比較される中でクリックしてもらうには、視覚的にも言語的にも惹きつける工夫が欠かせません。たとえば、「未経験歓迎」「年休120日」「柔軟な働き方」など、求職者のニーズに合ったキーワードを盛り込むと、閲覧数が増える可能性があります。
また、写真や動画を活用して職場の雰囲気を伝えることで、信頼性と魅力が格段に向上します。見せ方ひとつで反応率が大きく変わる可能性があるので、求職者の関心を引くための工夫を意識してみてください。
募集終了後に応募者の質と採用率をチェックする
応募数だけで判断するのではなく、実際に採用に至ったかどうか、その人材が定着しているかどうかも評価しましょう。採用率が低ければ選考基準や訴求内容を見直す必要がありますし、定着率が低ければミスマッチの可能性が考えられます。
また、求人サイトごとに「質の高い応募が集まるかどうか」を記録することで、次回以降の出稿判断に活かすことができます。このような振り返りを通じてPDCAサイクルを回し、効率的な採用サイクルの構築を目指しましょう。
複数媒体を使用する場合には棲み分けを意識する
複数の求人サイトを活用する場合は、それぞれの媒体の特性を理解し、役割分担を明確にすることが大切です。同じ求人でも媒体によって見せ方や訴求ポイントを変えることで、より広範囲に効果的な訴求が可能になります。
たとえば、一方では雰囲気重視、もう一方では条件重視といった具合に、アプローチを分けて展開するのも一つの方法です。戦略的に棲み分けを行うことで、重複を避けつつ、幅広い母集団形成が実現できます。
求人サイトは掲載料だけでなく総合的な比較・検討が重要
求人広告にかけられる予算が限られていても、成果につながる採用活動は可能です。重要なのは、掲載料の安さだけで判断せず、料金体系や無料掲載の有無、サポート内容、そして自社の採用ターゲットとの相性までを総合的に比較・検討することです。
また、掲載後のデータ分析や原稿改善を重ねることで、限られた予算で高品質な採用を実現することができます。そのため、まずは気になる求人サイトを無料または低コストで試しながら、効果を検証し、自社にとって最適なチャネルを見つけていくとよいでしょう。
求人サイトの選定にお悩みの際は、「Re就活」をぜひご検討ください。経験もポテンシャルもある若⼿⼈材をターゲットに、効果的な採⽤活動を実現。専任のカスタマーサクセス担当が求人掲載・採用活動をサポートし、費用対効果に優れた採用計画をご提案いたします。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。