中途採用比率とは?
計算方法から公表義務、企業の活用事例まで徹底解説
公開日:2025.08.29
更新日:2026.01.01

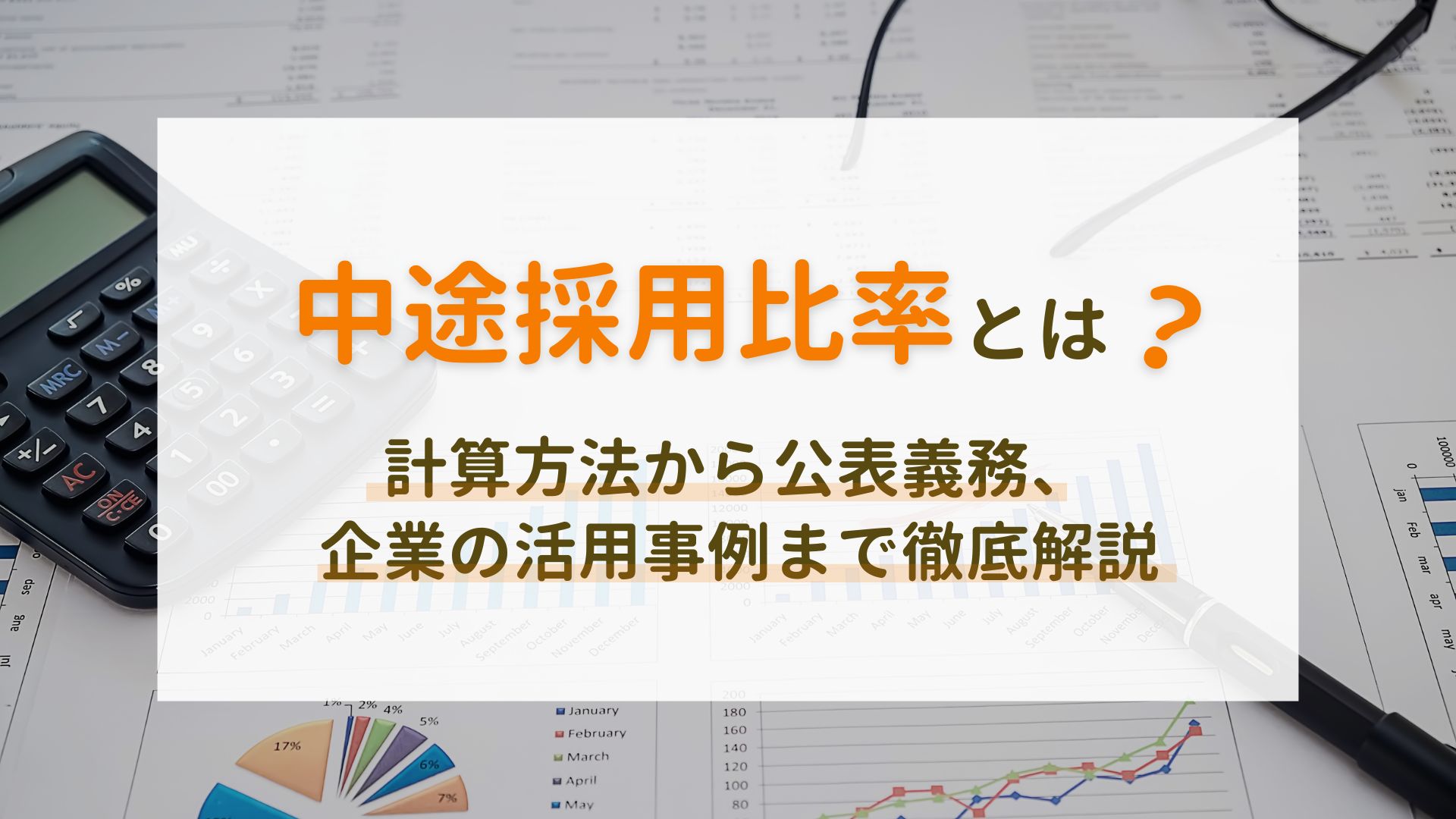
「自社の中途採用の割合は、他社と比べてどうなのだろうか」「法律で中途採用比率の公表が義務化されたと聞いたが、具体的に何をすればよいのかわからない」とお悩みの採用担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
中途採用比率は、単なる採用実績の数値ではなく、企業の成長戦略や人材に対する考え方を社外に示す重要な指標です。
本記事では、中途採用比率の定義や計算方法といった基本から、公表義務の対象企業、公表方法、業界別の平均値までを網羅的に解説します。さらに、比率の高低がもたらすメリット・注意点や、採用ブランディングへの活用方法についても触れていきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、中途採用比率に関するあらゆる疑問が解消され、自社の採用戦略を客観的に見直すヒントが得られるはずです。
まずは、中途採用比率の正しい知識を身につけ、戦略的な採用活動の第一歩を踏み出しましょう。
中途採用比率とは?
中途採用比率とは、企業が採用した正規雇用労働者のうち、中途採用者が占める割合を示す指標です。この比率を分析することで、企業の採用方針や組織の人材構成を客観的に把握できます。
本章では、中途採用比率の基本的な定義と、公表する際の具体的な計算方法について詳しく解説します。
定義・意義
中途採用比率は、正規雇用労働者として採用した人材全体の中で、新卒以外の採用者、すなわち中途採用者がどれくらいの割合を占めるかを示す指標です。
この数値は、企業が即戦力を重視しているのか、あるいは長期的な視点で人材を育成する文化があるのかといった、採用戦略の方向性を理解するための重要な手がかりとなります。
計算方法
中途採用比率は、以下の計算式で算出します。
中途採用比率(%) = (公表前3事業年度内に採用した中途採用者の数) ÷ (公表前3事業年度内に採用した正規雇用労働者の数) × 100
算出された数値は、小数点以下第一位を四捨五入して整数で公表するのが一般的です。
公表にあたっては、採用活動が終了した直近3事業年度について、各年度ごとに算出した比率を明記する必要があります。もし特定の年度で採用がなかった場合は、「採用なし」と記載します。
中途採用比率の公表義務
2021年4月に施行された改正労働施策総合推進法により、一定規模以上の企業に対して中途採用比率の公表が義務付けられました。これは、労働者が自身のキャリアプランに応じて多様な働き方を選択できる社会を目指すための施策の一環です。
ここでは、公表義務の対象となる企業や具体的な公表方法、注意すべき点について解説します。
対象企業と法的背景
中途採用比率の公表が義務付けられているのは、常時雇用する労働者の数が301人以上の企業です。この義務化は、労働施策総合推進法の改正によるもので、中途採用を希望する求職者が、企業の採用スタンスを判断しやすくする目的があります。
現時点では、公表義務を怠った場合の罰則規定は設けられていません。しかし、公表しないことで企業の透明性に疑問を持たれたり、採用市場でのイメージダウンにつながったりするリスクは考慮すべきでしょう。
公表方法と時期
中途採用比率は、年に1回以上、定期的に更新して公表する必要があります。
多くの求職者がアクセスしやすいように、自社の公式ウェブサイトの採用情報ページや、厚生労働省が運営する「しょくばらぼ」などのポータルサイトを活用して公表することが推奨されています。
公表のタイミングとしては、法律が施行された2021年4月以降に開始される事業年度から公表を始め、その後は概ね1年以内に最新の情報に更新していくことが求められます。
公表する際には、いつの時点のデータであるかを示す「公表日」や、集計の対象となった期間を明確に記載することが重要です。
注意点
公表にあたっては、いくつか注意すべき点があります。
まず、グループ企業の場合は、原則として企業ごとに比率を算出して公表します。グループで一括採用を行っている場合でも、可能な限り各社別の実態がわかるように公表することが望ましいとされています。
また、計算に含める「中途採用者数」は、対象となる事業年度内に雇用契約を開始した正規雇用の労働者に限り、内定段階の人は含めません。
直近3事業年度の比率を公表する際は、それぞれの年度の比率を個別に示し、3年分を合算して一つの数値として公表することは避けてください。
中途採用比率の全国平均と最新の動向
近年、日本の労働市場では人材の流動化が進み、中途採用の重要性が増しています。企業の成長戦略において、即戦力となるキャリア人材の獲得は不可欠な要素となりました。
日本経済新聞社の調査によると、2023年度の採用計画における中途採用の比率は37.6%に達し、過去最高を記録しました。特に大企業を中心に、従来の「新卒一括採用」から、経験やスキルを持つ人材を柔軟に受け入れる「中途採用」へとシフトする動きが加速しています。
さらに、この流れを裏付けるように、株式会社学情の調査でも、企業のキャリア採用(中途採用)は維持・拡大傾向にあり、3割を超える企業が前年度より採用人数を増やす計画であることが明らかになっています。
中でも注目すべきは、採用ニーズの中心が若手層へと移行している点です。
キャリア採用で特に採用したい年齢層として「20代後半〜30代前半」が7割を占めるという結果も出ており、多くの企業が事業の中核を担う次世代リーダー候補の獲得に意欲を高めていることがうかがえます。
※参考:日本経済新聞「中途採用比率が最高に、日本型雇用変わる?」
※引用:株式会社学情「キャリア採用動向調査2025」
中途採用比率が高い企業の事例
中途採用比率が高い企業は、特定の業界に偏る傾向があります。
例えば、常に新しい技術やビジネスモデルが生まれるIT業界や、専門性が求められる外資系企業、スピーディーな事業展開を目指すベンチャー企業などでは、即戦力人材を積極的に採用するため、中途採用比率が50%を超えるケースも珍しくありません。
具体的な企業例として、トヨタ自動車では技術職・事務職の中途採用比率が2020年度の約30%から2022年度には47%へと大幅に増加しています。
これは、自動車業界が「100年に一度の大変革期」を迎える中で、多様な専門知識を持つ人材を外部から積極的に取り入れる戦略の表れと言えるでしょう。
中途採用比率が高い企業のメリット・注意点
中途採用比率が高いことは、企業の成長戦略において多くのメリットをもたらす一方で、組織運営上の注意点も存在します。外部から多様な人材を受け入れることは、組織の活性化につながる反面、文化の融合や定着支援といった課題も生じさせます。
ここでは、中途採用比率が高いことによるメリットと、留意すべき注意点をそれぞれ解説します。
メリット
中途採用比率が高い最大のメリットは、多様な経験や専門スキルを持つ「即戦力人材」を確保しやすい点です。これにより、新規事業の立ち上げや既存事業の課題解決をスピーディーに進めることができます。
また、異なるバックグラウンドを持つ人材が集まることで、組織内に新しい視点やノウハウがもたらされ、イノベーションが生まれやすい環境が醸成されます。
さらに、「中途採用に積極的」という企業姿勢は、多様なキャリアを持つ求職者にとって魅力的であり、採用ブランディングの観点からも有利に働くでしょう。
注意点
一方で、注意すべき点も存在します。中途採用者はバックグラウンドが多様であるため、企業文化への適応や人間関係の構築をサポートするための教育・研修コストが増加する可能性があります。
また、既存の社員と新しく加わった中途採用者との間で、仕事の進め方や価値観の違いから摩擦が生じることも考えられます。組織としての一体感を醸成するための丁寧なコミュニケーションや、オンボーディング(受け入れ研修)の仕組みづくりが重要になります。
中途採用比率が低い企業のメリット・注意点
中途採用比率が低い、つまり新卒採用を中心とした組織にも、独自の強みと課題があります。長年にわたり同じ文化を共有する人材で構成される組織は、強い一体感を持つ一方で、環境変化への対応力が課題となることもあります。
ここでは、新卒採用中心の企業が持つメリットと、変化の激しい時代において注意すべき点を解説します。
メリット
新卒採用を中心とする企業では、社員が同じ価値観や企業文化を共有しやすく、組織としての一体感を醸成しやすいというメリットがあります。入社時から一貫した教育・研修プログラムを提供できるため、企業理念に沿った人材を計画的に育成することが可能です。
また、採用活動の時期や手法が定型化されているため、採用コストや工数の予測が立てやすく、安定した採用計画を運用できる点も強みと言えるでしょう。
注意点
しかし、新卒採用に偏ることはリスクも伴います。少子化の影響で新卒の応募者数が減少傾向にあるため、将来的に必要な人材を確保できなくなる可能性があります。
また、外部からの新しい視点や専門スキルが入りにくくなるため、組織の同質化が進み、ビジネス環境の変化に対応できない「組織の硬直化」を招く恐れがあります。常に市場の動向を注視し、必要に応じて外部の知見を取り入れる柔軟性が求められます。
中途採用比率と採用戦略
企業の持続的な成長のためには、中途採用比率を経営戦略や事業計画と連動させた、戦略的な採用計画が不可欠です。自社が目指す方向性や、各部門で求められる人材要件を明確にした上で、新卒採用と中途採用の最適なバランスを見極める必要があります。
例えば、新規事業の立ち上げフェーズでは専門スキルを持つ中途採用者の比率を高め、事業が安定期に入れば長期的な視点で新卒採用を増やすなど、事業のライフサイクルに合わせたハイブリッドな採用戦略が有効です。
また、人材紹介やリファラル採用など、多様な採用チャネルを駆使して、求める人材に的確にアプローチすることも重要となります。
中途採用比率を「攻めの採用ブランディング」に活かす
公表が義務化された中途採用比率は、単なる報告義務として捉えるのではなく、自社の魅力を伝える「攻めの採用ブランディング」のツールとして活用できます。
比率の数字そのものではなく、その背景にあるストーリーを語ることで、求職者の共感を呼び、採用競争力を高めることが可能です。
「なぜ、この比率なのか?」をストーリーで語り、候補者の共感を呼ぶ
自社の中途採用比率について、その背景にある経営戦略やビジョンをストーリーとして伝えることが重要です。
例えば、「当社は今、第二創業期を迎えています。既存の枠にとらわれない多様な知見を融合させ、新たなイノベーションを創出するために、意図的に中途採用比率を高めています」といったメッセージは、変化を求める優秀な人材に響くでしょう。
逆に、「私たちは100年続く企業を目指し、長期的な視点での人材育成を最重要視しています。そのため、新卒採用を中心に、次世代のリーダーをじっくりと育てています」というストーリーは、安定した環境で成長したいと考える人材に安心感を与えます。
20代・第二新卒に響くメッセージとは?
特に成長意欲の高い20代や第二新卒の若手層にアピールする際は、「成長機会」をキーワードにメッセージを設計することが効果的です。
中途採用比率が高い企業であれば、「多様なバックグラウンドを持つ先輩社員がロールモデルとなり、刺激を受けながら成長できる環境です」とアピールできます。
一方、比率が低い企業であれば、「体系化された研修制度と手厚いOJTがあり、着実にスキルアップできる環境が整っています」といった点を強調することで、若手層の成長したいというニーズに応えることができます。
中途採用比率に関するよくある質問
ここでは、中途採用比率に関して採用担当者から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
公表義務に罰則はある?
2025年現在、中途採用比率の公表義務に違反した場合の直接的な罰則規定は法律上設けられていません。
しかし、公表を怠ることで、求職者や投資家から「法令遵守の意識が低い」「情報の透明性が低い」といったネガティブな評価を受ける可能性があります。
中途採用比率を高めると評価は上がる?
中途採用比率が高いこと自体が、直接的に企業の評価を高めるわけではありません。重要なのは、その比率が企業の成長戦略とどう結びついているかを明確に説明できることです。
戦略に基づいた人材採用を行っていることを示すことができれば、投資家や求職者からのポジティブな評価につながる可能性があります。
公表するページはどこに掲載すればよい?
多くの企業では、自社のコーポレートサイト内にある「採用情報」や「IR情報」、「サステナビリティ」といったページに掲載しています。
求職者や関係者が容易にアクセスできる場所に掲載することが望ましいでしょう。
途中で年度区切りが変わった場合の対応は?
企業の合併や決算期の変更などにより事業年度の区切りが変わった場合は、変更後の新しい年度区切りに基づいて比率を算出し直す必要があります。
その際は、集計期間が変更になった旨を注記として明記することが望ましいです。
中途採用比率を引き下げるにはどうすれば?
中途採用比率を意図的に引き下げたい場合は、新卒採用の枠を拡大したり、既存社員の育成に力を入れて離職率を低下させたりといった、中長期的な人事戦略が必要になります。
短期的な施策で比率を操作するのではなく、自社の目指す組織像に基づいた計画的な取り組みが求められます。
中途採用比率を戦略に活かし、今後の採用へつなげる
本記事では、中途採用比率の定義や計算方法、公表義務といった基本的な知識から、比率の高低がもたらすメリット・デメリット、さらには採用ブランディングへの活用法までを解説しました。
中途採用比率は、単に公表義務を果たすための数値ではなく、自社の採用戦略や組織のあり方を社内外に示す重要な指標です。
大切なのは、比率の数字そのものに一喜一憂するのではなく、その背景にある自社の戦略を明確にし、求職者や社会に対して説得力のあるメッセージとして発信していくことです。
自社の中途採用比率を客観的に把握し、今後の採用計画や組織開発に活かしていくことで、より効果的な人材獲得と企業の持続的な成長につなげることができるでしょう。
この記事が、貴社の採用戦略を見直す一助となれば幸いです。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。








