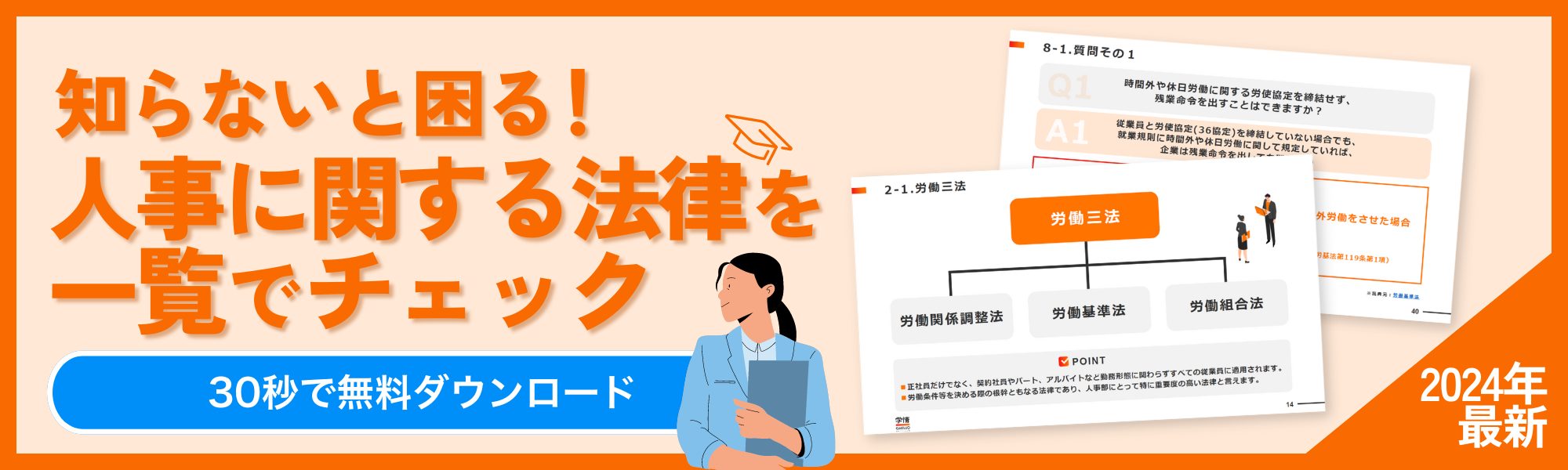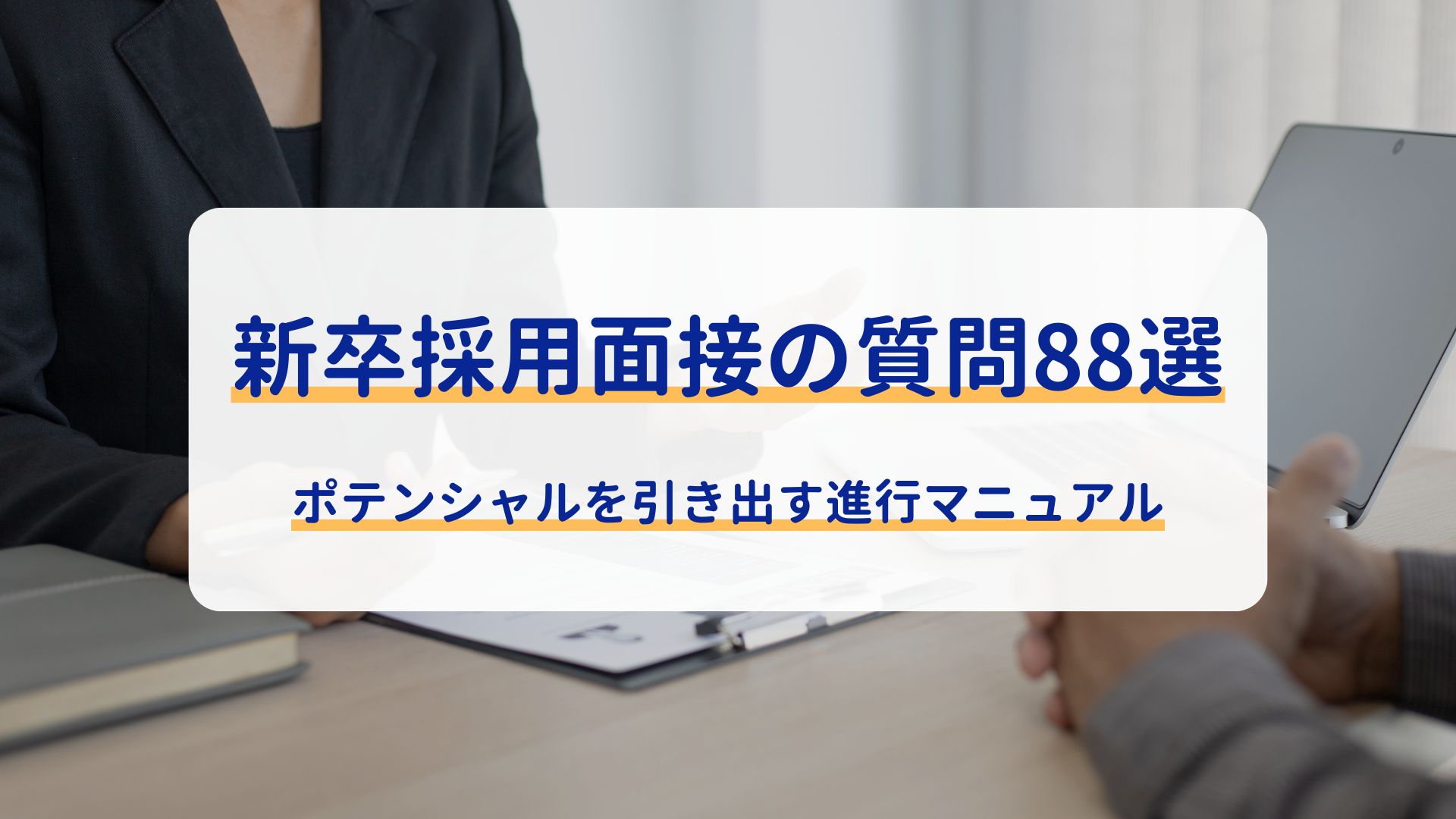「中途採用者の有給休暇はいつ付与すればいい?」「年5日の取得義務はどう管理する?」など、採用担当者として悩む場面は少なくないでしょう。
この記事では、中途採用における有給休暇の基本的なルールから、付与タイミングの具体例、日数計算、年5日取得義務への対応、試用期間中の扱いまで、採用担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、法的なリスクを回避し、適切な労務管理を実現できるだけでなく、従業員が安心して働ける環境を整え、エンゲージメント向上にも繋がります。
ぜひ、貴社の労務管理にお役立てください。
中途採用者の有給休暇に関する基本ルール
中途採用者に対する有給休暇の付与は、労働基準法で定められたルールに則って行う必要があります。
新卒採用か中途採用かに関わらず、原則は同じです。この章では、有給休暇を付与する上での基本的な条件や日数、有効期限について解説します。
法定の付与条件と日数
年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。
正社員や契約社員といった雇用形態に関わらず、①入社日から6ヶ月間継続して勤務し、②その期間の全労働日の8割以上に出勤した労働者に対して付与しなければなりません。
フルタイム勤務の場合、初回の付与日数は10日間です。
その後は勤続年数に応じて付与日数が増加し、入社から1年6ヶ月後には11日、2年6ヶ月後には12日と増えていき、勤続6年6ヶ月以上で最大の20日間が付与されます。このルールは中途採用者にも等しく適用されます。
出勤率の算出方法の具体例
有給休暇付与の条件である「全労働日の8割以上出勤」の出勤率は、以下の計算式で算出します。
- 出勤率 = 出勤日数 ÷ 全労働日数
この「全労働日」とは、就業規則などで定められた所定労働日のことです。休日出勤日は含まれません。また、「出勤日数」には、業務上の傷病による療養期間(労災)、産前産後休業、育児休業、介護休業の期間も出勤したものとして扱います。
例えば、全労働日が120日の場合、出勤率8割を満たすには96日以上の出勤が必要です。遅刻や早退は、1日単位の勤務が行われていれば原則として出勤日に含まれますが、就業規則の定めに注意が必要です。
有給の有効期限と繰越ルール
年次有給休暇には、2年間の有効期限があります。
付与された年度内に使い切れなかった有給休暇は、翌年度に限り繰り越すことが可能です。
例えば、今年度付与された10日間のうち7日間を取得した場合、残りの3日間は翌年度に繰り越せます。
ただし、繰り越せるのは前年度分のみで、前々年度分は時効により消滅します。そのため、労働者が保有できる有給休暇の日数は、当年度の付与日数と前年度からの繰越日数の合計が最大となります。
中途入社時の有給休暇付与タイミング
中途入社者の有給休暇をいつ付与するかは、企業の労務管理において重要なポイントです。
法律で定められた原則的なタイミングのほか、企業の実情に合わせて柔軟な対応も可能です。ここでは、代表的な3つの付与タイミングについて解説します。
標準的な付与タイミング(入社後6ヶ月)
法律上の原則では、有給休暇は入社日から起算して6ヶ月間継続勤務した時点で付与されます。
例えば、4月1日に入社した社員であれば、6ヶ月後の10月1日が最初の有給休暇付与日(基準日)となります。
この入社後6ヶ月間は法定の有給休暇がない状態のため、この期間に病気などで休んだ場合は欠勤扱いとなり、原則として無給となります。採用担当者は、入社時にこの点を本人に説明しておくと、後のトラブルを避けやすくなります。
入社時の前倒し付与・分割付与
企業によっては、法定のタイミングより早く有給休暇を付与する「前倒し付与」を導入しているケースがあります。
法律の基準を上回る、労働者にとって有利な条件であれば、このような対応も問題ありません。例えば、入社初日に独自の特別休暇を数日付与することで、中途入社者が新しい環境に慣れるまでの急な用事にも対応しやすくなり、安心感に繋がります。
また、本来6ヶ月後に10日付与するところを、入社時に5日、6ヶ月後に残りの5日を付与するといった「分割付与」も可能です。これにより、入社初期の休暇取得ニーズにも応えられます。
有給休暇基準日の統一(一斉付与)
全社員の有給休暇付与日を、特定の日(例:毎年4月1日)に統一する「一斉付与」という方法もあります。
この方法を採ることで、社員ごとに入社日が異なっていても、有給休暇の管理を一元化でき、人事担当者の業務負担を大幅に軽減できます。
中途入社者の場合、初回の付与は法定通り入社6ヶ月後に行い、2回目以降の付与を全社統一の基準日に合わせるのが一般的です。ただし、運用にあたっては労働者に不利益が生じないような配慮(比例付与など)が必要であり、就業規則への明記が求められます。
月途中入社の場合の起算日と扱い
有給休暇の付与要件を計算する上での「起算日」は、月の途中であっても実際に入社した日となります。
そのため、原則的なルール(個別管理)のもとでは、月初に入社しても月末に入社しても、その日から6ヶ月が経過した時点で有給休暇が付与されるという扱いに違いはありません。
中途入社社員の付与日数と2回目の有給付与タイミング
中途入社者の有給休暇について、初回の付与タイミングだけでなく、その後の付与日数や2回目の付与時期の管理も重要です。
勤続年数に応じた日数の変化や、管理方法による付与タイミングの違いを正しく理解しておきましょう。
勤続年数に応じた付与日数(法定基準)
有給休暇の付与日数は、勤続年数に応じて法律で定められた通りに増加します。
フルタイム労働者の場合、付与日数の推移は以下の通りです。
| 勤続年数 | 付与日数 |
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
採用担当者は、各社員の勤続年数を正確に把握し、法定の日数を下回ることがないよう、適切に付与する必要があります。
個別基準日の場合の2回目付与時期
社員一人ひとりの入社日を基準に有給休暇を管理する「個別基準日」の場合、2回目の付与タイミングは、初回の付与日(入社6ヶ月後)から1年後です。
例えば、2024年4月1日入社の社員は、2024年10月1日に初回10日が付与され、その1年後である2025年10月1日に2回目となる11日が付与されます。
この方法は、社員ごとに付与サイクルが異なるため、管理が煩雑になりがちです。特に中途採用者が多い企業では、管理システムなどを活用し、付与漏れがないよう注意が必要です。
基準日統一運用の場合の2回目付与時期
全社で有給休暇の基準日を統一している場合、中途入社者の2回目以降の付与は、その統一基準日に行われます。
初回付与後、最初に到来する共通の基準日に次年度分が付与されるため、入社時期によっては、初回の付与から1年を待たずに2回目の付与が行われることがあります。
例えば、基準日を毎年4月1日に定めている会社で、2024年7月1日に入社した社員の場合を考えます。まず、法律の原則通り、入社6ヶ月後の2025年1月1日に初回として10日間の有給休暇が付与されます。その後、会社は全社の付与サイクルを統一するため、本来の2回目の付与日(2026年1月1日)を待たずに、直近の統一基準日である2025年4月1日に2回目(11日間)の有給休暇を前倒しで付与します。
このように、付与のタイミングが法定より早まることは労働者の不利益にはならないため、適法な運用とされています。
比例付与の設計(初年度の按分)
有給休暇の基準日を全社で統一している企業では、管理を効率化するために、中途入社者の初年度の有給休暇を、次の基準日までの在籍期間に応じて按分(比例配分)して付与する運用が一般的です。
これは、入社日から最初の基準日までの期間に応じて、付与する日数を調整する考え方です。例えば、基準日を毎年4月1日としている会社の場合、以下のように入社月ごとの付与日数を就業規則で定めます。
【比例付与の具体例(基準日:4月1日)】
| 入社月 | 次の4月1日までの在籍月数 | 付与日数(例) |
| :— | :— | :— | | 4月 | 12ヶ月 | 10日 | | 5月 | 11ヶ月 | 9日 | | 6月 | 10ヶ月 | 8日 | | 7月 | 9ヶ月 | 7日 | | 8月 | 8ヶ月 | 6日 | | 9月 | 7ヶ月 | 5日 | | 10月 | 6ヶ月 | 5日 |
このように、入社月が遅くなるほど次の基準日までの期間が短くなるため、初年度に付与される日数も調整されます。そして、この初回の比例付与を受けた後は、翌年以降、全社員と同じ4月1日に規定の日数が一斉に付与されるサイクルに乗ることになります。
年5日有給休暇取得義務と中途入社者の対応
2019年4月の法改正により、すべての企業で「年5日の有給休暇取得」が義務化されました。
この義務は、もちろん中途入社者にも適用されます。ここでは、制度の概要と中途入社者への対応、違反した場合のリスクについて解説します。
年5日取得義務の概要
年5日の有給休暇取得義務とは、年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、付与日から1年以内に最低5日間、企業が時季を指定してでも取得させなければならない、というルールです。
これは、有給休暇の取得率向上を目的としたもので、企業には対象となる労働者の取得状況を管理する「年次有給休暇管理簿」の作成・保存も義務付けられています。
中途入社社員が義務対象となる条件
中途採用で入社した社員も、年次有給休暇が10日以上付与された時点で、この義務の対象となります。
通常のフルタイム勤務であれば、入社6ヶ月後の初回付与で10日間が付与されるため、その付与日から1年以内に5日間の有給休暇を取得させる必要があります。
例えば、10月1日に10日の有給休暇が付与された社員は、翌年の9月30日までの1年間が取得義務の対象期間となります。なお、前倒しや分割で付与した場合でも、年間の合計付与日数が10日に達した時点から義務が発生します。
年5日取得義務違反時のリスクと対策
年5日の取得義務を果たせなかった場合、企業には労働基準法違反として、対象となる労働者1人あたり最大30万円の罰金が科される可能性があります。
中途入社者は他の社員と有給休暇の付与タイミングや管理期間が異なるため、特に取得漏れが発生しやすい傾向にあります。
対策として、採用担当者は個別の有給休暇管理簿を正確に記録し、定期的に取得状況をモニタリングすることが不可欠です。取得日数が5日に満たない社員には、計画的な取得を促すなど、積極的な働きかけが求められます。
前倒し・分割付与時の義務発生タイミング
入社時に一部を有給休暇として前倒し付与した場合、年5日取得義務のカウント開始タイミングに注意が必要です。
義務が発生するのは、あくまで年間の付与日数が「合計で10日」に達した時点からです。
例えば、入社時に5日、入社6ヶ月後に5日を分割付与した場合、後者の5日が付与され、合計が10日になった日から1年間の取得義務期間がスタートします。このように、付与方法によっては義務の発生タイミングがずれるため、個別管理がより一層重要になります。
試用期間中の有給休暇の扱い
中途採用では、多くの場合に試用期間が設けられます。
この試用期間と有給休暇の関係性について、法的な解釈や実務上の注意点を解説します。
試用期間も継続勤務期間に含まれる
有給休暇の付与要件である「6ヶ月の継続勤務」には、試用期間も含まれます。
例えば、3ヶ月の試用期間を経て本採用となった場合でも、有給休暇の付与要件を計算する上での勤務期間は入社日からカウントされます。
したがって、試用期間3ヶ月+その後の勤務3ヶ月で合計6ヶ月が経過し、出勤率の要件を満たせば、有給休暇を付与しなければなりません。「試用期間中は勤務期間に含めない」といった扱いは違法となるため、注意が必要です。
試用期間中に有給休暇を取得できるか
試用期間中であっても、すでに有給休暇が付与されていれば、労働者はそれを取得する権利があります。
例えば、入社時に有給休暇を前倒しで付与する制度がある企業では、試用期間中に有給休暇を取得することが可能です。
会社が「試用期間中だから」という理由で有給休暇の取得を拒否することはできません。また、有給休暇を取得したことを理由に、本採用を拒否したり、評価を下げたりするなどの不利益な取り扱いをすることも、パワーハラスメントや労働基準法違反と見なされる可能性があるため、厳に慎むべきです。
有給休暇基準日の統一運用と比例付与の計算
中途採用者が増えるほど、個別の有給休暇管理は煩雑になります。
その解決策として有効な「基準日の統一」ですが、導入にはいくつかの手続きと注意点があります。ここでは、その運用方法と計算例を詳しく解説します。
基準日統一運用のメリット
有給休暇の付与日(基準日)を全社員で統一する最大のメリットは、管理の効率化です。
社員ごとに入社日が異なっていても、毎年決まった日に一斉に付与処理を行えるため、人事担当者の業務負担が軽減されます。
また、全社的な有給休暇の取得計画が立てやすくなり、計画的な取得促進にも繋がります。特に、年間を通じて中途採用を行う企業にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。
基準日統一運用に必要な手続き
基準日を統一するためには、まず就業規則にその旨を明記する必要があります。
具体的には、「年次有給休暇の基準日は、毎年4月1日とする」といった規定を設け、労働基準監督署に届け出なければなりません。
また、この運用変更によって、法定の付与日よりも遅れて有給休暇が付与されるなど、労働者に不利益が生じないように配慮することが絶対条件です。必要に応じて、労使協定を締結する場合もあります。
中途入社時の比例付与日数の計算方法
基準日を統一している場合、中途入社者の初年度の有給休暇は、入社日から次の基準日までの期間に応じて按分計算(比例付与)するのが一般的です。
例えば、基準日が4月1日の会社で、7月1日に入社した社員がいるとします。この場合、入社日から次の基準日(翌年4月1日)までの在籍期間である9ヶ月分を按分し、所定の日数(例:7日)を付与するといった計算になります。
この具体的な計算ルールや入社月ごとの付与日数は、就業規則で明確に定めておく必要があります。
基準日統一運用での注意点(不利益防止策)
基準日統一で最も注意すべき点は、労働者への不利益な取り扱いを避けることです。
法律で定められた付与日(入社6ヶ月後)よりも付与タイミングを遅らせることはできません。もし統一基準日が法定の付与日より後になる場合は、法定の付与日に先に付与する必要があります。
逆に、法定の付与日より前に統一基準日が到来し、前倒しで付与する場合、その短縮された期間も勤務したものとみなし、次年度以降の勤続年数の計算で不利にならないよう調整しなければなりません。
中途採用者の有給休暇管理におけるポイント
中途採用者の有給休暇を適切に管理し、トラブルを防ぐためには、いくつかの重要なポイントがあります。
日々の管理体制から、社員へのコミュニケーション、そして制度自体の見直しまで、採用担当者が押さえておくべき実践的なポイントを解説します。
年次有給休暇管理簿の作成・活用
企業には、労働者ごとに有給休暇の「基準日」「付与日数」「取得日数」「残日数」を記録した年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する義務があります。
これは中途採用者も例外ではありません。特に、中途採用者は他の社員と基準日や管理期間が異なるため、個別に正確な記録を残すことが極めて重要です。
勤怠管理システムなどを活用し、付与漏れや取得義務違反が発生しないよう、管理体制を整えましょう。
中途入社者への制度周知と取得促進
中途採用で入社した社員に対し、自社の有給休暇制度について丁寧に説明することは、円滑な労務管理の第一歩です。
入社オリエンテーションの場などで、「あなたの最初の有給休暇は、〇年〇月〇日に〇日付与されます」と具体的に伝えることで、本人の不安を解消できます。
また、年5日の取得義務があることも伝え、計画的な取得を促しましょう。入社したばかりで休みを取りづらいと感じる社員もいるため、「遠慮なく取得してください」というメッセージと共に、人事から積極的にフォローすることが大切です。
就業規則や運用ルールの定期見直し
労働関連の法律は、時代に合わせて改正されます。
自社の就業規則や有給休暇の運用ルールが、現在の法律に適合しているか、定期的に見直すことが重要です。
例えば、「試用期間中は有給休暇を付与しない」といった古い規定が残っていると、誤解やトラブルの原因になりかねません。法改正への対応はもちろん、自社の実態に合った、より良い制度となるよう、必要に応じて社会保険労務士などの専門家にも相談しながら、規定を整備していきましょう。
よくある質問:中途採用と有給休暇
Q1. 新卒入社と中途入社で有給休暇の付与ルールに違いはありますか?
A: 法律上の基本的なルールに違いはありません。どちらも「入社後6ヶ月継続勤務」「全労働日の8割以上出勤」という条件を満たせば、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。ただし、企業独自の制度として、中途入社者に対して入社時に特別休暇を付与したり、全社で基準日を統一したりする運用上の違いはあり得ます。
Q2. 中途入社初年度から「年5日」の有給取得義務を守る必要がありますか?
A: はい、守る必要があります。年次有給休暇が10日以上付与された時点から、年5日の取得義務が発生します。フルタイム勤務の中途採用者であれば、通常、入社6ヶ月後に10日付与されるため、その日から1年以内に5日間の有給休暇を取得させなければなりません。
Q3. 試用期間中に有給休暇を取得させても問題ないでしょうか?
A: 法的に全く問題ありません。試用期間中であっても、有給休暇が付与されていれば労働者は取得する権利があり、会社はこれを拒否できません。また、有給休暇の取得を理由に本採用の可否を判断したり、評価を下げたりすることは不利益な取り扱いにあたり、許されません。
Q4. 入社時に有給が付与されることは適法でしょうか?
A: 適法です。法律で定められているのは最低基準であり、それを上回る労働者に有利な条件(法定より早く付与するなど)で有給休暇を付与することは何ら問題ありません。入社直後の生活をサポートする目的や、管理の効率化のために、多くの企業で導入されています。
Q5. 有給は半日や時間単位でも取得できますか?
A: 可能です。有給休暇を半日単位や時間単位で取得できる制度は、多くの企業で導入されています。これを導入するには労使協定の締結が必要ですが、中途採用者も含め、全従業員が柔軟な働き方を選択できるメリットがあります。
Q6. 精勤手当・皆勤手当が有給取得で支給されないのは違法ですか?
A: 違法となる場合があります。有給休暇を取得したことを理由に精勤手当や皆勤手当を減額したり不支給にしたりすることは、労働基準法で禁止されている労働者の正当な権利行使の抑制に当たる可能性があるので注意が必要です。
まとめ
本記事では、中途採用における有給休暇の取り扱いについて、基本的なルールから具体的な運用方法、管理のポイントまで網羅的に解説しました。
中途採用者の有給休暇は、新卒者と同様に労働基準法に基づいた付与が原則ですが、管理を効率化するための「基準日統一」や、入社者の定着を支援する「前倒し付与」など、企業の実情に合わせた柔軟な運用が可能です。
重要なのは、いかなる運用を採用する場合でも、法律の基準を下回らず、労働者に不利益とならないように制度を設計・運用することです。
また、年5日の取得義務は中途採用者にも適用されるため、個別の付与日に合わせたきめ細やかな管理が求められます。
適切な労務管理は、法的なリスクを回避するだけでなく、従業員との信頼関係を築き、働きがいのある職場環境を実現するための基盤となります。本記事が、貴社の採用活動と労務管理の一助となれば幸いです。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。
関連記事
Sorry, no posts matched your criteria.