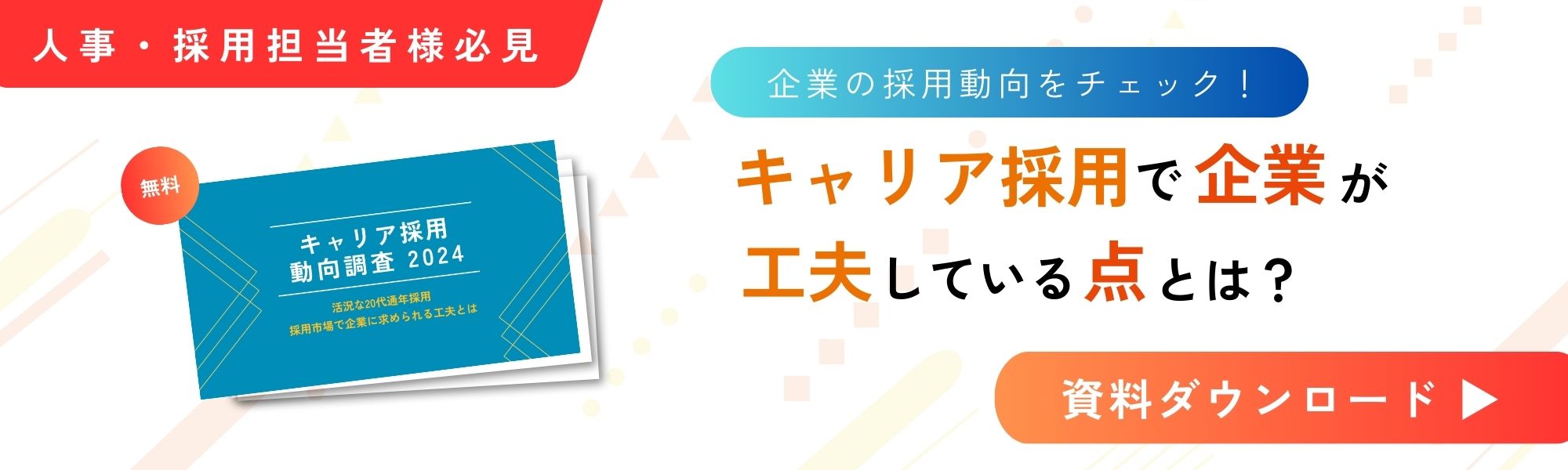ビッグファイブ理論とは?構成する5つの因子や分析するメリットを解説
公開日:2023.09.05
更新日:2025.02.10

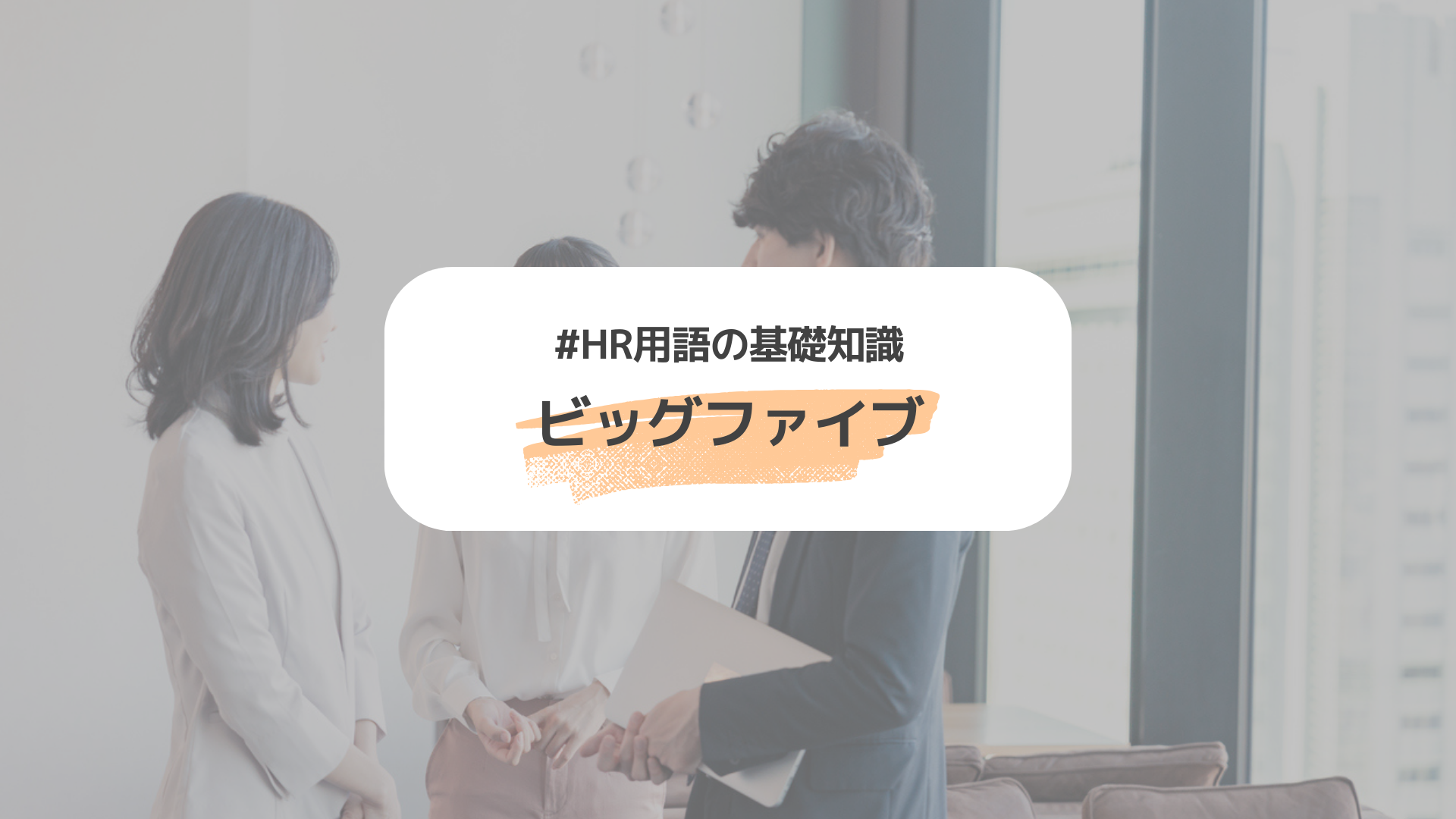
性格分析理論の一つ「ビッグファイブ理論」は、5つの因子を数値化することで一人ひとりの特性や傾向を分析できます。
本記事では、ビッグファイブを構成する因子や分析するメリットについて詳しく解説しています。
従業員のビッグファイブを把握して、人材配置やコミュニケーションに役立てたい方はぜひ参考にしてください。
ビッグファイブ理論とは

ビックファイブ理論とは、1990年代にルイス・R・ゴールドバーグという心理学者が提唱した、人間の性格を5つの基本的な因子で説明しようとする心理学の理論のことです。
人の性格は「外向性」「誠実性」「調和性」「開放性」「神経質的傾向」の5つの因子から成り立つとされています。ビッグファイブ理論は、これらの5つの因子が個人の性格を幅広くカバーしていると考えています。
5つの因子の高低や組み合わせが、個人の特徴や振る舞いの傾向を理解するのに役立つため、人材配置やコミュニケーションなどさまざまな場面で応用できるのです。
ビッグファイブを構成する5つの因子

「外向性」「誠実性」「調和性」「開放性」「神経質的傾向」の特徴や性格の傾向などを詳しく解説します。なお、因子の高低に良し悪しはなく、性格を客観的に捉えることに有効です。
外向性
社交性や積極性、外の世界への興味の強さ、活発さを指します。
外向性が高い人は、大人数での交流を好むのが特徴です。一方で低い人は、比較的一人の時間を好む傾向があります。
誠実性
責任感の強さや自身の思考や行動をコントロールする力を指します。
この因子が高い人は真面目で責任感が強いため、物事を達成させるのが得意です。一方で低い人は、計画性よりも直感的なため、迅速に行動できる傾向があります。
調和性
周囲への思いやりや配慮、共感する力を指します。
この因子が高い人は、対立や争いを避け、他者に協力的に貢献することを好みます。一方で低い人は、個人的な感情に流されにくいため冷静な判断が可能です。
開放性
文化的・知的・美的な新しい体験に対する開放度、想像力の豊かさを指します。
この因子が高い人は、想像力の豊かさから新しいアイディアを生み出すことが可能です。一方で低い人は手堅い選択を好むため、物事を慎重に進める傾向があります。
神経質的傾向
情緒面や感情面がどの程度安定しているのかや、ネガティブな刺激への耐性を指します。
この因子が高い人は、不安や緊張を感じやすいのが特徴です。ストレスの多い状況では精神的にも身体的にも影響を受けやすい傾向がありますが、感受性が高く繊細な気配りができるとも言えます。
一方で低い人は、情緒が安定しておりストレスを感じにくいため、どんな状況下でも冷静な対応が可能だとされています。
ビッグファイブの分析アプローチ

性格分析理論には、ビッグファイブが当てはまる「性格特性論」と、もう一つ「性格類型論」があります。
性格特性論
ビッグファイブ理論は特性5因子理論とも呼ばれ「性格特性論」に含まれます。「性格特性論」は、性格を構成する特性因子を数値化して、その度合いを分析する方法です。
特性の高さと低さを数値で表すため、それぞれの度合いを明確に判断することが可能です。
性格類型論
「性格類型論」は、性格に関する典型的なパターンをあらかじめ作り、カテゴリー分けします。対象者を最も近いカテゴリーに当てはめ、全体的な特性を把握する方法です。
「性格特性論」のように因子の数値を詳細に把握することはできませんが、全体的な特性を手軽に理解できます。
従業員のビッグファイブを分析するメリット

従業員の特徴や傾向を把握することで「コミュニケーションの円滑化」や「適材適所の人事配置」に役立てられます。
コミュニケーションの円滑化
ビッグファイブ理論の結果を共有することで、個人の特性や行動の傾向などが数値で把握できるため、従業員の相互理解が深まります。
特性を把握することで個人が持つ課題を可視化でき、必要なときに助け合う行動をとりやすくなります。結果的に、チーム間や従業員同士のコミュニケーションの円滑化にもつながるでしょう。
適材適所の人材配置
ビッグファイブ分析による従業員の特性把握は、組織内の人材配置やチーム編成の意思決定において重要な情報となります。
ビッグファイブ分析によって、従業員の外向性や協調性、誠実性などのポジティブな特性を明らかにできます。これにより、チームやプロジェクトに適したリーダーシップの発揮や協力関係の構築など、ポジティブな特性を活かした人材配置が可能となります。
また、従業員の弱点や課題も浮き彫りになるため、特定の従業員の弱点を他のメンバーの強みで補完し合うような人事配置も行うことができるでしょう。
ビッグファイブ理論を活用した人材配置の例

ビッグファイブ分析をすると、個人それぞれが持つ特性や行動傾向に合わせた人材配置が可能です。例をあげると次のようになります。
【外向性が高い】
積極性や社交性が高いため、コミュニケーション能力が求められる営業職や管理職、企画職などへの配置がおすすめです。
【誠実性が高い】
計画性があり真面目で責任感が強いため、中間管理職や経理・財務職などへの配置が向いています。
【調和性が高い】
周囲への配慮や他者への共感力が高いため、営業職や管理職のほか、チームワークが重視される職種へ配置することで、個人の特性を活かせます。
【開放性が高い】
新しいアイディアを出す想像力が豊かなため、企画職や開発職などへの配置がおすすめです。
【神経質的傾向が高い】
繊細な気配りに優れているものの、環境の変化や失敗には敏感なため、安定した環境で取り組める職種への配置をするとよいでしょう。
ビッグファイブ分析を活用して組織体制を見直そう

ビッグファイブ分析では、「外向性」「誠実性」「調和性」「開放性」「神経質的傾向」の5つの因子からわかる特性や傾向を知ることができます。企業においては、社内の相互理解を深めるきっかけになります。
ビッグファイブ分析に基づいた人材配置は、従業員の特性と業務のマッチングを最適化し、パフォーマンスの向上につながります。このように、個々の強みと弱点のバランスを考慮した組織体制の見直しは、企業の成長に寄与することが期待できるでしょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。