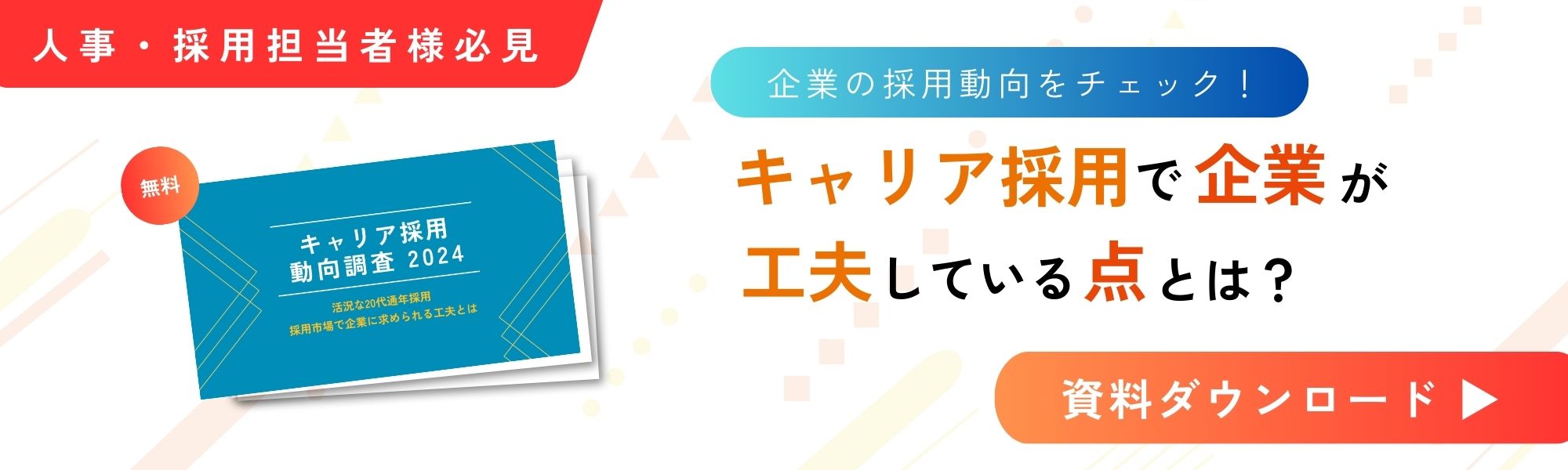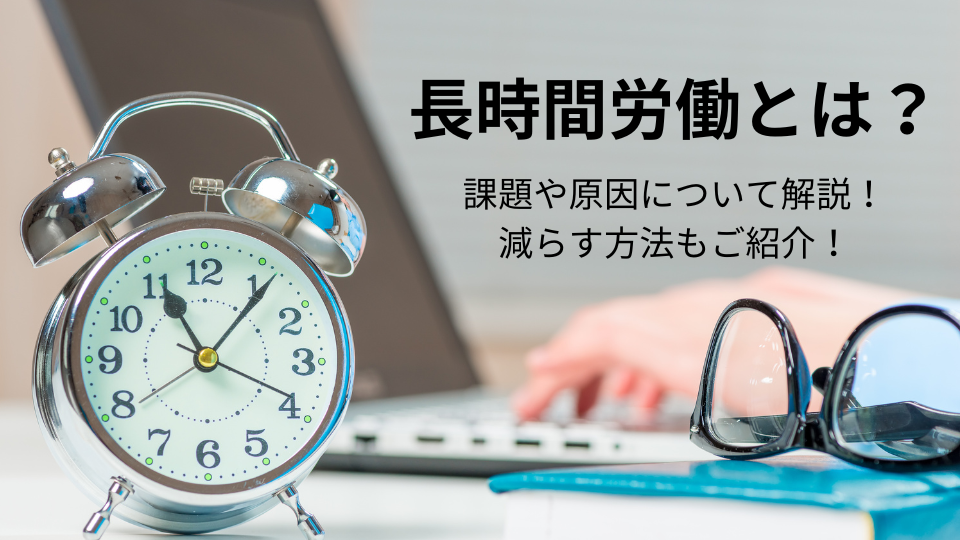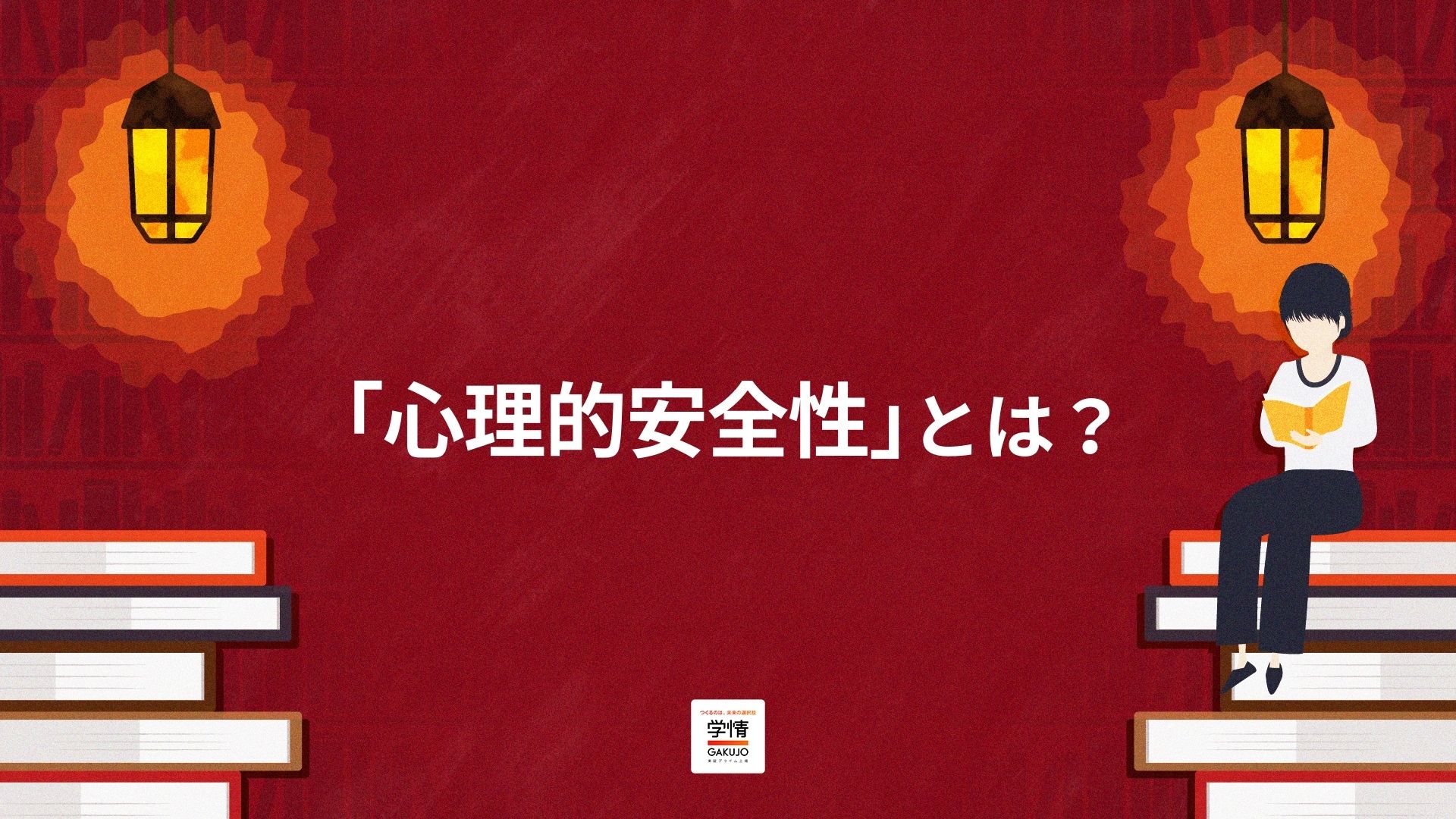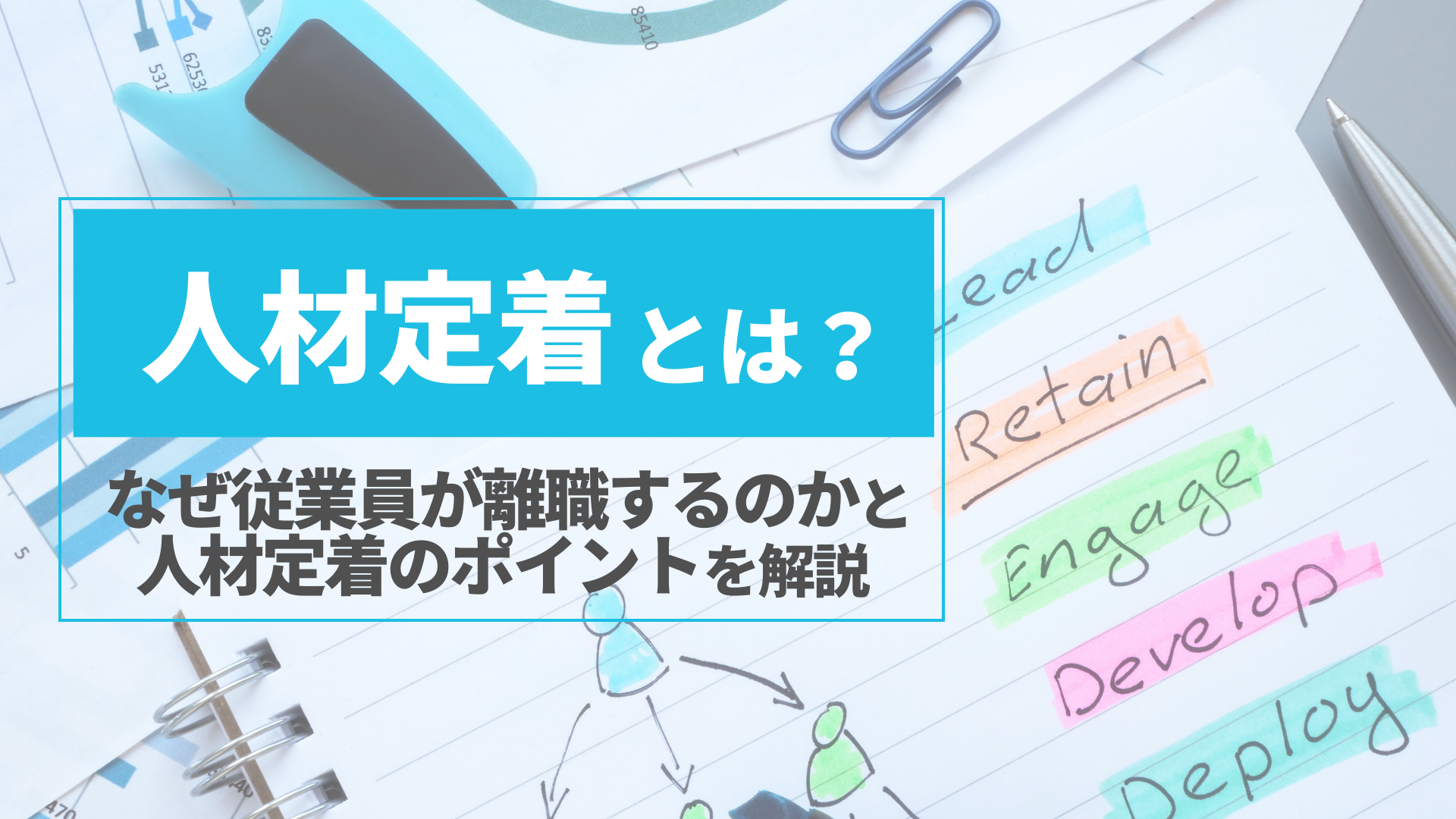ワーキングプアの現状とは?種類や問題点から企業ができる対策まで解説
公開日:2023.07.13
更新日:2025.02.11

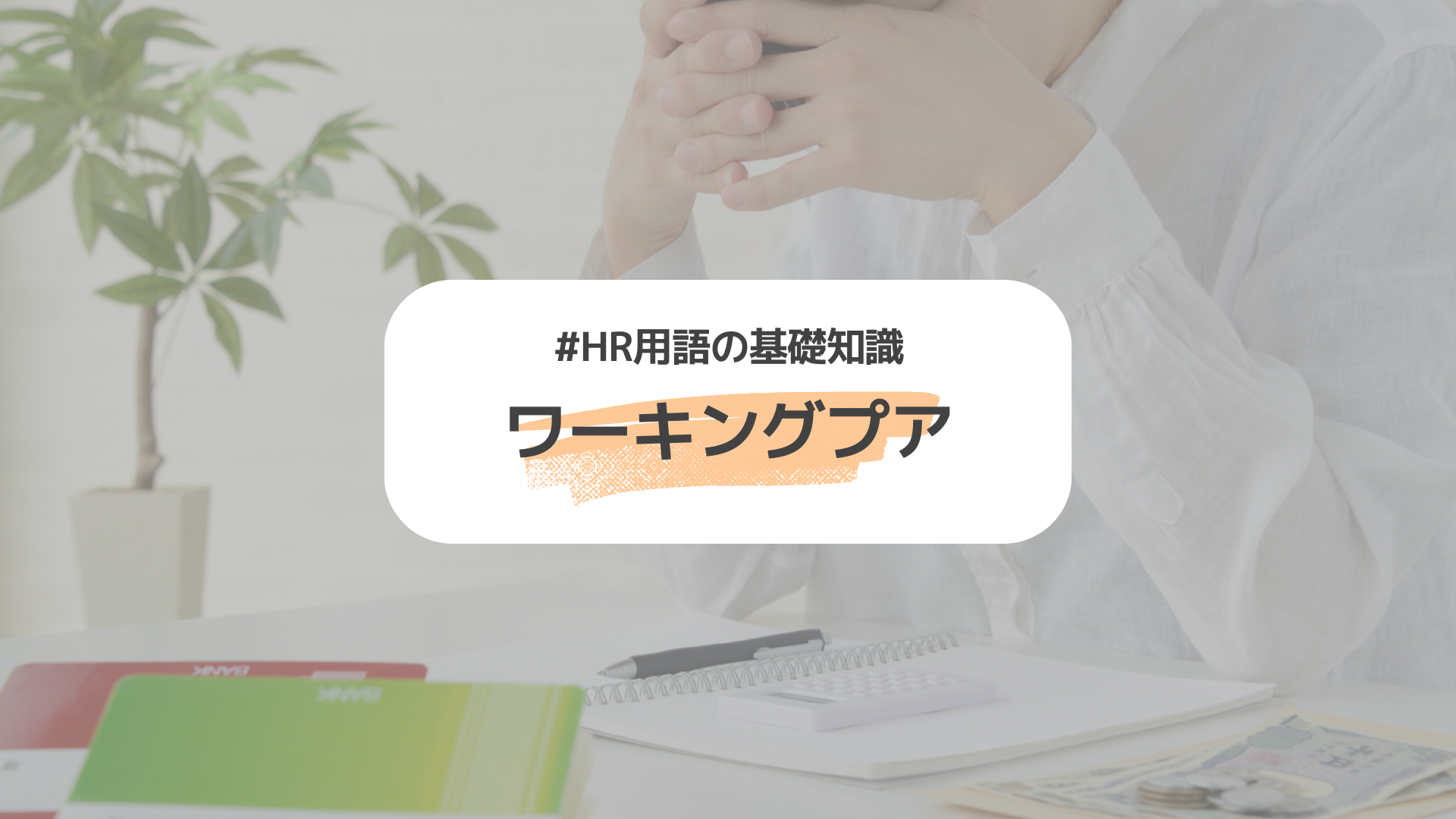
ワーキングプアとは、言わば「働く貧困者」です。就労していても充分な収入を得られず、貧困状態にある労働者のことを指します。ワーキングプアは社会全体の問題でもあり、企業においてもこの問題解決のため、「同一労働同一賃金」や「ワークシェアリング」などの取り組みが求められています。
本記事では、ワーキングプアの詳しい意味や種類、ワーキングプアが生まれた原因と解決策を詳しく解説します。自社でできる取り組みを検討できるよう、国が行っている施策例や企業ができる対策も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ワーキングプアとは

「ワーキングプア」とは就労していても充分な収入を得られず、貧困状態にある労働者を指します。日本では明確な定義がありませんが、生活保護の水準である「年収200万円未満」・「月収17万円以下」が一つの基準となっています。
現在日本では、正社員としてフルタイムで働いていても、所得水準が生活保護の水準程度、もしくはそれよりも低い場合があります。そのため、「貧困状態から抜け出せない労働者=ワーキングプア」がいるのが実情です。
貧困状態の労働者には、アルバイトやフリーター、契約社員や派遣社員など非正規雇用の就労者も含まれます。
ワーキングプアの現状

国税庁が取りまとめた「令和2年分の民間給与実態統計調査」のデータによると、日本の平均年収は430万円であり、年収200万円以下の人は全体の約2割という結果になりました。
男女別に見ると、年収200万円以下の男性は10.6%、女性は38.6%です。男女合わせると全体の22.2%となり、日本人の4~5人に一人は年収200万円以下のワーキングプアに該当することになります。
※出典:「令和2年分 民間給与実態統計調査」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2020/pdf/002.pdf
日本でワーキングプアが注目され始めたのは、高度経済成長期の1965年です。東京都の中野区が実施した課税台帳の電算集計で「住民の1/4が生活保護水準以下で生活している」と発覚したことがきっかけとなりました。
その後、バブル経済が崩壊して非正規雇用の労働者が増加したことで、問題が顕在化したとされています。
ワーキングプアの種類

ワーキングプアには大きく「高学歴ワーキングプア」、「中高年ワーキングプア」、「官製ワーキングプア」の3種類に分けられます。特徴や各ワーキングプアに陥る原因を詳しく解説します。
大卒・院卒の高学歴ワーキングプア
高学歴ワーキングプアは、大卒や院卒で、一流企業に就職したものの一度退職してしまい、再就職が上手く行かない場合に見られます。また、院卒時の就職活動がうまく行かなかったようなケースも該当します。
後者の場合は2つのケースが考えられます。一つは特に目標を持たずに「とりあえず大学院に進学した」という場合です。専攻に関する十分なスキルを身につけたり結果を残すことができなかった場合、「院卒」という高学歴の肩書きは一般採用や総合職の採用では敬遠されてしまうこともあります。
また、目的を持って大学院に進み、研究で成果を出した優秀な学生であったとしても、大学教員や研究職のポストが少ないために、終身雇用のポストを見つけられないケースもあります。教授や研究職は入れ替わりの少ない職種であるため間口が狭く、高学歴であっても安定したポストが見つからずにワーキングプアが発生しているのが現状です。
正規雇用に就けない中高年ワーキングプア
中高年のワーキングプアとは、不本意な状態で非正規として働き続けている「不本意非正規雇用労働者」のことです。中高年の正規雇用化が進まない理由は、中高年のスキルアップの機会が少ないためであると考えられます。
現在の日本における能力開発支援策は、対象者が若年層や失業者となっているものが多く、中高年層向けのものは少ないのが現状です。加えて、能力開発支援を利用するには休日の取得や労働時間の調整など、雇用主の理解と協力が必要です。そのため、非正規雇用で働いている中高年の労働者にとっては利用しづらいものとなっています。
中高年は、新卒採用の新人に比べて教育に時間とコストがかかりやすく、即戦力でなければ採用を敬遠される傾向にあります。スキルアップの機会が得られなかった中高年層は「充分なスキルを持った即戦力」とは判断されず、正規雇用化されないケースもあるのが実情です。
日本の就職事情では、一度退職して非正規雇用になってしまうと、キャリアの再形成が難しいのが現状です。特に出産・育児や介護などで退職してしまうと、ブランクが発生し正規雇用での再就職が難しくなるケースがあります。
非正規雇用に甘んじるしかない状況で年齢を重ねてしまうと、さらに年齢が壁となって正規雇用に採用されにくくなり、中高年ワーキングプアとなってしまうのです。
自治体が生み出す官製ワーキングプア
官製ワーキングプアは、国や地方自治体などの公的機関で働くワーキングプアです。非正規公務員と民間委託先の被雇用者に分けられます。本来、行政はワーキングプアを解消すべき立場ですが、自治体の人件費削減のため、嘱託や臨時職員、派遣社員といった非正規雇用の労働者が増えているのが現状です。
臨時職員は、民間の非正規雇用の労働者と同様に、低賃金の非正規雇用で不安定な働き方をしています。人件費削減による正規雇用との収入格差に加え、行政の臨時職員には労働契約法やパート契約法が適用されないことも原因の一つです。また、臨時職員は有期雇用で雇い止めにあうケースもあるのが現状です。
さらに、自治体のさまざまな業務を外部の民間企業へ委託するケースも増えていますが、受託者である民間企業は非正規労働者を雇用することがほとんどです。行政の民間企業への委託は数年契約といった契約期間の定めがあり、契約期間満了時には新たな入札がおこなわれて委託先が決まる仕組みがあるためです。
この仕組みは民間の特定企業が利権化しないための措置ではありますが、委託される民間企業側としては契約の継続性がないため、非正規労働者を雇用することになってしまうのです。
ワーキングプアの3つの問題点

ワーキングプアには、懸念されている問題点があります。
- 少子高齢化が加速する
- 抜け出すのが困難
- 心身崩壊の危険性がある
それぞれの問題を詳しく見ていきましょう。
少子高齢化が加速する
ワーキングプアによって少子高齢化が加速する恐れがあります。収入が低いために結婚や家庭を持てないケースや、たとえ結婚して家庭を持ったとしても子どもを育てるほどの余裕がないため、子どもを産めないといったケースもあります。
その結果、現在日本で深刻な社会問題となっている少子高齢化が、さらに加速してしまう可能性が問題視されています。
抜け出すのが困難
一度ワーキングプアになってしまうと貧困層から抜け出すのが困難で、子ども世代へも連鎖する可能性がある点も大きな問題です。
ワーキングプアの状態では経済的に常に余裕がありません。そのため、子どもの教育にもお金をかけられず、子どもが充分な教育を受けられなくなる恐れがあります。
低学歴で就職すると、就職しても収入が上がりにくかったり正規雇用で就職できなかったりする可能性が高まるため、子どももワーキングプアになるという負の連鎖が懸念されます。
心身に不調をきたす危険性がある
ワーキングプアになりやすい職業

非正規雇用が多い職業や専門的な知識・技術が必要とされにくいために給与が低い職業はワーキングプアのリスクが高いと言われています。たとえば次のような職業です。
- 飲食業
- 販売業
- 清掃従事者
- 警備員
- 保育士
- 農業関連
- 漁業関連
- 電話オペレーター
- 書類整理・データ入力などの単純事務作業員
専門知識が必要な職業でも、元々賃金設定が低い職種はワーキングプアになりやすいと言えるでしょう。
ワーキングプアに対する国の政策

ワーキングプアが抱える問題に対して国が行っているおもな政策は次のとおりです。
- 子育て世代への経済や教育の支援
- ハローワークによる就労支援
- 最低賃金の引き上げ
それぞれの政策を詳しく解説します。
子育て世代への経済や教育の支援
| 制度 | 概要 |
| 幼児教育の無償化 | 幼稚園や保育所、認定こども園などを利用する3~5歳児および住民税非課税世帯の0~2歳児までの子どもたちの利用料無料 |
| 義務教育の就学援助 | 経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する、市町村からの学用品や通学費などの支給支援 |
| 私立高校等の授業料減免 | 経済的理由から授業料の納付が難しくなった生徒に対する授業料軽減措置 |
| 高等学校等就学支援金 | 一定の収入額未満の世帯の生徒に対し、授業料に充てるための高等学校等就学支援金を給付 |
| 高校生等奨学給付金 | 所得が低い、または家計の急変などで経済的に困窮した場合、教育費の負担を軽減するために高校生等がいる低所得の家庭を支援 |
ハローワークによる就労支援
ハローワークでは、職種や年齢に関係なく利用できる就労支援を行っています。専用の相談窓口や、応募書類の書き方のアドバイス、面接指導や職業訓練などがおこなわれています。
非正規雇用で働いてきたワーキングプアの人たちは、社会人としてのビジネススキル
や専門知識などを身に着ける機会がなかったというケースも多いです。そのため、就労支援では職業訓練や教育の場も拡充されてきています。
職業訓練の教育を受けることは、ビジネススキルや知識を身に着け、転職して収入を高めることにもつながります。
最低賃金の引き上げ
現在では、最低賃金がどの地域でも上昇しています。この背景には、2022年8月に中央最低賃金審議会が最低賃金の目安を大幅に引き上げることを決定したことがあげられます。
最低賃金が引き上げられれば、低賃金で労働する人たちの待遇改善や格差是正、地域の活性化などにつながります。企業にとっては社会貢献となり、企業の担う社会的責任やSDGsの観点からメリットがあると考えられます。
しかし、最低賃金が引き上げられても物価の上昇に追いついておらず、実質の賃金は低下傾向なのが現状です。
企業ができるワーキングプア対策

ワーキングプアを自社で生み出さないためには、次のような対策が有効です。
- 業績を上げて給与を増やす
- 正社員での採用を増やす
- ワークシェアリングを導入する
それぞれの対策について、現在、社会の貧困層向けにおこなわれている施策をもとに解説します。
業績を上げて給与を増やす
第一に社員の給与を増やすことが、ワーキングプアの解消につながります。
給与を上げるには、会社の業績アップが必要です。業績を上げるには働き方改革や従業員の定着率向上など、さまざまな企業努力が欠かせません。
業績が上がれば給与を上げることができ、給与が上がれば従業員のモチベーションや企業への貢献意欲も高まります。モチベーションや貢献意欲が高まれば、業務効率や生産性が向上し、業績アップにつながりやすくなるでしょう。業績が上がれば従業員へ還元することもできるため、好循環が生まれます。
正社員での採用を増やす
企業ができる対策としては、正規雇用の社員を増やすことも有効です。正規雇用の社員になる人は、非正規雇用の社員よりも昇給やスキルアップが望めるでしょう。雇用が安定し昇給できる可能性が出てくれば、従業員のモチベーションも上がり生産性やエンゲージメントも高まります。
また、厚生労働省では、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保である「同一労働同一賃金」に取り組む事業主に向けて、非正規雇用の社員を正規雇用にするための「キャリアアップ助成金」の支援を行っています。そのほかにも「働き方改革推進支援センター」では働き方改革に関する事業主向けセミナーを実施したり、労務管理の専門家による無料相談をおこなったりしています。
このような支援や補助金を利用して正規雇用の社員採用を増やすことも、ワーキングプアを解決する糸口となるでしょう。
ワークシェアリングを導入する
ワークシェアリングとは、一つの業務を複数人で分かち合うことです。従業員同士で業務を分け合うことによって一人ひとりの労働時間を短縮し、従業員の雇用機会を確保・創出できます。
人員削減の回避や新たな労働者の雇用ができることから、ワーキングプア解消のために有効と言えます。また、ワークシェアリングでは雇用を守りながら労働時間を短縮するため、空いた時間に副業をする余裕が生まれ、収入を増やしやすくなります。
ワーキングプアを解決する取り組みを導入しよう

ワーキングプアは、個人の問題ではなく社会全体の問題となっています。このまま問題がさらに深刻化すれば、少子高齢化による労働人口の減少や国全体の税収入の減少などで国民全体の生活にさまざまな影響が出てくる可能性があります。
そのような事態を避けるためにも、企業ができる施策に取り組み、社会全体で問題の解決にあたることが急務となっています。
ワーキングプアを解消するための取り組みの代表例は、給与を上げることや正社員雇用を増やすこと、ワーキングシェアを導入することなどです。社会問題であるワーキングプアを解消しながら、自社も発展していくための施策を検討してみましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。