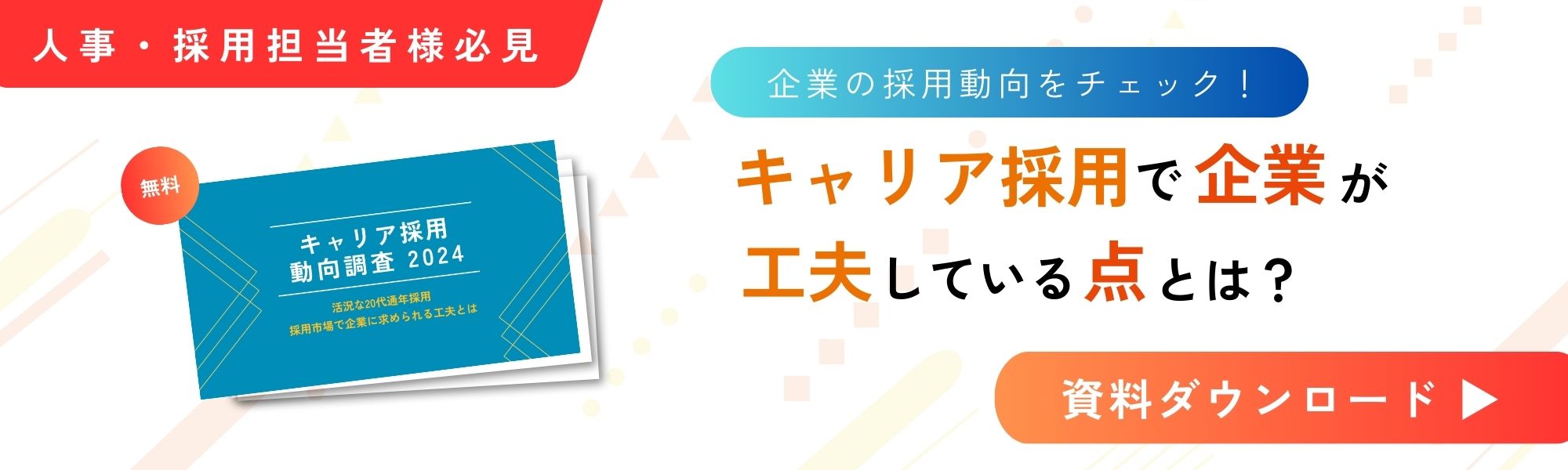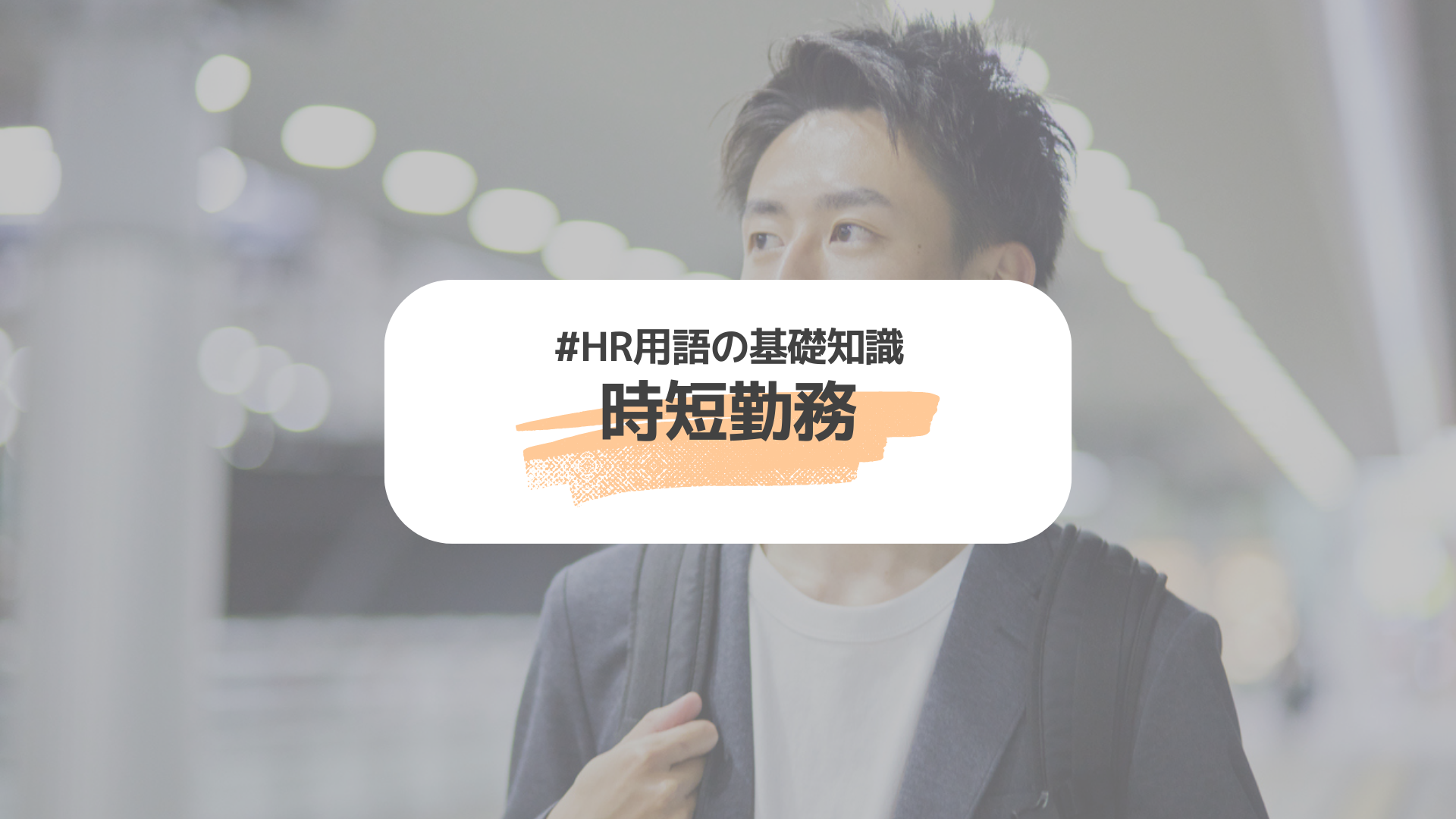
時短勤務とは短時間勤務制度のことで、育児介護休業法によってすべての企業に導入が義務付けられています。
本記事では、時短勤務について制度の内容や背景、適用条件などを詳しく解説します。また、時短勤務制度を導入するときの手順や注意点も紹介するので、これから時短勤務制度を導入する場合の参考にしてください。
時短勤務(短時間勤務制度)とは?

時短勤務とは、1日の労働時間を通常より短くして働くことです。たとえば、8時間と所定労働時間が定められている会社で、6時間や7時間勤務を行う場合、時短勤務となります。
このような所定労働時間の短縮のほか、出勤・退勤時間の変更、フレックスタイム制なども時短勤務に該当します。
なお、育児介護休業法によって、2012年7月よりすべての事業主に短時間勤務制度の導入が定められました。したがって時短勤務は企業が任意で導入を決めるのではなく、原則導入が義務付けられている制度であり、法律によって守られている労働者の権利です。
短時間勤務制度が設けられた背景

少子高齢化問題が深刻化している現在、働く人に対して家庭と仕事を両立できる環境を整えることが重要視されています。従来、仕事と家庭を両立できる環境が社会全体として整っておらず、出産や育児、介護などで就業を諦めなければならない状況に置かれていました。
しかし、深刻化する少子高齢化問題を解決するために、社会全体として仕事と家庭を両立させられる環境を整えなくてはなりません。
そこで政府は1991年に「労働者の仕事と育児や介護などの両立」を目的として育児・介護休業法を施行しました。
1991年の施行当初は、「子が1歳未満の労働者に対し、時短勤務、フレックス、始業就業時刻の変更などからいずれか一つを事業主が選択して措置する」という制度でしたが、その後2002年には対象者を「3歳未満の子を養育する労働者」とする制度に改正しています。
さらに2012年には、3歳未満の子を養育する労働者に対し、1日の労働時間を原則6時間とする短時間勤務制度を設けることが、すべての事業主に義務付けられました。そのため、従業員が希望を申し出れば、原則としてすべての企業で短時間勤務制度が適用されます。
※参考:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html)
時短勤務(短時間勤務制度)の内容

育児による時短勤務の場合
育児による時短勤務を利用する場合、適用期間と対象者、対象外となる労働者は次のとおりです。
| 適用期間 | 法令上は子どもが3歳になるまで |
| 対象者 | 3歳に満たない子どもを養育する労働者 |
| 対象外 |
|
ただし、企業によっては条件や期間に対する取り決めを緩和して、短時間勤務を認めているケースもあります。
※参考:厚生労働省「改正法の下での短時間勤務制度について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ikuji_kaigo_shiryou/dl/ikuji_kaigo_01_006.pdf
介護による時短勤務の場合
介護を理由とした時短勤務制度を利用する場合、適用期間と対象者、対象外となる労働者は次のとおりです。
| 適用期間 | 対象家族一人につき利用開始の日から3年間で2回 |
| 対象者 | 要介護状態にある対象家族を介護する労働者 |
| 対象外 |
|
介護による時短勤務の適用期間は、介護対象となる家族一人につき利用開始の日から3年間で2回までが最低基準です。これは最低基準であるため、企業によっては適用期間を延ばしたり、任意で回数を増やしたりすることもできます。
※参考:厚生労働省「短時間勤務等の措置について|介護休業制度」
時短勤務(短時間勤務制度)の導入手順

時短勤務制度を導入する際は、導入の目的を明確にし、給与や昇進などの条件を決めて適用後のトラブルが起こらないように進めていくことが大切です。ここでは時短勤務を導入する際の手順を詳しく解説していきます。
1.導入の目的を明確にする
まずは時短勤務制度を導入する目的を洗い出し、言語化しましょう。
従業員のニーズや自社の人員構成、人材活用のための戦略などを踏まえた上で、時短勤務を導入する目的を明確にしましょう。たとえば「出産・育児で優秀な人材が退職することを防ぐ」「従業員の要望や、働き方への不満改善」などがあげられます。
社内の事情に応じた具体的な目的をあげることで、その目的に沿った制度を設計できるでしょう。
2.時短勤務の社員の仕事内容・量を確認
次に、時短勤務制度適用後のトラブルを避けるため、時短勤務になる従業員の仕事内容や仕事量を把握しておく必要があります。
時短勤務になると、これまでと同じ量の仕事がこなせなくなる可能性があるだけでなく、周りのフルタイム従業員の負担が増えてしまうケースもあります。
周りの従業員の負担が増えると不満にもつながりやすいため、事前に時短勤務対象者の仕事内容や量を把握し、周りの従業員と一緒にどの程度の仕事を担当するように決めるか、話し合っておくと良いでしょう。
3.給与や昇進・昇格などの就業条件を決める
時短勤務になる従業員の仕事内容を把握し、所属部署や周りの従業員との担当業務の擦り合わせを行ったら、成果目標を設定して評価基準を設けましょう。
基本的に、仕事量の目標は労働時間に合わせて減らしますが、仕事の質としての目標は変えないのが原則です。業務内容や時短勤務対象者の希望も踏まえたうえで目標を決めると良いでしょう。
なお、目標に対する評価は達成状況に応じて行います。能力や行動に関する評価は、時短勤務対象者もフルタイムの従業員と同じ評価基準や要素を用いて評価しましょう。昇進や昇格も、人事評価基準に基づいて公正に決定することが重要です。
また、労働時間や賃金などの就業規則も見直します。基本給は労働時間に比例して減額し、支給額を検討しましょう。所定労働時間が8時間から6時間に短縮されると、通常の労働時間の75%になります。そのため、基本給も通常の75%にあたる金額に設定します。
基本給の計算式
時短勤務対象者の基本給を算出する際の計算式は、次のとおりです。
- 時短勤務時の基本給=通常時の基本給×時短勤務時の所定労働時間÷通常の所定労働時間
たとえば、通常の基本給が25万円で所定労働時間が8時間から6時間へ短縮された場合、「25万円×6時間÷8時間=18万7,500円」という計算になります。そのため、時短勤務対象者の1カ月の基本給は18万7,500円です。
この基本給に対して、社会保険料の天引きや各種手当の加算などを行い、実際に支払う給与金額を決定します。
残業代の計算方法
時短勤務の従業員が所定外労働をした場合や、休日・深夜労働をした場合の給与計算式は次のとおりです。所定外労働とは企業が定める労働時間を超えた労働のことで、一般的な「残業」に当たります。
【所定外労働の場合】
- 残業代=基礎時給×残業をした労働時間数
【時間外労働・休日労働・深夜労働の場合】
- 支払われる額=基礎時給×対象となる労働時間数×割増率
この場合の基礎時給は、「月給÷月の平均所定労働時間数」で算出します。なお、割増率は労働基準法で定められた割合で計算します。
時間外労働、休日・深夜労働とされる条件と、労働基準法に基づいた割増率は次のとおりです。
| 種類 | 条件 | 割増率 |
|
時間外 (時間外手当・残業手当) |
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた場合 | 25%以上 |
| 時間外労働が限度時間(1カ月45時間、1年360時間等)を超えたとき | 25%以上※1 | |
| 時間外労働が1カ月60時間を超えたとき※2 | 50%以上※2 | |
| 休日(休日手当) | 法定休日(週1日)に勤務したとき | 35%以上 |
| 深夜(深夜手当) | 22時~5時までに勤務したとき | 25%以上 |
※1:25%を超える率となるように努める
※2:中小企業については2023年4月1日から適用
※出典元:東京労働局「しっかりマスター 割増賃金編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
4.フルタイム正社員への復帰についても検討
時短勤務制度の利用期間満了後に、フルタイム正社員へ復帰する際の転換制度も検討しておく必要があります。復帰した社員に対する不利益な取り扱いがないように、配置には十分配慮しましょう。
育児介護休業法では、時短勤務の申請などをした従業員に対して不利益な取り扱いをすることを禁止しています。不利益な取り扱いには、労働契約内容や昇進・昇格に関して不利な状態に置くこと、必要以上の減給や解雇、降格などが該当します。
また、利用期間が満了して時短勤務制度の適用がなくなっても、従業員がフレックスタイム制度や時差出勤制度の利用へ移行できるように準備しておくことも必要です。
5.時短勤務の制度を社員へ周知する
これまでに決めた内容を就業規則に規定し、社内で周知しましょう。就業規則に明文化することで、不要なトラブルを防ぐことにもつながります。
周知の際には、社内報や社内ポータルサイトにおける人事部からのメッセージなどで発信すると良いでしょう。
社内研修や新人研修の際に、時短勤務制度が存在することや内容に触れておくのも効果的です。
時短勤務(短時間勤務制度)の対象外となる社員への措置

時短勤務の対象外となる社員への措置として、フレックスタイム制度、時差出勤制度などがあります。
それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
フレックスタイム制度
フレックスタイム制度とは、あらかじめ定められた労働時間の範囲内で、出勤・退勤時間や労働時間を従業員自らが自由に決められる制度です。
フレックスタイム制度では、多くの企業が「コアタイム」と呼ばれる「必ず勤務していなければならない時間」を設定しています。
コアタイムに勤務していれば、それ以外の時間帯には自由に出勤・退勤できるため、育児や介護の都合に合わせて時間調整をしながら働くことが可能です。
時差出勤制度
時差出勤制度とは、勤務時間は変えずに勤務する時間帯を前後にスライドさせる制度のことです。出勤時間を変更するだけであり、従業員の勤務時間には影響がありません。
たとえば、時差出勤制度で「出社時刻は8時~10時の間」とする場合、従業員の出勤・退勤時刻は次のようになります。
【所定労働時間が8時間(休憩1時間含む)場合の時差出勤】
- 8時に出社した場合:16時に退社
- 10時に出社した場合:18時に退社
時差出勤は、育児や介護の都合に合わせて出社や退社時刻を調整できるだけでなく、通勤ラッシュの緩和やラッシュ時の従業員のストレス緩和にも役立ちます。
保育施設の設置
時短勤務制度適用の対象外となる従業員に対しては、企業や事業所内に託児所や保育施設を設置し、従業員の負担を減らすことも時短勤務の代替措置となります。
そのほかにもベビーシッターを雇う費用の負担や、一時的に時短勤務が可能な部署への異動をさせることなども、必要に応じて検討すると良いでしょう。
ただし、一時的な異動で時短勤務終了後は元の部署に戻すといった場合、本人や異動元・異動先の部署で合意を得ておく必要があります。事前に合意を得ておけば、後々のトラブル発生を防げます。
時短勤務(短時間勤務制度)に関するQ&A

子どもが何歳になるまで適用可能?
法令上で定められた期間は、子どもが3歳になるまでの間です。ただし、延長期間は企業ごとに設定できます。
育児・介護休業法では、3歳未満の子どもを育てている従業員がいる場合、時短勤務制度を設けなければならないと定められていますが、3歳以上の子どもを育てている従業員に対する措置は企業努力となります。
時短勤務の雇用形態は正社員のまま?
時短勤務の従業員も雇用形態は「正社員」です。正社員とは、雇用期間を定めずに労働契約を結んだ労働者のことを指します。
なお、育児・介護休業法で規定されている時短勤務制度は「短時間正社員制度」の一部です。育児や介護以外の理由でも、次の条件に該当すれば短時間正社員制度が適用されます。
- 雇用形態:正社員
- 労働契約:期間の定めのない労働契約
- 賃金などの待遇:フルタイム正社員と同一の時間賃率・賞与・退職金などの算定方法を適用
- 社会保険:適用
時短勤務の社員の休憩時間は?
所定労働時間が6時間未満の場合、休憩時間を与えることは定められていません。そのため、勤務時間が6時間未満の場合は休憩時間がなくても問題ありませんが、6時間を超える場合、8時間以下までは少なくとも45分の休憩時間が必要です。
なお、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えることが労働基準法で定められています。
※参考:厚生労働省「労働時間・休憩・休日関係」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken02/jikan.html
時短勤務の社員の有給は?
就業条件が所定労働時間が週30時間以上・週5日以上であれば、基本日数の有給休暇を付与する必要があります。
有給日数は、所定労働時間ではなく労働日数によって決まります。週5日出勤している時短勤務者の場合、有給休暇の日数はフルタイム正社員と同じです。
なお、所定労働時間が週30時間未満で、労働日数が週4日以下の場合の有休付与日数は次のとおりです。
| 週所定 | 1年間の所定 | 勤務年数 | ||||||
| 労働日数 | 労働日数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年 |
| 週4日 | 169日から216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 121日から168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 73日から120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 48日から72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
※出典元:東京労働局「しっかりマスター 有給休暇編」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf
時短勤務の社員の社会保険料は?
時短勤務制度を利用する前から社会保険に加入していた社員の場合、引き続き適用対象となります。
時短勤務制度を利用している従業員が新たに社会保険加入の申請を行った場合は、次の条件を満たすと適用が認められます。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
なお、時短勤務への変更時の社会保険料は、申請により減額できます。
時短勤務の導入で働きやすい環境を整えよう

少子高齢化が社会問題となっている現在、子育てと仕事を両立できる環境を整えることは社会全体として重要視されています。
また、介護や家庭の事情によって今まで通りに仕事を続けることが難しくなった従業員が退職してしまったり、勤務条件の良いほかの企業へ流出してしまったりすることを防ぐためにも、時短勤務制度の導入は有効です。
働きやすい環境が整えば、企業に対する従業員の満足度やエンゲージメント向上も期待できます。時短勤務を導入する際には社内事情に応じた目的を明確にして、就業条件や規定を明文化し、制度導入の賛同を得られるように全体へ周知しましょう。導入後のトラブルを防ぐためにも、説明や事前の擦り合わせも大切です。
時短勤務制度を導入して、従業員が働きやすい環境を整えましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。