中途採用の流れとは?採用フローやポイント、改善策を徹底解説!
公開日:2023.06.14
更新日:2025.11.30


企業が採用を成功させるには、しっかりと計画を立てた採用フローが重要です。すでに採用フローを作成している企業でも、日々変化する求職者のニーズと自社のニーズをすり合わせて見直しを検討しましょう。
本記事では、採用フローとは何か、また採用フローを取り入れるメリットについて説明します。採用フローへの理解を深めたい方は必見です。
採用フローとは
採用フローとは、「求人掲載→書類選考→面接→内定→内定承諾」のように、企業が求人を出してから人材の採用に至るまでの一連の流れを指します。
これら一連の流れとなる採用フローを可視化することで、採用の進捗状況が一目で分かり、効率良く採用活動が進められます。
なお、採用フローを構成する要素は、新卒採用や中途採用、職種などによって変化します。
なぜ採用フローの作成が必要なのか

近年、労働者人口が減少していることや、ワーク・ライフ・バランスを重視する考え方が広まっていることから、各企業はさまざまな採用方法を導入しています。
しかし、採用方法が多様化したことで、人事担当者の業務が増えて大きな負担となっているのも事実です。
採用フローを作成し、可視化すれば、それぞれのプロセスにおける無駄を省くことができ、その結果、人事担当者の負担も軽減されるでしょう。
また採用ターゲットや業種、職種にあった採用フローを作成することで、自社が求める人材を効率良く採用できます。
「思うように優秀な人材が集まらない」「人事担当者の負担を軽減したい」と悩んでいる企業は、採用フローの作成・見直しの必要があるといえます。
採用フローを作成するメリット

採用フローを作成する具体的なメリットを解説します。
進捗状況を可視化できる
採用には、採用担当者だけでなく、役員などのさまざまな社員が関わります。スムーズに採用活動を進めるには、すべての関係者に情報を共有しておくことが重要です。
採用フローがあることで情報の共有漏れを防げます。
また、進捗状況を可視化できるため、すべての関係者が詳細を確認できます。
採用情報を共有することで認識を合わせられるため、情報の共有不足によるミスやトラブルの発生を防ぐことにつながります。
採用活動の見直しに役立つ
採用は、必ずしもスムーズに進むとは限りません。採用フローを用意することで、問題発生のタイミングや原因をその都度可視化できるので、それまでの振り返りがしやすくなります。
各プロセスで人数を計算し、次に進んだ人の割合を記載しておくことで、問題が起きた部分が明確になります。
蓄積したデータを分析し、採用フローの見直しを繰り返すことで、採用活動全体の質を向上させることが可能です。
採用フローを構成する3つの要素
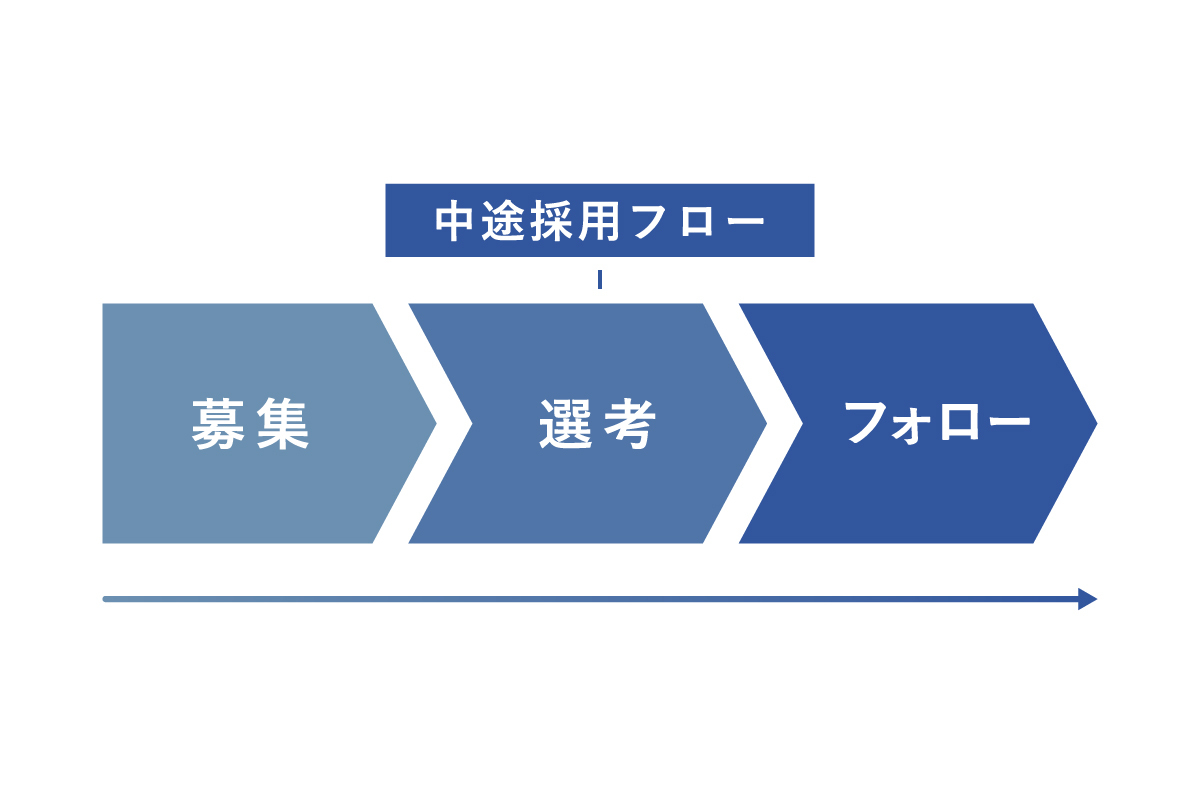
採用フローを作成する際に重要なのは、募集・選考・フォローという3つの要素です。
募集の段階
求人を募集する段階は、母集団の形成を図るときです。
母集団の形成とは、応募者を募るための広報活動を指します。具体的には、求人の掲載や会社説明会の実施などがあげられます。
自社への応募者をより多く集めるには、広く募集をかけることが必要です。
一方で、すべての応募者が自社の求める人材と合致するとは限らないため、ターゲットを絞ることも大切です。
母集団を形成する際には、企業の魅力が伝わる動画を活用するのも効果的です。
選考の段階
採用フローにおける選考は、書類選考や筆記試験、面接などで応募者を絞っていくフェーズです。選考には、おもに次のような方法があります。
| 書類選考 |
|
| 筆記試験 |
|
| 面接 |
|
企業によっては、グループワークやグループディスカッションを選考方法として採用するケースもあります。
ここでミスマッチが起きると内定辞退や早期離職を招くリスクがあるため、自社が求める人物像を明確にし、適した選考基準を定めるようにしましょう。
フォローの段階
フォローの段階は、応募者の内定から入社までを企業がフォローアップするときです。
優秀な人材に内定を出しても、必ず入社に至るとは限りません。ほかに魅力がある企業があれば内定辞退につながるおそれがあるため、フォローアップが必要です。
たとえば内定後に自社の従業員とコミュニケーションが取れる機会を作る、相談ができるように窓口を設ける、など内定者に寄り添うフォローを行いましょう。
中途採用の流れとポイント

中途採用を成功させるには、採用プロセスの最適化が重要です。プロセスが適切でないと、ミスマッチや早期退職につながるリスクが高まります。
中途採用の流れは次のとおりです。
- 採用計画を立てる
- 母集団形成
- 選考
- 入社
- 社員の定着を図る
それぞれのポイントについて詳しく解説します。
採用計画を立てる
採用計画の策定は、中途採用を成功させる第一歩です。
手当たり次第に募集をかけるのではなく、事前にしっかりと計画を練ることで、採用活動を効率的かつ効果的に進められます。
しかし、計画が不十分だと、採用のミスマッチやコスト増加といったリスクが高まるため、注意が必要です。
採用要件を設定する
採用要件を決める際は、採用ペルソナを作成し、求めるスキルや経験に加え、性格や志向性といったパーソナリティーに関する部分も詳細に設定することが重要です。
採用要件を詳細に設定することで、採用のミスマッチや入社後のギャップを防ぐことができます。
経営層や配属先の上司にヒアリングし、職務内容や必要なスキルを具体的に洗い出すことで、効果的な採用計画が立てやすくなるでしょう。
採用人数を決める
採用人数は、事業計画と組織の現状を総合的に考慮して決めます。
新規プロジェクトや欠員補充の必要性、現場の受け入れ能力、そして採用コストや人件費をバランス良く見極めることが大切です。
これにより、事業成長に貢献する最適な採用人数を設定できます。
採用予算を決める
中途採用では、求人広告の掲載費や人材紹介の手数料、選考にかかる人件費など、さまざまな採用コストが発生します。
中途採用を成功させるには、これらの費用を事前に見積もり、明確な予算を確保することが重要です。
綿密な予算計画を立てることで、無駄な出費を抑え、採用活動を効率的に進められます。
採用スケジュールを立てる
採用スケジュールを立てる際は、いつまでに採用を完了させたいかを明確にし、そこから逆算して各ステップの期間を設定します。
書類選考や面接の回数、技能審査の有無など、選考プロセスの各フェーズにかかる時間を具体的に見積もることが大切です。
また、面接官となる社員のスケジュール確保や、候補者への連絡期間もスケジュールに入れましょう。
選考プロセスを設計する
書類選考、筆記試験、面接など、どのステップをどの順番で進めるかを明確に定義します。
特に、面接回数や担当者の配置を検討する際には、候補者に過度な負担を与えずに企業側が十分な情報を得られるバランスを考慮する必要があります。
また、選考途中での歩留まり率を予測し、スケジュール調整に無理が出ないよう、各ステップの期間や担当割り当てを決めておくと効率的です。
母集団形成
採用手法を選定する
質の高い母集団形成を行うには、採用戦略に適した採用手法を選ぶことが重要です。
採用手法にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、それぞれの特徴をよく理解したうえで、自社の戦略にマッチするものを選びましょう。
それぞれの採用手法の特徴については、こちらの記事を参考にしてください。
ダイレクトリクルーティングを活用する
ダイレクトリクルーティングとは、企業が求職者に直接アプローチする採用手法です。
自社の採用要件に合う人材を能動的に探し、スカウトメールを使って企業の魅力や強みをアピールします。
従来の求人サイトでは接点を持ちにくかった転職潜在層にも、積極的に働きかけることができます。
ダイレクトリクルーティングの効果を高めるには、採用ターゲットに合った媒体を選ぶことが大切です。
たとえば、若手人材を求めているなら、登録者の93.3%が20代である「Re就活」のような特化型のサイトが効率的でしょう。
競合他社との差別化を図る
近年、売り手市場が続き、人材獲得競争が激化しています。優秀な人材を獲得するには、求職者が「この会社で働きたい」と感じるような、他社にはない付加価値を発信することが重要です。
競合他社との差別化を図ることで、質の高い母集団形成につながります。
株式会社学情が提供する“職場体感型”採用動画「Job Tube」は、採用のプロによるインタビューを通じて、企業の魅力や強みを求職者へ効果的に伝えられます。これにより、他社との差別化を図ることが可能です。
選考
選考プロセスは、採用基準に基づき、自社に最適な人材を見極める重要な段階です。選考を行う際は、事前に面接官と採用基準を共有しましょう。
採用基準が統一されていないと、面接官によって評価がばらつき、結果として採用のミスマッチにつながる可能性があります。このため、十分な注意が必要です。
書類選考
書類選考では、次のポイントを確認しましょう。
- 採用要件(経験・スキル)とマッチしているか
- 誤字脱字
- 転職理由
- 志望動機
- 自己PR
- 転職回数
- 離職期間
これらのポイントを総合的に評価し、次の面接でさらに深く掘り下げるべき求職者を選定します。
面接
面接では、求職者のスキルや経験だけでなく、人柄やカルチャーフィットも見極めましょう。
面接のポイントは次のとおりです。
- 履歴書や職務経歴書の内容を深掘りする
- 多角的な質問で行動特性や思考プロセスを引き出す
- 話し方や表情などから人柄やコミュニケーション能力を見極める
- 自社の魅力を伝え、相互理解を深める
質の高い面接を実施するには、こちらの記事を参考にしてください。
技能審査
IT系やクリエイティブ系などの専門スキルが求められる職種では、技能審査を実施することがあります。
これは、応募者の実務能力や専門スキルを客観的に評価するための重要なステップです。知識だけでなく、実際に業務で通用するレベルかを見極めます。
技能審査の方法や内容は、人事部だけで決定せず、配属先の上司や同僚に確認することが大切です。審査方法に誤りがあると、求職者を正しく評価できません。
また、公平に評価するためには、評価基準を統一し、選考に関わる社員全員と情報を共有しましょう。
内定・入社
内定・入社プロセスでは、求職者の入社意欲を最後まで高め、スムーズな受け入れ体制を整えることが重要です。
近年は人材獲得競争が激化しており、競合他社に流れてしまうケースも少なくありません。内定後も気を抜かず、戦略的なフォローで確実な入社へとつなげましょう。
内定通知は早く出す
内定通知は、出し惜しみせずにできるだけ早く出すことがポイントです。
優秀な人材ほど複数の企業からオファーを受けているため、内定通知が遅れると、他社へ流れてしまう可能性が高まります。
迅速な対応は、企業側の熱意を示すだけでなく、求職者の入社意欲を維持し、安心感を与えることにもつながるでしょう。
内定者フォローを実施する
内定者フォローは、内定を出してから入社までの期間に、求職者の入社意欲を維持するために必要です。
入社までの期間は、求職者が不安を感じやすいため、企業からの丁寧なフォローが求められます。
内定者フォローの具体的な方法は次のとおりです。
- 懇親会
- 社員との座談会
- オフィス見学
- 入社前研修
- 個別面談
- 定期的な連絡
社員の定着を図る
中途採用でせっかく優秀な人材を獲得しても、早期に離職してしまっては意味がありません。
入社した社員が定着し、長く活躍してもらうためには、受け入れ後の適切なフォローが重要です。
オンボーディング
オンボーディングとは、新入社員が会社に馴染み、早期に能力を発揮できるよう支援する一連のプロセスです。
単なる入社手続きや研修だけでなく、企業文化への適応、人間関係の構築、業務への理解促進までを総合的にサポートします。
これにより、新入社員の不安を軽減し、定着率向上や早期戦力化につながります。
メンター制度
メンター制度とは、新入社員や若手社員(メンティー)に対し、先輩社員(メンター)が個別につき、業務面だけでなく、精神的なサポートも行う制度です。
メンター制度を導入することで、新入社員は安心して会社に馴染むことができ、早期離職の防止やエンゲージメントの向上につながります。
1on1ミーティング
1on1ミーティングとは、上司と部下が定期的に行う個別面談です。
業務の進捗確認だけでなく、部下のキャリア形成やスキルアップ、抱えている悩みなどについて話し合う場として活用します。
定期的な1on1は、部下の離職防止やパフォーマンスの向上、そして信頼関係構築につながるでしょう。
中途採用の動向と求職者のニーズ
採用プロセスの最適化を図るには、中途採用の動向や求職者のニーズを把握することが大切です。
これらの情報を採用戦略に反映させることで、より効果的な採用活動につなげられます。
今、注目されているキャリア採用
株式会社学情の調査によると、「キャリア採用(中途採用)の割合が新卒採用を上回る」と回答した企業は36.5%でした。これは2024年の調査と比べ、5.9ポイント上昇しています。
キャリア採用において、採用人数を増やす年齢層は「20代後半(66.7%)」が最多で、次いで「30代前半(56.8%)」が続きます。
従来の中途採用は、即戦力人材の採用が主流でしたが、近年はこれまでの社会人経験を活かしつつ、企業文化にも早期に馴染みやすい20代後半から30代前半の層への需要が高まっています。
※参考:株式会社学情「若手採用に意欲!4社に1社がキャリア採用と新卒採用を同割合で計画(2025年5月)」
株式会社学情「「採用計画」に関する企業調査(2024年5月)」
第二新卒とヤングキャリアで異なる志向
株式会社学情の調査によると、キャリアチェンジを通じて実現したいこととして、社会人経験3年未満の第二新卒のトップは「興味のある仕事への挑戦(65.4%)」で、社会人経験3年以上のヤングキャリアは「労働条件の改善(68.1%)」が最多でした。
この結果から、第二新卒は仕事内容や挑戦を通じた自己実現を求める一方、ヤングキャリアは労働条件の改善を重視していることが分かります。
採用活動を効率的に進めるには、採用ターゲットに適したアプローチが重要です。それぞれの層の志向性を理解し、求職者が求める魅力を効果的に打ち出しましょう。
※参考:株式会社学情「20代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(転職で実現したいこと)2024年9月版」
新卒採用と中途採用の違い
新卒採用と中途採用では、募集時期や候補者の経験などが大きく異なります。
新卒はポテンシャル重視で年間スケジュールが固定されやすい一方、中途は即戦力を求めるため、面接回数や選考スピードなども柔軟に調整される傾向があります。
新卒採用
新卒採用では、大学生や専門学校生などが就職活動を行う時期に合わせ、説明会やインターンを通じて大人数の候補者と接点を持つのが一般的です。
企業側はポテンシャルや適性を重視し、筆記試験やグループディスカッションを採用フローに組み込む傾向があります。
また、内定出しから入社までに長い期間があるため、内定者フォローとして懇親会や研修を実施し、早期離職の防止に努める取り組みも重要となります。
さらに、学業との両立を配慮した日程調整や広報活動も欠かせず、企業イメージを高める戦略が求められます。
中途採用
中途採用は通年で必要人材を補充するケースが多く、即戦力を求める企業が中心となります。
書類選考や面接を短期間で行い、候補者のスキルや実務経験を詳しく確認する傾向があります。
また、内定から入社までの期間が比較的短いため、スピーディーな入社手続きや条件面のすり合わせが求められます。
一方、候補者が複数の企業からオファーを受けている場合、提示条件や面接時の印象がダイレクトに採否に影響するため、候補者との密なコミュニケーションが重要です。
新卒採用の4つの採用フロー
新卒採用では、企業によってさまざまな採用フローが存在します。
ここでは代表的な4つのモデルを取り上げ、スケジュールや選考方法の特徴を簡潔に解説します。
各フローには応募者数や選考ステップの多寡に差があり、自社のニーズに合わせた適切な運用が肝要です。
基本型
基本型は、一般的な新卒採用の流れを踏襲するオーソドックスなフローです。
まず募集告知やエントリー受付を行い、書類選考を経て1次面接から最終面接へと段階を進めます。
筆記試験や適性検査を挟む場合もありますが、採用期間が比較的長く確保されているため、企業によっては面接回数を複数回設定し、応募者の人物面やポテンシャルを丁寧に評価するのが特徴です。
通年型
従来の新卒採用は、卒業年度直前の3月に広報活動を開始し、6月から選考を行う「新卒一括採用」が主流でした。
しかし近年は、留学生の増加や多様な人材を求める企業のニーズから、時期を問わず採用活動を行う通年採用が広がりを見せています。
通年採用では入社時期が複数回に分かれることケースもあり、学業や研究、留学を理由に9月に卒業する学生にも柔軟に対応できます。
説明会・選考一体型採用フロー
説明会と選考を同日に実施するタイプは、大量の応募者を短期間で処理したい企業に向いています。
会社説明を受けた学生が、そのまま筆記試験や1次面接へ進む形となり、スケジュール効率が高い点がメリットです。
一方で、学生が企業理解を深める時間が短く、志望動機が定まらないまま選考に進んでしまう懸念もあります。
そのため、事前の情報提供を充実させたり、説明会で質問を受け付ける時間を十分に確保するなど、応募者がミスマッチを感じにくい工夫が大切です。
インターンシップ型採用フロー
インターンシップを活用した採用フローでは、学生に実際の業務を体験してもらうことで、企業理解と応募意欲の向上を図ります。
一定期間のインターンシップ終了後、選考に進む形式が一般的で、企業側も学生の適性やコミュニケーション能力を実務ベースで見極めやすい利点があります。
また、学生にとっても業界や企業の雰囲気を把握しやすいため、早期離職のリスクを下げる効果が期待できます。
ただし、企画や運営に手間やコストがかかるので、自社のリソースに合わせたプログラム設計が不可欠です。
中途採用の5つの採用フロータイプ

採用フローは、新卒採用と中途採用で異なります。中途採用の採用フローには、おもに次の5タイプがあります。
- 基本型
- 試験先行型
- 会社説明会・選考一体型
- 筆記試験・面接一体型
- リクルーター型
それぞれ特徴が異なるため、自社に適したタイプを導入するようにしましょう。
基本型
中途採用は、通年採用のケースがほとんどです。新卒採用とは異なり、求職者から応募があったタイミングで随時選考を進めていきます。基本型のおもな流れは、次のとおりです。
- 募集
- 書類選考
- 筆記試験・適性テスト
- 面接
- 内定
中途採用では、基本的に会社説明会のステップはありません。会社説明は、個別面接のときに行うのが一般的です。書類選考は、人事部が担当するケースと募集職種に該当する部署が担当するケースがあります。
中途採用の場合、書類選考の合格後に筆記試験や適性テストを実施しない企業もあります。内定者が出た後は、求人募集の停止を忘れないようにしましょう。
試験先行型
試験先行型は求職者から応募があった後、書類選考と筆記試験を実施し、人材を絞ってから本格的な選考を進めるタイプです。書類選考と筆記試験までのステップは、オンラインで行われるケースもあります。
基本的な流れは、基本型と変わりません。事前にスクリーニングできるため、応募者が多い場合や優秀な人材を絞り込みたい場合におすすめです。
ただし、試験の成績が良い応募者と自社が求める人材が必ず合致するとは限りません。企業への理解が浅い求職者が次の選考に進み、ポテンシャルの高い求職者を逃してしまうおそれもあります。
会社説明会・選考一体型
会社説明会・選考一体型は求職者からの応募後に、会社説明会と書類選考を同時に実施するタイプです。
2つのステップを同日に実施することで採用活動期間を短縮できるため、すぐに人材を確保したい場合におすすめです。
また、すべての応募者が自動的に選考に進むため、母集団を増やすことができます。
ただし、応募者は会社説明会参加後、時間に余裕がないまま書類選考を受けなければなりません。
企業への理解不足の状態で、あるいは志望動機が曖昧なまま選考に進むため、ミスマッチが起きる可能性があります。
筆記試験・面接一体型
筆記試験・面接一体型は、筆記試験や適性テストと1次面接を同日に実施するタイプです。
ほかの採用フロータイプでは、筆記試験や面接を別の日に実施しますが、筆記試験・面接一体型は別のタイプの選考を同日に実施できるため、総合的な結果で人材を判断したい企業におすすめです。
ただし、すべての応募者と面接するのが前提になるため、採用活動に関わる担当者は長時間拘束されることになります。
リクルーター型
企業から学生に接触するリクルーター型は応募者の人物像を重視して選考を進めていくタイプです。選考では、筆記試験や適性テストを行わないこともあります。
リクルーター型では人物像を見極めるために、ほかの採用フロータイプよりも応募者とのコミュニケーションを大切にします。本格的な選考に入る前に、カジュアル面談や体験入社を取り入れるケースも珍しくありません。
カジュアル面談は、気軽な雰囲気のなか、求人内容について企業側と応募者側の齟齬を無くす目的で行われます。応募者とのコミュニケーション機会を増やすことで、応募書類や面接では把握しきれない要素を判断しやすくなります。
リクルーター型は、リファラル採用やリクルーター制度で取り入れられています。
採用フローを準備する際の確認ポイント

中途採用の採用フローは、企業が求める人物像や職種などによって異なります。
採用フローの効果を発揮するためにも、自社に適したフローを作成することが大切です。
ターゲットを明確化する
従来の採用計画で自社が求める人材が集まらなかった企業では、ターゲットが曖昧になっている可能性があります。たとえば、応募者に必要以上の経験やスキルを求めているケースです。
まずはターゲットを明確にし、それに合わせた選考手法を取り入れることが大切です。配属予定の部署に確認し、応募者にどのくらいの経験やスキルを求めているかを確認しましょう。
現場が経験やスキルよりも、適性やポテンシャルを重視する傾向にある場合は、筆記試験よりも適性検査や面接を重視した選考手法に切り替えるのもひとつの方法です。
適切な選考期間を設定する
選考途中で辞退する応募者が多い場合は、選考期間の長さが原因の可能性があります。
中途採用の場合、応募から内定までの期間が長いと、他社に流れるケースも珍しくありません。
辞退者が出ると企業へのダメージが大きいため、適切な選考期間を設定するようにしましょう。選考期間の目安は、応募から内定まで1~2週間程度です。
このようなリスクを軽減するために、中途採用の選考期間をあえて短期間に設定している企業もあります。
選考の通過要件を再検討する
書類選考通過の応募者が少ない場合は、通過要件の基準が厳しい可能性があります。ターゲットを明確にするとともに、通過要件が適切かを再検討してみましょう。
また、選考に関わる担当者が複数人いる場合は、担当者の間で基準にずれが生じていることも考えられます。基準が曖昧であれば自社に適したものを再度設定し、担当者の間で認識を共有することが大切です。
面接では応募者の人間性やスキル、カルチャーフィットなど、見るポイントを定めておくと、基準にずれが生じるのを防ぐことができるでしょう。
採用フローの課題と改善方法
採用フローを運用する中で生じやすい課題を把握し、適切な対策を講じることが重要です。ここでは、代表的な四つの問題点と改善アプローチを挙げて解説します。
母集団形成が不十分
応募者が集まらない原因としては、求人情報の訴求力不足やターゲット設定の曖昧さが考えられます。求人票の内容を見直し、自社の魅力を具体的に伝える文章やビジュアルを用意しましょう。
また、求人媒体を複数活用したり、SNSやリファラル採用を併用するなど、接点を広げる工夫も有効です。募集要項と候補者像を明確にし、適切なチャネルで訴求することで、母集団形成を強化できます。
選考途中の離脱・辞退率が高い
書類選考や1次面接に通過した候補者が辞退するケースが多い場合、連絡の遅れや面接日程の不備が原因となっているかもしれません。
応募者とのコミュニケーションをスピーディーかつ丁寧に行い、日程調整や選考結果の通知を迅速に伝えることで、候補者の不安や他社への流出を防ぎやすくなります。
また、選考期間が長すぎるとモチベーションが下がるため、面接回数やステップを見直し、コンパクト化を図ることも検討しましょう。
内定辞退が多発する
最終面接まで進んでも内定を辞退される場合、条件提示や入社後のイメージ共有が十分でない可能性があります。
候補者との面接時に志望度をこまめに確認し、不安や疑問点を早めに解消するコミュニケーションを意識しましょう。
内定後には、社内見学や面談の機会を設けるなど、ミスマッチを減らす取り組みも有効です。
さらに、給与や福利厚生面などのオファー条件を明確に示し、他社との比較でも魅力を打ち出すことが大切です。
評価基準の不統一
複数の面接官や選考担当者がいる場合、評価項目や優先度が個々で異なると判断にばらつきが生まれます。
あらかじめ求める人物像を明確に定義し、面接質問や採点基準を共有することで、公平かつ一貫性のある選考が可能になります。
また、面接官同士でフィードバックを共有し合う場を設け、認識の擦り合わせを行うことも効果的です。
採用フローは自社に適したものを作成しよう
採用フローは、採用活動を効率的に進めることに役立ちます。すでに採用フローを作成している企業でも、日々変化する求職者のニーズと自社のニーズをすり合わせて、見直しを検討する必要があります。
採用フローを作成する際には、募集・選考・フォローの3つの要素を組み込み、自社に適した内容にすることが大切です。
また、人材採用をより効率的に行いたい場合は、Re就活の活用をご検討ください。
就活の登録会員は、93.3%が20代です。サービスを利用するとスカウト機能やキャリアアップイベントを通じ、20代の求職者に直接アプローチできます。
採用地域や職種に応じて多彩なプランをご用意しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。









