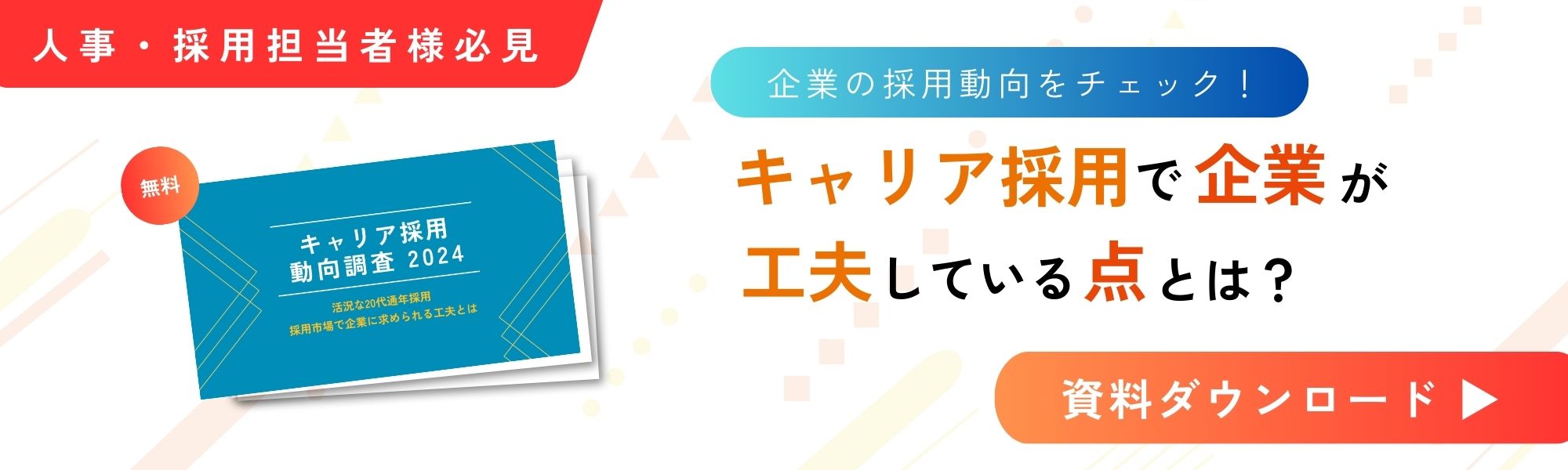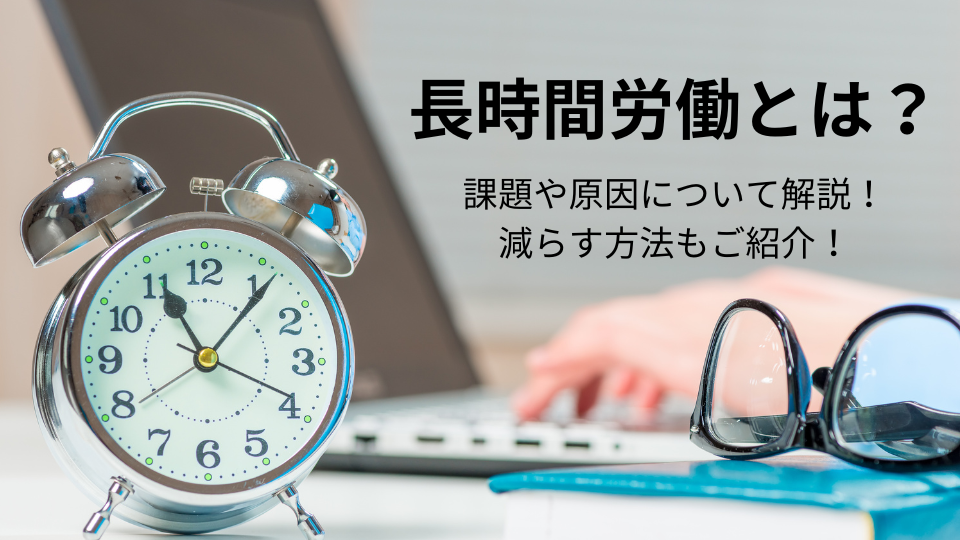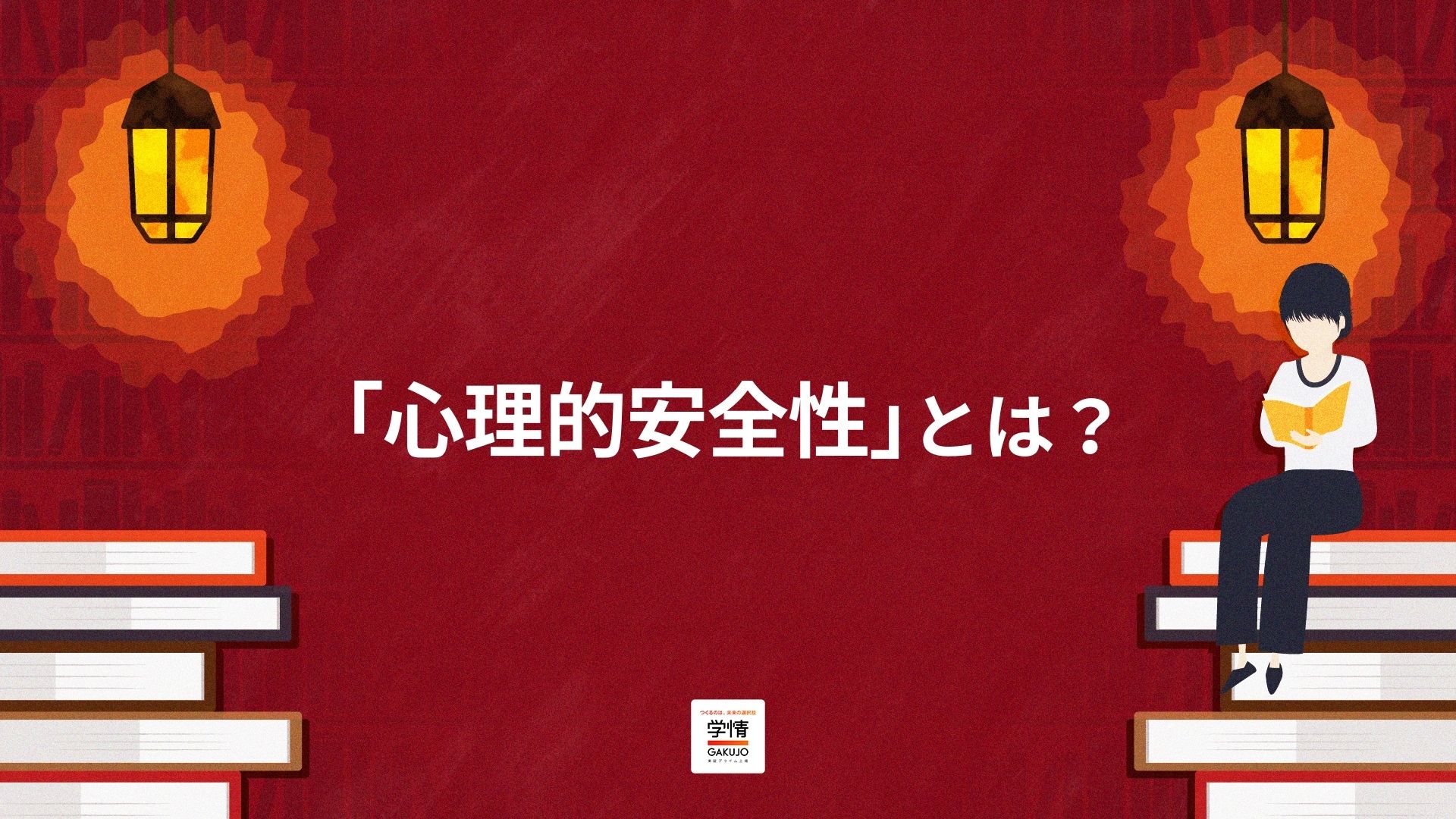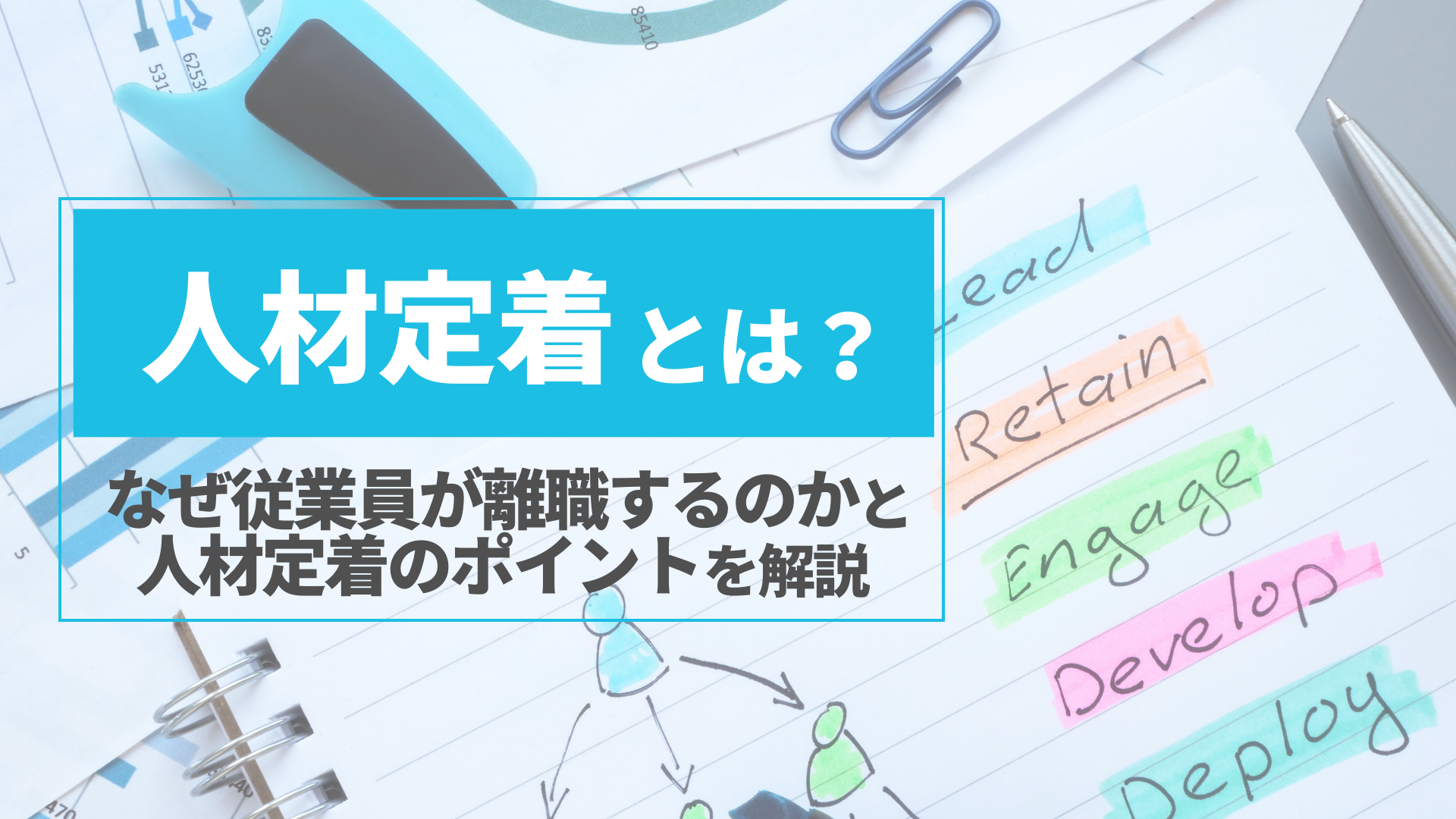ウェルビーイングの定義とは?企業が取り組むメリットや課題を解説
公開日:2023.05.26
更新日:2025.02.15

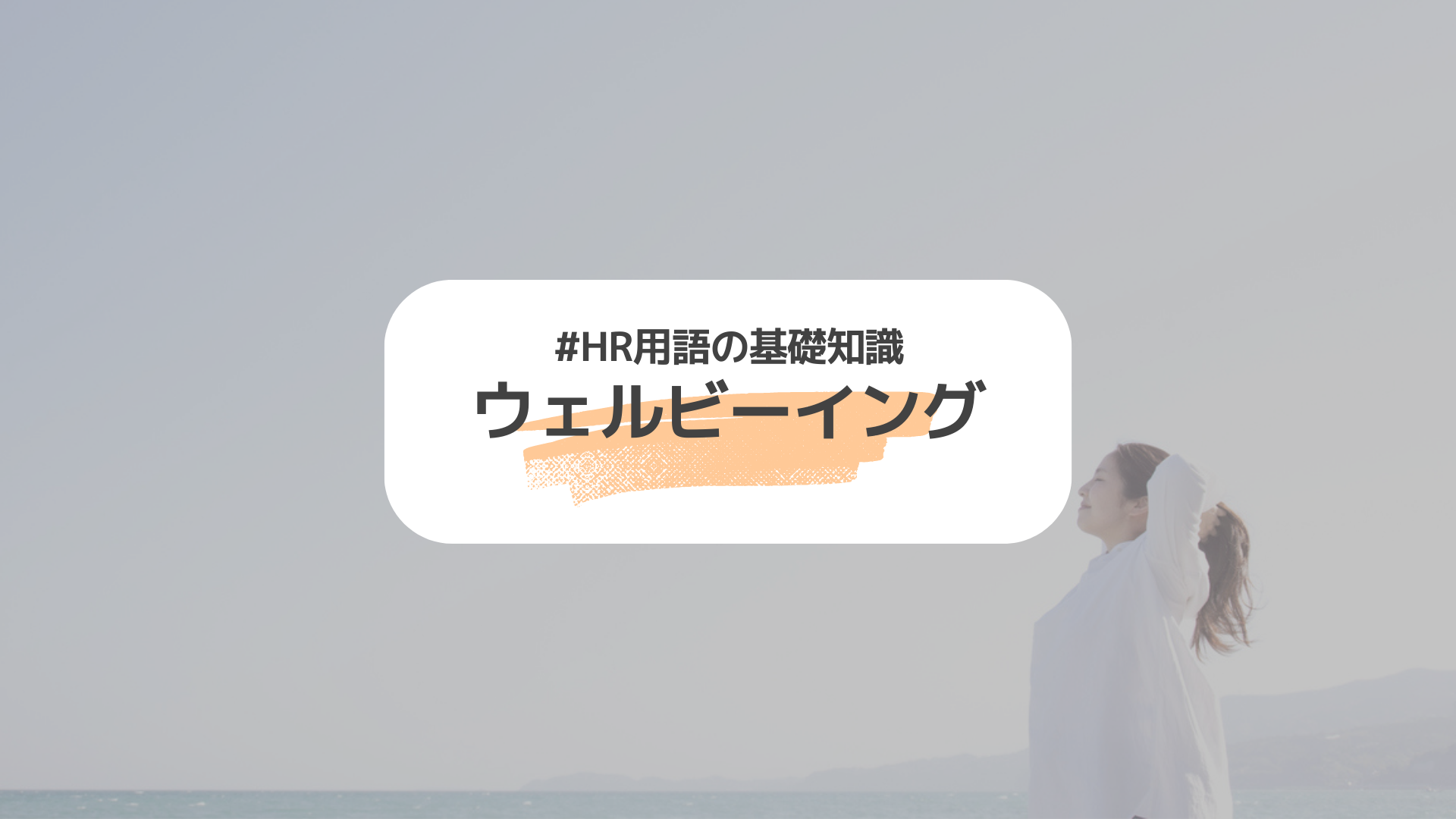
近年、ウェルビーイング経営に取り組む企業も増えています。自社でもウェルビーイング経営に取り組む予定があるものの、「ウェルビーイング経営とは何か」「自社にどのようなメリットがあるのか」と気になる企業の担当者もいるのではないでしょうか。
この記事ではウェルビーイングとは何か、企業が取り組むメリットは何かを解説します。ウェルビーイング経営の課題や具体的な方法も解説するので、自社で取り組む際に役立ててください。
ウェルビーイングとは

まずは、ウェルビーイングとは何かについて理解を深めましょう。
身体的、精神的、社会的に良好な状態にあるという概念
ウェルビーイングとは心身ともに健康なことに加え、社会的にも満たされた状態を指す概念です。
世界保健機関(WHO)と厚生労働省では、次のように定義しています。
| 世界保健機関(WHO) | 健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること |
| 厚生労働省 | 個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念 |
※出典:社団法人日本WHO協会「健康の定義」
https://japan-who.or.jp/about/who-what/identification-health/
※出典:厚生労働省「雇用政策研究会報告書 概要(案)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000467968.pdf
近年、ウェルビーイングの概念は「ウェルビーイング経営」としてビジネスシーンでも広まっています。ウェルビーイング経営とは、従業員の社会的な幸福にもフォーカスし、仕事へのモチベーションやエンゲージメントを高めることを目指す経営戦略の一つだと言えます。
健康経営との違い
健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点で捉えて取り組むことです。特定非営利活動法人健康経営研究会では、企業が従業員の健康に配慮することで、経営面においても大きな成果が期待できると定義されています。
健康経営の代表的な取り組みには、次のようなものがあげられます。
- 健康増進に向けて数値目標を設定
- 労働時間の見直し
- 健康診断の受診率100%を目指す
- 健康教育の機会を提供
- 健康相談の窓口を設置 など
ユニークな取り組みではマラソンイベント参加時の特別休暇の付与、自社にトレーニングルームを設置などの事例もあります。健康経営の目的は、基本的に従業員の健康の維持または増進です。
一方のウェルビーイング経営の目的には、従業員の健康に社会的な幸福度がプラスされているため、健康経営の次のステップとも言えます。
ウェルビーイングが企業に注目されている背景

近年、ビジネスシーンでウェルビーイング経営が注目されている背景には、企業が直面しているさまざまな課題があります。
労働者不足
少子高齢化にともない、多くの業界で労働者不足が深刻化しています。厚生労働省の「労働経済動向調査(令和3年8月)の概況」によると、多くの業界で労働者が過不足状況になっていることがわかっています。(※令和3年8月調査)
| 業種 | 不足 | 過剰 |
| 調査産業計 | 34% | 5% |
| 建設業 | 50% | 0% |
| 製造業 | 35% | 7% |
| 情報通信業 | 35% | 2% |
| 運輸業・郵便業 | 42% | 4% |
| 卸売業・小売業 | 18% | 4% |
| 金融業・保険業 | 10% | 1% |
| 不動産業・物品賃貸業 | 33% | 2% |
| 学術研究・専門・技術サービス業 | 34% | 6% |
| 宿泊業・飲食サービス業 | 16% | 4% |
| 生活関連サービス業・娯楽業 | 33% | 6% |
| 医療・福祉 | 45% | 4% |
| サービス業(他に分類されないもの) | 31% | 4% |
特に深刻な労働者不足に陥っているのは、建設業、運輸業・郵便業、医療・福祉です。2030年には最大79万人の労働者不足が予測されている情報通信業では、今後さらに過不足状態になる可能性があります。
※出典:厚生労働省「労働経済動向調査(令和3年8月)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/2108/dl/8roudoukeizaidouko.pdf
労働者不足が深刻な中で優秀な人材を集めるには、企業が従業員をより大切に尊重する必要があります。また、離職を防ぐには、従業員の帰属意識やエンゲージメントを高めることが重要です。
このような背景から、従業員の社会的な幸福を追求するウェルビーイング経営が注目されるようになりました。
労働環境の整備に対するニーズ
近年、政府が主導して働き方改革が推進されています。長時間労働の是正や有給休暇の取得などが順次義務化されている状況です。義務に従わなかった場合、事業者に対して罰則が設けられています。
たとえば年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対し、5日間取得させなかったときには、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、ライフスタイルの多様化にともない、オフィスに出社する従来型の働き方では働き続けるのが難しくなる従業員もいます。
従業員が働き続けるには、さまざまな働き方に対応する必要があります。たとえば育児や介護などのライフステージを迎えた従業員は、時間や場所にとらわれないテレワークなら働き続けられる可能性があるでしょう。労働環境を整備することは、働き方改革の推進だけでなく、従業員一人ひとりの幸福度を高めることにつながるのです。
ダイバーシティの推進
ダイバーシティとは、異なる属性を持った人たちが組織や集団で共存している状態を指します。ダイバーシティの広がりにともない、企業側も多様性を受け入れる必要性が出てきました。
さまざまな価値観の従業員が働ける環境整備が重要と考えた結果、ウェルビーイング経営が注目されるようになりました。ウェルビーイング経営によって従業員一人ひとりの幸福度が高まると、企業イメージの向上にもつながります。
企業がウェルビーイング経営に取り組むメリット
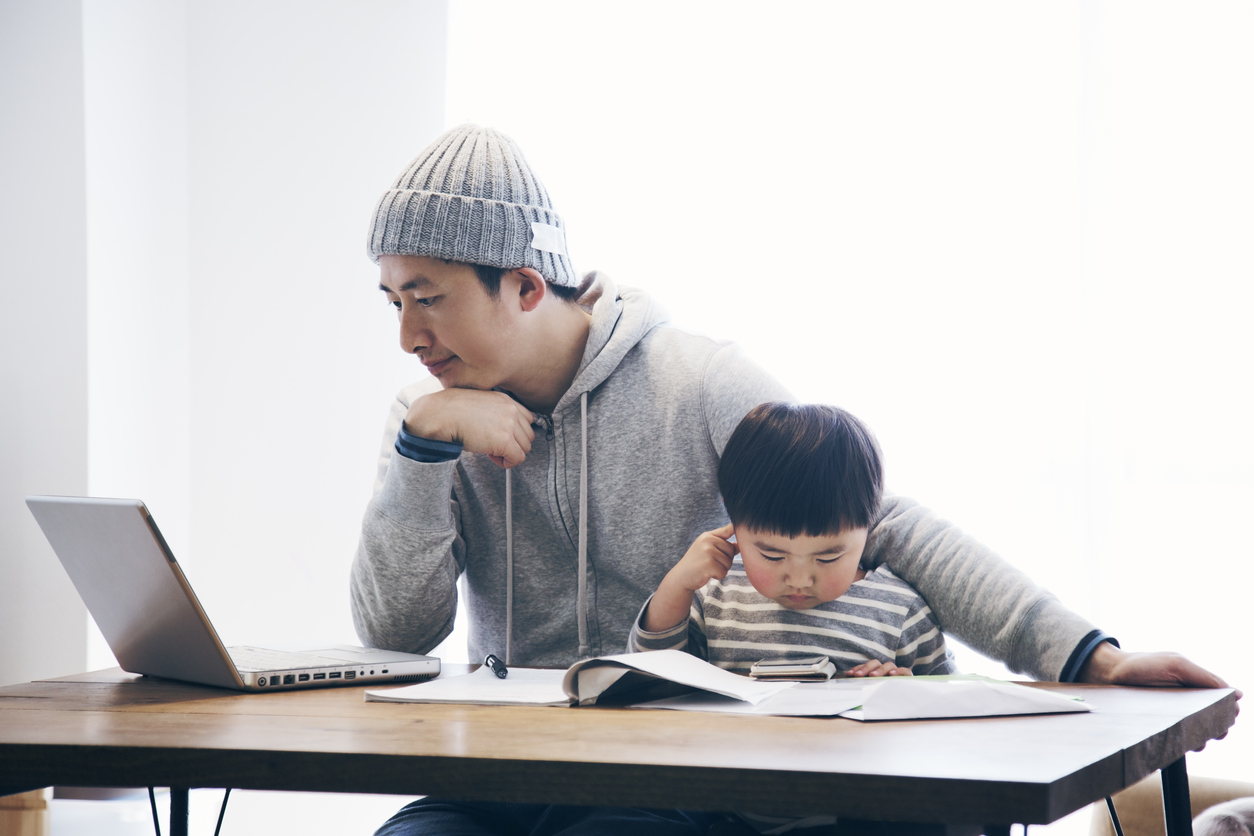
ウェルビーイング経営に取り組むと人材の獲得や離職率の低下など、企業にさまざまなメリットをもたらす可能性があります。
人材の獲得
労働者不足を課題に抱える業界も多い中で、いかに人材を獲得するかが重要になります。より多くの人材を獲得するには、働きやすい環境整備が必要です。働きやすい職場は求人への応募者が集まりやすいため、人材の獲得につながります。
Re就活キャンパスが実施したアンケートによると「就職活動中に企業がウェルビーイングに取り組んでいることを知ると、志望度が上がりますか?」という質問では、「志望度が上がる」「どちらかと言えば志望度が上がる」と回答した学生が80%を超えています。
| 就職活動中に企業がウェルビーイングに取り組んでいることを知ると、志望度が上がりますか? | 割合 |
| 志望度が上がる | 44.5% |
| どちらかと言えば志望度が上がる | 36.2% |
| どちらとも言えない | 14.2% |
| どちらかと言えば志望度は上がらない | 1.6% |
| 志望度は上がらない | 3.5% |
※出典:株式会社学情「2024年卒学生の就職意識調査(ウェルビーイング)2023年3月版」
https://ferret-one.akamaized.net/files/64058e2271663d0e94cb74e2/230308-navienq.pdf?utime=1678085666
ウェルビーイングを意識する学生が多い背景には、社会問題に対する関心が高いいわゆるZ世代が増えていることが考えられます。
離職率の低下
厚生労働省の「令和3年雇用動向調査結果の概況」によると、一般労働者の離職率は前年に比べて上昇していることがわかっています。
| 一般労働者の離職率 | |
| 令和3年 | 11.1% |
| 令和2年 | 10.7% |
※出典:厚生労働省「令和3年雇用動向調査結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/22-2/dl/gaikyou.pdf
労働者不足が懸念されるなか、企業にとって離職率の上昇は避けたいことの一つです。離職率をおさえるには、従業員の帰属意識を高めることが大切です。企業がウェルビーイング経営に取り組むと、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高められます。その結果、企業への帰属意識が高まり、離職を防ぐことにつながります。
人材確保の強化
ウェルビーイング経営への取り組みは、人材市場で有利に働く可能性があります。
Re就活キャンパス2024登録者を対象に実施したアンケート調査では、「ウェルビーイングを推進する企業に対して、好感が持てる」と回答した学生が多いことがわかっています。
| 社員の「ウェルビーイング」を推進する企業に持つ印象 | 割合 |
| 好感が持てる | 70.3% |
| どちらかと言えば好感が持てる | 20.2% |
| どちらとも言えない | 6.7% |
| どちらかと言えば好感が持てない | 1.2% |
| 好感が持てない | 1.6% |
※出典:株式会社学情「2024年卒学生の就職意識調査(ウェルビーイング)2023年3月版」
https://ferret-one.akamaized.net/files/64058e2271663d0e94cb74e2/230308-navienq.pdf?utime=1678085666
企業がウェルビーイング経営に取り組むと、学生に自社の魅力をアピールできるため、優秀な人材が集まりやすくなります。20代の優秀な人材を確保したい場合は、Re就活がおすすめです。
Re就活は、会員数280万人を誇る日本最大級の20代専門転職サイトです。登録者の84.7%が社会人経験があり、75.2%が初めて転職にチャレンジする20代です。20代の求職者に特化したアプローチが可能なので、20代の採用をお考えの企業様はぜひご相談ください。
労働生産性の向上
ウェルビーイング経営は従業員の健康だけでなく、社会的な幸福を追求する経営戦略です。従業員は整備された労働環境で働くと快適さが増し、仕事にやりがいを感じられるようになるでしょう。
ワークエンゲージメントが高まれば仕事への意欲が上がり、労働生産性の向上が期待できます。労働生産性は企業の業績に直結するため、従業員のワークエンゲージメントを高められるウェルビーイング経営の取り組みが必要です。
ウェルビーイング経営に取り組む際の課題点

ウェルビーイング経営は長期的に見ると、離職率の低下や労働生産性の向上が期待できます。
しかし、ステークホルダーの幸福度を追求するあまり、短期的には利益を上げることが難しくなる可能性があります。ウェルビーイング経営は、短期的な利益に直結しない取り組みにコストをかけるケースもあるためです。
そもそも利益を十分に出せていない企業では、ウェルビーイング経営の取り組みにコストをかけられないため、従業員をはじめとするステークホルダーの幸福度を高めることは難しいのが現状です。
ウェルビーイング経営にコストをかけ過ぎると、企業全体の業績が悪化するリスクもあるため、利益の追求と取り組みのバランスをとる必要があります。
ウェルビーイング経営に取り組む際の具体的な方法

ウェルビーイング経営は、健康経営の次のステップとも言えます。そのため、これまでの取り組みでは不十分なケースもあります。ここからはウェルビーイング経営の具体的な方法を解説するので、ぜひ参考にしてください。
労働環境を見直す
ウェルビーイング経営に取り組む際には、労働環境を見直してみましょう。労働環境が改善されて快適に働けるようになると、従業員のモチベーションやエンゲージメントが高まる可能性があります。
労働環境を見直す方法の具体例は、次のとおりです。
- 長時間労働の是正
- 有給休暇の取得推進
- 多様なワークスタイルの提供 など
労働環境を見直す際には、まず実態を把握することが大切です。労働時間の記録だけでは実態を十分に把握できないケースもあるため、社内アンケートを実施して従業員の声を拾いましょう。
テレワークを導入する際には、パソコンやインターネット環境がない従業員もいるかもしれません。パソコンやWi-Fiルーターは企業から貸し出すなど、従業員がテレワークできる環境を整備するようにしましょう。
福利厚生の充実
ウェルビーイング経営の目的には、従業員の社会的な幸福が含まれています。従業員の社会的な幸福度を高めるには、福利厚生を充実させ、プライベートを豊かにする方法もあります。
福利厚生を充実させるおもな方法は、次のとおりです。
- 家賃補助
- 財形貯蓄制度
- 法定以上の育児休業
- ジムやフィットネスクラブの割引
- 映画鑑賞の優待券
- 宿泊施設の優待券 など
また、福利厚生で従業員の食生活をサポートするには、社員食堂を充実させる方法もあります。社員食堂で高たんぱくや低脂質などの健康食を提供すれば、従業員の健康増進につながります。
子育て中の従業員向けには、福利厚生の一環としてベビーシッター費用の補助も検討してみるのも手です。
コミュニケーションツールの見直し
従業員同士のコミュニケーションが活性化すると、社内の人間関係が良好になり、労働生産性の向上が期待できます。社内コミュニケーションの活性化を促す具体的な方法は、次のとおりです。
- コミュニケーションツールの導入
- 共有スペースの設置 など
社内SNSやチャットツールを導入すると、離れた場所で仕事をしている従業員とコミュニケーションできます。チャットツールには、業務内容以外の会話ができる雑談専用のチャットルームを作っておくと、気軽にコミュニケーションが取りやすくなります。
また、社内のスペースに余裕がある場合は、リフレッシュスペースやマグネットスペースなどの共有スペースの設置を検討してみましょう。共有スペースはさまざまな部署や立場の従業員が集まるため、コミュニケーションの活性化を促せます。
健康増進のサポート
ウェルビーイングを目指すには、従業員が自身で心身の健康状態を把握することも大切です。企業は従業員が健康状態を把握できるよう、健康増進のサポートを行いましょう。
健康増進サポートのおもな方法は、次のとおりです。
- 健康診断や人間ドックの費用補助
- 予防接種の実施
- ストレスチェックの実施 など
2015年12月から、従業員50人以上の企業では年1回のストレスチェックが義務づけられました。ウェルビーイング経営で健康増進をサポートするなら、従業員50人未満の企業でもストレスチェックを行いましょう。
また、社内に健康相談できる窓口を設置すると、従業員が心身の健康についていつでも相談できる環境を整備できます。
ウェルビーイング経営で取得しておきたい認定制度

前述したように、ウェルビーイング経営の目的は、従業員の健康維持や増進が目的の健康経営に社会的な幸福度がプラスされます。
ウェルビーイング経営は健康経営の次のステップであるとも言えるため、ウェルビーイング経営に取り組む際は、まず健康経営からはじめるのもよいでしょう。
経済産業省が創設した「健康経営優良法人認定制度」では健康経営に取り組む企業を「健康経営優良法人」として可視化しています。
健康経営優良法人認定制度
健康経営優良法人認定制度とは、2016年に経済産業省が企業の健康経営の取り組みを推進するために創設された制度です。健康経営への取り組みを可視化することで、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、積極的に取り組んでいる企業として社会的な評価を受けられます。
制度には、大企業が対象の大規模法人部門と中小企業が対象の中小企業法人部門があります。これまでに6回の顕彰が行われており、令和4年3月9日に発表された「健康経営優良法人2022」では、大規模法人部門で2,299法人、中小企業法人部門で12,255法人が認定されました。
※参考:経済産業省「健康経営優良法人認定制度」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
認定されるメリット
健康経営優良法人に認定されると、社内外に企業の魅力をアピールできるため、企業イメージの向上や人材確保が有利になるなどのメリットがあります。
求職者に従業員の健康を考えてくれる企業であることが伝われば、「大切にしてもらえる」といった安心感を与えられ、応募を促せるかもしれません。自社のアピールポイントになり、採用活動の強化につながるでしょう。
また、民間の保険会社のなかには、健康経営優良法人向けのプランを設けているケースもあります。通常よりも安い保険料で加入できるため、コストカットにつながります。
自社と従業員のためにウェルビーイング経営に取り組もう

慢性的な労働者不足や労働環境の整備に対するニーズなどにより、ウェルビーイング経営に注目が集まっています。ウェルビーイング経営は健康経営の次のステップであり、取り組み内容によっては働き方改革にもつながります。
ウェルビーイング経営に取り組む際は、社内一丸となって行うことが重要です。労働環境の見直しや福利厚生の充実、コミュニケーションツールの見直し、健康増進のサポートなど各部署が連携して取り組みます。
また、ウェルビーイング経営は短期的に結果が得られるわけではありません。定期的に評価し改善を繰り返していきましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。