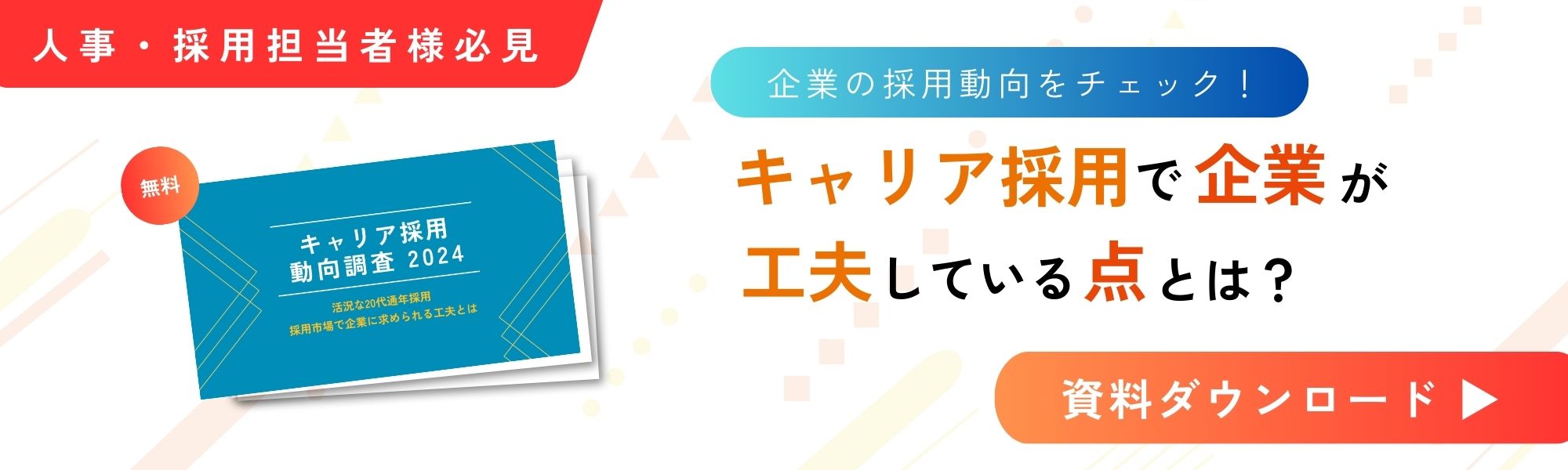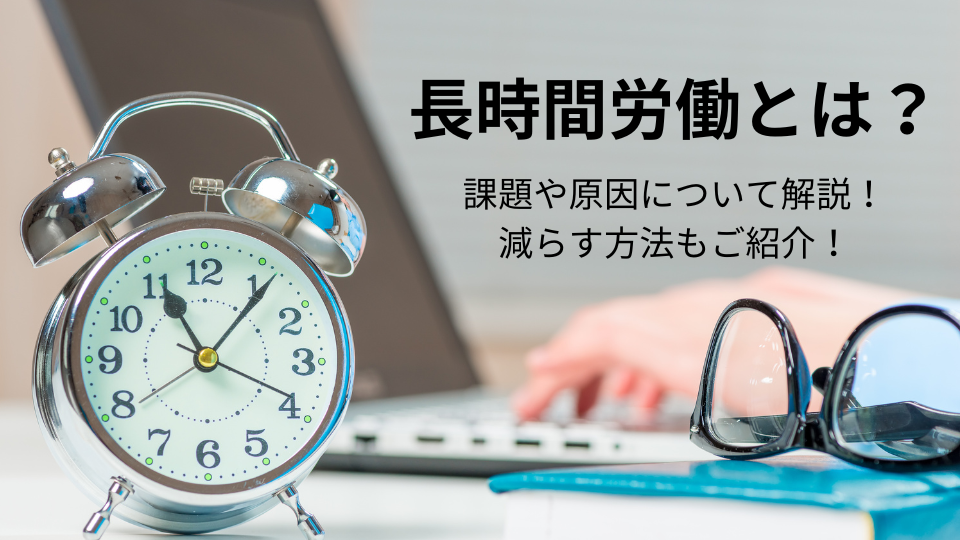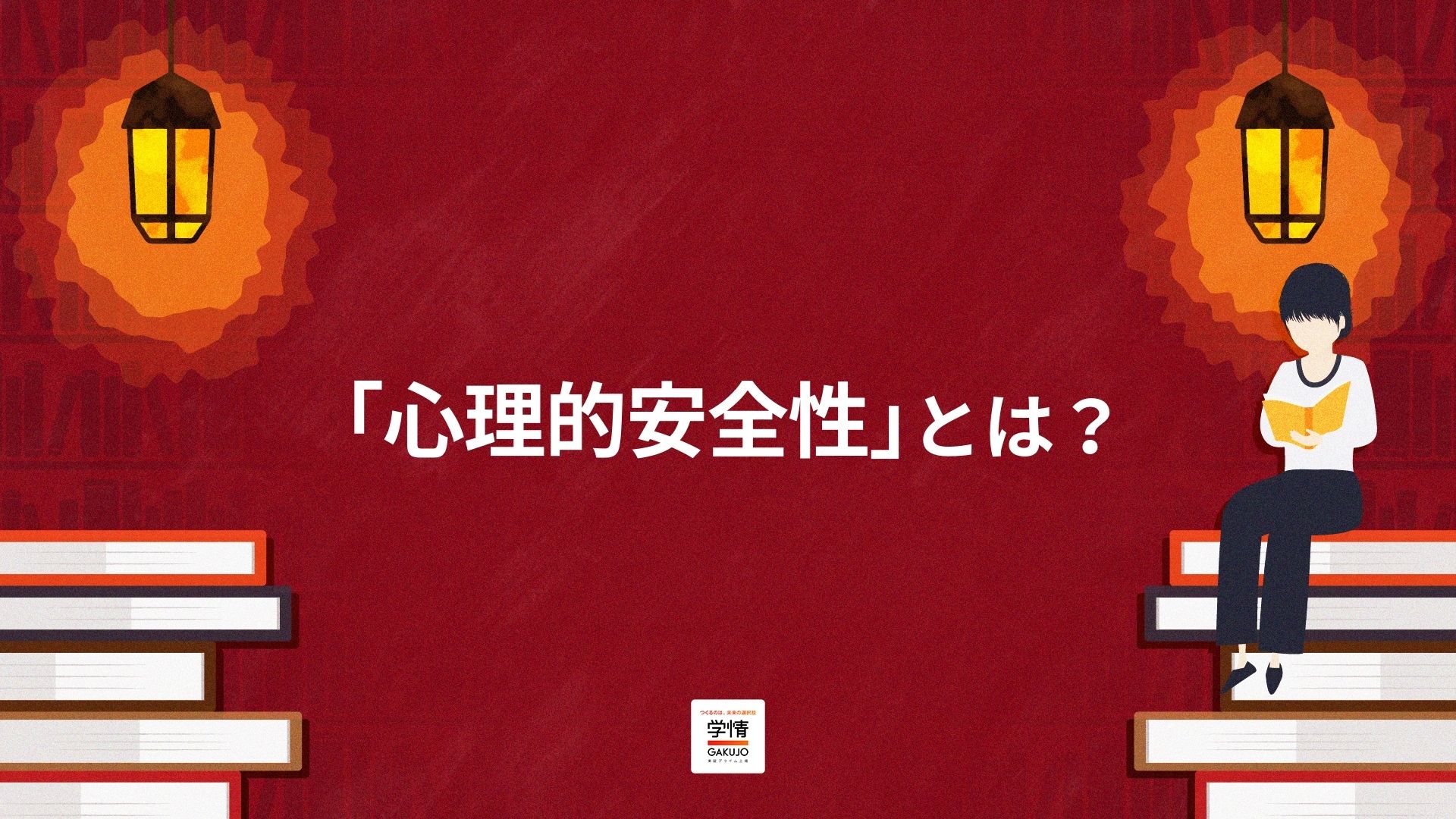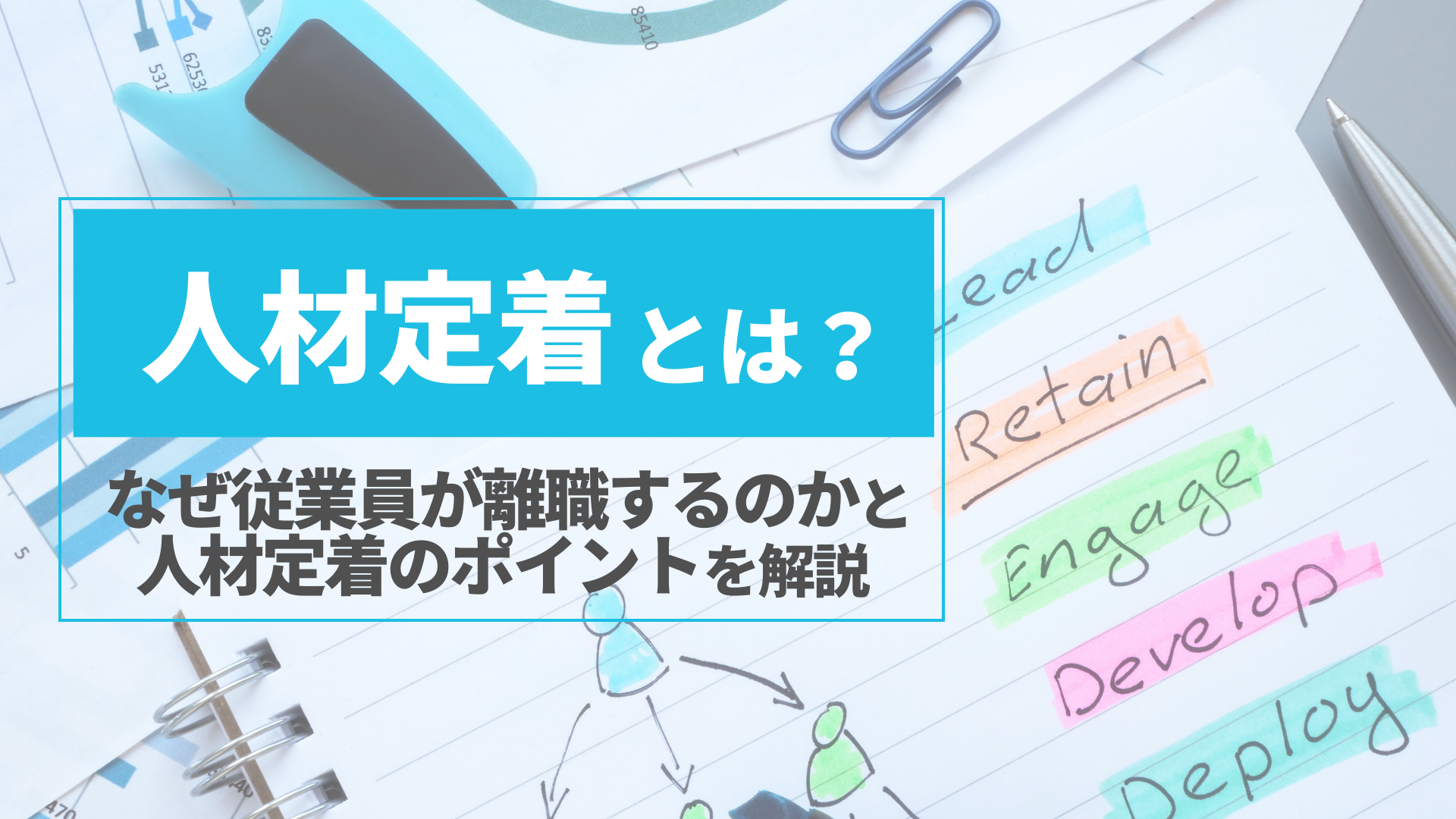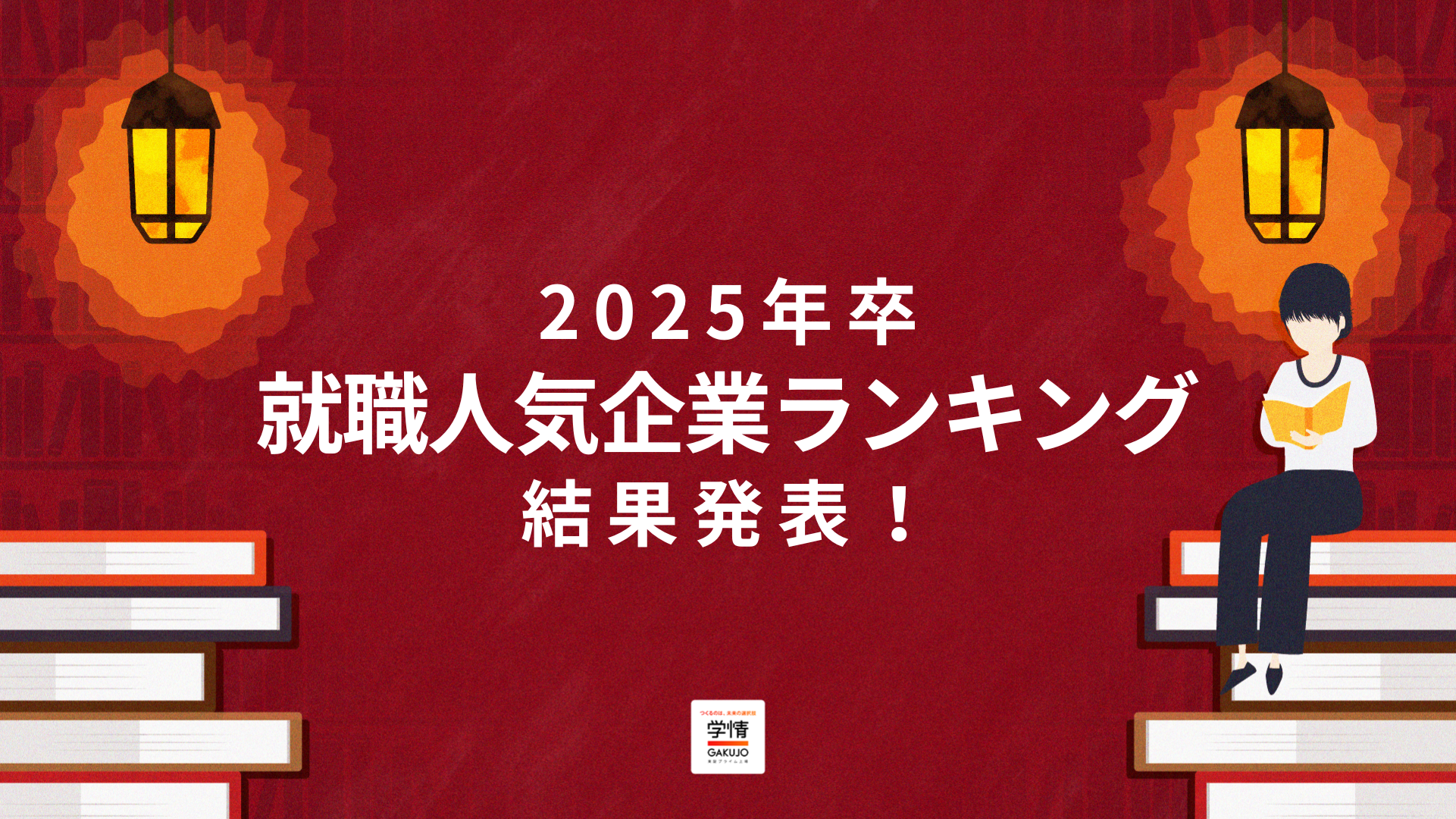アカハラとはどんなハラスメントのこと?おもな種類や具体例、予防策を徹底解説
2023.05.22

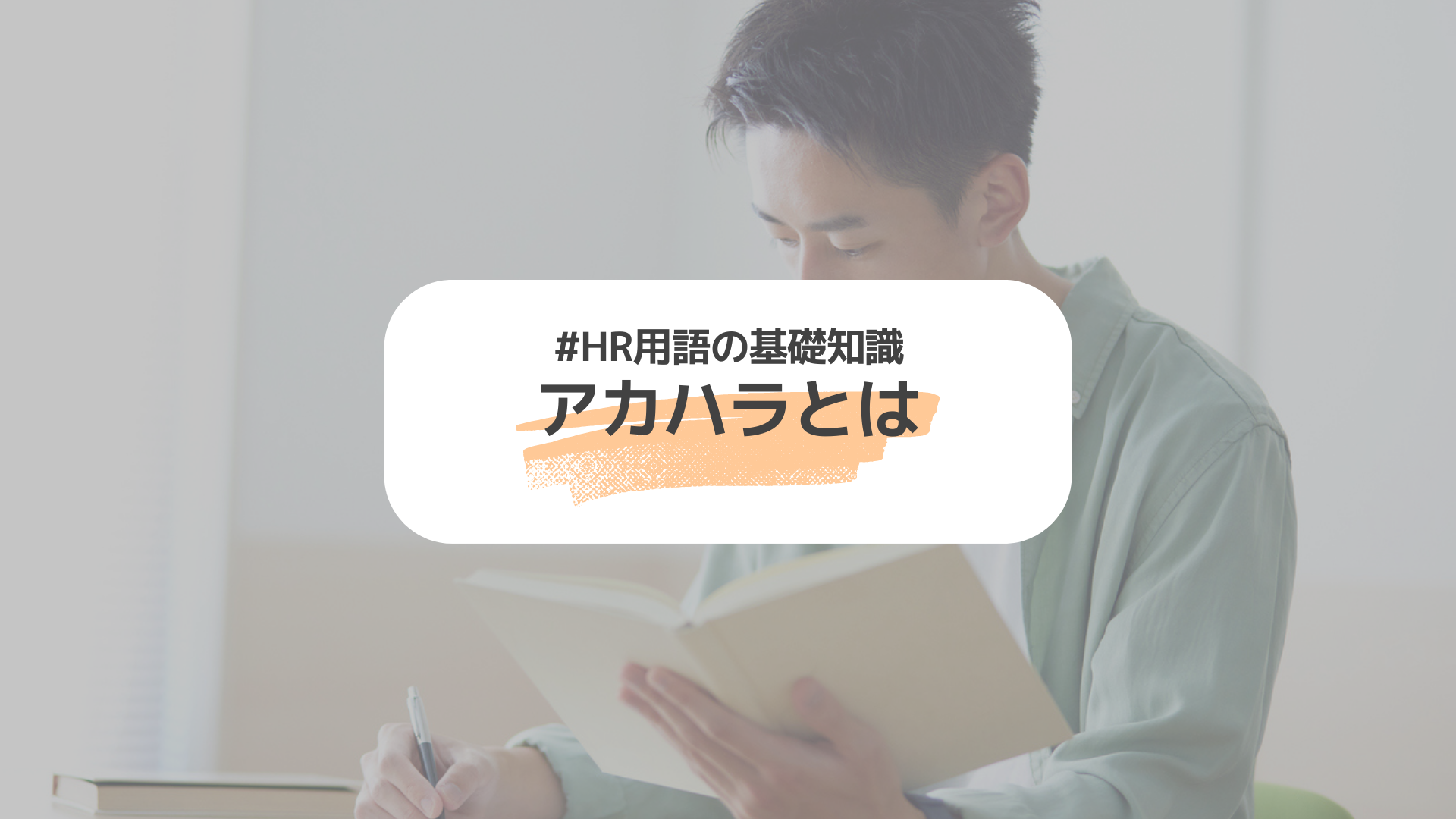
いじめや嫌がらせといった迷惑行為をハラスメントと言いますが、アカハラは大学や学術機関で起こるハラスメントを指します。
アカハラで訴訟になった場合、直接の加害者だけではなく大学も損害賠償を求められ金銭的にもイメージ的にも大きなダメージを負います。アカハラを起こさないためには原因や予防策を知らなければなりません。
この記事ではアカハラの基本的な説明だけでなく、具体例や発生する原因、アカハラを訴えられた場合の対処法、アカハラの予防策などを解説しています。アカハラを防止するための参考にしてください。
アカハラとは

アカハラはアカデミックハラスメントの略で、大学や学術機関などの教育の場で起こる「嫌がらせ」や「いじめ」などの迷惑行為のことです。アカハラによる訴訟が起こった際には、直接の加害者だけではなく大学側も安全配慮義務違反に問われ、損害賠償を求められてしまいます。また金銭面の問題だけでなく、大学のイメージも大きく損なわれるでしょう。
- 学習や研究の妨害
- 単位や学位の不認定
- 進学や就職の妨害
- 研究成果の盗用
- 侮辱的な言動
- プライバシーの侵害
またアカハラは研究生やゼミ生に対して発生するだけではなく、大学教授から准教授など教授間で行われるケースもあります。この場合、出張妨害や講師への推薦拒否などもアカハラに当たります。
アカハラはセクハラやパワハラ、ストーカー行為などと重なる部分もあり認定が難しいですが、もし相談を受けたらしっかりと受け止め、適切な対処をしましょう。
大学内は教員や職員が優位な立場で権力を利用しやすいため、ハラスメントが発生しやすい環境です。精神的・身体的損害を訴えられないためにも、大学側はアカハラを未然に防ぐための対策を取らなければなりません。どのような行為がアカハラにあたるのかを周知していく必要があります。
アカハラのおもな種類と具体例

アカハラはいくつかの種類に分けられます。具体例をあげながらみていきましょう。
学習や研究に対する妨害
学生には、学習や研究をする権利があります。教授が学習や研究のための正当な活動に対して、チャンスを与えなかったり邪魔をしたりするならその行為はアカハラに該当します。たとえば、締め切り間近なレポート作成に必要な機材が、教授の嫌がらせで使えないケースもアカハラです。
また直接学習や研究を妨害している行為ではありませんが、学習や研究に必要な時間を雑用などを押し付けて奪う、必要以上に長時間の講義を行うなどもアカハラに当たる可能性があるので注意が必要です。
<学習や研究に対する妨害例>
- 学習に必要な場所や機器、資料などを与えない
- 講義中に部屋から追い出す
- 本人が望んでいない研究テーマを押しつける
- 大量の雑務を無償で押しつけて研究時間を奪う
- 研究データを破棄する
- 一人だけ別の場所に隔離する
- 指導しない
- 論文を長期間放置してチェックしない
卒業・進級などの妨害
学生にとって卒業や進級は重要です。留年するのにも、学費や生活費がかかります。教授の嫌がらせで想定していた単位が取れなければ、退学に追い込まれるケースもあるでしょう。
「一度講義を休んだ」「講義に遅れたから」などの理由をつけて単位を与えないのは、明らかにアカハラに該当します。また「卒業したいなら、〇〇をするように」と卒業や進級を餌に、雑用や論文制作の手伝いなどを強要するのもよくありません。
<卒業・進級などの妨害例>
- 正当な理由がないのに単位を与えない
- 留年や退学を強要する
- 卒論を受けつけない
- 卒論を正当に評価しない
進学・就職の妨害
進学や就職は人生において大きな岐路に当たります。直接的・間接的に進学や就職の妨害をして不利益を与えれば、その行為はアカハラです。たとえば理系の研究室の学生が文系の就職先メインで就職活動している学生に、「就職先を理系に変えなさい」と執拗に迫り嫌がらせしてはいけません。
また推薦状を出して内定が決まった学生に対して、「引き続き就職活動をしてはいけない」と内定辞退にならないように圧力をかけるのも、アカハラに該当します。
アカハラは、教授から学生に対して起きるだけではありません。教授や准教授から地位の低い助手や講師に対して、学内講師推薦の拒否や昇進差別が行われるケースも対象となるので注意しましょう。
<進級・就職の妨害例>
- 進学や就職に必要な情報を故意に与えない
- 面接先や内定先に悪い噂を流す
- 就職活動内容が気に入らない場合に、進路や就職先を変えるように迫る
- 推薦状を出した就職先に対して、学生が内定辞退や選考辞退しないように圧力をかける学内講師推薦の拒否
- 学会に参加させない
- 研究費の応募申請を認めない
- 就職活動を禁止する
研究成果やアイディアの盗用
教授が有利な立場を利用して、学生や院生などの研究結果や論文を横取りするのもアカハラです。盗用された被害者が出版先の編集者に知らせた結果、教授から報復を受けるケースもあります。
また他社の論文を丸写しするのは明らかな盗用ですが、指導しただけの学生の論文に対して、第一著者として自分の名前を入れるように強要するのもアカハラに当たります。
<研究成果やアイディアの盗用例>
- 学生や院生の論文の一部または全部を、自分の論文として発表する
- 加筆訂正や指導を行った学生の論文に、第一著者として自分の名前を記させる
- 研究や論文の執筆に最も貢献した人を第一著者にしない
暴言や罵倒などの発言や威嚇
机をたたく、ものを投げるといった物理的な攻撃はもとより、人格を侵害するような発言もアカハラです。学生のためを思った言動だとしても、長時間にわたる叱責や拘束もいけません。
悪気なく暴言をはいてしまう教育者に対しては、どのような言動がアカハラに該当してしまうのか注意喚起をしていく必要があるでしょう。たとえば、提出されたレポートや論文について必要以上にけなしたり、講義から締め出すような言動はアカハラに該当します。
また、妊娠した女性に対して、退学や退職を促す言動もNGです。
<暴言や罵倒などの発言や威嚇例>
- 頭をたたく、突き飛ばすといった身体的攻撃をする
- 学生が作成した論文を丸めて捨てる
- ものを投げる
- 大勢の前できつく叱責する
- 人格を傷つけるような発言をする
- 妊娠した女性に退学や退職を促す
経済的負担の強要
研究費から支出しなければならない費用を、学生や指導員に負担させるのもアカハラです。研究に必要な試薬や実験器具は、大学側で用意しましょう。
また直接学生からお金を得なくても、金銭を得るための不正に手を貸すように強要するのもいけません。たとえば、研究費を不正に受給するため、学生に「バイトをした」「謝礼を受け取った」といった内容の架空の書類を書かせる行為もアカハラになります。
<経済的負担の強要例>
- 失敗した実験に対して、費用の支払いを強要する
- 研究に必要な試薬や物品、実験器具などを与えない
- 論文のチェックのために金銭要求する
- 論文の提出が遅れたことを理由に金銭要求する
プライバシーの侵害
家族や友人、恋人など職務とは関係のない情報を得ようとしたり、許可なく情報を公開するのはプライバシーの侵害です。プライベートに踏み込みすぎないように気をつけましょう。
また深夜や休日は、プライベートな時間帯です。連絡や指導を好まない学生も多いので、緊急性の高くない連絡は避けたほうがよいです。また指導する場所も、ホテルや居酒屋は適切ではありません。
<経済的負担の強要例>
- 成績や経歴など、人に知られたくない情報を話す
- 「彼氏いるの?」など交際相手について詳しく尋ねる
- スマホを見せるように迫る
- 電話番号やメールアドレスを許可なく公開する
アカハラが起きるおもな原因

大学や学術機関は、アカハラが起きやすい環境と言えます。アカハラが起きる原因を知り、対策を取りましょう。
公的機関によるチェックがない
職場でのハラスメント(パワハラ・マタハラ・セクハラなど)に対しては、労働基準監督署のような公的機関が相談窓口になり、会社に対してさまざまな働きかけを行っています。しかしアカハラに関しては、公的機関によるチェックがありません。
大学側がアカハラに関する問題を重要視していないと、アカハラに対する相談窓口が学内に設置されず被害者は悩みを相談できません。公的機関のチェックがない分、大学側が積極的にアカハラ防止に対して取りくむ必要があります。
ただし近年は文部科学省がハラスメントに関する積極的な対策を取り始めており、令和元年には大学数校に対してのアカハラ対策に関する調査も行っています。公的機関が今後アカハラの対策に関わる可能性もありそうです。
環境が閉鎖的になりやすい
大学という教育の場では自由な研究が尊ばれ、自律・自治がある程度確立しています。公的機関が入りにくく外部の目が届かないため、大学のゼミや研究室は閉鎖的になりやすい環境です。
アカハラの被害にあっても「相談する相手がいない」「問題が公になったら、大学に居づらい」「報復が怖い」などの理由で口外しにくく、一人で悩みを抱え込んでしまう可能性があります。そのため実態がなかなか把握できず、対策も民間企業のように進んでいません。
閉鎖空間におけるハラスメントだからこそ、被害者は逃げ場がなく追い詰められ、自殺や殺人事件などの事件に発展してしまうケースが実際にあります。大学の相談窓口が被害者のケアを行えるとよいですが、形ばかりで実際に機能していなかったり、学生や職員がその存在を知らなかったりするケースも多いようです。
大学側がアカハラを防止して被害者を救済する体制を整える必要があります。
権限が特定の人物に集中しやすい
大学は教授、准教授、研究員、学生などがピラミッド状のヒエラルキー構造となっています。指導教官ににらまれると「論文の評価や単位取得にも影響するかもしれない」などの恐れから、アカハラを受けても、ヒエラルキーの下層にいる学生や研究生は強く反論することが難しいでしょう。
任期付き雇用や非常勤講師といった雇用形態の多様さも、新たな権力構造が生まれる要因となっています。
また理系の学部では、巨額の研究費や研究設備を必要とします。必然的に研究をチームで行うことになりますが、指導教官に嫌われてチームから外された場合、研究者生命を絶たれてしまう可能性があります。チームに居続けるために、アカハラを訴えずに沈黙しているアカハラ被害者もいるでしょう。
アカハラを防止するためには教授のようなヒエラルキーの上層部に対して、アカハラに関する講習を行っていくことが重要だと言えます。
アカハラへの効果的な対策方法

アカハラを防止する方法、または起きてしまった際の対処方法を知っておくことが重要です。ここでは効果的な対策について解説します。
相談窓口を設置する
アカハラ被害者が悩みを相談できる窓口を、学内や学外に作りましょう。匿名での相談や相談員の指定、メールでの対応などが可能だと、相談しやすくなります。
相談員には、臨床心理士のようなハラスメントに対して知識を持つ専任の相談員が向いています。教職員が掛け持ちしなければならない場合は負担が大きく、相談案件が長期間放置されるなど、相談に適切に対応できない恐れがあるので注意してください。専門のハラスメント相談員の設置が難しい場合、外部の機関への委託を検討してもよいでしょう。
文部科学省が行った大学内のハラスメント対応に関する調査によると、相談件数は年々増え、相談者も学生だけではなく教員や職員など多岐にわたります。管理職から「ハラスメントのつもりではないのに、指導や指示がアカハラだととらえられてしまうがどうしたらよいのか」といった相談もあるようです。
また相談窓口に寄せられる内容は大学特有のアカハラだけではなく、セクハラやパワハラ、学生間のデートやDVに関するものまで多岐にわたる可能性があります。内容によっては労働法に関わるケースも含まれるので、相談員には専門的知識と対応が求められます。
※参考:文部科学省委託調査資料『「大学教育改革の実態把握及び分析等 に関する調査研究」 ~大学におけるハラスメント対応の 現状と課題に関する調査研究~』
https://www.mext.go.jp/content/20200915-mxt_gaigakuc3-000009913_1.pdf
アカハラを調査・審議する組織を作る
大学の相談窓口に寄せられる相談内容の半数程度は、相談者自身が意思決定することを助ける「相談」で終了することが多いようです。しかし相談者自身が解決できない場合があります。相談員で対応しきれない深刻なケースのために、アカハラを調査・審議する組織を作っておきましょう。
「相談」で解決しなかった場合、相談窓口が関係者に改善を呼びかける「調整」が一般的に行われます。所属長からの注意や、担当指導員の変更、話し合いの場を設けるなどの調整方法があります。「調整」で解決しないと、次は「調査・審議」です。調査委員は中立の立場にあるメンバー数名が選ばれ、調査結果は学内のハラスメント防止委員会などで審議されます。最終的な審議内容が学長に報告され、処罰や特別処置などが行われます。
調査段階に進んだ時のために、あらかじめ調査委員の候補や審議を行うメンバーを決めておくと、調査・審議がスムーズに進むでしょう。
アカハラ対策組織を整備する際の参考例
令和元年に文部科学省が、大学内のハラスメント対応に関する調査を行っています。調査内容をまとめた『「大学教育改革の実態把握及び分析等 に関する調査研究」 ~大学におけるハラスメント対応の 現状と課題に関する調査研究~』によると、平成28年の調査において「ハラスメント等の防止のための全学的な調査・対策の常設機関を設置」している大学は、65.4%です。
この調査では、ハラスメント対応において先進的な対応をしている5つの大学(広島大学・名古屋市立大学・東京経済大学・立教大学・神戸学院大学)の取り組みも紹介されているので、相談窓口設置の参考にするとよいでしょう。
※参考:文部科学省委託調査資料『「大学教育改革の実態把握及び分析等 に関する調査研究」 ~大学におけるハラスメント対応の 現状と課題に関する調査研究~』
https://www.mext.go.jp/content/20200915-mxt_gaigakuc3-000009913_1.pdf
外部の専門機関と連携する
アカハラの相談員は、被害者からも加害者からも中立の立場でなければなりません。また学生だけではなく、教授やさまざまな雇用形態の職員からの相談もあるので幅広い知識と対応が必要です。
大学内に専門の相談員を常設するのが難しい場合は、外部の専門機関と連携しましょう。弁護士事務所やNPO法人と契約すれば、相談者は大学を介さずに直接専門家に相談ができるようになりますし、被害者と加害者双方に対して公平です。臨床心理士のようなメンタルヘルス専門のカウンセラーに、学内相談員のスーパーバイザーや学外相談員になってもらうのも一つの方法です。
大学と連携を取りながら解決まで導いてくれる組織も、数は多くないですが存在するので探してみてください。コールセンター会社にカウンセリングを外注する方法は、完全に問題が解決しないケースが多いので注意が必要です。
アカハラについて正しい理解を促す
アカハラに対して積極的に取り組んでいる大学には、ほとんどの場合アカハラに対するガイドラインがあり、アカハラについての正しい理解を促す努力をしています。アカハラに該当する可能性のある行為を具体例として示し、教職員や学生に周知しましょう。
ガイドラインには、大学のアカハラに対する基本姿勢やガイドラインの目的、ガイドラインの適用範囲(職員や学生など)、アカハラとは何かの説明と具体例、相談窓口や相談後のプロセスなどが記載します。
またガイドラインを作成しただけでなく、多くの人に知ってもらうことが重要です。紙面で提示するだけでなく、大学のHP上から閲覧できるようにすると多くの人に見てもらえます。
ナラティブアプローチを行う際のポイント

アカハラは起きてしまった際の対処方法だけでなく、起きにくい環境を整えることが大事です。アカハラの予防策について解説します。
アカハラ防止を積極的に呼びかける
アカハラに関するリーフレットやポスターを配布・掲示して、教職員や学生などのアカハラに対する関心を高めましょう。立場は違っても「お互いに平等な人間」なのだと、意識してもらうのが重要です。配布物に相談窓口を記載すれば、アカハラ相談窓口の認知度も上がります。
アカハラを受けた学生の多くは、まず身近な教職員に相談するケースが多いでしょう。教職員がアカハラ相談窓口の存在を知っていれば、学生をアカハラ相談窓口に誘導できます。アカハラ防止を積極的に呼びかけるなら、アカハラを行う可能性のある学内ヒエラルキーのトップ層や、相談を受けやすい教職員を対象にすると効果的です。
アカハラ防止対策に力を入れている大学のなかには、教職員に対して行う研修の一コマに、ハラスメント研修を取り入れているとこもあります。
定期的に現状を調査する
アカハラ防止対策に携わるなら、現状を知らなければなりません。アカハラに関するアンケートを定期的に実施すれば、現状把握が可能です。
アンケートの対象は、偏りがないように教員、常勤職員、非常勤職員、大学院生・研究生など幅広く行うとよいでしょう。匿名を可能にすれば、被害の報告も上げやすくなります。
また学生サポーターを募るのも、現状を把握する一つの方法です。年に数回学生サポーターやハラスメント相談員などがミーティングを行い、学内で見聞したアカハラについて報告を上げてもらいます。実際に取り入れている大学では、学生サポーターからの報告により、職員同士のアカハラが発覚したケースもあります。
相談窓口の設置やガイドラインでアカハラを防ごう

大学内は閉鎖的でヒエラルキーもあり、ハラスメントが起きやすい環境です。被害者を守るためにも、大学側はアカハラ防止対策をしなければなりません。
また訴訟により問題が顕在化してしまうと、加害者だけの問題にとどまらず、大学側も損害賠償を求められ大学のイメージも傷つきます。アカハラに対する認知を深め早期の段階でアカハラを発見するためにも、ガイドラインの策定や相談窓口の設置をしましょう。
学校側がまずはアカハラに対する積極的な姿勢を取り、アカハラの発生防止に向けた対策を取っていくことが重要です。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。