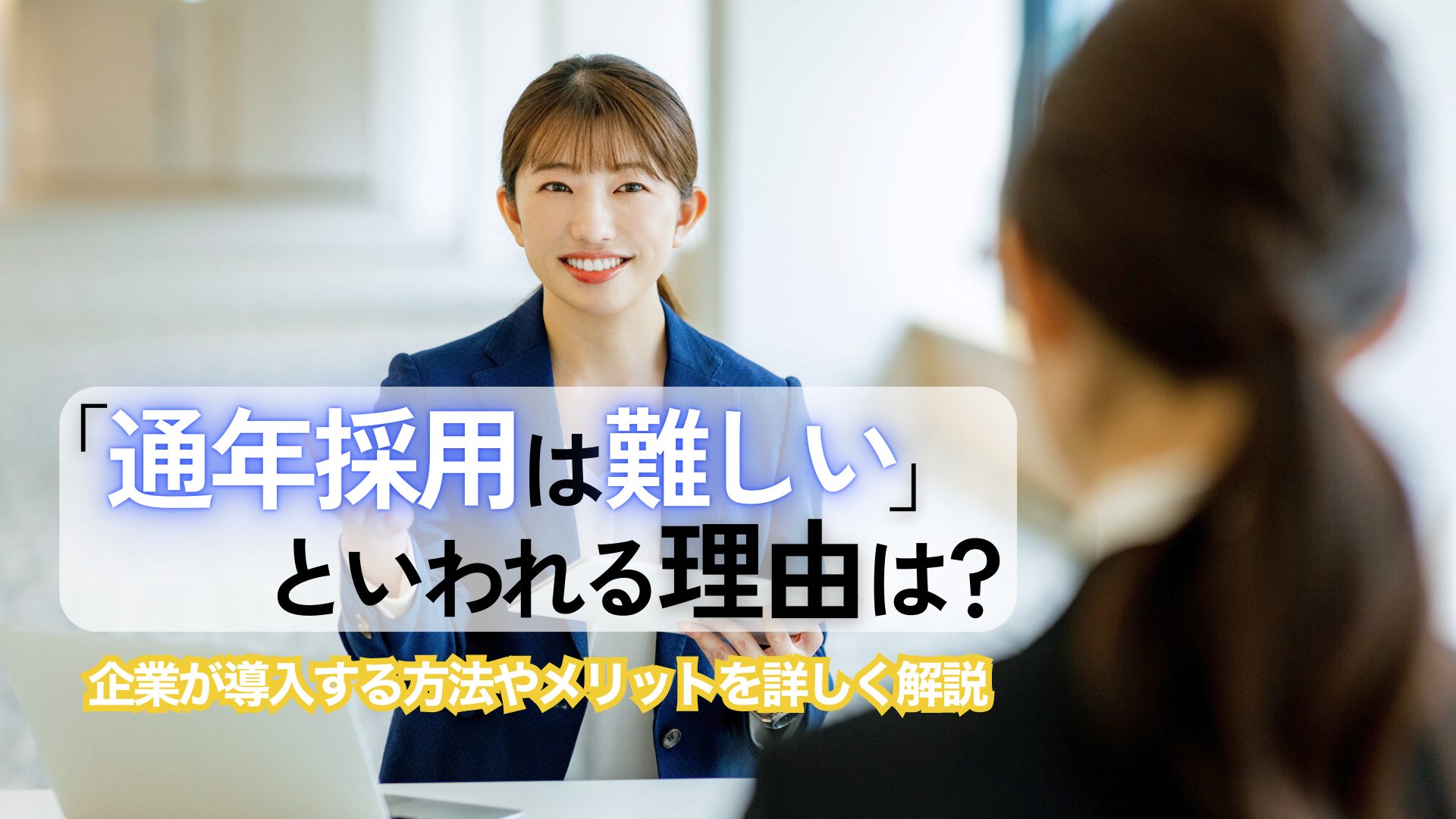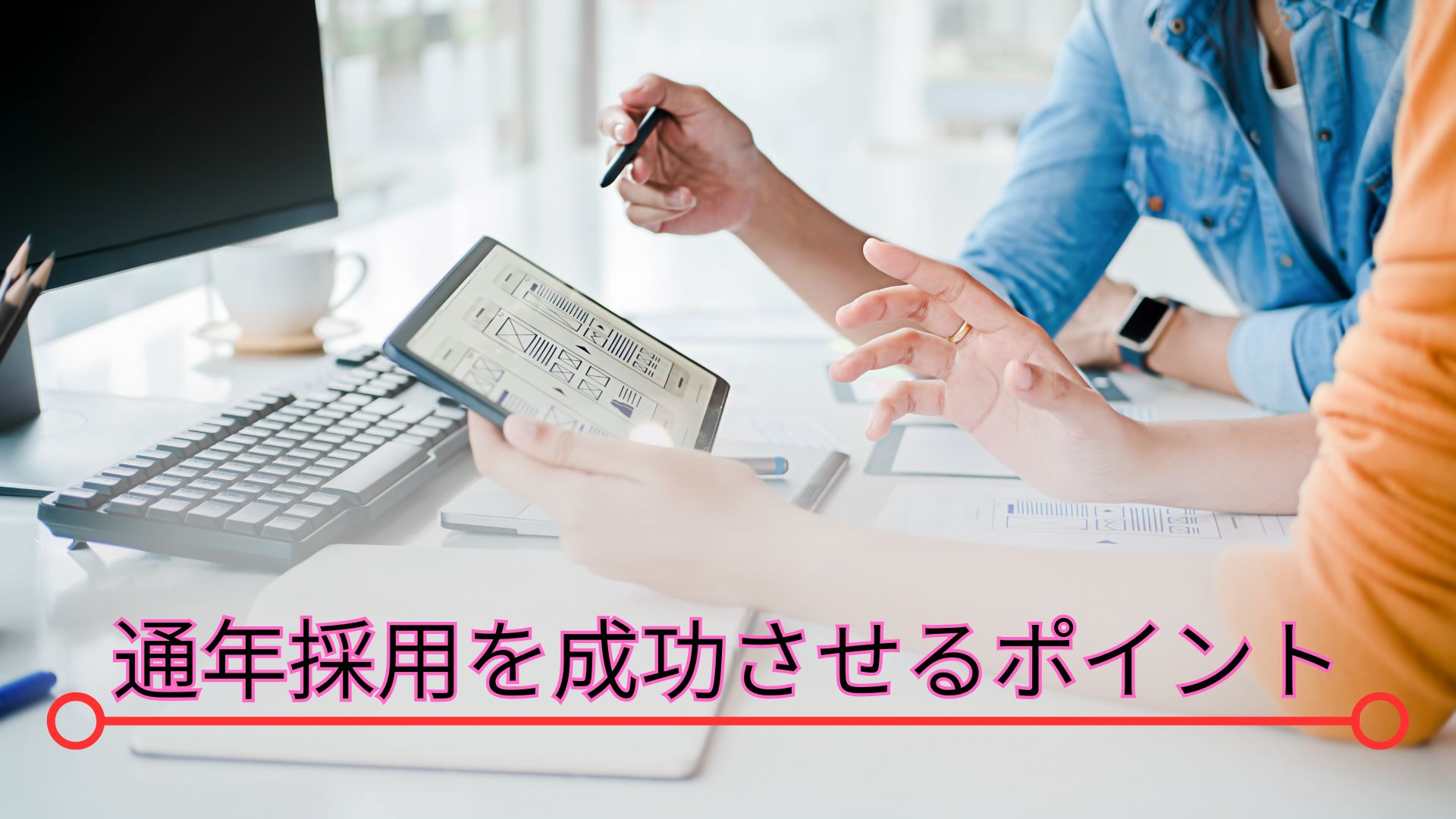
通年採用は、単に採用活動の期間を延ばすだけでは成功しません。
多様な人材を惹きつけ、確実に採用へと繋げるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、通年採用を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。
通年採用を成功させる3つのポイント
ポイント1:継続的な情報発信と、候補者との接点を保つ仕組み
通年採用を導入する上でまず重要なのが、継続的な情報発信と、候補者との接点を保つ仕組みづくりです。
新卒一括採用とは異なり、通年採用では企業の採用活動が「いつ行われているのか」が学生や求職者に伝わりにくいという側面があります。
そのため、自社の採用サイトやSNS、ダイレクトリクルーティングサービスなどを通じて、「現在、〇〇職を募集中です」といった具体的な情報を継続的に発信し続けることが不可欠です。
候補者がいつでも最新の採用情報にアクセスできる状態を作ることが、母集団形成の第一歩となります。
ポイント2:「選考プロセスの標準化」と「効率化」の両立
次に、年間を通じて安定した選考を行うための体制構築も欠かせません。
採用担当者が年間を通じて選考に対応する場合、面接官による評価のバラつきを防ぎ、常に一定の基準で候補者を判断するための「選考プロセスの標準化」が重要になります。
評価基準を明確にし、面接官トレーニングを行うなどの対策が有効です。
同時に、採用活動を効率化するツールの積極的な活用も求められます。
説明会や一次面接のオンライン化、Webテストの導入、採用管理システム(ATS)の活用など、テクノロジーの力を借りて担当者の負担を軽減し、候補者とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境を整えましょう。
ポイント3:内定承諾から入社までの「帰属意識」の醸成
最後に、内定者のフォロー体制も通年採用ならではの工夫が必要です。
通年採用では、内定を出してから実際に入社するまでの期間が、候補者によって数週間から1年以上と大きく異なります。
この期間、内定者の不安を解消し、入社意欲を維持・向上させることが重要です。
内定者懇親会や、社員との定期的な面談、オンラインでの研修コンテンツの提供など、帰属意識を高めるための丁寧なコミュニケーションを計画的に実行しましょう。
一人ひとりの入社時期に合わせたフォローが、入社後のスムーズな立ち上がりと定着に繋がります。
【企業タイプ別】通年採用は本当に『自社に』向いているのか?判断チェックリスト
通年採用は全ての企業にとって最適な手法とは限りません。
自社の事業フェーズや採用したい人材像によって、向き不向きがあります。
ここでは、企業タイプ別に通年採用への適性を判断するためのチェックリストをご紹介します。
【成長・拡大フェーズのベンチャー/スタートアップ向け】チェックリスト
事業の急成長に伴い、即戦力となる人材を常に求めているベンチャーやスタートアップにとって、通年採用は非常に有効な戦略です。
年間を通じて、常に採用したいポジションがある
専門スキルを持つ学生や、第二新卒・既卒者も積極的に採用したい
4月一括入社にこだわらず、一日でも早く入社してほしい
採用担当者がスカウト送付など、能動的な採用活動に時間を割ける
事業環境の変化が速く、常に新しい人材を求めている
→ 3つ以上当てはまるなら、通年採用が事業成長の鍵になる可能性大です。
【専門職・技術職の採用を行う中小企業向け】チェックリスト
専門的な知識やスキルを持つ人材の採用を狙う中小企業も、通年採用によってターゲット層と効率的に出会える可能性が高まります。
ターゲットとなる学生が所属する研究室や学部が明確だ
留学経験者や、大学院進学・公務員試験などと迷っている学生もターゲットになる
経営者や役員が、自社の魅力を直接学生に語る場を設けることができる
入社後の育成は、OJTを中心に柔軟に対応できる体制がある
一括採用の時期では、大手企業と採用競争になりやすい
→ 3つ以上当てはまるなら、通年採用で独自の採用戦略を築くことをおすすめします。
【多様な人材確保を目指す大手・中堅企業向け】チェックリスト
多様なバックグラウンドを持つ人材を確保し、組織のダイバーシティを推進したい大手・中堅企業にとって、通年採用は新たな可能性を開く鍵となります。
海外の大学を卒業する学生や、留学経験者を積極的に採用したい
既存の採用チャネルでは出会えない、尖った才能を持つ人材を発掘したい
入社時期の分散に対応できる、体系的な研修プログラムや部署がある
採用ブランディングに力を入れており、年間を通じて情報発信が可能だ
画一的な人材構成からの脱却や、組織の活性化が経営課題だ
→ 3つ以上当てはまるなら、通年採用が、企業の新たな成長エンジンとなる人材の獲得に繋がります。
通年採用に関するよくある質問
最後に、通年採用に関して企業の人事担当者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1.通年採用と秋採用・冬採用は何が違うのですか?
A.秋採用・冬採用は、主に「新卒一括採用の延長線上」で行われる採用活動を指します。
春の採用活動で採用目標人数に達しなかった企業が、採用枠を埋めるために継続するケースが一般的です。
一方、通年採用は、年間を通じた「計画的な採用活動」です。
時期によってターゲット(例:夏まではポテンシャル層、秋以降は専門スキルを持つ学生や留学経験者など)を戦略的に変え、継続的に母集団形成を行う点に大きな違いがあります。
Q2.採用コストは、新卒一括採用と比べてどうなりますか?
A.活動期間が長くなるため、求人広告費や合同説明会などのイベント出展費といった「外部コスト」は、新卒一括採用に比べて増加する傾向にあります。
一方で、企業の魅力を直接候補者に伝えるダイレクトリクルーティングや、社員の紹介によるリファラル採用などを積極的に活用し、ターゲットを絞って効率的にアプローチできれば、一人当たりの採用単価を抑えることも可能です。
採用チャネルの組み合わせ方がコストを最適化する鍵となります。
Q3.採用担当者の負担が大きくなりそうで心配です。
A.確かに、採用活動が長期化・恒常化するため、採用担当者の業務量は増加する可能性があります。
これが通年採用を導入する上での大きな懸念点の一つです。
この負担を軽減するためには、本記事の「通年採用を成功させるポイント」でも述べた通り、「選考プロセスの効率化」が不可欠です。
採用管理システム(ATS)の導入や、Web面接、動画面接などを活用し、ノンコア業務を自動化・効率化することで、担当者は候補者とのコミュニケーションといった本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。