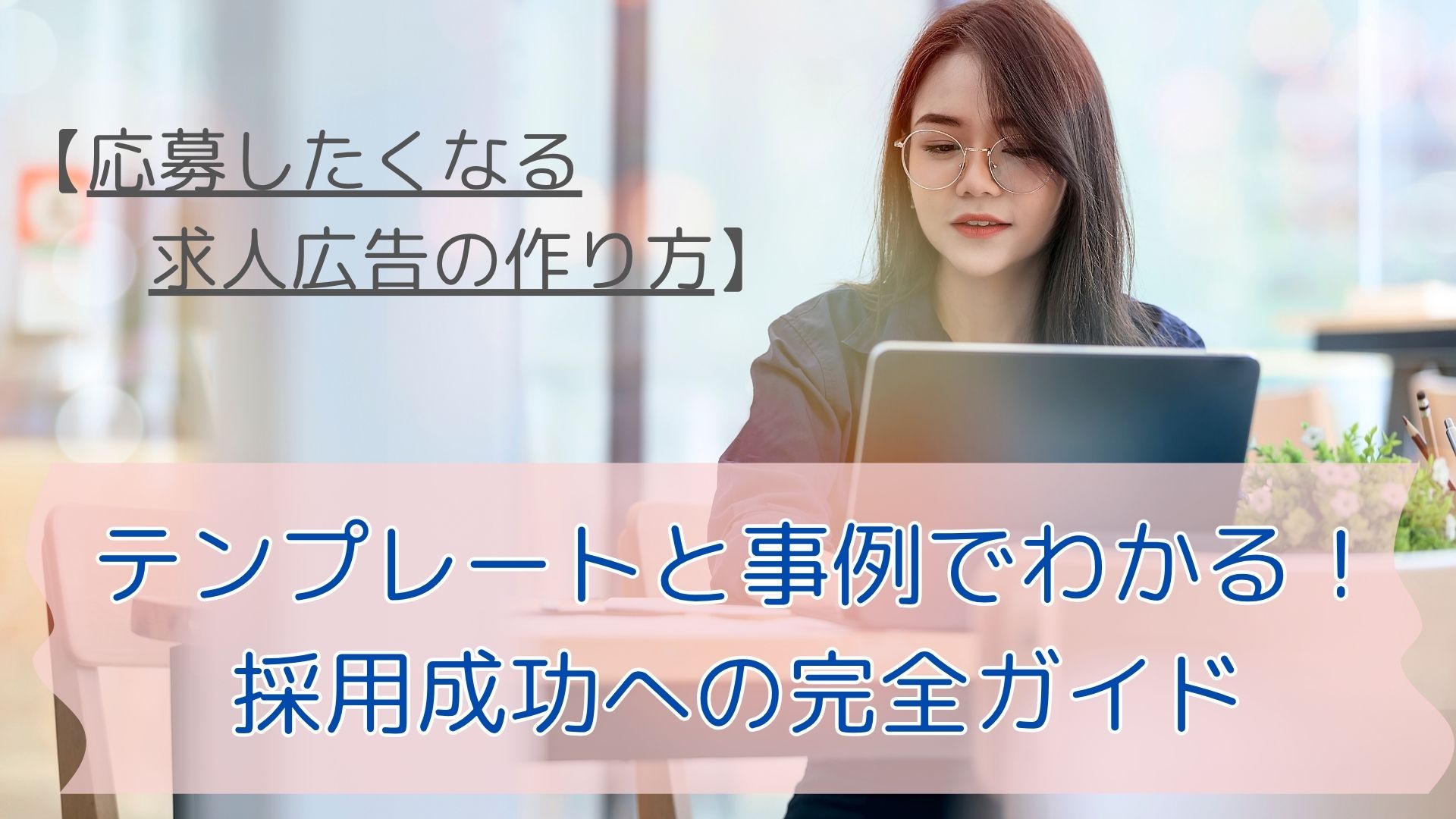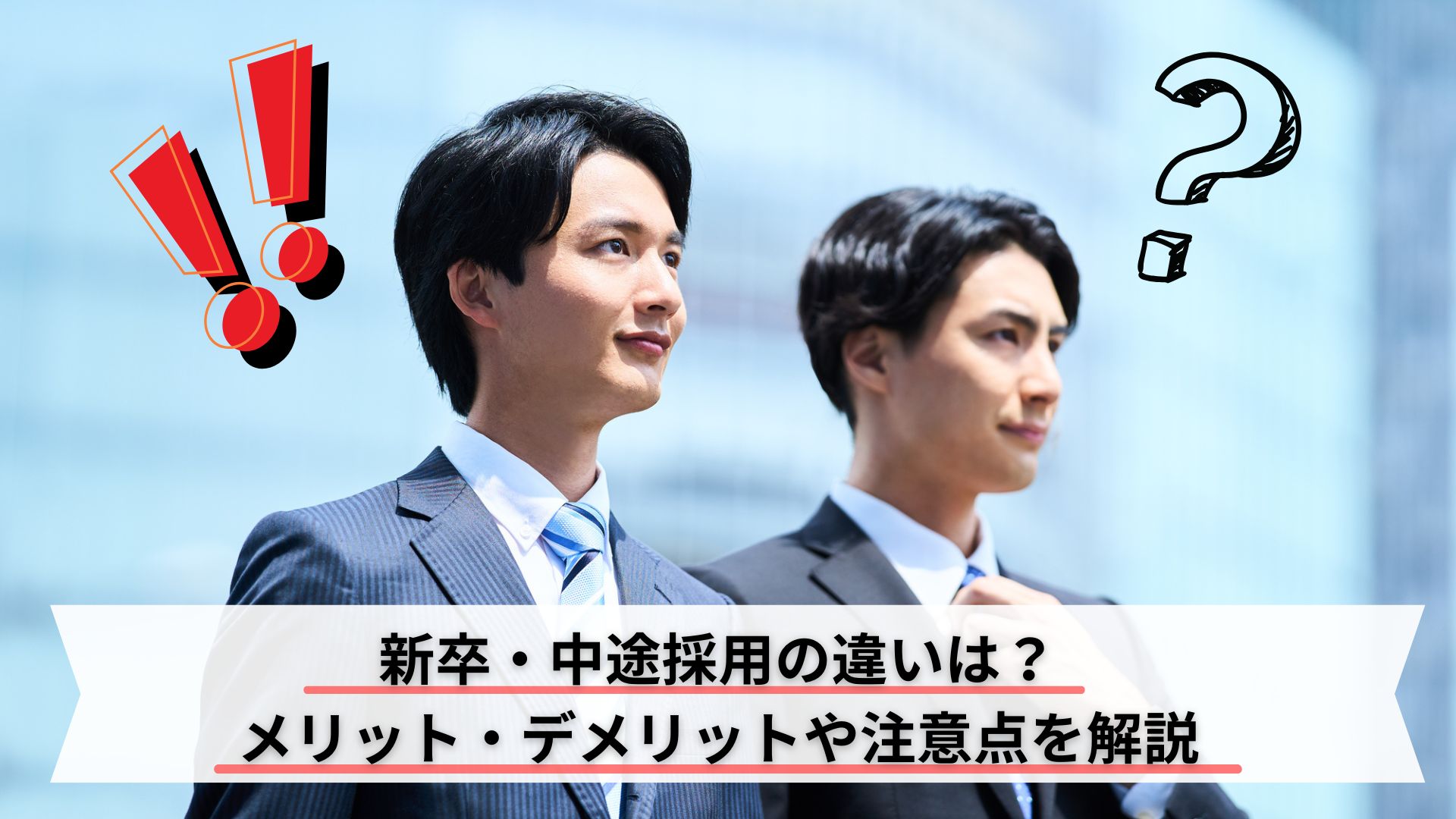「ダイレクトリクルーティングとスカウト採用、言葉は聞くけれど違いがよく分からない」「自社の採用活動にはどちらが適しているのだろうか」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
この二つの手法の最も大きな違いは、候補者一人ひとりへのアプローチの「深さ」と「個別最適化」の度合いにあります。
本記事では、ダイレクトリクルーティングとスカウト採用の基本的な定義から、それぞれのメリット・デメリット、そして自社の状況に合わせた最適な選び方までを、網羅的に解説します。
この記事を読み終える頃には、両者の違いを明確に理解し、自社の採用活動を成功に導くための具体的な戦略を描けるようになっているでしょう。
まずは両者の本質的な違いを理解し、採用戦略の第一歩を踏み出しましょう。
ダイレクトリクルーティングとスカウト採用の違い
ダイレクトリクルーティングとスカウト採用は、どちらも企業側から候補者へアプローチする「攻めの採用手法」ですが、その性質は大きく異なります。
ここでは、それぞれの定義と、両者を比較した際の違いについて具体的に解説します。
ダイレクトリクルーティングとは
ダイレクトリクルーティングとは、企業が自社の採用要件に合致する人材を主体的に探し出し、一人ひとりに対して個別に直接アプローチする採用手法です。
候補者の経歴やスキル、価値観などを深く理解した上で、なぜあなたに興味を持ったのかを伝えるパーソナライズされたメッセージを送るのが特徴です。
特に、高い専門性を持つ人材や、転職市場には現れにくい潜在層へのアプローチに強みを発揮します。
ダイレクトリクルーティングについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
スカウト採用とは
スカウト採用とは、あらかじめ設定した条件に合致する候補者群に対し、多くの場合、同一のテンプレート文面を用いて一斉にアプローチする採用手法です。
短期間で多くの候補者にアプローチできるため、効率的に応募の母集団を形成したい場合に適しています。
効率性を重視する企業や、複数名の採用を計画しているケースで広く利用されています。
ダイレクトリクルーティングとスカウトの違い
両者の違いは、アプローチの個別最適化の度合いに集約されます。ダイレクトリクルーティングが「一人ひとりへの手紙」だとすれば、スカウト採用は「ターゲット層への一斉案内」に近いと言えます。
この違いは、アプローチの精度、運用にかかる工数やコスト、候補者からの反応率、そして企業ブランディングへの影響など、多岐にわたる側面で具体的な差を生み出します。
ダイレクトリクルーティングのメリット
ダイレクトリクルーティングは、採用の「質」を極めて重視する手法です。
候補者と深く向き合うからこそ得られる、3つの大きなメリットについて解説します。
採用ミスマッチを防ぎやすい
採用担当者が候補者一人ひとりの経歴や価値観を深く理解した上でアプローチするため、企業の文化や求める人物像とのマッチング精度が非常に高くなります。
これにより、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを未然に防ぎ、長期的な活躍と定着率の向上に繋がります。
市場に出にくい優秀な人材に直接アプローチできる
転職を積極的に考えていない潜在層の中には、自社にとって必要不可欠な高い専門性を持つ人材や、他社で活躍しているキーパーソンが数多く存在します。
ダイレクトリクルーティングでは、そうした市場に出てきにくい優秀層に対し、「あなただからこそ声をかけた」という熱意ある個別メッセージでアプローチできます。
これにより、他社との差別化を図り、優秀層の獲得競争で優位に立てることが可能です。
候補者一人ひとりの入社意欲を高められる
パーソナライズされた特別なコミュニケーションを通じて、候補者は「自分は正当に評価されている」と感じ、企業に対して強い興味・関心を抱くようになります。
選考過程全体で丁寧なフォローを継続することで、候補者の入社意欲を最大限に引き出し、「この会社で働きたい」という気持ちを醸成する「口説き落とす」採用が実現できます。
ダイレクトリクルーティングのデメリット
多くのメリットがある一方で、ダイレクトリクルーティングには相応の工数とスキルが求められます。
導入を検討する上で理解しておくべき、3つのデメリットを解説します。
一人当たりにかかる採用工数が非常に大きい
候補者のリサーチから個別のメッセージ作成、その後の丁寧なコミュニケーションまで、一人ひとりに多くの時間と労力を要するのが最大のデメリットです。
採用担当者のリソースが限られている場合、アプローチできる人数が限定され、採用活動全体のスピードが遅くなる可能性があります。
採用担当者のスキルに成果が大きく左右される
候補者を見つけ出すサーチ能力、興味を引くメッセージを作成するライティング能力、候補者を惹きつけるコミュニケーション能力など、採用担当者個人のスキルに成果が大きく依存します。
そのため、採用活動が属人化しやすく、担当者が交代することで採用成果が大きく落ち込んでしまうリスクも考慮しなければなりません。
大量採用や急な欠員補充には不向き
一人ひとりと時間をかけて丁寧に関係を構築していく手法であるため、一度に多くの人材を採用したい場合や、急な欠員を迅速に補充したい場合には適していません。
あくまでも、特定の重要なポジションを充足させるための「質」を最優先した手法であると割り切ることが重要です。
スカウト採用のメリット
スカウト採用は、採用の「効率性」と「スピード」に強みを持つ手法です。
特に母集団形成のフェーズにおいて、大きなメリットをもたらします。
短期間で効率的に母集団を形成できる
指定した条件に合致する候補者群に対して、テンプレート化したメッセージを一括で送信できるため、短期間で非常に多くの人にアプローチできます。
これにより、応募の母集団を効率的に形成することが可能です。「まずは多くの候補者に会ってみたい」という採用活動の初期フェーズにおいて、非常に有効な手法と言えるでしょう。
採用担当者の工数を削減しやすい
メッセージの一括送信機能を活用したり、転職エージェントにスカウト業務を代行させたりすることで、採用担当者の工数を大幅に削減できる点も大きなメリットです。
採用担当者が面接や社内調整といった、よりコアな業務に集中したい場合に特に効果を発揮します。
スカウト採用のデメリット
効率的である反面、スカウト採用には個別アプローチではないことから生じるデメリットも存在します。
運用にあたって注意すべき3つのポイントを解説します。
候補者からの反応率が低くなりやすい
テンプレート化された一括送信メールは、他の多くの企業から送られてくるスカウトメールの中に埋もれてしまいがちです。
候補者から「自分宛ての特別なメッセージではない」と判断され、開封すらされないケースも少なくありません。結果として、送信数に対する返信率が低くなる傾向にあります。
志望度が低い候補者との面談が増える可能性がある
「とりあえず話だけ聞いてみよう」といった、志望度の低い候補者からの応募が増える可能性があります。
そのため、面談の数は確保できても、なかなか内定承諾に繋がらなかったり、面談の場で志望動機を高めるのに苦労したりするケースが見られます。
ミスマッチが起こるリスクがある
アプローチの網を広げる分、自社のカルチャーや詳細な求める人物像とは必ずしも合致しない候補者からの応募も一定数発生します。
もちろん選考プロセスで丁寧に見極める必要はありますが、個別アプローチのダイレクトリクルーティングに比べると、ミスマッチのリスクは高まる傾向にあると言えるでしょう。
ダイレクトリクルーティングとスカウトの戦略的な使い分け方・選び方
これまで見てきたように、両者には明確な特性の違いがあります。
どちらか一方が優れているというわけではなく、自社の採用課題や状況に応じて戦略的に使い分けること、あるいは組み合わせることが採用成功の鍵を握ります。
ここでは、自社に最適な手法を見極めるための、具体的な4つの判断軸を掘り下げて解説します。
選び方① 採用ポジションの「重要度」と「人数」で判断する
まず考えるべきは、「どのようなポジションを、何人採用したいのか」という採用計画の根幹です。ポジションの事業へのインパクトや専門性によって、最適なアプローチは大きく異なります。
- ダイレクトリクルーティングが適しているケース
- 対象
経営幹部、事業部長、CTO、研究開発のリーダーなど、事業の根幹を担うキーパーソン(1人の採用が事業に大きな影響を与えるポジション) - 理由
候補者一人ひとりの価値観やビジョンを深く理解し、口説き落とすような丁寧なコミュニケーションが不可欠なため。時間をかけてでも、最高の1人を見つけ出すことに価値がある。
- 対象
- スカウト採用が適しているケース
- 対象
営業職、カスタマーサポート、マーケティング担当など、複数名の採用を計画している職種 - 理由
まずは一定数の母集団を形成し、その中から有望な人材を見つけ出すというプロセスが効率的。スピード感を持って採用活動を進めたい場合に有効。
- 対象
選び方② 社内の「リソース(人・スキル・コスト)」で決める
次に、自社の採用体制を客観的に評価することが重要です。理想的な手法であっても、運用できる体制がなければ絵に描いた餅になってしまいます。
- ダイレクトリクルーティングの運用に必要なもの
- 人・スキル
候補者を見つけ出すサーチ能力、魅力的なスカウト文面を作成するライティング能力、候補者と関係を構築するコミュニケーション能力を高いレベルで備えた採用担当者。 - コスト
主に採用担当者の人件費(時間コスト)。成果が出るまで時間がかかることも見越した上でのリソース投下が必要。
- 人・スキル
- スカウト採用の運用に必要なもの
- 人・スキル
媒体の選定や基本的な運用スキル。外部エージェントに委託する場合は、エージェントとの連携や進捗管理能力が求められる。 - コスト
媒体のシステム利用料や、転職エージェントへの成功報酬といった外部コスト。予算計画が立てやすい側面も。
- 人・スキル
選び方③ ターゲット人材の「希少性」と「転職意欲」で見極める
アプローチしたい人材が、転職市場にどれくらい存在し、どの程度活発に動いているのか、という視点も不可欠です。
- ダイレクトリクルーティングが有効なターゲット
- 特徴
特定の技術を持つトップエンジニア、競合他社で活躍するキーパーソンなど、市場に数少なく、転職意欲も高くない「潜在層」。 - 戦略
今すぐの転職を前提とせず、まずは情報交換から始めるなど、中長期的な視点で関係性を構築(タレントプーリング)し、最適なタイミングでアプローチする戦略が求められる。
- 特徴
- スカウト採用が有効なターゲット
- 特徴
転職サイトに登録しており、良い企業があれば話を聞きたいと考えている「顕在層〜準顕在層」。 - 戦略
多くの企業がアプローチする中で、自社に興味を持ってもらうための工夫が必要。迅速なレスポンスや、他社とは違う魅力(具体的な仕事内容、働きがいなど)を簡潔に伝えることが重要。
- 特徴
選び方④ 企業の「採用フェーズ」と「ブランド力」を考慮する
企業の成長段階や、世間的な知名度も、手法選択に影響を与えます。
- ダイレクトリクルーティングを積極的に活用すべき企業
- 特徴
創業期のスタートアップや、知名度は低いが独自の魅力を持つ中小企業。 - 理由
企業の知名度に頼れない分、経営者や社員が自らの言葉でビジョンや事業の魅力を熱く語ることで、候補者の心を動かすことができる。パーソナルなアプローチが、ブランド力の差を埋める武器になる。
- 特徴
- スカウト採用も有効に機能する企業
- 特徴
既に一定の知名度やブランド力がある大手・中堅企業。 - 理由
企業名だけで一定の信頼性を得られるため、スカウトメールの開封率や返信率も比較的高く、効率的に母集団を形成しやすい。
- 特徴
ダイレクトリクルーティング/スカウトの実践事例
他社がどのようにこれらの手法を活用し、どのような成果を上げているのかを知ることは、自社の戦略を練る上で非常に参考になります。
ここでは、3つの異なるケースでの実践事例を紹介します。
事例①:「待ち」から「攻め」の採用へ転換し、理系若手人材の獲得に成功した事例
理化学機器メーカーである柴田科学株式会社は、従来の大手ナビサイトを中心とした「待ちの採用」に限界を感じ、特に難易度の高い機電系理系学生の母集団形成に苦戦していました。
そこで、ダイレクトリクルーティングによる「攻めの採用」へ転換するため「Re就活」「Re就活キャンパス」の利用を開始しました。
スカウト機能を活用し、ターゲット学生へ直接アプローチすることで、エントリーの約半数をスカウト経由で獲得し、質の高い母集団形成に成功しました。結果として、理系出身者4人を含む5人の新卒・第二新卒採用を実現しました。
当初は採用担当者の工数負担を懸念していましたが、学情の専門の担当者が希望に沿った内容でスカウトメールの配信等の作業を行いました。
これにより、想像以上に負担がなく学生と向き合う時間に集中することができたことも成功の要因となりました。
事例②:中小企業が自社とマッチする母集団形成に成功した事例
商社のイカリ建商株式会社は、大手ナビサイトでは自社が埋もれてしまい、十分な母集団を形成できないという課題を抱えていました。
そこで、中堅・中小企業を志望する学生が多い「Re就活キャンパス」の利用を強化しました。
スカウトメールに加え、職場の雰囲気を伝える動画コンテンツ「JobTube」も活用し、自社の魅力を多角的にPRしました。
その結果、これまでより質の高い、自社とマッチング度の高い学生の母集団形成に成功し、採用予定数のほぼ全てを同サイト経由で採用することができました。
事例③:カルチャーフィットを重視し、事業拡大の核となる経験者採用に成功した事例
メディア・広告事業を手がける株式会社サクラアルカスは、新規事業部を牽引できる即戦力人材の採用を目指していました。
求める経験やスキルに加え、「カルチャーフィット」を最重要視していたため、ピンポイントでの人材探索が課題でした。
そこで、履歴書を見ながら主体的に人材を探せる成果報酬型のダイレクトリクルーティングサービス「Re就活30」を導入しました。
コストを抑えつつ、攻めたい領域の経験者であり、かつコミュニケーション能力の高い理想的な人材1人の採用に成功しました。採用担当者自らが主体的に動くことで、求める人物像がより明確になったことも大きな収穫でした。
ダイレクトリクルーティングとスカウトの違いに関するよくある質問
ここでは、採用担当者の方から寄せられることの多い、両者の違いに関する質問とその回答をまとめました。
Q1.結局、どちらの手法を使えばいいですか?
A1.採用の「目的」と「人数」によって使い分けるのがおすすめです。
- ダイレクトリクルーティングがおすすめの企業
経営幹部や専門職など、替えの効かない特定の人材を1〜2人、じっくり時間をかけて採用したい場合。
- スカウト採用がおすすめの企業
営業職など複数名の採用枠を充足させるため、短期間で多くの候補者と会い、母集団を形成したい場合。
Q2.ダイレクトリクルーティングとスカウト、コストが高いのはどちらですか?
A2.一概には言えませんが、一人当たりの採用単価は「スカウト採用」の方が低くなる傾向にあります。ただし、コストのかかり方が異なります。
- ダイレクトリクルーティング
主に採用担当者の「人件費(時間コスト)」が大きくかかります。
- スカウト採用
媒体の「システム利用料」や、転職エージェントへの「成功報酬」などがかかります。
「質」を追求して時間コストをかけるのがダイレクトリクルーティング、「量」を求めてシステムや外部サービスに費用をかけるのがスカウト採用と捉えると分かりやすいでしょう。
Q3.スタートアップや中小企業でもダイレクトリクルーティングは可能ですか?
A3.はい、むしろ非常に有効な手法です。
企業の知名度では大手に劣る場合でも、候補者一人ひとりに自社のビジョンや事業の魅力を直接、熱意をもって伝えられます。
経営者自らがメッセージを送るなど、企業の「顔」が見えるアプローチは、候補者の心を動かす強力な武器になります。
Q4.返信率を高めるスカウトメールのコツはありますか?
A4.スカウト採用で一括送信する場合でも、少しの工夫で返信率は改善できます。
- 件名に候補者の名前を入れる
- 文頭で「なぜあなたに連絡したのか」を簡潔に伝える
- 「まずはカジュアル面談で話しませんか」と提案し、応募へのハードルを下げる
Q5.採用担当者が1人しかいません。どちらの手法が向いていますか?
A5.状況によりますが、「スカウト採用」から始めるのが現実的かもしれません。
まずはスカウト採用で母集団を形成しつつ、その中で特に魅力的な候補者が見つかった場合に、個別フォローを手厚くする(=ダイレクトリクルーティングに切り替える)というハイブリッドな進め方がおすすめです。
Q6.両方の手法を併用することはできますか?
A6.はい、併用することで採用力を最大化できます。
例えば、営業職や若手層は「スカウト採用」で、マネージャー層やエンジニアリーダーは「ダイレクトリクルーティング」で、というように採用ポジションの重要度や緊急性に応じて手法を使い分けることで、効率的かつ戦略的な採用活動が実現できます。
まとめ
本記事では、ダイレクトリクルーティングとスカウト採用の違いについて、定義からメリット・デメリット、選び方までを解説しました。
ダイレクトリクルーティングは「質」を重視し、候補者一人ひとりと深く向き合う手法である一方、スカウト採用は「量」と「効率」を重視し、スピーディーに母集団を形成する手法です。
両者の特性を正しく理解し、自社の採用課題や目的に合わせて最適な手法を選択、あるいは組み合わせることが、採用成功への最短ルートとなります。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。