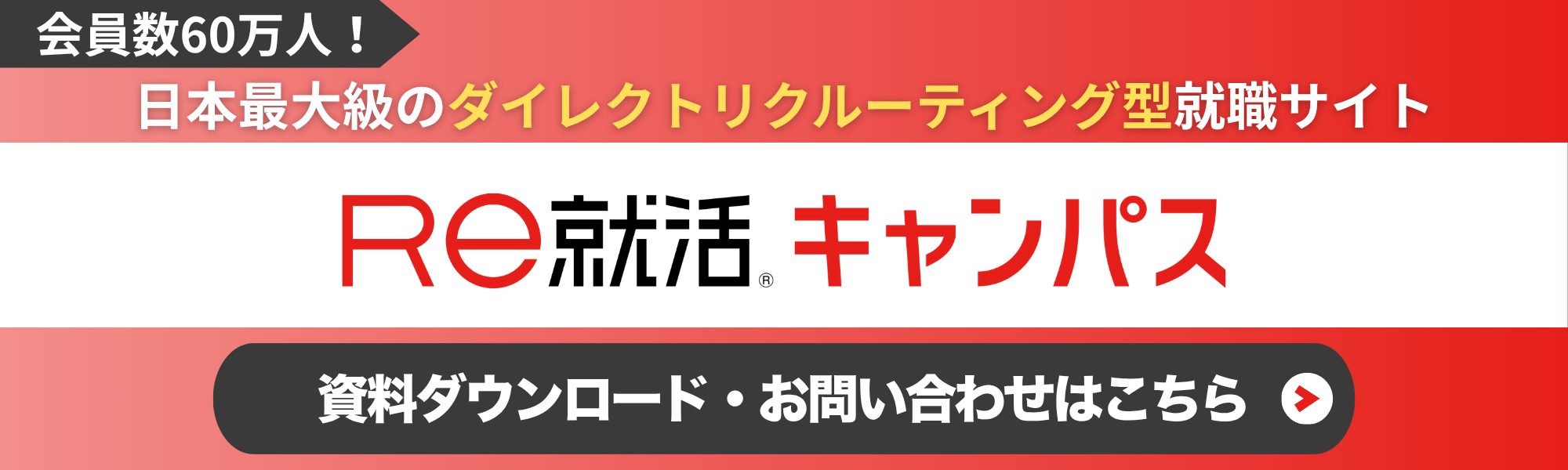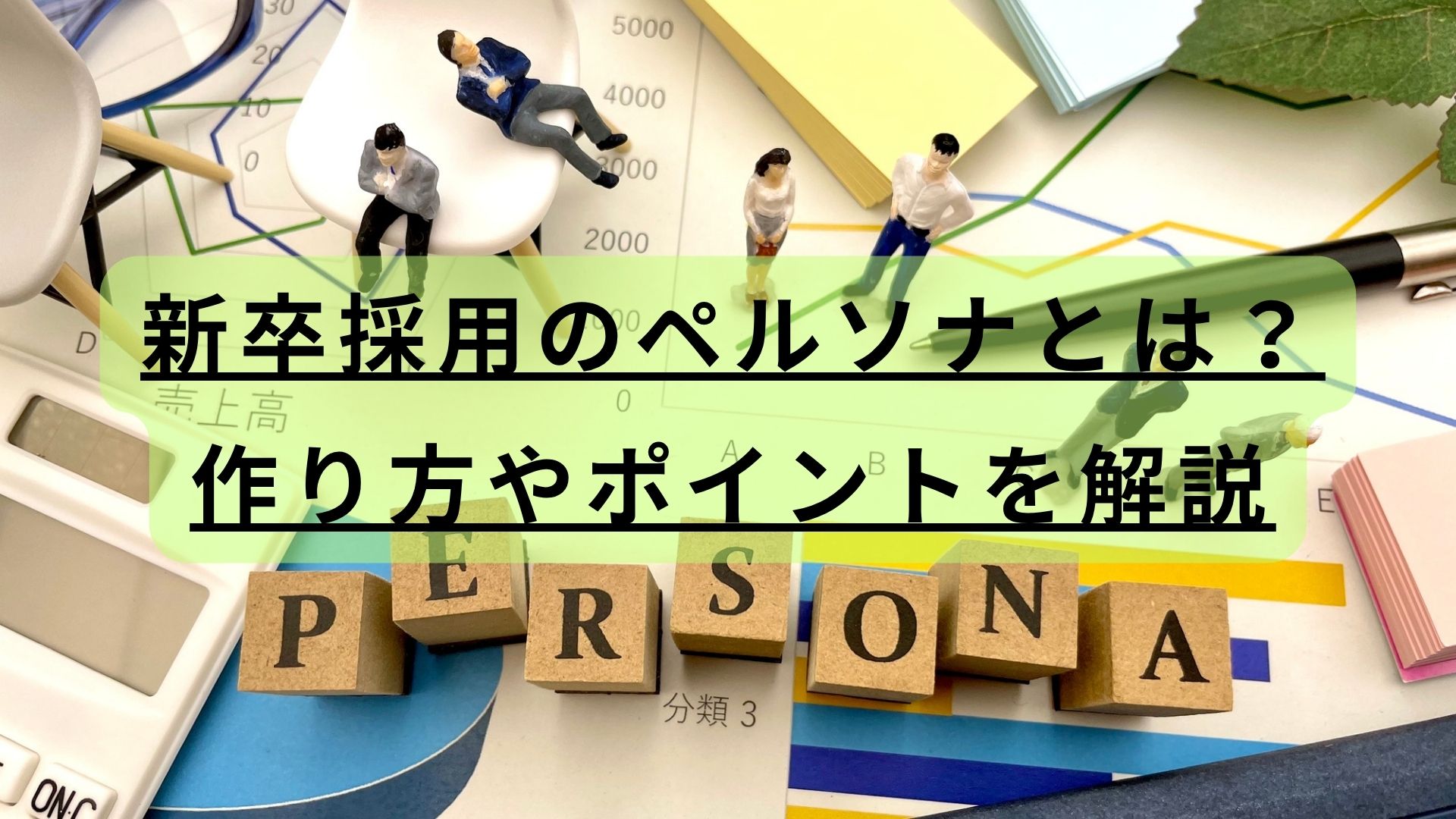「自社の新卒採用の割合は適正なのだろうか」「他社は新卒と中途をどのようなバランスで採用しているのだろうか」とお悩みの採用担当者様も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、全ての企業に共通する「最適な割合」は存在しません。しかし、客観的なデータやフレームワークを用いることで、自社の事業戦略に合致した最適な採用比率を導き出すことは可能です。
本記事では、2025年の最新データを基にした国内の新卒採用の動向から、企業規模・業界別の採用割合、そして自社に最適な採用ポートフォリオを策定するための具体的なステップまでを網羅的に解説します。
この記事を最後までお読みいただくことで、データに基づいた客観的な視点から自社の採用戦略を見つめ直し、自信を持って人員計画を推進できるようになるでしょう。
ぜひ、貴社の持続的な成長に向けた採用戦略の策定にお役立てください。
そもそも「新卒採用の割合」とは?3つの視点と重要性
一言で「新卒採用の割合」と言っても、どの数値を基準にするかでその意味は大きく異なります。
採用戦略について、しっかり考えるため、まずは言葉の定義を明確にし、なぜ新卒採用の割合が経営において重要視されるのかを解説します。
「新卒採用の割合」3つの定義
「新卒採用の割合」を考える際には、主に以下の3つの指標が用いられます。それぞれが示す意味を正しく理解し、自社の状況に合わせて使い分けることが重要です。
- 採用計画に占める新卒の比率
当該年度の全採用計画人数のうち、新卒採用者が占める割合です。企業の採用方針が新卒重視か、キャリア重視かを最も端的に示します。 - 実際の採用者に占める新卒の比率
採用活動が終了した時点で、実際に入社が決定した全採用者のうち、新卒が占める割合です。採用市場の動向や選考の難易度によって、計画との乖離が生まれることもあります。 - 全正社員に占める新卒入社者の構成比
在籍している全正社員のうち、新卒で入社した社員が占める割合です。組織の年齢構成やカルチャー、人材の定着率を反映する指標と言えます。
なぜ新卒採用の割合が重要なのか
新卒採用の割合は、単なる採用活動の指標にとどまりません。それは、組織の未来を創るための経営戦略そのものと深く結びついています。
例えば、この割合は組織の持続的な成長に不可欠な人材パイプラインの構築、企業文化の醸成と継承、そして人員構成の最適化といった重要な役割を担っています。
適切なバランスを維持することが、組織の活力を保ち、将来のリーダーを育む土壌となるのです。
【2025年最新】データで見る日本の新卒採用のリアル
自社の採用戦略を考える上で、まずは市場全体の動向を客観的なデータで把握することが不可欠です。
ここでは最新の調査結果を基に、現在の日本の新卒採用市場の実態を解き明かし、自社の立ち位置を把握するための情報を提供します。
企業の採用計画:新卒と中途どちらが優勢?
2025年度の採用市場では、中途採用への意欲が新卒採用を上回る傾向が見られます。
帝国データバンクの調査によれば、中途採用を予定している企業が51.0%であるのに対し、新卒採用を予定している企業は37.1%に留まりました。
また、キャリア採用と新卒採用の比率を『5:5』と回答した企業が、全体の約4社に1社と最も多く、即戦力となるキャリア人材への期待が高いことが伺えます。
特に20代後半の若手層を増員する動きが活発化しており、新卒採用市場においても優秀な人材の獲得競争が激化しています。
※出典:帝国データバンク「2025年度の雇用動向に関する企業の意識調査」
株式会社学情「2025年卒採用・2026年卒採用の意向」
採用の難易度:計画通りに採用できているか?
多くの企業が新卒採用の計画達成に苦戦しているのが現状です。
2025年卒の新卒採用における充足率(採用計画に対する実績)は70.0%と、過去最低水準に落ち込んでいます。
この背景には、生産年齢人口の減少と、学生優位の「売り手市場」が継続していることがあります。
企業は採用計画の見直しだけでなく、採用手法そのものの抜本的な改革を迫られています。
※出典:株式会社マイナビ「マイナビ 2025年卒 企業新卒採用活動調査」
学生の動き:求人倍率と内定率のトレンド
学生優位の市場環境は、各種データからも明らかです。2026年卒の大学生・大学院生対象の大卒求人倍率は依然として高い水準で推移しており、学生にとっては選択肢の多い状況が続いています。
このような状況を受け、企業側は初任給の引き上げや待遇改善に踏み切るケースが増加しています。
学生の企業選びの軸も多様化しており、企業はこれまで以上に自社の魅力を明確に伝え、学生一人ひとりに寄り添ったコミュニケーションが求められています。
【企業規模・業界別】他社の新卒採用割合は?
市場全体の動向を掴んだ次は、より自社に近い立ち位置の企業、つまり同規模や同業界の他社がどのような採用戦略をとっているのかを見ていきましょう。
他社との比較を通じて、自社の採用戦略を相対的に評価するためのヒントが得られます。
企業規模で見る新卒採用への注力度の違い
企業規模によって、新卒採用に対する考え方や注力度は大きく異なります。
2025年度は全体の72.5%の企業が正社員の採用予定があると回答しており、人材獲得への意欲は依然として高い状況です。
その上で、企業規模別の戦略の違いを理解することが重要です。
大企業では、潤沢な経営資源を背景に、長期的な人材育成と組織の安定性を重視し、定期的な新卒一括採用が主流です。
将来の幹部候補を内部で育成するパイプラインとして、新卒採用を戦略的に位置付けています。
一方、中小企業に目を向けると、2025年度に中途採用を予定している企業が47.0%であるのに対し、新卒採用を予定しているのは30.8%に留まります。
これは、多くの中小企業が将来への投資として新卒採用の重要性を認識しつつも、限られたリソースの中で事業を推進するため、足元の事業運営においては即戦力となる中途採用を優先せざるを得ないという実情を反映しています。
※出典:帝国データバンク「2025年度の雇用動向に関する企業の意識調査」
業界ごとの新卒採用割合の傾向
業界の特性やビジネスモデル、そして抱える課題も、新卒採用の割合に大きく影響します。
自社の属する業界の動向を深く理解し、自社の戦略に活かしましょう。
- IT・情報通信業
技術革新のスピードが速く、常に新しい技術や発想が求められるため、柔軟な思考を持つ若手人材への需要が非常に高い業界です。そのため、新卒採用に積極的な企業が多く、ポテンシャルを重視した採用が活発に行われています。
- 製造業・建設業
専門的な技術やノウハウの継承が経営の重要課題となっています。ベテラン層の高齢化が進む中、長期的な視点で技術者を育成する必要があるため、安定的に新卒採用を行う企業が多いのが特徴です。
- 金融・保険業
伝統的に大規模な新卒一括採用を行ってきた業界です。入社後の手厚い研修制度を通じて一人前のプロフェッショナルに育てる文化が根付いており、総合職としてのポテンシャルを持つ人材を新卒で確保する傾向が強いです。
- 運輸・倉庫業
いわゆる「2024年問題」に直面し、労働力不足が深刻な課題となっています。将来の担い手を確保するため、若手人材である新卒者の採用意欲が非常に高い傾向にあります。
- サービス・小売業
店舗運営などを支える人材を安定的に確保する必要があるため、毎年一定数の新卒採用を行う企業が多いです。
一方で、人材の流動性も高いことから、新卒採用と並行して中途採用も積極的に行い、人員構成のバランスを取る傾向が見られます。
新卒 vs 中途、最適な採用バランスの考え方
新卒採用と中途採用は、どちらか一方が優れているというものではなく、それぞれに固有のメリットとデメリットが存在します。
ここでは、両者の特性を比較し、自社の事業フェーズや組織課題に応じた最適な採用バランスを見つけるための戦略的な視点を提供します。
新卒採用のメリット・デメリット
新卒採用の最大のメリットは、企業文化や価値観をゼロから浸透させやすい点にあります。また、長期的な視点での計画的な人材育成が可能であり、将来のリーダー候補を内部で育てることができます。
一方で、育成には相応のコストと時間がかかる点がデメリットです。研修制度の整備や現場のOJT担当者の負担も考慮する必要があり、入社後すぐに即戦力として活躍することは難しいでしょう。
中途採用のメリット・デメリット
中途採用の魅力は、何と言っても即戦力の確保にあります。教育コストを抑えつつ、事業拡大や新規プロジェクトに迅速に対応できる人材を獲得できます。
しかし、前職の企業文化が根付いているため、自社のカルチャーに馴染むかどうかの「カルチャーフィット」にはリスクが伴います。また、専門性や経験に応じて人件費が高くなる傾向がある点も考慮が必要です。
【事業フェーズ別】自社に合った採用ポートフォリオの作り方
最適な採用バランスは、企業の置かれた状況によって常に変化します。自社の事業フェーズを客観的に見極め、戦略的に採用ポートフォリオを設計することが重要です。
- 創業期・成長初期
事業の立ち上げや急成長を支えるため、特定分野の高い専門性や即戦力性が最優先されます。このフェーズでは、新卒1:中途9のように中途採用の比率を高く設定し、事業の基盤を迅速に固める戦略が有効です。
- 成長後期・拡大期
事業が軌道に乗り、組織が拡大していくフェーズです。即戦力となる中途採用で事業成長を加速させつつ、将来の組織の中核を担う人材を育成する必要が出てきます。
新卒採用の割合を徐々に増やし(例:新卒3:中途7)、持続的な組織成長に向けた土台づくりを進めます。
- 成熟期・安定期
事業が安定し、市場での地位も確立されたフェーズです。組織文化の継承や、次世代リーダーの計画的な育成が重要課題となります。
新卒採用の比率を高く(例:新卒7:中途3)し、組織の安定性と長期的な発展を目指します。中途採用は、新規事業や専門性が特に求められるポジションに限定するなど、戦略的に活用します。
- 変革期・再成長期
既存事業の停滞や市場の変化に対応し、新たな成長を目指すフェーズです。組織に新しい風を吹き込み、変革をドライブする人材が不可欠となります。
再び中途採用の比率を高め(例:新卒4:中途6)、外部からの新しい知見やスキルを積極的に取り入れ、組織の再活性化を図ります。
自社の適正な新卒採用割合の具体的な決め方
採用戦略の方向性が定まったら、次は具体的な採用人数に落とし込んでいきましょう。
ここでは、実務的な観点から適正な新卒採用割合を算出するための目安と、割合の偏りがもたらす潜在的なリスクについて解説します。
採用人数の実務的な目安
一般的に、新卒の採用人数は「従業員100人あたり3〜5人」が一つの目安とされています。例えば、従業員数が1,000人の企業であれば、年間の新卒採用人数は30人〜50人程度が目安となります。
ただし、これはあくまで初期的な参考値に過ぎません。より自社の実態に即した人数を算出するには、現従業員の年齢構成や平均離職率を考慮に入れることが不可欠です。
新卒採用割合が高すぎる/低すぎる場合のリスク
採用割合のバランスが崩れると、組織に歪みが生じる可能性があります。新卒採用の割合が高すぎると、教育コストの増大や育成担当者の疲弊を招き、結果的に一人ひとりの成長が阻害される恐れがあります。
逆に、割合が低すぎると、数年後に組織の高齢化やリーダー候補の不足といった問題に直面します。企業文化の継承が途絶え、組織の活力が失われるリスクも高まるでしょう。
自社の新卒採用割合を見直すための具体的な3ステップ
最後に、本記事の内容を踏まえ、明日から自社の採用戦略を見直すために行動できる具体的なアクションプランを3つのステップでご紹介します。
このステップに沿って、自社の採用活動を最適化していきましょう。
Step1:現状分析-自社の「今」をデータで客観視する
まずは、自社の現状を正確かつ客観的に把握することから始めます。感覚的な議論を避け、具体的なデータに基づいた分析が、精度の高い戦略策定の第一歩となります。
- 定量的分析
- 人員構成の可視化
全従業員の年齢・勤続年数・役職・所属部署などをデータ化し、年齢構成ピラミッドや各種グラフを作成します。これにより、特定の年代層の偏りや将来の空洞化リスクなどを洗い出します。
- 人員構成の可視化
-
- 離職率の分析
過去3〜5年間の新卒・中途別の離職率を算出します。特に入社3年以内の早期離職率が高い場合は、採用のミスマッチや受け入れ体制に課題がある可能性を深掘りする必要があります。
- 離職率の分析
-
- 事業計画との接続
中期経営計画や各部門の事業計画を確認し、3〜5年後に必要となる人員の数とスキル要件を整理します。
- 事業計画との接続
- 定性的分析
- 現場へのヒアリング
各部門の責任者や若手・中堅社員にヒアリングを行い、人員の過不足感、育成の課題、組織文化で感じていることなどを収集します。
- 現場へのヒアリング
-
- 退職者データの活用
可能であれば、退職時のアンケートや面談記録を分析し、退職理由の傾向を掴みます。
- 退職者データの活用
Step2:目標設定-3〜5年後の「あるべき姿」から逆算する
次に、現状分析の結果と、企業として目指す将来像を基に、具体的で測定可能な採用目標を設定します。
- 理想の人員構成の定義
5年後の事業計画を達成するために、どのような年齢構成、スキル構成の組織が理想かを定義します。
例えば、「技術継承のため、20代の技術職の割合を現在の15%から25%に引き上げる」「新規事業のために、デジタルマーケティングの知見を持つ中途人材を10人増員する」といった具体的な目標を設定します。
- 採用人数の算出
理想の人員構成と現状のギャップ、そして予測される自然減(定年退職や通常の離職)を考慮し、今後数年間で採用すべき新卒・中途の具体的な人数を算出します。
ここから、当該年度の採用計画における新卒と中途の最適な「割合」が導き出されます。
- 定性的な目標の設定
採用人数だけでなく、「多様な価値観を取り入れるため、女性管理職比率向上に繋がる採用を目指す」「グローバル展開のため、外国籍人材の採用を強化する」といった定性的な目標も併せて設定することが重要です。
Step3:採用計画の最適化-目標達成のためのアクションプランを練る
目標となる採用人数と割合が決まったら、それを達成するための具体的な施策へと落とし込み、実行(採用)計画を作成します。
- 母集団形成の戦略見直し
- ターゲット設定
設定した採用目標に基づき、どのような経験、スキル、価値観を持つ人材にアプローチすべきかを明確にします(ペルソナ設計)。 - チャネル選定
ターゲット人材に最も効果的にアプローチできる採用チャネル(求人媒体、ダイレクトリクルーティング、エージェント、リファラル採用など)を選定し、予算を配分します。
- ターゲット設定
- 選考プロセスの改善
- 魅力付け(アトラクト)
自社のビジョンや働きがい、キャリアパスなどを候補者に効果的に伝えられているか、面接や面談の内容、会社説明資料などを全面的に見直します。 - 見極めの精度向上
評価基準を明確にし、面接官による評価のブレをなくすためのトレーニングを実施します。必要に応じて、適性検査などのアセスメントツール導入も検討します。
- 魅力付け(アトラクト)
- 内定者フォローと受け入れ体制の強化
- 内定辞退の防止
内定者との定期的なコミュニケーション(懇親会、社員との面談、社内報の送付など)を計画し、入社意欲を維持・向上させます。 - オンボーディング
入社後のスムーズな立ち上がりと定着を支援するため、研修プログラムやOJT、メンター制度などの受け入れ体制を整備・改善します。
- 内定辞退の防止
新卒採用割合に関するよくある質問
Q.結局、新卒採用の「適正な割合」は何パーセント?
A.全ての企業に共通する適正な割合はありません。
一般的に「全従業員の3〜5%」が新卒採用人数の目安と言われることもありますが、これはあくまで参考に過ぎません。
自社の年齢構成、事業計画、そして業界平均を考慮し、将来のあるべき組織像から逆算して独自の適正値を設定することが最も重要です。
Q.新卒採用の割合が高すぎると、どんな経営リスクがある?
A.主に3つのリスクが考えられます。1つ目は教育コストの増大と現場の負担増です。
育成リソースが不足し、OJTが機能しなくなる可能性があります。
2つ目は組織文化の同質化です。似た価値観の社員ばかりになり、イノベーションが生まれにくくなる懸念があります。
3つ目は、経験豊富な中堅・ベテラン層の不足による事業遂行能力の低下です。
Q.逆に、新卒採用の割合が低すぎると、将来何が問題になる?
A.短期的には問題が見えにくいですが、5年後、10年後に深刻な課題となります。
具体的には、将来の管理職・リーダー候補の枯渇、組織全体の高齢化による活力の低下、そして企業文化や技術・ノウハウの継承断絶といった問題です。組織の持続的な成長が困難になるリスクを抱えます。
Q.事業フェーズ(成長期、安定期など)によって最適な比率は変わる?
A.はい、大きく変わります。
創業期や急成長期は即戦力となる中途採用の比率が高くなる傾向があります。
一方、事業が軌道に乗った安定期では、将来を見据えた人材育成や文化醸成のために、毎年一定数の新卒を安定的に採用する比率が望ましいでしょう。
自社の置かれたステージに合わせて採用ポートフォリオを柔軟に見直すことが肝心です。
Q.離職率が高い場合、新卒採用の割合はどう考えるべき?
A.新卒採用の割合を増やす前に、なぜ離職率が高いのかという根本原因の分析が最優先です。
「穴の空いたバケツ」に水を注ぎ続けるように、定着しないまま採用を増やしても教育コストが無駄になり、現場が疲弊するだけです。
まずは受け入れ体制や職場環境の改善に取り組み、定着率が安定してから、新卒採用の割合を再検討すべきです。
Q.ジョブ型雇用の浸透で、今後の新卒採用割合はどう変化する?
A.ジョブ型雇用は職務(ジョブ)を明確にして採用するため、即戦力の中途採用と親和性が高いです。
この流れにより、従来のポテンシャル重視型の新卒一括採用の割合は、一部の企業や職種で減少する可能性があります。
しかし、将来の幹部候補や専門家を育成するパイプラインとして新卒採用の重要性は変わらないため、完全に無くなることは考えにくいでしょう。
新卒採用も「総合職」ではなく、より職務内容を明確にした形に変化していくと予想されます。
まとめ
本記事では、最新のデータを基に新卒採用の割合に関する動向を解説し、自社に最適な採用バランスを見つけるための具体的な考え方やステップをご紹介しました。
新卒採用の割合に唯一の正解はないため、他社の数値を鵜呑みにするのではなく、自社の事業戦略と組織課題に真摯に向き合うことが何よりも重要です。
市場環境が厳しさを増す中、持続的な成長を遂げるためには、客観的なデータに基づいた戦略的な人員計画が不可欠です。
ぜひ、本記事でご紹介した「現状分析」「目標設定」「採用計画の最適化」という3つのステップを参考に、貴社の未来を担う人材の採用戦略を見つめ直し、力強い組織創りを実現してください。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。