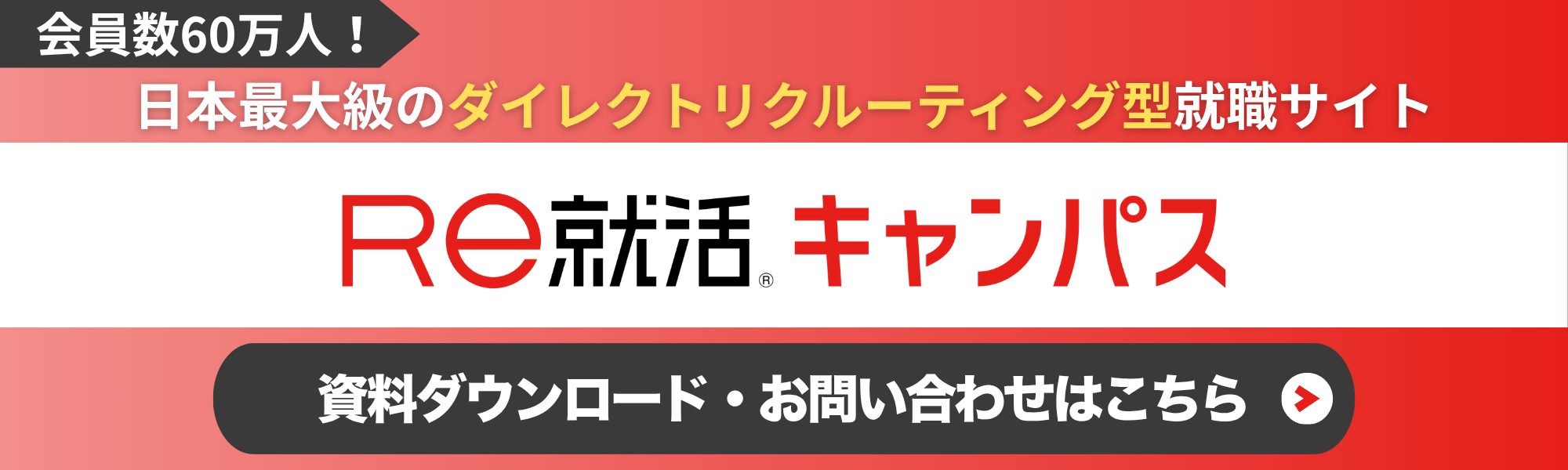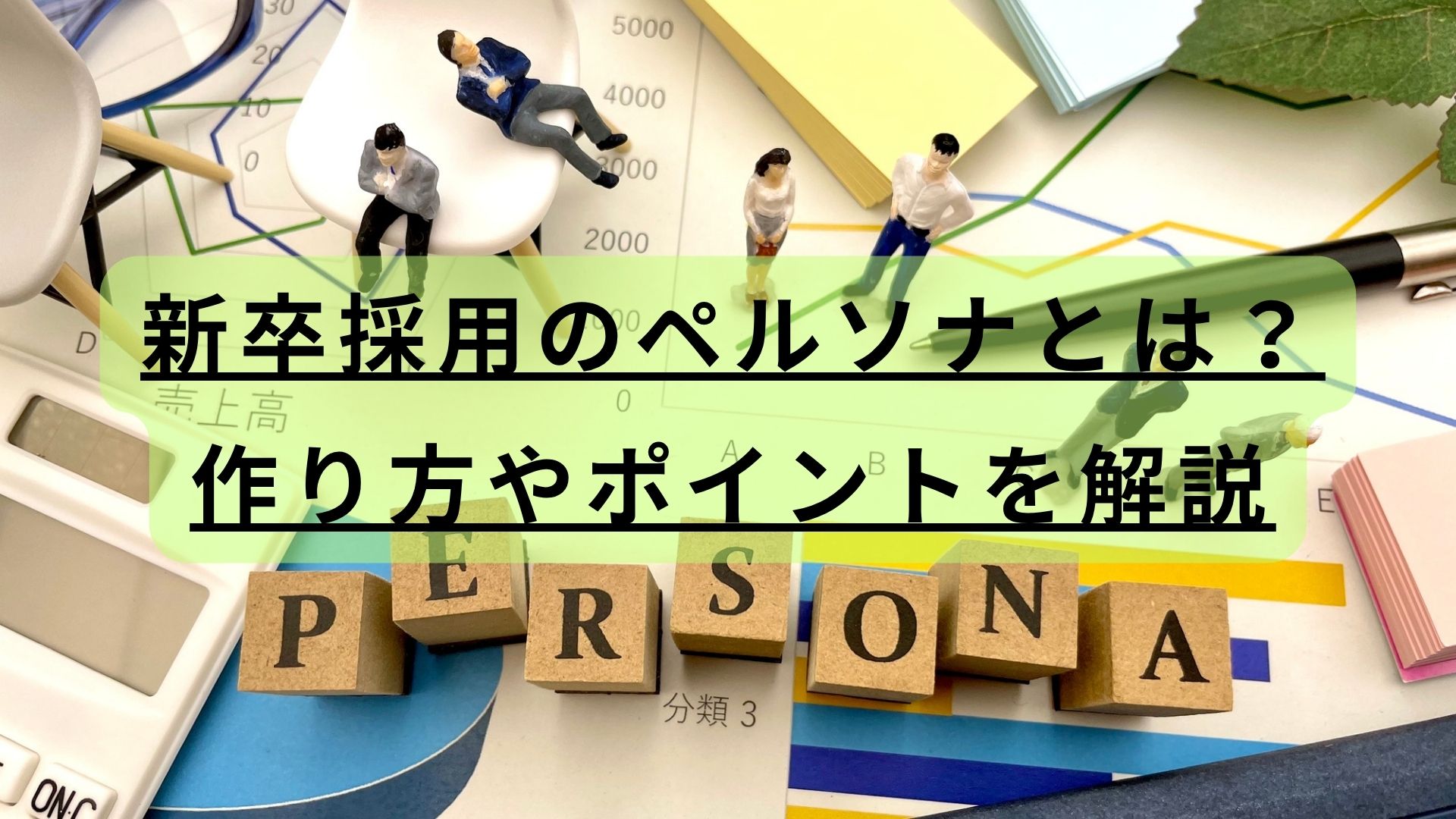「採用サイトだけでは、自社が求める学生にアプローチしきれない」「新卒採用の新たな一手として学校訪問を検討しているが、何から始めれば良いかわからない」といったお悩みをお持ちではないでしょうか。
学校訪問は企業と学校の信頼関係を構築し、自社にマッチした人材へ効率的にアプローチできる非常に有効な採用手法です。
本記事では、新卒採用における学校訪問の目的やメリット・デメリットといった基礎知識から、訪問に適した時期、具体的な準備や当日の流れ、訪問後のフォローアップまでを網羅的に解説します。
最後までお読みいただくことで、学校訪問の全体像を体系的に理解し、自信を持って実践への第一歩を踏み出せるようになります。さっそく、効果的な学校訪問の進め方を見ていきましょう。
新卒採用における学校訪問とは?
新卒採用における学校訪問とは、企業の採用担当者が大学や専門学校、高校などを直接訪れ、キャリアセンターや就職課の教職員に対して自社の魅力や採用情報を伝え、関係性を構築する採用活動の一環です。
主な目的は、学校との連携を深めることで、学内での求人票の掲示や会社説明会の開催、さらには優秀な学生の紹介といった協力体制を築き、安定的な母集団形成につなげることにあります。
重要なのは、訪問先は学生ではなく、あくまで学校の教職員であるという点です。
学生への直接的なスカウト活動ではなく、学校との信頼関係を時間をかけて築き、自社のファンになってもらうことが成功の鍵となります。
学校訪問の目的
学校訪問の目的は多岐にわたりますが、最終的なゴールは「自社とマッチする学生の採用」に集約されます。
そのゴールを達成するために、訪問時には具体的な目的を複数設定し、段階的に関係を構築していくことが重要です。
主な目的としては、「求人票や会社パンフレットの設置」「学校主催の就職イベントへの参加依頼」「学内での自社説明会の実施許可」「学校推薦応募の増加」などが挙げられます。
また、教職員の方々と直接対話し、学生の就職活動の動向や企業に求めることといった情報を交換することも、採用戦略を練る上で非常に価値のある目的と言えるでしょう。
学校訪問のメリット
学校訪問を戦略的に活用することで、企業は多くのメリットを享受できます。
採用コストの最適化や、自社が求める人材への効率的なアプローチが可能になるなど、他の採用手法では得難い利点が存在します。
ここでは、学校訪問がもたらす具体的なメリットを4つの側面から詳しく解説します。
特定ターゲット層への効率的アプローチが可能
学校訪問最大のメリットは、自社が求める特定のスキルや知識、価値観を持つ学生が在籍する学校へ直接アプローチできる点にあります。
例えば、理系の技術職を採用したい場合は工業大学や高専に、デザイン職を求めるなら美術大学に、といった形でターゲットを絞り込むことで、採用活動の効率を大幅に向上させることが可能です。
また、教職員との関係性が深まれば、自社の社風や事業内容にマッチしそうな学生を推薦・紹介してもらえるケースもあり、質の高い母集団形成につながります。
採用コストの低減
採用サイトへの掲載や大規模な合同企業説明会への出展には、多額の費用がかかることが一般的です。
その点、学校訪問は、採用担当者の交通費や人件費が主なコストとなり、比較的低予算で実施できる採用広報活動と言えます。
多くの学校では、求人票の設置やパンフレットの配布を無料で受け付けており、コストを抑えながら学生への認知度を高めることが可能です。
特に、採用予算が限られている中小企業にとっては、費用対効果の高い有効な一手となり得ます。
学校主催イベント参加につながる可能性
一度きりの訪問で終わらせず、継続的に学校へ足を運び、担当者と良好な関係を築くことで、学内で開催される就職イベントへの参加機会が得られやすくなります。
例えば、学内合同企業説明会に空き枠が出た際に優先的に声をかけてもらえたり、業界研究セミナーの講師として招待されたりする可能性が高まります。
学内イベントへの参加は、就職活動に意欲的な学生と直接的な接点を持てる貴重な機会です。
一度参加して実績を作れば、次年度以降も継続的に招待されるという好循環を生み出すことが期待できます。
安定した採用ルートの構築
学校との信頼関係は、一朝一夕には築けませんが、時間をかけて丁寧に関係を築くことで、企業の採用活動における強力な資産となります。
キャリアセンターの担当者が自社の事業や求める人物像を深く理解してくれるようになると、「貴社に合いそうな学生がいますよ」といった形で、継続的に学生を紹介してくれるようになります。
このような強固なパイプは、毎年の新卒採用において安定した応募者数を確保するための重要なルートとなります。
特に、知名度や規模で大手企業に及ばない中小企業にとって、学校からの後押しは採用成功の大きな後押しとなるでしょう。
学校訪問のデメリット
多くのメリットがある一方で、学校訪問にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。
特に、成果が出るまでに時間を要する点や、訪問にかかるコスト、さらには学校との関係性から生じる特有のプレッシャーなどが挙げられます。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることが重要です。
信頼関係構築に時間がかかる
学校訪問の成果は、訪問回数や接触頻度に比例する傾向があり、一回の訪問ですぐに採用成果に結びつくことは稀です。
教職員に自社を認知してもらい、信頼に足るパートナーとして認めてもらうためには、複数年にわたる継続的なアプローチが必要になることも少なくありません。
そのため、短期的な成果を求める採用戦略には不向きな側面があります。
学校訪問を始める際は、すぐに結果が出なくても諦めず、中長期的な視点で腰を据えて取り組む姿勢が不可欠です。
遠方校への訪問はコスト増
自社の所在地から離れた地域の学校へ訪問する場合、交通費や宿泊費、そして担当者の移動時間といったコストが増加します。
全国の大学や高校を網羅的に訪問しようとすると、コスト負担は看過できないレベルになる可能性があります。
そのため、やみくもに訪問先を広げるのではなく、過去の採用実績や自社のターゲット層の分布などを分析し、訪問する学校の優先順位を明確にすることが重要です。
オンラインでの面談を組み合わせるなど、訪問計画を工夫することで、コストを最適化する努力も求められます。
学校からの紹介学生を不採用にしづらい
学校との良好な関係が構築され、キャリアセンターなどから学生を紹介してもらった場合、心理的なプレッシャーから不採用の判断を下しにくくなることがあります。
もし紹介された学生が自社の採用基準や求める人物像と合致しない場合でも、「学校の顔に泥を塗るわけにはいかない」という思いから、難しい判断を迫られる可能性があります。
このような事態を避けるためには、訪問の初期段階で、自社がどのような人材を求めているのか、選考基準は何かを具体的に、かつ明確に学校側へ伝えておくことが不可欠です。
事前の相互理解を深めることで、ミスマッチそのものを減らす努力が重要となります。
「大学訪問」と「学校訪問」の違い
「学校訪問」という言葉は、大学、短期大学、専門学校、高校といった高等教育機関全般への訪問を指す総称です。
一方で「大学訪問」は、その名の通り大学のみを対象とした活動を指します。
対象とする教育機関が異なると、アプローチの方法にも違いが生まれます。
例えば、大学ではキャリアセンターや就職課が主な窓口となり、学生自身も主体的に情報収集を行っています。
一方、高校では進路指導の先生が窓口となり、訪問時には生徒への直接的なアプローチが制限されるなど、特有のルールが存在します。
これらの校種ごとの特性を理解し、それぞれの目的に応じて訪問先を戦略的に使い分けることが、学校訪問を成功させるための重要なポイントです。
学校訪問に適した時期
学校訪問の成果を最大化するためには、「いつ訪問するか」というタイミングが極めて重要です。
学校の年間スケジュールは、就職ガイダンスや学内説明会などでタイトに組まれているため、適切な時期を逃すと、求人票の設置やイベント参加の機会を失いかねません。
大学と高校では採用活動のスケジュールが異なるため、それぞれの特性に合わせた訪問計画を立てる必要があります。
大学への訪問時期
大学への訪問は、学生の就職活動が本格化する前のタイミングを狙うのが効果的です。
具体的には、大学3年生(修士1年生)の10月頃から、学内合同企業説明会が活発になる翌年の3月前までが最初のピークとなります。
多くの大学では、10月頃から就職ガイダンスが始まり、11月から1月にかけて業界研究セミナーが開催されます。
この流れに乗り遅れないよう、夏から秋にかけてアポイントを取り、関係構築の土台を作っておくことが理想的です。
ただし、大学によってイベントの開催時期は異なります。事前にターゲット大学のキャリアセンターのウェブサイトなどで年間のイベントスケジュールを確認し、逆算して訪問計画を立てましょう。
高校への訪問時期
高校生の採用活動(高卒採用)は、大学生とはスケジュールが大きく異なります。
行政が定めたルールにより、企業の求人票の受付が6月1日から、学校への提出・公開が7月1日からと厳密に定められています。その後、9月に学校推薦、9月中旬以降に採用選考が解禁となります。
そのため、企業は7月1日の求人票公開に合わせて速やかに訪問できるよう、6月から準備を始め、7月以降に訪問のピークを迎えるのが一般的です。
この時期に訪問し、進路指導の先生に自社の魅力や求人内容を直接説明することで、多くの生徒に自社を認知してもらう機会を増やすことができます。
夏休み期間中も含め、選考開始までに訪問を完了させることを目標に、早めに準備を進めましょう。
学校訪問の流れ
学校訪問を成功させるためには、事前の準備から当日の立ち居振る-舞い、そして訪問後のフォローアップまで、一連の流れを計画的に進めることが不可欠です。
それぞれのフェーズで押さえるべきポイントを理解し、丁寧に対応することで、学校との良好な関係構築につながります。ここでは、具体的な3つのステップに分けて解説します。
訪問前の準備
訪問前の準備が、学校訪問の成否を大きく左右します。
まず、「今回の訪問で何を達成したいのか」という目的(ゴール)を明確に設定しましょう。
次に、自社で活躍する社員の出身校や過去の採用実績校をリストアップし、訪問する学校を選定します。
訪問先が決まったら、キャリアセンターや就職課に電話またはメールでアポイントを依頼します。
その際、訪問目的と希望日時を簡潔に伝え、担当者の都合を伺う姿勢が大切です。
アポイントが取れたら、当日持参する求人票や会社パンフレット、名刺などを十分な数だけ準備し、自社の魅力を伝えるための説明内容も整理しておきましょう。
学校訪問当日のポイント
当日は、企業の代表として訪問しているという意識を持ち、マナーを徹底することが重要です。
約束の5〜10分前には学校に到着し、受付で所属と氏名、アポイントの旨を伝えます。
担当者との面会では、まず名刺交換を行い、時間を割いてもらったことへの感謝を述べましょう。
持参した資料を基に、自社の事業内容や求める人物像、学生にとっての魅力などを簡潔に説明します。
一方的に話すのではなく、学校側の就職状況や学生の動向について質問するなど、双方向のコミュニケーションを心がけることで、信頼関係が深まります。
服装は清潔感のあるビジネスフォーマルを基本とし、面談時間は長くなりすぎないよう配慮しましょう。
訪問後のフォロー
学校訪問は、訪問して終わりではありません。
訪問後の丁寧なフォローアップが、次につながる関係を築く上で非常に重要です。
訪問後、当日か翌日中には、対応してくださった担当者宛にお礼のメールや手紙を送ります。
感謝の意を伝えるとともに、面談で話題に上がった内容に触れると、より丁寧な印象を与えられます。
その後も、採用活動の進捗状況を報告したり、新たなイベント情報を提供したりと、定期的に連絡を取り、関係性を維持することが大切です。
可能であれば、毎年同じ担当者が訪問を続けることで、学校側との個人的な信頼関係も深まり、より強固なパートナーシップを築くことができるでしょう。
卒業生の新入社員・若手社員による母校訪問
採用担当者による訪問と並行して、OB/OGである若手社員が母校を訪問する取り組みも有効です。ただし、大学と高校ではその目的と手法が異なります。
大学では、キャリアセンター主催のOB/OG懇談会などで学生と直接対話する機会を得やすいですが、高校では原則として進路指導の先生との面談が中心となります。この違いを理解した上で、戦略的に活用することが重要です。
新入社員が母校訪問する目的とメリット
学生の共感と信頼を得やすい(主に大学)
大学訪問では、年齢の近い先輩として学生と直接対話することで、仕事のリアルな情報を伝え、共感を得やすくなります。
これにより、学生は具体的な入社後のイメージを描くことができます。
教職員との関係を深化させる(主に高校)
高校訪問では、若手社員が先生に直接、仕事のやりがいや会社の現状を伝えることで、先生はより具体的な情報を持って生徒に進路指導ができるようになります。卒業生の活躍する姿は、先生にとって何よりの信頼の証となります。
新入社員自身の成長促進
母校訪問は、訪問する社員自身の成長にも繋がります。後輩や恩師に自社の魅力を語ることで、会社への理解とエンゲージメントが深まり、プレゼンテーション能力の向上も期待できます。
実施する際の流れとポイント
1. 訪問目的の明確化と人選
まず、訪問が「大学向け(学生との対話目的)」なのか「高校向け(先生との関係構築目的)」なのかを明確にします。その上で、自社で活躍し、後輩のキャリア支援に意欲的な社員を選びます。
2. 事前の打ち合わせと準備
訪問の目的を本人と共有し、会社の基本情報や採用方針をレクチャーします。
特に高校訪問の場合は、先生に対してどのような情報を伝えれば生徒のためになるかを一緒に考え、準備します。採用担当者が同行する場合は、制度説明と経験談で役割分担を明確にしておきましょう。
3. 学校側との調整
アポイントを取る際に、若手社員が同行する旨を伝え、訪問の形式(学生との懇談会、先生との面談など)を事前にすり合わせます。学校側のニーズやルールを尊重することが、良好な関係構築の第一歩です。
4. 訪問後のフォロー
訪問後は、担当した社員から学生や先生の反応についてフィードバックをもらい、次回の採用活動に活かします。協力への感謝を伝え、本人の成長に繋がるような声かけを行うことも忘れないようにしましょう。
新卒採用の学校訪問に関するよくある質問
ここでは、採用担当者が学校訪問に関して抱きがちな、よくある質問とその回答をまとめました。
アポイントの取り方から当日の服装、会話の内容まで、具体的な疑問を解消し、安心して学校訪問に臨めるよう準備しましょう。
学校訪問のアポイント連絡は電話とメールのどちらが良い?
基本的には、まず電話で連絡することをお勧めします。
担当者と直接話すことで、用件が伝わりやすく、その場で日程調整まで進められる可能性が高いからです。
ただし、教職員は授業や会議で多忙な場合が多いため、電話をかける時間帯には配慮が必要です。
最初に電話で訪問の趣旨を伝えて了承を得た上で、後から詳細をメールで送る、という組み合わせが最も丁寧で確実な方法と言えるでしょう。
学校訪問では服装はどんな格好で行くべき?
企業の代表として訪問するため、リクルートスーツのようなビジネスフォーマルな服装が基本です。
学生が就職活動で着用するような、黒や紺のスーツが無難でしょう。
大切なのは、相手に不快感を与えない清潔感です。
髪型や靴、鞄といった細部にも気を配り、企業の顔としてふさわしい、誠実で信頼感のある印象を与えることを心がけてください。
学校訪問では具体的にどんな話をすれば良い?
一方的な自社のPRにならないよう、双方向のコミュニケーションを意識することが重要です。
まずは、自社がどのような事業を行っており、どのような人材を求めているのかを簡潔に説明します。
その上で、「最近の学生さんの動向はいかがですか」「貴校の学生さんはどのような業界に興味を持っていますか」など、学校側から情報を引き出す質問を投げかけましょう。
相手の話に耳を傾ける姿勢を見せることで、信頼関係の構築につながり、有益な情報交換が可能になります。
訪問の対象校はどのように選べば良い?
やみくもに訪問するのではなく、戦略的に対象校を選定することが重要です。
まずは、過去に採用実績のある学校や、現在活躍している社員・内定者の出身校が有力な候補となります。
また、自社が求める専門性を持つ学生が多く在籍する学部や学科から逆引きで探す方法も有効です。
重要なのは、訪問後のフォローが可能な範囲に絞り込むこと。
少数でも継続的に関係を築ける学校を選ぶことが、最終的な成果につながります。
学校訪問はどのくらいの頻度・期間で行うべき?
関係構築のためには、年に1回の訪問では不十分です。
理想は、採用シーズンが本格化する前と、その後のフォローアップを兼ねて、少なくとも年に2回以上は訪問することです。
例えば、求人票を提出するタイミングと、学内説明会の開催をお願いするタイミングなど、目的を分けて定期的に接点を持つことで、学校側に顔と名前を覚えてもらいやすくなります。
中長期的な視点を持ち、継続することが何よりも大切です。
高校・大学への訪問でマナーや連絡手順に違いは?
基本的なマナーは同じですが、連絡方法には若干の違いがあります。
大学のキャリアセンターはメールでのやり取りに慣れていることが多いですが、高校の場合は、先生方が多忙であるため、電話をかける時間帯に配慮する必要があります。
一般的に、始業前や昼休み、放課後などが繋がりやすいとされています。
どちらの場合も、初回のアポイントは電話で担当者の都合を確認するのが最も確実な方法と言えるでしょう。
継続的な関係構築で、自社にマッチした人材を確保する
本記事では、新卒採用における学校訪問について、その目的から具体的な実践方法、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。
学校訪問は、ナビサイトや合同説明会とは異なり、企業と学校が直接的な信頼関係を築くことで、自社にマッチした優秀な人材と出会える可能性を秘めた採用手法です。
成功の鍵は、短期的な成果を求めず、中長期的な視点で継続的にアプローチし、学校側との強固なパートナーシップを構築することにあります。
本記事で紹介した準備や当日の流れ、訪問後のフォローを実践することで、貴社の採用活動は新たなフェーズに進むはずです。
まずは自社に合った一校へのアポイントから、未来の仲間と出会うための第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。