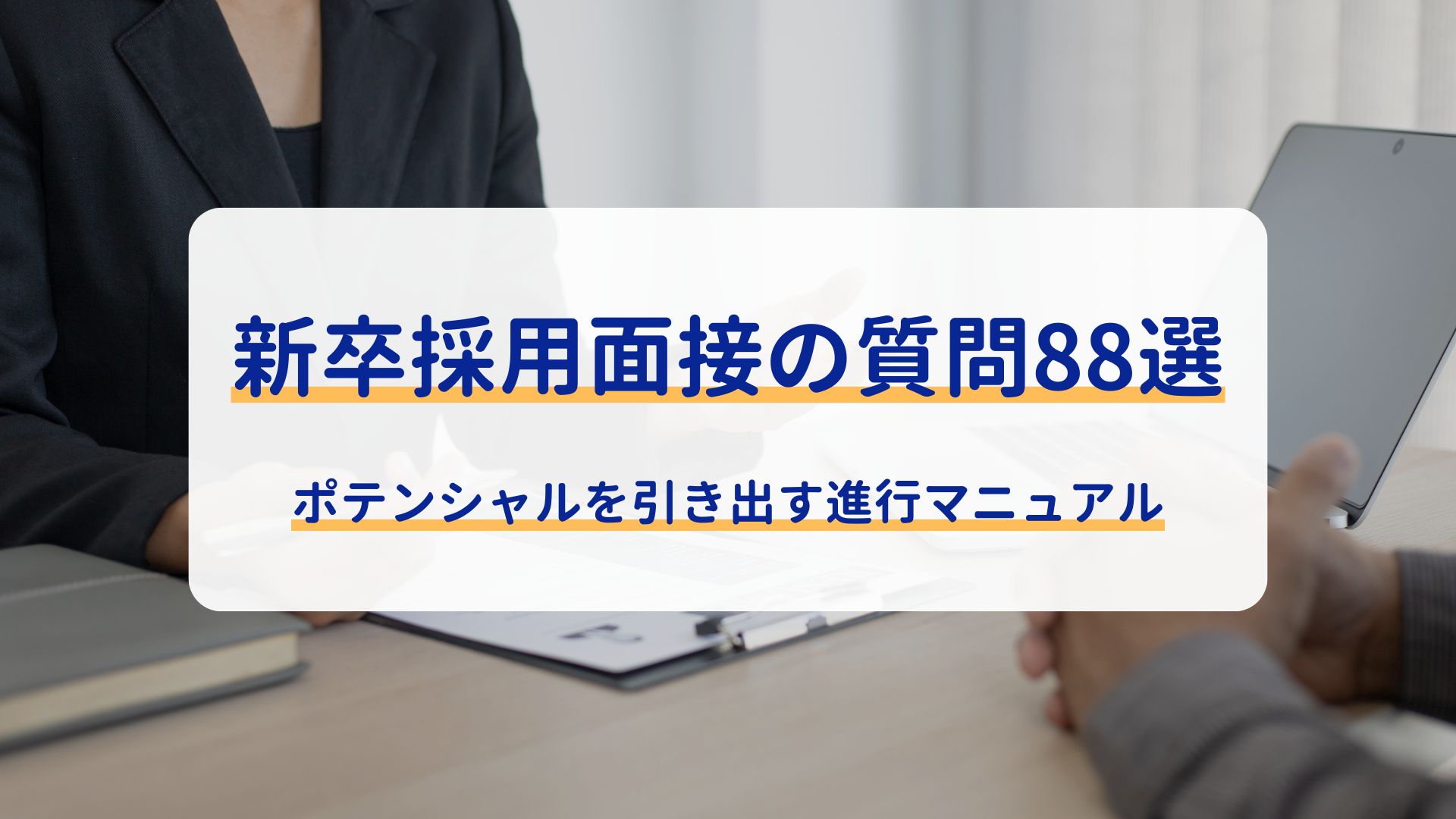ミスなく進める!中途採用の入社手続きと必要書類リスト
公開日:2025.08.25
更新日:2026.01.01

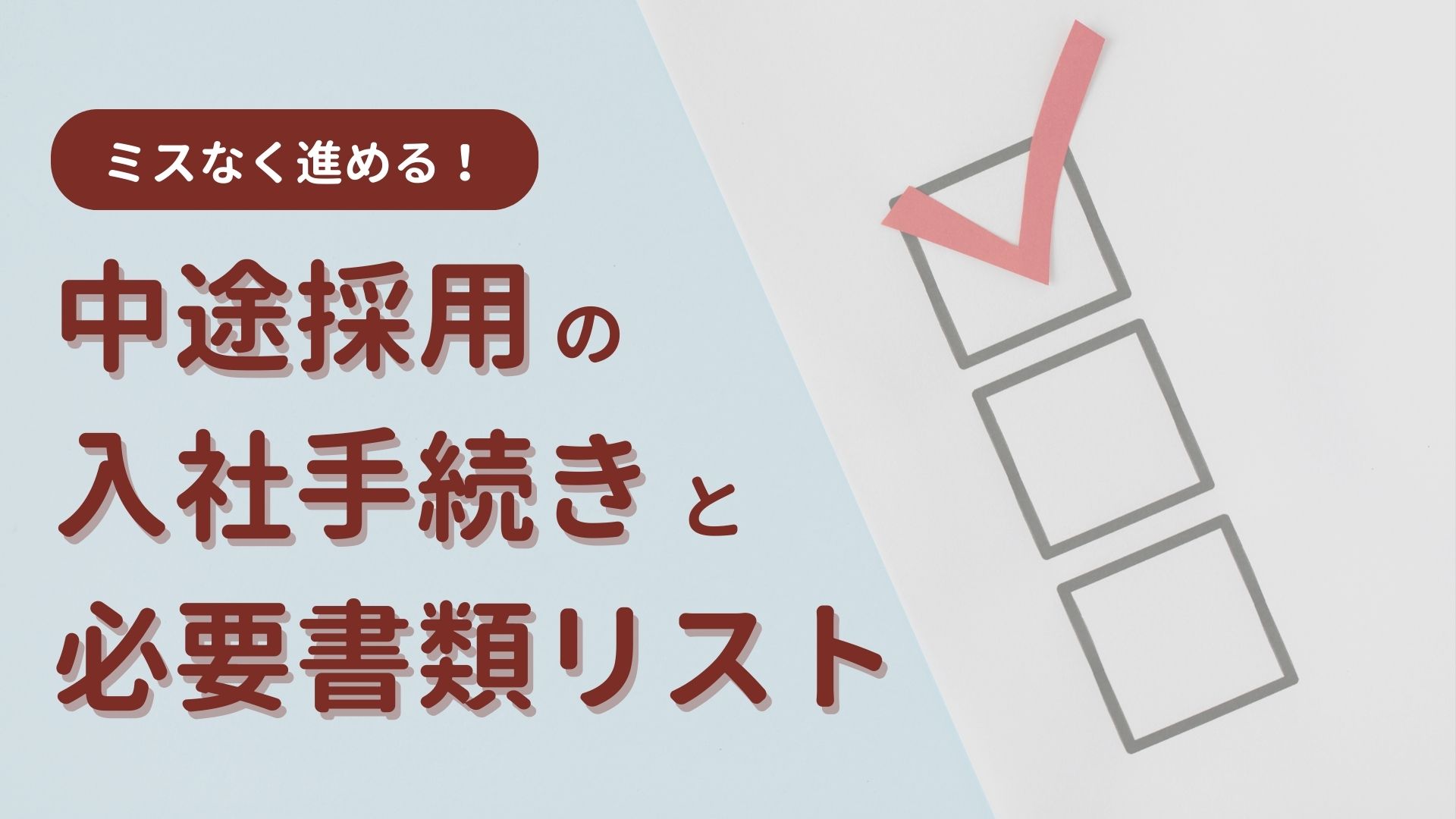
「中途採用者の入社手続き、何から手をつければよいのだろう…」「書類の不備や手続きの漏れが心配だ」と感じていませんか。
中途採用は即戦力を迎える重要な機会ですが、その裏側には複雑な事務手続きが伴います。中途採用の入社手続きを成功させる鍵は、入社前・入社日・入社後の3つのフェーズで全体像を捉え、必要なタスクと書類を時系列で正確に管理することです。
本記事では、中途採用の入社手続きに関する全体フローから、具体的な必要書類の一覧、社会保険や税金の手続き、さらにはよくあるトラブルへの対応策まで、採用担当者が知りたい情報を網羅的に解説します。
この記事を最後まで読めば、煩雑な手続きをミスなくスムーズに進めるための知識が身につき、新しい仲間を万全の体制で迎えられるようになります。さっそく、具体的な手続きの流れから確認していきましょう。
中途採用入社手続きの全体像
中途採用者の入社手続きは、多岐にわたる業務を正確かつ効率的に進めることが求められます。
手続きの全体像を「入社前」「入社日」「入社後」の3つのフェーズに分けて捉えることで、タスクの抜け漏れを防ぎ、新入社員がスムーズに業務を開始できる体制を整えることができます。
この体系的なアプローチが、円滑なオンボーディングの第一歩となります。
中途採用の入社手続きの流れ・時系列
中途採用の入社手続きを成功させるには、時系列に沿った計画的な進行が不可欠です。
内定の通知から始まり、入社日までに必要な書類のやり取りや環境整備、そして通勤手当の準備まで、各ステップには明確な目的と注意点が存在します。
ここでは、内定決定から入社日までの具体的な手続きの流れを、項目ごとに詳しく解説していきます。
内定通知書・採用通知書の送付
内定通知書は、応募者に対して正式に採用が決定したことを伝えるための重要な書類です。
送付のタイミングは、最終面接後、1週間から10日以内が一般的です。書面には、採用ポジション、入社予定日、提出書類の案内、返信期限などを明記し、企業の代表者名で発行します。
近年はメールで第一報を伝え、後から原本を郵送するケースも増えていますが、その場合も正式な書面として送付することが、応募者に安心感を与え、誠実な印象を築く上で重要です。
入社承諾書・誓約書の回収
入社承諾書(または内定承諾書)は、応募者が内定を承諾し、正式に入社する意思があることを企業側が確認するための書類です。
誓約書は、服務規律や秘密保持義務など、入社にあたって遵守すべき事項について同意を得るために提出を求めます。
これらの書類を回収することで、入社意思を明確にし、後の「言った・言わない」といったトラブルを未然に防ぐことができます。通常、内定通知書に同封し、指定した期限内に返送してもらいます。
雇用契約書・労働条件通知書の締結
雇用契約の締結は、入社手続きの中でも法的に極めて重要なプロセスです。
企業には、労働者に対し、労働契約の期間、就業場所、業務内容、賃金、労働時間といった労働条件を明示する義務があります(労働基準法第15条)。
この「労働条件通知書」と、双方の合意を示す「雇用契約書」を取り交わすことで、労使間の認識の齟齬を防ぎます。
特に賃金や労働時間に関する項目は明確に記載し、入社日までに内容の合意を得て、署名・捺印済みの書類を回収することが不可欠です。
入社前の案内業務
新入社員が安心して初日を迎えられるよう、入社前の丁寧な案内が重要です。
提出が必要な書類の一覧とそれぞれの提出期限、入社初日のスケジュール(出社時間、場所、当日の流れなど)、持参物などをまとめて連絡します。
案内の方法は郵送またはメールが一般的ですが、メールの場合はファイルにパスワードを設定するなど、個人情報の取り扱いに注意が必要です。チェックリスト形式で案内すると、新入社員も準備が進めやすくなります。
就労環境の準備・備品の手配
新入社員が着任後すぐに業務を開始できるよう、物理的な就労環境を整えておく必要があります。
具体的には、業務用PCやスマートフォン、メールアドレスや各種システムのアカウント発行、名刺、社員証、デスクや椅子、文房具といった備品の手配が挙げられます。
これらの準備をチェックリスト化し、情報システム部門や総務部門と連携して計画的に進めることで、受け入れ当日の混乱を防ぎ、歓迎の意を示すことができます。
通勤手当額の決定
通勤手当を支給するためには、新入社員から通勤経路と利用する交通機関の情報を事前に収集する必要があります。
提出された情報をもとに、最も経済的かつ合理的な経路であるかを確認し、社内規定に照らし合わせて支給額を決定します。
決定した金額や支給ルールについては、事前に本人へ通知しておくことが望ましいです。特に、定期代の支給対象期間(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月など)は企業によって異なるため、明確に伝えておきましょう。
中途採用の入社時に必要な書類一覧
中途採用者の入社手続きでは、社会保険や税金関連の手続きのために、本人から提出してもらうべき書類が数多くあります。
これらの書類が不足すると、各種手続きが滞り、給与計算や年末調整にも影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、企業が新入社員に提出を求めるべき主要な書類について、それぞれの目的や注意点を詳しく解説します。
年金手帳・基礎年金番号通知書
年金手帳または基礎年金番号通知書は、厚生年金保険の加入手続きに不可欠な書類です。
基礎年金番号を確認するために提出を求めます。もし新入社員が紛失してしまった場合は、前職の会社に確認するか、最寄りの年金事務所で再発行の手続きを行うよう案内しましょう。
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている従業員の場合は、マイナンバーの提出をもって代用することも可能です。
雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険の加入者であることを証明する書類で、被保険者番号を引き継ぐために必要です。
通常、前職の退職時に本人へ交付されます。企業は、この書類に記載されている被保険者番号をもとに、ハローワークで資格取得(または切替)の手続きを行います。
紛失した場合は、本人の住所を管轄するハローワークで再発行が可能であることを伝え、速やかな手続きを促しましょう。
源泉徴収票
前職の源泉徴収票は、その年の年末調整を行う際に、前職での給与所得と合算して正しい所得税額を計算するために必須となります。
通常、退職後1ヶ月以内に前職の企業から発行されます。年の途中で入社した社員からは必ず回収する必要があります。
もし受け取りが遅れている場合や紛失してしまった場合は、速やかに前職の企業に再発行を依頼するよう本人に伝え、会社としてもしっかりとフォローすることが重要です。
扶養控除等申告書・給与所得者異動届出書
扶養控除等(異動)申告書は、毎月の給与から源泉徴収される所得税の額や、年末調整で配偶者控除や扶養控除などを受けるために必要な書類です。
給与所得者である従業員は、原則として入社時に提出する必要があります。
企業はこの申告書に基づいて税額を計算するため、記載内容に誤りがないかを確認し、扶養家族の状況などに変更があった場合には速やかに再提出を求める必要があります。
マイナンバー関連書類
マイナンバー(個人番号)は、税金や社会保険の手続きにおいて法律で利用が定められており、企業には従業員本人およびその扶養家族のマイナンバーを収集・管理する義務があります。
収集する際は、利用目的を明確に通知し、番号確認(マイナンバーカードなど)と身元確認(運転免許証など)を厳格に行う必要があります。
また、収集したマイナンバーは漏洩や不正利用がないよう、法令に基づいた安全管理措置を講じなければなりません。
健康保険被扶養者(異動)届
従業員に配偶者や子供など、健康保険の被扶養者となる家族がいる場合に提出が必要な書類です。
この届出により、被扶養者も会社の健康保険に加入することができます。被扶養者として認定されるには、収入などの一定の条件を満たす必要があります。
対象となる家族がいる場合は、続柄を証明する書類(住民票など)とあわせて提出を求め、速やかに健康保険組合や年金事務所へ手続きを行います。
給与振込先届出書
毎月の給与を振り込むための金融機関口座情報を取得するための書類です。
希望する金融機関、支店名、口座種別、口座番号、口座名義人などを正確に記入してもらいます。
給与振込という重要な業務に関わるため、記載内容に誤りがないかを確認することが不可欠です。
また、口座情報は重要な個人情報であるため、その取り扱いには細心の注意を払い、厳重に管理する必要があります。
健康診断書
雇入時の健康診断は、労働安全衛生法に基づき、企業に実施が義務付けられています。
そのため、企業が費用を負担し、指定の医療機関で受診してもらうのが一般的です。
ただし、入社前3ヶ月以内に本人が受けた健康診断の結果を提出してもらうことで、雇入時健康診断に代えることも可能です。
この方法をとる企業も多いため、その場合は健康診断書(結果のコピー)の提出を求めます。
身元保証書(必要に応じて)
身元保証書は、従業員が会社に損害を与えた場合に備えるものですが、近年では提出を求めない企業も増えています。
これらの書類を求める場合は、その必要性を明確にし、内定通知の段階で案内しておくことが望ましいです。
社会保険・雇用保険・労災保険手続き(入社後)
従業員を雇用する企業には、社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険、労災保険への加入が法律で義務付けられています。
新入社員の入社後は、これらの保険に関する資格取得手続きを迅速かつ正確に行わなければなりません。
手続きの遅延は、従業員の不利益に直結するだけでなく、企業の法的責任を問われる可能性もあります。ここでは、各保険手続きの具体的な実務ポイントを解説します。
社会保険(健康保険・厚生年金)手続き
社会保険の資格取得手続きは、原則として入社の事実があった日から5日以内に、管轄の年金事務所または事務センターへ「被保険者資格取得届」を提出して行います。
手続きには、基礎年金番号やマイナンバー、被扶養者がいる場合はその情報が必要です。
提出方法は、窓口持参、郵送、そして近年推奨されている電子申請があります。
電子申請は24時間いつでも手続きが可能で、業務効率化に大きく貢献します。
雇用保険切替・資格取得手続き
雇用保険の手続きは、入社した月の翌月10日までに、管轄のハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して行います。
この際、前職から引き継いだ「雇用保険被保険者証」に記載された被保険者番号が必要となります。
手続きが完了すると、新しい「雇用保険被保険者証」と「資格取得等確認通知書」が交付されるので、本人へ渡します。こちらも電子申請が可能であり、迅速な手続きが推奨されます。
労働保険(労災)の対応
労災保険は、業務中や通勤中のケガや病気に対して給付を行う保険制度です。
従業員を一人でも雇用した時点で、企業は労働保険関係成立届を提出し、加入する義務があります。個別の入社手続きは不要で、年度更新時に全従業員の賃金総額を申告・納付することで、全従業員が保険の対象となります。
採用担当者としては、労災保険の適用事業所であることを認識し、万が一の事故発生時に適切な対応が取れる体制を整えておくことが重要です。
税金関連手続き(入社後)
従業員の入社に伴い、企業は給与から天引きする住民税や所得税に関する手続きを行う必要があります。
これらの税金関連の手続きは、従業員の納税を代行する重要な業務であり、正確な処理が求められます。
特に中途採用者の場合は、前職からの引き継ぎが発生するため、手続きの流れを正しく理解しておくことが不可欠です。
住民税(特別徴収)対応
住民税の特別徴収は、企業が従業員の給与から住民税を天引きし、本人に代わって市区町村に納付する制度です。
中途入社した社員の住民税を特別徴収に切り替えるには、「特別徴収切替届出(依頼)書」を、その従業員がその年の1月1日時点で居住していた市区町村へ提出します。
前職で普通徴収だった場合や、退職から入社までに期間が空いている場合に必要な手続きです。
所得税(源泉徴収・年末調整)
企業は、従業員に提出してもらった「扶養控除等申告書」に基づき、毎月の給与から所得税を源泉徴収します。
そして、年末にはその年の所得総額を確定させ、正しい税額を計算して過不足を精算する「年末調整」を行います。
年の途中で入社した社員については、前職の「源泉徴収票」に記載された給与や社会保険料、源泉徴収税額を合算して年末調整を行う必要があるため、書類の確実な回収が極めて重要です。
法定三帳簿の整備(入社後)
労働基準法では、企業に対して「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の作成と保存が義務付けられています。
これらは「法定三帳簿」と呼ばれ、適切な労務管理の基礎となる重要な書類です。新入社員の入社に伴い、これらの帳簿を速やかに整備し、常に最新の状態に更新していく必要があります。
- 労働者名簿:従業員の氏名、生年月日、履歴、従事する業務の種類といった情報を記載した名簿です。
- 賃金台帳:従業員ごとの給与計算の基礎となる事項、賃金額、手当などを記録した台帳です。
- 出勤簿:タイムカードやICカードの記録など、従業員の出勤日や労働日数、始業・終業時刻を記録したものです。
これらの帳簿は、従業員の退職や死亡の日から5年間(当分の間は3年間)の保存が義務付けられています(労働基準法第109条)。
企業タイプ別に必要な可能性のある入社手続き
企業の規模や業態、文化によって、基本的な入社手続きに加えて、特有のプロセスや書類が必要になることがあります。
ここでは「IT・スタートアップ」「大企業」「外資系企業」の3つのタイプに分け、それぞれで発生しうる特有の入社手続きについて解説します。自社の特徴と照らし合わせ、準備の参考にしてください。
IT・スタートアップ
リモートワークが浸透し、独自の報酬制度を持つことが多いIT・スタートアップでは、セキュリティや柔軟な働き方に関連する手続きが特徴です。以下は法的義務ではないですが、状況に応じて必要な場合があります。
- セキュリティ誓約書・情報管理規定への同意:自宅など社外からのアクセスを前提とし、情報漏洩リスクを防ぐための厳格なルールへの同意を求めます。
- ストックオプション付与契約書:インセンティブとして付与されるストックオプションの権利行使条件や税務上の扱いを明確にするための契約です。
- リモートワーク規定同意書・在宅勤務手当申請書:通信費や光熱費の補助、貸与するIT機器の取り扱いなど、在宅勤務に関するルールを定めます。
大企業
充実した福利厚生制度や独自の年金制度を持つ大企業では、それらへの加入手続きが追加で必要になります。
- 確定拠出年金(401k)移管依頼書:前職で加入していた確定拠出年金の資産を、自社の制度に移換するための手続きです。
- 企業年金基金加入申込書:確定給付企業年金(DB)など、会社独自の年金制度への加入申込と掛金設定を行います。
- カフェテリアプラン選択届:多様な福利厚生メニューの中から、付与されたポイントの範囲内で利用したいものを選択・申請します。
- 社宅・寮入居申請書:転勤者や新卒者向けに用意された社宅や独身寮への入居を希望する場合に必要な手続きです。
外資系企業
グローバルで統一された人事制度やコンプライアンス基準を持つ外資系企業では、英文での契約や海外本社への報告といった特有の手続きが発生します。
- Employment Agreement(英文雇用契約書):グローバル共通の契約条項が含まれた英文の雇用契約書への署名が求められます。
- Global HR System登録フォーム:海外本社が管理するグローバル人事システムへ、自身の個人情報を英語で登録します。
- Code of Conduct(行動規範)への署名:全世界共通のコンプライアンス基準や倫理規定への同意を示します。
- Stock Award Agreement:RSU(譲渡制限付株式ユニット)やESPP(従業員株式購入プラン)など、海外本社の株式に関連する報酬プランへの参加手続きです。
中途採用入社手続きにおけるよくあるトラブルと対応策
どれだけ慎重に準備を進めても、中途採用の入社手続きでは予期せぬトラブルが発生することがあります。
事前に典型的なトラブル事例とその対応策を把握しておくことで、いざという時に冷静かつ迅速に対処できます。
ここでは、採用担当者が直面しがちな4つのトラブルと、その具体的な解決策を解説します。
書類の提出遅延・不備
最も頻繁に発生するトラブルの一つが、必要書類の提出遅延や記載ミスです。
対応策としては、まず提出期限を明確に伝え、期限前にリマインダーを送るなど、事前の働きかけが有効です。
遅延が発生した場合は、速やかに本人に連絡し、状況を確認します。記載ミスや記入漏れがあった場合は、どの部分をどのように修正すればよいか具体的に指示し、速やかな再提出を依頼しましょう。
前職との書類受け渡し不備
源泉徴収票や雇用保険被保険者証など、前職から受け取るべき書類が届かないケースも少なくありません。
この場合、まずは本人から前職の担当者へ連絡してもらうのが基本です。それでも解決しない場合は、本人の同意を得た上で、自社の担当者から前職へ問い合わせることも検討します。
紛失してしまった場合は、源泉徴収票は前職へ、雇用保険被保険者証はハローワークへ、それぞれ再発行を依頼するよう案内します。
社会保険切替のタイムラグによるトラブル
社会保険の資格取得手続きには数週間かかることがあり、その間、新しい健康保険証が手元にない状態になります。
この期間中に医療機関を受診した場合、一旦医療費を全額自己負担しなければならない可能性があることを事前に本人へ伝えておきましょう。
その際は、後日「療養費支給申請書」を提出すれば自己負担分を除いた金額が払い戻されることも併せて案内し、従業員の不安を解消することが大切です。
急な内定辞退の発生
入社承諾後、入社日直前になって内定辞退の連絡が来ることもあり得ます。
内定辞退を防ぐためには、内定承諾後も定期的に連絡を取り、入社への意欲を維持してもらうためのコミュニケーションが重要です。
それでも辞退が発生してしまった場合は、理由を丁寧にヒアリングし、今後の採用活動の改善に繋げます。同時に、速やかに代替人材の確保に向けて、採用計画の見直しに着手する必要があります。
中途採用入社手続きに関する注意点・ポイント
中途採用の入社手続きを円滑に進めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
特に、個人情報の厳重な管理、書類の適切な保管、そして労使間のトラブルを未然に防ぐための明確な雇用条件の提示は、コンプライアンス遵守の観点からも極めて重要です。
個人情報管理・取扱い
入社手続きでは、マイナンバーや銀行口座情報、家族構成など、機密性の高い個人情報を多数取り扱います。
これらの情報は、個人情報保護法やマイナンバー法に基づき、厳重に管理しなければなりません。
収集時には利用目的を明確に伝え、アクセス権限を限定し、保管場所の施錠やデータへのパスワード設定など、物理的・技術的な安全管理措置を徹底することが企業の責務です。
書類回収・保管のルール
入社時に回収した各種書類は、それぞれの法律で定められた保存期間に従って、適切に保管する必要があります。
例えば、労働者名簿や賃金台帳などの法定三帳簿は5年間(当分の間は3年間)、雇用保険関連書類は4年間の保存が義務付けられています。
書類の保管場所や管理責任者を明確にし、必要な時にすぐに取り出せるよう、ファイリングルールを定めておくことが重要です。
雇用条件通知と労使トラブル回避
給与や労働時間、休日といった雇用条件は、後の労使トラブルを避けるためにも、書面で明確に通知し、双方の合意を得ておくことが不可欠です。
特に、口頭で伝えた内容と契約書の内容に相違があると、信頼関係を損なう原因となります。
「労働条件通知書」や「雇用契約書」を事前に提示し、疑問点がないかを確認するプロセスを踏むことで、誤解やミスマッチを防ぎ、安心して入社してもらえる体制を築きましょう。
中途採用入社手続きの効率化・業務改善のコツ
毎年のように発生する入社手続きは、少しの工夫で大幅に効率化できる可能性があります。
手続きのフローを標準化し、ITツールを積極的に活用することで、担当者の負担を軽減し、本来注力すべきコア業務に時間を割けるようになります。
ここでは、すぐに実践できる業務改善のコツを3つ紹介します。
手続きフローの標準化・チェックリスト活用
担当者個人の経験や記憶に頼るのではなく、誰が担当しても同じ品質で業務を遂行できるよう、手続きのフローを標準化することが重要です。
「いつまでに」「誰が」「何をすべきか」を時系列でまとめたチェックリストやマニュアルを作成しましょう。これにより、業務の抜け漏れやミスを防ぎ、新任担当者への引き継ぎもスムーズに行えるようになります。
クラウド・ペーパーレス化の推進
入社手続きに関する書類を電子化し、クラウド上で管理することで、業務効率は飛躍的に向上します。
入社承諾書や各種申請書をオンラインで提出・回収できるようにすれば、印刷、郵送、ファイリングといった手間とコストを削減できます。また、書類の検索性も高まり、保管スペースも不要になるなど、多くのメリットが期待できます。
社内関係部署との連携体制
入社手続きは、人事・労務部門だけでなく、情報システム、経理、そして配属先の現場部門など、多くの部署が関わります。
各部署の役割と責任分担を明確にしたフロー図を作成し、定期的な情報共有の場を設けることで、連携ミスを防ぎます。
例えば、入社が確定した時点で関係部署に一斉通知する仕組みを作るなど、スムーズな情報共有体制を構築することが、円滑な受け入れの鍵となります。
入社準備の質が早期活躍を左右する
本記事では、中途採用の入社手続きについて、その全体像から具体的なフロー、必要書類、各種保険・税金の手続き、さらにはトラブル対応や業務効率化のコツに至るまで、網羅的に解説しました。
中途採用の入社手続きを成功させるには、入社前・入社日・入社後のフェーズごとにタスクを整理し、計画的に進めることが不可欠です。特に、多岐にわたる必要書類をチェックリスト化し、提出期限や手続きのスケジュールを明確に管理することが、ミスや抜け漏れを防ぐ鍵となります。
また、社会保険や税金といった法的な手続きを正確に行うことはもちろん、新入社員が安心して入社日を迎えられるよう、丁寧なコミュニケーションを心がけることも重要です。本記事で紹介したポイントを参考に、自社の手続きフローを見直し、新しい仲間を万全の体制で迎え入れることで、新入社員の早期活躍と組織全体の活性化に繋げていきましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。