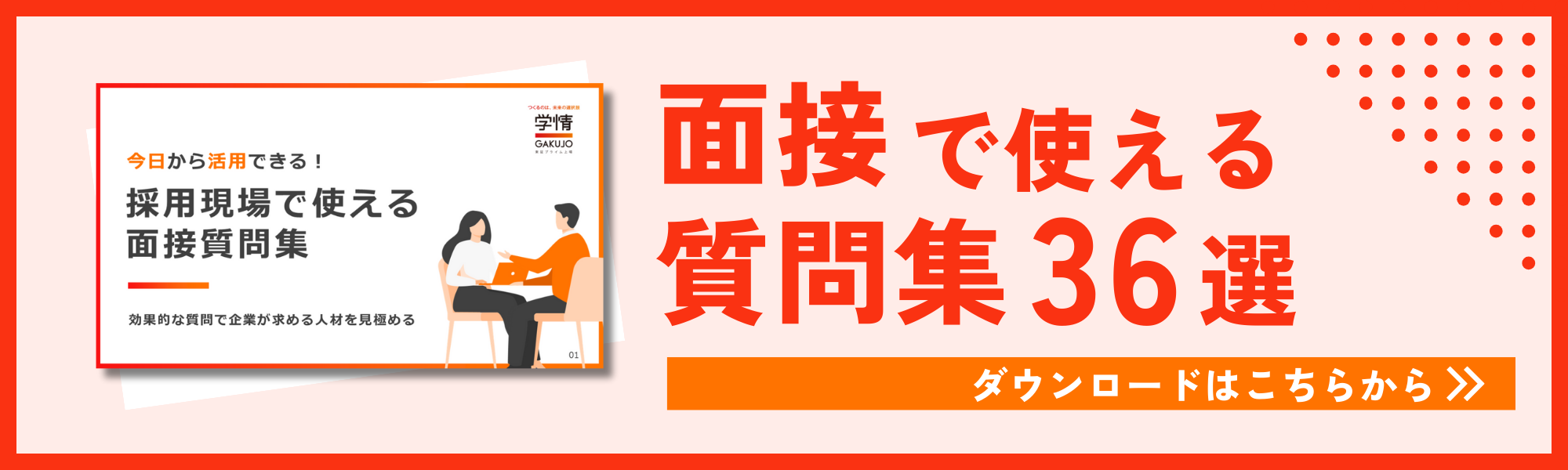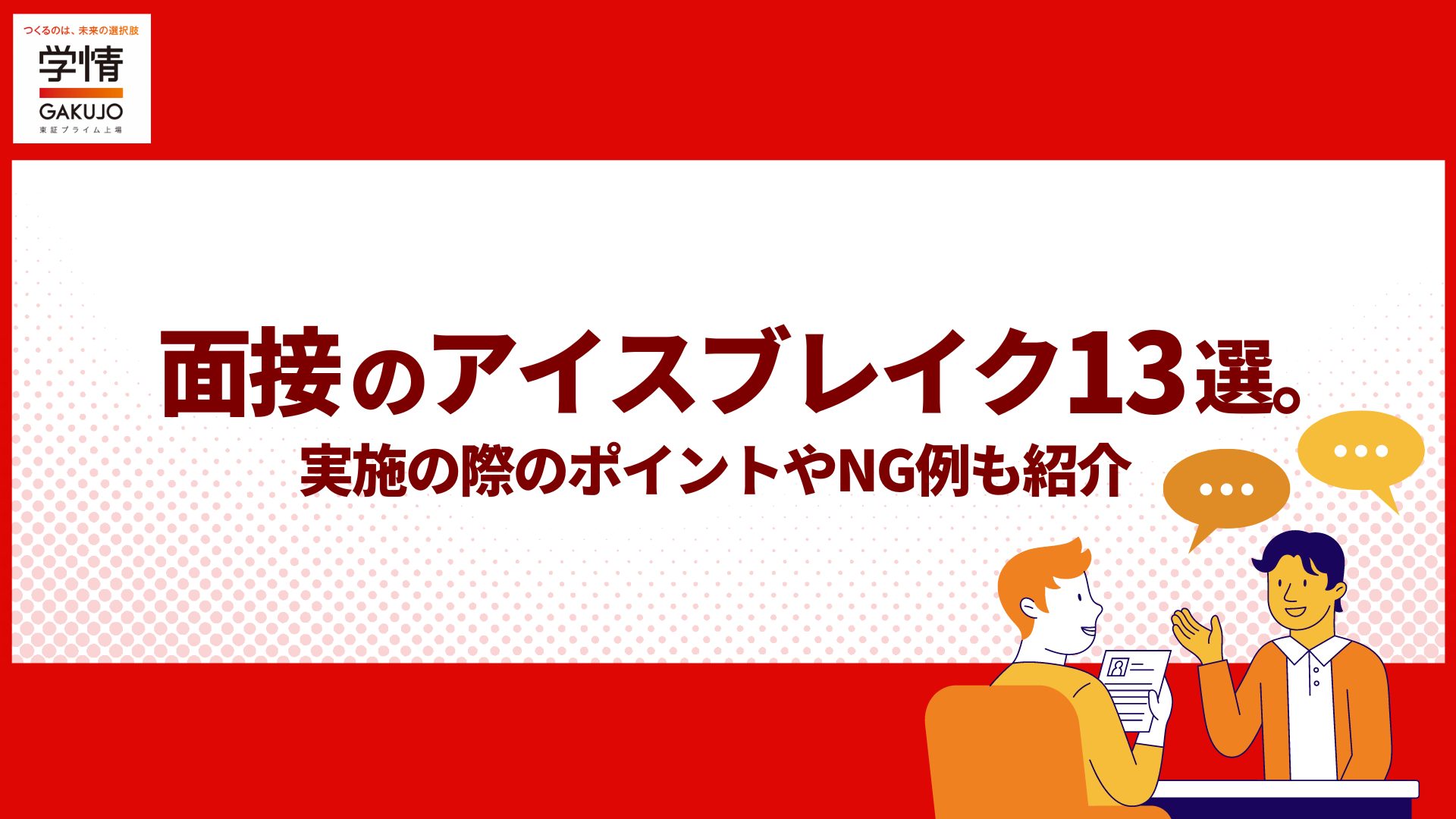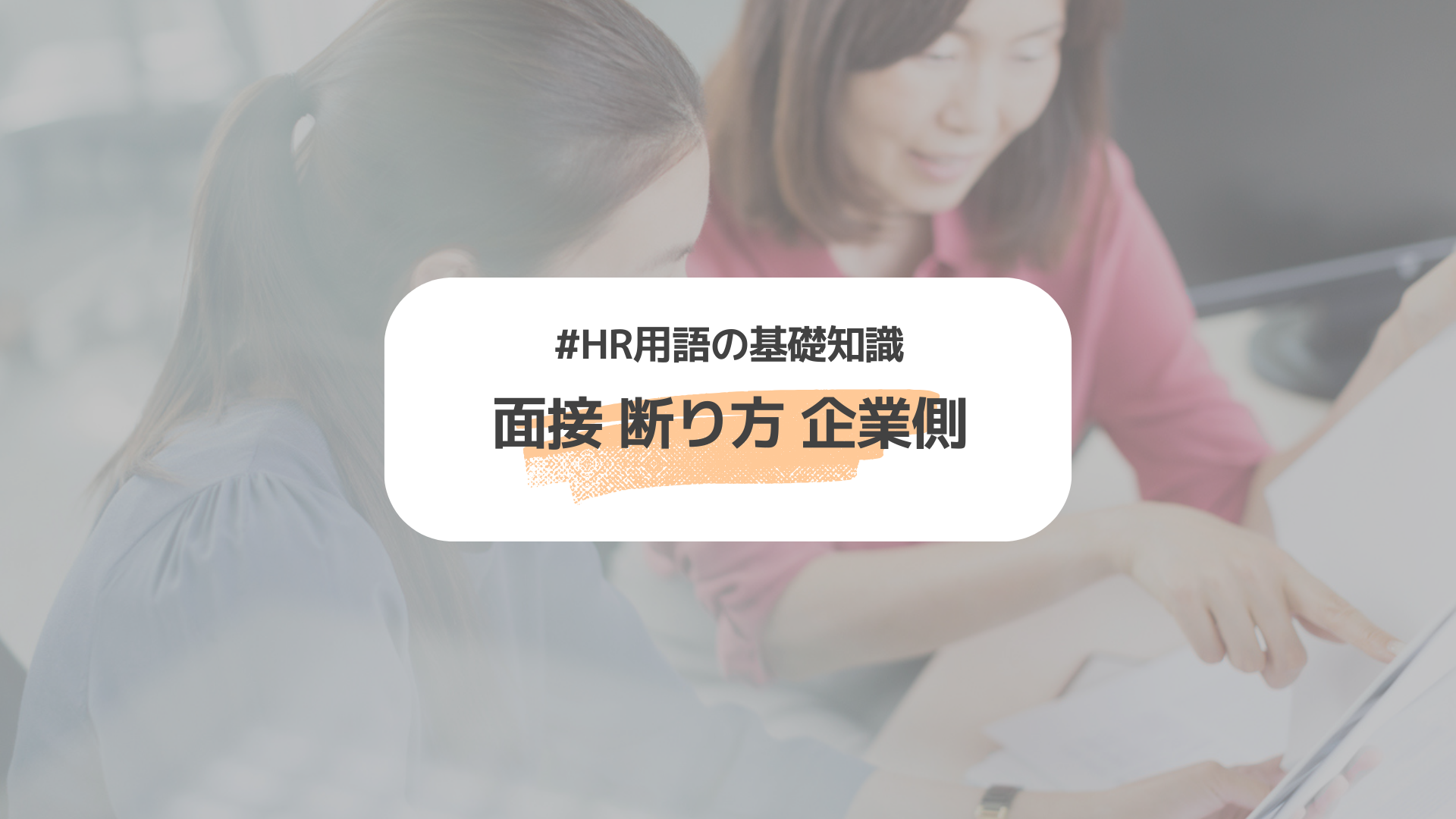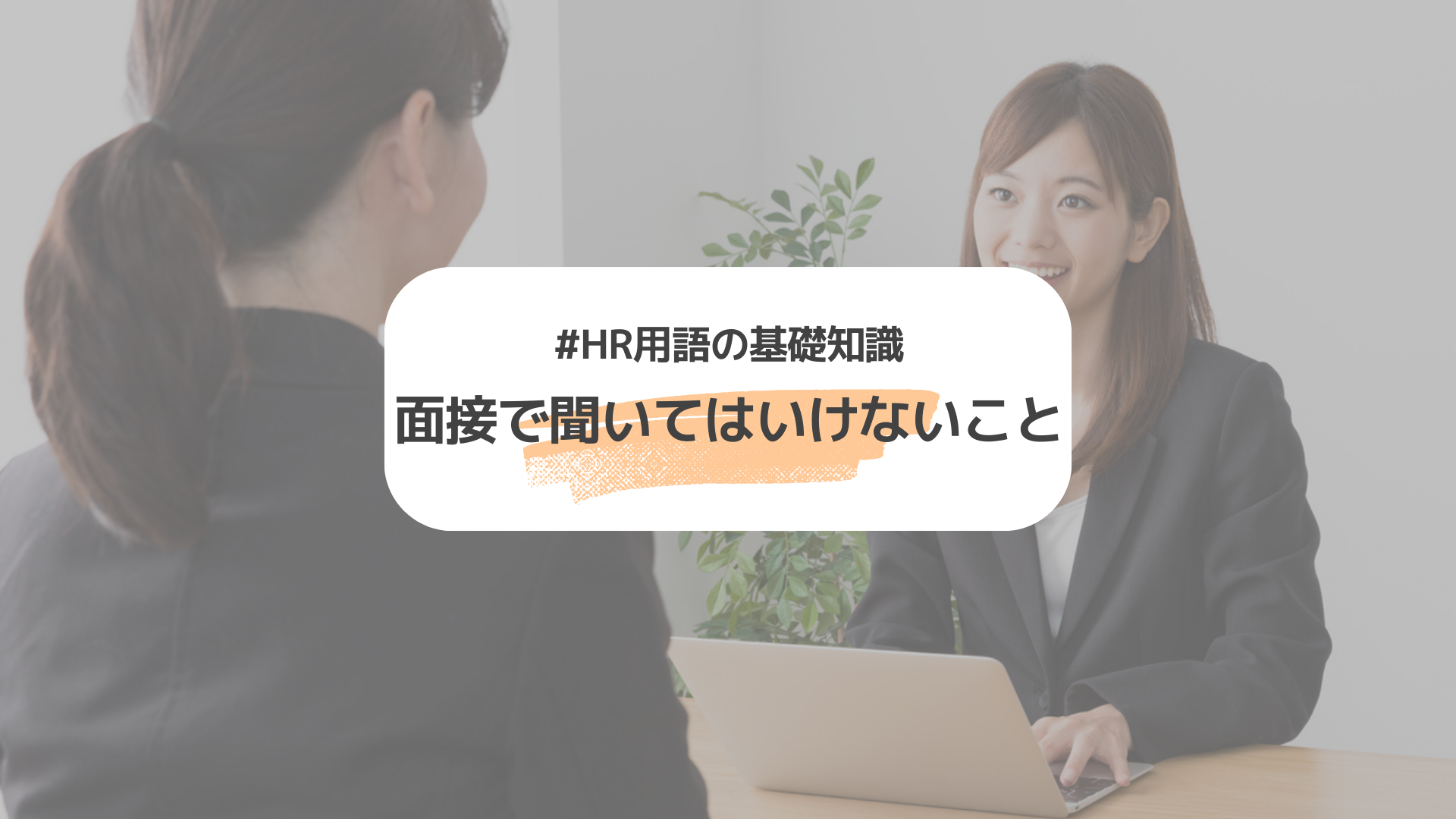
採用活動における面接では、応募者に何を聞いても良いわけではありません。厚生労働省では企業が公正な選考採用を行うよう、採用面接で聞いてはいけない事項を定めています。
優秀な人材を獲得するには、応募者に不快な思いをさせないことが大切です。採用担当者は優秀な人材を逃さないよう、聞いてはいけない事項をおさえておきましょう。
本記事では、採用面接で聞いてはいけない質問や聞いてしまったときに与える影響などを解説します。
【原則】採用面接に求められる考え方

厚生労働省では、採用選考において次の2点を基本的な考え方としています。
- 応募者の基本的人権を尊重すること
- 応募者の適性・能力に基づいて行うこと
企業には応募者を差別せず、公正な選考を行うように求めています。
また、公正な採用選考の基本として「応募者に広く門戸を開くこと」「本人のもつ適性・能力に基づいた採用基準とすること」の2点をあげています。
公正な採用選考を行うには、自社の雇用条件や採用基準に合うすべての人が応募できる環境を作ること、応募者の適性や能力で公正に選考することが必要です。たとえば、本籍地や家族構成、支持政党などは、本人の適性や能力に関係がないため、採用基準にしてはいけません。
※出典:厚生労働省「公正な採用選考の基本」
【法律違反の可能性】採用面接で聞いてはいけない13のタブー質問

厚生労働省の「公正な採用選考の基本」では、採用選考時に配慮すべき事項を定めています。これらの事項は採用基準にしてはいけないため、企業が把握する必要はありません。
企業側は把握するつもりがなくても、応募書類に記入させたり面接で質問したりすることは、基本的な考え方から逸脱しており、就職差別につながるおそれがあります。
最悪のケースでは法律違反と見なされ、何らかの処分を受ける可能性もあるため、注意が必要です。
採用面接で配慮すべき事項は、次の3つに分けられます。
- 本人に責任のない事項
- 本来自由であるべき事項
- そのほか気を付けなければならない事項
ここからは、採用面接で配慮すべき、聞いてはいけない事項とその質問例を紹介します。
本人に責任のない事項
ルーツや環境などは、応募者本人に責任がない事項です。採用面接で聞くことは就職差別につながるリスクがあります。
1.本籍・出生地に関すること
応募者の本籍や出身地に関することは、本人に責任がないため、採用面接で聞いてはいけません。
たとえば次のような質問は避けるべきです。
- あなたの本籍地はどこですか?
- 生まれてからこれまで同じ住所に住んでいますか?
- ご両親はどちらのご出身ですか? など
戸籍謄本や本籍が記載された住民票を提出させることも、就職差別に該当するおそれがあるため、適切ではありません。
2.家族に関すること
採用面接では、家族に関する質問にも配慮すべきだとされています。家族に関することとは、職業・続柄・健康・病歴・地位・学歴・収入・資産などです。これらの事項も採用面接では聞かないようにします。
家族に関する質問例は、次のとおりです。
- あなたのご両親は共働きですか?
- 家族構成を教えてください。
- ご両親の健康状態は良好ですか? など
3.住宅状況に関すること
採用面接では、応募者の自宅の間取りや部屋数、物件種別、周辺施設などの住宅状況に関することも配慮すべきとされています。
住宅環境に関する質問例は、次のとおりです。
- どのような間取りの家に住んでいますか?
- 自宅は戸建てですか?
- 自宅は持ち家ですか? など
住宅環境も応募者の適性や能力に直接関係がありません。採用面接では聞かないようにしましょう。
4.生活環境・家庭環境に関すること
採用面接では、応募者の生活環境や家庭環境に関することも配慮すべきです。
生活環境や家庭環境に関する避けるべき質問例は、次のとおりです。
- 自宅は〇〇駅のどちら側ですか?
- あなたは長男ですか?
- 家業を継ぐ予定はありますか? など
生活環境や家庭環境に関する質問は、応募者と家族の生活水準を推測し、それを基準に評価してしまうリスクがあります。
応募者をリラックスさせるためのアイスブレイクとして使用した場合でも、職業差別と見なされる可能性があるため、注意が必要です。
本来自由であるべき事項
価値観や支持政党などは人によってさまざまで、本来自由であるべき事項です。
5.宗教に関すること
応募者の宗教に関することは本来自由であるべき事項として、配慮すべきとされています。たとえば次のような質問は、避けるべきです。
- 何の宗教を信仰していますか?
- あなたは神や仏を信じますか? など
日本国憲法第20条では、信教の自由が保障されています。
応募者の信仰する宗教を採用基準にすることは、憲法の精神に反します。信仰する宗教は応募者の適性や能力に直接関係がないため、採用面接では質問しないようにしましょう。
6.支持政党に関すること
応募者の支持政党に関することも本来自由であるべき事項です。支持政党に関する次のような質問はしないようにしましょう。
- あなたは何党を支持していますか?
- 前回の選挙では誰に投票しましたか?
- ご家族は何党を支持していますか? など
採用面接では応募者本人だけでなく、家族の支持政党に関する質問も避けます。
また、2016年6月より選挙権が20歳から18歳に引き下げられたことから、たとえば高校生のアルバイトの採用面接で「選挙に行きましたか?」といった質問をするケースがあるかもしれません。しかし、年齢を問わず応募者の投票行動や政治的な活動に関する質問は、それを基準にした評価につながるおそれがあるため、聞かないようにしましょう。
7.人生観・生活信条に関すること
応募者の人生観や生活信条に関することも、採用選考では配慮すべきとされています。
信条とは「自分が思考・行動するときの決めごと」を意味し、本来自由であるべき事項です。たとえば次のような質問を指します。
- あなたは何を信条としていますか?
- あなたの人生観は何ですか? など
採用面接では応募者の人生観や生活信条を推しはかり、評価の対象にするような質問は避けるようにしましょう。
8.尊敬する人物に関すること
本来自由であるべき事項として、応募者の尊敬する人物に関することに関しても配慮すべきとされています。
次のような質問は、就職差別につながるおそれがあるため、注意しましょう。
- あなたが尊敬している人は誰ですか?
- あなたには将来の目標とする人はいますか? など
尊敬する人物は応募者の思想・信条に関わる可能性があります。また、日本国憲法第19条では思想の自由が保障されており、本来自由であるべき事項です。働く上で関係のないことのため、採用面接では質問しないようにしましょう。
9.思想に関すること
応募者の思想に関することは本来自由であるべき事項として、配慮すべきです。就職差別につながるおそれがある思想に関する質問例は、次のとおりです。
- 自分の生き方についてどのように考えていますか?
- 今の世の中をどう思いますか? など
思想の自由は日本国憲法第19条で保障されており、採用選考に持ち込むと基本的人権を侵害する可能性があります。
応募者の思想を詮索するのはプライバシーの侵害になるため、たとえ表現を変えても質問しないようにしましょう。
10.社会運動に関すること
応募者の社会運動に関することも配慮すべきです。社会運動とは、労働組合や学生運動などを指します。
次のような質問は避けましょう。
- 労働組合への加入歴はありますか?
- 学生運動に参加した経験はありますか? など
応募者本人が社会運動へ参加したかどうかだけでなく、デモに対する考え方を聞くこともタブーとされています。
11.愛読書に関すること
アイスブレイクに聞きがちな応募者の愛読書に関することも、配慮すべき事項に含まれています。たとえば次のような質問です。
- 現在購読している新聞は何新聞ですか?
- あなたの愛読書を教えてください など
愛読書に関する質問は、応募者本人の思想信条を探ることにつながりかねません。応募者の緊張をほぐすためのアイスブレイクでも、質問しないように注意しましょう。
そのほか気を付けなければならない事項
本人に責任のない事項や本来自由であるべき事項のほかに、採用面接では配慮すべきとされている事項があります。
12.男女雇用機会均等法に抵触すること
男女雇用機会均等法は、性別に関わらず均等な雇用を得て、意欲と能力に応じた均等な待遇を受けられることを目的としています。
応募者の男女差別につながる質問は、男女雇用機会均等法に抵触するおそれがあるため、タブーとされています。たとえば次のような質問です。
- 結婚の予定はありますか?
- 出産の予定はありますか?
- 出産後も働く予定ですか?
- スリーサイズは?(制服のサイズ確認など) など
応募者の返答に応じて採用・不採用が判断される要素になる場合は、採用選考に性差別を用いていると判断されます。
これらの質問は相手に不快感を与えるだけでなく、企業のイメージ低下や法律に抵触する恐れがあるため、注意しましょう。
13.容姿に関すること
容姿に関することも配慮すべき事項です。次のような質問は避けましょう。
- あなたの身長は何センチですか?
- あなたの体重は何キロですか? など
ただし、一定の身体能力が求められる職業(自衛隊など)は、正当な理由がある場合に限り認められるケースもあります。
必ずしも法律違反にはならないが注意すべき面接の質問例
法律上ただちに違反とまでは言えないものの、質問の意図や深掘り次第では差別・プライバシー侵害と受け取られかねない項目も少なくありません。企業イメージや候補者体験に影響を与えやすい点を把握し、適切に対応しましょう。
ここでは特に注意したい代表例を確認していきます。
犯罪歴について
犯罪歴は応募者のプライバシーに深く関わる機微情報であり、職業安定法上ただちに違法とまでは言えませんが、公正な採用選考を損なう恐れがあります。警備業法などで確認義務がある職種を除き、原則として質問は控えるべきです。
どうしても必要な場合は、職務遂行上の合理性を明示し、質問範囲と利用目的を限定するとともに、本人同意を得て厳重に管理することが必須です。過去の犯罪歴の有無を二者択一で尋ねるのも社会復帰を妨げると受け取られやすいため、就業規則への誓約書提出などの代替手段でコンプライアンスを担保する方法を検討してください。
在宅勤務の可否について
在宅勤務の可否を尋ねること自体は違法ではありませんが、育児・介護・障害など個々の家庭事情を掘り下げる形になると間接差別やプライバシー侵害に発展するリスクがあります。
質問する際は「当社は週3日以上出社必須ですが対応可能ですか」など職務要件に即した具体条件に絞り、理由追及は控えるのが原則です。対応が難しい応募者には時差通勤や出社頻度調整など代替策を提示し、公平な評価基準で選考しましょう。
コロナ禍以降は地方居住・海外勤務希望も増えているため、勤務時間帯や情報セキュリティ要件を明文化し、標準化した質問票で運用するとトラブル防止に有効です。
採用面接で聞いてはいけない質問をしたときの企業への影響

採用面接で応募者に聞いてはいけない質問をした場合、相手に不快感を与えるだけでなく、企業に大きなダメージを与える可能性があります。
法律違反行為と見なされると懲役や罰金の対象になるため、採用面接での質問には細心の注意を払う必要があります。
法律違法行為と見なされるリスクがある
- 人種
- 民族
- 社会的身分
- 門地
- 本籍
- 出生地
- 家族の職業
- 家族の収入
- 資産状況
- 容姿
- スリーサイズ など
- 人生観
- 生活信条
- 支持政党
- 購読新聞
- 購読雑誌
- 愛読書 など
- 労働運動
- 学生運動
- 消費者運動 など
これらに違反した場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることもあります。
企業のイメージ低下につながる可能性がある
近年、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSを利用する人が増えています。それに伴い、SNSを利用して採用活動を行う企業も増えました。SNSは便利なツールである一方、一つの投稿が社会を巻き込む大きな事態に発展しかねない側面もあります。
採用面接で不快な質問をされた応募者がその内容をSNSに投稿する可能性があります。印象の悪い内容が拡散されると、企業イメージの低下につながるおそれがあるでしょう。
企業イメージが低下すると、自社への応募者が減るでしょう。すでに優秀な人材を獲得していても、SNSによる悪評がきっかけとなり、内定辞退者が出てくることも考えられます。
また、企業イメージが低下することで顧客や取引先の信用を失い、業績に悪影響を及ぼすケースもあります。
採用面接を正しく行うために企業が事前に準備すべきこと

採用面接を適切に行うために、まずは自社の採用活動に関する内容を見直してみましょう。
採用基準を明確にする
採用面接を正しく行うためには、自社の採用基準を見直し、明確にすることが大切です。
採用基準が曖昧な場合、面接官によって質問内容にブレが生じ、聞いてはいけない質問をしてしまう可能性があります。
自社の採用基準を明確にしておけば、聞いてはいけない質問を避け、公平で客観的な評価ができるようになるでしょう。応募者が自社に合う人物かを正しく見極められるようにもなるため、優秀な人材の獲得が期待できます。
採用要件、評価基準、質問項目をすべて事前に決めておく「構造化面接」の手法を取り入れることも有効です。構造化面接について詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。
面接官の教育を徹底する
採用面接を正しく行うためには、面接官の教育も必要です。
企業側が採用面接で聞いてはいけない内容を把握していても、面接官に共有していなければ、リスクは避けられません。
まずは採用面接用のマニュアルを作成し、すべての面接官に共有しましょう。内容がきちんと共有されたかを確認するためには、定期的な模擬面接の実施が有効です。
面接官の教育を徹底すると、採用面接で聞いてはいけない質問をしてしまうリスクを避けられます。
採用面接での質問を事前にまとめておき、面接官に共有しておくことも有効です。質問例を知りたい方は以下のページをご覧ください。
面接評価シートを活用する
採用面接で聞いてはいけない質問を避けるには、面接評価シートの活用が効果的です。
面接評価シートとは、自社で決めた評価項目や評価基準が記載されているシートです。質問内容が固定されているため、聞いてはいけない質問をしてしまうリスクを避けられます。
項目や基準に沿って採用面接を進められるため、面接官ごとのブレを軽減し、自社に合う人物を見極めやすくなります。
正しい採用面接を行うには企業全体で認識を合わせることが大切

採用面接では、たとえ自社に合う人物を見極めるためでも、応募者に不快感を与えるような質問をしてはいけません。近年は、聞いてはいけない質問をしてしまった事実がSNS拡散され、企業イメージを低下させるリスクもあります。
採用面接を適切に行うにはマニュアルの見直しや研修などで、企業全体で認識を合わせておくことが重要です。
また、近年は生産年齢人口の減少により、人材獲得が激化しています。採用活動を慎重に進めても自社が求める人材が必ず見つかるとは限らないのが現状です。
効率的に採用活動を進めるには、転職サイトを活用するのも選択肢の一つです。株式会社学情では、20代向けの転職サイト「Re就活」を運営しています。Re就活の登録会員の多くは20代なので、若手の優秀な人材を獲得できる可能性があります。
企業様のニーズに対応したさまざまなプランをご用意しておりますので、採用活動にお悩みの場合はぜひご相談ください。

株式会社学情 エグゼクティブアドバイザー(元・朝日新聞社 あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)編集長)
1986年早稲田大学政治経済学部卒、朝日新聞社入社。政治部記者や採用担当部長などを経て、「あさがくナビ(現在のRe就活キャンパス)」編集長を10年間務める。「就活ニュースペーパーby朝日新聞」で発信したニュース解説や就活コラムは1000本超、「人事のホンネ」などでインタビューした人気企業はのべ130社にのぼる。2023年6月から現職。大学などでの講義・講演多数。YouTube「あさがくナビ就活チャンネル」にも多数出演。国家資格・キャリアコンサルタント。著書に『最強の業界・企業研究ナビ』(朝日新聞出版)。