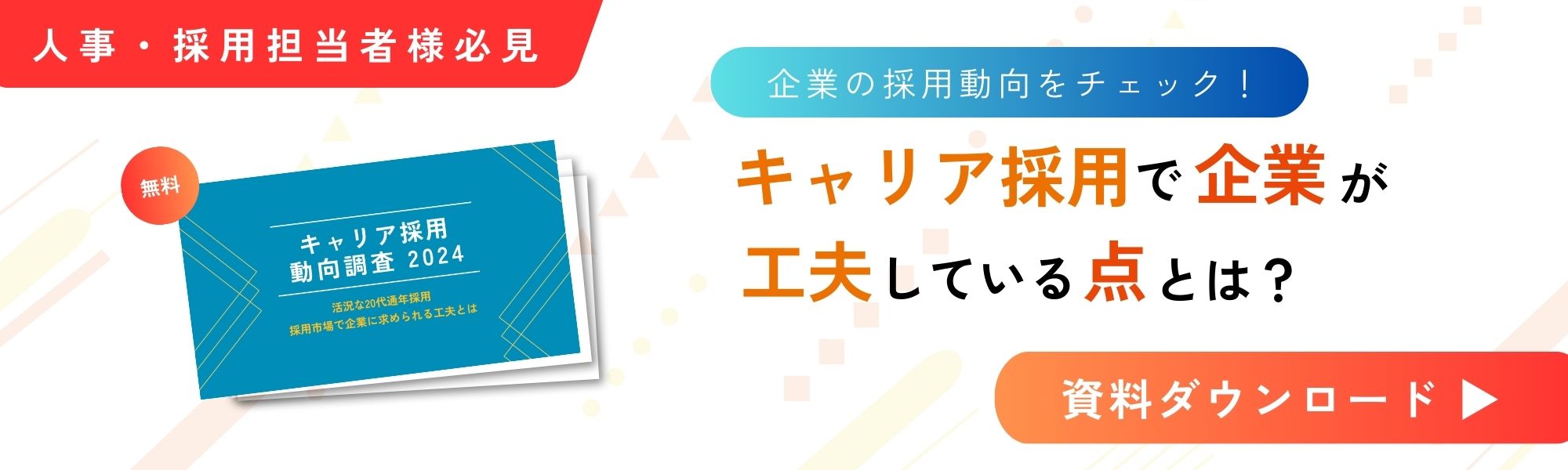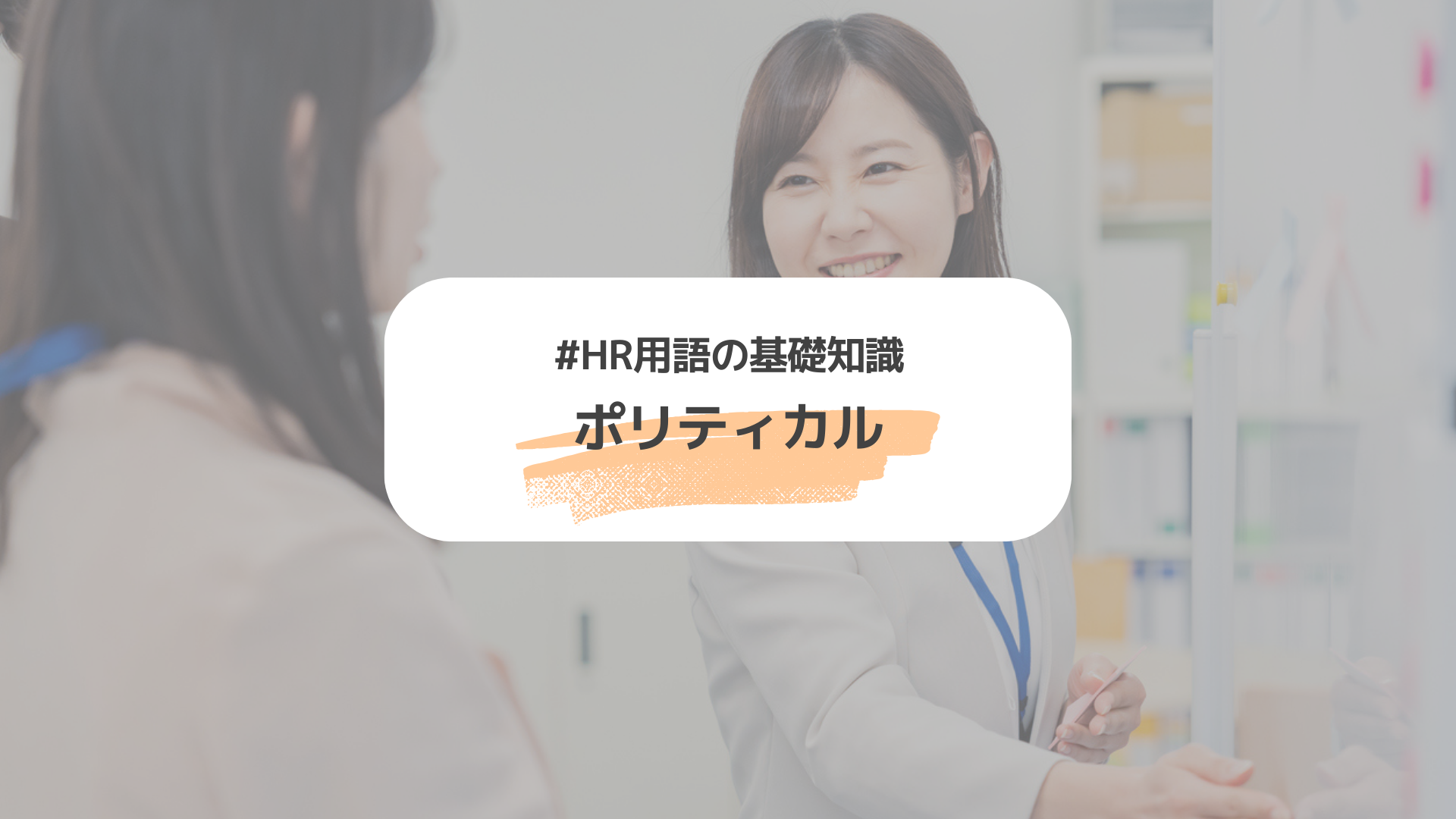ダイバーシティ・インクルージョンとは?具体的な企業の取り組み事例を紹介
公開日:2023.06.21
更新日:2025.02.11


「ダイバーシティ・インクルージョン」という言葉を初めて聞いた人もいるのではないでしょうか。聞いたことはあるけれど詳しい意味や目的、内容はよく分からないという場合もあるでしょう。
ダイバーシティ・インクルージョンとは、性別や国籍、文化や価値観などさまざまなアイデンティティを持つ者がお互いを認め合いながら企業の一体感を醸成し、成長を促すための取り組みです。
本記事ではダイバーシティ・インクルージョンの意味や目的、メリットを詳しく解説します。国や企業が行っている具体的な取り組みや導入方法も紹介するので、企業の抱える問題解決やさらなる成長のための参考にしてください。
ダイバーシティ・インクルージョンとは

「ダイバーシティ」は「多様性」という意味です。ビジネスシーンでは「多様な人材を社内で受け入れ、チームや組織の生産性を高める」という意味で使われています。
「インクルージョン」は「包括」や「包含」という意味を示します。ビジネスシーンでは「国籍や性別、障がいの有無に関わらず、多様な人がお互いを認め合い一体となって働いている状態」を意味する言葉として使われます。
「ダイバーシティ・インクルージョン」は、これら2つを両立している取り組みや考え方のことです。
性別や年齢、国や文化、働き方など、さまざまな価値観を持つ人材を活用し、それらの多様性を受け入れ、お互いに認め合いながら組織の一体感を醸成することで成長と変化を促進する取り組みが「ダイバーシティ・インクルージョン」です。
ダイバーシティ・インクルージョンが注目される背景

ダイバーシティ・インクルージョンは、市場のグローバル化やニーズの多様化、労働人口の減少、ワークスタイルの変化などに対応するために注目され始めました。
国外市場が発展し急速に変化する現代社会において、企業は多様な価値観を持った人材を活用してさまざまな考え方を取り入れ、変化・成長していく必要性が高まっています。
さらに少子高齢化の影響で、企業は人材の確保が深刻な課題となりました。そのため、性別や年齢、働き方や価値観など、働く人の多様性を認め、受け入れながら柔軟に対応していく姿勢が重要視されています。
ダイバーシティ・インクルージョンの3つのメリット

ダイバーシティ・インクルージョンのメリットは次の3つです。
- 人材を確保しやすくなる
- 新たなイノベーションが生まれる
- 従業員のモチベーションが高まる
それぞれのメリットを詳しく紹介します。
人材を確保しやすくなる
性別や年齢、国籍や文化などにとらわれず雇用することで、従来の採用基準が柔軟になり、より雇用できる人材の幅が広がります。さまざまな価値観を受け入れる姿勢を持つ企業は、従業員の満足度が高く、就業定着率の向上も見込めます。
ここで、就職活動を行う学生を対象に取ったアンケート結果を見てみましょう。
「Re就活キャンパス2024」による「ダイバシティ&インクルージョン(D&I)」をテーマにした2024年卒学生の意識調査では、「ダイバシティ&インクルージョン(D&I)」の取り組みを知ると「志望度が上がる」という回答が6割を超えました。
回答のなかには「個性を活かして働けそう」「私たちの世代の価値観とも合致している」といった声もあり、「ダイバシティ&インクルージョン(D&I)」を推進する企業に好感を持つといった回答が8割を超える結果となりました。
このように、ダイバーシティ・インクルージョンの取り組みは企業への高評価とつながり、求職者の志望度を上げるきっかけにもなります。
新たなイノベーションが生まれる
多様な人材の登用によって、発想の固定化を防げることもメリットです。さまざまな価値観や視点、背景や考え方を持った人たちが働く環境では、新たなイノベーションが生まれやすくなるでしょう。今までにはなかった視点で、新しい商品やサービスが生まれる可能性も高まります。
人材が画一化した企業では、発想の方向性や販売・営業方針なども固着しがちです。従来のやり方や考え方をなかなか刷新できない場合もあるでしょう。
しかし、ダイバーシティ・インクルージョンの取り組みによってさまざまな価値観や背景を持った多様な人材が投入されると、企業に新たな風が吹き込み、変化・成長を促すことが期待できます。
従業員のモチベーションが高まる
ダイバーシティ・インクルージョンの取り組みのもとでは、従業員の個性を活かし、それぞれが活躍できる場となるため、個々のモチベーションが高まり、成長しやすい環境作りが実現できます。
さまざまな価値観や多様性を認めることで、「企業の一員として必要とされている」といった感覚や、「自分もここで能力を発揮して働ける」といった考えを持ちやすくなります。
従業員のモチベーション向上に加えて、企業への愛着心やエンゲージメント向上、離職防止にもつながります。
ダイバーシティ・インクルージョンの問題点

現代社会で必要とされるダイバーシティ・インクルージョンの取り組みですが、メリットだけではなく、問題点も抱えています。
たとえば、次のような問題があげられます。
- チームワークの一時的な低下
- 新たな人材が目立つことによる差別や排他意識の助長
- パワハラ・モラハラなどのコミュニケーション障害
- 評価が変化したことに対する既存従業員の不満
新しい取り組みを導入する際には、一時的に混乱やトラブルが発生する可能性もあります。新たに登用する人材や特定の層の人材だけでなく、すべての従業員に対して公平な仕組みにできていなければ反発が起きるリスクもあります。
既存従業員においては、変化を受け入れられない場合もあります。ダイバーシティ・インクルージョンの目的や意味を理解しないまま推進すると、何らかの問題が起きかねません。
導入時にはすべての従業員に対して十分な説明を行うことが必要です。ダイバーシティ・インクルージョンの必要性と、導入する目的や意味をわかりやすく伝えて、誤解のないように理解してもらうことが必要です。平等で公平な機会が与えられる取り組みであることをしっかりと伝えましょう。
ダイバーシティ・インクルージョンに関する国の取り組み

国としての取り組みには、内閣府の「女性活躍推進法」や厚生労働省の「職場におけるダイバーシティ推進事業」、経済産業省の「ダイバーシティ経営の推進」などがあげられます。それぞれの内容を詳しく解説していきます。
内閣府「女性活躍推進法」
平成27年8月に内閣府が発表した「女性活躍推進法」は、妊娠や出産で離職した女性に対して、再就職や正規雇用の環境改善を目指す取り組みです。
従業員が300人を超える企業では、女性の働き方に関する現状を把握し、行動計画を策定することが法律によって義務付けられました。
※出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html
厚生労働省「職場におけるダイバーシティ推進事業」
令和元年度に厚生労働省は「多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集」のリーフレットを作成しました。これからダイバーシティ・インクルージョンに取り組む企業に向けて具体的な事例を示し、導入を促す資料です。
さまざまな企業の実例を紹介しながら、ダイバーシティ・インクルージョンに賛同する意義や、意識している取り組みのポイントなどを盛り込み、ダイバーシティ・インクルージョンの理解を促しています。
さらに詳しくは、厚生労働省厚生労働省「障害者雇用促進法・高年齢者雇用安定法」もご覧ください。
厚生労働省「障害者雇用促進法・高年齢者雇用安定法」
厚生労働省は、障がい者や高年齢者の雇用に関して「障害者雇用促進法」と「高年齢者雇用安定法」を制定しています。
障害者雇用促進法は、障がい者の安定雇用を促し、能力や適性に応じた雇用機会を創出することで、誰もが自立した生活ができる社会を目指す法律です。企業は従業員の一定割合以上で障がい者の雇用義務があり、障がい者を雇用する企業は、設備投資などの負担を軽減する「障害者雇用納付金制度」を利用できます。
高年齢者雇用安定法は、意欲のある高年齢者が長く働き続けられるように雇用の確保や職場環境を整備する目的で施行されました。
これらの法律によって、すべての方が自立した生活を送ることを目指しています。
経済産業省「ダイバーシティ経営の推進」
経済産業省では、「新・ダイバーシティ経営企業100選」や「なでしこ銘柄」など優れた企業を選定し、先進事例として情報発信しています。
また、「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」を作成し、企業がとるべき行動も公表しました。日本の経済を持続的に成長させるため、経済産業省では企業の経営戦略としてのダイバーシティ経営を推進しています。
女性をはじめとする多様な人材が活躍できる環境を整えることは、少子高齢化社会で人材を確保し、現代の市場ニーズやリスクへの対応力を高めるために必要不可欠な取り組みであると言えるでしょう。
ダイバーシティ・インクルージョンの一般企業の取り組み事例

女性を継続的に登用
女性を継続的に登用している企業では、女性が働きやすい環境を整え、働きがいのある職場環境の整備に取り組んでいます。
女性リーダー候補の選抜型研修や各種ワークショップを実施。実際にこの取り組みを始めてから女性が管理職に就任する割合が上がっています。
多様な考え方があることを発信
多様な考え方を発信している企業では、LGBTQに対する無意識のバイアスを解消するため、社内アンケートなどで意見を集めて結果を共有しています。
さまざまな考え方があるという気づきの場を設けることで、多様な人材が企業の中で存在位置を持ち、互いに認め合いながらそれぞれのパフォーマンスを発揮し、共存していくことを目指しています。
多様な働き方に対応できる新制度の採用
多様な働き方に対応した新制度を採用している企業も増えています。たとえばテレワークで就業場所を選ばない働き方を採用することや、副業を容認すること、フリーアドレスのオフィスにすることなどがあげられます。
そのほかにも、多様な人材が自由に発言できる環境づくりのため、ビジネスカジュアルの導入や役職名ではなく「さん付け」で呼ぶといった取り組みを行っている企業もあります。
育児や介護サポート制度の拡充
性別に関係なく育休や産休を取りやすくするため、育児や介護を支援する制度に力を入れている企業も増えています。
また、育児や介護などの家庭の事情がある方に向けて、時短勤務やフレックス制度、時差出勤や在宅勤務など、働く場所や時間を柔軟に選べるサポート制度を導入する企業もあります。
従業員の強みを生かした人材配置
年齢や社歴に関係なく、従業員の強みが生きる人材配置にする取り組みも行われています。企業経営においては、従業員一人ひとりが持つ能力やスキルを最大限に発揮できるよう、必要に応じた人材の配置転換・適材適所が求められるケースが往々にしてあります。
具体的なステップとして、まずは、上司や人事担当者が従業員との定期的な面談を行い、個々のキャリアを踏まえた能力・スキルを把握するようにします。また一定の業務期間を終えた際は、自社で成し遂げた業績およびプロセスについて細かく評価します。これらの情報に基づいて、企業の人員計画と照らし合わせた最適な人員配置を考えることができます。
従業員の適性を慎重に見極める際は、個々の強みや長所がわかる外部の適性検査サービスを利用するのも一つの方法です。社内では認識していなかった従業員の強みを発見できるため、最適な人材配置に生かせることができるでしょう。
ダイバーシティ・インクルージョンを自社に実現させるための方法

ダイバーシティ・インクルージョンを実現させるための方法は、次のとおりです。
- 従業員全員の意識を改革する
- 目標を数値で可視化する
- 自社の状況を踏まえて取り組みを検討する
- 外部サービスの活用を検討する
一つずつ詳しく見ていきましょう。
従業員全員の意識を改革する
ダイバーシティ・インクルージョンに取り組む際は、まず目的を明確にしてすべての従業員に共有し、十分な説明を行いましょう。
社内セミナーや研修などでダイバーシティ・インクルージョンについて理解を深める機会を設け、管理職も含めた全従業員にしっかりと理解してもらうことが大切です。
セミナーや研修では次のような内容を盛り込むと良いでしょう。
- ダイバーシティ・目標を数値で可視化する
偏見や無意識の思い込みがあると、ダイバーシティ・インクルージョンの考え方は浸透しません。そのためセミナーや研修では、ダイバーシティ・インクルージョンの目的や意義、メリットを伝えるだけでなく、それぞれが持っている無意識の思い込みや偏見に気づくことが必要です。
目標を数値で可視化する
「採用数」や「離職率」「管理職比率」「従業員満足度」などの具体的な目標数値を設定します。
目標が明確になっていないと、形ばかりの取り組みになってしまう恐れがあります。数値で可視化されていれば目標への進捗状況も把握できるため、具体的な数値にして共有しましょう。
自社の状況を踏まえて取り組みを検討する
他社で成功している取り組みでも、自社には合わない可能性があります。そのため、自社の現状を把握し、自社が抱えている課題を解決するための取り組みや、現場の状況に合った取り組みを検討しましょう。
さまざまな企業の導入事例を参考に、自社ではどのような取り組みを行えば問題解決や事業の成長につながるのかを考えて計画することが大切です。
外部サービスの活用を検討する
ダイバーシティ・インクルージョンを掲げたからといって、すぐに多様な人材が集まるわけではありません。多様な人材を採用するためには外部サービスを活用するのもおすすめです。
たとえば、学情の採用支援サービス「Re就活キャンパスJapan Jobs」では、外国人留学生へもアプローチできます。「多様な人材を採用して社内を活性化したい」「海外展開に向けた人材を雇用したい」「国籍は関係なく優秀な人材を確保したい」という目的や目標がある場合、ぜひ活用してみてください。
また、自社に欲しいタイプのターゲットに絞った内容の会社案内パンフレットを作成して、学生や求職者へアピールする方法も有効です。
多様性を認め合う風土を醸成し社内を活性化させよう

ダイバーシティ・インクルージョンは、少子高齢化による労働人口の減少や市場のニーズに対応し、企業が持続的に成長していくために不可欠な取り組みです。
働き方や価値観が多様化する現代において、さまざまな考え方を受け入れ、認め合いながらそれぞれの持つ個性や能力を発揮していくことが求められています。
また、取り組みを行う際には、すべての従業員に対して目的や意義、メリットなどを説明しましょう。理解不足のまま取り組みを推進すると、不満や反発を生む可能性があるからです。
説明する際には偏見や無意識の思い込みによるデメリットがあることも説明し、それらに気づくことが大切な第一歩となります。
多様な人材が持つさまざまな価値観を認め合い、それぞれの能力を活かし合える風土を醸成し、社内を活性化させましょう。

就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、株式会社学情が運営するオウンドメディアです。