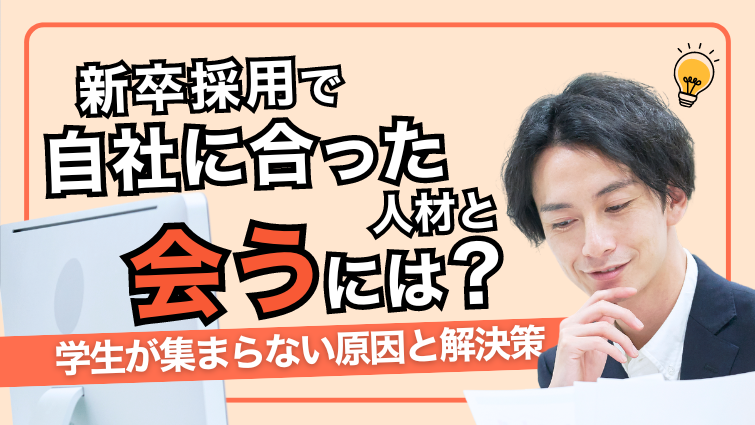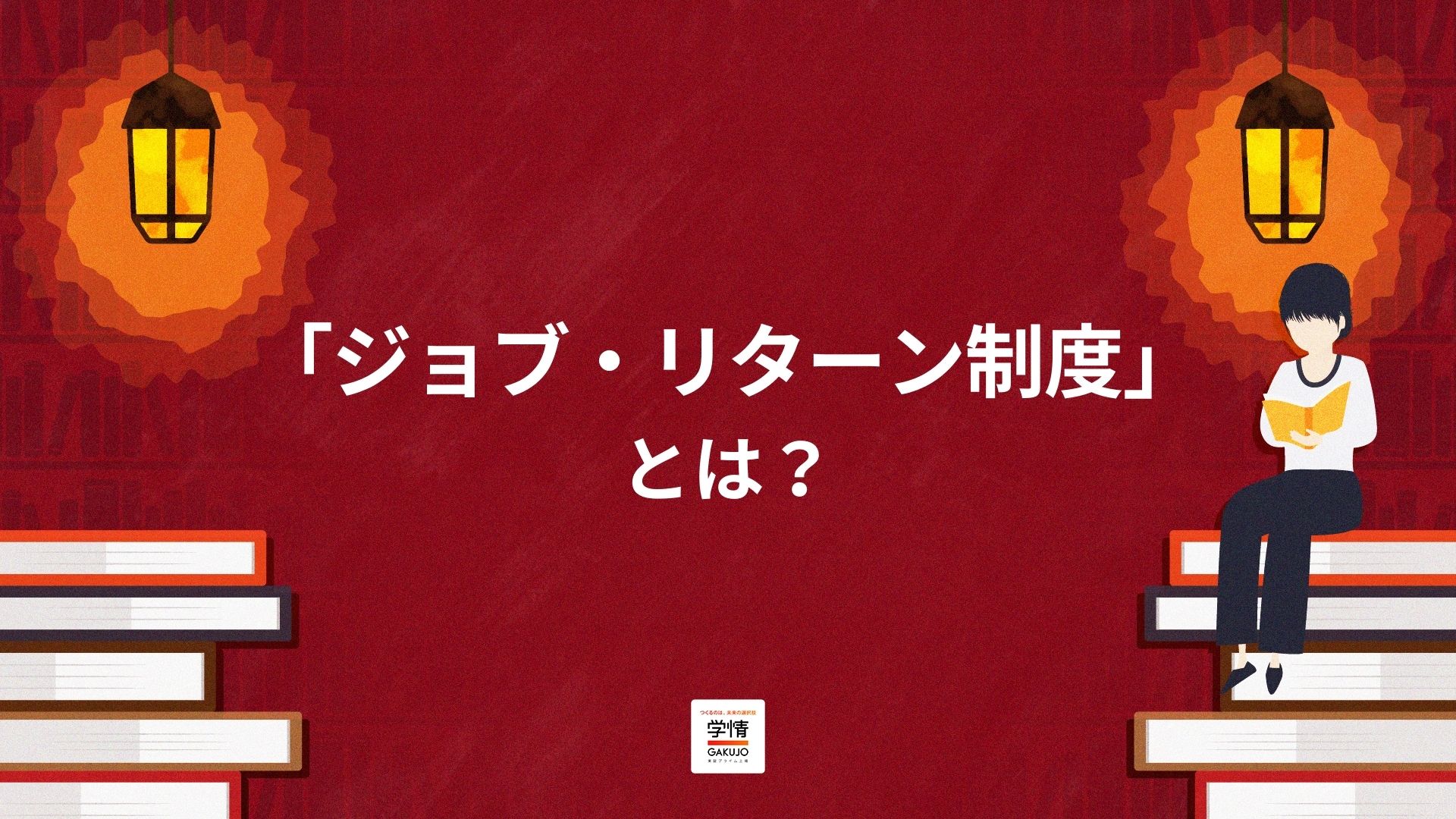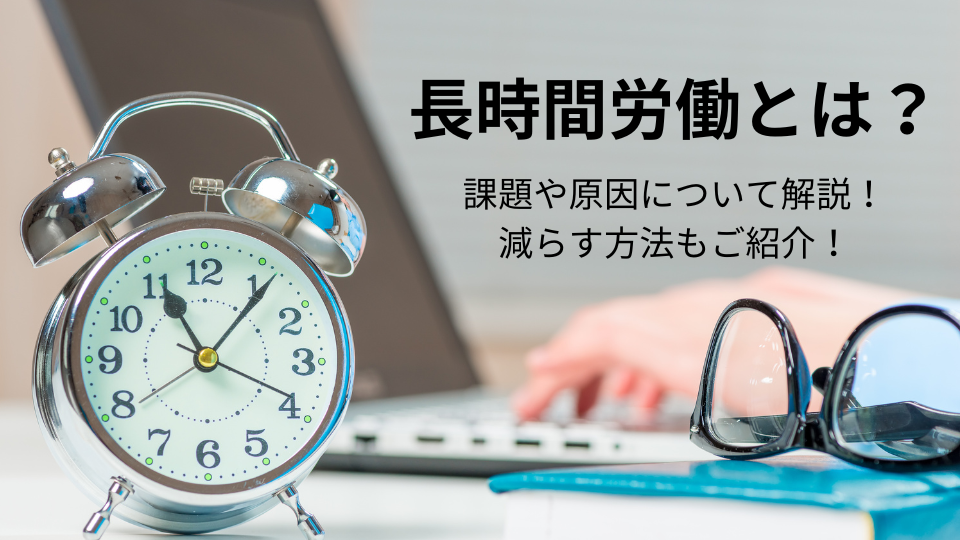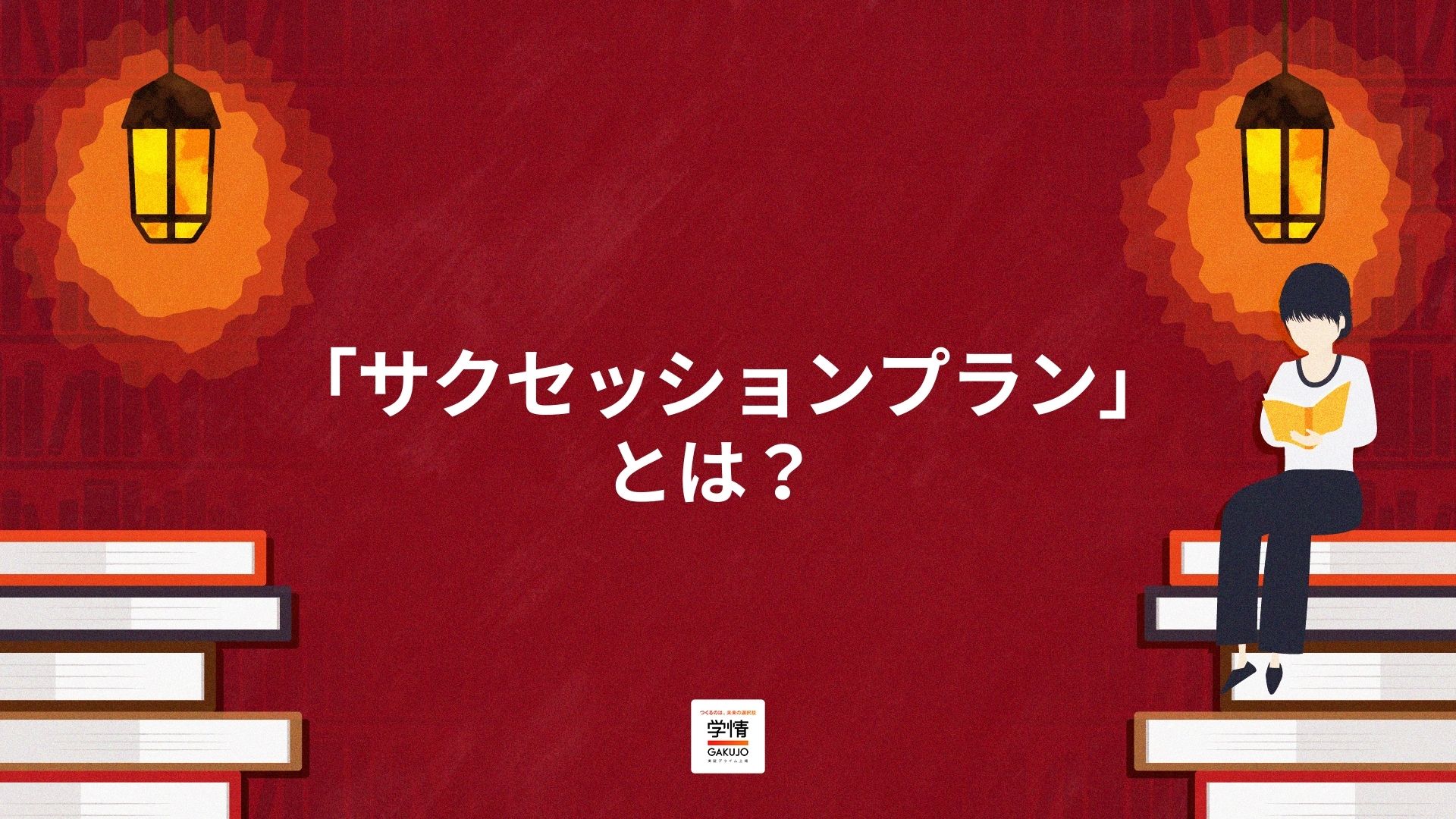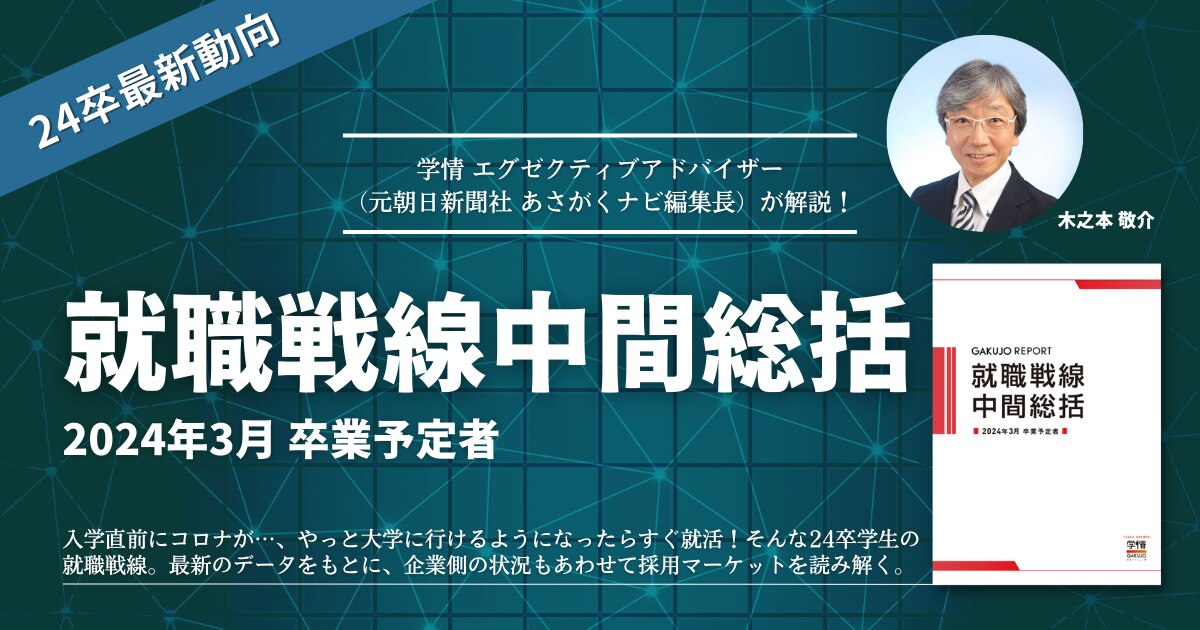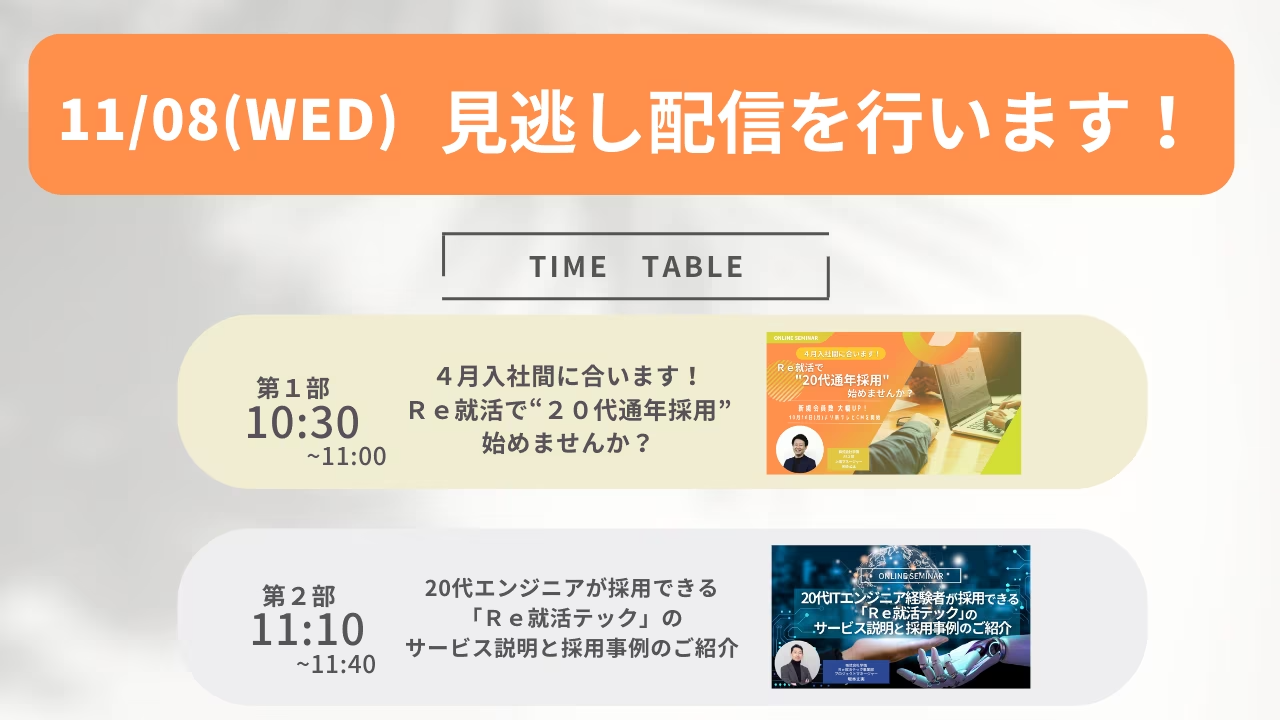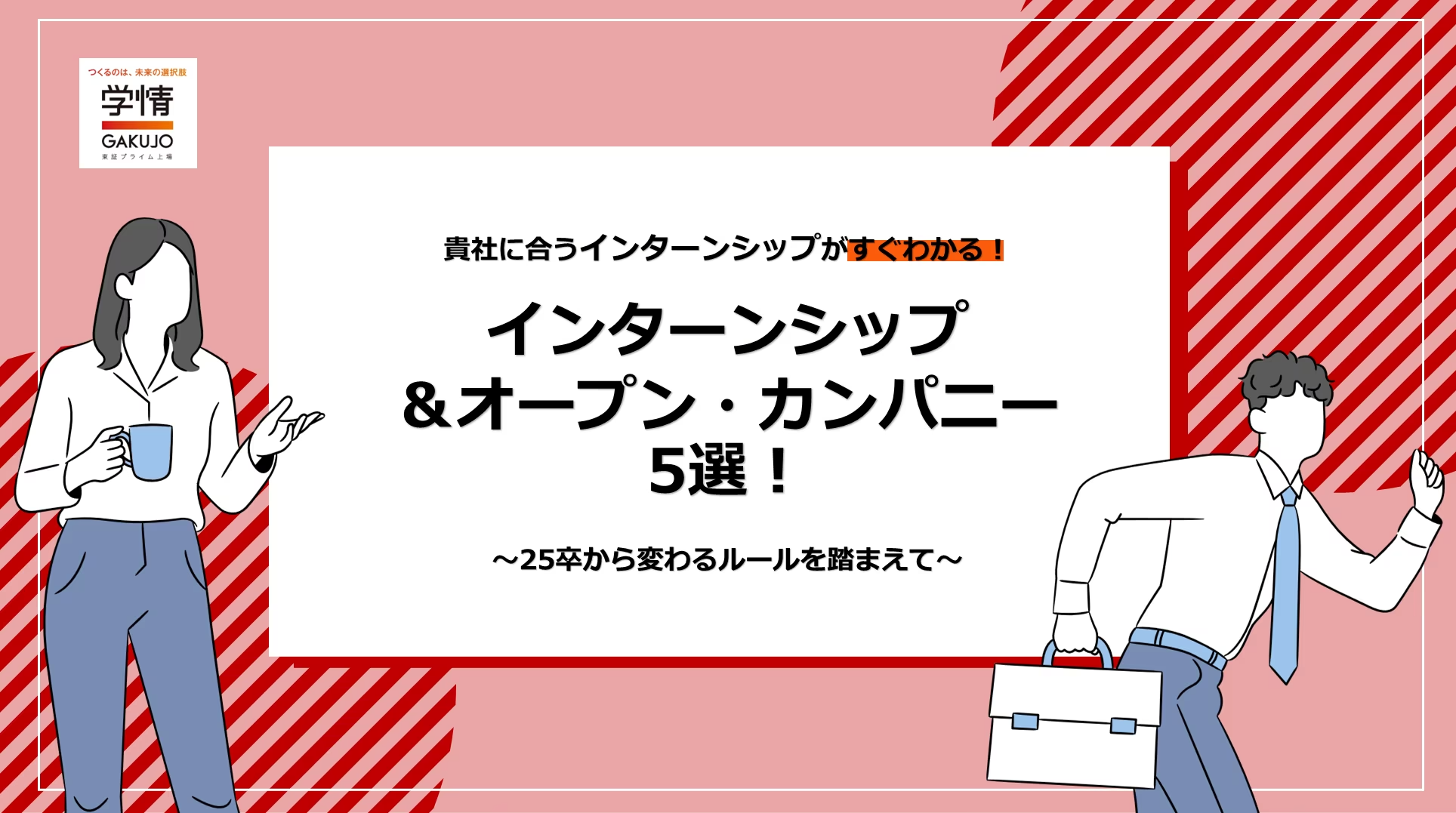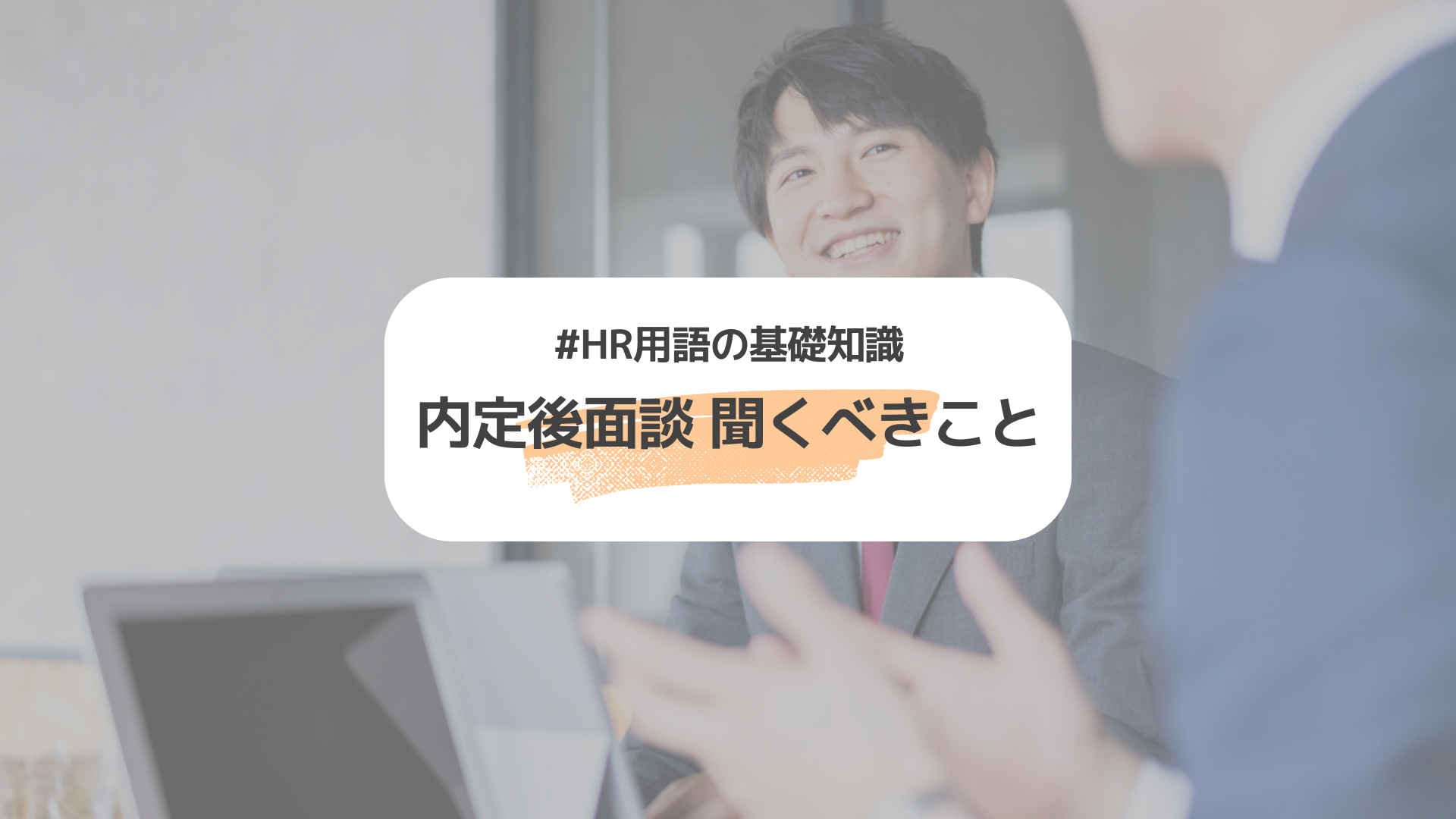Pick up article
![【2024年5月28日開催】20代採用を成功させる新オプションリリース <br>~[20分で50人にアプローチ]Re就活TV×VTuber~](https://service.gakujo.ne.jp/wp-content/uploads/2024/04/240412_rekatsutvgakujo.png)
【2024年5月28日開催】20代採用を成功させる新オプションリリース
~…
Pick up article
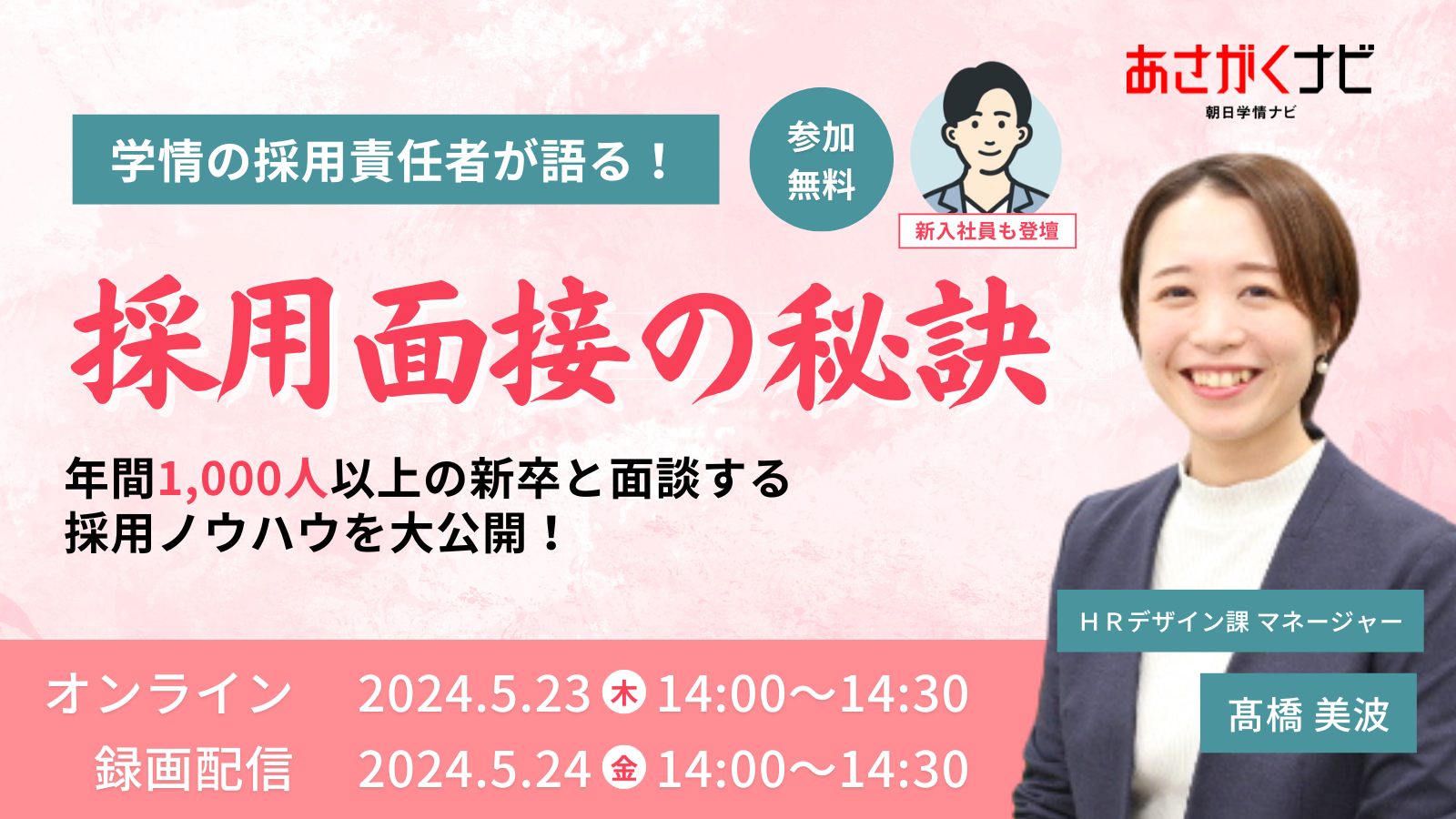
【2024年5月23日・24日開催】学情の採用責任者が語る!採用面接の秘訣
Pick up article
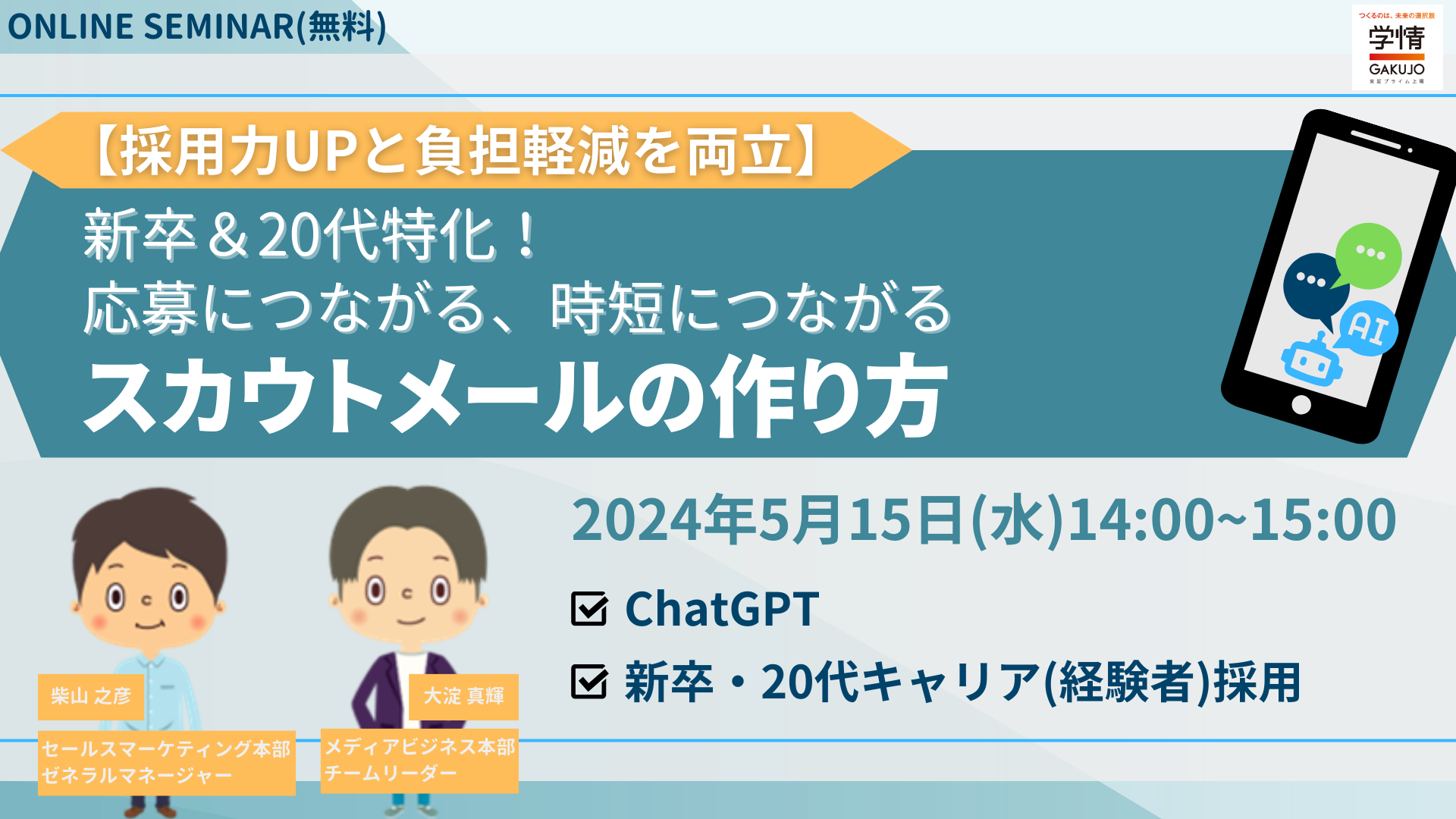
【2024年5月15日開催】<採用力UPと負担軽減を両立>新卒&20代特化!
…
Pick up article

【チェックリスト付き】カジュアル面談導入のすすめ~導入から振り返りま…
Pick up article

【アーカイブ配信/2024年5月10日(金)12時まで】20代採用の理想的なあ…
Pick up article
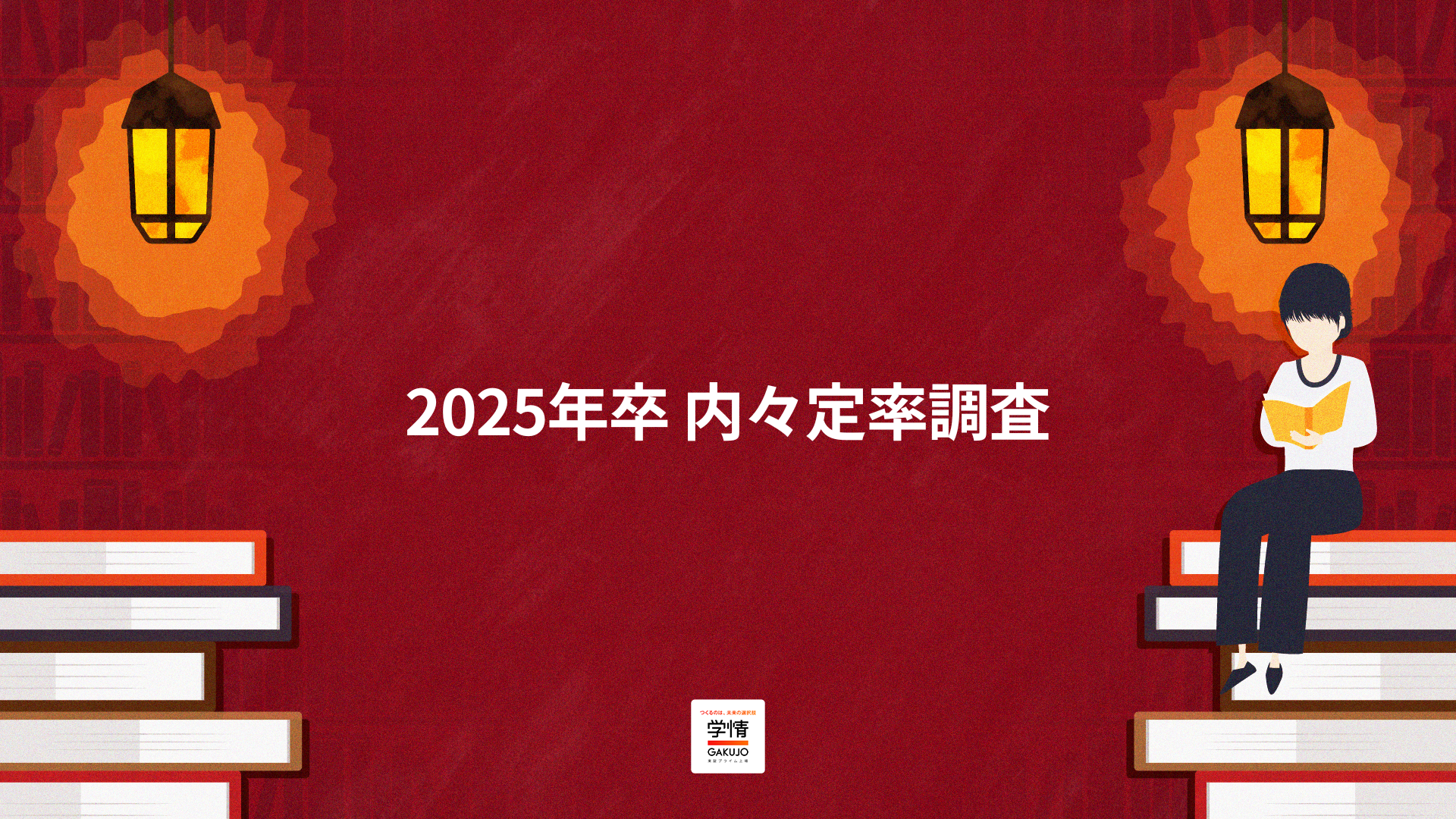
2025年卒 内々定率調査 2024年4月度
Pick up article
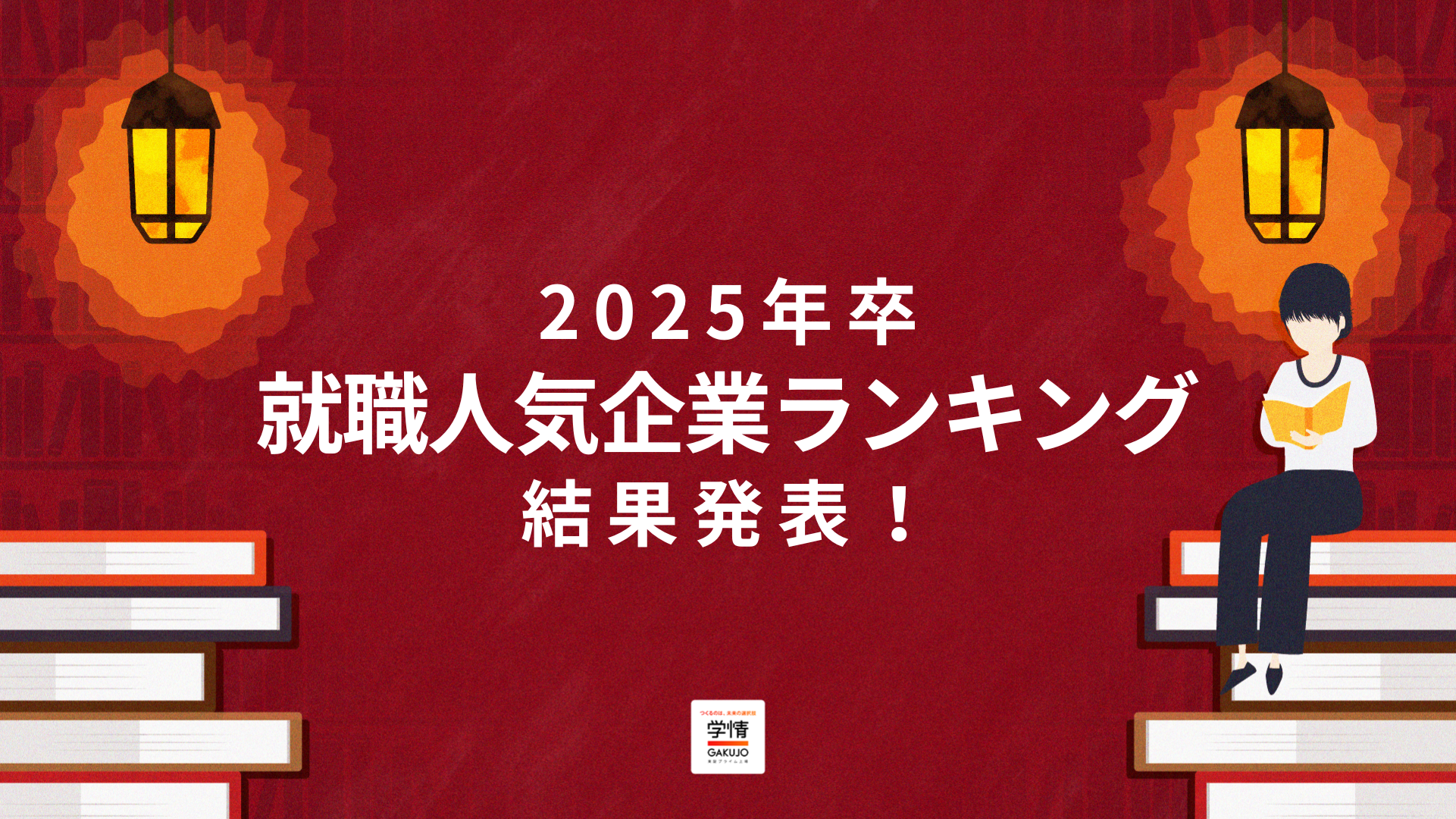
2025年卒「就職人気企業ランキング」を発表!
トップは6年連続のあの…
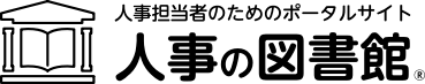
人事の図書館とは?
就職・転職・採用を筆頭に、調査データ、コラムをはじめとした担当者の「知りたい」「わからない」にお応えする、
株式会社学情が運営するオウンドメディアです。
採用ノウハウ資料
人事業務に関する
お役立ち情報が満載!